| 資料7 |
図表の解説
| I | 児童扶養手当と生活保護は非常に似通った動きをしている。 |
| (1) | 全体的特徴 |
| ( | 社会保障給付費)(図1) |
| 1. | 社会保障給付費に占める生活保護費の割合、1957年 10.3%→2003年 2.9%に低下。 |
| 2. | 社会保障給付費に占める児童扶養手当額 1971年 0.12%→1984年 0.7%→2003年 0.47%に低下。 |
| ( | 国民医療費)(図2) |
| 3. | 国民医療費に占める生活保護法(医療扶助)の割合 1954年 10.6%→2003年 4% に低下。 |
| ( | 生活保護の扶助種類別構成比)(図3) |
| 4. | 医療扶助費の割合 1957年 54%→2003年 51% このおよそ50年間ほとんど変化がない。 |
| 5. | 生活扶助費の割合は、1957年 37%→2003年 34%とほとんど変化がない。 |
| 6. | 住宅扶助費の割合は、1957年 2%→2003年 12%であり、大都市部における保護世帯の増加を反映して今後も増加しよう。 |
| (2) | 児童扶養手当世帯率と生活保護世帯率は非常に似通った動きをしている。 |
| ( | 児童扶養手当の所得上限)(図4) 児童扶養手当の所得上限は、1985年に全部支給と一部支給の2段階になり、全部支給の所得上限は1985年以降ほぼ動きがなかったが、2002年に90.4万円から57万円に低下した。一方、一部支給の上限は1985年以降毎年のびていたが、1998年に272.2万円から192万円に大幅に低下したあと、2002年に230万円に上昇した。 |
| ( | 児童扶養手当全部支給の割合)(図5) 全部支給割合が低下した。 |
| ( | 児童扶養手当受給者数と生活保護受給世帯数)(図6) 生活保護受給世帯数と児童扶養手当受給世帯数はほぼ同数であり、2段階の所得上限が導入された1985年以降非常に似通った動きを示す。 |
| ( | 児童扶養手当受給世帯率と生活保護世帯率)(図7) 生活保護受給世帯率と児童扶養手当受給世帯率はほぼ同率であり、2段階の所得上限が導入された1985年以降非常に似通った動きを示す。 |
| ( | 生保受給者1世帯当扶助費、児童扶養手当受給者1世帯当児童扶養手当)(図8) 1世帯当児童扶養手当受給額は1世帯当生活保護費のおよそ5分の1である。 |
| II | 就労支援はこの30年間実施してきたが効果は非常に限定的であった。 |
| ( | 生活保護受給世帯帯に占める高齢者世帯+傷病者世帯+障害者世帯の割合)(図9) 生活保護受給世帯帯に占める高齢者世帯+傷病者世帯+障害者世帯の割合は、1973年からすでに75%、2003年には82% |
| ( | 被保護世帯に占める自立助長推進効果)(図10) 選定率(保護世帯に占める自立助長推進対象世帯の割合)は1975年で6.5%、2003年で3.80%、廃止世帯割合は1985年で3%、2003年で1%、稼働開始世帯割合は1975年で1.3%ともともと低いものが、ますます低下してきた。 |
| ( | 自立推進対象世帯のうち廃止世帯など)(図11) 自室推進対象世帯のうち保護廃止世帯の割合は1986年の49%から2003年の27%に低下。自立更生世帯や稼動収入増世帯の割合も同様の動き。 対象者が高齢化などしていくなかで、就労支援の困難さを物語る。 |
|
社会保障給付費に占める生活保護費の割合、児童扶養手当額の推移 (1957−2003) |
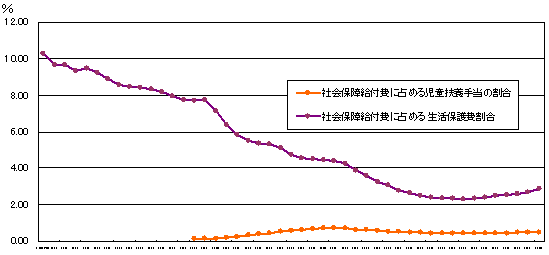
|
|
国民医療費に占める生活保護法(医療扶助)及び医療保険+老人保健+患者負担割合の推移 (1954−2003) |
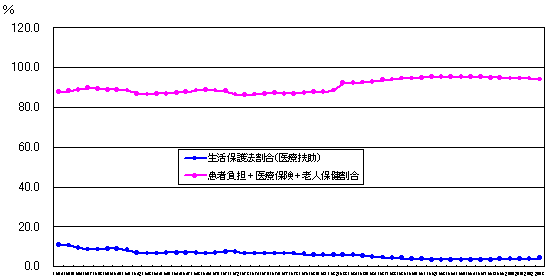
|
|
生活保護費の扶助別構成比の推移(1957−2003) |
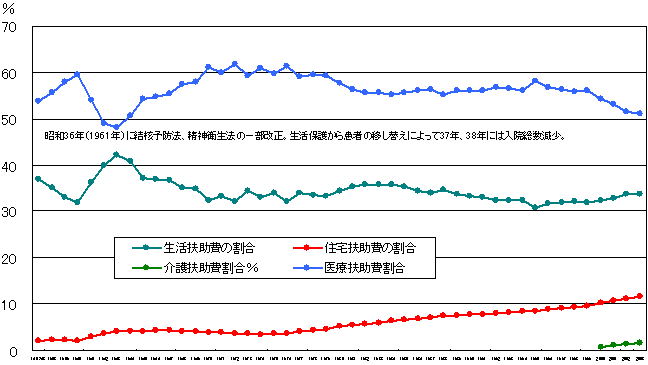
|
|
児童扶養手当全部支給、一部支給の所得上限の推移(扶養親族1人) (1977−2003) |
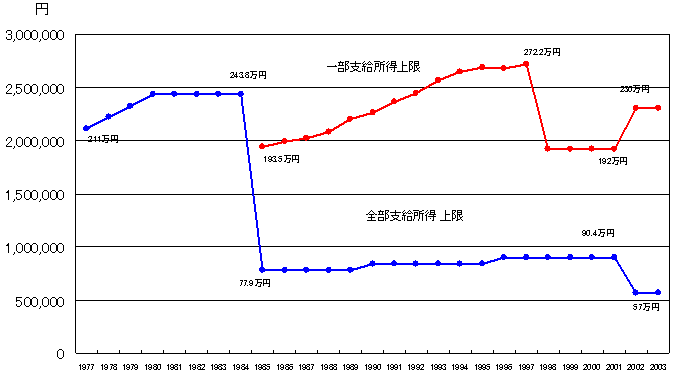
|
児童扶養手当受給者にしめる全部支給の割合の推移 (1986−2003) |
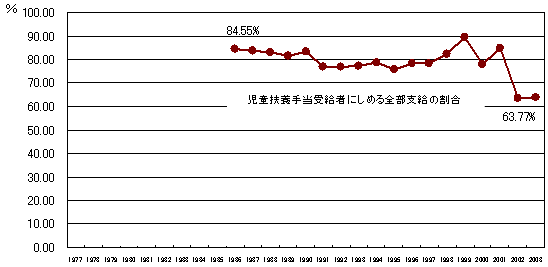
|
|
児童扶養手当受給世帯数、生活保護受給母子世帯数、生活保護世帯数 (1973−2003) |
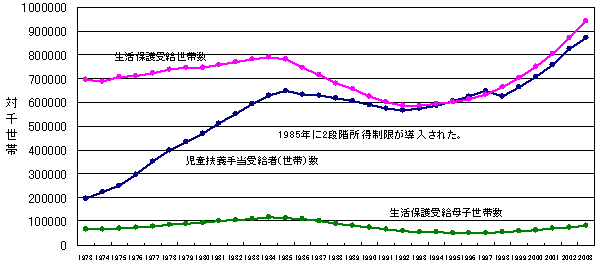
|
|
世帯保護率と児童扶養手当受給世帯率の推移(1963−2003) |
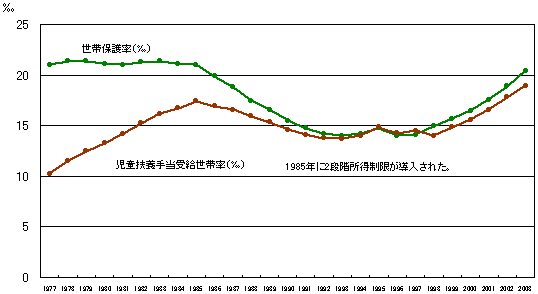
|
|
1世帯当生活保護費、1世帯当児童扶養手当費等の推移(1963−2003) |
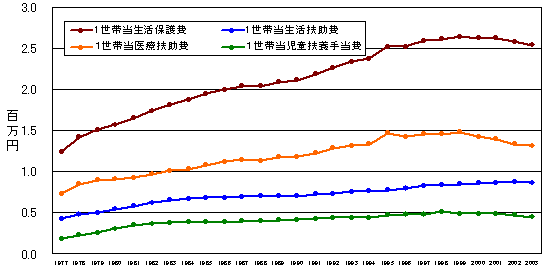
|
|
保護世帯に占める世帯類型別構成比の推移(1973−2002) |
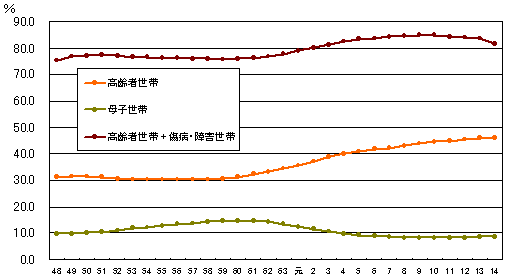
|
|
自立助長推進効果の推移(1975−2003)(対被保護世帯) |
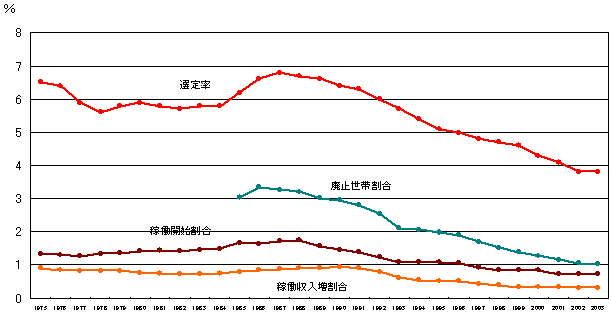
|
|
自立推進対象世帯のうち廃止世帯、稼働収入増世帯の割合の推移(1975−2003) |
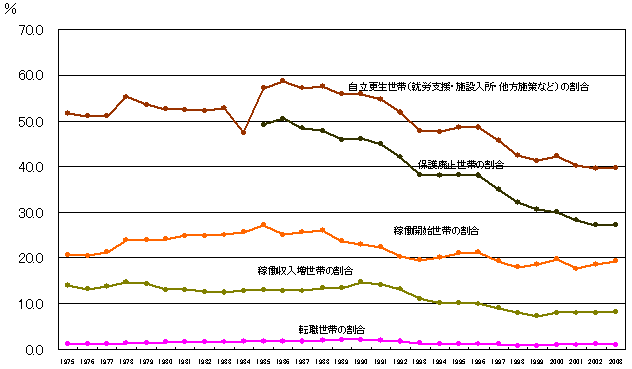
|