| 資料2−2 |
時 2005年9月26日 所 厚労省
新たな医療計画を求めて
・・・住民の視点と医療の連携に基づく
国立保健医療科学院
(旧国立医療・病院管理研究所)
政策科学部
部長 長谷川敏彦
国立保健医療科学院
埼玉県和光市(2002-)
保健医療福祉の
総合的政策研究を目指して
国立医療・病院管理研究所と
国立公衆衛生院と統合
第1部
医療計画の問題とWGの提案
地域医療計画の問題点
| 問題 | 提案 | |
| 理念 | ||
| 目的曖昧 目標値無(病床規制除く) |
目的の明確化 医療計画の定義 |
|
| 内容 | ||
| 医療の成果(安全・質)取組無 高齢社会へ対応無 |
高齢社会に向け医療システム再構築 医療の質・安全の確保 |
|
| 手法 | ||
| 誘因無 住民参加無 追跡評価無 |
生涯コース/疾病シナリオアプローチ 誘因との結合 評価指標選定と追跡システム確立 |
| 医療計画外部環境歴史分析(PEST) 医療計画導入当初、現状、そして未来 |
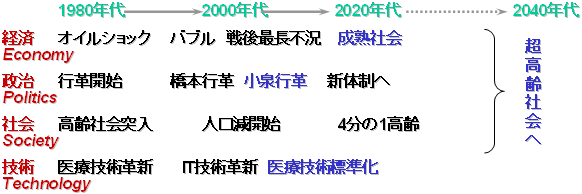
医療技術評価総合研究事業
2004-2006
|
政府の役割と質・安全・公平から見た 地域医療システム運営の 評価手法と改善誘因の研究
国立医療・病院管理研究所 医療政策研究部長 長谷川 敏彦 |
第2部
高齢社会と連携
連携3段階理論
連携の歴史的発展段階
| 段階 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |
| 時期 | -1990 | 1990- | 2000- | |
| 中心 | 診療所 | 病院 | システム | |
| 背景 | 開業医 高齢化 |
経営環境 競合激化 |
本格的 高齢社会 |
第1部
診療所から
| 医師職場分布 | 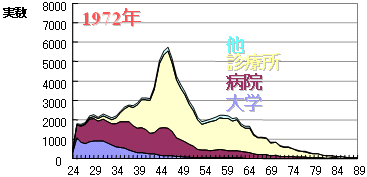 |
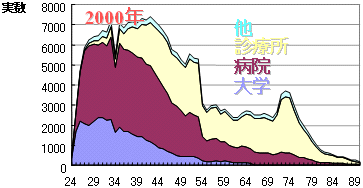 |
小さくなるパイを奪い合う病院と診療所には 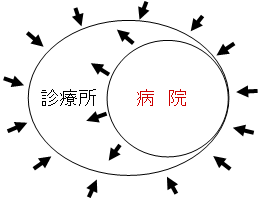 |
第2部
病院から
| 平均在院日数短縮プロセス | 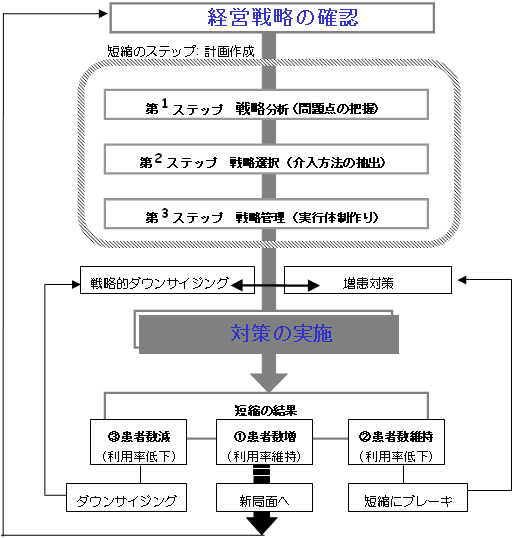 |
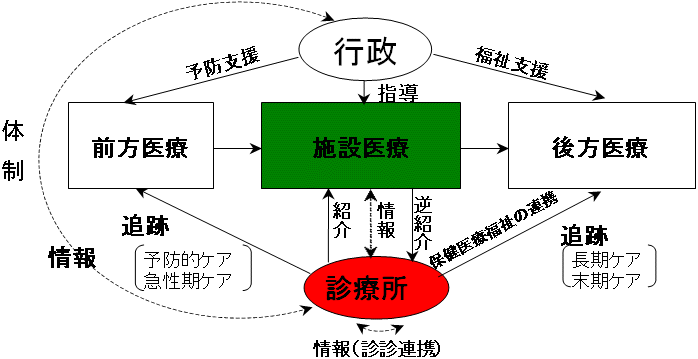 |
第3部
システムから
今なぜ患者中心の医療か
↓
そうでなければ有効、安全でない
↓
多数の急変する慢性疾患を抱える
第3部
患者中心の医療と高齢社会
| 2つの患者中心の医療 臨床レベル 意思決定、価値観の反映 システムレベル 提供体制、継続性 |
年齢階級と傷病数(標準誤差つき)
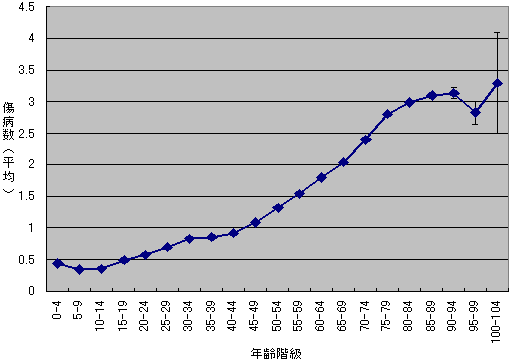
| 生活習慣病ー日野原重明1996 継続診療を必要とする |
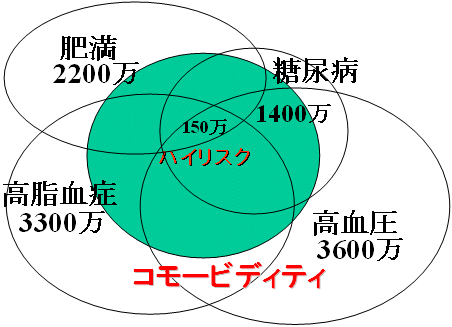 |
→ | 心疾患 脳卒中 腎疾患 他 |
| 生活習慣病とは、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症に関与する疾患群」と定義 | * H12年度循環器疾患基礎調査より推計 ** H14年度糖尿病実態調査公表データ |
患者中心医療を追求すると
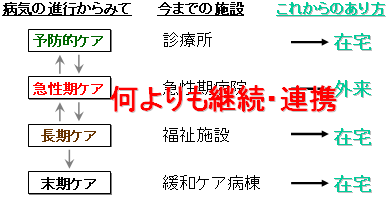
|
|
|||
| 医療の集中 | 医療の外来化 | 医療の宅配 | ||
| 技術集積性 規模の経済 |
利便性 近接性 |
|||
| 質・安全 | ↑ | ↑ | ||
| 効率 | ↑ | |||
| 公平 | ↓ | ↑ |
| 患者中心の医療 |
・・・ | 個々の臨床レベル |
| ↓ | ||
| 患者中心の医療 |
・・・ | 病院の経営レベル |
| ↓ | ||
| 患者中心の医療 |
・・・ | 地域のレベル |
高齢社会と
必要な医療システム
日本人口と高齢者
| 2000 1.26億人 |
2050 1.0億人 |
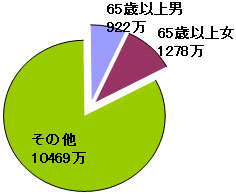 |
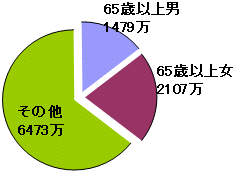 |
| 究極の社会 貧乏婆さんの世界 | |
20世紀のイメージ
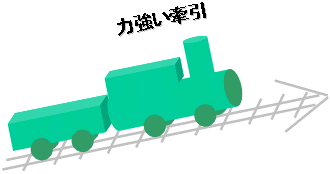 |
限りなき成長 |
21世紀とは
| 一つ一つ達成 様様な方角から、 様様な時期に ファイナルデスチネーションへ ファイナルランディング |
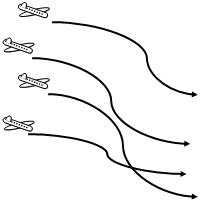 |
究極の最終到達地 | 何時か見た光景、超高齢社会 |
| 日本の軌跡 近代3度めの舵取り |
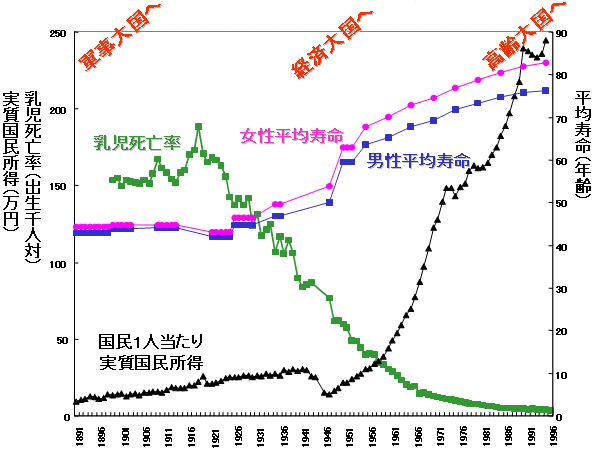
日本医療の歴史・・・健康転換の諸相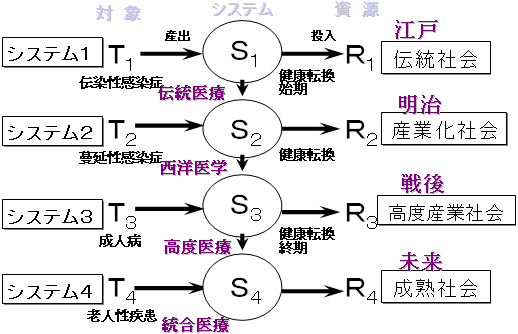 |
医療システムの概念
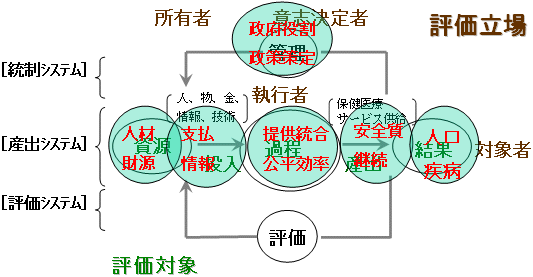
第4部
連携の類型
連携の類型
| 類型 | 0 0a型0b型 |
I Ia型Ib型 |
II IIa型IIb型 |
III IIIa型IIIb型 |
| 事例 | 上田 | 秋田 熊本 | 名古屋 | |
| 二次医療圏 | 150 | 100 | 50 | 30 |
| 人口 | -10万 | 10-20万 | 40-70万 | 130万 |
| 全人口 | 2000万人 | 3000万人 | 3000万人 | 4000万人 |
| 地域中核病院 | -1 | 1-2 | 4-7 | 10-20 |
| 特徴 | 郡部 | 地方中小都市 | 県庁所在地 | 大都会 |
第0段階(郡部型)
| 0a型 | 0b型 | ||
|
|||
|
|||
| 連携すべき 病院がない |
|
第1段階(地方中小都市型)
| Ia型 | アクセス有 → |
Ib型 | |
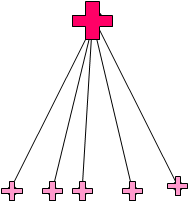 |
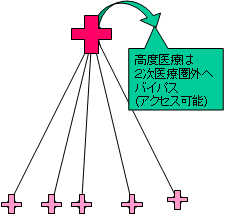 |
||
|
|
上田市:城下町連携
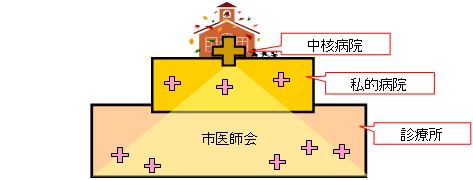
第2段階(地方中核型)
| IIa型 | 機能 → 分化 |
IIb型 | |
|
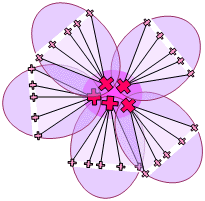 |
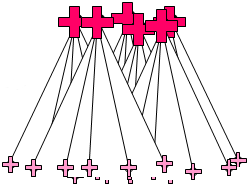 |
|
|
|||
| 地域分担型 | 機能分担型 |
秋田市:医師会と総合病院のたすきがけ
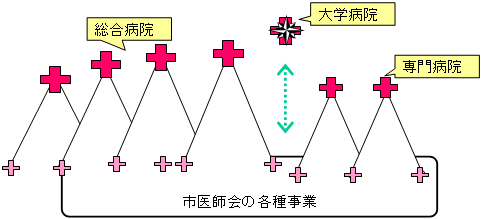
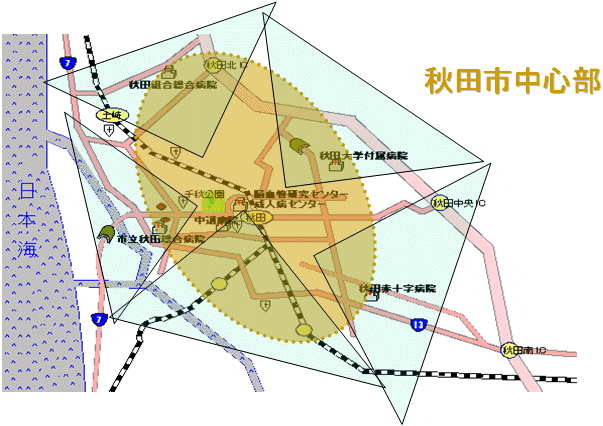
熊本市:公的急性期病院の競合・分担
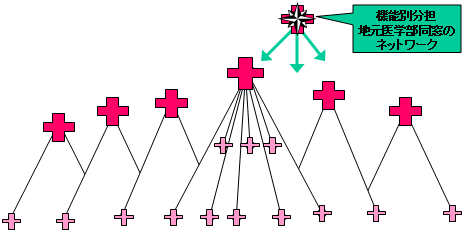
連携の類型
| 類型 | 0 0a型0b型 |
I Ia型Ib型 |
II IIa型IIb型 |
III IIIa型IIIb型 |
| 事例 | 上田 | 秋田 熊本 | 名古屋 | |
| 二次医療圏 | 150 | 100 | 50 | 30 |
| 人口 | -10万 | 10-20万 | 40-70万 | 130万 |
| 全人口 | 2000万人 | 3000万人 | 3000万人 | 4000万人 |
| 地域中核病院 | -1 | 1-2 | 4-7 | 10-20 |
| 特徴 | 郡部 | 地方中小都市 | 県庁所在地 | 大都会 |
第3段階(都市・郊外型)
| IIIa型 | 機能 → 分化 |
IIIb型 | |
|
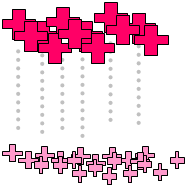 |
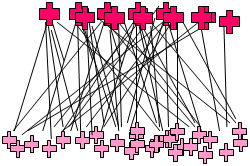 |
|
|
急性期病院の機能パターン
|
||||||||||||||||
地域別二次医療圏分布
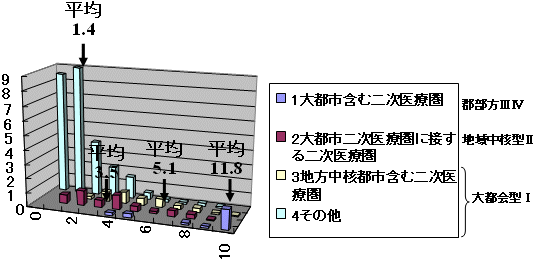
| 分類 | 課題 | |
| I | 郡部型 | 必須医療機能確保 (プライマリケア、救急) |
| II | 城下町型 | 3次機能へのアクセス (需給分析、道路整備) |
| III | 地方中型型 | 機能棲み分け (地域分担から機能分担) |
| IV | 大都市型 | 機能分化強化分担 (疾病別ネットワーク) |
第3部
新たな計画手法の提案
地域医療計画の問題点
| 問題 | 提案 | |
| 理念 | ||
| 目的曖昧 目標値無(病床規制除く) |
目的の明確化 医療計画の定義 |
|
| 内容 | ||
| 医療の成果(安全・質)取組無 高齢社会へ対応無 |
高齢社会に向け医療システム再構築 医療の質・安全の確保 |
|
| 手法 | ||
| 誘因無 住民参加無 追跡評価無 |
生涯コース/疾病シナリオアプローチ 誘因との結合 評価指標選定と追跡システム確立 |
2つの新たなアプローチ
| ライフコースアプローチ 生涯の段階毎の疾病 ディジーズシナリオアプローチ 患者の視点、病気の過程から見た |
生涯コース概念
生涯過程からみた病気
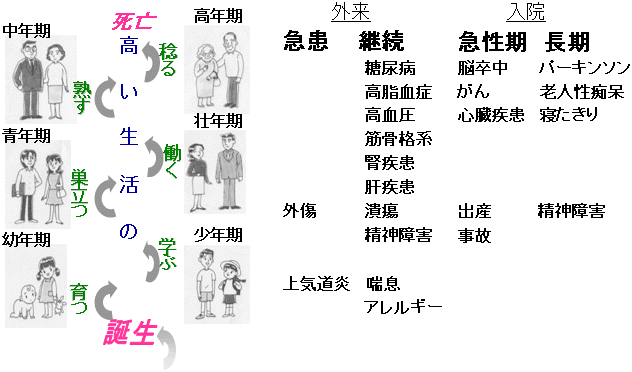
|
ライフコースアプローチ 生涯の段階毎の疾病 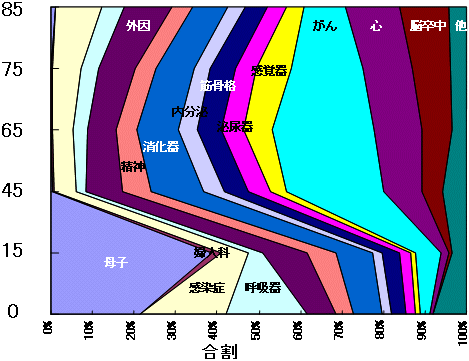 |
||
| (C) T Hasegawa NIPH,Japan |
患者調査退院票2002 | |
疾病シナリオ手法
ディジーズシナリオアプローチ
| 診断 52歳の太り気味(170cm、78kg)の男性会社員、15年前、健診1)で「糖尿病の気」があると指摘されたが放置したが、8年前通勤時に過労で倒れ入院し糖尿病と診断された2)。 治療 退院後、病院の糖尿病専門医に紹介され、それ以来、経口糖尿病薬と栄養・運動療法を受けてきた3)。病院が遠いので栄養や運動療法、薬による血糖のコントロールうまく守れていない4)。特に、最近数年間会社が傾き、仕事の量が増え、治療の継続が難しい。 資源 近くにかかりつけの医師がいれば便利なのだが8)。そして気軽に栄養や運動の生活指導をしてくれる人や場所が近くにあればと思っている5)6)7)。 合併症予防 最近視力が落ちたような気がし、。また、最近手足のしびれがあるように覚え、体の動きもままならない8)。気になるのは、足がむくみ気味で、腎臓の機能が低下しているのかしら。 各種専門医の受診が必要なのか。糖尿病は管理を良くすれば合併症も防げ天寿も全うできるといわれているのだが |
県別評価指標 ■評価例■
|
予防(詳細指標)
| 個人願望 | 過程 | 分子 | 調査データ | 期間 | 最近年 | 分母 |
| 運動したい | 一次予防 | 運動している人の割合 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 全人口 |
| 運動したい | 一次予防 | 運動量/日 | 国民栄養調査 | プール毎年 | 1991-2002 | 全人口 |
| 痩せたい | 一次予防 | 腹八分目 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 人口 |
| 痩せたい | 一次予防 | 規則正しく食事をとる | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 人口 |
| 痩せたい | 一次予防 | バランス良い食事をしている | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 人口 |
| 痩せたい | 一次予防 | BMI>25 | 国民栄養調査 | プール毎年 | 1991-2002 | 人口 |
| 健診受けたい | 二次予防 | 健診カバー率 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 人口 |
治療
| 個人願望 | 過程 | 分子 | 調査データ | 期間 | 最近年 | 分母 |
| 受診したい | 受療 | 受診カバー率 | 患者調査 | 3年 | 2002 | 人口 |
| 身近な診療所に行きたい | 身近な治療 | 診療所割合 | 患者調査 | 3年 | 2002 | 全患者 |
| 長く続けたい | 継続性 | 継続期間 | 患者調査 | 3年 | 2002 | 人口 |
| 病院に紹介されたい | 連携 | 診療所から病院への紹介 | 患者調査 | 3年 | 2002 | 病院外来患者 |
| 診療所に紹介されたい | 連携 | 病院から診療所への紹介 | 患者調査 | 3年 | 2002 | 診療所外来患者 |
| 指導受けたい | 生活管理 | 食生活や生活習慣の改善の有無 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 全患者 |
| 指導受けたい | 生活管理 | 指導の実行状況 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 全患者 |
| 専門教育受けたい | 生活管理 | 教育施設 | 学会登録 | 毎年 | 2004 | 総患者数/人口 |
| 指導受けたい | 生活管理 | 療養指導士 | 学会登録 | 毎年 | 2004 | 総患者数/人口 |
| 専門医に診てもらいたい | 専門性 | 専門医 | 学会登録 | 毎年 | 2004 | 総患者数/人口 |
結果
| 個人願望 | 過程 | 分子 | 調査データ | 期間 | 最近年 | 分母 |
| 患者になりたくない | 有病率 | 総患者数 | 患者調査 | 3年 | 2002 | 人口 |
| 健康でいたい | 活動 | 健康よい割合 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 総患者数 |
| 障害なくしたい | 活動 | 日常生活への影響の有無 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 総患者数 |
| 目が見えたい | 合併症 | 症状目のかすみ | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 総患者数 |
| 目が見えたい | 合併症 | 症状物を見づらい | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 総患者数 |
| 手足を動かしたい | 合併症 | 症状手足のしびれ | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 総患者数 |
| 腎臓を患いたくない | 合併症 | 腎臓の病気 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 総患者数 |
| 心臓を患いたくない | 合併症 | 狭心症・心筋梗塞 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 総患者数 |
| 脳卒中になりたくない | 合併症 | 脳卒中 | 国民生活基礎調査 | 3年 | 2001 | 総患者数 |
| 死にたくない | 死亡 | 糖尿病死亡 | 人口動態統計 | 毎年 | 2003 | 人口 |
| 紹介率 糖尿病診療所外来、患者調査、2002 |
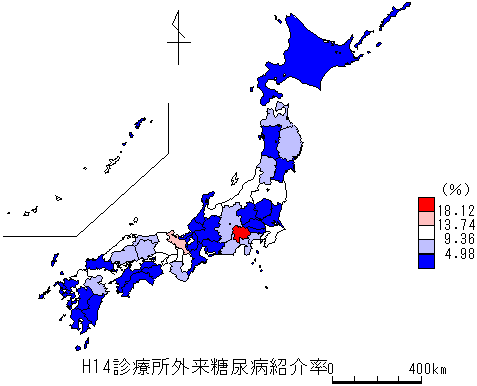
糖尿病専門医数の分布
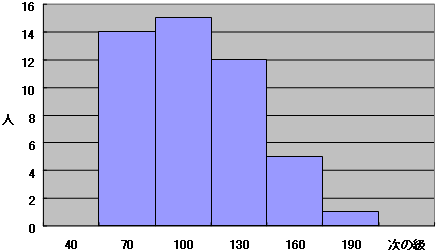 患者10万人あたり専門医数 学会調査 |
県別専門医数
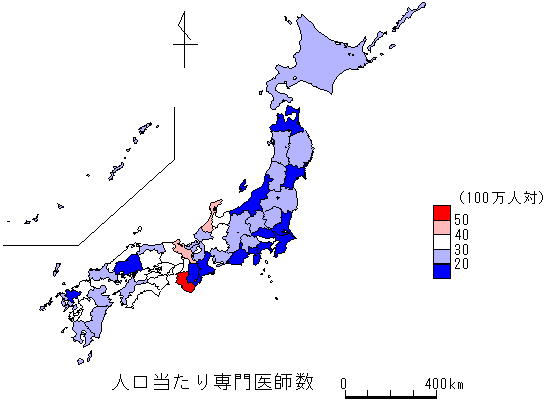 人口10万対 学会調査 2004 |
県別評価の例
| 歩行 | BMI | 健康診断 | カバレッジ | 身近 | 継続性 | 診療所に紹介 | 療養指導士 | 専門医 | 目のかすみ | 手足のしびれ | 腎臓病 | |
| 上位5県 | 8000歩以上 | 25以上 | % | % | % | 日 | % | 10万対 | 10万対 | % | % | % |
| 石川県 | 39.4 | 14.4 | 63.4 | 40.3 | 37.7 | 1412 | 3.8% | 17.1 | 3.8 | 17.3 | 20.1 | 3.0 |
| 京都府 | 39.0 | 14.2 | 56.3 | 41.9 | 51.2 | 496 | 17.0% | 7.3 | 3.8 | 26.8 | 16.1 | 2.8 |
| 富山県 | 38.1 | 16.3 | 70.1 | 47.0 | 34.6 | 739 | 9.9% | 12.1 | 3.7 | 27.6 | 22.9 | 3.3 |
| 岡山県 | 34.8 | 15.3 | 69.8 | 44.6 | 45.2 | 674 | 6.6% | 10.0 | 3.3 | 27.0 | 21.5 | 2.5 |
| 奈良県 | 44.1 | 13.5 | 58.3 | 47.2 | 39.0 | 936 | 10.3% | 7.2 | 1.5 | 26.1 | 22.2 | 2.8 |
| 下位5県 | 歩行 | BMI | 健康診断 | カバレッジ | 身近 | 継続性 | 診療所に紹介 | 療養指導士 | 専門医 | 目のかすみ | 手足のしびれ | 腎臓病 |
| 高知県 | 35.7 | 17.7 | 63.5 | 39.9 | 38.0 | 424 | 3.1% | 6.9 | 3.7 | 24.1 | 28.6 | 5.4 |
| 茨城県 | 38.9 | 18.4 | 66.3 | 42.6 | 62.6 | 605 | 2.8% | 5.9 | 1.6 | 29.9 | 28.4 | 4.6 |
| 鹿児島県 | 34.1 | 16.6 | 64.2 | 32.7 | 54.8 | 491 | 3.3% | 7.1 | 2.0 | 30.2 | 19.5 | 3.8 |
| 岩手県 | 33.5 | 20.3 | 72.3 | 37.9 | 28.9 | 600 | 9.2% | 6.3 | 2.0 | 32.8 | 22.2 | 1.5 |
| 長崎県 | 37.9 | 15.3 | 62.7 | 42.0 | 45.4 | 309 | 3.6% | 10.2 | 2.0 | 32.2 | 27.9 | 3.9 |
各項目の重みを1とし、順位を足してベンチマークしたもの
12指標レーダーチャート比較
糖尿病,上位5県
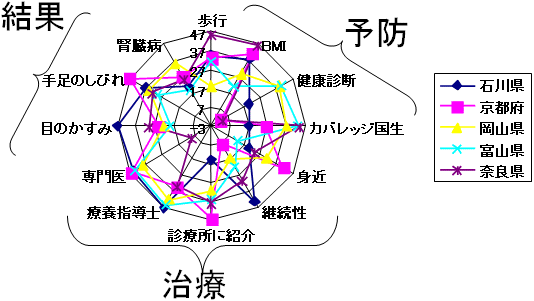
第5部
病院経営と連携
| 政策 | 経営 | |||
| 安全・高質 | → | 連携 | ← | マーケティング |
| 効率 | → | ← | 戦略 | |
| 患者中心視点 | → | ← | ブランディング | |
| 医療システム再構築 | 理念、機能の選択 | |||
戦略
3つの戦略過程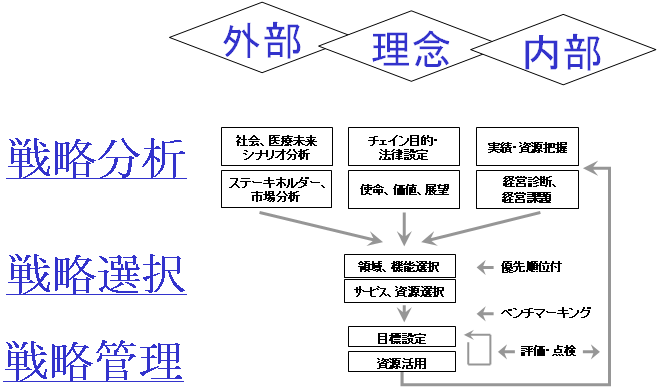 |
3つの戦略レベル
|
主要・事業領域(domain) 事業多角化や縮少の決定 |
||
| ↓ | |||
|
個別事業(port forio)の選択 販売商品の決定 | ||
| ↓ | |||
|
各事業のための機能推進の戦略 人事、購入、マーケティング |
企業戦略ドメイン選択と連携
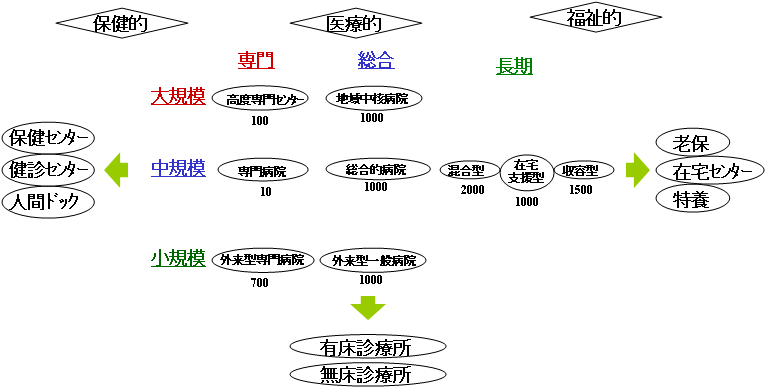
3つの戦略レベル
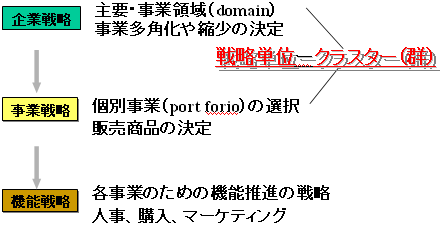
クラスター(群)
疾患例
部門別例
|
クラスター例
虚血性心疾患
|
新たな形態
| <供給者> | <院内> | <受益者> | |||||
|
紹介 連携 |
|
診療 説明 |
|
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
| 情報共有 | 院内連携 | 情報発信 |
診療統合システム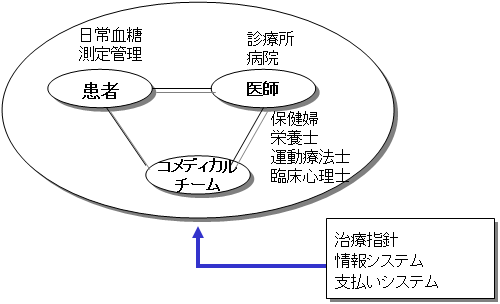 |
クラスター
クラスターとその特徴
| 前方連携 | 院内連携 | 後方連携 | ||||||
| クラスタ | 診療所 | 救急 | 急性期 | 慢性期 | 回復期 | 末期 | ||
| 疾病系 | 母子 | (NICU、他) | ○ | ○ | ||||
| 呼吸器 | (喘息・COPD) | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| 感染症 | (消化器・呼吸器) | |||||||
| 外傷 | (頭部・骨折) | ○ | ○ | |||||
| 消化器 | (内視鏡・潰瘍・肝) | ○ | ||||||
| 内分泌 | (肥満・糖尿病) | ○ | ○ | |||||
| がん | 消化器系(食道・胃・肝臓含む) | |||||||
| 呼吸器系 | ||||||||
| 婦人科系 | ||||||||
| 泌尿器科系 | ||||||||
| 脳神経系 | ||||||||
| 婦人科 | (更年期障害中心) | ○ | ||||||
| 泌尿器 | △ | ○ | ○ | |||||
| 心 | (救急・開心・PTCA) | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| 脳卒中 | ○ | ○ | ||||||
| 筋骨格 | (腰痛・リウマチ) | △ | ○ | |||||
| 精神 | (うつ・合併症) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 感覚器 | (目・耳) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 政策系 | 安全安心 | 感染(伝染病) | ○ | ○ | ||||
| 災害 | ||||||||
| (小児・産科) | ○ | |||||||
| 支援公平 | 僻地 | ○ | ○ | |||||
| 難病(神経・自己免疫疾患) | ○ | ○ | ||||||
| 精神(救急・触法) | ○ | |||||||
|
退院回数 年間回数、年齢 疾病別 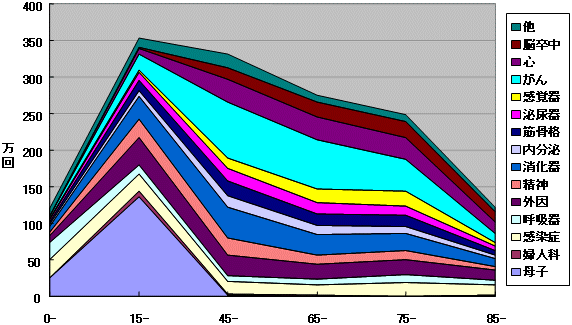 |
||
| (C) T Hasegawa NIPH,Japan |
患者調査2002 | |
年齢階級別クラスター別入院回数(万回)
患者調査退院票2002 |
クラスタ
| 救急系 | 技術系 | 支援系 | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
| |||||||||
|
|
|||||||||
第6部
新たな地域医療計画の提案
ベンチマーキングとパフォーマンス評価
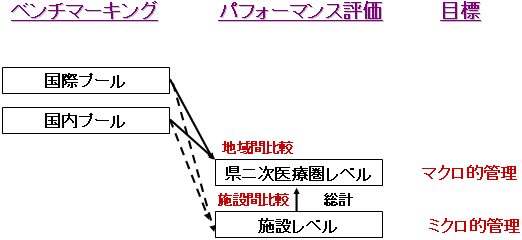
各層の評価
| 対象 | 側面 | ||
| 1. | 臨床家 | ・コンピテンシイ、 | 臨床結果 |
| 2. | 施設 | ・パーフォーマンス、 | 診療成果 |
| 3. | 集団全体 | ・シナリオ、 | 集団使命 |
| 4. | 国・県 | ・システム | 国への貢献 |
行政も
新たな地域医療計画
病床規制から質安全の向上へ
階層型構造の医療提供体制から
住民・患者の視点に立った診療ネットワークへの転換
| 〔これまでの医療計画の考え方〕 | → | 〔新しい医療計画の考え方(イメージ)〕 |
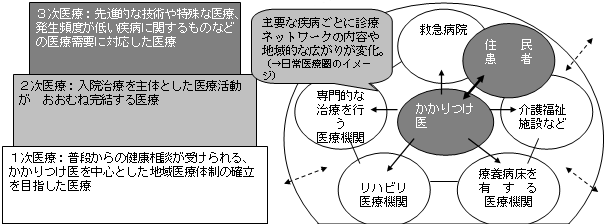 |
||
|
|
| 日常医療圏と診療ネットワークの関係 「医療機関完結型医療」から「地域完結型医療」へ |
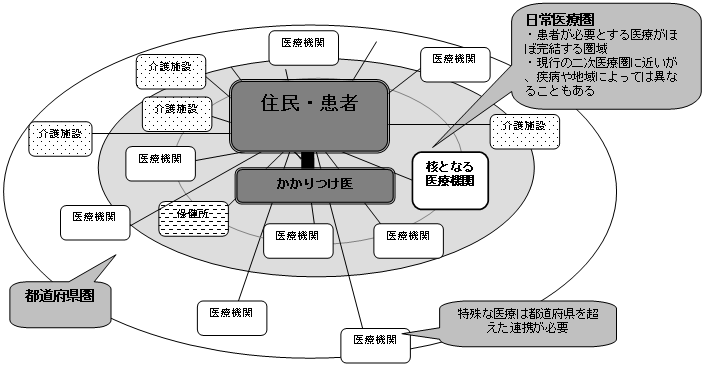
日常医療圏の診療ネットワークのイメージ(「糖尿病」の場合)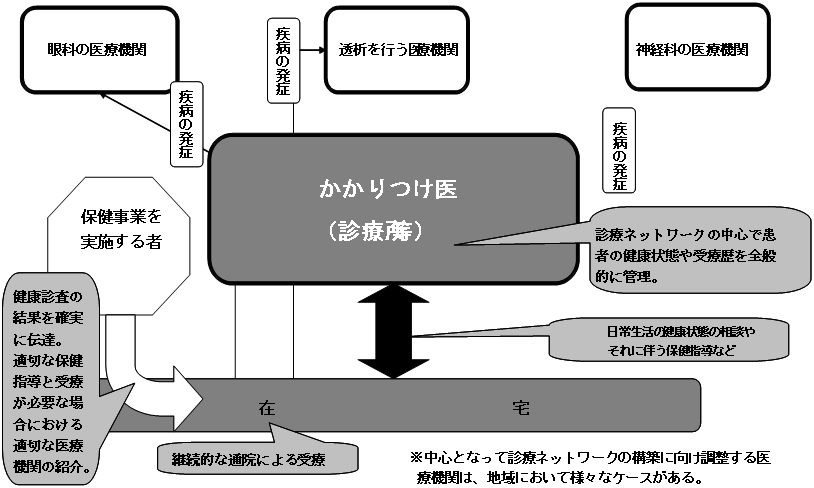 |
新地域医療計画の提案
| 理念 目的 高齢社会に向け医療システム再構築 医療の質・安全の確保 医療計画の定義 行政と住民との医療システム構築運営上の約束 政府の役割 必要な機能資源確保 医療をとうして安全安心の確保 安全・高質・効率的な医療の確保 方法 住民患者の視点から策定 生涯コース/疾病シナリオアプローチ 目標値の設定と誘因との結合 評価指標選定と追跡システム確立 |
| 個人診療段階と行政支援の対応 ・・・・・「がん」の例 |
| 個人(患者) | 地域(行政) | 評価追跡指標 | |
| 発見 | がんのことを知りたい いい病院を紹介してほしい |
・検診受診率の上昇 ・がんについての周知 ・医療機関の情報集積、公開システム |
左にあった指標を選択 |
| 診断 | 治療の支援をしてほしい セカンドオピニオンが聞きたい |
・誤診の回避 ・連携の推進 |
|
| 治療 | いい治療を受けたい 医療事故に遭いたくない |
・カバー率を上げる ・質・安全性の高い医療の提供 ・死亡率の低下 |
|
| 回復 | 早く帰りたい 質の高い生活をしたい |
・リハビリ施設の整備 ・相談窓口 |
|
| 末期 | 苦痛なく死にたい 自分らしく死にたい |
・在宅医療の整備 |