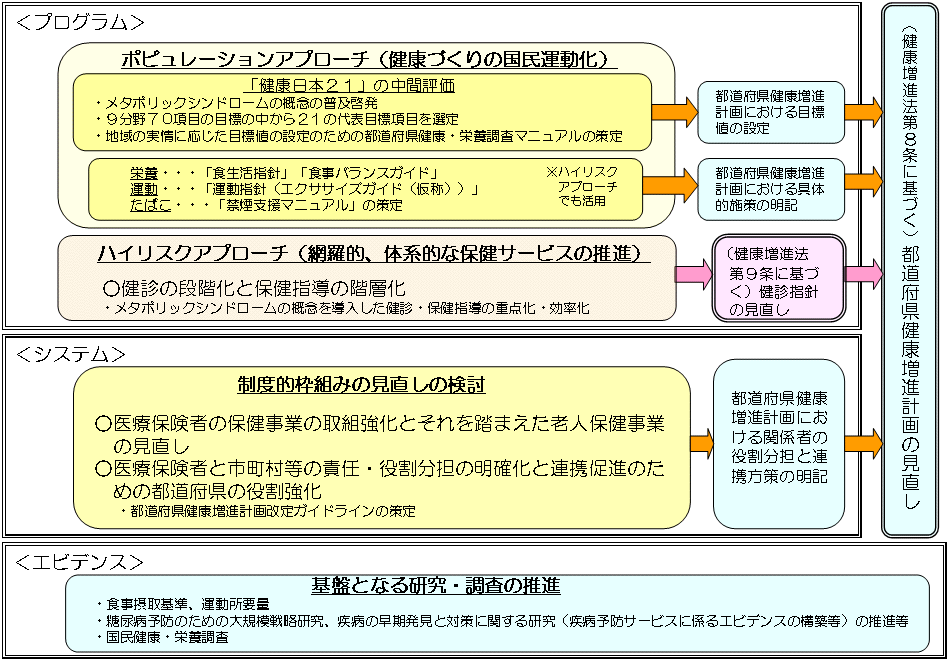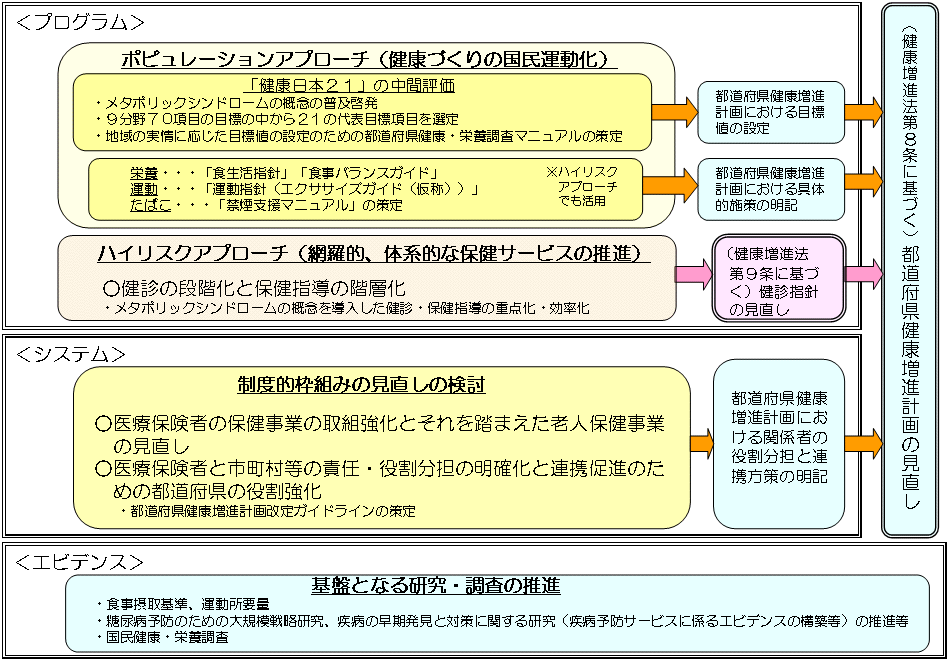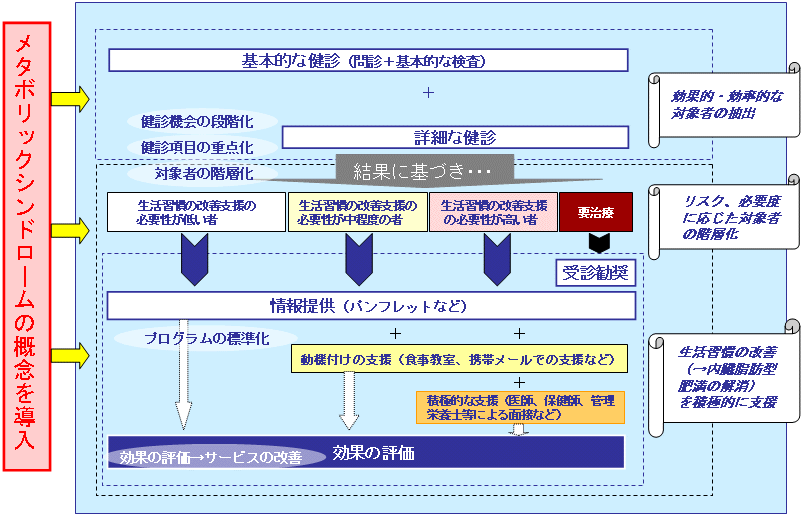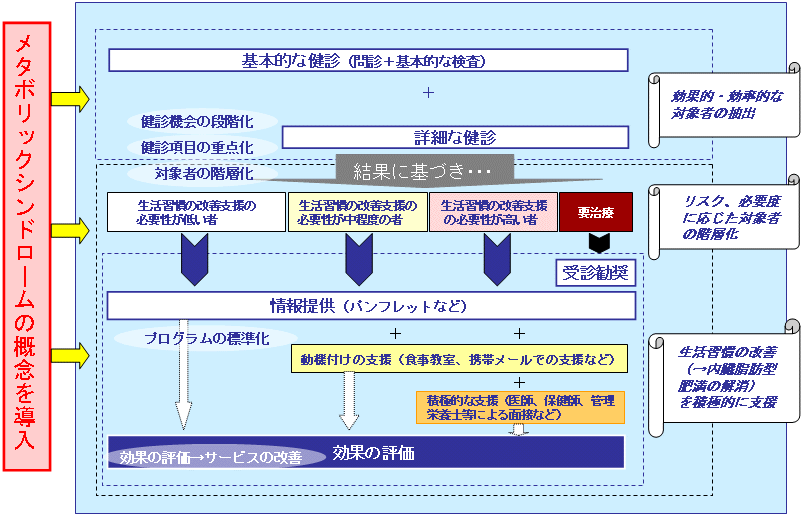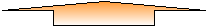| 第20回社会保障審議会医療保険部会 |
資料
3−1 |
| 平成17年9月21日 |
今後の生活習慣病対策の推進について
(中間とりまとめ)
概要
| 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会において、昨年10月以降、「健康日本21」の中間評価の作業を進めるとともに、これまでの生活習慣病対策の現状と課題及び今後の方向性について審議を行ってきたところであり、本年9月に、今後の生活習慣病対策の方向性について中間とりまとめを行った。その概要は以下のとおり。 |
| 1 |
これまでの生活習慣病対策の現状と課題
(これまでの生活習慣病対策の展開)
| ○ |
昭和53年からの第一次、昭和63年からの第二次の国民健康づくり対策に続き、平成12年からの「健康日本21」においては、健康寿命の延伸等を実現するため、健康づくりに向けた国民運動について基本的な方向を提示するとともに、9分野70項目にわたる具体的な目標を提示。 |
| ○ |
その後、「健康日本21」を中心とする健康づくり施策を推進する法的基盤として、健康増進法が制定。 |
| ○ |
「健康フロンティア戦略」では、生活習慣病対策について、がん対策、心疾患対策、脳卒中対策、糖尿病対策の具体的な数値目標が掲げられ、平成17年度から10年間、重点的に政策を展開。 |
(「健康日本21」中間評価における暫定データから見た現状)
| ○ |
「健康日本21」中間評価における暫定データからは、例えば、肥満者の割合や野菜摂取量、日常生活における歩数のように、「健康日本21」の策定時のベースライン値より改善していない項目や悪化している項目が見られるなど、これまでの進捗状況は必ずしも十分ではない点が見られる。 |
(生活習慣病対策を推進していく上での課題)
| (1) |
一次予防施策の課題
| ・ |
健康に関する情報の氾濫 |
| ・ |
日常生活で意識されるには目標項目を絞り込むことが必要 |
| ・ |
ターゲットが必ずしも明確ではなく、具体的な施策プログラムも不十分 |
| ・ |
個人の取組を支援する社会全体としての環境整備が不十分 |
|
| (2) |
二次予防施策の課題
| ・ |
生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導の徹底が不十分 |
| ・ |
若年期から生涯を通じた健康管理が不十分 |
| ・ |
科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底が必要 |
| ・ |
健診・保健指導の質の更なる向上が必要 |
|
| (3) |
推進体制の課題
| ・ |
国としての具体的な戦略やプログラムの提示が不十分 |
| ・ |
医療保険者、市町村等の責任・役割分担が不明確 |
| ・ |
関係者を総合調整する都道府県の役割が不十分 |
| ・ |
現状把握、施策評価のためのデータの整備が不十分 |
|
|
| 2 |
今後の生活習慣病対策の基本的な方向性
| 〜 |
国民の健康づくりに対する意識の高まりを具体的な行動変容に結びつけるために〜 |
| 〜 |
メタボリックシンドロームの概念を導入した対策の推進〜 |
| ○ |
健康に関心のある人が自主的に行う健康づくりの支援にとどまらず、健康に関心のない人や、生活習慣病の「予備群」でありながら自覚していない人に対し、「予防」の重要性や効果を認識してもらうため、社会全体として支える環境整備が必要であり、今後、「メタボリックシンドローム」の考え方を取り入れた生活習慣病対策を推進し、国民や関係者の「予防」の重要性に対する理解の促進を図っていくことが有効と考えられる。 |
| ○ |
さらに、生活習慣病の予防は、個人の健康度の改善や生活の質(QOL)の向上にとどまらず、国民の健康寿命の延伸や、さらに、特に若年期からの予防の徹底が医療費の適正化にもつながっていくことを、社会全体として積極的に評価していくべきである。 |
| 〜 |
エビデンスに基づく施策展開と事業の実績評価の推進〜 |
| ○ |
最新の科学的知見を実際の健康づくり施策や保健事業に反映させていくため、国の役割として、生活習慣病に関する研究や調査の成果をできる限り速やかに整理していくとともに、新しい科学的知見を不断に集積していくことが必要である。 |
| ○ |
生活習慣病対策の企画立案、評価等の基礎となる国民健康・栄養調査等については、(1)現状の把握、(2)目標値の設定、(3)事業の実績評価といった、効果的な施策を展開する上で重要である。各都道府県においても、地域の状況を的確に把握・評価する体制を 整備していくことが必要である。 |
| III |
生活習慣改善の効果的なプログラムの開発と普及 |
|
| 〜 |
ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの相乗効果〜 |
| ○ |
生活習慣病の「予備群」の発症予防を徹底するためには、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを適切に組み合せて対策を推進していくことが必要であり、これにより相乗効果が発揮できる。 |
| ○ |
ハイリスクアプローチでは、保健指導を中心に据えた一体的なサービスとして捉え直すことが必要である。また、生活習慣の改善については、「バランスの良い楽しい食事や日常生活の中での適度な運動」といった良い生活習慣は気持ちがいいという快適さや達成感をいかに実感してもらうかが重要である。 |
| IV |
個人の取組を社会全体で支えるための責任・役割の明確化 |
|
| 〜 |
都道府県の役割強化と産業界も含めた関係者との連携促進〜 |
| ○ |
個人の主体的な取組を社会全体で支援していくため、多様な関係者が具体的に連携を進めていくには、まず、関係者それぞれの責任・役割分担を明確にした上で、役割分担に基づいた具体的な施策ごとの連携方策を検討していくことが必要である。 |
| ○ |
特に、ハイリスクアプローチについては、今後は、医療保険者による保健事業の取組強化を図っていくことが必要である。
さらに、こうした多数の関係者間の役割分担と連携を進めていくためには、各関係者の総合調整を行う都道府県の役割が重要であり、都道府県の生活習慣病対策における役割強化が必要である。 |
|
| 3 |
今後の生活習慣病対策における具体的な対応方針
| I |
健康づくりの国民運動化(ポピュレーションアプローチ) |
|
| (1) |
メタボリックシンドロームの概念の普及定着
安易に薬に頼るのではなく運動習慣の徹底と食生活の改善が基本といった考え方を国民に広く普及するとともに、生活習慣改善の達成感や快適さを実感し、良い生活習慣は気持ちがいいものということを再認識し、継続した取組を支援する環境整備が重要である。
|
| (2) |
「健康日本21」の代表目標項目の選定
生活習慣病予防のため日常生活において具体的に何に取り組めばいいのかを国民にわかりやすく示すためにも、「健康日本21」の目標から選定した21の代表目標項目を普及啓発に積極的に活用することが必要であり、都道府県健康増進計画にも、地域の実情を踏まえつつ、具体的目標値を設定すべきである。
|
| (3) |
具体的な施策プログラムの提示
| 〜 |
「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」〜 |
| (1) |
身体活動・運動施策(「エクササイズガイド(仮称)」の策定、普及、活用等)
ライフスタイルに応じ、運動不足の解消を目指した具体的な実践方法等をわかりやすく示した「エクササイズガイド(仮称)」を策定し、フィットネス業界等の産業界や運動関連団体等を通じ、地域や職場を通じた普及活用を進めることが必要である。
|
| (2) |
栄養施策(「食事バランスガイド」の普及、活用等)
「何を」「どれだけ」食べればよいかをわかりやすく示した「食事バランスガイド」を、食品選択の場で積極的に活用していくことが重要であり、ファミリーレストラン、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の食品関連産業における情報提供や商品開発を進めるとともに、関係者が連携し、地域や職場を通じた普及啓発活動を進めることが必要である。
さらに、食育基本法が制定されたところであり、食育の国民運動としての展開の中で、「食事バランスガイド」の普及・活用等を一層図っていくことが必要である。
|
| (3) |
たばこ対策(禁煙支援マニュアルの策定、普及、活用等)
たばこ対策に関しては、喫煙率の低下の数値目標の設定、未成年者の喫煙防止対策として自動販売機の規制の大幅強化、受動喫煙防止対策の推進、たばこの価格又は税を引き上げ、その財源を生活習慣病予防対策に充当することの検討、といった意見が出された。こうした意見については、関係省庁が十分に連携し、検討、さらには取組を進めていくことが必要である。また、自主的な禁煙の試みを積極的に支援するため、禁煙を支援するマニュアルの策定、普及、活用を進めるとともに、喫煙率の低下についての新たな数値目標の設定の検討も含め、国民全体の喫煙率の低下を目指すべきである。 |
|
| (4) |
産業界も巻き込んだ国民運動の戦略的展開
国民運動として生活習慣病対策を推進していくためには、地域住民に対するポピュレーションアプローチの中心的な役割を市町村が果たす必要があるが、産業界が「エクササイズガイド(仮称)」や「食事バランスガイド」等を広く普及、活用していくことが重要であり、関連業界を始めとする幅広い産業界の自主的な取組との一層の連携が不可欠である。 |
| II |
網羅的・体系的な保健サービスの推進(ハイリスクアプローチ) |
|
| (1) |
メタボリックシンドロームの概念に基づく健診・保健指導の導入
ハイリスク者の「予防」を徹底していくためには、「予備群」を重点的な対象として、生活習慣改善の必要性が高い者を健診によって効率的かつ確実に抽出するとともに、効果的な保健指導を徹底していくことが必要である。このため、健診・保健指導について、メタボリックシンドロームの概念に基づき、生活習慣の改善支援という観点から一体のものとして捉え直した上で、保健指導を中心にその徹底を図っていくべきである。
|
| (2) |
若年期からの健診・保健指導の徹底
30歳代の3割が肥満であるといった現状を踏まえれば、メタボリックシンドロームの「予備群」に対する健診・保健指導の観点からは、40歳未満のより若年期からの健診・保健指導の徹底が必要と考えられることから、今後、40歳未満の者に対する健診・保健指導の在り方について検討すべきである。
|
| (3) |
健診機会の段階化と保健指導の階層化
網羅的な保健サービスの推進という観点から、基本的な健診により、リスクの度合いを効率的に把握した上で、基本的な健診でリスクがあると判断された者などに詳細な健診の受診勧奨を徹底することが、予備群の確実な抽出に有効と考えられる。
また、生活習慣の改善を支援する上で中心となる保健指導については、詳細な健診の結果を踏まえ、病態の重複状況や行動変容の困難さの度合い等に応じたサービスを効果的・効率的に提供するため、保健指導の必要度に応じた対象者の階層化を図ることが重要である。
|
| (4) |
保健指導プログラムの標準化
保健指導の実施に当たっては、対象者それぞれの健康に対する意識のレベルや、個々のライフスタイル等を理解した上で、それぞれの状況等に応じ、必要な時に、的確に、本人の自主的な行動変容の支援を行うことが重要であり、こうした保健指導については、国としても、保健指導プログラムを標準化し、その普及を図る必要がある。その際には、運動指導と栄養指導が一体的なものとして行われることが必要である。
|
| (5) |
健診項目の重点化、精度管理の徹底等
最新の科学的知見を具体的な健診事業に結びつける観点から、健診項目の重点化、精度管理の在り方等についての研究の成果をできる限り速やかに整理し、それを踏まえた取組を進めていくことが必要である。 |
| ○ |
糖尿病・循環器病対策については、メタボリックシンドロームの予防のための施策により生活習慣の改善を徹底することが基本であり、ポピュレーションアプローチとしての運動施策、栄養施策等の推進や、ハイリスクアプローチとしての健診・保健指導の徹底等が重要であるが、糖尿病・循環器病対策としては、こうした発症予防の取組だけでなく、診断・治療までを含めた総合的な対応も重要である。
特に糖尿病対策については、大規模な戦略研究を実施することとしているところであり、これらの成果を速やかに予防や診断・治療に活用していくことが重要である。また、関係団体等の取組を踏まえ、官民一体となった糖尿病対策を推進していくべきである。 |
| ○ |
がんは、喫煙等の不健康な生活習慣が発症の確率を高めはするものの、遺伝要因、病原体等の外部環境要因も発症に大きく関わるほか、発見された場合には直ちに手術や化学療法などの適切な治療を開始することが必要となる。したがって、がんについては、メタボリックシンドローム等の生活習慣病とは分けて対策を考えることが必要であり、禁煙支援等の発症予防や早期発見のためのがん検診の充実等のがん予防対策は、治療や緩和ケアまで含めた、がんの病態に応じた総合的な対策全体の中で考えられるべきである。 |
| (1) |
生活習慣病対策の推進に向けた関係者の責務と役割
生活習慣病対策を今後より一層推進していくためには、国民、国、都道府県、市町村、医療保険者等のそれぞれの役割を明確化し、その上で具体的な施策ごとに連携を進めていくことが重要である。
|
| (2) |
医療保険者による保健事業の取組強化
被用者保険の被保険者本人については、今後は、特にこれまで必ずしも十分には行われてこなかった保健指導について、より積極的な取組が必要である。
被用者保険の被扶養者及び自営業者等については、市町村と医療保険者の責任・役割分担が不明確となり、未受診者の把握や受診勧奨の徹底が必ずしも十分には行われてこなかった。
今後は、未受診者の把握、保健指導の徹底、医療費適正化効果まで含めたデータの分析・評価といった観点から、医療保険者による保健事業の取組強化を図っていくことが必要であり、医療保険者による保健事業の取組強化の内容等について、更に検討を進めるべきである。
|
| (3) |
健康づくりに関する都道府県の総合調整機能の強化と都道府 県健康増進計画の内容充実
関係者の役割分担を明確にした上で、連携を一層促進していくためには、関係者間の総合調整を図る都道府県の役割が重要である。今後は、都道府県が中心となって、医療保険者、市町村等の関係者が協議した上で、共通の目標の下、それぞれの実施主体の事業内容や事業量を明確化するとともに、具体的な連携事業を推進していくことが必要である。
このため、健康増進法に基づく都道府県健康増進計画の内容を充実し、
| (1) |
「健康日本21」の代表目標項目のほか、メタボリックシンドロームの概念に対応した目標項目について、地域の実情を踏まえ、職域を含めた具体的な数値目標の設定 |
| (2) |
医療保険者、市町村等の関係者の具体的役割分担と連携促進のための都道府県の総合調整機能の強化 |
| (3) |
各主体の取組の進捗状況や目標の達成度の評価の徹底 |
といった観点から、関係者が一体となった取組を進めていくことが必要である。
|
| (4) |
保健指導のアウトソーシング
今後、生活習慣病の予備群を中心にきめ細かく個別のニーズに対応していくためには、保健事業に係る市町村、医療保険者等の内部の実施体制のみでは十分に対応できないことが想定され、民間事業者は、医療機関等との連携により積極的なサービス展開を行うことが求められる。
良質な保健サービスを提供できる民間事業者を育成していく際には、医師、保健師、管理栄養士や運動指導の専門家等のマンパワーや、提供されるサービスの内容等について、一定の基準を設けることが必要であり、国として、医療保険者等が保健指導を民間事業者にアウトソーシングする際に考慮すべき基準を示したガイドライン等を策定し、提示することが必要である。
|
| (5) |
保健サービスのアウトカム評価の実施
保健サービスの質を評価する上で、その効果を見るためには単年度の結果では判断できず、継続的なデータの蓄積とその分析が必要になる。保険者協議会における医療費の分析評価などの実施状況も踏まえつつ、保健サービスのアウトカム評価の在り方について更に検討を進めるべきである。
|
| (6) |
市町村の保健師、管理栄養士等の役割
市町村の保健師、管理栄養士等については、介護予防、児童虐待などの他の業務との関係などを踏まえつつ、今後、健康づくり施策における企画・調整・評価等の業務に重点を置いていく方向で体制強化を図ることが必要であり、ポピュレーションアプローチ、ハイリスクアプローチそれぞれにおける市町村の保健師等の役割について検討していくことが必要である。 |
|
| 4 |
最後に
| ○ |
今後の生活習慣病対策の推進については、メタボリックシンドロームの概念を導入し、「健康づくりの国民運動化」としてのポピュレーションアプローチの推進とともに、「網羅的・体系的な保健サービスの推進」としてのハイリスクアプローチの徹底のため、科学的根拠に基づく効果的なプログラムの開発・普及、健診・保健指導の重点化・効率化、医療保険者による保健事業の取組強化、健康づくりに関する都道府県の総合調整機能の発揮と都道府県健康増進計画の内容充実などを中心に積極的な取組を進めていくことが必要である。
なお、特にポピュレーションアプローチについては、産業界も巻 き込んだ国民運動の戦略的展開が不可欠である。
|
| ○ |
現時点で残された主な検討課題としては、(1)「健康日本21」の中間評価、(2)医療保険者による保健事業の取組強化の具体的な内容とそれを踏まえた老人保健事業の見直し、(3)基本的な健診と詳細な健診の具体的な内容、(4)保健指導プログラムの標準化、(5)保健指導 のアウトソーシングの在り方、(6)メタボリックシンドロームの概念に対応した指標の設定などが挙げられるが、これらはいずれも今後の生活習慣病対策を進めるに当たっての鍵となるものであり、引き続き精力的な検討を進めていくべきである。 |
|
今後の生活習慣病対策の推進について
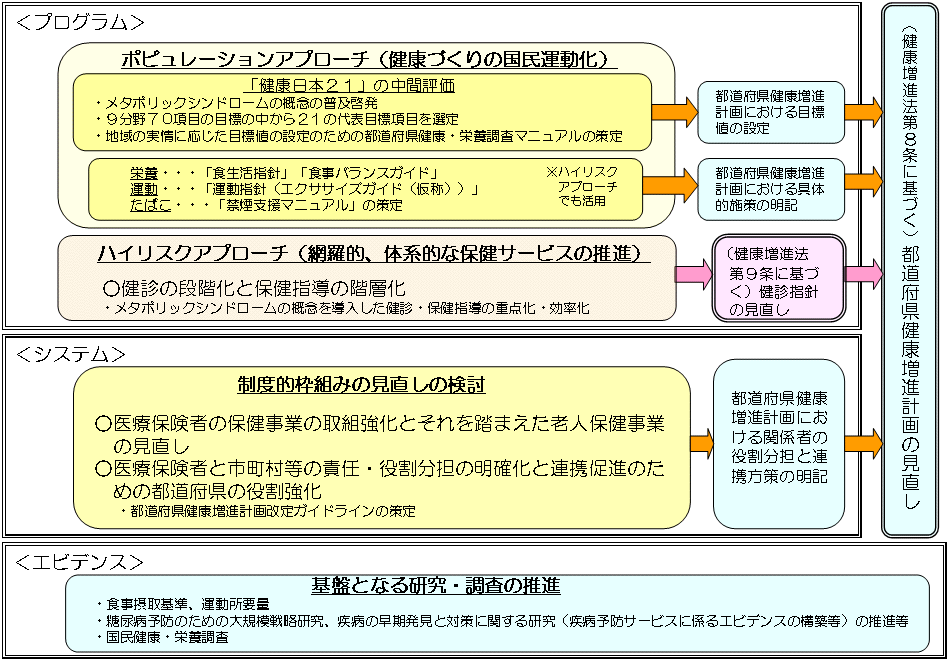
「健康日本21」における代表目標項目
| 一次予防(健康増進、健康づくり) |
| 栄養・食生活 |
適正体重を維持している人の増加 |
| 脂肪エネルギー比率の減少 |
| 野菜の摂取量の増加 |
| 朝食を欠食する人の減少 |
| 身体活動・運動 |
日常生活における歩数の増加(成人、高齢者) |
| 運動習慣者の増加 |
| 休養・こころの健康づくり |
睡眠による休養を十分にとれていない人の減少 |
| たばこ |
未成年者の喫煙をなくす |
| 公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及 |
| 禁煙支援プログラムの普及 |
| アルコール |
多量に飲酒する人の減少 |
| 未成年者の飲酒をなくす |
| |
| 二次予防(疾病の早期発見、早期対策) |
循環器病
(糖尿病) |
健康診断を受ける人の増加
(糖尿病検診の受診の促進) |
| がん |
がん検診の受診者の増加 |
| 糖尿病 |
糖尿病検診受診後の事後指導の推進 |
| |
| 疾病の発症、死亡者等の減少 |
| 休養・こころの健康づくり |
自殺者の減少 |
| 歯の健康 |
(学齢期のう蝕予防)一人平均う歯数の減少 |
| (歯の喪失防止)80歳で20歯以上、60歳で24歯以上の自分の歯を有する人の増加 |
| 糖尿病 |
糖尿病有病者の増加の抑制(推計) |
| 循環器病 |
高脂血症の減少 |
| 生活習慣の改善等による循環器病の減少(推計) |
健診から保健指導への流れ(イメージ図)
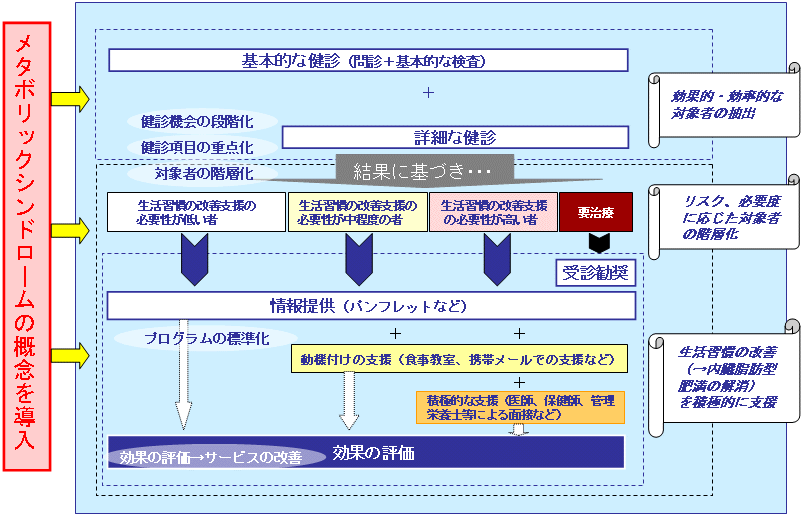
都道府県健康増進計画の見直しに関する国の具体的支援
| 都道府県健康増進計画の見直しの基本的な方向性 |
| 1 |
地域の実情を踏まえた具体的な数値目標の設定
| ・ |
「健康日本21」の代表目標項目を始めとして、地域の実情を踏まえた地域住民にわかりやすい目標値を提示。 |
|
| 2 |
医療保険者、市町村等の関係者の役割分担・連携促進のための都道府県の総合調整機能の強化
| ・ |
都道府県の総合調整の下、関係者が協議して、具体的施策に即し、医療保険者、市町村等の役割分担を明確化するとともに、関係者間の連携を促進。 |
|
| 3 |
各主体の取組の進捗状況や目標の達成度の評価の徹底
| ・ |
各主体の取組の進捗状況や目標の達成度について、都道府県が定期的に評価し、計画の見直しに反映。 |
|
|
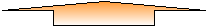
| 都道府県健康増進計画の見直しに関する国の具体的支援 |
| 1 |
都道府県健康・栄養調査マニュアルの策定
| ・ |
「健康日本21」の代表目標項目について、各都道府県で地域の実情を踏まえた目標値の設定を支援する観点から、目標値設定のための現状把握等に資するよう、各都道府県が実施する健康・栄養調査等に関するマニュアルを策定。 |
|
| 2 |
地域・職域連携推進協議会の設置支援
| ・ |
都道府県の総合調整の下、医療保険者、市町村等の関係者が、具体的施策に即したそれぞれの役割分担や連携方策について協議する場である、地域・職域連携推進協議会の設置を支援。 |
|
| 3 |
都道府県健康増進計画改定ガイドラインの策定
| ・ |
(1)目標項目の選定、(2)関係者の具体的な役割分担と連携促進、(3)各主体の取組の進捗状況や目標の達成度の評価等に関する基本的な考え方を示した都道府県健康増進計画改定のためのガイドラインを策定。 |
|
|