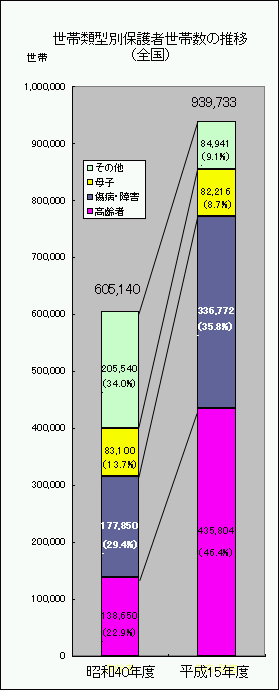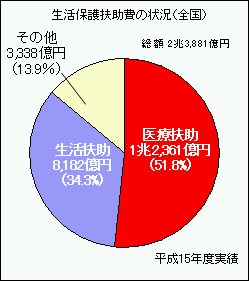厚生労働省提出「生活保護及び児童扶養手当に関する問題提起」 |
高知市長 岡﨑誠也
| I | 生活保護に関する問題提起について |
| 1. | 「生活保護業務における国と地方の役割分担」について |
| ○ | 国は、法律を制定し、制度の基本的な枠組み、基準の設定や保護の決定・実施の要件などを定め、また、国の責務に相応しい高率の費用負担を行い、憲法第25条の趣旨に沿った責任を果たすことが基本である。 |
| ○ | その上で、保護の決定・実施などの生活保護事務について、
|
| 2. | 「地方分権の流れと生活保護業務」について |
| ○ | 平成12年の地方分権改革により、機関委任事務が廃止され、生活保護については、旧厚生省の強い意向により、法定受託事務とされた。 |
| ○ | これは、(1)生活保護の決定・実施に関する事務は、現金給付等の生活困窮者の扶助に関わるものであり、生存にかかわるナショナル・ミニマムを確保し、全国一律に公平・平等に実施する必要がある、(2)生活保護は、国が本来果たすべき役割であって、国において適正な執行を特に確保する必要がある、との考えのもとに、自治事務としてではなく、国の関与の強い法定受託事務として制度化されたものである。 |
| ○ | また、生活保護法において、国の指揮監督権は廃止されたが、地方自治法において、法定受託事務について国の強い関与(是正の指示、代執行等)が一般ルールとして認められ、個別具体に関与することができるとされている。更に、一般ルールのほかに、生活保護法において、特に国による事務監査の規定が置かれている。 |
| 3. | 「問題提起」について |
| (1) | 「生活保護事務実施に当たっての地方自治体間の較差」について |
| 地方自治体間の較差については、社会的、経済的、歴史的等の要因によるところが大きく、そのような中で、各地方自治体は懸命に努力しているところである。 被保護世帯の状況などの実態が同じにもかかわらず、実施状況に適正を欠くほどの幅が出ているという、具体的な根拠を明らかにした上で、問題提起をすべきである。 |
| (2) | 「今後の生活保護業務における国と地方の役割分担」について |
| (1)「地域別の生活保護基準の在り方」について 生活保護事務は、国の責任において、全国一律に公平・平等に実施されるべきもので、制度上、年齢、家族構成、級地区分、各種扶助等の分類を踏まえて生活保護基準を定めることが基本であり、地方に裁量の幅はない。また、生活保護に係る基本的事項について、地方自治体がそれぞれの基準を定めることは、生活保護制度の趣旨に反する。 収入認定や資産保有、扶養家族等について国が基準を定めることとしても、地方自治体の取扱いに差を認めるのであれば、例えば、A県で収入認定された収入が、B県では収入と認定されないなどといった実態が生まれ、結果的に最低限度の生活内容に較差が生じ、不公平を生じることとなる。 |
| (2)「自立・就労支援の在り方」について 年金、失業保険等は、国が行っているものであり、それぞれ重要な施策であるが、地方自治体の事務ではない。生活保護法上、被保護者の自立助長のための相談・助言のみが自治事務とされている。 自立支援プログラムは、従前から地方自治体が行ってきた「他法他施策の活用」への新たな一形態に過ぎず、裁量の拡大とは本質的に視点を異にするものである。 自立支援プログラムの具体的な仕組みや法的位置付けなどが明らかでない。 |
| (3) | 「地方自治体の裁量の拡大に伴う生活保護費国庫負担金の在り方の見直し」について |
| 問題提起に挙げられている「地方自治体の裁量の拡大」は、国庫負担金の見直しの議論にはつながらない。また、同負担金の見直しを行っても、地方の自由度は高まらず、三位一体改革の趣旨に沿うものではない。 |
| II | 児童扶養手当に関する問題提起について |
児童扶養手当の認定基準は収入のみであり、地方自治体に裁量の余地はない。
国庫負担割合の引下げは、単なる地方への負担転嫁に過ぎない。
生活保護制度の現状について
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次のような各種の地域要因により、保護率に大きな差が生じている。 |
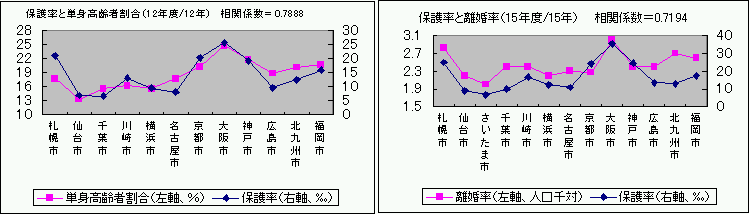 | |||
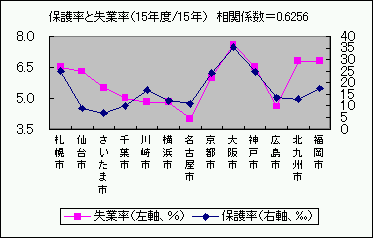 |
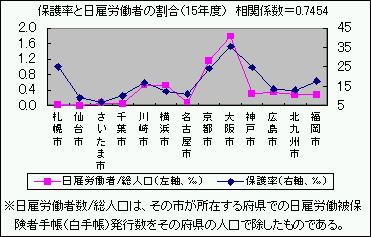 | ||
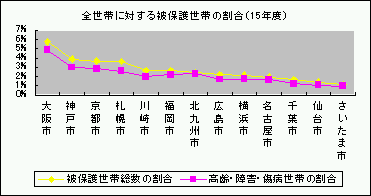 |
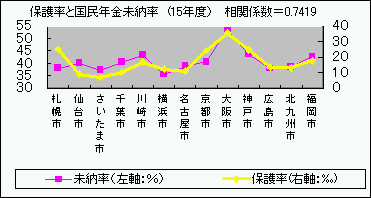 | ||
| ||||||||||||||||||