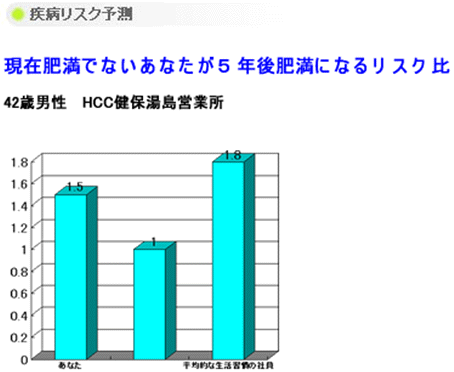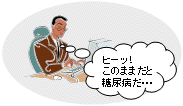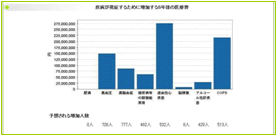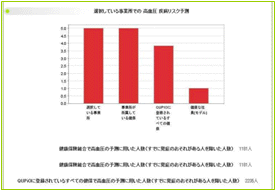資料2(古井先生資料)
実効性ある保健事業の可能性
〜職域保険者の事例に基づいて〜
実効性ある保健事業の可能性
〜職域保険者の事例に基づいて〜
「生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会」第2回資料
「実効性ある保健事業の可能性」
〜職域保険者の事例に基づいて〜
2005年8月4日
〜職域保険者の事例に基づいて〜
2005年8月4日
| 古井祐司 博士(医学) yfurui-tky@umin.ac.jp 東京大学医学部附属病院22世紀医療センター健診情報学講座教官 HCC代表/NPO法人メディカル・ブリッジ理事長 |
| 1 | リスク者に対する保健事業(生活習慣改善指導プログラム) |
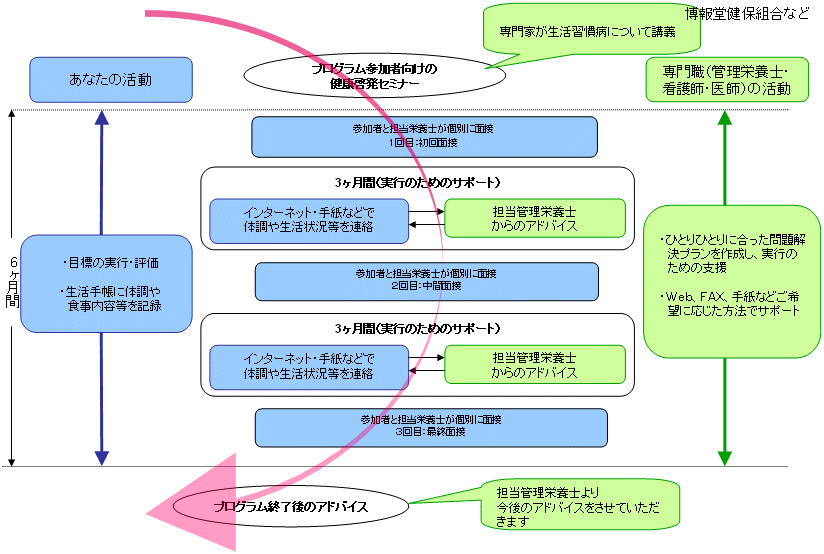
健康度の改善効果
| 生活習慣病になりかけている状態を放置しておけば、動脈硬化の原因となり、重症化して狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの大きな疾患の危険因子となります。一度、発症してしまうと、仕事や普段の生活にも大きな影響を与え、医療費の増大もまねきます。 下表に挙げているこれらの項目を改善することは、ダイレクトに重症化防止につながります。 今回の一次予防プログラムでは、継続率が94%(91名)ということだけではなく、主な健診項目についても、それぞれ4割〜7割の方が改善しており、意識の変容が取組み姿勢、行動変容につながり、結果として客観的な健康指標の改善にも現れました。 |
| 目標達成度別のグループ例 | 体重 減少 | 総Chol 減少 | HDL-Chol 上昇 | 中性脂肪 減少 |
| 目標達成 | 72.7% | 63.6% | 100% | 63.6% |
| 目標未達成 | 43.8% | 50.0% | 75.0% | 50.0% |
| 資料) | HCC予防医学研究センター 健保組合会、厚労省健康フロンティア戦略推進室報告資料改変 |
医療費増加の軽減効果
| 今回の個別指導プログラムでは、健康度の改善効果と同時に、医療費の増加抑制効果が見られました。ただ、単年度では一次予防プログラムでは費用対効果が示されませんでした。 下表に示したように、実施群と非実施群(いずれも健診で要指導と判定されたハイリスク者)とで比較すると、非実施群は医療費が31%増加している一方で、実施群では15%程度となっており、医療費増加が16%抑制されたことが示されました。 なお、今後、数年間継続して評価していくと、疾病管理をせずに放置された場合に生活習慣病が重症化・合併症化して年間数百万円の医療費となるケース自体を防止し、より大きな医療費軽減効果が認められる可能性が考えられます。 また、今回の対象は、いわゆる生活習慣病の予備群であることから医療費の額自体が大きくありませんが、ハイリスク者を対象とした場合(三次予防を含む)には、より大きなインパクトが考えられます。 |
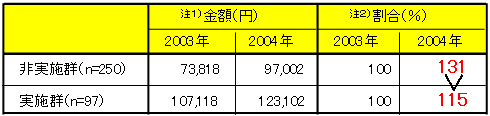
| 注1) | 「未実施群」「実施群」について、プログラム実施前の2003年、プログラム実施後の2004年の医療費を各年ともにレセプトの疾病コードを把握している6〜7月分を集計し年間に換算した金額 |
| 注2) | 「未実施群」「実施群」ともに、2003年の医療費を100とした割合 |
| 資料) | HCC予防医学研究センター 健保組合会、厚労省健康フロンティア戦略推進室報告資料改変 |
三次予防の事業スキームの可能性
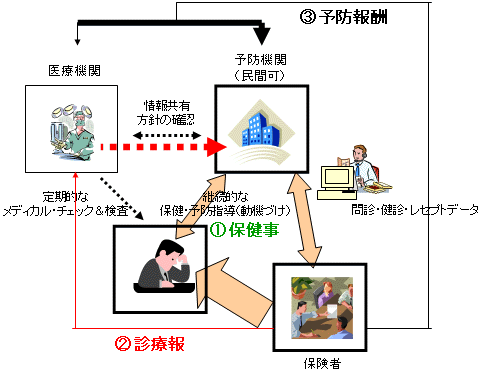
| 2 | 被保険者全体に対する保健事業 | (健康チェック(問診)/対象者の層別化/情報提供/動機づけ支援までの包括プログラム) |
富士写真フィルム健保組合など
実施の理念
富士写真フィルム健康保険組合組合会より
|
富士写真フィルム健康保険組合組合会より
| 主要機能の概要(1) | 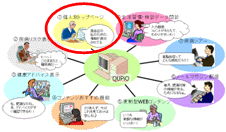 |
|
| ・ | 被保険者・被扶養者ごとに自分用のページが作成される |
| ・ | このトップページから、種々の機能が表示され、必要に応じてそこに行ける |
 |
| 2 | 被保険者全体に対する保健事業 | (健康チェック(問診)/対象者の層別化/情報提供/動機づけ支援までの包括プログラム) |
| 主要機能の概要(2) | 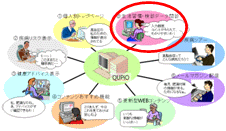 |
|
| ・ | 健診データや生活習慣を被保険者・被扶養者がIT上で入力できる機能 |
| ・ | 被保険者・被扶養者を飽きさせず、入力してもらう工夫あり |
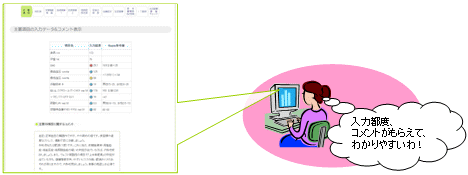 |
| 2 | 被保険者全体に対する保健事業 | (健康チェック(問診)/対象者の層別化/情報提供/動機づけ支援までの包括プログラム) |
| 主要機能の概要(3)-1 | 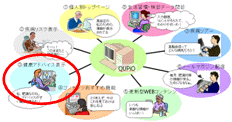 |
|
| ・ | 被保険者・被扶養者が、自分の健康データの数値、意味を確認し、健康データにそった(リスクに応じた)アドバイスを受けられる |
| ・ | 健康データ画面で健康データを確認し、前回値と今回の健康データとの比較も、経年でデータを入れることで可能となる |
| ・ | 専門用語で分かりにくい健康データの意味を解説する機能がある |
| ・ | 個々人の健康データをもとに、被保険者・被扶養者各人のリスクに応じた健康状態を改善するためのアドバイスを表示 |
| ・ | 動脈硬化を進行させる肥満、高血圧、高脂血症、耐糖尿異常の4つの危険因子をいくつ持っているか判定し、表示する |
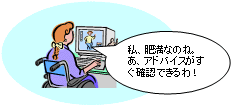 |
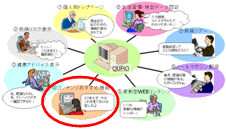 |
|
| ・ | 被保険者・被扶養者の健康状況やサイトのアクセス状況から、その人が読むべき情報、興味がある情報を常に画面上へ「おすすめ」機能として表示、情報提供を行います |
| ・ | クリックした先の内容が本当に必要なものであること、興味深いものが多くなり、サイトアクセスへの動機づけとなります |
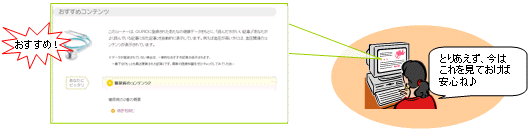 |
| 主要機能の概要(3)-3 | 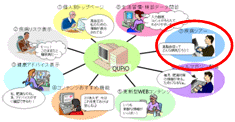 |
|
| ・ | 生活習慣病、肥満症、高血圧症、高脂血症、糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞・狭心症、アルコール性肝疾患などの疾病について、インターネットで相互通信しながら学習できるコンテンツ |
| ・ | 「(3)-2おすすめ機能」から被保険者・被扶養者に推薦され、案内に従って進むことで、簡単に疾病について理解できるツアー構造となっている |
| ・ | 医学的な正しさと健康行動理論が融合した内容 |
 |
| 主要機能の概要(3)-4 | 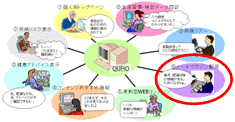 |
|
| ・ | 被保険者・被扶養者が自分の健康状況に合わせたメールマガジンを受信することが可能 |
| ・ | 今までの画一的な健康情報から、被保険者・被扶養者個人が必要な情報・気になる情報を自動的・定期的に受け取ることができ、効果的な健康意識向上が期待できる |
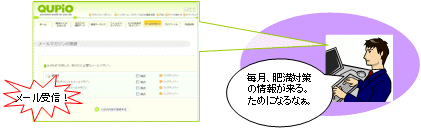 |
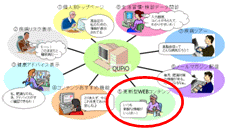 |
|
| ・ | 「健康日本21」の内容に基き、エビデンスの確かな情報をわかりやすい文章で解説 |
| ・ | 「健康レシピ」「糖尿病」「メンタルヘルス」など20タイトルを毎月1回更新 |
| ・ | 信頼性を重視した正しい健康・医療情報の提供 |
| ・ | 「(3)-2おすすめ機能」が自動的に働き、被保険者のマイページに読むべき内容をリストアップ |
| ・ | 被保険者・被扶養者が必要な情報・興味ある情報を中心に提供 |
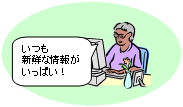 |
| 2 | 被保険者全体に対する保健事業 | (健康チェック(問診)/対象者の層別化/情報提供/動機づけ支援までの包括プログラム) |
| 主要機能の概要(4) | 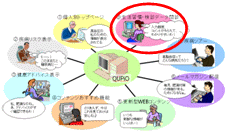 |
|
| ・ | 個々人の健康データをもとに、被保険者・被扶養者それぞれが今後5年間で疾病にどのくらい罹りやすいかをリスク比で表示 |
| ・ | 予測できる疾病は、肥満、高血圧、高脂血症、耐糖能異常(糖尿病等)、脳梗塞、心筋梗塞・狭心症、アルコール性肝疾患、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の8疾病 |
| ・ | エビデンスに基くアルゴリズムが予測を導き出す |
| ・ | 将来予測を示すことで健康維持・改善に取り組む動機づけにつながる |
|
|
| 3 | 被扶養者全体を含むモデル的保健事業 |
新日鐵健保組合など
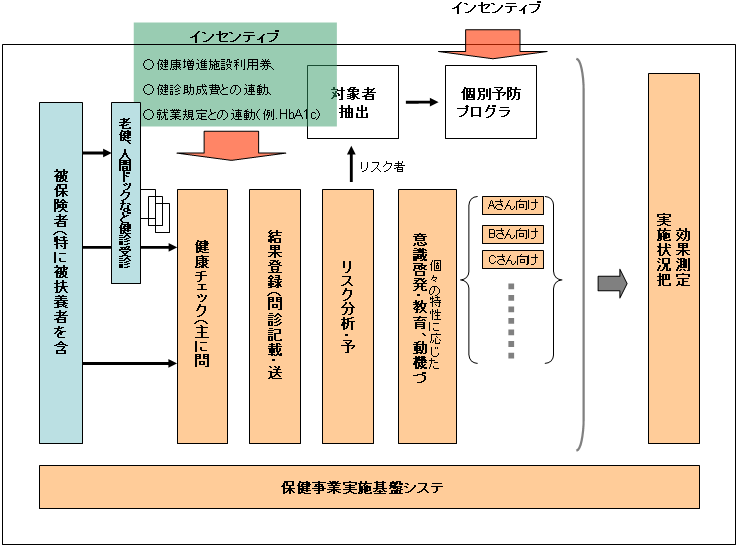 |
【参考】 健保組合を取り巻く環境など
予防により病気の重症化及び高医療費の要因を絶つ
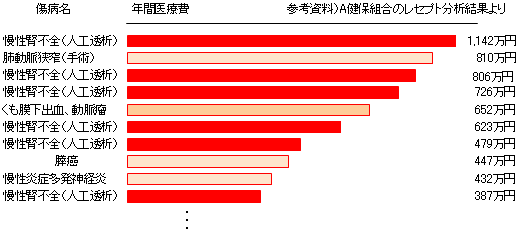
厚生労働省辻元保険局長との意見交換会資料より
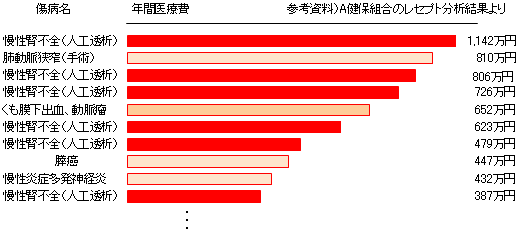
|
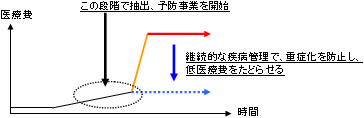 |
「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」
2004年7月30日厚生労働大臣告示より
・ ・
|
保健事業(健診・事後指導)の考え方
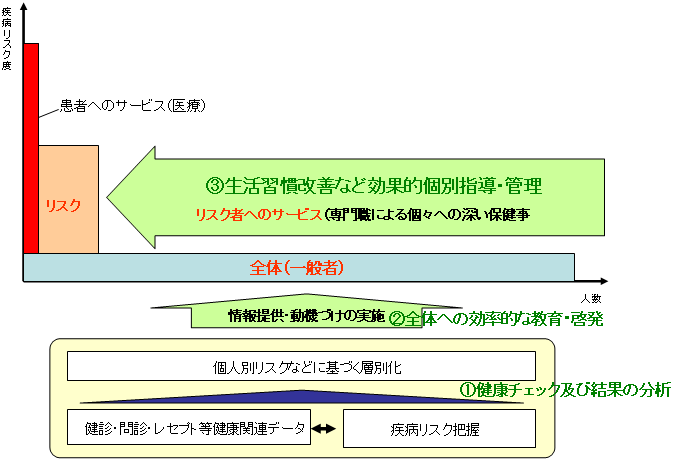
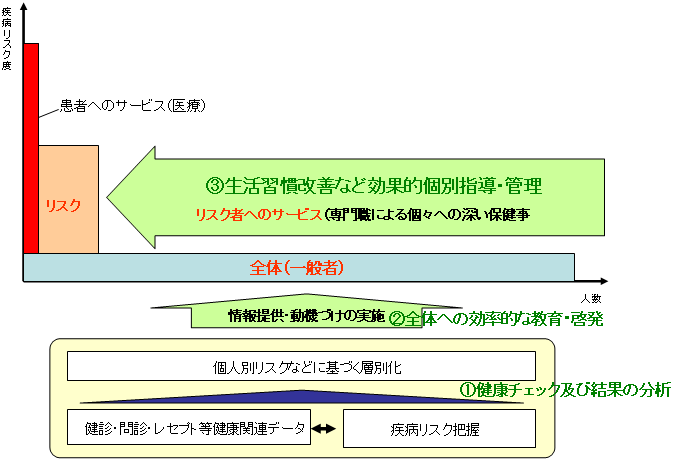
| 平成16年度厚生労働省科学研究特別研究事業「最新の科学的知見に基づいた保健事業に係る調査研究」(主任研究者福井次矢)改変 |
保健事業(健診・事後指導)の流れ
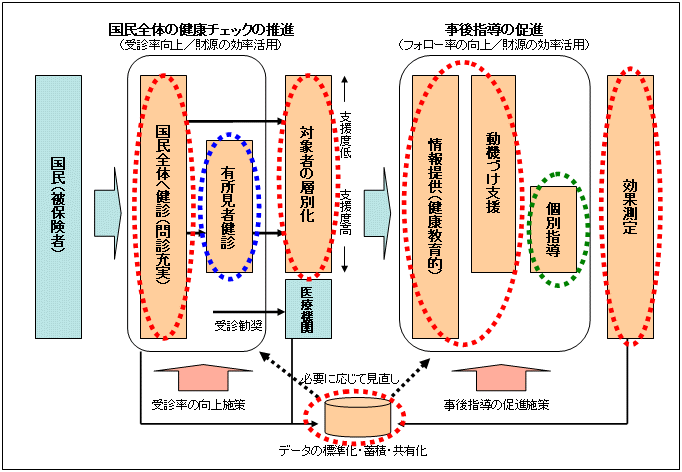
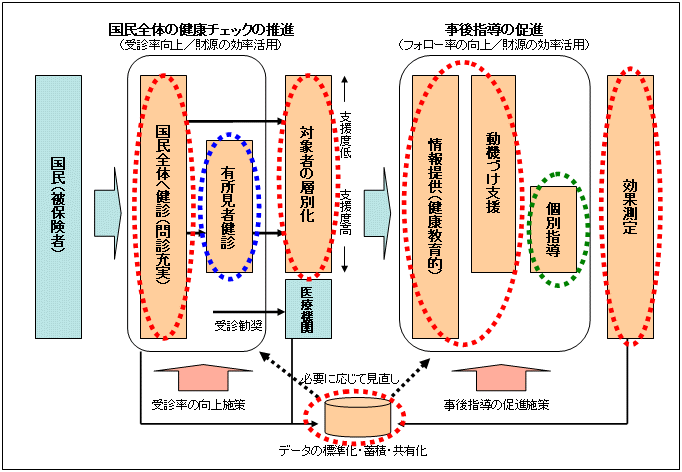
| 平成17年度厚生労働省科学研究健康科学総合研究事業「疾病予防サービスに関する研究」(主任研究者東大病院院長永井良三)第2回連絡会議改変 |
保健事業(健診・事後指導)の事業費(例)
| * | それぞれの数値については、今後、精査・検討が必要 |
|
| 保険者機能の有効活用に向けた検討開始〜関係機関との共同のもと 2001・2002年度厚生労働科学研究「保険者機能の在り方に関するモデル研究」 |
|
関連記事(平成14年5月3日 日経新聞朝刊 1面&社会面)
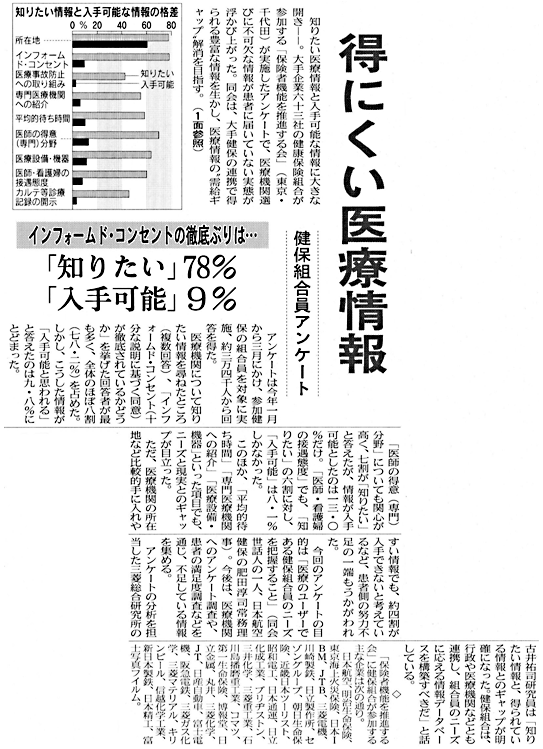 |
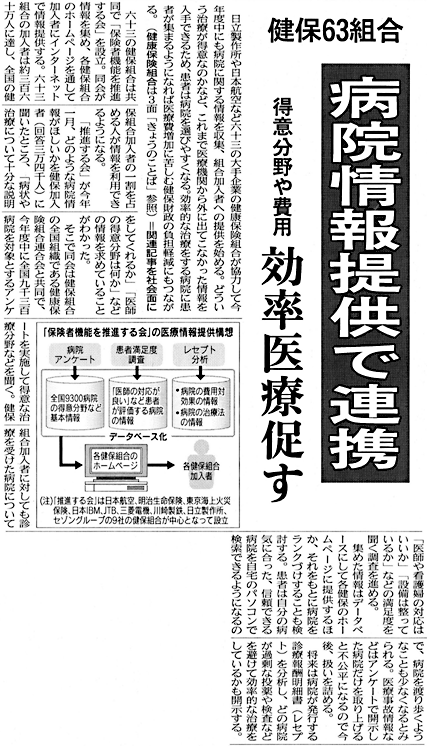 |