| 第17回社会保障審議会医療保険部会 | 資料2 |
| 平成17年7月29日 |
| ○ | 高額療養費制度の在り方について |
| ○ | 医療保険における食費・居住費の在り方について |
| ○ | 現金給付の在り方について |
| ○ | 高額療養費制度における自己負担限度額の基準について、昭和48年の制度創設時に月収の50%であったことを踏まえ、平成14年改正において、月収の22%から25%に3%引き上げたこと、及び平成15年度から総報酬制が導入されたことを勘案し、現行の基準をどう考えるか
|
| ○ | 高額な医療費について、医療サービスを受ける者と受けない者の負担の公平を図る観点から、低所得者を除いて、定額の限度額を超える部分について求めている医療費の1%の負担をどう考えるか |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| (備考) | ・ | 金額は1月当たりの限度額。 |
| ・ | ( )内の額は、多数該当の場合(4月目以降)。 |
|
| ○ | 当時定額負担であった被保険者本人と異なり、定率負担の被扶養者の負担軽減措置として、月収の50%程度の自己負担限度額で創設 |
|
| ○ | 被保険者本人に定率1割負担が導入されたことに伴い、本人についても対象とし、世帯合算、多数該当、高額長期疾病(1万円特例)を創設 |
|
| ○ | 所得が高い者ほど所得に占める医療費の実質的な負担率が低いため、負担の均てん化を図る観点から、自己負担限度額の高い上位所得者区分を創設 |
| ○ | 医療を受けた者とこれを支える者の負担の公平やコスト意識の喚起の観点から、医療費連動の1%負担を創設 |
|
| ○ | 所得水準の上昇に見合った引上げが行われず、14年改正前の時点で、自己負担限度額が月収の22%程度であったため、負担のバランスを図る観点から、制度創設当初は50%程度であったことを踏まえ、月収の4分の1(25%)程度に引上げ |
| 改定年度 | 自己負担限度額 (A) |
標準報酬月額の平均値 (B) |
割合(A/B) |
| S48 | 30,000 | 59,241 | 51% |
| S51 | 39,000 | 105,832 | 37% |
| S59 | 51,000 | 189,548 | 27% |
| S61 | 54,000 | 207,362 | 26% |
| H元 | 57,000 | 224,360 | 25% |
| H3 | 60,000 | 244,616 | 24% |
| H5 | 63,000 | 270,214 | 23% |
| H8 | 63,600 | 289,694 | 22% |
| H12 | 63,600+1% | 290,701 | 22% |
| H14 | 72,300+1% | 289,700 | 25% |
| ※ | 標準報酬月額の平均値は、原則として改定年度の前年度の数値 |
| (1) | 胃がん(医療費約150万円・30日入院)の場合の自己負担額(一般)
|
|||||
| (2) | 大動脈解離(医療費約3,000万円・15年度最高月額)の場合の自己負担額(一般)
|
|||||
| (3) | 入院レセの平均医療費(約39万円・16日入院)の場合の自己負担額(一般)
|
| (1) | 食費 |
| ○ | 医療保険における食費については、「入院時食事療養費」として評価されており、被保険者等は、所得等に応じて、平均的な家計における食費を勘案した標準負担額を負担 |
| ※ | 標準負担額は、食材費相当額を踏まえ、所得に応じて1日につき780円・650円・500円・300円となっており、基準額(1日につき1,920円)から標準負担額を控除した額が入院時食事療養費として給付 |
| (2) | 居住費 |
| ○ | 医療保険における居住費については、療養の給付として入院基本料において包括的に評価されており、これに伴う定率負担 |
| ※ | 病院の療養病棟に入院した場合には、療養病棟入院基本料として、1日につき1,209点(=12,090円)を評価 |
介護保険給付と年金給付との調整、在宅と施設の給付と負担の公平性の観点から、介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)における食費及び居住費について、以下のとおり、保険給付外・利用者負担とする。(平成17年10月施行)
| (1) | 食費 |
<現行>
| ○ | 介護保険における食費については、「基本食事サービス費」として評価されており、被保険者等は、所得に応じて、平均的な家計における食費を勘案した標準負担額を負担 |
<見直し後>
| ○ | 基本食事サービス費を廃止(栄養管理については、施設サービス費の加算として評価) |
| ○ | 調理コスト及び材料コスト相当を利用者負担(4.2万円〔1人当たり月額モデル負担額〕) |
| (2) | 居住費 |
<現行>
| ○ | 介護保険における居住費については、施設介護サービスとして包括的に評価されており、これに伴う定率を負担 |
<見直し後>
| ○ | 施設介護サービス費から、多床室については光熱水費相当(1.0万円〔1人当たり月額モデル負担額〕)を、個室については減価償却費及び光熱水費相当(6.0万円〔1人当たり月額モデル負担額〕)を保険給付外・利用者負担 |
|
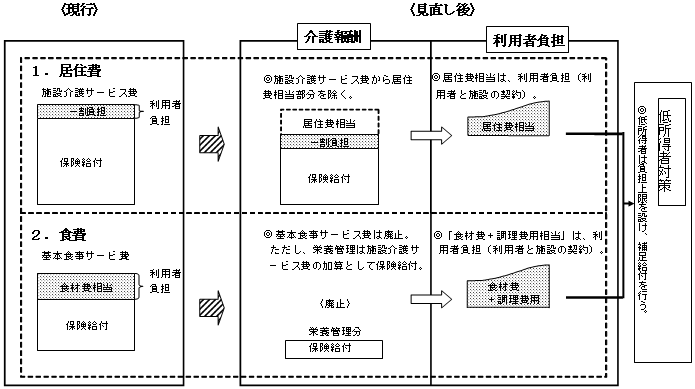
| 介護療養型医療施設の入所者(要介護5・甲地)における利用者負担の変化 (モデル 万円/月) |
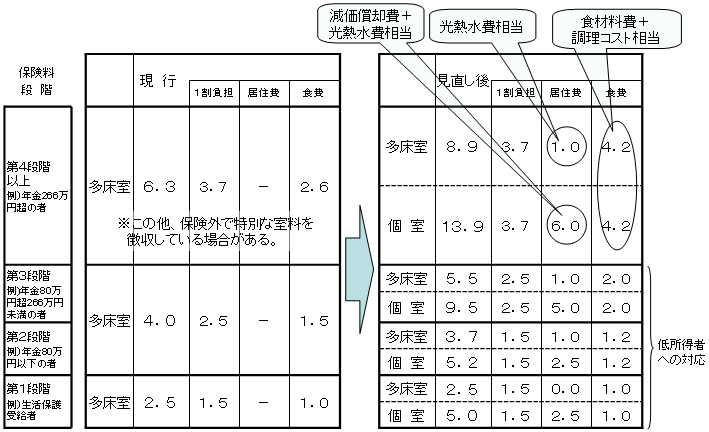
| ○ | 疾病又は負傷に関する療養の給付等のほか、休業補償や実費補償として行われている以下の現金給付についてどう考えるか |
| ・ | 出産育児一時金 |
| ・ | 出産手当金 |
| ・ | 傷病手当金 |
| ・ | 埋葬料 |
| (1) | 出産育児一時金について |
| ○ | 出産費用の負担の軽減を図るため、医療機関における分娩料の状況等を踏まえ、現在30万円(*)を支給
(参考1)
(参考2)出産育児一時金の財源
|
| 分娩費 | 育児手当金 〔本人・配偶者とも〕 |
||
| 本人 | 配偶者 | ||
| 昭和36.6.15 | (6,000円)※2 |
3,000円 | 2,000円 |
| 昭和44.9.1 |
|
10,000円 | |
| 昭和48.10.1 |
|
60,000円 | |
| 昭和51.7.1 |
|
100,000円 | |
| 昭和56.4.1 |
|
150,000円 | |
| 昭和60.4.1 |
|
200,000円 | |
| 平成4.4.1 |
|
240,000円 | |
| 平成6.10.1 | 300,000円〔本人・配偶者とも定額〕 〔分娩費及び育児手当金を統合し、「出産育児一時金」を創設〕 |
||
| 平成14.10.1 | 対象者を本人又は配偶者から、全被扶養者に拡大 | ||
| ※1 | 育児手当金創設(昭和36年6月15日)以後の変遷 |
| ※2 | ( )内は最低保障額 |
出産育児一時金
家族出産育児一時金
出典「事業年報(平成14年度)社会保険庁」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 出産手当金について |
| ○ | 出産のため労務に服さなかったことによる所得の喪失または減少を補うため、産休中(出産日以前42日から出産日後56日まで)の間、1日につき標準報酬日額の6割相当額を健康保険から支給 |
| ○ | 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格喪失日後6ヶ月以内に出産した場合にも支給 |
| ○ | 任意継続被保険者に対しても支給 (参考)資格喪失日後6ヶ月以内に出産した場合の支給の意義について
|
出典「事業年報(平成14年度)社会保険庁」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 傷病手当金について |
| ○ | 被保険者が業務外の事由による療養のため労務不能となった場合、労務不能の期間中、最長で1年6ヶ月間、1日につき標準報酬日額の6割相当額を健康保険から支給 |
| ○ | 任意継続被保険者に対しても支給 |
(参考1)
| ・ | 制度創設当時(大正12年)の家計調査により、報酬の60%程度が家計の生活必需品(衣食住)に充てられているものと推定された。 |
| ・ | 直近(平成14年)の家計調査では、報酬の41.6%が衣食住に充てられている。 |
(参考2)
| ・ | 休業中等の各種給付について(別添) |
別添
| 傷病手当金 | 出産手当金 | 休業補償給付 | 育児休業給付 | 介護休業給付 | 失業保険給付 | |
| 内容 | 業務外の事由による療養中、賃金日額の60%相当額を、最長1年6ヶ月支給 | 出産による休業中、賃金日額の60%相当額を、出産日以前42日から出産日後56日までの期間支給 | 業務上の事由による療養中、賃金日額の60%相当額を、休業期間中支給 | 育児休業中の賃金日額の40%相当額を、育児休業期間中支給 | 介護休業中の賃金日額の40%相当額を、最長3ヶ月間支給 | 離職時の賃金日額の50%〜80%(賃金日額の額に応じて設定)相当額を、失業期間中の雇用保険加入期間及び失業事由に応じた期間(90日〜330日)支給 |
| 支給割合の考え方 | 大正12年の重要工業地域における労働者家計調査で、報酬の60%程度が生活必需費に充てられているものと推定されたため | 傷病手当金に準じて設定 | 「業務災害の場合における給付に関する条約」(第3号)により60%以上と定められており、また、旧工場法における60%を踏襲 | 出産期の女性が失業した場合の、失業給付の給付率(50%以上)との均衡や、育児休業中の者は社会保険料が免除されていること(約10%相当)を考慮して40%に設定 | 育児休業給付に準じて設定 | 失業者の再就職を支援するための失業期間中の一時的な期間の保障するため(最低基準を60%よりも低く設定) |
| 我が国が批准したILO条約における支給基準 | 45%(※1) (社会保障の最低基準に関する条約) 【1976年批准】 |
45%(※2) (社会保障の最低基準に関する条約) 【1976年批准】 |
60% (上記参照) 【1974年批准】 |
なし (家族的責任を有する労働者条約) 【1995年批准】 |
なし (家族的責任を有する労働者条約) 【1995年批准】 |
45%(※3) (社会保障の最低基準に関する条約) 【1976年批准】 |
| ※1 | 医療及び疾病給付に関する条約においては、60%の水準を求めているが、予防医療への保険給付について求めているため未批准 |
| ※2 | 母性保護条約においては、3分の2の水準を求めている等のため未批准 |
| ※3 | 雇用の促進及び失業に対する保護条約においては、年齢に基づく給付差別の禁止等を求めているため未批准 |
| (参考) 厚生年金給付・・・ | 現役の賃金の一定割合を保障するという考え方に立って給付額を設定 標準的な高齢者夫婦のモデル年金額は、現役の賃金の59.3%(平成16年度)、50.2%(平成35年度)
|
出典「事業年報(平成14年度)社会保険庁」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 埋葬料について |
| ○ | 被保険者が死亡した場合、死亡した被保険者の収入により生計を維持していた者で葬儀を行うべきもの等に対し、被保険者の標準報酬月額相当額(最低保障10万円)を健康保険から支給 |
| ○ | また、被扶養者が死亡した場合、被保険者に対し、定額10万円の家族埋葬料を支給 |
| (参考) | 被保険者本人の最低保障額(被扶養者は定額)は、最低葬儀費用については保障すべきとの考え方から設けられているもの。 |
| 本人 | 被扶養者 | |||
| 昭和48.10.1 |
|
30,000円 | ||
| 昭和51.7.1 |
|
50,000円 | ||
| 昭和56.4.1 |
|
70,000円 | ||
| 昭和60.4.1 |
|
100,000円 |
| ※1 | 最低保障制再開(昭和48年10月1日)以後の変遷 |
| ※2 | ( )内は最低保障額 |
埋葬料(費)
家族埋葬料
出典「事業年報(平成14年度)社会保険庁」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||