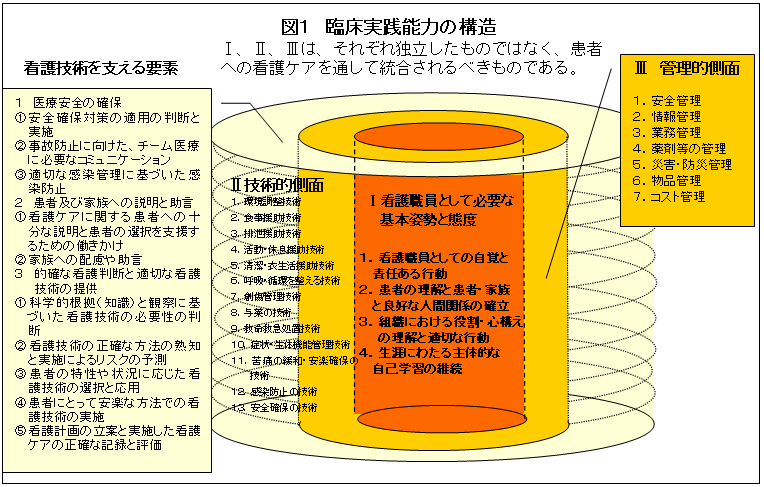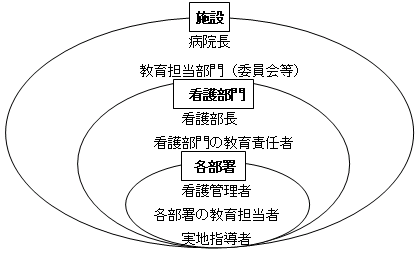「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」報告書
平成16年3月10日
はじめに
| |
近年の保健医療を取り巻く環境が大きく変化する中、看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)の業務にも様々な変化が生じている。例えば、目覚ましい医療技術の進歩への対応、医療安全の確保、インフォームド・コンセントへの国民の期待等、山積する多くの課題があり、これらに適切に対応していくためには、看護職員の臨床実践能力の向上を図ることが必須である。特に新人看護職員に対しては、学生時代と大きく異なる環境の中で安全に看護業務を遂行できるようにするために、臨床実践能力を向上させる組織的、体系的な取組が必要である。
これまでも、旧厚生省において「看護職員生涯教育検討会報告書」(平成4年)が取りまとめられ、卒業直後から概ね3年間の「看護実務研修」について言及されている。しかし、新人看護職員の研修についての明確な記述はなく、現実にも新人看護職員研修について国としての取組は十分ではなかった。
このような現況を踏まえ、当検討会は、厚生労働省医政局長の依頼を受けて設置され、医療安全の確保及び臨床看護実践の質の向上の観点から、新人看護職員の卒後1年間の看護実践の到達目標及び目標達成に向けた研修体制構築のための指針について、平成15年9月25日の第1回開催以後、全4回にわたって議論を重ねてきた。
新人看護職員研修到達目標(以下「到達目標」という。)及び新人看護職員研修指導指針(以下「指導指針」という。)の作成に当たっては、検討会の下に看護管理者及び教育・研究者から成るワーキンググループを設置して、たたき台を作成した。さらに、検討会において、医療安全、看護管理に関する専門家の意見、新人看護職員の指導者、新人看護職員等の関係者からのヒアリングを踏まえ、議論を深め、起草委員によって報告書の文言の整理等に取り組むなど、新人看護職員研修の在り方について精力的に検討してきたところである。
今般、当検討会としてこれまでの議論を整理し、本報告書を取りまとめたので、これを公表する。
なお、報告書は、第一部において新人看護職員をめぐる現状と課題について述べ、第二部において新人看護職員が卒後の1年間で備えるべき看護技術等を示した到達目標、新人看護職員の指導に必要な要件・指導方法等を示した指導指針を提示した。 |
| |
医療技術の進歩、患者の高齢化・重症化、平均在院日数の短縮化等により、療養生活支援の専門家としての看護職員の役割は、複雑多様化し、その業務密度も高まっている。看護のあらゆる場面で、患者にわかりやすい丁寧な説明を行った上で納得してもらい、看護ケアを提供することが求められている。特に、高齢者に対しては、身体機能の低下を踏まえた緻密な観察と生活援助、ときには精神機能の低下を受容しつつ、人権を尊重し、抑制の回避など適切な看護を提供しなければならない。また、在院日数の短縮化に伴い、患者・家族への療養生活指導や退院調整に多くの時間を費やすとともに、頻繁な入退院に伴う看護業務も増加している。さらに、操作や用法を間違えれば患者の生命に多大な影響を与える医療機器や医薬品の種類は増加の一方にある。そのため、看護職員は、医療機器の確実な操作・管理をしながら、多様な作用を有する多種類の医薬品について、医師の指示に基づき、患者名・量・時間等を確認し誤りなく与薬し、経過を緻密に観察することが求められている。
個々の看護職員に目を向けると、複数の患者を同時に受け持ちながら、限られた時間の中で業務の優先度を考えつつ、多重の課題に対応しなければならない状況にある。また、ひとつの業務を遂行する間にも他の業務による中断がある等、複雑な状況に即応できる能力が求められている。
一方、看護職員は、患者に直接に療養上の世話及び診療の補助業務を行う最終実施者の役割を担うことが多い。近年の医療事故裁判の判決においては、医師以上の刑事責任を問われる事例もある。さらに、平成13年の保健師助産師看護師法の改正により、守秘義務が課され、医師と同等の罰則となるなど、看護職員に求められる社会的責任は非常に大きくなっている。
さらに、「厚生労働大臣医療事故対策緊急アピール」(厚生労働省平成15年12月)が公表されたことでも分かるように、医療安全の確保は最重要課題となっているが、特に、医療機関におけるヒヤリ・ハット事例の報告においては、当事者として新人看護職員の占める割合が高いことが指摘されている。
以上のことから、看護の質を確保、向上させ、国民に安全な医療を提供するために、新人看護職員の卒後の研修を充実させる必要性は非常に高い。 |
| |
平成15年3月に看護師等学校養成所を卒業後、就業した新人看護職員数は54,041人(保健師1,134人、助産師1,263人、看護師41,017人、准看護師10,627人)であった。このうち、病院に就業した者は47,823人(88.5%)であり、新人看護職員の就業先は病院が圧倒的に多い(保健師218人(19.2%)、助産師1,205人(95.4%)、看護師39,199人(95.6%)、准看護師7,201人(67.8%))。
新人看護職員に対する研修についての法制度を見ると、「保健師助産師看護師法」においては「薬剤師法」と同様に、「医師法」及び「歯科医師法」と異なり、免許取得後の研修に関する規定は設けられていない。しかし、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」では、国及び地方公共団体においては看護師等の資質の向上に必要な措置を講ずること、病院等の開設者等においては看護師等が専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分発揮できるような措置を講ずること、看護師等においては自ら進んでその能力の開発及び向上を図ることが求められている。
このような状況の下で、国、地方公共団体においては、中堅看護職員実務研修、看護職員専門分野研修等が実施されている。しかし、新人看護職員についての取組は十分ではない。
一方、「看護職新規採用者の臨床能力の評価と能力開発に関する研究」(平成14年度厚生労働科学研究)でも明らかなように、多くの病院では、自施設の職員としての意識の向上、看護職員として求められる知識・技術の獲得、医療安全の確保等を目的に新人看護職員に対する研修を実施している。ただし、その方法、期間、内容等は施設によって様々であり、研修に関する標準的な考え方や指針の策定を期待する声が多い。
こうした状況の中、「新たな看護のあり方に関する検討会報告書」(厚生労働省平成15年3月)、さらには「医療提供体制の改革のビジョン」(厚生労働省 平成15年8月)において看護基礎教育を充実するとともに、看護職員の臨床研修の在り方について制度化を含めた検討を行うなど、新人看護職員教育の充実のための対策の必要性が指摘されている。 |
| 1 |
看護基礎教育の課題とこれまでの取組
| |
現在の看護職員養成課程には、看護師については高卒者を対象とした3年課程、准看護師免許を取得した者を対象とした2年課程があり、その教育機関は大学、短期大学(3年課程、2年課程)、養成所(3年課程、2年課程)、高等学校専攻科(2年課程)及び高等学校専攻科5年一貫教育校に分かれる。また、保健師及び助産師については大学、短期大学専攻科及び養成所で養成されている。さらには、保健師・看護師、助産師・看護師の国家試験受験資格を同時に取得できる、保健師・看護師、助産師・看護師の統合カリキュラムによる教育も行われている。准看護師については養成所及び高等学校衛生看護科において養成されている。
このように多様な養成課程がある中、厚生労働省では、「看護師等養成所の運営に関する指導要領について」(平成15年3月26日医政発第0326001号厚生労働省医政局長通知。以下「指導要領」という。)において、「人々の健康上の問題を解決するため、科学的根拠に基づいた看護を実践できる基礎的能力を養う」、「健康の保持増進、疾病予防と治療、リハビリテーション、ターミナルケア等、健康の状態に応じた看護を実践するための基礎的能力を養う」等、看護師養成の基本的考え方を示している。
しかし、指導要領においては細部まで規定しておらず、看護基礎教育卒業時の看護実践能力の具体的な到達目標は、各学校養成所が設定しているため、看護技術の到達度には差異が生じていると指摘されている。
また、看護基礎教育では医療機関における医療安全管理体制の強化や患者及び家族の意識の変化等により、従来、患者を対象として実施されてきた看護技術の訓練の範囲や機会が限定される傾向にある。こうした現状に鑑み、文部科学省は「看護学教育の在り方に関する検討会報告」(平成14年3月)を取りまとめ、さらに平成15年度の「看護学教育の在り方に関する検討会」においては、学士課程における看護学教育で育成する看護実践能力の到達目標とその評価に関する検討が行われている。
一方、厚生労働省では「看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書」(平成15年3月)において、看護学生が看護行為を行うための法的及び倫理的要件を示し、基礎教育における看護実践能力の育成のための体制整備に関する検討が行われたところである。 |
|
| 2 |
看護基礎教育における臨地実習の現状と課題
| |
看護基礎教育における臨地実習は「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」(昭和26年文部・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)及び指導要領において、保健師3単位(135時間)以上(実習以外の講義及び演習18単位(540時間)以上)、助産師8単位(360時間)以上(同、14単位(360時間)以上)、看護師23単位(1,035時間)以上(同、70単位(1,860時間)以上)、准看護師735時間以上(同、1,155時間以上)と定められている。
さらに看護師の場合、指導要領において臨地実習は「知識・技術を看護実践の場面に適用し、看護の理論と実践を結びつけて理解できる能力を養う内容」とし、助産師においては、指定規則において「分娩の取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生1人につき10回程度行わせること」としている。
また、多くの学校養成所において臨地実習で採られている教育方法は、学生が一人の患者を受け持ち、その患者及び家族と関わりながら、看護ニーズを判断し、看護ケアを計画、実践し、評価するものである。そのため、チームメンバーの一員として、臨床現場の多重課題の優先度を考えながら時間内に業務を実施するなどの能力を、基礎教育の中で身につけることは極めて困難である。
したがって、複数の患者の受持ちや多重課題への対応等については、新人看護職員研修において修得できる体制を構築する必要がある。 |
|
| |
以上のことを踏まえると、新人看護職員研修を充実・普及させていくよう、行政、医療従事者、看護教育の専門家等、幅広い関係者による積極的な取組が必要である。そのための第一歩として、新人看護職員研修に関する内容(修得すべき知識・技術・態度、研修体制等)の標準化を進めることが有効であると考えられることから、第二部において、現場で広く活用できる標準的な到達目標と指導指針を示すこととした。
|
| 第二部 |
新人看護職員研修到達目標及び新人看護職員研修指導指針 |
|
| 1 |
看護は人間の生命に深く関わる職業であり、患者の生命、人格及び人権を尊重することを基本とし、生涯にわたって研鑽されるべきものである。新人看護職員研修は、看護実践の基礎を形成するものとして、極めて重要な意義を有する。
|
| 2 |
医療における安全の確保及び質の高い看護の提供は重要な課題である。このため、医療機関は組織的に全職員の研修に取り組む必要があり、新人看護職員研修はその一環として位置付けられる性質のものである。
|
| 3 |
新人看護職員研修は、看護基礎教育では学習することが困難な、医療チームの中で多重課題を抱えながら複数の患者を受け持ち、看護ケアを安全に提供するための看護実践能力を強化することに主眼をおくことが重要である。
|
| 4 |
専門職業人として成長するためには、新人看護職員自らがたゆまぬ努力を重ねるべきであることは言うまでもないが、新人の時期から生涯にわたり、継続的に自己研鑽を積むことができる研修支援体制が整備されていることが重要である。 |
| II |
新人看護職員研修到達目標及び新人看護職員研修指導指針の前提 |
| 1 |
到達目標及び指導指針は、新卒者の就業の状況、安全な看護ケア提供に当たっての優先度を考慮し、病院において看護ケアを提供する看護職員を想定した。
|
| 2 |
到達目標に含まれる内容は、看護職員として必要な姿勢及び態度並びに卒後1年間に新人看護職員が修得すべき知識、技術の目標とした。
また、新人助産師については、看護職員として修得すべき到達目標に加え、法で業務独占とされる助産を含む助産技術に関わるものも示した。
|
| 3 |
指導指針に含まれる内容は、到達目標を達成するために必要な要件、指導方法等とした。
|
| 4 |
到達目標及び指導指針の内容は、新人看護職員研修として実施されるべき基本事項として提示するものであり、各施設の多様性を踏まえつつできる限り広く活用できるよう考慮した。
しかしながら、施設規模、看護職員の構成、教育に係る予算等の状況から、各施設内での調整を行うことも必要である。
さらに、到達目標は、新人看護職員の受けた教育課程や教育内容、個人の資質等の背景を加味し、各施設で適宜、調整を行うことを想定した。
|
| 5 |
各部署に特有な疾患とその症状及び治療・薬剤・検査・処置の理解と看護ケアに関する到達目標は、各施設において設定することを想定した。
|
| 6 |
到達目標の作成に当たっては「看護学教育の在り方に関する検討会報告」、「看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書」等の看護基礎教育における看護技術教育のあり方に関する検討結果との連携を考慮した。 |
| (1) |
新人看護職員には、臨床現場で複数の患者を受け持ちながら、優先度を考慮し看護を行うことが求められることから、必要な知識、技術、態度を以下の構成要素ごとに提示した。
| 1) |
看護職員として必要な基本姿勢と態度(表1) |
| 2) |
看護実践における技術的側面
看護技術(表2−1)、助産技術(表2−2) |
| 3) |
看護実践における管理的側面(表3) |
しかしながら、例えば、看護技術の実施に際しては、患者への十分な説明等「看護職員として必要な基本姿勢と態度」に含まれる内容も同時に必要とされるように、これらの到達目標はそれぞれ独立したものではなく、患者への看護ケアを通して臨床実践の場で統合されるべきものであるとの認識が必要である。(図1)
|
| (2) |
特に、看護技術の到達目標については、単に手順に従って実施するのではなく、以下の「看護技術を支える要素」を全て確認した上で実施する必要がある。
| 1) |
医療安全の確保
| (1) |
安全確保対策の適用の判断と実施 |
| (2) |
事故防止に向けた、チーム医療に必要なコミュニケーション |
| (3) |
適切な感染管理に基づいた感染防止 |
|
| 2) |
患者及び家族への説明と助言
| (1) |
看護ケアに関する患者への十分な説明と患者の選択を支援するための働きかけ |
| (2) |
家族への配慮や助言 |
|
| 3) |
的確な看護判断と適切な看護技術の提供
| (1) |
科学的根拠(知識)と観察に基づいた看護技術の必要性の判断 |
| (2) |
看護技術の正確な方法の熟知と実施によるリスクの予測 |
| (3) |
患者の特性や状況に応じた看護技術の選択と応用 |
| (4) |
患者にとって安楽な方法での看護技術の実施 |
| (5) |
看護計画の立案と実施した看護ケアの正確な記録と評価 |
|
|
| (3) |
看護実践における管理的側面については、それぞれの科学的・法的根拠を理解し、チーム医療における自らの役割を認識した上で実施する必要がある。
|
| (4) |
患者への看護技術の実施においては、高度なあるいは複雑な看護を必要とする場合は除き、比較的状態の安定した患者の看護を想定している。
しかし、日常生活援助に関する目標の中で、高度なあるいは複雑な看護技術であっても、新人看護職員が修得を目指す必要がある項目については、その代表的な患者の状況等を例として付記した。
なお、重症の患者等への特定の看護技術の実施を到達目標とすることが必要な施設、部署においては、想定される患者の状況等を適宜調整することとする。 |
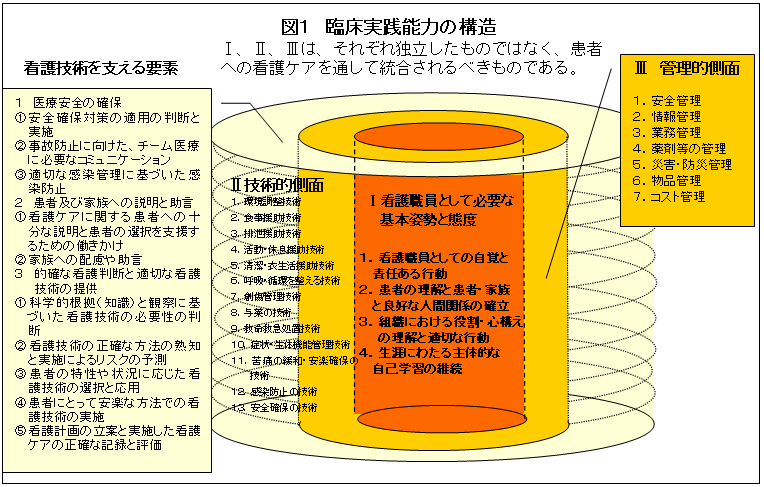
| 表1 |
看護職員として必要な基本姿勢と態度についての到達目標 |
| 領域 |
到達目標 |
| 看護職員としての自覚と責任ある行動 |
| (1) |
医療倫理・看護倫理に基づき、人間の生命・尊厳を尊重し患者の人権を擁護する。 |
| (2) |
看護行為によって患者の生命を脅かす危険性もあることを認識し行動する。 |
| (3) |
職業人としての自覚を持ち、倫理に基づいて行動する。 |
|
| 患者の理解と患者・家族との良好な人間関係の確立 |
| (1) |
患者のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する。 |
| (2) |
患者を一個人として尊重し、受容的・共感的態度で接する。 |
| (3) |
患者・家族が納得できる説明を行い、同意を得る。 |
| (4) |
家族の意向を把握し、家族にしか担えない役割を判断し支援する。 |
| (5) |
守秘義務を厳守し、プライバシーに配慮する。 |
| (6) |
看護は患者中心のサービスであることを認識し、患者・家族に接する。 |
|
| 組織における役割・心構えの理解と適切な行動 |
| (1) |
病院及び看護部の理念を理解し行動する。 |
| (2) |
病院及び看護部の組織と機能について理解する。 |
| (3) |
チーム医療の構成員としての役割を理解し協働する。 |
| (4) |
同僚や他の医療従事者と安定した適切なコミュニケーションをとる。 |
|
| 生涯にわたる主体的な自己学習の継続 |
| (1) |
自己評価及び他者評価を踏まえた自己の学習課題をみつける。 |
| (2) |
課題の解決に向けて必要な情報を収集し解決に向けて行動する。 |
| (3) |
学習の成果を自らの看護実践に活用する。 |
|
日常生活援助に関する目標の中で、高度なあるいは複雑な看護技術であっても、新人看護職員が修得を目指す必要がある項目については、その代表的な患者の状況等を例として付した。
| 領域 |
到達目標 |
| 環境調整技術 |
| (1) |
温度、湿度、換気、採光、臭気、騒音、病室整備の療養生活環境調整
|
| (2) |
|
|
| 食事援助技術 |
| (1) |
食生活支援 |
| (2) |
食事介助 例:臥床患者、嚥下障害のある患者の食事介助 |
| (3) |
経管栄養法 |
|
| 排泄援助技術 |
| (1) |
自然排尿・排便援助(尿器・便器介助、可能な限りおむつを用いない援助を含む) |
| (2) |
浣腸 |
| (3) |
膀胱内留置カテーテルの挿入と管理 |
| (4) |
摘便 |
| (5) |
導尿 |
|
| 活動・休息援助技術 |
| (1) |
歩行介助・移動の介助・移送 |
| (2) |
体位変換
| 例: |
(1)及び(2)について、手術後、麻痺等で活動に制限のある患者等への実施 |
|
| (3) |
関節可動域訓練・廃用性症候群予防 |
| (4) |
入眠、睡眠の援助 |
| (5) |
体動、移動に注意が必要な患者への援助
| 例: |
不穏、不動、情緒不安定、意識レベル低下、鎮静中、乳幼児、高齢者等への援助 |
|
|
| 清潔・衣生活援助技術
|
| (1) |
清拭 |
| (2) |
洗髪 |
| (3) |
口腔ケア |
| (4) |
入浴介助 |
| (5) |
部分浴・陰部ケア・おむつ交換 |
| (6) |
寝衣交換等の衣生活支援、整容
| 例: |
(1)から(6)について、全介助を要する患者、ドレーン挿入、点滴を行っている患者等への実施 |
|
|
| 呼吸・循環を整える技術 |
| (1) |
酸素吸入療法 |
| (2) |
吸引(気管内、口腔内、鼻腔内) |
| (3) |
ネブライザーの実施 |
| (4) |
体温調整 |
| (5) |
体位ドレナージ |
| (6) |
人工呼吸器の管理 |
|
| 創傷管理技術 |
| (1) |
創傷処置 |
| (2) |
褥瘡の予防 |
| (3) |
包帯法
|
|
| 与薬の技術 |
| (1) |
経口薬の与薬、外用薬の与薬、直腸内与薬 |
| (2) |
皮下注射、筋肉内注射、皮内注射 |
| (3) |
静脈内注射、点滴静脈内注射 |
| (4) |
中心静脈内注射の準備・介助・管理 |
| (5) |
輸液ポンプの準備と管理 |
| (6) |
輸血の準備、輸血中と輸血後の観察 |
| (7) |
抗生物質の用法と副作用の観察 |
| (8) |
インシュリン製剤の種類・用法・副作用の観察 |
| (9) |
麻薬の主作用・副作用の観察 |
| (10) |
薬剤等の管理(毒薬・劇薬・麻薬、血液製剤を含む) |
|
| 救命救急処置技術
|
| (1) |
意識レベルの把握 |
| (2) |
気道確保 |
| (3) |
人工呼吸 |
| (4) |
閉鎖式心臓マッサージ |
| (5) |
気管挿管の準備と介助 |
| (6) |
止血 |
| (7) |
チームメンバーへの応援要請 |
|
| 症状・生体機能管理技術 |
| (1) |
バイタルサイン(呼吸・脈拍・体温・血圧)の観察と解釈 |
| (2) |
身体計測 |
| (3) |
静脈血採血と検体の取扱い |
| (4) |
動脈血採血の準備と検体の取扱い |
| (5) |
採尿・尿検査の方法と検体の取扱い |
| (6) |
血糖値測定と検体の取扱い |
| (7) |
心電図モニター・12誘導心電図の装着、管理 |
| (8) |
パルスオキシメーターによる測定 |
|
| 苦痛の緩和・安楽確保の技術 |
| (1) |
安楽な体位の保持 |
| (2) |
罨法等身体安楽促進ケア |
| (3) |
リラクゼーション |
| (4) |
精神的安寧を保つための看護ケア |
|
| 感染防止の技術 |
| (1) |
スタンダードプリコーション※(標準予防策)の実施 |
| (2) |
必要な防護用具(手袋、ゴーグル、ガウン等)の選択 |
| (3) |
無菌操作の実施 |
| (4) |
医療廃棄物の規定に沿った適切な取扱い |
| (5) |
針刺し事故防止対策の実施と針刺し事故後の対応 |
| (6) |
洗浄・消毒・滅菌の適切な選択 |
|
| 安全確保の技術 |
| (1) |
誤薬防止の手順に沿った与薬 |
| (2) |
患者誤認防止策の実施 |
| (3) |
転倒転落防止策の実施 |
| (4) |
薬剤・放射線暴露防止策の実施 |
|
看護技術を支える要素
| 1) |
医療安全の確保
| (1) |
安全確保対策の適用の判断と実施 |
| (2) |
事故防止に向けた、チーム医療に必要なコミュニケーション |
| (3) |
適切な感染管理に基づいた感染防止 |
|
| 2) |
患者及び家族への説明と助言
| (1) |
看護ケアに関する患者への十分な説明と患者の選択を支援するための働きかけ |
| (2) |
家族への配慮や助言 |
|
| 3) |
的確な看護判断と適切な看護技術の提供
| (1) |
科学的根拠(知識)と観察に基づいた看護技術の必要性の判断 |
| (2) |
看護技術の正確な方法の熟知と実施によるリスクの予測 |
| (3) |
患者の特性や状況に応じた看護技術の選択と応用 |
| (4) |
患者にとって安楽な方法での看護技術の実施 |
| (5) |
看護計画の立案と実施した看護ケアの正確な記録と評価 |
|
|
| ※ |
スタンダードプリコーション:患者の血液・体液や患者から分泌排泄される全ての湿性生体物質(尿・痰・便・膿等)は感染症のおそれがあるとみなして対応する方法 |
| 領域 |
到達目標 |
| 妊産婦 |
| (1) |
正常妊婦の健康診査と経過診断、助言 |
| (2) |
外診技術(レオポルド触診法、子宮底・腹囲測定、ザイツ法、胎児心音聴取(ドップラー法、トラウベ)) |
| (3) |
内診技術 |
| (4) |
分娩監視装置の装着と判読 |
| (5) |
分娩開始の診断、入院時期の判断 |
| (6) |
分娩第1〜4期の経過診断 |
| (7) |
破水の診断 |
| (8) |
産痛緩和ケア(マッサージ、温罨法、温浴、体位等) |
| (9) |
分娩進行促進への援助(体位、リラクゼーション等) |
| (10) |
心理的援助(ドゥーラ効果、妊産婦の主体的姿勢への援助等) |
| (11) |
正常分娩の直接介助、間接介助 |
| (12) |
妊娠期、分娩期の異常への援助(指導の下での実施) |
|
| 新生児 |
| (1) |
新生児の正常と異常との判断(出生時、入院中、退院時) |
| (2) |
正常新生児の健康診査と経過診断 |
| (3) |
新生児胎外適応の促進ケア(呼吸・循環・排泄・栄養等) |
| (4) |
新生児の処置(口鼻腔・胃内吸引、臍処置等) |
| (5) |
沐浴 |
| (6) |
新生児への予防薬の与薬(ビタミンK2、点眼薬) |
| (7) |
新生児期の異常への援助(指導の下での実施) |
|
| 褥婦 |
| (1) |
正常褥婦の健康診査と経過診断(入院中、退院時) |
| (2) |
母親役割への援助(児との早期接触、出産体験の想起等) |
| (3) |
育児指導(母乳育児指導、沐浴、育児法等) |
| (4) |
褥婦の退院指導(生活相談・指導、産後家族計画等) |
| (5) |
母子の1か月健康診査と助言 |
| (6) |
産褥期の異常への援助(指導の下での実施) |
|
| 証明書等 |
| (1) |
出生証明書の記載と説明 |
| (2) |
母子健康手帳の記載と説明 |
| (3) |
助産録の記載 |
|
助産技術を支える要素
| 1) |
医療安全の確保
| (1) |
安全確保対策の適用の判断と実施 |
| (2) |
事故防止に向けた、チーム医療に必要なコミュニケーション |
| (3) |
適切な感染管理に基づいた感染防止 |
|
| 2) |
妊産褥婦及び家族への説明と助言
| (1) |
ケアに関する妊産褥婦への十分な説明と妊産褥婦の選択を支援するための働きかけ |
| (2) |
家族への配慮や助言 |
|
| 3) |
的確な判断と適切な助産技術の提供
| (1) |
科学的根拠(知識)と観察に基づいた助産技術の必要性の判断 |
| (2) |
助産技術の正確な方法の熟知と実施によるリスクの予測 |
| (3) |
妊産褥婦及び新生児の特性や状況に応じた助産技術の選択と応用 |
| (4) |
妊産褥婦及び新生児にとって安楽な方法での助産技術の実施 |
| (5) |
助産計画の立案と実施したケアの正確な記録と評価 |
|
|
| 表3 |
看護実践における管理的側面についての到達目標 |
看護実践における管理的側面については、それぞれの科学的・法的根拠を理解し、チーム医療における自らの役割を認識した上で、実施する必要がある。
| 領域 |
到達目標 |
| 安全管理 |
| (1) |
施設における医療安全管理体制について理解する。 |
| (2) |
インシデント(ヒヤリ・ハット)事例や事故事例の報告を速やかに行う。 |
|
| 情報管理 |
| (1) |
施設内の医療情報に関する規定を理解する。 |
| (2) |
患者等に対し、適切な情報提供を行う。 |
| (3) |
プライバシーを保護して医療情報や記録物を取り扱う。 |
| (4) |
看護記録の目的を理解し、看護記録を正確に作成する。 |
|
| 業務管理 |
| (1) |
業務の基準・手順に沿って実施する。 |
| (2) |
複数の患者の看護ケアの優先度を考えて行動する。 |
| (3) |
業務上の報告・連絡・相談を適切に行う。 |
| (4) |
決められた業務を時間内に実施できるように調整する。 |
|
| 薬剤等の管理 |
| (1) |
薬剤を適切に請求・受領・保管する(含、毒薬・劇薬・麻薬)。 |
| (2) |
血液製剤を適切に請求・受領・保管する。 |
|
| 災害・防災管理 |
| (1) |
定期的な防災訓練に参加し、災害発生時(地震・火災・水害・停電等)には決められた初期行動を円滑に実施する。 |
| (2) |
施設内の消火設備の定位置と避難ルートを把握し患者に説明する。 |
|
| 物品管理 |
| (1) |
規定に沿って適切に医療機器、器具を取り扱う。 |
| (2) |
看護用品・衛生材料の整備・点検を行う。 |
|
| コスト管理 |
| (1) |
患者の負担を考慮し、物品を適切に使用する。 |
| (2) |
費用対効果を考慮して衛生材料等の物品を適切に選択する。 |
|
| (1) |
修得方法の適切な組合せ
現場教育、集合教育、自己学習を適切な形で組み合わせる。
なお、各施設、各部署の条件によって経験の機会が少ない看護技術については、集合教育を取り入れるなど、修得方法を工夫する必要がある。 |
| (2) |
侵襲性の高い行為への配慮
侵襲性の高い行為については、事前に集合教育等により、新人看護職員の修得状況を十分に確認した上で段階的に実践させる必要がある。 |
| (3) |
看護職員として必要な基本姿勢と態度
「看護職員として必要な基本姿勢と態度」については、早期に集合教育等において具体的に説明し、更に、患者の自己決定や患者の抑制等の医療の倫理的課題に関する事例検討等を通して、看護職員としての基本的な考え方を確認することが望ましい。 |
| (4) |
五感を用いた観察と判断の重要性
バイタルサインの観察等、看護の基本となる能力については、医療機器の数値にのみ頼って患者の状態を判断するのではなく、実際に患者に触れるなど、五感を用いて患者の状態を判断することの重要性を認識させ、その能力を養う必要がある。 |
| (1) |
評価内容
評価は、到達目標の達成度について行う。 |
| (2) |
目標到達時期及び評価時期
| 1) |
到達目標は1年間で到達するものとするが、各部署の特性、優先度に応じて評価内容と到達時期を具体的に設定する。評価時期は、就職後1か月、3か月、6か月、1年を目安とする。
到達目標には、施設あるいは配属部署によっては経験の機会が少ないものもあるため、優先度の高いものから修得し、状況によっては到達期間を卒後1年以降に設定しなければならないこともあり得る。その場合には、看護部門の教育責任者の支援を受けて、到達目標達成のために必要な対応を検討する必要がある。 |
| 2) |
就職後早期の評価は、新人看護職員の職場への適応の把握等の点から重要であり綿密に行う必要がある。 |
| 3) |
評価は、担当することとなる業務を安全に遂行することが出来るか否か、看護業務一つひとつの到達状況を確認する必要がある。新人看護職員を初めて夜勤業務につかせる際には、それらを踏まえて、各部署の状況に応じて看護管理者がその可否を確認する必要がある。 |
|
| (3) |
評価者
| 1) |
評価は、自己評価に加え、実地指導者(IV 新人看護職員研修指導指針 3(2)実地指導者の配置参照)及び看護管理者による他者評価を取り入れる。 |
| 2) |
最終評価は、看護部門の教育担当者又は看護管理者が行う。 |
|
| (4) |
評価方法
| 1) |
他者評価は、実地指導者との面接等も加え、個別に行う。 |
| 2) |
評価には、到達目標に関する評価表(自己評価及び他者評価)を用いることとし、総括的な評価を行うにあたっては、患者の看護ケアに関するレポート等も適宜取り入れる。 |
|
| (5) |
評価の留意点
| 1) |
安全管理、感染管理については、確実な修得を確認するための評価方法を考慮する。 |
| 2) |
看護技術については、単に個々の行為を評価するのではなく、「医療安全の確保」、「患者及び家族への説明と助言」、「的確な看護判断と適切な看護技術の提供」等、個々の看護技術を支える要素を含んだ、包括的な評価を行う。 |
| 3) |
評価においては、研修計画、研修体制等についての新人看護職員による評価も併せて行う必要がある。 |
|
| (1) |
新人看護職員の準備状態
新人看護職員は、それぞれの教育機関において看護基礎教育を修了し、新卒者が持つべき知識及び技能を問う資格試験に合格した者であり、成人の学習者である。
しかしながら、学校養成所における教育内容の違い、新人看護職員個人の特性等により、新人看護職員一人一人の準備状態は多様であることを、新人看護職員の指導に関わる者は理解しておく必要がある。
|
| (2) |
新人看護職員指導の方向性
新人看護職員研修では、この準備状態を踏まえて、医療チームの中で多重課題を抱えながら複数の患者を受け持ち、決められた時間内で優先度を判断し、安全に看護を提供するために必要な姿勢、知識及び技術に焦点を当てて指導していく必要がある。
|
| (3) |
新人看護職員研修を通しての看護実践能力の統合
新人看護職員の指導に当たって、到達目標で示した「看護職員として必要な基本姿勢と態度」、「看護実践における技術的側面」、「看護実践における管理的側面」はそれぞれ個々に達成するものではなく、3つの目標が互いに関連しあい、統合されて初めて臨床実践能力が向上するということを、指導に関わる者が理解している必要がある。
|
| (4) |
指導の方法
新人看護職員研修は、現場教育においても集合教育においても、単に新しい知識・技術を提供するに留めず、新人看護職員が自らの看護実践に取り込み活用していけるよう、その内容及び方法を工夫する必要がある。
例えば、集合教育で学んだ知識を、受持ち患者の看護ケアと結びつけるような働きかけを指導に関わる者が意識的に行う等である。
また、新人看護職員が自ら受け持った患者に必要な看護を考え判断する能力を養うために、日々の看護実践において、常に到達目標で示した「看護技術実施時の確認項目」を新人看護職員と指導に関わる者とで確認しあうことが重要である。 |
| (1) |
研修体制整備の意義
各施設は、新人看護職員研修の充実が、医療安全の確保、看護の質の向上、さらには、看護職員の人材確保及び離職防止に貢献することを認識する必要がある。
特に、新人看護職員研修に当たって、各施設、各職員は改めて日常の看護を振り返り、看護実践の根拠を確認する必要があることから、質の高い研修の実施は、組織全体としての医療の質の向上に繋がることを再認識する必要がある。
|
| (2) |
職員の研修への参加
新人看護職員研修は、各施設の全ての職員が、それぞれの立場から関わるものであり、全ての職員に研修内容が周知される必要がある。
|
| (3) |
施設における教育担当部門の設置
人材育成は医療の質に関わる重要な要素であり、新人看護職員を含めた職員の教育は、施設全体で考え構築すべきものである。このため、各施設は職員の教育についての理念を明確にするとともに、複数の職種で構成される教育担当部門(委員会等)を設置し、施設全体の継続教育を統括することが望ましい。
施設における教育体制の例を図2に示す。
|
| (4) |
看護部門における教育理念の明確化及び研修体制の整備
施設の教育理念に基づき、看護部門の教育理念を明確にし、看護部門の長の責任において、研修体制を構築する必要がある。研修体制は、看護部門及び各部署に教育担当者を配置し、役割を明確化する必要がある。
また、臨床現場での研修体制の充実には、責任者が明確にその役割を果たす環境整備が不可欠であり、新人看護職員研修を含めた看護職員全員の研修の企画等を行う看護部門の教育責任者は専任での設置が望ましい。
なお、看護部門の教育責任者は、各部署の到達目標作成の指導や助言を行うとともに、到達目標の達成度の評価にも積極的に関わる必要がある。
|
| (5) |
教育担当者及び新人看護職員に対する業務上の配慮
教育担当者及び新人看護職員双方にとって効果的、効率的な研修を行うためには、新人看護職員が研修を行う看護単位に、新人看護職員研修を中心となって企画・運営する看護職員を配置することが望ましい。
なお、新人看護職員の業務への適応の観点から、頻繁に勤務時間帯を変えることなく、同一の勤務時間帯を一定程度継続させるような配慮が必要である。
|
| (6) |
新人看護職員の精神的支援
新人看護職員の多くがリアリティショック※を経験することから、精神的な支援の知識・技術を持つ専門家によって新人看護職員の相談に対応するなどの支援体制を整備することが望ましい。
また、看護部門の長をはじめ、各部署の看護管理者や教育担当者、各指導者は、新人看護職員の職場適応の状況を十分に把握すると同時に、必要な場合には専門的な支援に繋げなければならない。
| ※リアリティショック: |
理想や期待と現実とがかけ離れていることによって生じる葛藤 |
|
| (7) |
関係部署、他職種との連携
看護部門の教育責任者は、新人看護職員研修に当たって医療安全等の担当部署との連携をとり、医療安全管理や感染管理等の特定分野において専門的な知識・技術を有する職員の新人看護職員研修への参画を求める必要がある。
また、チーム医療を円滑に推進するために、新人看護職員研修に関して他職種との連携を密にとるとともに、新人看護職員が他職種の業務を理解するための機会を設けることが望ましい。 |
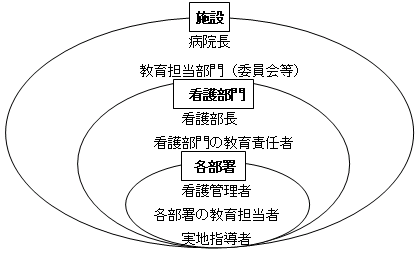
| (8) |
看護基準及び看護手順等の整備
新人看護職員研修に活用するためにも、各施設の看護基準及び看護手順等を整備しておく必要がある。
|
| (9) |
新人看護職員研修へのITの導入
医療機関におけるIT(情報技術)の導入が加速度的に進んでいる現在、新人看護職員研修においても、今後IT等を用いた効果的な学習方法を検討することも有益である。
|
| (10) |
研修計画の評価、改善等
研修計画及び研修内容については、定期的に評価し改善することにより充実を図る必要がある。
また、新人看護職員研修は看護職員の生涯教育の一環であり、新人看護職員研修修了後の研修計画についても明示する必要がある。
|
| (11) |
施設間の支援体制
自施設内での新人看護職員研修の充実が望まれる一方で、施設内で実施できる研修に限界がある施設については、新人看護職員研修に実績のある施設と連携して必要な研修を受けさせたり、さらに教育機関、専門職能団体等において実施される研修を院内研修の計画に取り入れていくことが望ましい。また、新人看護職員研修に実績のある施設は、院内研修を公開する等、他施設への支援を積極的に行うことが求められる。
施設間の支援体制の例:
| 1) |
新人看護職員研修に関する情報提供や研修担当者の交流を行う連携施設の確保 |
| 2) |
新人看護職員研修への他施設の新人看護職員の受入れ |
| 3) |
新人看護職員の指導者育成のための研修への他施設の看護職員の受入れ |
|
| (1) |
看護管理者の役割及び教育担当者の配置
各部署における新人看護職員研修の実施に当たっては、各部署の看護管理者が研修を統括し、更に、各部署で実施される研修の企画、運営の中心となる教育担当者(教育委員等)を配置することが必要である。
|
| (2) |
実地指導者の配置
新人看護職員の看護技術等の実地指導を行い、到達目標の到達状況等を定期的に評価する指導者(以下「実地指導者」という。)については、以下のような配置が考えられるが、就職後一定の期間は、指導・相談を行う実地指導者を配置することが望ましい。
実地指導者の配置例:
| 1) |
新人看護職員に対し継続的に指導を行う一人の指導者を配置する。 |
| 2) |
各新人看護職員に対し複数の看護職員を指導者として配置する。 |
| 3) |
チームナーシングにおけるチームの看護職員全体の中で、日々の指導者を配置する。 |
| 4) |
上記3つの方法を就職後の期間別に組み合わせる。 |
|
| (3) |
実地指導者の負担の軽減
各部署の看護管理者は、実地指導者への負担が過剰にならないように、実地指導者の役割を明確にすることが必要である。
また、新人看護職員研修においては、新人を直接に指導する実地指導者だけでなく、臨床経験を積んだ先輩の看護職員が併せて支援する「屋根瓦方式」等の厚味のある研修体制を整えることが望ましい。
|
| (4) |
教育内容等の明示
施設全体の教育計画に基づき、各部署での教育内容、指導時期、指導方法等を含んだ年間教育計画を明示し、部署の全ての看護職員に周知する必要がある。
なお、各部署の教育計画は、施設で定めた研修内容の他に、各部署で新人看護職員に必要な教育内容を含むものとする。
|
| (5) |
各部署に必要な看護手順等の整備
各部署における指導に当たっては、施設で定められた看護基準及び看護手順に基づいて実施するとともに、さらに各部署で必要な看護手順等を整備しておくことが必要である。 |
| (1) |
実地指導者の要件
新人看護職員研修に当たっては、屋根瓦方式の指導体制によって、全ての看護職員が新人看護職員の指導にあたることが基本であると考えられるが、中でも実地指導者は、指導を通して新人看護職員に与える影響が非常に大きいため、臨床実践経験2年以上であり、知識、技術の指導のみならず、情緒的に安定した教育的指導ができる者であることが望ましい。
|
| (2) |
実地指導者研修の場
新人看護職員が各施設で充実した研修を受けることができる環境を整備するためには、実地指導者に対する施設内外での教育が重要である。実地指導者育成の場としては以下のものが想定される。
| 1) |
実地指導者が所属する施設内での研修 |
| 2) |
連携をとっている他施設で行われる研修 |
| 3) |
地方公共団体等で開催される研修 |
| 4) |
専門職能団体等が主催する研修 |
| 5) |
学術団体による学術集会等 |
| 6) |
看護基礎教育機関で実施される講演会等 |
|
| (3) |
実地指導者研修のプログラム
施設内外で実施される実地指導者育成のプログラムには、以下の内容を含めることが望ましい。
なお、実地指導者に対する教育においては、指導者としての不安・負担感を軽減することを目的として、看護部門の教育責任者あるいは各部署の長による面接や指導者の支援のための研修を定期的に実施する必要がある。
| 1) |
教育についての基本的な考え方 |
| 2) |
専門職業人としての生涯教育の考え方 |
| 3) |
看護職員の継続教育の考え方 |
| 4) |
指導者の役割
| (1) |
新人看護職員の理解 |
| (2) |
教育ニーズの把握 |
| (3) |
教育目標の設定 |
| (4) |
教育計画の作成 |
| (5) |
教育計画の実施 |
| (6) |
教育計画の評価及び評価結果のフィードバック |
|
| 5) |
指導者に求められる要件 |
| 6) |
各施設、部署における教育計画の実施方法等、各施設、部署において新人看護職員の指導に必要な事項 |
|
| 5 |
各医療機関への適用
| |
到達目標及び指導指針は、各施設の新人看護職員研修の基本事項として位置付けるが、施設規模、看護職員の構成、教育に係る予算等の状況に合わせた調整も必要である。
また、既に研修体制が整備された施設においても、本報告書をもとに自施設の研修プログラムや指導方法の確認や見直しを行い、研修体制を一層充実させていくことが期待される。 |
|
| (1) |
情報公開の意義
新人看護職員研修に関する情報は、看護学生の就職先の選定に当たって重要な情報である。また、施設間の協力・連携体制を構築する上でも、各施設の新人看護職員研修に関する情報の公開は有益である。
|
| (2) |
各施設の研修内容等の公開
各施設で実施されている新人看護職員研修の教育内容や方法には、看護学生から大きな関心が寄せられており、各施設はホームページ等を活用し、新人看護職員研修に関する情報を幅広く公開することが望ましい。
公開が期待される情報としては、新人看護職員研修についての施設の理念、施設が求める看護職員像、施設及び各部署の具体的な研修計画、研修内容、指導体制等である。
|
| (3) |
就職前の学生への情報提供等
各医療機関は、採用を決定した学生等に対して、就職前に、臨床現場に必要な知識・技術等を主体的に学習するための情報を提供したり、先輩看護職員との交流の場を設ける等、新人看護職員のリアリティショックを軽減するための対応を行うことが望ましい。 |
おわりに
| |
検討会・ワーキンググループでは、看護系大学や学校養成所の教育者、様々な規模の医療施設の看護管理者、研究者、医療関係者、医療関係団体、マスコミ関係者等の幅広い分野の関係者の参画の下に、国民の期待に応える看護の提供のために必要となる新人看護職員の研修のあり方について議論を重ねてきた。
今後、本報告書が関係者に周知され、報告書に盛り込まれた内容の新人看護職員研修が広く実施され、看護の質の確保、向上が図られることは、医療関係者の願いであり、また、国民の医療に対する期待に応える途であると考える。
その実現に向け、国は、研修体制についての情報公開や模範となるような研修を行っている施設についての情報提供を推進する等、新人看護職員研修に関する支援の充実を図ることが必要である。
専門職能団体において、現在実施されている新人看護職員及び指導者等を対象とした研修が今後も継続して実施されることが望まれる。
学術団体には、新人看護職員研修に関わる研究を推進し、研修方法等について科学的根拠に基づいた情報を提供することが期待される。
看護師等学校養成所においては、臨床現場で求められる看護実践能力に関する情報を常に収集し、臨地実習の方法の工夫など、教育内容の改善に活かすことが必要である。このため、専任教員は実習施設等の新人看護職員研修に積極的に関わる必要がある。また、臨床現場で現実に看護業務に従事している看護職員が看護基礎教育に一層参画することも求められる。
なお、新人看護職員研修においては、指導者、看護管理者が果たす役割が重要であり、その資質向上に向けた取組も必要である。
さらに、今後、在宅医療・訪問看護の充実を図るために、将来、訪問看護師として活躍することを希望する新人看護職員については、様々な疾病、状態の患者の看護に対応できるよう、訪問看護師としての看護実践能力を開発するための研修プログラムを検討する必要がある。
以上、新人看護職員研修の現行の仕組みの下での充実策を述べたが、新人看護職員であろうとも、医療の最前線で24時間医療提供に責任を持つことに変わりはなく、臨床現場からは研修の実施を単に医療機関の自主性に任せるだけではなく、新人看護職員全員に必要な研修が提供されるような制度を望む声が多く寄せられている。しかしながら、全ての医療機関において、望ましい形で新人看護職員研修を実施するためには解決すべき課題も多い。例えば、十分な現場教育を行うための看護職員の配置や労働条件等の確保、医療機関間の連携の問題などであり、これらは一医療機関の努力だけでは限界がある。また、これらの課題の検討に当たっては、看護業務に影響を与える医療機関の機能分化と連携等を図る医療提供体制の改革の動向なども十分に踏まえる必要がある。さらに、関連して、看護基礎教育における臨床実践能力の向上に向けた教育の強化と教育期間の延長などの課題もある。
このように、新人看護職員研修のあり方についての検討は、新人の一時期における研修をどうすべきかの課題に止まらず、看護職員の養成・教育の基本に立ち返って検討を行うべき問題を含んでいる。「医療提供体制の改革のビジョン」においては、看護職員の臨床研修のあり方について制度化を含めた検討を行うこととされており、その目標は、新人看護職員に求められる一定の資質の確保を図ることであると考えられる。したがって、国は、看護基礎教育における臨床実践能力の向上の取組や、新人看護職員研修の効果的な実施のための研究等を通じ、また、今後の新人看護職員研修の実施状況及び医療提供体制改革の推移等を踏まえて、全ての新人看護職員が求められる資質を確保できるような仕組みの構築に向けて今後も継続して検討を行う必要がある。 |
検討経過
| ○ |
「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」 |
| 回数 |
開催日時 |
議事内容 |
| 第1回 |
平成15年
9月25日(木)
10:00〜12:00 |
| (1) |
趣旨説明 |
| (2) |
委員からの意見発表
| ・ |
新人看護職員の臨床実践能力の現状と課題
(北里大学病院 教育看護科長 野地金子) |
| ・ |
医療安全の立場からみた新人看護職員の臨床実践能力の現状と課題
(杏林大学保健学部 教授 川村治子) |
| ・ |
医療機関における新人看護職員教育の現状と課題
(三重大学医学部看護学科 助教授 明石惠子) |
|
|
| 第2回 |
平成15年
10月29日(水)
10:00〜12:00 |
| (1) |
「新人看護職員研修到達目標」、「新人看護職員研修指導指針」の考え方(案)について |
| (2) |
新人看護職員研修の実際に関する意見発表
(聖路加国際病院 副院長・看護部長 佐藤エキ子)
(東札幌病院 副院長・看護部長 石垣靖子)
(北原脳神経外科病院 チーフマネジャー 熊谷節子) |
| (3) |
ワーキンググループ検討状況の発表と意見交換 |
|
| 第3回 |
平成15年
12月24日(水)
10:00〜12:00 |
| (1) |
新人看護職員研修に関するヒアリング
| ・ |
新人看護職員の立場から
(日本赤十字社医療センター 看護師 齋藤水誉) |
| ・ |
新人看護職員の指導者の立場から
(筑波メディカルセンター病院 看護師 宇都宮百恵) |
|
| (2) |
「新人看護職員研修到達目標」、「新人看護職員研修指導指針」(案)について |
| (3) |
起草委員選出について |
|
| 第4回 |
平成16年
2月26日(木)
10:00〜12:00 |
「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会報告書」(案)について
|
| ○ |
「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会ワーキンググループ」 |
| 回数 |
開催日時 |
議事内容 |
| 第1回 |
平成15年
9月25日(木)
13:00〜16:00 |
| (1) |
趣旨説明 |
| (2) |
委員からの意見発表
| ・ |
新人看護師教育の実際について
国家公務員共済組合連合会虎の門病院
看護部次長 佐藤八重子
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院
教育担当師長 黒田久美子
|
|
| (3) |
検討計画について |
|
| 第2回 |
平成15年
10月20日(月)
10:00〜16:00 |
「新人看護職員研修到達目標」、「新人看護職員研修指導指針」検討 |
| 第3回 |
平成15年
11月10日(月)
10:00〜16:00 |
| (1) |
第2回検討会における意見説明 |
| (2) |
「新人看護職員研修到達目標」、「新人看護職員研修指導指針」(案)について |
|
| 第4回 |
平成15年
12月12日(金)
10:00〜16:00 |
「新人看護職員研修到達目標」、「新人看護職員研修指導指針」(案)とりまとめ |
| ○ |
「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会起草委員会」 |
| 回数 |
開催日時 |
議事内容 |
| 第1回 |
平成16年
1月21日(水)
9:30〜12:00 |
| (1) |
趣旨説明 |
| (2) |
「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会報告書」(案)の構成について |
|
| 第2回 |
平成16年
2月2日(月)
14:00〜17:00 |
| (1) |
「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会報告書」(案)について
|
|