| ○ | 個人への業務委託の利用状況 |
|
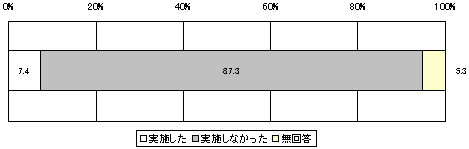
個人への業務委託を行った事業場の割合(業種・企業規模別)
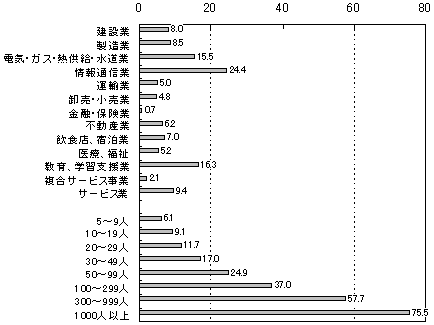
(単位:%)
| ※資料出所: | 労働政策研究・研修機構「採用戦略と求める人材に関する調査」(平成14年) |
| ○ | 業務委託契約を結んでいる業務(仕事)の内容 |
|
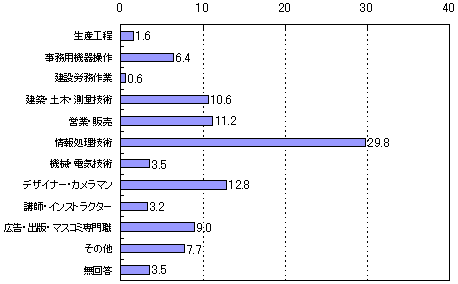
(単位:%)
| ※資料出所: | 労働政策研究・研修機構「業務委託契約従事者の活用実態に関する調査」(平成16年) |
| ○ | 業務委託契約従事者と正社員・非正社員の業務の異同 |
|
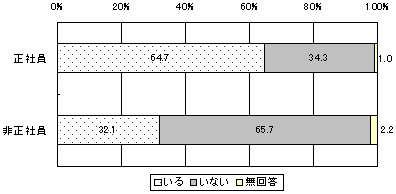
| ※資料出所: | 労働政策研究・研修機構「業務委託契約従事者の活用実態に関する調査」(平成16年) |
| ○ | 業務委託契約従事者の仕事の裁量度 |
|
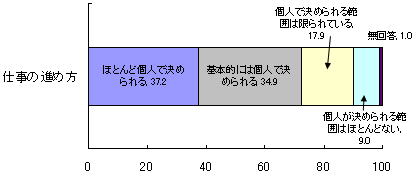
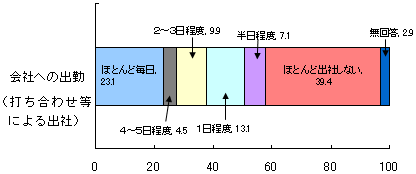
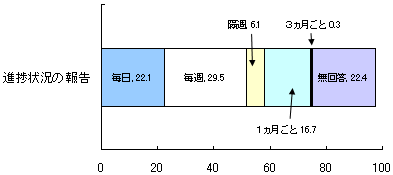
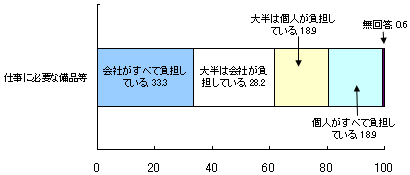
(すべて単位:%)
| ※資料出所: | 労働政策研究・研修機構「業務委託契約従事者の活用実態に関する調査」(平成16年) |
| ○ | 業務委託契約における業務内容や条件の取り決めの程度 |
|
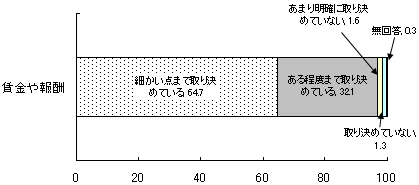
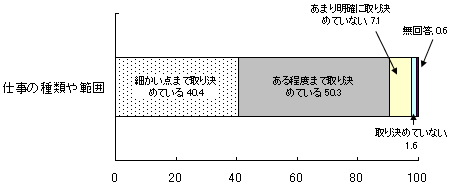
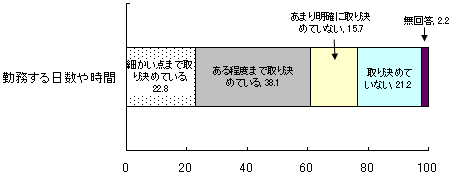
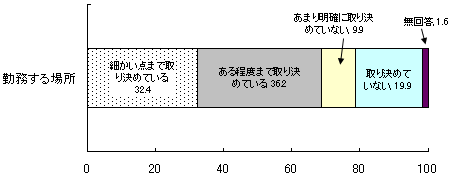
(すべて単位:%)
| ※資料出所: | 労働政策研究・研修機構「業務委託契約従事者の活用実態に関する調査」(平成16年) |
| ○ | 企業が個人への業務委託契約を活用する理由 |
|
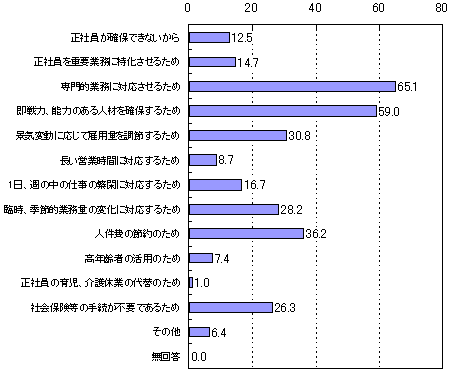
(複数回答、単位:%)
| ※資料出所: | 労働政策研究・研修機構「業務委託契約従事者の活用実態に関する調査」(平成16年) |
| ○ | 専属契約者の割合 |
|
当該企業のみと契約している割合(専属割合)
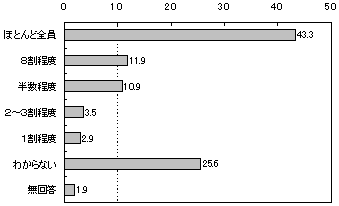
(単位:%)
| ※資料出所: | 労働政策研究・研修機構「業務委託契約従事者の活用実態に関する調査」(平成16年) |
| ○ | テレワーカー・在宅就業者の人口 |
|
≪テレワーク人口推計値(週8時間以上)≫
| テレワーカーの人口 | 比率 | |||||
| 自営型テレワーカー | 雇用型テレワーカー | 合計 | 自営業者に占める割合 | 雇用者に占める割合 | 全体 | |
| 週8時間以上テレワークを実施 | 97万人 | 311万人 | 408万人 | 8.2% | 5.7% | 6.1% |
≪在宅就業者・在宅勤務者人口推計値(週8時間以上)≫
| 在宅就業・在宅勤務の人口 | 比率 | |||||
| 在宅就業者 | 在宅勤務者 | 合計 | 自営業者に占める割合 | 雇用者に占める割合 | 全体 | |
| 週8時間以上在宅就業・在宅勤務を実施 | 82万人 | 214万人 | 296万人 | 6.9% | 3.9% | 4.4% |
| 資料出所: | 国土交通省「テレワーク・SOHO推進による地域活性化のための総合的支援方策検討調査」(平成15年3月) |
(注)
| ○ | 情報通信手段を活用して時間や場所に制約されない働き方をテレワークといい、非雇用型を「自営型テレワーカー」と、雇用型を「雇用型テレワーカー」といっている。 |
| ○ | また、テレワークを実施している者のうち自宅で実施することがある者について、ここでは非雇用型を「在宅就業」、雇用型を「在宅勤務」という。 |
| ○ | 自宅での実施以外にモバイルワークなどがある。 |
| ○ | 自営型テレワークを始めた理由 |
|
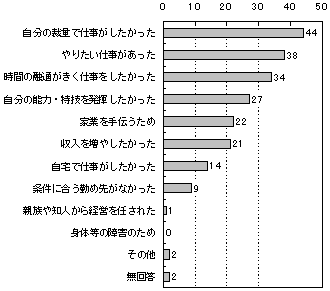
(複数回答、単位:%)
| 資料出所: | 国土交通省「テレワーク・SOHOの推進による地域活性化のための総合的支援方策検討調査」(平成15年3月) |
| ○ | 自営型テレワーカーの感じる課題 |
|
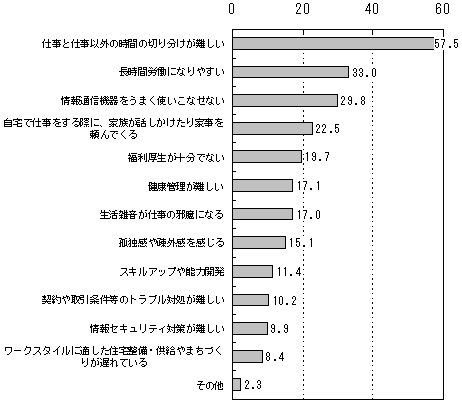
(複数回答、単位:%)
| 資料出所: | 国土交通省「テレワーク・SOHOの推進による地域活性化のための総合的支援方策検討調査」(平成15年3月) |
| ○ | 自営型テレワーカーが体験したトラブル |
|
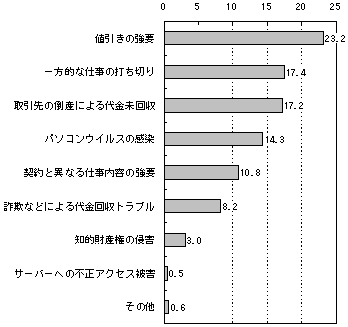
(複数回答、単位:%)
| 資料出所: | 国土交通省「テレワーク・SOHOの推進による地域活性化のための総合的支援方策検討調査」(平成15年3月) |
| ○ | 在宅就業を始めた理由 |
|
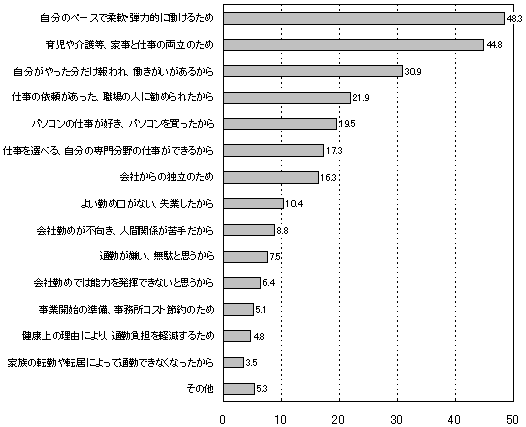
(複数回答、単位:%)
| ※ | 下記調査において「在宅就業」とは、パソコン、ワープロあるいはファックスなどの情報通信機器を使って自宅で請負・フリーの仕事を行うことをいう。 |
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働等実態調査結果報告〜情報通信機器の活用による在宅就業実態調査〜」(平成13年度) |
| ○ | 在宅就業を行っている主な職種 |
|
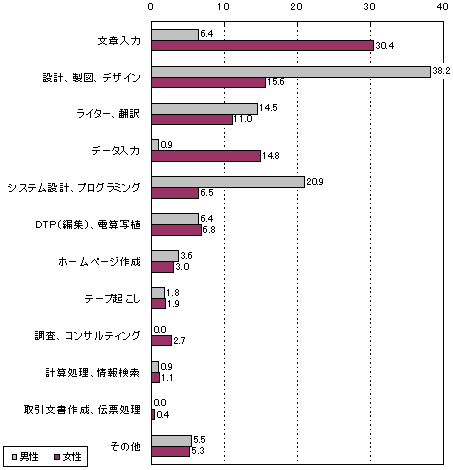
(複数回答、単位:%)
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働等実態調査結果報告〜情報通信機器の活用による在宅就業実態調査〜」(平成13年度) |
| ○ | 在宅就業者が今困っていること |
|
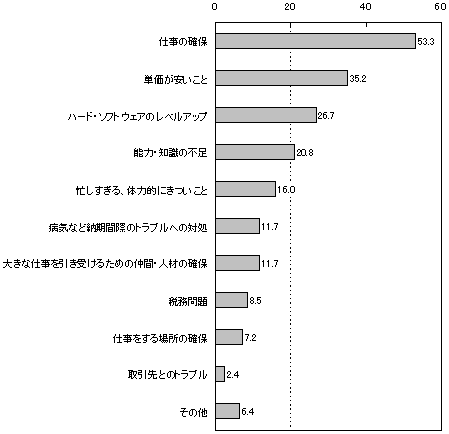
(複数回答、単位:%)
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働等実態調査結果報告〜情報通信機器の活用による在宅就業実態調査〜」(平成13年度) |
| ○ | 在宅就業者からみた発注者とのトラブルの内容 |
|
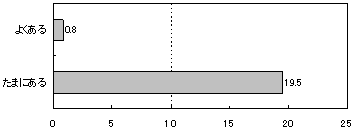 |
|
| (単位:%) | |
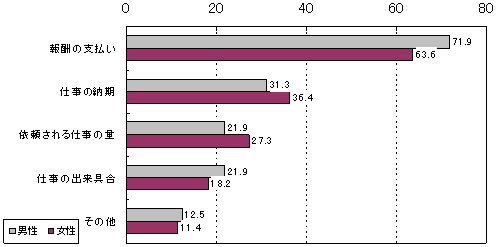
(複数回答 単位:%)
| ※ | トラブルが「よくある」「たまにある」と回答した者を対象に集計 |
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働等実態調査結果報告〜情報通信機器の活用による在宅就業実態調査〜」(平成13年度) |
| ○ | 発注者からみた在宅就業者とのトラブルの内容 |
|
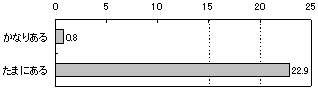 |
|
| (単位:%) | |
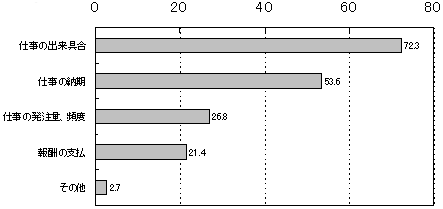
(複数回答 単位:%)
| ※ | トラブルが「かなりある」「たまにある」と回答した者を対象に集計 |
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働等実態調査結果報告〜情報通信機器の活用による在宅就業実態調査〜」(平成13年度) |
| ○ | 在宅就業者とのトラブルへの対処方法 |
|
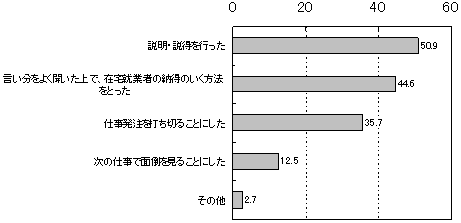
(複数回答 単位:%)
| ※ | トラブルが「かなりある」「たまにある」と回答した発注者を対象に集計 |
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働等実態調査結果報告〜情報通信機器の活用による在宅就業実態調査〜」(平成13年度) |
| ○ | 家内労働を選んだ理由 |
|
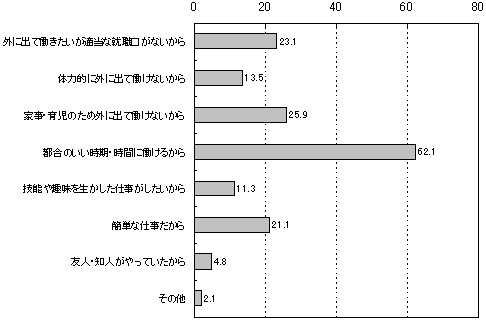
(回答者1人につき2つまでの複数回答、単位:%)
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働調査結果報告」(平成15年) |
| ○ | 家内労働を継続する意思の有無及び今後の希望 |
|
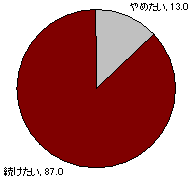 (単位:%) |
 |
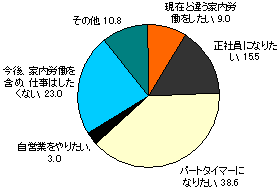 (単位:%) |
|
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働調査結果報告」(平成15年) |
| ○ | 家内労働をする上で困っていることの有無及びその理由 |
|
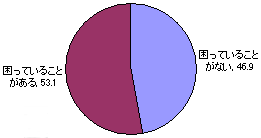 |
|
| (単位:%) | |
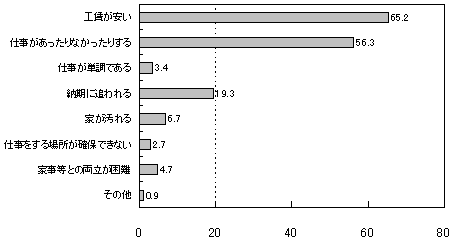
(回答者1人につき2つまでの複数回答、単位:%)
| 資料出所: | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「家内労働調査結果報告」(平成15年) |
| ○ | 労働組合の推定組織率 |
|
労働組合の推定組織率の推移
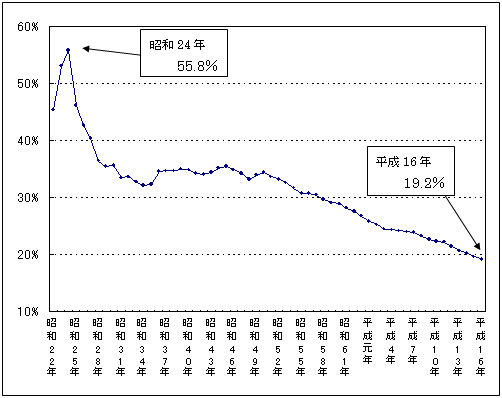
| ※ 資料出所: | 「労使関係総合調査 労働組合基礎調査報告」(厚生労働省) |
| ※ | 推定組織率は、労働組合員数を雇用者数(総務省「労働力調査」による)で除して算出したもの。 |
| ※ | 昭和48年以前は沖縄県を含まない。 |
| ○ | 労働組合の有無 |
|
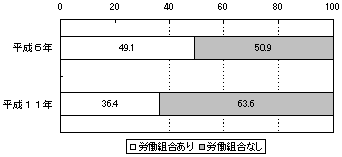
(単位:%)
| ※ | 調査対象 |
| 平成6年調査 | ・・・ | 9大産業(下記注)に属する常用労働者50人以上を雇用する民営事業所 |
| 平成11年調査 | ・・・ | 9大産業に属する常用労働者30人以上を雇用する民営事業所 |
| (注) | 9大産業 |
| (1) | 鉱業 | (6) | 卸売・小売業、飲食店 |
| (2) | 建設業 | (7) | 金融・保険業 |
| (3) | 製造業 | (8) | 不動産業 |
| (4) | 電気・ガス・熱供給・水道業 | (9) | サービス業 |
| (5) | 運輸・通信業 | ||
| 資料出所: | 労働省「労使関係総合調査 労使コミュニケーション調査報告」(平成6年、同11年) |
| ○ | 労働組合の有無とその企業における労働組合の数 |
|
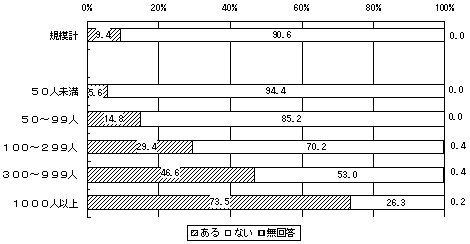
| ※ | 調査対象企業全数に尋ねたもの。 |
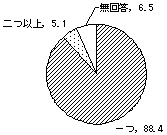
(単位:%)
| ※ | 上記問で「労働組合がある」と回答した企業に尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労働組合の組織率階級別労働組合の割合 |
|
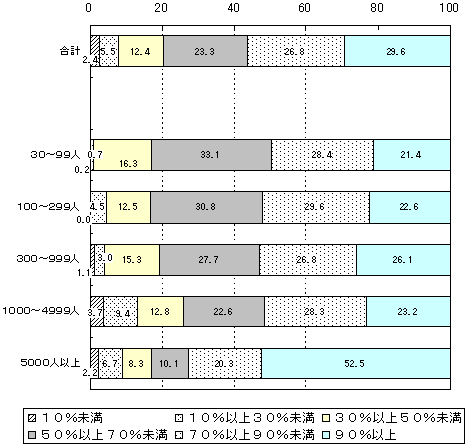
(単位:%)
| 資料出所: | 厚生労働省「労使関係総合調査 労働組合実態調査」(平成15年) |
| ○ | 企業における過半数労働組合の有無 |
|
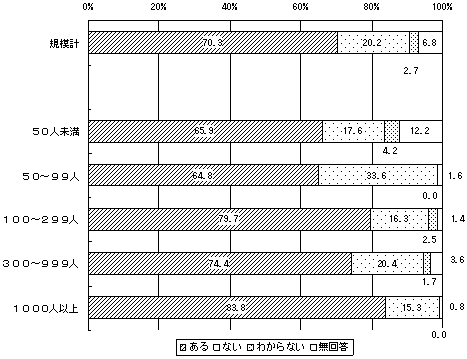
| ※ | 労働組合がある企業を対象に、従業員の過半数を組織する労働組合があるか否かを尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 事業所ごとの過半数労働組合の状況 |
|
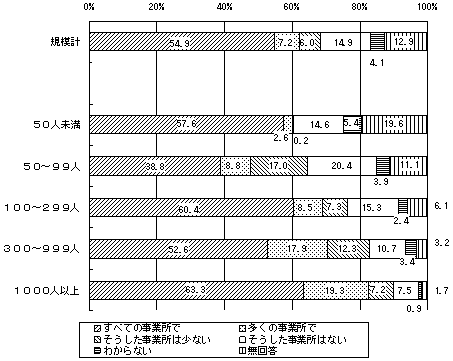
| ※ | 労働組合がある企業を対象に、事業場ごとにみて従業員の過半数を組織する労働組合があるか否かを尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労働組合員の範囲 |
|
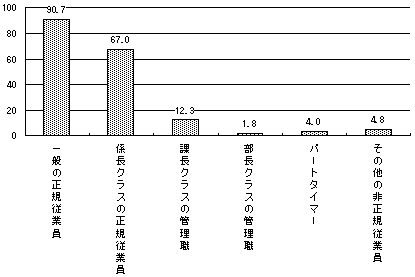
(複数回答、単位:%)
| ※ | 労働組合がある企業を対象に、労働組合員となりうる者の属性を尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労使協議機関の有無 |
|
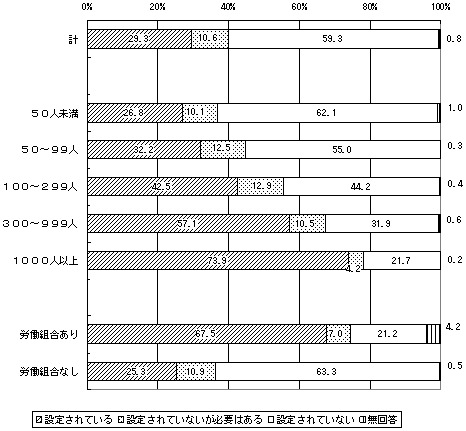
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労使協議機関の設置単位 |
|
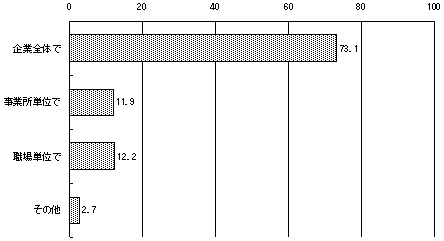
(複数回答、単位:%)
| ※ | 労使協議機関が「設置されている」と回答した企業を対象に、その設置単位を尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労使協議機関の招集主体 |
|
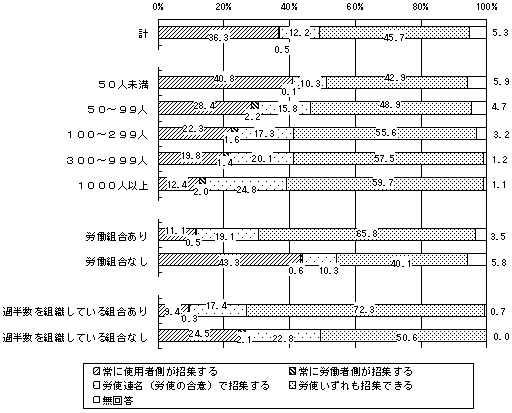
| ※ | 労使協議機関が「設置されている」と回答した企業を対象に、その招集主体を尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労使協議機関の従業員側委員の人数 |
|
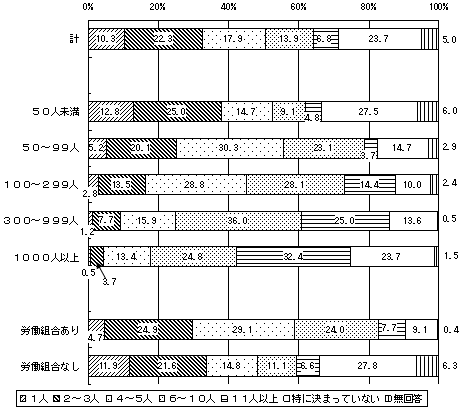
| ※ | 労使協議機関が「設置されている」と回答した企業を対象に、従業員側委員の人数を尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労使協議機関の従業員側委員の任期 |
|
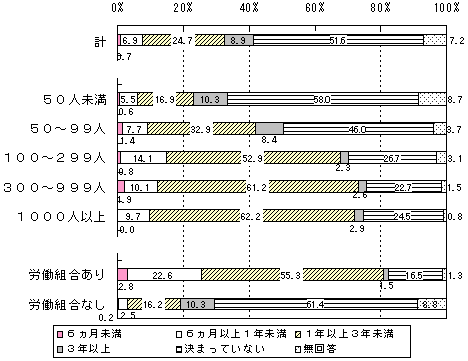
| ※ | 労使協議機関が「設置されている」と回答した企業を対象に、従業員側委員の任期を尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労使協議機関での合意内容の確認措置 |
|
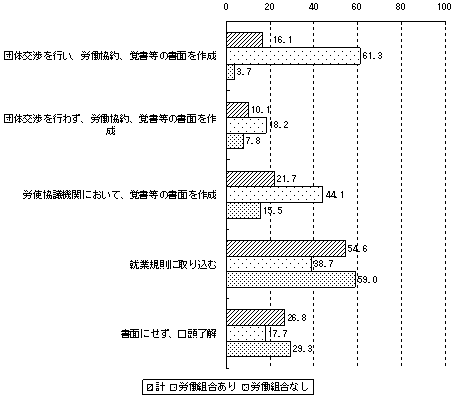
(複数回答、単位:%)
| ※ | 労使協議機関が「設置されている」と回答した企業を対象に、労使協議機関で合意に達した場合の確認方法を尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 労使協議機関の協議と労働組合の団体交渉の関係 |
|
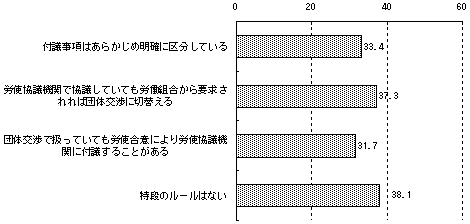
(複数回答、単位:%)
| ※ | 労使協議機関が「設置されている」と回答した企業のうち労働組合がある企業を対象に、労使協議機関と労働組合と団体交渉との関係について尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 苦情処理機関・手続の社内設置とその内容 |
|
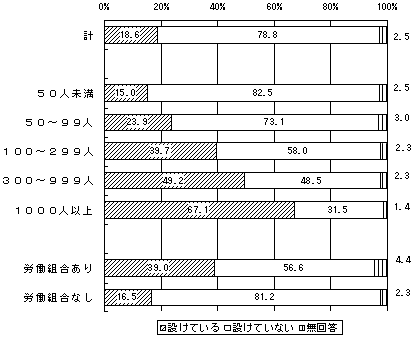
| ※ | 調査対象企業全数に尋ねたもの。 |
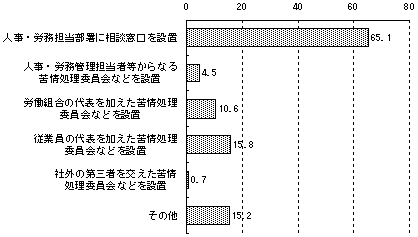
(複数回答、単位:%)
| ※ | 上記問で苦情処理機関・手続を社内に「設けている」と回答した企業を対象に、その内容を尋ねたもの。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |