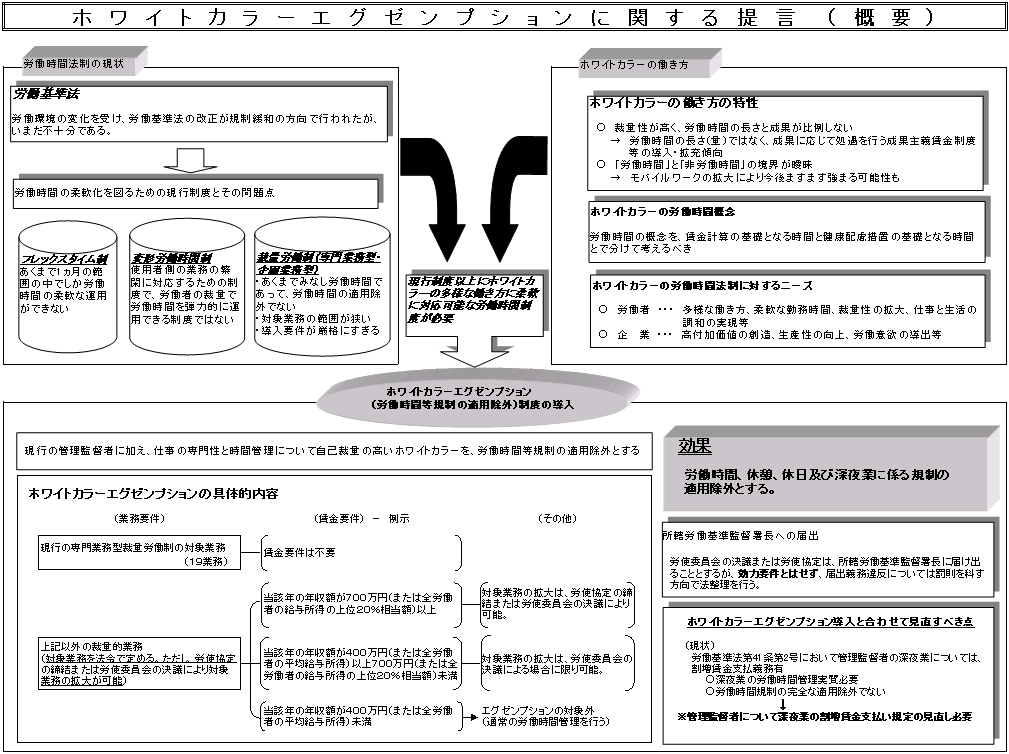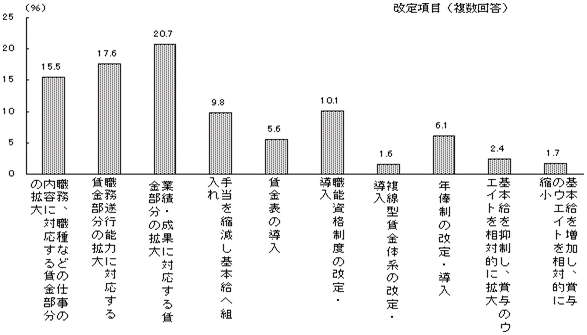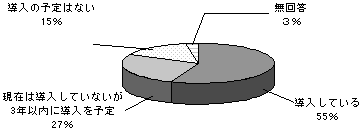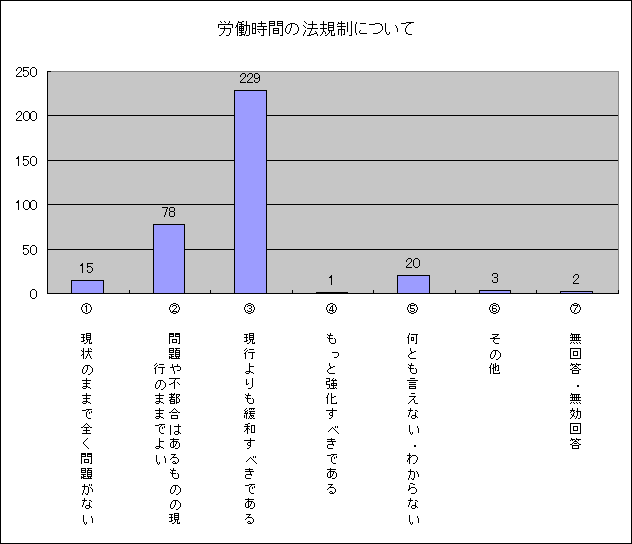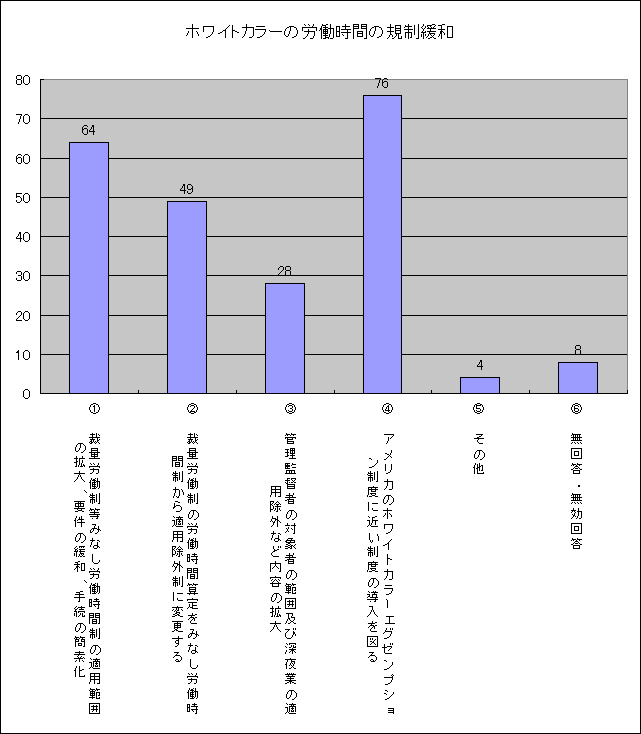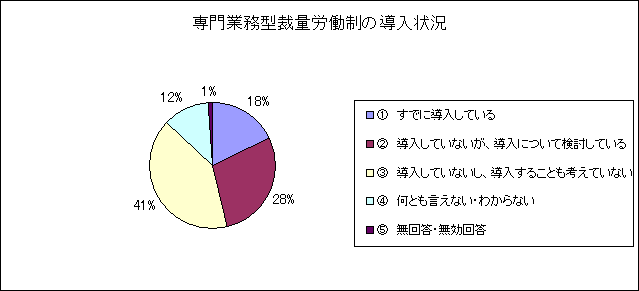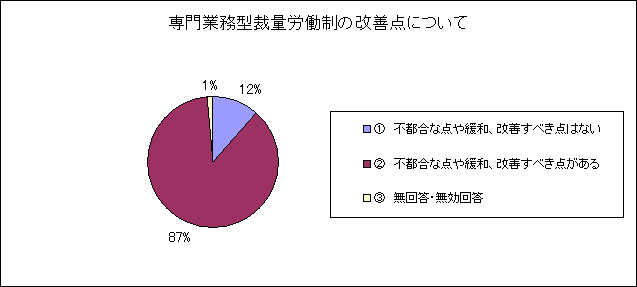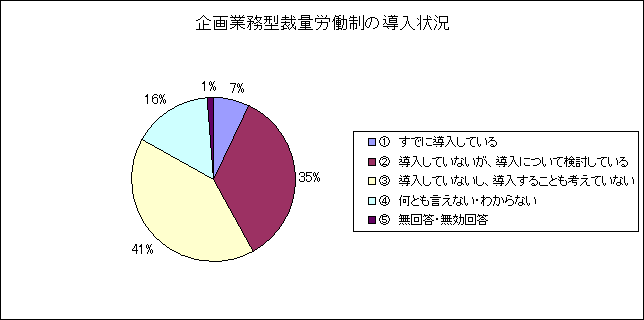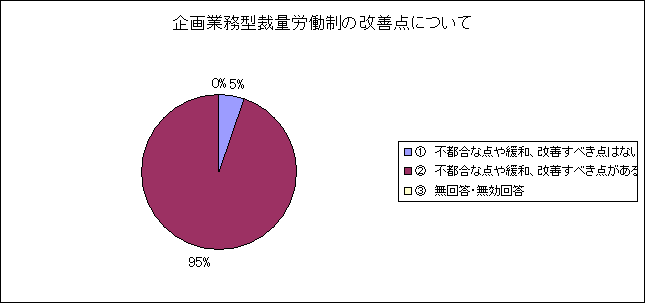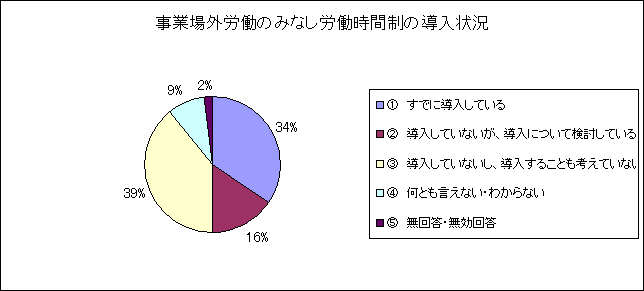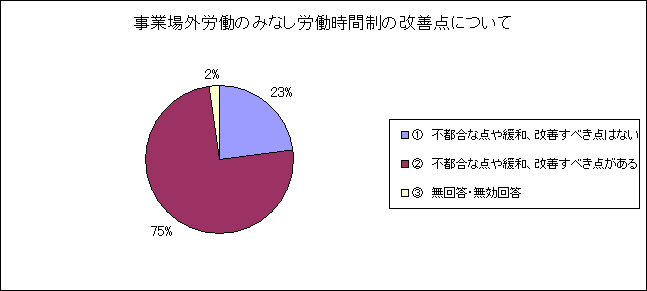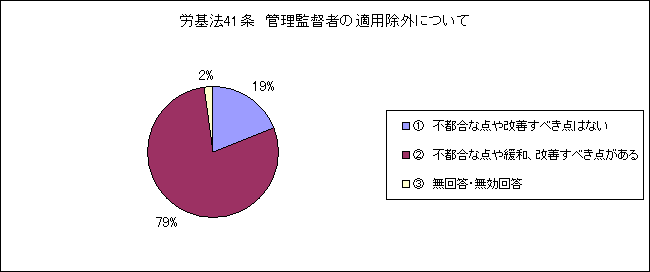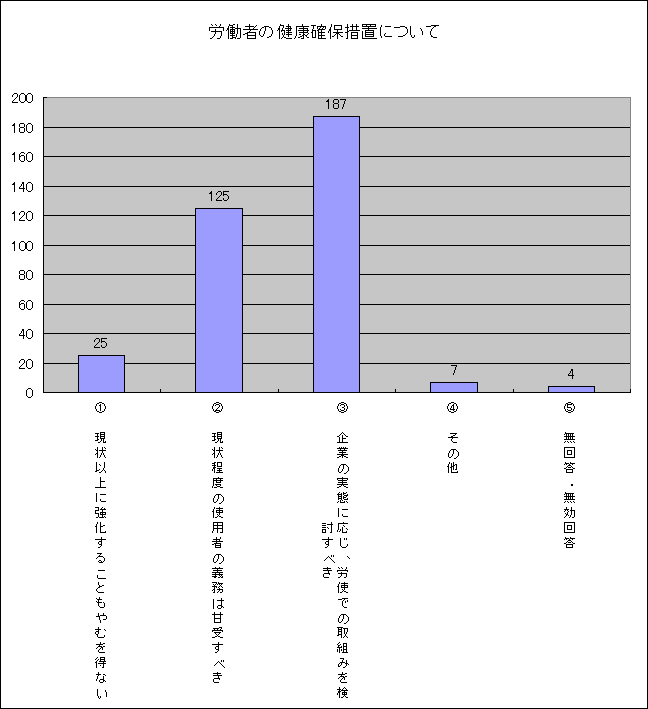2005�N6��24��
�����J���Ȍ�����q�A�����O�@�g�p�ґ��ӌ�
���{�o�ϒc�̘A����
�햱�����@�I���F
| �P�D | �V�����J�����Ԑ��x�Ƃ��Ẵz���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V����
| (�P) | ���x�n�݂̔w�i
| �E | �z���C�g�J���[�̓������̓��� |
| �E | �J�g�̃j�[�Y |
|
| (�Q) | ���x�̓��e(�v��)
|
| (�R) | ���ʂɂ���
| �E | �[��J�����ӂ��ߘJ�����ԋK���̓K�p���O�� |
|
| (�S) | ���̑��@�J���҂̌��N�m�ۂ̂��߂̔z�� |
|
| �Q�D | ���s�@��(��L�ȊO��)�������ɂ���
| (�P) | �ٗʘJ�����ɂ���
| (1) | �ΏۋƖ��͈̔͂ɂ���
|
| (2) | �v��
| �E | �ꕔ�ɘa���ꂽ�Ƃ͂����A���i�ɂ����� |
|
| (3) | ����
|
| (4) | ���̑��@�����葱��
|
|
| (�Q) | �Ǘ��ē҂ɂ���
| (1) | �͈͂ɂ���
| �E | �J�g�̎��ԂƔ���E�s�����߂̂��� |
|
| (2) | �@����
| �E | �[��J���ɂ��Ă��J�����ԋK���̓K�p�O�� |
|
|
|
| �R�D | ���̑��̖��
| (�P) | �N���L���x�ɂ̎擾���i�ɂ���
| �E | ���{�ɂ͂��Ƃ��Ƌx�������� |
| �E | �N�x�̎擾���i�|�v��N�x�̐ϋɓI���p���i |
|
| (�Q) | ����O�J���̍팸
| �E | �����s�����c�Ƃ��Ȃ������Ƃ͓��R |
| �E | �J���҂������̂��ߐϋɓI�Ɏc�Ƃ��邱�Ƃ�����B�������̈����グ�́A�������ċt���ʂɁB |
| �E | �J�����ԍ팸�̊�Ƃ̎���I�Ȏ�g�݂̗� |
|
|
�ȏ�
�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�����Ɋւ����
2005�N6��21��
�i�Ёj���{�o�ϒc�̘A����
�ڎ�
�͂��߂�
| �P�D | �z���C�g�J���[�̘J�����ԊT�O�ƘJ�����ԊǗ��̍l����
|
| �Q�D | �z���C�g�J���[�ɂ�����J�����ԂƐ��ʂ̖��
|
| �R�D | �z���C�g�J���[�ɂ����鑽�l�ȓ������ƘJ�����Ԃ�
�e�͉��̕K�v��
|
| �S�D | �݂Ȃ��J�����Ԑ��̖��_
| �m�P�n | <���Ɩ��^�ٗʘJ����> |
| �m�Q�n | <���Ɩ��^�ٗʘJ����> |
|
| �T�D | �Ǘ��ēҁi�J����@��41���2���j�̘J�����ԓ�
�K�p���O�̖��_
|
| �U�D | �J�����ԋK���̌������ɂ���
| �m�P�n | <�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�̐V��> |
| �m�Q�n | <�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�̋�̓I���e> |
| �m�R�n | <�J���҂̌��N�ւ̔z���[�u�ɂ���> |
| �m�S�n | <�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�����̖@�����ɂ���> |
|
������
�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�����Ɋւ����
�͂��߂�
�@�J����@�́A���Ԃ��Ȃ�1947�N�ɐ��肳��A�J���ҕی�ɑ傫����^���Ă����B���@�́A��1���2���Łu���̖@���Œ�߂�J�������̊�͍Œ�̂��̂ł���v�Ƃ��������ŁA��O�̍H��@���N���҂⏗����ی삷�邽�߂ɘJ�����ԋK�����s���Ă����̂Ɠ��l�ɁA�J���ҕی�̊ϓ_����J�����Ԃ𐧌����邱�Ƃ���̑傫�Ȓ��Ƃ��Ă���B�������A���������J�����ԋK���̍l�����́A�H����̒�^��Ə]���ғ��ɂ͓K��������̂́A���݂̃z���C�g�J���[�̏A�Ǝ��Ԃɂ͕K���������v���Ă��Ȃ��B
�@�ٗʐ��������Ɩ����s���A�J�����Ԃ̒����Ɛ��ʂ���ʂɔ�Ⴕ�Ȃ����]�J���ɏ]������悤�ȃz���C�g�J���[�ɑ��A�ꗥ�ɍH��J�������f���Ƃ����J�����ԋK�����s�����Ƃ͓K�Ƃ͂����Ȃ��B�����A�d���Ɛ����̒��a��}�邽�߁A���l�ȋΖ��`�Ԃ̒�����A�����I�Ŏ��炪�[���ł��铭������I�����A�S�g�Ƃ��ɏ[��������ԂŔ\�͂��\���ɔ������邱�Ƃ�]��ł���҂����Ȃ��Ȃ��B
�@���������J�����̕ω����A�J����@�̉��������x�ɂ킽��s��ꂽ�B�Ƃ�킯�A2000�N�Ɋ��Ɩ��^�ٗʘJ��������������A2003�N�ɂ͓K�p���Ə�̊g��ȂNjK���ɘa�̕����ʼn������s��ꂽ���Ƃ́A������x�]���ł���B�������Ȃ���A�K���ɘa�Ƃ͂����Ă����̓��e�͂��܂��s�\���ł���A���s�̘J�����Ԗ@���͈ˑR�Ƃ��ăz���C�g�J���[�̎�̓I�ȓ������ɏ\����������e�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
�@���s�̘J�����Ԗ@���ɂ́A��̓I�ŏ_��ȓ������ɓ�����x�Ƃ��āA���Ɩ��^�ٗʘJ�����̂ق��ɂ��A�t���b�N�X�^�C�����A���Ə�O�݂Ȃ��J�����Ԑ��A���Ɩ��^�ٗʘJ�������p�ӂ���Ă���B�������A�������J�����ԋK���Ƃ����l��������E�p���Ă��炸�A�J�����ԂɂƂ���Ȃ����R�ȓ������ɑΉ�����ɂ͕s�\���ł���B
�@�܂��A�J����@��41���Q���ɒ�߂�Ǘ��ē҂̋K����A�[��Ƃ̊��������̎x�������K�p���O�Ƃ���Ă��Ȃ��Ƃ����_�ŁA�^�̈Ӗ��ɂ�����J�����Ԃ̓K�p���O�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�������A���̑Ώێ҂͈̔͂��A����E�ʒB�̉��߂ɂ��A�ɂ߂ċ����͈͂Ɍ��肳��Ă���A���݂̊�Ƃ̎��ԂɊӂ݂�ƁA�傢�ɋ^�₪�c��B
�@�o�ϊ����̃O���[�o�����A�Y�ƁE�A�ƍ\���̕ω��A�A�ƈӎ��̕ω��A�ٗp�`�Ԃ̑��l���ȂǁA�J�������߂���̕ω��ɏ_��ɑΉ����邽�߂ɂ́A����܂ł̉��I�ȓ�������O��Ƃ��ĘJ�����ԋK�����s���l�������{�I�ɉ��߂�K�v������B���Ȃ��Ƃ����̗v�������z���C�g�J���[�ɂ��ẮA�J�����ԋK���̓K�p���O�Ƃ��鐧�x�𑁋}�ɐ������ׂ��ł���B
�@2004�N�ɓ��{�o�c�A���s�����u�J�����Ԗ��Ɋւ���A���P�[�g�����v�i�ȉ��u���{�o�c�A�̃A���P�[�g�����v�Ƃ����j�ɂ����Ă��A�z���C�g�J���[�ɂ��ẮA�J�����ԋK���̓��e���u���s�����ɘa���ׂ��ł���v�Ƃ����ӌ��������B�����āA�K���ɘa�̕������ɂ��ẮA�u�A�����J�̃z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�ɋ߂����x�̓�����}��ׂ��v�A�u�ٗʘJ�����̓K�p�͈͂̊g��A�v���̊ɘa�A�葱�̊ȑf���Ȃǂ��K�v�v�Ƃ������ӌ����吨���߂Ă���B
�@�������̑I�����𑝂₵�A�J���҂̋ΘJ�ӗ~�ɏ\���ɉ����A���Y�������コ���A�䂪���Y�Ƃ̍��ۋ����͂̋����ɂ��q����z���C�g�J���[�ɓK�����J�����Ԑ��x�Ƃ͈�̂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�ȏ�̓_�܂��A�ȉ��ł́A���̂�����ɂ��ċ�̓I�Ɍ�������B
�P�D�z���C�g�J���[�̘J�����ԊT�O�ƘJ�����ԊǗ��̍l����
�@�z���C�g�J���[�́A�u�l���邱�Ɓv����̏d�v�Ȏd���ł���A�E��ɂ��鎞�Ԃ����d�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B����ɋ���Ƃ���ʋΓr��Ȃǂł��A�d���̂��ƂɎv�����߂��炷���Ƃ́A���������Ƃł͂Ȃ��B�t�ɁA�I�t�B�X�ɂ��Ă��A�����d�������Ă���Ƃ͌���Ȃ��B�܂�A�u�J�����ԁv�Ɓu��J�����ԁv�̋��E���A�z���C�g�J���[�A���̒��ł��Ƃ�킯�m�I�J���ґw�ɂ����ẮA�B���Ƃ�����B
�@����ɁA�z���C�g�J���[�̏ꍇ�A��Ђ̋Ɩ����I��������A�����̋��������镪��̌����⎩�Ȍ[���Ȃǂ������I�ɍs�����Ƃ�����B�����̎��Ԃ́A��Ђ̋Ɩ��ł͂Ȃ�����Ƃ����āA��T�Ɂu�J�����ԁv�ł͂Ȃ��Ƃ���������Ȃ��B�ꍇ�ɂ���ẮA�������������⎩�Ȍ[�����{�l�̐E�Ɣ\�͂̌���Ɍq����A�Ɩ��ɖ𗧂��Ƃ��\���ɍl�����邩��ł���B
�@���̂悤�ɁA�z���C�g�J���[�̏ꍇ�A�u�J�����ԁv�Ɓu��J�����ԁv�̋��E���B���ł���Ƃ��������́A�h�s�@��̕��y�ɂ�郂�o�C�����[�N�̊g��ɂ���č���܂��܂����܂��Ă������Ƃ��\�z�����B
�@�����ŁA�z���C�g�J���[�̘J�����Ԃɂ��čl����ꍇ�ɂ́A�܂��J�����Ԃ̊T�O�ɂ��Đ�������K�v������B
�@����܂ŁA�J�����Ԃɂ��ẮA�u�g�p�҂̎w�����߉��ɒu����Ă��鎞�ԁv�A�u�����v�Z�̊�b�ƂȂ鎞�ԁv�A�u���N�m�ۑ[�u�̑ΏۂƂ��ׂ����ԁv�ȂǂƁA���̐������\���ɂȂ���Ȃ��܂܁A���܂��܂ȋc�_���s���Ă����B
�@�u���[�J���[�Ƃ͈قȂ�A�u�J�����ԁv�Ɓu��J�����ԁv�̋��E���B���ȃz���C�g�J���[�̏ꍇ�A�����v�Z�̊�b�ƂȂ�J�����Ԃɂ��ẮA�o�Ў�������ގЎ����܂ł̎��Ԃ���x�e���Ԃ����������ׂĂ̎��Ԃ�P���ɘJ�����ԂƂ���悤�ȍl�������̂邱�Ƃ͓K�ł͂Ȃ��B�u�Ɩ��𒆒f���Ă��鎞�ԁv�Ƃ����̂����R�l������킯�ł��邪�A�������x�������ɂƂ��Ă��������Ɩ��̒��f���Ԃ������ɔc�����A����I�ɏؖ����邱�Ƃ́A������s�\�Ƃ����邩��ł���B
�@�����A�J���҂̌��N�m�ۂ̖ʂ���́A�����s���ɗR�������J�̒~�ς�h�~����Ȃǂ̊ϓ_����A�ݎЎ��Ԃ�S�����Ԃ���Ƃ��ēK�ȑ[�u���u���邱�ƂƂ��Ă����قǑ傫�Ȗ��͂Ȃ��Ƃ�����B
�@���̂悤�ɁA�J�����Ԃ̊T�O���A�����v�Z�̊�b�ƂȂ鎞�Ԃƌ��N�m�ۂ̂��߂̍ݎЎ��Ԃ�S�����ԂƂŕ����čl���邱�Ƃ��A�z���C�g�J���[�ɐ^�ɓK�����J�����Ԑ��x���\�z���邽�߂ɂ́A���̑����ƂȂ�ƍl����B
�Q�D�z���C�g�J���[�ɂ�����J�����ԂƐ��ʂ̖��
�@�z���C�g�J���[�̘J���ɂ́A�d���̐��ʂƘJ�����Ԃ̒������K���������v���Ȃ��Ƃ�������������B���������āA�z���C�g�J���[�̘J���ɑ��ẮA�J�����Ԃ̒����i�ʁj�ł͂Ȃ��A�����E���ʂɉ����ď������s���Ă������������I�ł���B�J���҂ɂƂ��Ă����̕����A���������ۂāA���`�x�[�V�������オ��B
�@�܂��A�o�ς̃O���[�o�����̐i�W�⍑�ۋ����̌����ɔ����āA�z���C�g�J���[�ɂ́A����܂ňȏ�ɍ������Y�������߂��Ă���B���������f���Ă��A�����̌���ɍۂ��A�ƐсA���ʁA�E�����s�\�́A�E���A�E��Ȃǂ̗v�f���d�����鐬�ʎ�`�������x��\�͎�`�������x���A�g�[�����Ƃ������Ă���i�}�\�P�Q�Ɓj�B���̌X���́A��������炭�������̂ƍl������i�}�\�Q�Q�Ɓj�B
�}�\�P�@�ߋ�3�N�Ԃ̒������x�̉����
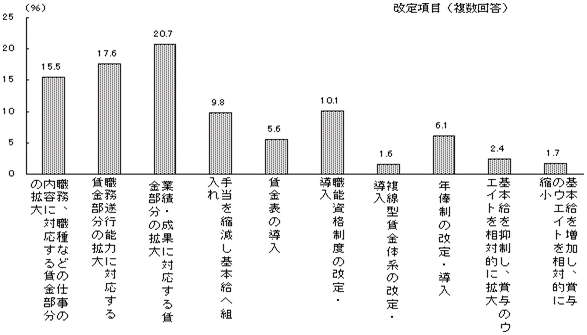 |
| �o���F�����J���ȁu����16�N�A�J���������v��� |
�}�\�Q�@�d���̐��ʂ�����ɔ��f�����鐧�x�̓�����
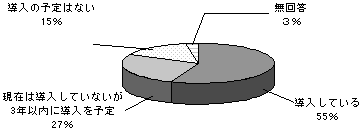
| �����F | �J�������E���C�@�\�iJILPT�j�u�J���҂̓����ӗ~�ƌٗp�Ǘ��̂�����Ɋւ��钲���i��ƒ����j�v�i2004�N�j |
�@�Ƃ���ŁA�J�����Ԃ̒���������x�����̊�Ƃ��錻�s�@�����ł́A������I�ɒ����ԓ������҂͎��ԊO�����������x�������̂ŁA�����I�ɒZ���Ԃœ������ʂ��グ���҂����A���ʂƂ��Ă��̕�V�������Ȃ�Ƃ�����������������B���̂悤�Ȗ����͈�ߐ��̂��̂ŁA�����I�Ɍ���A�����I�ɓ������҂̕����A���i�����܂߁A���ʓI�ɕ�V�������Ȃ�A�s�����͎����Ɛ��������Ƃ������l��������B�������Ȃ���A�J���҂̍v���ɑ���Ή��������I�Ɍ��Č����ŋύt�������̂ɂȂ�悢�Ƃ����l���́A�ٗp�̗�������J���҂̃��`�x�[�V�������ɒ��ڂ����ꍇ�A�����͂��������ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ɁA�z���C�g�J���[�̎d���̓������l����ƁA�����ƘJ�����Ԃ̒����Ƃ��֘A�����Ă��錻�s�̘J�����Ԗ@���ɂ͑傫�Ȍ��E������A�z���C�g�J���[�ɂ��ẮA���������J�����Ԃƒ����̒��ړI�Ȍ��т��������������ɂ���Ƃ�����B�Ƃ�킯�A�J�����Ԃ̌����ȎZ�肪����ȋƖ��A�ٗʐ��̍����Ɩ��ɏ]������z���C�g�J���[�ɂ��ẮA���̗v���������Ƃ������ɁA���Ȃ��Ƃ������ƘJ�����ԂƂ����邱�Ƃ��}���Ƃ����悤�B
�R�D�z���C�g�J���[�ɂ����鑽�l�ȓ������ƘJ�����Ԃ̒e�͉��̕K�v��
�@�J���҂̒��ɂ́A�����̂��߂����ɓ��������A�d�����������̎��ƒ�c�R�ɏd�_�����������A���������Č��߂�ꂽ���Ԉȏ�͓��������Ȃ��ƍl����҂�����B����A�J�����ԂɂƂ��ꂸ�A�[���̂����d���A�����̂����d�����������A���R�Ɏ����̔\�͂��������A�d����ʂ��Ď��Ȏ������������ƍl����҂�����B���̂悤�ɁA���l�ς͐l���ꂼ��ł���B
�@�������Ȃ���A�킪���̘J�����Ԗ@���́A�O�҂̂悤�ȍl����������J���҂݂̂�z�肵�Ă���悤�Ɏv����B�z���C�g�J���[�̒��ɂ́A�^����ꂽ�d����P���ɏ�������̂ł͂Ȃ��A�d���̖ړI�A�Ӗ��A���l���\���ɔF��������ŁA�����I�A��̓I�Ɏd���Ɏ��g�݁A�n�ӍH�v�ɂ��d���̌��������߂悤�Ƃ���J���҂���������B�����āA�����������l����������J���҂ɂ́A�W�����Č����悭�����A���ʂƂ��ĘJ�����Ԃ�Z������悤�w�͂��Ă���҂����Ȃ��Ȃ��B
�@�z���C�g�J���[�̏ꍇ�A���A���āA�������̎�v�ȋƖ��ȊO�ɂ��A�ł����킹�⏤�k���A�K���������X�̎��Ԃ����܂��Ă��Ȃ����^�I�Ɩ���ӑR�ƍs���Ă���҂������B���̏ꍇ�A�W���I�ɓ����K�v�����镔���Ǝ��ԓI�ɗ]�T�̂��镔��������A���R�̂��ƂȂ���A�d�����x�̔Z�W�́A�J���҂̐E���Ɩ����e���ɂ��قȂ�B1���A1�T�ԁA1�����A3�����A���N���̒P�ʂŊ�������̂ł͌����ĂȂ��B
�@���̂悤�ȋƖ��̔ɊՂɑΉ����邽�߂ɁA�n�Ƌy�яI�Ƃ̎�����J���҂̌���ɂ䂾�˂�t���b�N�X�^�C���������ݔF�߂��Ă��邪�A���Z���Ԃ��P�����ȓ��̊��ԂƂ���A�P����������Ԃɂ��Ă͑Ή��ł��Ȃ��Ƃ�����肪����B
�@�����A�P�T�̕��Ϗ���J�����Ԃ��@��J�����Ԃ��Ȃ����Ƃ������ɁA����̏T���͓���̓��ɖ@��J�����Ԃ��ĘJ�������邱�Ƃ��\�Ƃ��鐧�x�Ƃ��āA�ό`�J�����Ԑ�������B�����A�t���b�N�X�^�C�����Ƃ͈قȂ�A�e�T��e���̘J�����Ԃ�J���҂����R�Ɍ��߂�����̂ł͂Ȃ��A�J���҂̑����猩���ꍇ�A�J�����Ԃɑ����̐��͎����Ɛ�������邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�ό`�J�����Ԑ��͎g�p�ґ��̋Ɩ��̔ɊՂɑΉ����邽�߂̐��x�ł��邱�Ƃ���A�d���̐i���ɂ��킹�ĘJ���Ҏ��g���J�����Ԃ�����I�ɃR���g���[�����邱�Ƃ͓���Ƃ�����B
�@���l�ȓ��������������邽�߂ɂ́A�X�̘J���҂̋Ɩ��̔ɊՂɉ����A�K�v������Ƃ��ɂ͏W�����ē������A���ԓI�ɗ]�T�̂���Ƃ��͋x�ɂ��Ƃ�����A�J�����Ԃ�Z��������ł���悤�ɂ��鐧�x�A�܂莩�Ȃ̍ٗʂŘJ�����Ԃ�e�͓I�ɉ^�p�ł��鐧�x���K�v�ł���B
�@�܂��A���]�J���̏ꍇ�A���q����������Ƃ��ɏW���I�ɓ������������I�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��邵�A���̕����{�l�̔�J�������Ȃ��A�t�ɒB�����▞�����͍����Ȃ�B���̂��Ƃ�����A�J���҂̌��N�ɔz�����Ȃ���A�J���҂��J�����Ԃ�����I�ɐv�ł���悤�Ȓe�͓I���x�̓������]�܂��B�����āA���̂悤�Ȍ����I�ȓ������́A���ʓI�ɂ͑��J�����Ԃ̒Z�k�Ɍq����ƍl������B
�@����ɁA���ԊǗ��̖ʂ�����A���̗v�������z���C�g�J���[�ɂ��ẮA�v�������J�����Ԃ̒e�͉����K�v�ł���B�������ɁA�J����@�ɂ͍ٗʘJ������Ǘ��ē҂̓K�p���O�K�蓙���p�ӂ���Ă���B�������A���̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��z���C�g�J���[�̒��ɂ��A���J�����ԊǗ��ɂȂ��܂Ȃ��҂��������݂���̂����Ԃł���B
�@�����ŁA����܂Œʂ茵�i�Ȏ��J�����ԊǗ���K�v�Ƃ���J���҂Ƃ����łȂ��J���҂Ƃm�ɋ敪���A���J�����ԊǗ������ׂ��J���҂ɂ��ẮA������Ǝ��ԊǗ����s�����A�����łȂ��z���C�g�J���[�ɂ��ẮA���̎��ԂɓK�������J�����Ԓe�͉��̕������������K�v������B
�S�D�݂Ȃ��J�����Ԑ��̖��_
�@��3���Y�Ƃ̊g���Z�p�v�V�̐i���ɔ����A��̓I�Ȏw���ē��y���A�J�����Ԃ̎Z�肪����ȋƖ����g�������B
�@�����ɋƖ��̐�����A���̋�̓I�Ȑ��s���@��J���҂̍ٗʂɂ䂾�˂�K�v�����邱�Ƃ���A�ʏ�̕��@�ɂ��J�����Ԃ̎Z�肪�K�Ƃ͂����Ȃ��Ɩ����������B
�@���̂悤�ȏɑΉ����邽�߁A�݂Ȃ��J�����Ԑ��̋K��̐������s���Ă����B��̓I�ɂ́A1987�N�̘J����@�̉����Łu���Ə�O�J�����v�Ɓu���Ɩ��^�ٗʘJ�����v�̋K�肪�V�݂���A����ɁA1998�N�̘J����@�����ɂ��u���Ɩ��^�ٗʘJ�����v���݂���ꂽ�B
�@�]���̘J�����Ԑ��x�̂�����Ɋւ���c�_�́A�ٗʐ��̍����z���C�g�J���[�̘J���ɓK������悤�J�����Ԃ̏_���啝�ɐi�߂�ׂ��ł���Ƃ���咣�ƁA�����ԘJ����T�[�r�X�c�Ƃ������錜�O�����邱�Ƃ���A�J�����Ԃ̏_����Œ���ɂƂǂ߁A���邢�͂���Ɍ������v�����ۂ��ׂ��ł���Ƃ������咣���Η�����`�Ői��ł����B
�@�Ƃ�킯�A�ٗʘJ�����Ɋւ��Ă͂��̌X���������A���݂̐��x�́A���̓�����^�p�ɂ������Č������v�����ۂ����Ă���B2003�N�̘J����@�����ɂ���̋K���ɘa���Ȃ��ꂽ�Ƃ͂����A�J�g�ψ���̐ݒu���͂��߁A�J�g�ψ���ł̌��c�A�{�l���ӗv����������A���x�̓������e�ՂłȂ��������������c���Ă���B���{�o�c�A�̃A���P�[�g�����ɂ����Ă��A�ٗʘJ���������Ă��邩�A�܂��͂��̓������������Ă����Ƃ̎���85���ȏオ�A���x�ɂ��āu�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������v�Ɖ��Ă���B
�@�{���A�u�݂Ȃ��J�����Ԑ��v�́A�����ʂ���̎��ԘJ���������̂Ɓu�݂Ȃ��v���Ƃ�ړI�Ƃ������x�ł����āA�J�����ԋK��̓K�p�����O������̂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��_�ɖ�肪����B�O�q�̃A���P�[�g�����Łu���x�ɕs�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������v�Ɖ�����Ƃ̖����u�݂Ȃ��J�����Ԑ��v�ɂ��ĉ��P�����߂Ă��邱�Ƃ�����A�u�݂Ȃ��J�����Ԑ��v�͊�Ƃ̎��Ԃɍ����Ă��Ȃ��Ƃ�����B�܂��A���J���Ȃ́u�ٗʘJ�����Ɋւ��錤����v�i�����F���@������w�@�ȑ�w�@�����@����a�v���j�ɂ����Ă��A�ٗʘJ������J����@��41���ɒ�߂�u�K�p���O�v�Ƃ��Ĉʒu�t����ׂ��ł���Ƃ����咣���Ȃ���Ă������Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B
�@�����̗��R�ɉ����A�Ɩ��̐��s���@�⎞�Ԕz������啝�ɘJ���҂̍ٗʂɂ䂾�˂�Ƃ����ٗʘJ�����̖{���̎�|����l���Ă��A�u�݂Ȃ��J�����Ԑ��v�ł͂Ȃ��A�u�J�����Ԃ̓K�p���O�v���x���̗p���邱�Ƃ��A���x�{���̎p���Ƃ�����B
�@�����ŁA�ȉ��A���Ɩ��^�ٗʘJ�����Ɗ��Ɩ��^�ٗʘJ�����ɂ����邻�̑��̖��_�ɂ��Ă���Ɍ�������B
�m�P�n<���Ɩ��^�ٗʘJ����>
�@���Ɩ��^�ٗʘJ�����ɂ�����ő�̖��_�́A�����J���ȗ߂ƌ����J����b�����ɒ�߂�ΏۋƖ��͈̔͂������Ƃ����_�ɂ���B���݁A�ΏۋƖ���19�Ɍ��肳��Ă���A�J�g�������������Ƃ��Ă��A����ȊO�̋Ɩ��ɍٗʘJ������K�p���邱�Ƃ͔F�߂��Ă��Ȃ��B
�@���{�o�c�A�̃A���P�[�g�����ɂ����Ă��A���Ɩ��^�ٗʘJ�����ɂ��āu�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������v�Ɖ��Ă����Ƃ̖�7�����A�u�ΏۋƖ��͈̔́v�ɂ��ĉ��P�����߂Ă���B
�@�u�Ɩ��̐�����A�Ɩ����s�̎�i����@�A���Ԕz������啝�ɂ䂾�˂�K�v������Ɩ��v�Ƃ����̂́A�e��Ƃ̋Ǝ�E�ƑԂɂ���Ĉꗥ�ł͂Ȃ��A�ΏۋƖ��͈̔͂�J�g�����肷�邱�Ƃɂ��g�傷�铹��K�v������B
�@�����A2003�N�̘J����@�����ɂ����āA�J�g����Ɂu�ΏۘJ���҂̘J�����Ԃ̏ɉ����Ď��{���錒�N�E�������m�ۂ��邽�߂̑[�u�̋�̓I���e���v���lj�����A�J���ҕی삪�}���A���x�^�p�̓K�����Ɍ�������g�݂̋����͏\���}���Ă���B
�@�����ŁA�ȗߋy�ё�b�����Œ�߂�ꂽ�Ɩ��ȊO�ɂ��A�X�̊�Ƃ̎��Ԃɉ����āA�J�g����ɂ����Ɩ��^�ٗʘJ�������ł���Ɩ������肷�邱�Ƃ��ł���悤�Ȑ��x���K�v�ł���B
�m�Q�n<���Ɩ��^�ٗʘJ����>
�@���{�o�c�A�̃A���P�[�g�����ł́A���Ɩ��^�ٗʐ������Ă��邩�A�܂��͂��̓������������Ă����Ƃ̎���94�D5�����A���s���x�ɂ��āu�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������v�Ɖ��Ă���B
�@���ł��A���Ɂu�Ɩ����������鎖�Ə�̎��Ƃ̉^�c�Ɋւ�����̂ł��邱�ƁA���A���āA�����y�ѕ��͂̋Ɩ��ł��邱�Ɠ��̗v�����ۂ��Ă���ΏۋƖ��͈̔͂ɂ��Ă��̊ɘa�A���P�����߂�v�Ƃ������������Ȃ��Ă���B
�@2003�N�̘J����@�����ɂ����ẮA���Ɩ��^�ٗʘJ�����̓����������܂�ɂ��Ⴂ���Ƃ���A���Љ��ɂ��x�X���ւ̖{�Ћ@�\�̈ړ]�Ƃ�����Ƃ̎��Ԃ��l�����u�{�ЂȂǎ��Ɖ^�c��̏d�v�Ȍ��肪�s���鎖�Ə�Ɍ���v�Ƃ������Ə�̐������p�~���ꂽ�B
�@�������A�ΏۋƖ��ɂ��Ă͌��������s��ꂸ�A�u���A���āA�����y�ѕ��͂̋Ɩ��v�̂܂܂ƂȂ��Ă���A�u�o�c��敔�v�u�o�c�헪���v���̂���߂Č���ꂽ�Z�N�V�����ł����A���̐��x��K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ɂ���B�{�X�̂����̋@�\���x�X���Ɉڂ�����Ƃł͓K�p�ΏۘJ���҂�������������A�����łȂ���Ƃł́A�ˑR��������ꂽ�J���҂ɂ������̐��x��K�p�ł��Ȃ��̂�����ł���B
�@�܂��A�u���A���āA�����y�ѕ��͂̋Ɩ��v�ȊO�̋Ɩ��A���Ƃ��A�L��ł��L������A���Ă���҂ɂ��ẮA���Ɩ��^�ٗʘJ�����̓K�p�ΏۂƂ��邪�A���e�̍Z���̋Ɩ��S���҂͑ΏۊO�Ƃ���̂��s�����߂ł���B�������A���e�Z���̃A���o�C�g�����̂����A�L��̘J���҂́A�L��̊�旧�Ă��A���e�̍Z�����ӑR��̂Ƃ��čs���̂��ʏ�ł���B���������s�����߂͕s���R�ł�����肩�A�s�����߂̂悤�ȋ敪�ɏ]���A������L��(�����ς���A���āA�����y�ѕ��͂̋Ɩ��ȊO�̕���)�ɂ͓K�p�ł��Ȃ����ƂɂȂ�B
�@�����ŁA���x�̗��p������ɑ��i����ׂ��A���Ƃ��A�L��A�@���A��Č^�c�ƁA�t�@�C�i���V�����v�����i�|���ɂ��Ă��A�ΏۋƖ��Ɋ܂߁A�K�p�ΏۋƖ��̊g���}��ׂ��ł���B
�@�܂��A���Ɩ��^�ٗʘJ�����́A�{���A���Ɗ����̒����Ɉʒu����J���҂��n���I�Ȕ\�͂��\���ɔ����ł���悤�ɂ��邽�߂̐��x�ł���Ƃ����邪�A���x�̗��p�����O���邠�܂�A���̓����葱�����G�ɉ߂�����̂ƂȂ��Ă���B
�@�����ŁA���x�̂���Ȃ闘�p�̊g���}�邽�߂ɂ́A�葱�̊ȑf������w�i�߂�K�v������B��̓I�ɂ́A���Ɩ��^�ٗʘJ�����ɂ��Ă��A���Ɩ��^�ٗʘJ�����Ɠ��l�A�{���͘J�g����ɂ�铱�����\�Ƃ��邱�Ƃ��]�܂����B�������A�J���_��@�������钆�ŁA�J�g�ψ���ɓ��ʂ̌��\�i�A�ƋK���̕ύX�ɂ����č������𐄒肷��@�\���j��t�^���铮��������A�������������ɂ��ڂ�z��K�v������B�Ȃ��A���ɘJ�g�ψ���̌��c��v���Ƃ���ꍇ�ɂ����Ă��A���s��5����4�ȏ�̌��c�v���͌��i�ɉ߂���̂ŁA���̊ɘa��}��ׂ��ł���B
�T�D�Ǘ��ēҁi�J����@��41���2���j�̘J�����ԓ��K�p���O�̖��_
�@�J����@��41���2���ɒ�߂邢����Ǘ��ē҂́A�J�����ԓ��̋K���̓K�p�����O����Ă���B�������A���������Ǘ��ē҂ɂ��ẮA�O�q�����悤�ɂ��͈̔͂��߂�����߂ɖ�肪����A��������Ԃɉ��������̂ɉ��߂�K�v������ق��A�[��ƂɊւ���K�����K�p���O�̑ΏۂƂ���Ă��Ȃ��Ƃ�����肪����B
�@�����A�o�ς̃O���[�o������24���ԉ�����w�̐i�W�������钆�ŁA�C�O�Ƃ̂��Ƃ���͂��߂Ƃ��āA�d�v�ȐE����ӔC��L���邱���Ǘ��ē҂��[��Ɋ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��͐������z�肳���B
�@�J����@��41���2�����Ǘ��ē҂�J�����Ԃ̋K���̓K�p���珜�O������|���A�����̎҂��J�����ԁA�x�e�y�ыx���Ɋւ���K��̋K�����Ċ������Ȃ���Ȃ�Ȃ���ƌo�c��̕K�v�ɂ���Ƃ���A���̊������Ԃ͈̔͂��[��ɂ��g�����Ă�����Ԃ����ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�܂��A�Ǘ��ē҂ɂ��Ă��A�[��J���Ɋւ���K��������сA�[��i�ߌ�10������ߑO5���܂Łj�ɓ������ꍇ�ɂ́A���������̎x�������`���t�����邱�Ƃ���A������A�Ǘ��ē҂ɂ��Ă��[��̎��ԑтɌ����Ď��ԊǗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����肪�����Ă���B
�@���̂悤�ɁA�@�������ʂɎ��ԊǗ��̋`����Ȃ��Ǘ��ē҂ɂ��āA�[��̎��ԑтɌ����Ď����㎞�ԊǗ����`���t����Ƃ����̂́A�����ɂ��s���R�ł���B����ɁA�J����@�{�s�K����54���ɒ�߂�����䒠�̋L���������݂Ă��A�Ǘ��ē҂��͂��ߘJ����@��41���e���̈�ɊY������J���҂Ɋւ��ẮA�[��J���̎��Ԑ��ɂ��Ă�������L�����邱�Ƃ�v���Ȃ��|�����L����Ă���B���̂��Ƃ́A�䂪���̖@�ߎ��̂��[��ɂ�����Ǘ��ē҂̎��ԊǗ����K�v�ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă���Ƃ������Ƃ��ł��A���̓_�ɂ����Ă����s���x�ɂ͖���������Ƃ�����B
�@���{�o�c�A�̃A���P�[�g�����ɂ����Ă��A���̊Ǘ��ē҂̘J�����ԓ��̓K�p���O���ɂ��āA�u�Ǘ��ē҂ł����Ă��[��J���Ɋւ���K��̓K�p�͔r������Ȃ��Ƃ����_�v�ɂ��ĉ��P�������߂���A�u�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������v�Ɖ�����Ƃ̂�����4�����ɂ̂ڂ��Ă���B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�Ǘ��ē҂ɂ��ẮA���}�ɐ[��J���ɂ��Ă����������K���̓K�p�����O����邱�Ƃm�ɂ���悤�A�K�v�Ȗ@�������s���ׂ��ł���B
�U�D�J�����ԋK���̌������ɂ���
�m�P�n<�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�̐V��>
�@���s�̘J�����ԋK���̎�Ȗ��_�Ɖ��P�̕���ɂ��ẮA�ȏ�ɏq�ׂ��Ƃ���ł���A����܂ŏq�ׂ��ӌ��ɉ������@���������߂��邪�A�����A�X�̐��x�̌����������邱�Ƃł́A���͂�J�g�̃j�|�Y(���l�ȓ������A���t�����l�̑n����)�ɑΉ����邱�Ƃ͍���ƂȂ��Ă���A���{�I�Ȍ��������}���ł���B
�@�����ŁA�J�����ԊǗ��ɓK���Ȃ��z���C�g�J���[�ɂ��ẮA���̗v���̂��ƂɘJ�����ԋK���̓K�p�����O����z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x��V�݂��邱�Ƃ�������B
�m�Q�n<�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�̋�̓I���e>
�@���̐V�������x�̓��e(�K�p�Ώێ҂̗v���ƌ��ʓ�)�͈ȉ��̂Ƃ���B
| �@�P | �@�K�p�Ώێ҂̗v��
| (�P) | �@���s�̐��Ɩ��^�ٗʘJ�����̑ΏۋƖ��ɏ]�������
�@���s�̐��Ɩ��^�ٗʘJ�����̑ΏۋƖ�(�V���i���̌����J���A����V�X�e���̕��͐v��)�ɏ]������J���҂ɂ��ẮA���̔N���̑��ǂɂ�����炸�A�z���C�g�J���|�G�O�[���v�V�������x��K�p����B
|
| (�Q) | �@���s�̐��Ɩ��^�ٗʘJ�����̑ΏۋƖ��ȊO�̋Ɩ��ɏ]�������
�@���s�̐��Ɩ��^�ٗʘJ�����̑ΏۋƖ��ȊO�̋Ɩ��ɏ]������J���҂ɂ��ẮA���L��(1)�y��(2)�̗v�����[������ꍇ�Ɍ���A�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x��K�p����B
| (1) | �Ɩ��v��
���̂����ꂩ�̋Ɩ��ɊY�����邱�ƁB
| �i�@�j | �@�߂Œ�߂��Ɩ��i���s�̐��Ɩ��^�ٗʘJ�����̑ΏۋƖ��������B�j |
| �i�A�j | �u�Ɩ����s�̎�i����@�A���̎��Ԕz������J���҂̍ٗʂɂ䂾�˂邱�Ɓv��J�g���薔�͘J�g�ψ���̌��c�ɂ���߂��Ɩ� |
|
| (2) | �����v��
| �i�@�j | �����̎x���`�Ԃ����������͔N��ł��邱�ƁB���������Ē������T���A�������͎��ԋ��Ŏx�����Ă���J���҂ɂ��Ă͐V���x��K�p���Ȃ��B |
| �i�A�j | ���Y�N�ɂ�����N���̊z��400���~�i���͑S�J���҂̕��ϋ��^�����j�ȏ�ł��邱�ƁB�N���z��400���~�����̘J���҂ɂ��Ă͐V���x��K�p���Ȃ��B
�@�@�߂Œ�߂�Ɩ��ɉ����ĘJ�g�őΏۋƖ����߂�ꍇ�A�N���z��700���~�i���͑S�J���҂̋��^�����̏��20�������z�j�ȏ�̎҂ɂ��ẮA�J�g����̒������͘J�g�ψ���̌��c�̂�����ɂ����Ă��lj����\�Ƃ���B
�@�܂��A�O�L�̏ꍇ�A�N���z��400���~�i���͑S�J���҂̕��ϋ��^�����j�ȏ�A700���~�i���͏��20���̋��^�����ɑ�������z�j�����ł���҂ɂ��ẮA�J�g�ψ���̌��c�݂̂ɂ��lj����\�Ƃ���B |
| ��1 | �@�����v���Ƃ��ĉۂ������̋�̓I�Ȋz�ɂ��ẮA���܂��܂Ȋp�x����̋c�_���K�v�ł���A�����_�ł͂����܂ŗᎦ�ɂƂǂ߂�B |
| ��2 | �@�����z�ɂ��ẮA���ԋ��^���ԓ��v���������w�W�Ƃ��đS�J���҂̋��^��������Ƃ��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă��邪�A���Y��Ɠ��ɂ�����e�J���҂̏���������w�W�Ƃ��āu�������������ʁZ���̎ҁv�Ƃ���悤�Ȓ����v�����l������B�Ȃ��A�������v�����������p����ꍇ�ɂ́A�K����������������Ƃ���{�Ƃ���B |
�Ɩ��v���ƒ����v�����Ƃ̊֘A
| �Ɩ��v�� |
�����v�� |
���̑� |
| ���s���Ɩ��^�ٗʘJ�����ΏۋƖ� |
�i�����v���Ȃ��j |
�@ |
��L�̋Ɩ��������ٗʓI�Ɩ��ł����Ė@�߂Œ�߂��Ɩ�
�@�������A����ȊO�̋Ɩ��ł����Ă��A���J�g����̒������͘J�g�ψ���̌��c�ɂ��ꍇ�ɂ́A�ΏۋƖ���lj����邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���B |
���Y�N�ɂ�����N���z��700���~�i���͑S�J���҂̋��^�����̏��20�������z�j�ȏ�̎� |
���̏ꍇ�A�J�g����̒����A�J�g�ψ���̌��c�̂�����ł��lj����\�B |
| ���Y�N�ɂ�����N���z��400���~�i���͑S�J���҂̕��ϋ��^�����j�ȏ�700���~�i���͑S�J���҂̋��^�����̏��20�������z�j�����̎� |
���̏ꍇ�A�J�g�ψ���̌��c�ɂ��ꍇ�Ɍ���lj����\�B |
| �@�@�� | �@���Y�N�ɂ�����N���z��400���~�i���͑S�J���҂̕��ϋ��^�����j�����̎҂ɂ��ẮA�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x��K�p�����A�ʏ�̘J�����ԊǗ����s���B |
| ���P | �@�z�͂����܂ł��Ꭶ�ł���A����ɏڍׂȌ������K�v�ł���B |
| ���Q | �@�N���ɂ́A�Ƒ��蓖���}�{�Ƒ����ɂ���ĕϓ���������A���n�蓖�⊦��n�蓖���Ζ��n�ɂ��ϓ�����������ړ������ׂĊ܂߂�B |
| �m�Q�l�n | �@�N��700���~�̊�́A�E�ƈ���@�{�s�K���Ɋ�Â��A���E�҂���萔�����ł���o�c�Ǘ��ҁA�Ȋw�Z�p�ғ��͈̔͂̊�Ƃ���Ă���z�ł���B |
|
|
|
| �@�Q | �@����
�@�J�����ԁA�x�e�A�x���y�ѐ[��ƂɌW��K���̓K�p���O�Ƃ���B |
| �@�R | �@�����J����ē����ւ̓͏o
�@�@�߂ɒ�߂�Ɩ��ȊO�Ƀz���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�̑ΏۂƂȂ�Ɩ���J�g�Œlj�����ꍇ�A���������J�g����܂��͘J�g�ψ���̌��c�������J����ē����ɓ͂��o�邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�������A�͏o�����Ȃ������ꍇ�ł���L2�́u���ʁv�ɂ͉e�����Ȃ��B�i�͏o�`���ᔽ�ɂ��ẮA�ߗ��ɂ�鐧�ق��l������B�j |
| �@�S | �@���̑�
�@�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�̓K�p�Ώێ҂ɑ��āA�A�ƋK�����ɏo�ދΎ����̒�߂����Ă��悢���A�J�����Ԃ̊Ǘ��͍s�킸�A�u�x���v�u���ށv�u�x�e���ԁv�ɂ��Ă̒����T���͍s��Ȃ��i�������A�u���v�ɂ��Ă͒������T������j�B
| �@�� | �ݎЎ��Ԃ̔c�����̌��N�ւ̔z���ʂ̑[�u�͉��L�m�R�n�ȉ��Ō�������B |
|
�m�R�n<�J���҂̌��N�ւ̔z���[�u�ɂ���>
�@�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�̓����ɂ������ẮA�J���Ҏ���̓����߂��ɂ�錒�N��Q��h�~���邽�߂̑[�u�������Ɍ�������K�v������B�����A�����ԘJ�����J���҂ɗ^������̓I�A���_�I���חv���Ɋւ��ẮA�E�����Ɩ����e�����͂��߂Ƃ��đ傫�Ȍ̍������邱�Ƃ��ے�ł��Ȃ��B���������āA�J���҂̌��N�ɂ��ẮA���ꂼ��̊�Ƃ̋Ǝ�A�Ɩ��A�E����e�̎��Ԃɉ����A�J�g�ŎY�ƈ�̊��p���@���g�݂Ȃǂ�����I�Ɏ�茈�߂�ׂ��ł���ƍl����B
�@����ɁA�e��Ƃɂ�����J���҂̌��N�ւ̔z���Ɋւ����̓I�Ȏ�g�݂Ƃ��ẮA���̂悤�ȗႪ�l������B
| �@�E | �J�g�Ńz���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�K�p�Ώێ҂̈����Ԃ̍ݎЎ��Ԃ�S�����Ԃ̏������茈�߁A���̎��Ԃ��Ȃ��悤�ɂ���B |
| �@�E | ���̊��ԓ��Ɉ�x�ȏ�A��i�܂��͎Y�ƈ�A�Y�ƕی��X�^�b�t�ɂ��q�A�����O�i�ʐځj�����{���A�J���҂̌��N��Ԃ�c������B |
| �@�E | �������߂�ꂽ�����ɑΏێ҂ɑ̒�����^�������Ɋւ���u��f�\�v��z�z���A�L������̏�A�Y�ƈ��ی��w�������̏������B |
| �@�E | ���Ə���Ɍ��N���k��������݂���B |
| �@�E | ������N�f�f���̖@�߂ɋ`���t�����Ă��錒�N�f�f�Ƃ͕ʂɁA���ʌ��N�f�f�����{����B |
| �@�E | �����Ԃɂ����Ĉ��̍ݎЎ��Ԃ�S�����Ԃ����҂ɑ��ď���̋x�ɂ�^����B |
| �@�E | �J�g�ŔN���L���x�ɂ̖ڕW�擾���Ȃǂ���茈�߁A���̎擾�𑣐i����B |
�m�S�n<�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�����̖@�����ɂ���>
�@�ȏ�̂悤�ȃz���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�̖@�������ǂ̂悤�ɍs���ׂ��ł��낤���B
�@���̓_�ɂ��ẮA�J����@�̑�41���i�J�����ԓ��Ɋւ���K��̓K�p���O�j�̑�4���ɁA�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�Ɋւ���K���V�݂��ׂ��ł���ƍl����B
�@���̍ہA���̑�4���̋K��Ɂu���Y�J���҂ɂ��ẮA�[��ƂɊւ���K��̓K�p�����O����v���ƂL����B�Ȃ��A�O�q�̂悤�ɁA��2���̊Ǘ��ē҂ɂ��Ă��A�[��ƂɊւ���K��̓K�p�����O���ׂ��ł���B
�@�Ƃ���ŁA�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�Ƒ�41��2���ɒ�߂�Ǘ��ē҂̓K�p���O�Ƃ̍ł��傫�ȍ��ق́A�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�ɂ����ẮA�@�߂Œ�߂�ق��ɁA�J�g�őΏۂƂȂ�Ɩ������߂邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł���B���̏ꍇ�A�J���҂̒n�ʁA�����A�ӔC�A�����l�����Ƃ͖��W�ɁA�J�����ԋK���̓K�p���O���F�߂���_�ɂ���B
�@���̂悤�ɁA�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�́A�����Ƃ��Ċe��Ƃ̘J�g�œK�p�Ɩ���E������茈�߁A�J�����ԋK���ɂƂ���Ȃ��ٗʓI�ȓ��������������悤�Ƃ�����̂ł���B
������
�@�ȏ�A�z���C�g�J���[�̘J�����ԂɊւ��ďq�ׂĂ������A���s�̘J�����Ԗ@����S�ʓI�ɔے肷����̂ł͂Ȃ��B�܂��A�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�́A���R�̂��ƂȂ��玞�ԊO�J���ɑ�������̎x������Ƃꂽ��A�J�����Ԃ������I�ɒ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��B
�@�J���҂̈ӗ~�����߁A�����I�ɓ������Ƃɂ���Ďd���Ɛ����̒��a���������Ă������߂ɂ́A����܂ł̘J�����ԋK���̘g�����A�V���Ȕ��z�ɂ��ƂÂ��J�����Ԑ��x�̍\�z���}���ł���B�����A�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�́A�ǂ̂悤�ȘJ���҂ɓK�p���Ă��悢�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�J���̎�������A�n���I�������I�ȓ�����������z���C�g�J���[�ň��̗v�������J���҂Ɍ�����B
�@��q�����u�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�v���������邱�Ƃ������A�J���҂̎d����J�����Ԃɑ���ٗʐ��������������߁A���l�ȓ������⌋�ʓI�Ƃ��ĘJ�����Ԃ̒Z�k�ɂ��傢�Ɏ�����ƍl����B
�@���{�́A���̂悤�ȃz���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x���܂ޘJ�����ԋK���̂�����ɂ��āu�K�����v�E���ԊJ�����i3���N�v��i����j�v�ɑ������`�Ō�������i�߂��邪�A�Љ��o�ς̓����������x�I�ɑ��܂��Ă��鍡�A���̌��������ɉ�邱�Ƃ��Ȃ��悤�A�v���������ȑΉ����������߂����B
�@�������̑��l����Y���̌����}�邽�߂ɂ��A���̓����͕K�v�s���Ȃ��̂ł���A�o�ϊE�Ƃ��Đ��{�E�W�Ȓ��ɑ��A���̑���������ϋɓI�ɓ��������Ă��������B
�ȏ�
�Q�l����
|
�J�����Ԗ��Ɋւ���A���P�[�g�����̏W�v���ʂɂ���
| �A���P�[�g�z�t���@�F�@2004�N10��29�� | �@�@ ���ԁ@�F�@10��29���`11��30�� |
| �A���P�[�g�z�t�����@�F�@�P�C�S�V�X�� | �@�@�����@�F 348 �Ё@�i���@23.5%�j |
| �@I | �@�J�����ԂɊւ���@�K���ɂ��āi��P�`��Q�j |
| �@II | �@�e�J�����Ԑ��x�ɂ��āi��R�`��X�j |
| �@III | �@�J���҂̌��N�m�ۑ[�u���ɂ��āi��P�O�j |
|
| ��P�D | �d���̐��ʂ�P���ɘJ�����Ԃ̒����ő���Ȃ��A������z���C�g�J���[�ɂ��čl�����ꍇ�A���s�̘J�����ԂɊւ���@�K���ɂ��āA�ǂ�����ׂ��ƍl���邩 |
| �@ |
�� |
�� |
|
15 |
4.3% |
| (2) | �@����s�s���͂�����̂̌��s�̂܂܂ł悢 |
|
78 |
22.4% |
| (3) | �@���s�����ɘa���ׂ��ł��� |
|
229 |
65.8% |
|
1 |
0.3% |
| (5) | �@���Ƃ������Ȃ��E�킩��Ȃ� |
|
20 |
5.7% |
|
3 |
0.9% |
|
2 |
0.6% |
| ��Q�D | �z���C�g�J���[�̘J�����ԂɊւ���@���ɂ��K���ɂ��ẮA�ǂ̂悤�Ȋɘa���ł��K�v�ƍl���邩
����P��(3)�Ɖ�����Ƃ̂݉� |
| �@ |
�� |
�� |
| (1) | �@�ٗʘJ�������݂Ȃ��J�����Ԑ��̓K�p�͈͂̊g��A�v���̊ɘa�A�葱�̊ȑf�� |
|
64 |
27.9% |
| (2) | �@�ٗʘJ�����̘J�����ԎZ����݂Ȃ��J�����Ԑ�����K�p���O���ɕύX���� |
|
49 |
21.4% |
| (3) | �@�Ǘ��ē҂̑Ώێ҂͈̔͋y�ѐ[��Ƃ̓K�p���O�ȂǓ��e�̊g�� |
|
28 |
12.2% |
| (4) | �@�A�����J�̃z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�������x�ɋ߂����x�̓�����}�� |
|
76 |
33.2% |
|
4 |
1.7% |
|
8 |
3.5% |
�mII�@�e�J�����Ԑ��x�ɂ��ān
| ��R�D | ���Ɩ��^�ٗʘJ�����̓����ɂ��� |
| �@ |
�� |
�� |
|
63 |
18.1% |
| (2) | �@�������Ă��Ȃ����A�����ɂ��Č������Ă��� |
|
97 |
27.9% |
| (3) | �@�������Ă��Ȃ����A�������邱�Ƃ��l���Ă��Ȃ� |
|
143 |
41.1% |
| (4) | �@���Ƃ������Ȃ��E�킩��Ȃ� |
|
41 |
11.8% |
|
4 |
1.1% |
�m(3)�ɂ��āA�ǂ̂悤�ȗ��R���炩�n
| ��S�D | ���s�̐��Ɩ��^�ٗʘJ�����ɂ����āA�s�s���ȓ_�₳��Ɋ��p���₷���Ȃ�悤�v�����̊ɘa����P��v����Ɗ����镔���͂��邩�A����Ƃ���ǂ�ȂƂ��납����R��(1)�A(2)�Ɖ�����Ƃ̂݉� |
| �@ |
�� |
�� |
| (1) | �@�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_�͂Ȃ� |
|
19 |
11.9% |
| (2) | �@�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������ |
|
139 |
86.9% |
|
2 |
1.3% |
�m(2)�ɂ��āA�ɘa�E���P���ׂ��Ƃ���͂ǂ�ȓ_��]�i�����j
�i���̓I�v���j
| �� | �@�����J���ȗ߂ɒ�߂�ΏۋƖ��͈̔� |
|
98 |
�i�葱�I�v���j
|
49 |
| �� | �@�J�g����ɂ���߂������̘J����ē����ւ̓͏o |
|
40 |
| �� | �@�Ɩ��̐��s�̎�i�y�ю��Ԕz���̌��蓙�Ɋւ��J���҂ɋ�̓I�Ȏw�������Ȃ����ƂƂ���v�� |
|
44 |
�i���ʁj
| �� | �@�݂Ȃ��J�����Ԃł���J�����ԋK��̓K�p���O�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��������ʂ̕��� |
|
75 |
�i���̑��j
| �� | �@���N�E�����m�ۑ[�u�Ɋ�Â��ΏۘJ���҂̋Ζ��c���`���̕��� |
|
30 |
|
4 |
| ��T�D | ���Ɩ��^�ٗʘJ�����̓����ɂ��� |
| �@ |
�� |
�� |
|
25 |
7.2% |
| (2) | �@�������Ă��Ȃ����A�����ɂ��Č������Ă��� |
|
121 |
34.8% |
| (3) | �@�������Ă��Ȃ����A�������邱�Ƃ��l���Ă��Ȃ� |
|
143 |
41.1% |
| (4) | �@���Ƃ������Ȃ��E�킩��Ȃ� |
|
55 |
15.8% |
|
4 |
1.1% |
�m(3)�ɂ��āA�ǂ̂悤�ȗ��R���炩�n
| ��U�D | ���s�̊��Ɩ��^�ٗʘJ�����ɂ����āA�s�s���ȓ_�₳��Ɋ��p���₷���Ȃ�悤�v�����̊ɘa����P��v����Ɗ����镔���͂��邩�A����Ƃ���ǂ�ȂƂ��납����T��(1)�A(2)�Ɖ�����Ƃ̂݉� |
| �@ |
�� |
�� |
| (1) | �@�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_�͂Ȃ� |
|
8 |
5.5% |
| (2) | �@�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������ |
|
138 |
94.5% |
|
0 |
0.0% |
�m(2)�ɂ��āA�ɘa�E���P���ׂ��Ƃ���͂ǂ�ȓ_��]�i�����j
�i���̓I�v���j
| �� | �@�ΏۋƖ��͈̔͂ɂ��āA�Ɩ����������鎖�Ə�̎��Ƃ̉^�c�Ɋւ�����̂ł��邱�ƁA���A���āA�����y�ѕ��͂̋Ɩ��ł��邱�Ɠ��̗v�����ۂ��Ă��邱�� |
|
101 |
| �� | �@�ΏۋƖ���K�ɐ��s���邽�߂̒m���E�o������L����҂Ƃ���ΏۘJ���҂͈̔� |
|
49 |
�i�葱�I�v���j
|
52 |
| �� | �@�ψ���4�^5�ȏ�̑������ɂ����̂Ƃ���J�g�ψ���ɂ����錈�c�v�� |
|
67 |
| �� | �@�J�g�ψ���c�̘J����ē��ւ̓͏o�v�� |
|
57 |
|
51 |
�i���ʁj
| �� | �@�݂Ȃ��J�����Ԃł���J�����ԋK��̓K�p���O�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��������ʂ̕��� |
|
69 |
�i���̑��j
| �� | �@�ΏۂƂȂ�J���҂̘J�����ԏƌ��N�y�ѕ����̊m�ۑ[�u���{�Ɋւ���6�����ȓ���1��̘J����ē��ւ̒���� |
|
66 |
|
1 |
| ��V�D | �@���Ə�O�J���݂̂Ȃ��J�����Ԑ��̓����ɂ��� |
| �@ |
�� |
�� |
|
120 |
34.5% |
| (2) | �@�������Ă��Ȃ����A�����ɂ��Č������Ă��� |
|
54 |
15.5% |
| (3) | �@�������Ă��Ȃ����A�������邱�Ƃ��l���Ă��Ȃ� |
|
136 |
39.1% |
| (4) | �@���Ƃ������Ȃ��E�킩��Ȃ� |
|
31 |
8.9% |
|
7 |
2.0% |
�m(3)�ɂ��āA�ǂ̂悤�ȗ��R���炩�n
| ��W�D | ���s�̎��Ə�O�J���݂̂Ȃ��J�����Ԑ��ɂ����āA�s�s���ȓ_�₳��Ɋ��p���₷���Ȃ�悤�v�����̊ɘa����P��v����Ɗ����镔���͂��邩�A����Ƃ���ǂ�ȂƂ��납����V��(1)�A(2)�Ɖ�����Ƃ̂݉� |
| �@ |
�� |
�� |
| (1) | �@�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_�͂Ȃ� |
|
40 |
23.0% |
| (2) | �@�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������ |
|
130 |
74.7% |
|
4 |
2.3% |
�m(2)�ɂ��āA�ɘa�E���P���ׂ��Ƃ���͂ǂ�ȓ_��]�i�����j
�i���̓I�v���j
| �� | �@���Ə�ɂ����āA�K���A�A�Ў����������̋Ɩ��̋�̓I�w�������̂��A���Ə�O�Ŏw���ǂ���ɋƖ��ɏ]�����A���̌㎖�Ə�ɂ��ǂ�ꍇ�ȂǁA�݂Ȃ��J�����Ԑ��̓K�p�͂Ȃ��Ƃ��ĒʒB�ɒ�߂��Ă��鎖�Ə�O�J���͈̔� |
|
106 |
�i�葱�I�v���j
| �� | �@����Œ�߂鎞�Ԃ��@��J�����Ԃ���ꍇ�̘J�g����̘J��������ւ̓͏o�`���v�� |
|
36 |
�i���ʁj
| �� | �@�J�����Ԃ݂̂Ȃ��Ɋւ���K�肪�K�p�����ꍇ�ł����Ă��A�x�e�Ɋւ���K�p�͔r������Ȃ��Ƃ��������� |
|
33 |
| �� | �@�J�����Ԃ݂̂Ȃ��Ɋւ���K�肪�K�p�����ꍇ�ł����Ă��A�[��ƂɊւ���K�p�͔r������Ȃ��Ƃ��������� |
|
43 |
| �� | �@�J�����Ԃ݂̂Ȃ��Ɋւ���K�肪�K�p�����ꍇ�ł����Ă��A�x���Ɋւ���K�p�͔r������Ȃ��Ƃ��������� |
|
40 |
�i���̑��j
| ��X�D | ���݂̘J����@��41��2���̊Ǘ��ē҂̘J�����ԓ��̓K�p���O���ɂ��āA�s�s���ȓ_����P�̕K�v������ƍl���镔�������邩�A����Ƃ���ǂ�ȂƂ��납 |
| �@ |
�� |
�� |
| (1) | �@�s�s���ȓ_����P���ׂ��_�͂Ȃ� |
|
67 |
19.3% |
| (2) | �@�s�s���ȓ_��ɘa�A���P���ׂ��_������ |
|
274 |
78.7% |
|
7 |
2.0% |
�m(2)�ɂ��āA�ɘa�E���P���ׂ��Ƃ���͂ǂ�ȓ_��]�i�����j
�i���̓I�v���j
| �� | �@�Ώێ҂͈̔͂ɂ��āA�@���ɋ�̓I���f���������Ă��Ȃ��ɂ��ւ�炸�A����E�ʒB�Łu�o�c�҂ƈ�̓I�ȗ���ɂ���҂̈Ӗ��v�ł���ȂǂƂ��Ă��͈̔͂��w������Ă��邪�A����̊�Ƃ̎��Ԃɑ����Ă���Ƃ����Ȃ��_ |
|
236 |
�i���̑��j
| �� | �@�Ǘ��ē҂ł����Ă��A�[��J���Ɋւ���K��̓K�p�͔r������Ȃ��Ƃ��������� |
|
123 |
| �� | �@�Ǘ��ē҂ł����Ă��A�N���L���x�ɂɊւ���K��̓K�p�͔r������Ȃ��Ƃ��������� |
|
12 |
| �� | �@�[��Ƃ�ߏd�J���h�~�̊ϓ_����A�����I�ɘJ�����ԊǗ��̑ΏۂƂ���Ă���Ƃ��������� |
|
90 |
|
5 |
�mIII�@�J���҂̌��N�m�ۑ[�u���n
| ��P�O�D | �J�����Ԃ̋K���E�Ǘ��Ɋւ��ẮA����Ŏg�p�҂̈��S�z���`����J���҂̌��N�m�ۑ[�u�Ƃ̊֘A�����ɂȂ�ƍl�����邪�A����ɂ��Ăǂ̂悤�ɍl���邩 |
| �@ |
�� |
�� |
| (1) | �@����ȏ�ɋ������邱�Ƃ���ނȂ� |
|
25 |
7.2% |
| (2) | �@������x�̎g�p�҂̋`���͊Îׂ� |
|
125 |
35.9% |
| (3) | �@��Ƃ̎��Ԃɉ����A�J�g�ł̎�g�݂��������ׂ� |
|
187 |
53.7% |
|
7 |
2.0% |
|
4 |
1.1% |