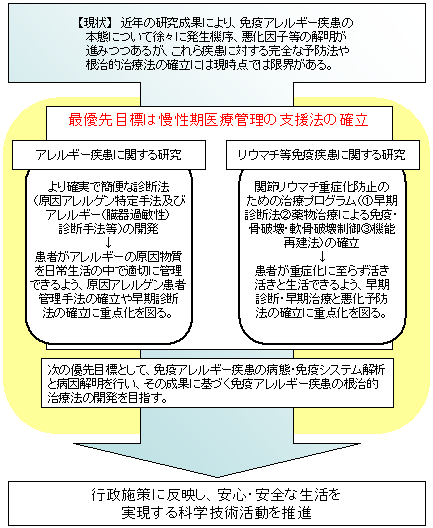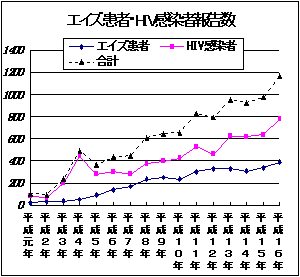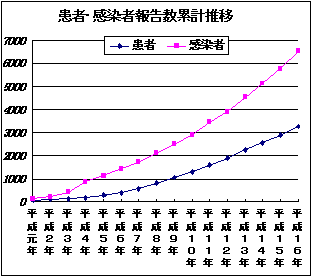| 研究事業:(研究事業中の分野名):エイズ対策研究事業 |
| 所管課:健康局疾病対策課 |
| 予算額(平成17年度):1,914,726千円 |
我が国の新規エイズ患者・HIV感染者報告数は年々増加しており、特に国内における日本人男性の同性間性的接触による感染、及び性行動の開放化等による若年者層への感染拡大が懸念されている。
| |
また、HIV訴訟の和解を踏まえ、恒久対策の一環としてエイズ治療・研究をより一層推進させることが求められている。 |
本事業は、エイズに関する基礎、臨床、社会医学、疫学等の研究を推進するとともに、必要なエイズ対策を行うための研究成果を得ることを目的としている。 |
(別途添付)
課題採択に当たっては、「HIV薬剤耐性対策プロジェクト(平成15年9月)」を踏まえて、副作用軽減のための研究、服薬を容易にするための研究、飲み忘れ防止のためのプログラムや機器の開発及びNGO等が医療機関と連携するモデル開発研究やエイズ動向調査体制の確立、検査ガイドラインに関する検討研究を優先した。
その他、既存の抗HIV薬の作用機序である逆転写酵素阻害剤、プロテアーゼ阻害剤以外の宿主因子等の要因を考慮した作用機序を持つ療法を長期目標とする研究や先進諸国の発生動向、調査体制、感染経路別の対策とその評価と我が国のエイズ 対策に対する提言を含む研究を優先した。 |
(社会的な意義や施策・ガイドライン等への反映状況を含む)
| 1. |
多剤併用療法の長期服薬に関するリスクの検討 |
| 2. |
ワクチン、治療新薬の開発 |
| 3. |
エイズ脳症の病態解明 |
| 4. |
HIV治療ガイドライン、日和見感染症診療マニュアルの作成 |
| 5. |
抗HIV薬の血中・細胞内濃度測定及び薬剤耐性検査等によるモニタリングシステムと簡便な手技の開発 |
| 6. |
HIV・HCV重複感染時のガイドラインの改訂 |
| 7. |
HIV感染男性、非感染女性夫婦間の生殖補助医療 |
| 8. |
血友病の遺伝子治療に関する基礎的検討 |
| 9. |
HIV抗体迅速検査を含む利便性の高いHIV検査体制の確立、 |
| 10. |
非政府組織(NGO)の活用による効果的な普及啓発への提言 |
| 11. |
男性同性間性的接触における効果的なエイズ予防対策 |
| 12. |
若者への効果的なHIV予防介入マニュアルの作成 |
| 13. |
HIV医療体制の現状把握と今後の在り方に関する提言 |
| 14. |
エイズ動向調査の情報等を用いたHIV感染者・エイズ患者の有病数・発生数の推計 |
| 15. |
アジア太平洋地域における国際人口移動から見た危機管理としてのHIV感染症対策の分析 |
| 16. |
HIV歯科診療マニュアルの作成 |
| 17. |
拠点病院診療案内の作成 |
|
| (4) |
行政施策との関連性・事業の目的に対する達成度 |
1997年に導入された多剤併用療法により死亡率が低下したとされる一方で、抗HIV薬の長期投与に伴う副作用や薬剤耐性ウイルスの出現が問題となっている。また、HIV感染者・エイズ患者報告数の増加が続いている(図参照)ことから、医療と予防の両者において研究の推進が必要である。なお、HIV検査体制の充実により、HIV感染者報告数は見かけ上、増加する可能性がある。
|
我が国の新規エイズ患者・HIV感染者報告数は年々増加しており、特に国内における日本人男性の同性間及び異性間性的接触による感染の拡大は危機的な状況にある。特に同性間性的接触におけるHIV感染拡大及び、性の低年齢化・開放化伴い若年者層におけるHIV感染拡大が懸念されており、持続的・効果的な予防対策を実施するための緊急提言が求められている。
また、エイズ医療については、最新の診断・治療法、医療体制の整備等の多方面において、患者の医療環境の向上に寄与している。ただし、多剤併用療法(HAART)が長期化するに従い、薬剤耐性ウイルスの問題が出てきており、アドヒランスの確保や日和見感染症対策の研究も今後、見直していく必要がある。
このように、HIV訴訟の和解に基づき、原告団からの要望を反映した研究を引き続き実施しており、患者の医療環境、肝炎対策及びQOL・精神衛生の向上に寄与している。また、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業においてもエイズ対策研究と有機的に連携し、効果的に研究を推進していく必要がある。 |
|
HIV感染症は効果的な予防ワクチンも完治する治療法も開発されていない現在、HAARTの導入により、慢性感染症の性格を帯びてきている。また、新規HIV感染するもののうち、そのほとんどが性的接触に由来するものであるため、性感染症対策に関する研究も必要となる。このような状況に対応するため、本研究事業は、効果的な予防対策と疾患概念を変える治療法及びエイズ医療の体制確立について着実な結果を示しており、行政施策の推進に大きく貢献しているところである。 |
| 研究事業(研究事業中の分野名):肝炎等克服緊急対策研究 |
| 所管課:健康局結核感染症課 |
| 予算額(平成17年度):792,541千円 |
| ・ |
肝炎ウイルスの病態及び感染機構の解明並びに肝炎、肝硬変、肝がん等の予防及び治療法の開発等を目的とする。 |
|
| ・ |
肝炎ウイルス等について、その病態や感染機構の解明を進めるとともに、肝炎、肝硬変、肝がん等の予防、診断及び治療法等に資する研究 |
| ・ |
C型肝炎の治療とキャリアからの発症予防に関する基盤研究の課題採択にあたっては、(1)プロテオミクス解析を基盤としたC型肝炎治療薬標的分子の網羅的検索と創薬に関する研究、(2)動物モデルの開発と創薬への応用に関する研究、(3)慢性C型肝炎に対する治療用抗体の開発に係る研究を優先する。 |
|
(社会的な意義や施策・ガイドライン等への反映状況を含む)
必要に応じて代表的な研究成果の説明図などを添付してください。
| ・ |
肝炎の治療効果予測のアルゴリズムを作成し、インターフェロンの投与量や種類などが治療効果に関与し、それぞれの属性を満たす集団の治癒率を算出した。 |
| ・ |
肝疾患の重症度、進行度によるQOL、効用値を測定し、慢性肝疾患の医療費を推計した。 |
| ・ |
進行性肝細胞がんに対するインターフェロン化学療法のランダマイズド・コントロール・トライアルを開始するとともに、症例登録を行った。 |
| ・ |
肝炎ウイルスに感染した労働者の健康管理に関する提言を行い、肝炎にかかった労働者に対する留意事項づくりに寄与した。 |
| ・ |
輸血後肝炎の追跡調査を実施した。 |
| ・ |
透析によるC型肝炎の集団感染に関する具体的な対策を緊急勧告として提示した。 |
| ・ |
C型肝炎陽性妊婦からの出生児を追跡調査し、母子感染率を算定するとともに、HCVキャリア妊婦とその出生児の管理指導指針を策定した。 |
| ・ |
我が国のB型肝炎、C型肝炎キャリアの年齢別偏在の状況を明らかにした。 |
| ・ |
B型肝炎の治療ガイドラインを確立した。 |
| ・ |
我が国のヒト、ブタ、イノシシ、シカにおけるE型肝炎ウイルスの感染実態を把握した。
|
|
| (4) |
行政施策との関連性・事業の目的に対する達成度 |
| ・ |
C型慢性肝炎における持続型インターフェロン・リバビリンの併用など、最も効果的でかつ経済的な治療法を確立し、情報提供を行うことによって、地域間、病院間の治療レベルの均てん化に貢献した。 |
| ・ |
進行性肝細胞がんに対するインターフェロン併用化学療法の治療効果を確認し、集学的治療による肝がんの治療法を確立した。
|
|
| ・ |
C型肝炎ウイルス感染による長期の経過、予後の解明、透析施設、歯科診療、母子保健による感染など疫学的に解明すべき点が多い。 |
| ・ |
抗ウイルス剤、ペグインターフェロンなど新しい薬剤の実用化(保険診療として認可)を踏まえ、標準的な治療ガイドラインを普及していくことが求められる。 |
| ・ |
肝癌に至った症例に対する肝移植も含めた治療法の進歩も待たれる。 |
| ・ |
E型肝炎については、検査技術の向上等により、多くの研究成果が期待できることから、感染防止対策へも反映させていくことが求められる。 |
|
| ・ |
国民の健康の安心・安全の実現のための重要な研究であり、積極的に実施する必要がある。 |
|
| 研究事業:(研究事業中の分野名):新興・再興感染症研究 |
| 所管課:健康局結核感染症課 |
| 予算額(平成17年度):1,917,175千円 |
| ・ |
近年、新たに発見された感染症や既に制圧したかにみえながら再び猛威をふるいつつある感染症が世界的に注目されている。 |
| ・ |
これらの新興・再興感染症は、その病原体、感染源、感染経路、感染力、発症機序について解明すべき点が多く、また迅速な診断法、治療法等の開発に取り組む必要がある。 |
| ・ |
このため、本事業は、国内外の新興・再興感染症研究を推進し、研究の向上に資するとともに、新興・再興感染症から国民の健康を守るために必要な施策を行うための研究成果を得ることを目的とする。 |
|
| ・ |
ウイルス、細菌、寄生虫・原虫による感染症等に関する研究で新型インフルエンザ、ウエストナイル熱、アジアで流行している感染症等の国内でのまん延防止のための研究でそれらの解明、予防法、診断法、治療法、情報の収集と分析、行政対応等に関する研究を行う。 |
| ・ |
新型インフルエンザ到来に備えての診断、予防対策への基盤的研究の課題採択にあたっては、(1)東南アジア諸国との共同研究により、アジアで分離されるウイルス株の分子遺伝学的解析及びデータベース化研究、(2)LAMP法等の迅速診断技術に関する研究、(3)ワクチン開発、パイロットスタディに係る研究を優先する。 |
| ・ |
ウエストナイルウイルスの侵入に備えての診断、予防対策への基盤的研究の課題採択にあたっては、(1)世界で流行しているウエストナイルウイルスの分子疫学的解析とデータベース化、(2)迅速診断法の確立とその普及、(3)ワクチン開発、パイロットスタディに係る研究を優先する。 |
| ・ |
アジアで流行している感染症の我が国への侵入監視の強化に関する研究の課題採択にあたっては、アジアで流行している細菌及び原虫に起因する感染症に焦点を当て、アジア諸国との共同研究体制(分子疫学的解析、データベース化)を構築し、赤痢菌、腸チフス菌、マラリア、赤痢アメーバ等の監視体制強化のための研究を優先する。 |
| ・ |
海外で発生した新興感染症に関する分析疫学的手法を用いた臨床研究の課題採択にあたっては、臨床の記述疫学的手法を用いた院内感染の発生機序や、抗ウイルス薬の開発研究を優先する。 |
| ・ |
感染症の原因となる細菌、ウイルスに対するバイオセーフティ及びバイオセキュリティに関する研究の課題採択にあたっては、SARSの実験室内感染の問題が起こってきていることから、効果的で、安全なバイオセーフティ及びバイオセキュリティ対策に関する研究を優先する。 |
| ・ |
インフルエンザをはじめとした、各種の予防接種の政策評価に関する分析疫学研究の課題採択にあたっては、予防接種の対象となっている疾患に対する現行の予防接種の有効性について、分析疫学的手法を用いて検討し、予防接種政策の評価を行う研究を優先する。 |
| ・ |
海外渡航者に対する予防接種の在り方に関する研究の課題採択にあたっては、海外における在留邦人の感染症の罹患の実態調査を行うとともに、日本における罹患数、保菌者数などを調査するとともに、流行時に必要なワクチンの供給について提言し、欧米各地にあるトラベラーズクリニックなど予防接種が可能な場所の普及を目指した研究を優先する。 |
(採択課題については別添参照) |
(社会的な意義や施策・ガイドライン等への反映状況を含む)
必要に応じて代表的な研究成果の説明図などを添付してください。
| ・ |
SARSコロナウイルスの迅速診断法として、LAMP法を開発した。 |
| ・ |
鳥インフルエンザワクチンの緊急開発、試験製造及び非臨床試験を実施した。 |
| ・ |
感染症法の見直しのための基礎資料を作製した。 |
| ・ |
性感染症の全数調査データと発生動向調査データを比較し、罹患率の推定方法を開発した。BCGより1万倍強力な結核予防ワクチンの開発に成功した。 |
| ・ |
性感染症特定指針、エイズ特定指針の見直しのため、全国自治体の意向調査を行った。 |
| ・ |
犬のエキノコックス症対策ガイドラインを作製した。 |
| ・ |
輸入ハムスター等の病原体汚染状況を把握した。 |
| ・ |
全国の病院について、バンコマイシン分離施設の実態調査を行い、院内感染の実態を把握した。 |
| ・ |
リアルタイムRT−PCRによるノロウイルス定量法を確立した。 |
| ・ |
ツベルクリン反応に代わる新しい結核感染特異的診断法の開発に成功した。 |
| ・ |
結核予防法に基づく都道府県の予防計画の策定に向けて、提言を行った。 |
| ・ |
生物テロに使用される可能性の高い、天然痘、ペスト菌、炭疽菌、野兎病菌等の核酸迅速診断法を作製した。 |
| ・ |
生物テロ関連疾患の臨床、検査、治療についてマニュアルを作製し、公表した。 |
| ・ |
生物テロに使用されることが懸念されている天然痘について、対応マニュアルを作製するとともに、天然痘予防接種シミュレーションを実施した。 |
| ・ |
不明物質散布によるテロ行為対応の机上演習ビデオを作製した。 |
| ・ |
インフルエンザワクチンの有効性に関する文献について、研究デザイン、疾病定義などの視点から評価した。 |
|
| (4) |
行政施策との関連性・事業の目的に対する達成度 |
| ・ |
H5N1型高病原性鳥インフルエンザに対するアジュバント添加ワクチンの試験製造、前臨床試験を実施し、新型インフルエンザ発生時のワクチンの大量生産と供給を可能にする基盤づくりを行った。 |
| ・ |
生物テロ関連疾患の臨床・検査マニュアルを作成、ホームページに公開することにより、臨床医に適切かつ最新の情報を提供した。 |
|
| ・ |
鳥インフルエンザやウエストナイル熱など、アメリカ、ロシア、韓国からの渡り鳥等の野生動物が伝播する動物由来感染症について、農林水産省、環境省、文部科学省等の関係機関が連携したネットワーク研究が必要である。 |
| ・ |
生物テロ対策として、原因となる病原体検出法の開発・普及と、バイオセキュリティに関する研究、さらには、病原性微生物の保管法、輸送法、安全性の強化法、予防・治療法について、警察庁、防衛庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省党の関係機関が連携した研究が必要である。 |
| ・ |
感染症研究分野でのアジア地域の研究機関のネットワークを構築し、アジア地域に蔓延する感染症対策の一助として、鳥インフルエンザ、ウエストナイル熱、マラリア等の予防、診断、治療に関する研究が必要である。 |
| ・ |
コンピュータシミュレーション技術等を用い、感染症発生動向を分析することにより、感染症リスクモデリング研究を推進する必要がある。 |
| ・ |
性感染症対策のため、迅速診断法の開発を行うとともに、予防のためのスキルの向上に関する研究を実施する。 |
|
| ・ |
重症急性呼吸器症候群(SARS)や鳥インフルエンザのような新興・再興感染症による危険も増大しており、国民の関心も深い。 |
| ・ |
国民の健康の安心・安全の実現のための重要な研究であり、積極的に実施する必要がある。 |
|
| 研究事業:免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業 |
| 所管課:健康局疾病対策課 |
| 予算額(平成17年度):1,112,000千円 |
花粉症、食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、リウマチ等の免疫アレルギー疾患を有する患者は国民の30%以上に上り、ますます増加傾向にあるといわれている。また、一般的に免疫アレルギー疾患の病態は十分に解明されたとは言えず、根治的な治療法が確立されていないため、長期的に生活の質(Quality of Life: QOL)の低下を招き、一部のアレルギー疾患については不適切な治療等の結果により致死的な予後をもたらす等、疾患毎に様々な問題を抱えている。
本研究事業においては、国民病である免疫アレルギー疾患に関して患者QOL等の実態を把握するとともに、予防・診断・治療に関する新規技術等の開発を進め、その成果を臨床現場に還元し、患者のQOLの向上を図ることを目的とする。 |
平成16年度の分野別配分額は、以下の通り。
| アレルギー疾患に関する研究 |
21課題 |
461,800千円 |
|
| リウマチ等免疫疾患に関する研究 |
14課題 |
487,060千円 |
|
| その他横断的な研究 |
1課題 |
29,630千円 |
(交付決定額) |
課題採択については、事前評価委員会において行政的・専門的に必要性の極めて高い研究課題を厳選している。具体的には、
| ・ |
環境要因、ゲノム情報を取り入れた予防法の確立 |
| ・ |
個人の病態を考慮したテーラーメード医療の確立等、免疫システムを考慮した治療法の確立 |
| ・ |
疫学情報、予防法、治療法等の正しい情報の還元
|
といったテーマを中心に、明確な目標を設定し、効率的な研究を推進することとしている。 |
(社会的な意義や施策・ガイドライン等への反映状況を含む)
(代表的な研究成果の説明図は別添)
最近の主な成果
(アレルギー疾患に関する研究)
| ・ |
花粉症QOL調査を実施し、初期治療を花粉飛散後4週目までに行うと有意にQOLを改善させることがわかった。また、新しい治療法として舌下減感作療法の臨床試験を国内で初めての試みとして行い、その有効性を確認しつつあり、今後対象者の拡大や段階的投与量の決定等検討する必要がある。これら研究成果をもとに一般国民向けパンフレットを作成・普及し、花粉症に関する正しい情報の普及を図った。 |
| ・ |
小児花粉症患者の増加が指摘されており、患者のおよそ20年間における長期経過の検討が実施され、2年以上の減感作療法の実施により有意に症状の改善が見られることが報告された。 |
| ・ |
わが国において未だアトピー性皮膚炎に対する治療に混乱があり民間療法が氾濫しているにもかかわらず、わが国におけるアトピー性皮膚炎の治療のEBM集は今までなく、また世界的にみても最新の治療の解説が含まれているものはなかった。本研究において、アトピー性皮膚炎に対する各種治療法(健康食品等民間療法から免疫抑制薬内服の最新の治療法まで)をエビデンスによって整理し、その結果をインターネット上において医療従事者・一般国民向けに公開したことは社会的意義も大きい。 |
(リウマチ等免疫疾患に関する研究)
| ・ |
関節リウマチ患者の臨床疫学研究を実施し、一般高齢者に比べて有意に高頻度、高度に骨粗鬆症と骨折を合併する実態を解明し、その評価法を確立した。 |
| ・ |
全身性自己免疫疾患に関して、研究成果を活かしてエビデンスを重視した診療ガイドラインを作成し、全国主要施設に配布した。 |
| ・ |
社会的に注目されている線維筋痛症(リウマチ性疾患の一つ)に関して疫学調査が実施され、欧米と同様に大都市で有病率が高く、また診断まで平均5年かかっている現状を示した。 |
| ・ |
膠原病等免疫疾患の生命予後は重篤な臓器病変や治療による合併症に左右されることから、膠原病に合併する肺病変・腎病変・精神神経病変・血液病変・感染症・骨粗鬆症の実態を分析し、EBMに基づく治療法及び予防法について診療ガイドラインを作成した。 |
(その他横断的な研究)
| ・ |
免疫アレルギー疾患予防・治療研究に係る企画に関する研究として、花粉症関連医療関係者への相談窓口を開設し、FAQを研究班ホームページに掲載した。 |
|
| (4) |
行政施策との関連性・事業の目的に対する達成度 |
免疫アレルギー疾患の研究成果に関する情報提供媒体の効果的な連携等
平成16年12月、厚生労働省ホームページに「リウマチ・アレルギー情報」サイトを開設し、研究班ホームページや関係学会ホームページのリンクを掲載するとともに、ガイドラインやパンフレット等研究成果をより効果的に提供できるよう、当該ホームページへの掲載を研究者にお願いしているところである。
リウマチ・アレルギー相談員養成研修会
| ・ |
リウマチ・アレルギー疾患についての地域相談体制を整備するため、保健師等従事者を対象とした相談員の養成研修会を開催し、研究成果の積極的な還元を図っている。 |
| ・ |
平成14年度から食物アレルギーに関する講義、平成15年度から総括講義として行政施策に関する講義、平成16年度から参加者による自治体施策の発表を追加する等、内容の充実に努めている。 |
| ・ |
講師として研究班の主任研究者等を活用し、リウマチ・アレルギー分野における一般的な知見と併せて、研究成果を踏まえた最新の知見を盛り込む等、工夫を凝らして研究成果の活用を図っているところである。 |
| 平成17年花粉症対策及び関係省庁との連携による花粉症対策研究 |
特に平成17年春は全国的に1,2位を争う多さの花粉が飛散すると予測されていたため、厚生労働省においては研究班の主任研究者等の協力を得、医療従事者向けQ&A集や地方自治体向け相談マニュアルの作成、シンポジウムの開催等を通じて、正しい情報に基づく花粉症の予防や早期治療の更なる徹底を進めた。また、平成2年から各省庁(厚労・文科・環境・農水・気象)で連絡会議を開催し適宜情報交換を行ってきたが、先般、総合科学技術会議のもとで、関係省庁における花粉症対策研究の総合的な推進について科学的観点から検討され、減感作療法、花粉症緩和米、ワクチンの研究開発に重点を置いて研究を推進すべきであると報告された。 |
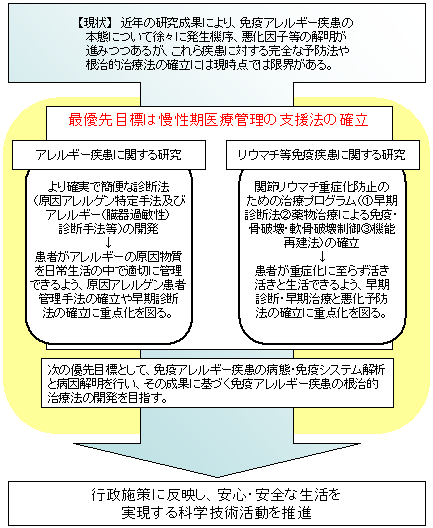
|
花粉症、食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、リウマチ等の免疫アレルギー疾患を有する患者は国民の30%以上に上り、ますます増加傾向にあるといわれている。また、一般的に免疫アレルギー疾患の病態は十分に解明されたとは言えず、根治的な治療法が確立されていないため、長期的に生活の質(Quality of Life: QOL)の低下を招き、一部のアレルギー疾患については不適切な治療等の結果により致死的な予後をもたらす等、疾患毎に様々な問題を抱えている。このような国民病である免疫アレルギー疾患に関して患者QOL等の実態を把握するとともに、予防・診断・治療に関する新規技術等の開発を進め、その成果を臨床現場に還元し、患者のQOLの向上を図ることは非常に重要で着実に実施するべきテーマである。
特に、平成16年度は行政と研究者が連携し、研究成果を積極的に活用して一般国民や医療従事者等への普及啓発を実施した点が評価でき、国として進めるべき研究事業の体制が強化されたと考える。 |
| 研究事業(研究事業中の分野名):こころの健康科学研究事業 |
| 所管課: |
社会・援護局障害保健福祉部企画課
(研究費の執行、精神分野の調整;社会・援護局障害保健福祉部企画課)
(推進事業費の執行、神経分野の調整;健康局疾病対策課) |
|
| 予算額(平成17年度): 千円 |
|
高い水準で推移する自殺問題をはじめ、社会的関心の高い統合失調症やうつ病、睡眠障害、ひきこもり等の思春期精神保健の問題、また自閉症やアスペルガー症候群等の広汎性発達障害等のこころの健康に関わる問題と、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病等の神経・筋疾患に対して、疫学的調査によるデータの蓄積と解析を行い、心理・社会学的方法、分子生物学的手法、画像診断技術等を活用し、病因・病態の解明、効果的な予防、診断、治療法等の研究・開発を推進する。 |
|
(別途添付) |
| ○ |
本研究事業において得られた具体的な成果は以下の通り。 |
(精神分野)
| ・ |
重症精神障害者に対する、新たな訪問型の包括的地域生活支援サービス・システムの開発に関する研究(塚田班)
|
| ・ |
自殺多発地域における中高年の自殺予防を目的とした地域と医療機関の連携による大規模介入研究(酒井班)
| → |
リエゾンナース事業の取り組みが厚生労働省のうつ対応マニュアルに反映された。 |
|
| ・ |
ゲノム医学を活用した統合失調症及び気分障害に対する個別化治療法の開発(染矢班)
| → |
統合失調症、及び気分障害について、薬物療法の治療反応性及び副作用の予測に、遺伝子多型が予測因子として有用である可能性を示した。この成果は海外誌に掲載され、国内外から大きな反応があった。 |
|
| ・ |
感情障害の発症脆弱性素因に関する神経発達・神経新生的側面からの検討並びにその修復機序に関する分子生物学的研究(三國班)
| → |
感情障害の亜型の区別や重症度の評価に関する客観的検査指標を見出し、保険収載の申請中である。実施されれば18億円の医療費削減に繋がるという試算がある。 |
|
| ・ |
ストレス性精神障害の予防と介入に携わる専門職のスキル向上とネットワーク構築に関する研究(加藤班)
| → |
専門職が業務をとおして受ける心理的影響を明らかにした。その成果は複数の消防本部において、惨事ストレス対策を推進する根拠となった。 |
|
| ・ |
自閉症の原因解明と予防、治療法の開発―分子遺伝・環境・機能画像からのアプローチ―(加藤班)
| → |
脳画像研究で、高機能自閉症では社会性やコミュニケーションに関わる脳部位のネットワーク障害が存在することを明らかにした。研究成果については、当事者・家族を中心とする1000名規模の公開シンポジウムで発表を行い、当事者・家族の理解が得られた。 |
|
(神経分野)
| ・ |
選択的リンパ球吸着療法による免疫性神経筋疾患の治療に関する研究班
| → |
本研究は、全血フロー系で標的となるCD4陽性T細胞を特異的に除去することで免疫調節を行うもので、今後、担体物質の最適化やリガンドの精製技術を改良することで自己反応T細胞または病因となる免疫担当細胞のより選択的な除去・補足による免疫調整技術を更に発展させることが可能である。これらの技術は世界に類をみないもので、全く独創的な研究である。 |
|
| ・ |
ALS2分子病態解明とALS治療技術の開発に関する研究班
| → |
ALS2遺伝子における56ヶ所における遺伝子多型配列を新たに同定した。ALS2遺伝子産物であるALS2タンパク質が低分子量Gタンパク質Rab5の活性化因子であることを明らかにした。Als2遺伝子ノックアウトマウスの作出に成功した。神経変性疾患原因遺伝子の一つであるALS2の遺伝子産物機能を世界に先駆けて明らかにするとともに、Als2ノックアウトマウスの作出にも成功した本成果は国際誌に掲載され、国内外から大きな反響があった。 |
|
| ・ |
発現型RNAiを用いた神経・筋疾患の画期的遺伝子治療法の開発に関する研究班
| → |
筋萎縮性側索硬化症の原因遺伝子、脳卒中の発症に係わる細胞接着因子の遺伝子などを効率よく抑制するsiRNAの作製に成功し、筋萎縮性側索硬化症の発症予防等を示した。効果的siRNAデザインシステムを開発しsiRNA発現ライブラリーを構築して、小胞体ストレス経路に係わる新規機能遺伝子を同定した。これらの業績はNature等に掲載され多くのメデイアにも取り上げられ国内外から非常に高い評価を受けている。 |
|
|
| (4) |
行政施策との関連性・事業の目的に対する達成度 |
| ○ |
行政的に求められるニーズに対しては、適宜具体的な成果を上げている。
(上記(3)参照) |
|
| ○ |
今後更に行政的なニーズを明確にした研究課題の公募と進捗状況の把握、活用 |
| ○ |
研究経費の適切な執行体制の整備 |
|
| ○ |
わが国の精神障害者は250万人を超え、年間の自殺死亡者は3万人を超えている。また、犯罪被害者や災害被災者のこころのケアなども社会的に注目されている。このように「こころの健康問題」には、従来からのテーマである統合失調症に加えて、うつ病、神経症、摂食障害、ストレス性精神障害、睡眠障害、発達障害等、非常に広範かつ深刻な問題が含まれている。 |
| ○ |
また、「こころの健康問題」の特性として、基礎的な遺伝子解析・分子機構解明・画像解析等による病態解明や診断・治療法の開発のみならず、表現される行動の評価、福祉を含む社会システムとの関連、倫理や人権上の配慮などの行政的な課題の解決も必要であり、重層的な視野での取り組みが不可欠である。 |
| ○ |
「こころの健康科学研究事業(精神分野)」においては、このような状況を踏まえて、平成14年度の事業再編統合から、基礎、及び行政的ニーズに沿った研究の推進とその評価を進めてきたところである。 |
| ○ |
その結果、以下のような成果が得られている。
| ・ |
精神疾患の病態解明においては、最新の遺伝子解析、分子機構解明、画像解析等の手法に基づく研究が進められた結果、新たな機構や新たな分子の発見等により新たな予防手法や治療薬の開発、客観的診断手法の開発を前進させる成果が得られた。 |
| ・ |
精神保健福祉上の重要な課題である自殺予防対策について、平成15年度の研究成果として、「行政担当者のための自殺予防対策マニュアル」が作成された。自殺予防対策に関する研究は、現在も継続されている。 |
| ・ |
精神疾患の実態把握と政策立案の基礎資料となる、各種精神疾患に関する疫学的なデータが蓄積された。 |
| ・ |
思春期保健対策に係る診断や治療に関する知見が得られた。方向性等に関する一定の成果が得られた。 |
| ・ |
医療観察法の施行という行政施策と関連が深い司法精神医学の研究が推進された。 |
|
| ○ |
神経分野についても、研究によって解明された病態に基づき予防法や新しい治療の展望が開けており、神経疾患の医療の向上に資する大きな成果を挙げている。
今後も脳・神経疾患についてゲノム解析や分子生物学的手法を駆使して病因、病態の解明を進める。 |
| ○ |
今後は、これらの成果を遺伝子治療再生治療に繋げるなどして、新しい治療の開発とその臨床応用を目指している。
|
| ○ |
以上のように、研究事業の目的に沿った具体的な成果が得られ、随時、行政にもフィードバックされている。 |
| ○ |
今後とも、国民の健全な生活に不可欠な「こころの健康」の重要性に鑑み、本事業を強力に推進していく必要がある。
|
|
| 研究事業(研究事業中の分野名):難治性疾患克服研究事業 |
| 所管課:健康局疾病対策課 |
| 予算額(平成17年度):2,083,684千円 |
|
根本的な治療法が確立しておらず、かつ後遺症を残すおそれが少なくない自己免疫疾患や神経疾患等の不可逆的変性を来す難治性疾患に対して、重点的・効率的に研究を行うことにより進行の阻止、機能回復・再生を目指した画期的な診断・治療法の開発を行い、患者のQOLの向上を図ることを目的とする。 |
16年度採択課題一覧【別紙1】
| (1) |
臨床調査研究班 |
38班 |
| (2) |
横断的基盤研究班 |
10班 |
| (3) |
重点研究班 |
18班 |
研究課題については、特定疾患治療研究事業への成果反映の具体的な方法、研究成果の普及等ついて評価委員会で考慮の上、採択している。 |
特定疾患の診断・治療等臨床に係る科学的根拠を集積・分析し、医療に役立てることを目的に積極的に研究を推進している。また、重点研究等により見いだされた治療方法等を臨床調査研究において実用化につなげる等治療法の開発といった点において画期的な成果を得ている。
最近の主な成果(抜粋)
(原発性免疫不全症候群に関する調査研究班)
uracil-DNA glycosylase (UNG)の同定に貢献し、UNG遺伝子変異が高IgM症候群をもたらすことがNature Immunologyに掲載され、国内外から大きな反響があった。
(難治性血管炎に関する調査研究班)
欧米に比べ我が国に多い顕微鏡的多発血管炎に限定した前向き臨床研究は世界初の試みである。病態と密接に関与する遺伝子を3種類同定した。
世界に先駆けてBurger病に対する遺伝子治療の臨床応用実現に向けて大きく前進した。これらの解析を通して血管炎原因遺伝子の同定や血管炎発症機序のさらなる解明が期待される。
(自己免疫疾患に関する調査研究班)
関節リウマチおよびSLEの発症に関与する新たな遺伝子が同定され、Nature Genetics,誌に発表され、またマスコミでも報道され社会的な反響をよんだ。
(プリオン病及び遅発性ウイルス感染に関する調査研究班)
未だ発症機序も全く不明であるプリオン病の克服には正確な実態の把握が重要であるがそれが達成されつつあることが示され、この変異型CJD例により脳波上、MRI上の新知見が明らかとなり、2005年5月英国での国際サーベイランス会議で発表しWHOの基準の見直しが進んでいる。キナクリン/ペントサン治療は本邦で開発され英国での治験を指導するまでになっている。プリオン病の発症機序の解明も着実に進んでおり大きな貢献をしている。
SSPEについても実態の把握が進み、疫学的危険因子や遺伝的危険因子、SSPE特有のゲノムが明らかとなり、リバビリンの治験も進んでいる。
PMLについては発症機序解明で大きな進展があったのみならず、診断基準の作成等により全国的実態調査が進んだ。これらの成果は一流の学術誌に掲載され班会議にて発表されたのみならず、2004年にはPMLおよびプリオン病の国際会議を共催し全世界にむけて発信された。
(神経変性疾患に関する調査研究班)
| ・ |
SOD2遺伝子導入トランスジェニック・マウス作成により発症機構の解明が進んだ(gain of function)。 |
| ・ |
世界で初めてトランスジェニック・ラットを作成し,大型動物による実験が可能になり,病態と治療薬の研究が進んだ。 |
| ・ |
孤発性ALSの脊髄運動ニューロンではグルタミン酸AMPA受容体GluR2RNAの編集率が正常対象と比較して有意に低下していることを発見した。 |
| ・ |
紀伊半島多発地の再調査により,高発生率の持続を確認した.更にグアムと同じパーキンソン痴呆複合(PDC)の存在を発見し,多くが家族性発症であることを確認した. |
| ・ |
電気生理学的検査 Motor Unit Number Estimation (MUNE)を用いて,発症後の運動ニューロン活動量が測定できることを示した. |
| ・ |
人工呼吸器装着後の患者の臨床徴候を長期間研究し,完全閉じ込め症候群(total locked-in : TLI)に至るALS臨床像の全経過を解明した. |
| ・ |
新たに作成した臨床個人調査票を用いて我が国の患者の療養実態を明らかにした. |
| ・ |
メチルコバラミン(ビタミンB12)の臨床効果を検証中である. |
| ・ |
有用な鑑別診断法として,MIBG心筋シンチグラフィーの異常所見が発見された. |
| ・ |
レビー小体出現剖検例の研究により,DLBとPDDの病理学的所見に本質的差異はないことが示された. |
| ・ |
本研究班の分担研究者が中心になって,日本神経学会でPD治療ガイドラインが作成された(2002年). |
| ・ |
定位脳手術の技術的改良(手術部位決定法,破壊か電気刺激か)が進んでいる. |
| ・ |
MPTP投与PDモデルサルにおいて,アデノ随伴ウィルスベクターによるドパミン合成酵素遺伝子導入治療が成功した. |
| ・ |
患者のQOLを決定する影響因子が解析され,それを利用した改善事項を提唱した. |
(モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)関する調査研究班)
不明な点が多かった本疾患の疫学像、病因・病態の解明に寄与した。また予後不良因子である再出血予防に関する治療指針確立の端緒となった。
(特発性心筋症に関する調査研究班)
心筋症を細分化し、それぞれの診断基準を作成し、国際的な診断・治療のスタンダードを提供した。疫学的検討により予後を評価しようとした。病因の解析について、遺伝子解析や免疫学的解析を中心に検討し、新規の遺伝子や病態を数多く発見した。
(進行性腎障害に関する調査研究班)
IgA腎症の全国疫学調査にて予後に影響するのは、高血圧、高度蛋白尿、腎生検での高度障害であった。IgA腎症予後不良群に対して、ステロイド薬・抗凝固薬・アンジオテンシン阻害薬による多剤併用療法の有効性が示唆された。MPO-ANCA型急速進行性糸球体腎炎に対するシクロフォスファミドパルス療法の有用性が示唆された。膜性腎症の予後調査について長期予後の点では、発症15年までは良好であるが、それ以降低下する傾向が明確となった。加齢以外にも悪化の要因があると考えられた。治療法別の予後解析では、ステロイド薬単独療法の有効性が示唆された。高血圧を有する多発性嚢胞腎症例に対し、カルシウム拮抗薬投与群に比較して、アンジオテンシン受容体拮抗薬投与群では、尿中蛋白排泄量やアルブミン排泄量を減少させることが明らかとなった。
(特定疾患の地域支援体制の構築に関する研究班)
精神的支援体制
身体的支援体制整備と並列して精神的・心理的サポート体制の必要性を研究した。 療養環境・生活支援・相談事業など特定モデル地域での成果を全国に普遍化する戦略を確立した。 研究事業での成果は利用者の視点から検証し、今後の研究戦略、問題解決策として提言した。研究事業での成果を国の難病対策事業として普遍化、その進捗と効果について研究した。
医療体制
都道府県単位に難病医療ネットワークを構築してより円滑に専門医療を供給できる体制整備、拠点病院と協力病院の役割分担、個々の患者の長期支援に専門医師がより積極的に参画する意義、効果について研究、これらの支援体制整備の具体的な効果を実証できた。
(進行性腎障害に対する腎機能維持・回復療法に関する研究班)
新規腎障害進行因子としてプロレニン・プロレニン受容体を同定し、新たなIgA腎症進行に関わる遺伝因子を同定した。腎臓の再生に、骨髄間葉系幹細胞および内皮前駆細胞が有用であることが初めて示されるとともにSall 1ファミリー、MTF-1などの分化誘導因子のクローニングを行った。
(筋萎縮性側索硬化症の病因・病態に関わる新規治療法の開発に関する研究班)
変異SOD1特異的に結合するユビキチンライゲースを同定した。また数種の変異SOD1遺伝子導入トランスジェニックマウスを作製し、臨床病像との相関を明らかにした。さらには治療法の開発に応用するために髄腔内への薬剤投与が可能なトランスジェニックラットを作製し、新規治療法の開発を行った。(ウ)特に、ラットによるALSモデルを用いた新規治療法の開発手法に関しては国内外から大きな反響があった。 |
| (4) |
行政施策との関連性・事業の目的に対する達成度 |
| ・ |
特定疾患治療研究事業の対象疾患について、患者の療養状況を含む実態、診断・治療法の開発等に大きく寄与しており、これに基づく診断基準の改定・治療指針の改訂は、我が国の医療水準の向上につながっている。 |
| ・ |
研究成果である新規治療法により、病気の軽快者も出ており、難病医療に貢献している。 |
| ・ |
現在でも、多くの難病患者が病院や在宅で療養しているが、「難病患者の心理サポートマニュアル」の作成・改訂や「難病相談・支援センター」の整備等を通じて、福祉施策が大きく進められており、医療福祉環境の向上に寄与している。 |
最近の主な成果(抜粋)
(特発性造血障害に関する調査研究班)
臨床調査個人票に基づき、旧様式で8,000余、新様式で4,000余件のデータを集計し、実態を解析した。
(自己免疫疾患に関する調査研究)
抗リン脂質抗体の測定のための標準抗体となるモノクローナルマウス・ヒトキメラ抗体を作成し、WHO/アメリカリウマチ学会標準抗体に認定され、世界標準抗体になっている。
抗プロトロンビン抗体およびループスアンチコアグラント測定の標準化を行った。
日本人の抗リン脂質抗体症候群の治療ガイドラインを作成した。
(プリオン病及び遅発性ウイルス感染に関する調査研究班)
プリオン病は現在根本的治療法のない致死的感染疾患でありサーベイランスとそれにもとづく感染予防がきわめて重要であるが、変異型CJDの発見と対応により本研究によるサーベイランスと疫学研究がきわめて有効に機能していることが示された。
事実、本研究では班会議の他にプリオン病ではサーベイランス委員会、SSPEとPMLではそれぞれの分科会をもち、何度もの会議を行い、さらには得られた知見をいち早く全国に周知するというCJDサーベイランス全国担当者会議をも行っており、厚生労働行政に対する貢献は非常に大きい。
また、診断基準の策定、見直しに加えそれぞれに治療への試みが開始されたことも厚生労働行政にとって大きな貢献であり、最終的には発症機序の研究の進展も大きな貢献をすることと期待される。
(稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班)
天疱瘡に関してデスモグレイン1,3のELISA抗体価測定法の開発とその健保収載により、本症の診断と疾患活動性評価が容易に行なわれるようになり全国の病院で適切な診断に基づいた適切な治療が可能となった。
(特定疾患の疫学に関する研究班)
臨床調査個人票を用いて治療研究事業対象者の18年間の特徴、将来の受給者数の推計を示した。難病対策の評価として「難病30年の研究成果」を発行した。患者の保健医療福祉とQOLの向上に資するための研究も実施した。
(特定疾患の地域支援体制の構築に関する研究班
研究成果から政策的提言がなされ、2つの都道府県事業が実現した。研究班は事業進捗を推進、阻害要因を解決する戦略を求め、実質的な成果を得た。
| ・ |
難病に対してより円滑な医療サービスと実質的な生活支援環境が整備されることによってより多くの難病患者が例え人工呼吸器を装着してでも生きる決心ができ、障害や社会的不利益を克服して生きがいを持ち、より高い生活の質を保持した生活ができることを実証。 |
| ・ |
本研究班の主導で、各地で多専門職種を包括する難病支援体制整備やその実践的研究が実施され、難病医療と生活支援体制のケアシステムが質・量共に向上した。 |
| ・ |
難病者にとっても最大の生きがいとなる『雇用の拡大等就労支援体制』について研究を進め、最終的に難病者の自立支援、難病克服体制を創造する。 |
|
| ○ |
治療法の開発等による難病の克服(ゲノム、再生、免疫等他の基盤開発研究の成果を活用した臨床研究の推進)
 |
| ○ |
研究の進捗状況、治療成績等を評価する体制を構築した上で、疾病毎の研究の必要性を見極め、難治性疾患克服研究の対象疾患(121疾患)以外の難病についても、緊急性の高い疾患については、研究の実施を進めていくよう研究の実施体制を見直していく。 |
(具体的な研究課題及び内容)
今後は以下の方向性の下、効率的な研究の推進を図る。
| ・ |
免疫システムに関する分子生物学的研究の成果を活用した難治性自己免疫性疾患の治療法の開発 |
| ・ |
難病患者の就労支援のための研究 |
| ・ |
災害時における難病患者に対する医療支援体制の構築のための研究 |
| ・ |
現在、研究対象となっていない疾病についても、緊急性等を考慮して治療法の開発等を推進 |
|
特定疾患対策事業等の行政施策と密接な関係があり、行政ニーズと学術的な問題点とを十分把握した上で、研究が進められている。なお、診断基準の作成等の研究成果を効果的に行政施策へ反映されるなど、行政施策への貢献度が高い研究事業である。
今後とも、各疾患の研究の進捗状況や対策の緊急性等を十分考慮した上で研究を進めて行く必要がある。 |