| 1. | 厚生労働科学研究費補助金制度の概要 |
厚生労働科学研究費補助金は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行いつつ、厚生労働科学研究の振興を一層推進するものである。
厚生労働科学研究は、研究及びエビデンスの結果を施策に反映させ、また施策の成果をエビデンスとして把握し、国民の健康・安全確保を推進することを目指して実施されている。(図1参照)
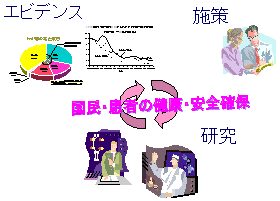
| 図1. | 厚生労働科学研究と施策の関連性 |
2)厚生労働科学研究費の経緯
厚生科学研究費補助金制度は昭和26年度に創設された。昭和26年度に厚生行政科学研究費、昭和36年度に医療研究費、昭和59年度に対がん10ヵ年総合戦略経費、昭和62年度エイズ調査研究費、平成10年度に厚生科学研究費補助金取扱規程、取扱細則決定などの制度の整備を経て、平成14年度から厚生労働科学研究費補助金に改称され、現在に至っている。
3)厚生労働科学研究の4分野
厚生労働科学研究費補助金の研究事業は、行政政策研究分野、厚生科学基盤研究分野、疾病・障害対策研究分野、健康安全確保総合研究分野の4分野に大別される。
各分野の予算額の割合は、図2に示すように、行政政策研究分野が約3%、疾病・障害対策研究分野が50%、その他の2分野がほぼ4分の1ずつをしめている。
| 4)研究の課題設定と公募 厚生労働科学研究費補助金制度では、18の研究事業毎に事業を実施している。(表) それぞれの研究事業ごとに、国民の健康、福祉、労働面の課題を解決する目的志向型の研究課題設定を行い、その上で、原則として公募により研究チームを採択している。 国内の試験研究機関等(国公私立大学、国公立・民間研究機関等)に属する研究者、または法人を対象としている。 |
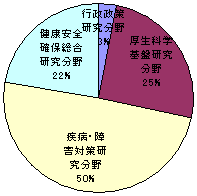 図2.分野別予算額の割合 |
5)予算額及び採択件数の推移
厚生労働科学研究費は、厚生労働省の科学技術関係予算のほぼ1/3を占め、平成17年度予算では420億円を計上し、1,400課題余の研究を実施している。
科学技術基本計画の策定に伴い、平成16年度から研究費は着実に増額を続けている。
また、採択課題数も大幅に増加している(図3)。
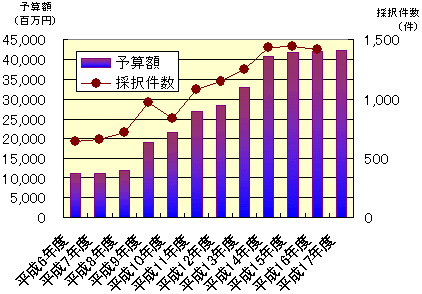
| 図3. | 厚生労働科学研究費の予算額と採択件数の推移 |
6)研究事業の構成
厚生労働科学研究の各研究事業の予算額の割合は図4のとおりである。
| 図4 | 各研究事業毎の当初予算額の割合(平成16年度) |
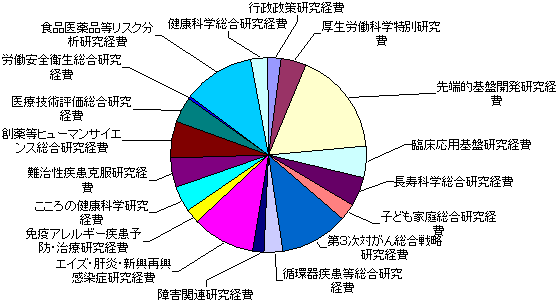
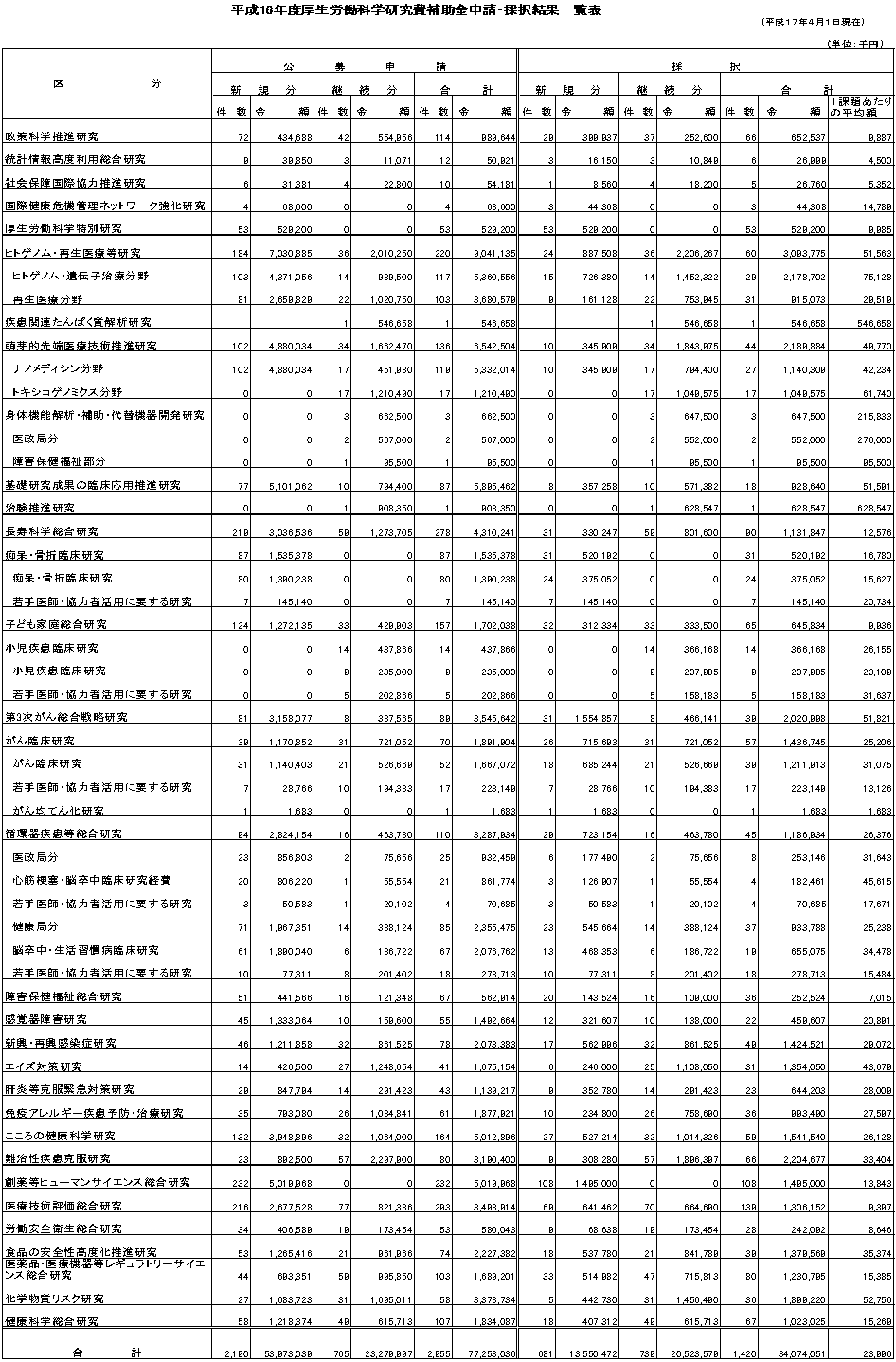
7)研究課題あたり研究費別金額割合
厚生労働科学研究費の研究課題当たりの金額は平均23,996千円である。金額の割合では、20,000千円台(図5)、件数では5,000〜20,000千円未満が多い(図6)。
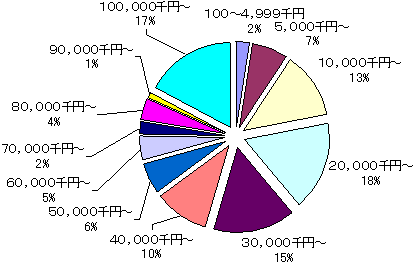
| 図5. | 研究課題当たりの研究費の割合 |
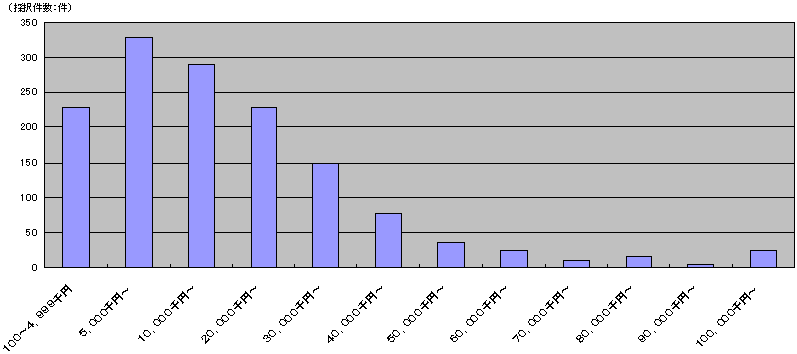 (1研究課題当たり研究費額) |
| 図6. | 研究課題当たりの研究費額の分布 |
一課題毎の研究費額は、研究事業毎に異なっており、図7の配分となっている。研究費額は、実験的な内容を含む研究事業とそれ以外の研究事業により異なっている。
| 図7 | 研究事業毎の一課題あたり研究費額(千円) |
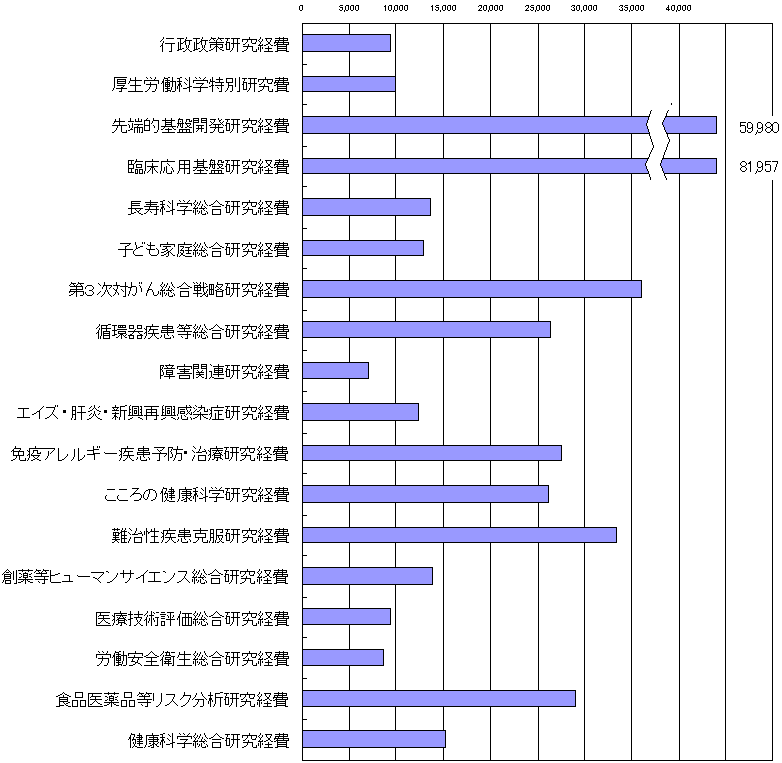
| 2. | 申請課題の評価 |
1)公募課題の決定手順、決定について
公募課題については、各研究事業の評価委員会において課題の検討を行い、その意見を基に、各研究事業を所管する部局の科学技術調整官が厚生科学課(プログラムオフィサーを含む)と調整の上、課題の選定を行い、厚生科学審議会科学技術部会において審議、決定する。公募課題は、行政施策の科学的な推進、技術水準の向上のために必要性の高いものについて検討することとしている。
2)研究課題の評価
厚生労働科学研究費補助金の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に係る指針」、「厚生労働科学研究費実施要項」に基づき行われる。
研究の透明性の確保と活性化及び公正な執行を図ることを目的とし、研究課題ごとに、事前評価委員会、中間・事後評価委員会を設置している(委員:10〜15名程度)。
提出された研究開発課題は、各研究事業の評価委員会において、専門家による専門的・学術的観点と、行政担当部局の行政的観点から評価を行っている。(図8参照)
厚生労働科学研究費全体で、事前評価に述べ約450人、中間・事後評価に述べ約380人の評価委員が評価にあたっている。(評価委員名簿をホームページ上で公開)
書面審査を基本とし、各評価委員会の判断にヒアリングを実施している。
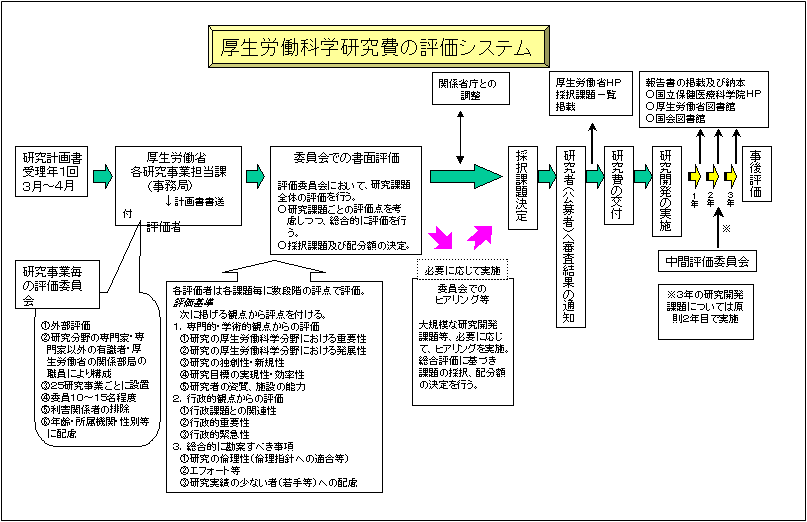
| 図8 | 厚生労働科学研究の評価システム |
3)評価の観点
それぞれの研究事業の評価委員会において、次に掲げる観点から評点を付け、評価を行っている。
| 3−1) | 事前評価 |
| 1. | 専門的・学術的観点からの評価
|
||||||||||
| 2. | 行政的観点からの評価
|
||||||||||
| 3. | 総合的に勘案すべき事項
|
| 3−2) | 中間評価 |
| 1. | 専門的・学術的観点からの評価
|
||||||
| 2. | 行政的観点からの評価 期待される厚生労働行政に対する貢献度など |
||||||
| 3. | 総合的に勘案すべき事項
|
| 3−3) | 事後評価 |
| 1. | 専門的・学術的観点からの評価
|
||||||||
| 2. | 行政的観点からの評価 期待される厚生労働行政に対する貢献度など |
||||||||
| 3. | 総合的に勘案すべき事項
|
| 3. | その他の取組事項 |
各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性について検討している。
医学研究に係る厚生労働省関連の指針についてホームページで公開。
2)被評価者に評価結果を通知(平成10年以降)
3)若手研究者への配慮
研究の評価にあたっては、これまで研究実績の少ない者(若手研究者等)についても、研究内容や計画に重点を置いて的確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、研究開発の機会が与えられるように配慮するよう指針で定めている。一部の研究事業において若手研究者(36歳以下)を対象とした枠を設定している。
| ・ | 萌芽的先端医療技術推進研究事業 |
| ・ | 食品の安全性高度化推進研究事業 |
| ・ | 循環器疾患等総合研究事業 |
4)間接経費の計上
3,000万円以上の新規研究課題を対象に研究費の30%の間接経費を導入している。
| ・ | 平成16年度(実績):12億円 |
5)大学院博士課程学生への支援
研究者を対象とした制度であり、大学院生への支援措置はないが、実験補助等に対する賃金を支払うことは可能としている。
| 4. | 申請と採択の状況 平成16年度実績では、新規課題の採択率は、約40.4%となっている。
|
| 5. | 厚生労働科学研究の推進事業 |
当該分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招聘し、海外との研究協力を推進している。
2)外国への日本人研究者派遣事業
国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施することにより、わが国における当該研究の推進を図っている。
3)リサーチレジデント事業(若手研究者育成活用事業)
主任又は分担研究者の所属する研究機関に当該研究課題に関する研究に専念する若手研究者を一定期間(原則1年、最長3年まで延長)派遣し、当該研究の推進を図っている。将来のわが国の研究の中核となる人材を育成するための事業を行っており、年間約400名を派遣している。
4)その他
研究成果発表会や、研究事業毎のパンフレット作成等を行っている。
| 6. | 公表に関する取組 |
厚生労働省ホームページ上で、次の事項を公開している。
| ・ | 事業概要、募集要項、評価指針 |
| ・ | 評価委員会委員名簿 |
| ・ | 採択研究課題名、主任研究者、交付金額 |
研究報告書を厚生労働省図書館、国会図書館、国立保健医療科学院等に配布し、保管・公表するほか、国立保健医療科学院ホームページ上で、研究課題、研究者名、研究成果(報告書本文等)を含み、検索も可能な厚生科学研究成果データベースを公開しており、平成17年3月28日から1万件以上(平成17年5月現在)のアクセスがある(図9)。
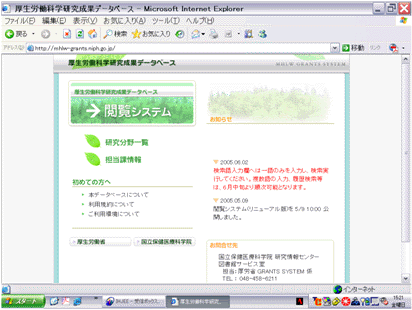
| 図9. | 厚生労働科学研究成果データベース |