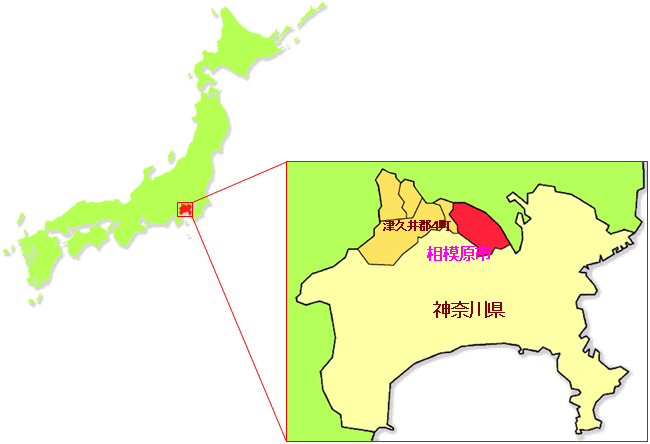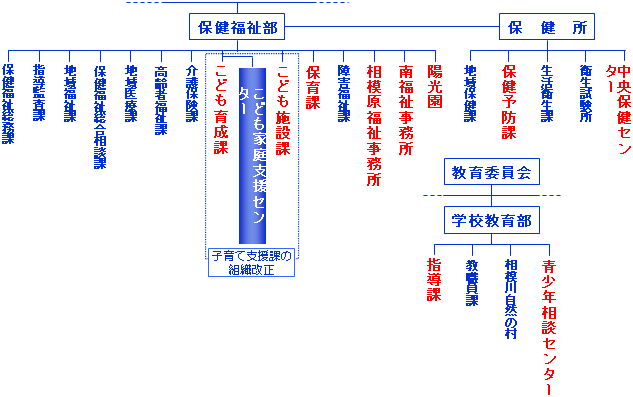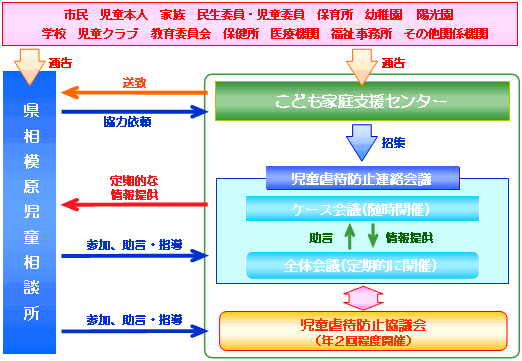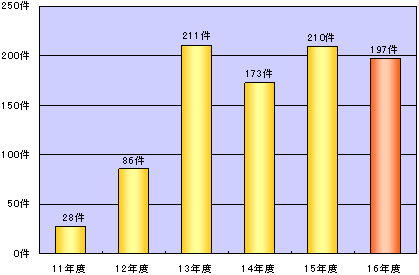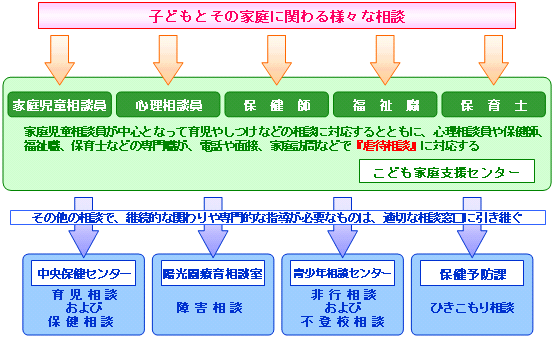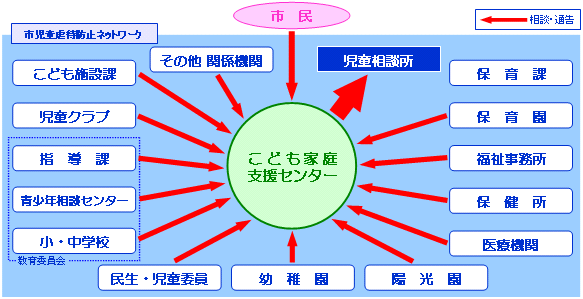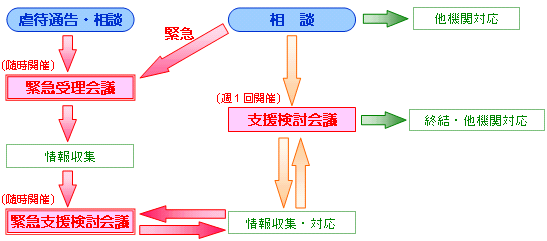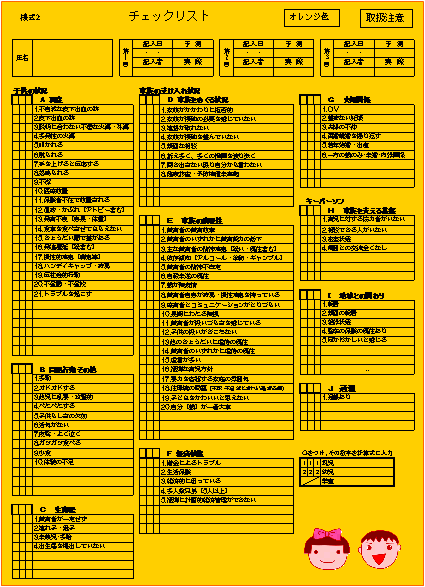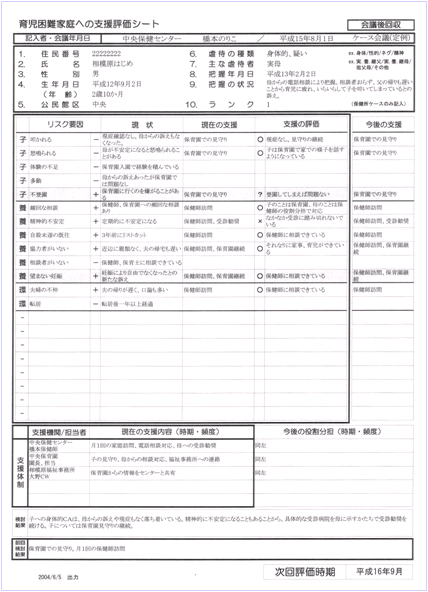(資料3)
相模原市における児童虐待防止対策事業
相模原市 保健福祉部 こども家庭支援センター
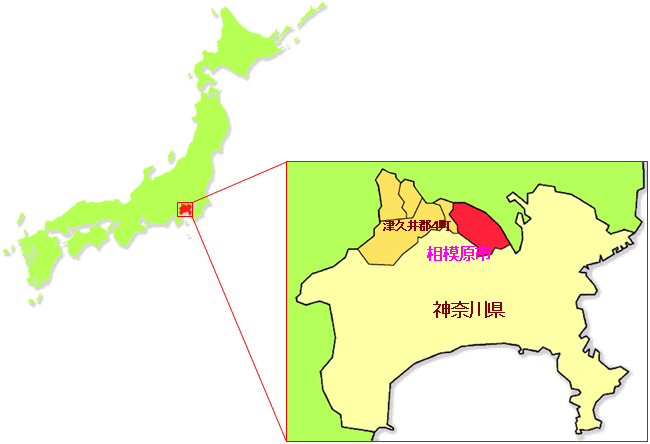
| ○ |
面積:90.41平方キロメートル |
| ○ |
人口:623,642人(平成17年4月1日現在) |
| ○ |
人口増加数(平成16年度中):3,043人
| ・ |
自然増加 |
2,353人
(出生 5,819人、死亡 3,466人) |
| ・ |
社会増加 |
690人
(転入 33,848人、転出 33,158人) |
|
|
| ○ |
平成12年4月 保健所政令市 |
| ○ |
平成15年4月 中核市 |
|
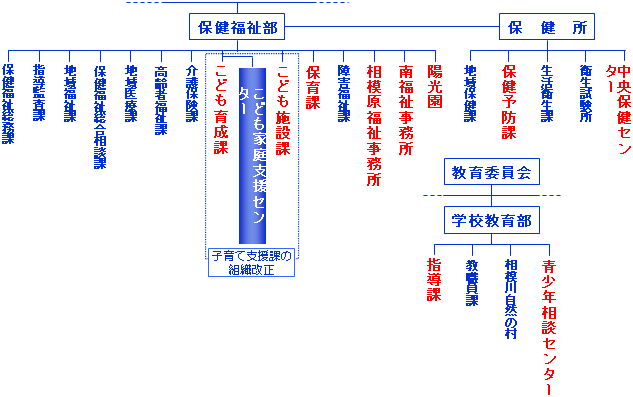
※太字の機関には虐待担当を置き、こども家庭支援センターと
連携して児童虐待対応にあたる |
|
| ◇ |
平成12年11月「児童虐待の防止等に関する法律」施行 |
| → 平成13年5月 |
「相模原市児童虐待防止ネットワーク」設置
| ※ |
関係機関が相互に連携し、児童虐待の早期発見と早期対応に努める |
|
| |
| 関係機関の代表者による虐待問題への取り組みに関する情報交換、協議、連携等
→平成16年度 2回開催 |
|
| |
|
関係機関の長等による児童虐待防止対策事業の方向性の検討や、庁内関係機関のスムーズな連携
→平成16年度 2回開催
個々の事例の担当者による具体的な対応方法や役割分担などの検討等
→平成16年度 80回開催 |
|
|
| 相模原市 |
保健福祉部長 |
| 保健福祉部保健所長 |
| 学校教育部長 |
| 関係機関 |
相模原児童相談所長 |
| 児童養護施設中心子どもの家所長 |
| 相模原市民生委員児童委員協議会から推薦された者 |
| 相模原市医師会から推薦された者 |
| 相模原歯科医師会から推薦された者 |
| 相模原市私立保育園長会から推薦された者 |
| 横浜弁護士会相模原支部から推薦された者 |
| 相模原市人権擁護委員会から推薦された者 |
| 相模原警察署から推薦された者 |
| 相模原南警察署から推薦された者 |
| 相模原市幼稚園関係団体から推薦された者 |
| 相模原市公立小学校校長会から推薦された者 |
| 相模原市公立中学校校長会から推薦された者 |
| 相模原市 |
企画部 |
男女共同参画課長 |
| 保健福祉部 |
保健福祉総務課長 |
| 地域福祉課長 |
| 保健福祉総合相談課長 |
| 地域医療課長 |
| こども育成課長 |
| こども家庭支援センター所長 |
| こども施設課長 |
| 保育課長 |
| 相模原福祉事務所長 |
| 南福祉事務所長 |
| 陽光園所長 |
| 保健福祉部保健所 |
保健予防課長 |
| 中央保健センター所長 |
| 教育委員会管理部 |
学務課長 |
| 教育委員会学校教育部 |
指導課長 |
| 青少年相談センター所長 |
| 消防本部 |
救急対策課長 |
| 関係機関 |
相模原児童相談所 |
指導課長 |
| |
|
個々の事例の担当者による具体的な対処方法や役割分担などの検討等
→平成16年度 80回開催 |
|
| |
|
子育て支援課、福祉事務所、保健所、教育委員会による全ケースについての対応方法の確認(17年度からは、こども家庭支援センター、保健所、教育委員会で実施)
→5月と11月の年2回実施
県相模原児童相談所と連携して対応しているケースについての対応方法の確認
→年1回実施
新年度に就学予定のケースについて、3月に教育委員会と対応方法を検討
→年1回実施
新たに把握したケースの報告や、状況改善などによるケースの終結を検討(17年度からは、支援検討会議で対応)
→月1回実施 |
|
|
| |
8人(保健師2人、福祉職2人、保育士1人、事務職3人)
| ※ |
非常勤特別職(心理相談員、家庭児童相談員、育児支援家庭訪問相談員) |
|
| |
ウェルネスさがみはらA館6階に設置。相談室及びプレイコーナーを配置し、相談業務に対応 |
| (1) |
保健師、福祉職、保育士などによる専門相談(電話、面接、家庭訪問) |
| (2) |
心理相談員による専門相談【新規事業】 |
| (3) |
家庭児童相談員による相談【増員による充実】 |
| (1) |
児童虐待の相談、通告受付 |
| (2) |
児童虐待防止ネットワークの運営、個別ケースの進行管理 |
| (3) |
育児支援教室(MCG)の運営 |
| (4) |
育児支援家庭訪問事業の実施【新規事業】 |
児童福祉法、児童虐待防止法の改正に伴い、児童虐待対応における市町村の役割が強化されたことから、こども家庭支援センターは、本市における児童虐待対応の中心的機関として、各機関と連携し、児童虐待に対応する
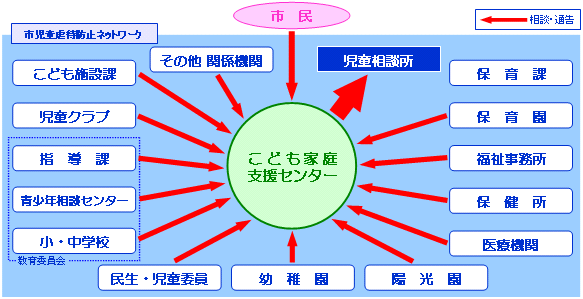
| ※ |
児童虐待対応にあたってはネットワークの各機関が連携して対応 |
| ※ |
緊急時などの各機関からの児相への通告は省略 |
|
| ・ |
ケース会議(随時)…… |
必要時、個別ケースについて対応を検討 |
| ・ |
定例ケース会議………… |
半年に1回、全ケースについて対応を検討 |
| ・ |
新就学児ケース会議…… |
新年度に就学児になるケースについて対応を検討 |
| ・ |
虐待担当者会議………… |
児童虐待対応の課題などを、各機関の虐待担当者で検討 |
|
一般的なチェックリストの項目を、予防の視点から現場にあった形で、88項目11グループに整理するとともに、重症度判定のための客観的な指標を導入する |
| (1) |
チェックリストの項目整理によって、記入時間および重症度判定時間が短縮された |
|
| (2) |
重症度自動計算式によって、客観的な重症度の判定が可能になった |
|
| (3) |
記入の手引きの作成によって、共通の認識でチェックリストを記入できるようになった |
|
|
| ※ |
こども家庭支援センターおよび保健所で使用。保育園などには県が作成した一般的なチェックリストを提示 |
|
チェックリストで把握した各リスク要因について実施した支援の効果を評価し、今後の支援方針や虐待対応の終結を効率的に検討する |
| (1) |
リスク要因の有無から支援の効果までが視覚的に把握できるようになり、支援が不足しているリスク要因を効率的に把握できるようになった |
|
| (2) |
ケースの現状把握や関係機関による共通理解のために必要な時間が短縮され、支援方針について検討する時間が確保できるようになった |
|
| (3) |
リスク要因の新旧を把握できることで、これまでの経過を含めた継続的な支援評価ができるようになった |
|
|
・
PDF:135KB