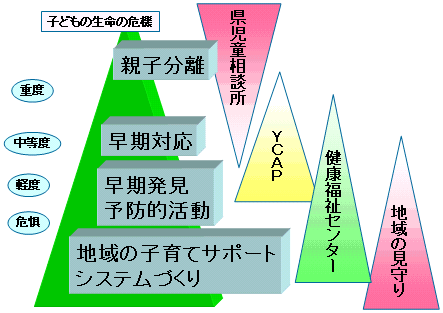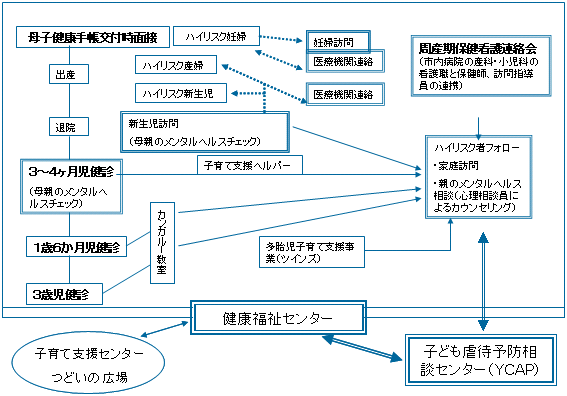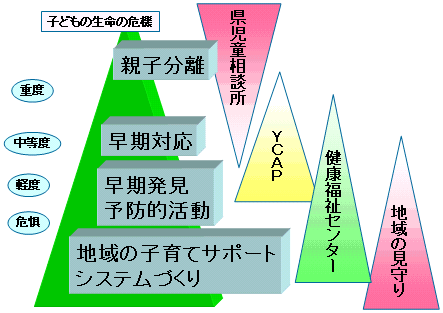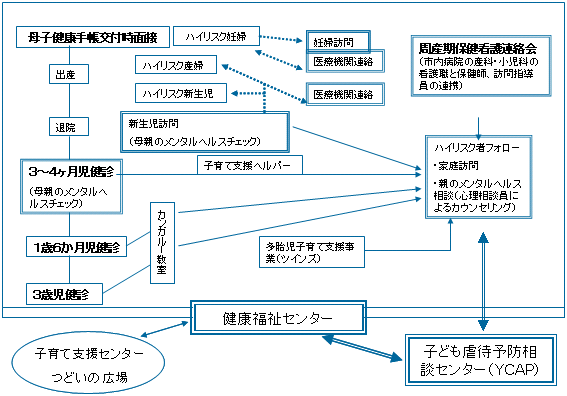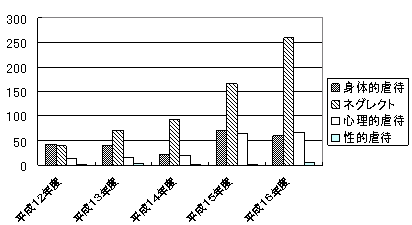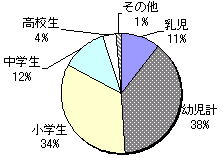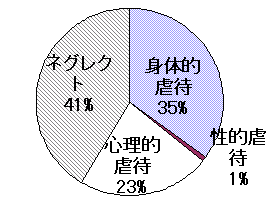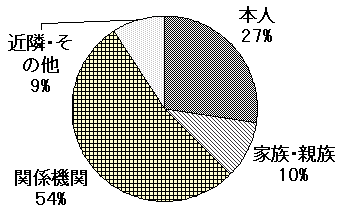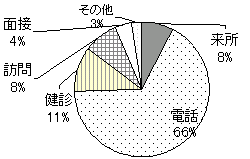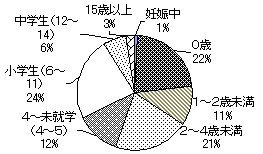(資料2)
横須賀市の児童虐待対策への取り組み
〜母子保健からの出発〜
横須賀市こども育成部子育て支援課 高橋
横須賀市の概況
人口 430,274人
出生数 3,661人 出生率 8.5 (H15.10.1)
中核市
保健師の活動形態 地区分担制+一部業務分担
母子保健事業に従事する保健師 35人 (H17.4.1)
(含 本庁・YCAP)
虐待関連家庭訪問(H16年度)
| 実313件 |
(乳幼児訪問の14.9%) |
| 延783件 |
(乳幼児訪問の24.2%) |
|
子育ち・子育て支援と母子保健
| ・ |
家庭訪問機能・・・アウトリーチ
|
| ・ |
|
| ・ |
|
| ・ |
他事業との連動 |
|
周産期保健看護連絡会
| 目的: |
地域と医療機関で周産期を中心とする情報の共有をはかり、要支援ケースに早期に必要な支援が届くようにする。 |
| 参加者: |
市内病院小児科・産科看護職
市保健師
訪問指導員 |
|
産後うつ早期発見のために
〜EPDS質問紙を用いて〜
| ・ |
母親のメンタルヘルスチェックのために新生児訪問、3〜4か月児健診にEPDS導入 |
↓
| 要支援者⇒ |
| ○ |
心理職によるカウンセリング
「親のメンタルヘルス相談」 |
| ○ |
個別相談 |
| ○ |
家庭訪問 |
|
YCAPの相談(精神科医・心理職) |
横須賀市の児童虐待防止事業取り組みの経緯
母子保健事業の中から
従来の母子保健事業での取り組みの限界
| ・ |
ケースの孤立 |
| ・ |
かかわる保健師の限界 |
| ・ |
児童相談所に頼ってばかりはいられない |
| ・ |
スーパーバイズ機能の必要 |
⇒H12年度「子ども虐待防止事業」立ち上げ
| ・ |
ネットワークミーティング(全体会・部会) |
| ・ |
ラベンダー(MCG) |
| ・ |
従事者研修 |
| ・ |
スーパーバイザーの予算化 |
|
児童虐待防止事業の看板を上げることによる変化
| ○ |
相談件数の増加 |
| ○ |
緊急対応のための体制作りの必要 |
| ○ |
乳児への対応策の必要 |
レスパイトのための施策
| → |
H14年4月
子ども虐待予防相談センター
(YCAP yokosuka child abuse pribention)設立 |
|
児童相談所・YCAP・健康福祉センターの役割分担図
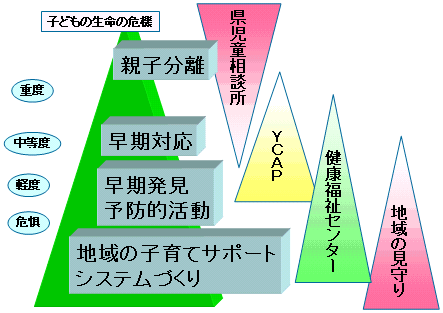 YCAPの事業内容
YCAPの事業内容
| 一般相談 |
電話・面接による相談
保育士・保健師・心理相談員が対応 |
| 心理相談 |
心理相談員が対応(要予約) |
| メンタルヘルス相談 |
精神科医師が対応(要予約) |
| ラベンダー |
虐待をしているまたは危惧される母親を対象としたグループミーティング |
ネットワーク
ミーティング |
情報の共有と連携の強化を目的。各機関の所属長で構成する全体会、担当者で構成する部会からなる。 |
| 緊急一時保育 |
虐待の重症化を予防するため、日中親子分離をし、保育園で一時保育をする。(原則6日間)利用者負担なし |
| 緊急一時入院 |
虐待の重症化を予防するため、昼夜親子分離をし、子どもを入院させます。(原則6日間)利用者負担なし |
| 啓発活動 |
子ども虐待を予防するための研修会や講演会を実施 |
|
啓発活動
対象
民生委員・主任児童委員
幼稚園・保育園職員
学校職員
医療機関職員
行政職員 |
等 |
場所
学校・医療機関 等 |
|
現行の母子保健事業と子ども虐待防止事業関連図
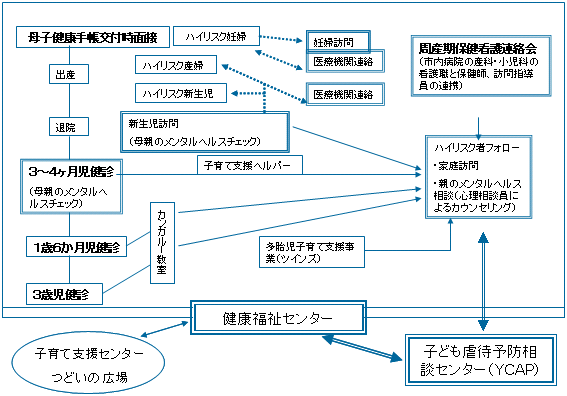
他機関との連携
| ○ |
|
保育園・幼稚園へのサポート
YCAP職員(医師・保健師・心理職)による相談助言 |
| ○ |
|
主任児童委員へのサポート
地区毎の定期的な連絡会、研修会の開催 |
| ○ |
|
医療機関との連携
早期の情報提供依頼と医療費に関するサポート |
|
今後の横須賀市の取り組み
| ・ |
児童家庭相談窓口の強化
相談体制の整備(相談員の配置と教育)
休日・夜間相談体制の整備(子育てホットライン H18年1月〜予定)
|
| ・ |
児童家庭相談ネットワーク会議の設置
虐待のネットワーク会議の再構築
|
| ・ |
児童相談所開設
H18年4月開設に向けて準備中 |
|
横須賀市の児童虐待の状況
神奈川県横須賀児童相談所虐待受理件数年次推移
| |
身体的虐待 |
ネグレクト |
心理的虐待 |
性的虐待 |
計 |
| 平成12年度 |
43 |
39 |
13 |
1 |
96 |
| 平成13年度 |
41 |
72 |
15 |
3 |
131 |
| 平成14年度 |
23 |
93 |
19 |
1 |
136 |
| 平成15年度 |
71 |
166 |
64 |
1 |
302 |
| 平成16年度 |
60 |
259 |
66 |
5 |
390 |
|
神奈川県横須賀児童相談所虐待受理件数年次推移
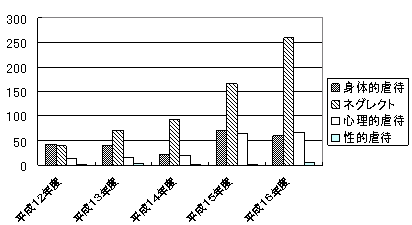 |
平成16年度年齢別件数
| |
乳児 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
6歳 |
幼児計 |
| 16年度 |
41 |
25 |
34 |
29 |
24 |
27 |
11 |
150 |
| |
小学生 |
中学生 |
高校生 |
その他 |
計 |
| 132 |
48 |
14 |
5 |
191 |
|
16年度年齢別件数
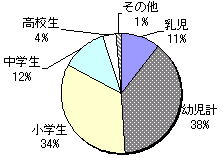 |
YCAPの活動状況
| |
H16年度 |
H15年度 |
H14年度 |
H13年度 |
H12年度 |
H11年度 |
H10年度 |
| 身体的虐待 |
335 |
245 |
160 |
101 |
124 |
67 |
50 |
| 性的虐待 |
9 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
| 心理的虐待 |
217 |
134 |
111 |
57 |
33 |
32 |
19 |
| ネグレクト |
396 |
290 |
196 |
134 |
132 |
80 |
76 |
| 計 |
957 |
670 |
469 |
294 |
292 |
182 |
147 |
|
H16年度虐待の種類
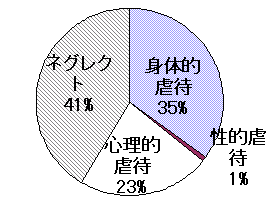 |
| |
H16年度 |
H15年度 |
| 本人 |
263 |
216 |
| 家族・親族 |
95 |
41 |
| 関係機関 |
510 |
329 |
| 近隣・その他 |
89 |
84 |
| 計 |
957 |
670 |
|
H16年度把握契機
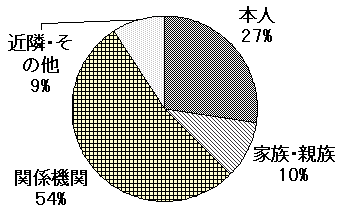 |
| |
H16年度 |
H15年度 |
| 来所 |
72 |
46 |
| 電話 |
640 |
424 |
| 健診 |
105 |
91 |
| 訪問 |
79 |
58 |
| 面接 |
37 |
19 |
| その他 |
24 |
32 |
| 計 |
957 |
670 |
|
H16年度把握契機
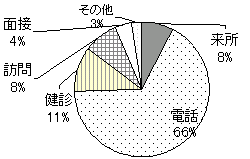 |
| |
H16
年度 |
H15
年度 |
H14
年度 |
H13
年度 |
H12
年度 |
H11
年度 |
H10
年度 |
| 妊娠中 |
8 |
3 |
6 |
6 |
21 |
13 |
11 |
| 0歳 |
212 |
156 |
98 |
74 |
80 |
70 |
62 |
| 1〜2歳未満 |
106 |
80 |
72 |
47 |
60 |
39 |
28 |
| 2〜4歳未満 |
203 |
151 |
110 |
80 |
77 |
38 |
30 |
| 4〜未就学(4〜5) |
119 |
92 |
62 |
50 |
24 |
7 |
6 |
| 小学生(6〜11) |
221 |
141 |
97 |
32 |
25 |
12 |
8 |
| 中学生(12〜14) |
61 |
37 |
19 |
5 |
5 |
3 |
2 |
| 15歳以上 |
25 |
10 |
5 |
|
|
|
|
| 計 |
957 |
670 |
469 |
294 |
292 |
182 |
147 |
|
H16年度把握時年齢
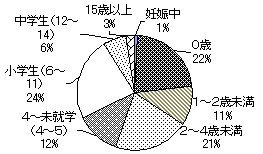 |
| |
平成14
年度 |
平成15
年度 |
平成16
年度 |
| 延べ件数 |
| 一般相談 |
440 |
945 |
1,169 |
| 心理相談 |
254 |
340 |
280 |
| メンタルヘルス相談 |
17 |
34 |
25 |
| 合計 |
711 |
1319 |
1,474 |
|
| 開始回数 |
24回 |
| 参加者実数 |
8人 |
| 参加者延数 |
30人 |
|
3年間のYCAPの活動を通して
見えてきたもの
<効果>
| ・ |
「虐待防止」という看板を掲げることによる効果・・・本人からの相談の増、関係機関からの情報の増 |
| ・ |
関係職員のサポート・・・精神科医師、心理相談員によるサポート |
| ・ |
虐待者本人のサポート・・・ラベンダー、個別相談 |
| ・ |
啓発活動の効果・・・ネグレクトの把握の増 |
|
今後の課題
| ○ |
学校教育との連携の強化 |
| ○ |
早期対応・重症化予防 |
| ○ |
児童相談所との役割の明確化と連携 |
| ○ |
非行等今まで経験のない分野への対応をどうするか |
| ○ |
職員のスキルアップ |
|