| 船員保険制度在り方検討会 | 資料3 |
| 平成17年6月1日 |
| ※ | 平成17年4月20日社会保障審議会医療保険部会提出資料 |
政府管掌健康保険の改革について
基本方針(※)において示されている改革の方向
|
| ○ | 政管健保については、事業運営の効率性等を考慮しつつ、財政運営は、基本的には、都道府県を単位としたものとする。 |
| ○ | 都道府県別の年齢構成や所得について調整を行った上で、保険料率の設定を行う仕組みとし、国庫補助の配分方法の見直しや、被保険者等の意見を反映した自主性・自律性のある保険運営が行われるような仕組みについて検討する。 |
| ○ | こうした取組を通じ、各都道府県単位で政管健保の健全な財政運営が確保され、被保険者の適切な負担の下で、地域の実情に応じた医療サービスが保障される姿を目指す。 |
| ○ | 引き続き、政管健保の組織形態等の在り方について検討する。 |
| 保険料率決定の過程(イメージ) |
| 保険運営に当たっての自主性・自律性、安定性、事務の効率性等の観点から、どのような保険料率の決定過程が望ましいか |
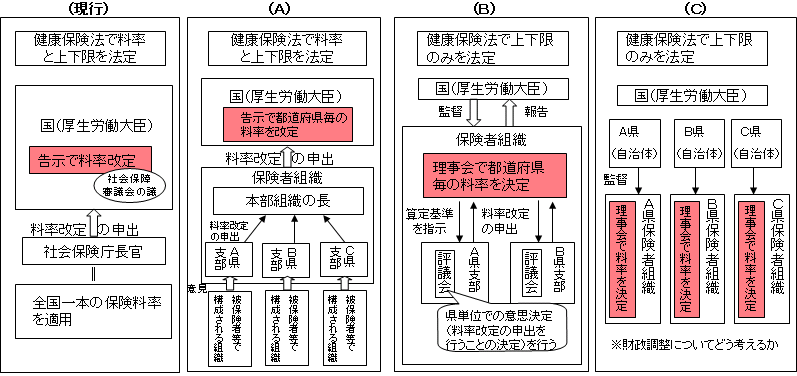
| 現行 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||
| 「自主性・自律性のある保険運営」 「安定的な財政運営」 「事務の効率性」等の観点からのメリット・デメリット |
|
|
|
|
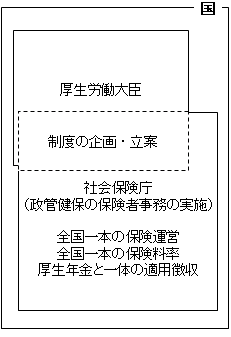 |
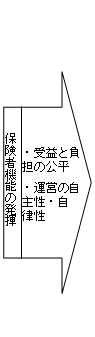 |
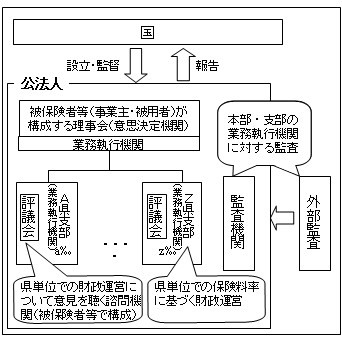 |
||||||||||||
|
|
| 政管保険者組織を国から分離する意義について |
| ○ | 年金と異なり、医療保険の保険者は、医療費適正化努力等の自らの保険者努力に対応して自ら保険料水準を定められるようにすることにより、一層効率的な保険運営が期待できること。 |
| ○ | 医療費適正化等の保険者努力や保険料水準の決定といった保険者機能が十分に発揮されるためには、事業運営は、被保険者等(事業主・被用者)の意見に基づく自主自律の仕組みとすることが必要であるが、国での事業運営ではそのような措置は困難であること。 |
| ○ | 保健事業等について各都道府県ごとの自律的な事業展開を可能とするためには、被保険者等(事業主・被用者)の合意の下で、マンパワーや財源等を柔軟に確保できるようにすることが適当であること。 |
| ○ | 制度設計主体である国が保険者でもあるため、保険料率の変更が制度改正と一体として議論されることが多く、保険者として柔軟な対応が困難となってきた面があったが、制度設計主体と保険者を分離することにより、保険者として柔軟な対応が可能となること。 |
| ※ | なお、現在、社会保険事務局で行っている保険医療機関の指定等の行政事務については、政管保険者組織ではなく、国に残すことが適当。 |
| ○ | 保険者の機能としては、主として「適用」「徴収」「保険給付」「保健事業」「保険料設定」が考えられ、現在の政管健保は、国が保険者としてこれらの機能を直接果たしている。 |
||||||
| ○ | 今後、保険者機能の発揮の観点から、国とは別の主体である公法人を保険者とし、「保険給付」「保健事業」「保険料設定」の事務について実施させる。 |
||||||
| ○ | ただし、「適用」及び「徴収」の事務については、
|
| ○ | 現在、厚生年金・政管健保の保険料の徴収は、それぞれの根拠法に基づき、国(社会保険庁)において一体的に行われており、いずれか一方のみの納付は認めていない。 【厚生年金保険法】
|
||||
| ○ | 今回の見直し後においても、政管健保の保険料の徴収事務は、機動的な公権力の行使の観点から、国が行うことが適当であり、また、事務の効率性の観点から、厚生年金と同一の主体が実施することが適当である。 したがって、政管健保と厚生年金の保険料徴収を国が一体的に実施する場合には、その取扱いは現在と変わらない。 |
|
|
|||||||
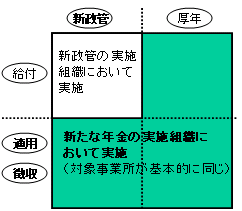 |
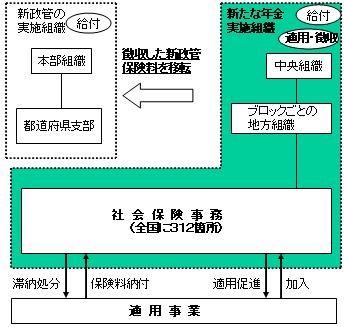 |
(参考)
|
| 社会保険庁の在り方に関する有識者会議 |
| 1 | 新組織の業務範囲について
|
||||||||||||||||||
| 2 | 新しい組織の基本コンセプト
|
||||||||||||||||||
| 3 | 基本コンセプトに基づく新組織の枠組み
|