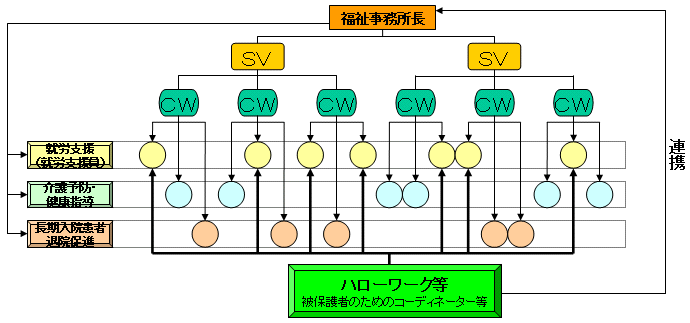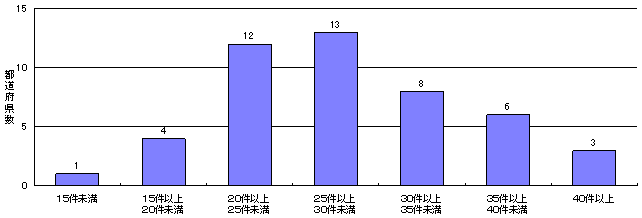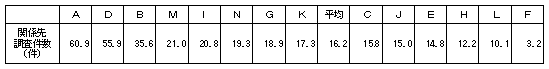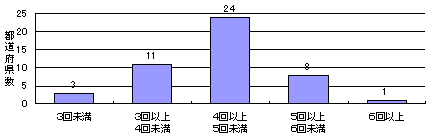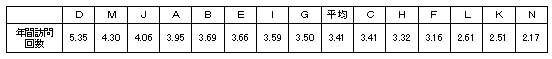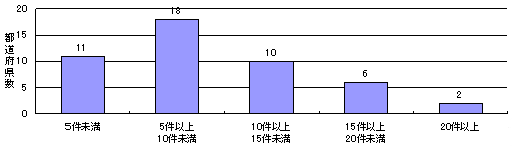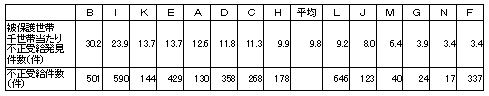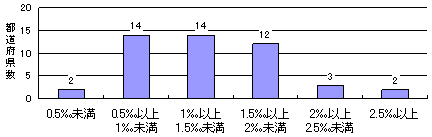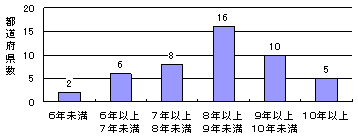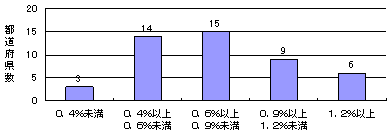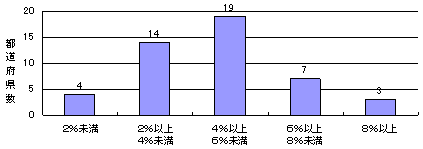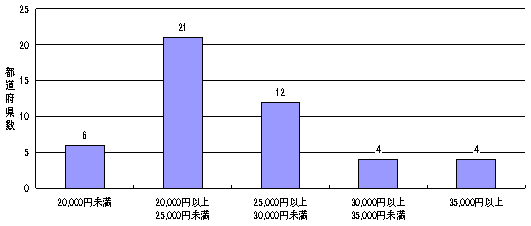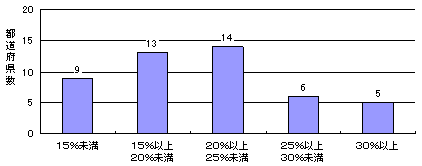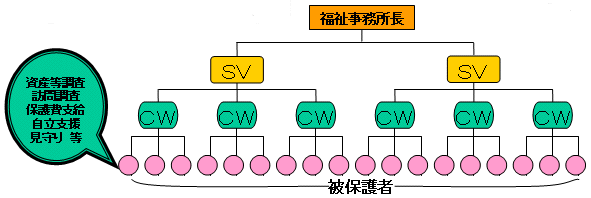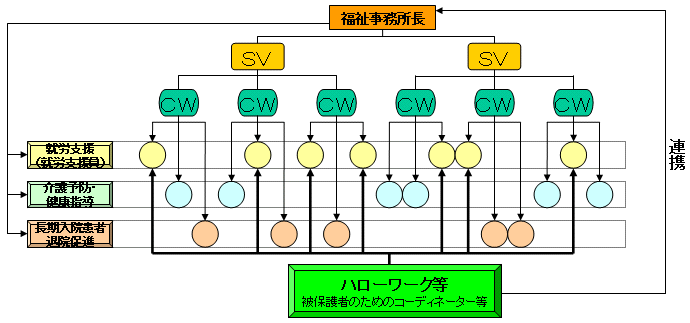生活保護制度運営における地域間の較差の状況
− 目次 −
| 1 |
生活保護業務及び実施体制
|
| 2 |
生活保護事務実施上の問題
|
| 3 |
福祉事務所における組織的対応
|
| |
生活保護業務の適正実施のためには、年金等の給付業務と異なり、受給者との密接で継続的な接触・関与が不可欠
| → |
継続的に被保護世帯の生活状況を把握するとともに、自立支援への取組を実施 |
|
|
|
|
┌
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└ |
・ |
申請者及びその世帯の
生活状況の聴取
|
| ・ |
資産・収入調査
の実施
→預貯金、保険、不動産の
保有状況を金融機関等
に調査
|
| ・ |
稼働能力
活用状況の把握
→求職活動の状況や
主治医や嘱託医からの
病状を把握
|
| ・ |
扶養能力調査
の実施
→戸籍等による
扶養義務者
の存否確認や
扶養能力調査を実施
|
| ・ |
他法他施策の活用が
可能かどうか検討し
関係他部局と連絡調整 |
|
|
┌
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└ |
・ |
保護費の算定及び
支給決定事務
|
| ・ |
定期的な調査の実施
→収入申告書、課税台帳、
扶養履行状況等の
調査・確認
|
| ・ |
訪問調査活動による
被保護世帯の生活状況
の把握
|
| ・ |
個々の被保護者の
実情に応じた
自立支援プログラム
への参加指導
※取組状況による
指導・指示を含む。
|
| ・ |
ハローワーク、
社会保険事務所、
医療機関等との
連絡調整 |
|
|
| (1) |
福祉事務所の設置
| ◇ |
都道府県及び市は、福祉事務所を設置しなければならない。(社会福祉法第14条第1項) |
| ◇ |
町村は、福祉事務所を設置することができる。(社会福祉法第14条第3項)
○設置数
全国 1,225カ所
| |
都道府県の設置する福祉事務所:328カ所
市の設置する福祉事務所:892カ所
町村の設置する福祉事務所:5カ所 |
|
|
(平成16年4月現在:厚生労働省社会・援護局調べ)
| (2) |
職員の配置
| ◇ |
福祉事務所には、所長、査察指導員(指導監督を行う所員)及び現業員(ケースワーカー)を置かなければならない。
(社会福祉法第15条第1項) |
| ◇ |
現業員の定数は、被保護世帯数80世帯につき1人(市町村)又は65世帯に1人(都道府県)を標準。
(社会福祉法第16条)
○実配置数
| (ア) |
査察指導員 全国で2,307人 |
| (イ) |
現業員(ケースワーカー) 全国で11,944人 |
|
|
(平成16年度生活保護法施行事務監査資料)
| |
| 地方分権一括法による生活保護法及び社会福祉事業法の改正により、地方自治体の裁量が拡大 |
|
| (1) |
生活保護法の改正(平成12年4月1日施行)
| ・ |
自立助長のための相談及び助言事務を自治事務として明確化 |
(相談及び助言)
| 第 |
二十七条の二 保護の実施機関は、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。 |
|
| ・ |
相談及び助言事務以外の事務(保護の決定・実施に関する事務)について法定受託事務として明確化 |
| ・ |
機関委任事務の廃止に伴い指揮監督に係る事務を廃止 |
(指揮及び監督機関)(職権の委任)
| 第 |
二十条 この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。 |
2 |
都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 |
|
|
| (2) |
社会福祉事業法(現在は社会福祉法)の改正(平成12年4月1日施行)
| ・ |
福祉事務所の現業員の配置数を「法定数」から「標準数」に見直し |
(所員の定数)
| 第 |
十五条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数以上でなければならないを標準として定めるものとする。
| 一 |
都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数 |
| 二 |
市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数 |
| 三 |
町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数 |
|
(現行は第十六条) |
|
| (1) |
現業員の充足状況 (平成16年度生活保護法施行事務監査資料)
現業員の配置数は全国の福祉事務所において標準数に比べ1,198人が不足。不足数は拡大する傾向。
標準数以上配置している地方自治体がある一方で、大きく不足している地方自治体もある。 |
|
| |
総数 |
現業員数が標準数を
満たしている福祉事務所 |
現業員数が標準数に
不足している福祉事務所 |
| 福祉事務所数 |
現業員数 |
標準数 |
事務所数 |
標準数を超える
人員の合計 |
事務所数 |
標準に不足する
人員の合計 |
| 平成14年度 |
1,198 |
10,847 |
10,725 |
947 |
980 |
251 |
858 |
| 平成15年度 |
1,212 |
11,408 |
11,534 |
943 |
963 |
269 |
1,089 |
| 平成16年度 |
1,225 |
11,944 |
12,210 |
944 |
932 |
281 |
1,198 |
| (2) |
現業員及び査察指導員の業務経験の状況 (平成16年度生活保護法施行事務監査資料)
| 現業員の指導監督を行う査察指導員の4分の1弱が現業員を経験したことのない者である等、業務経験が十分ではない者が配置されている。 |
|
| |
現業員 |
査察指導員 |
| 総数 |
現業員経験1年
未満の者数 |
構成比 |
総数 |
現業員
未経験者数 |
構成比 |
| 平成14年度 |
10,847 |
2,577 |
23.8 |
2,220 |
615 |
27.7 |
| 平成15年度 |
11,408 |
2,840 |
24.9 |
2,269 |
593 |
26.1 |
| 平成16年度 |
11,944 |
2,846 |
23.8 |
2,307 |
550 |
23.8 |
| (3) |
現業員業務の問題点 (生活保護担当職員の資質向上検討委員会(※)提言 平成15年3月) |
| |
・ |
典型的な個人ワーク(個人で問題を抱えやすく個人で悩みやすい) |
| ・ |
被保護者等の生活問題の複雑化(対応が難しく、仕事に対する達成感が得られない) |
| ・ |
生活保護業務に対する過小評価(自分が誇れる仕事をしていないとの感覚) |
| ・ |
現業員業務の仕事範囲が不明確(被保護者等に関する雑多な相談が持ち込まれる) |
| |
| ※ |
生活保護担当職員の資質向上検討委員会
社会福祉の研究者や自治体の生活保護担当者により構成。
平成14年11月から平成15年3月に開催。 |
|
|
| (4) |
地方自治体の実施体制(現業員の配置数等)と保護率の伸びの関係
指定都市等(注)における現業員充足率の平均は、91.0%。
平成9年度と比較した平成15年度の保護率は1.52倍。 |
|
指定都市等における保護率の増減と現業員充足率の関係
| |
保護率増減 |
保護率
(‰) |
現業員充足率
(%) |
失業率増減 |
| A |
0.94 |
13.0 |
116.0 |
1.58 |
| B |
1.20 |
17.6 |
94.8 |
1.58 |
| C |
1.22 |
24.2 |
100.7 |
1.50 |
| D |
1.45 |
25.0 |
106.4 |
1.76 |
| 平均 |
1.52 |
16.4 |
91.0 |
- |
| E |
1.61 |
12.2 |
94.0 |
1.30 |
| F |
1.63 |
15.9 |
101.6 |
1.22 |
| G |
1.64 |
9.0 |
93.2 |
1.91 |
| H |
1.65 |
10.9 |
82.9 |
1.38 |
| I |
1.65 |
24.7 |
92.0 |
1.71 |
| J |
1.67 |
16.7 |
112.8 |
1.30 |
| K |
1.75 |
13.6 |
80.6 |
1.64 |
| L |
1.82 |
35.4 |
57.6 |
1.62 |
| M |
2.09 |
10.0 |
75.7 |
1.43 |
| ※ |
保護率増減=平成15年度保護率/平成9年度保護率 |
| ※ |
保護率(‰)=平成15年度保護率 |
| ※ |
現業員充足率(%)=平成15年度現業員の法定標準数(被保護世帯数80世帯につき1人)に対する現業員数の割合 |
| ※ |
失業率増減=平成15年度失業率/平成9年度失業率
(失業率は、都道府県の数値。このため、同一の県に属するA及びB並びにE及びJの市については、失業率増減の数値が同値。) |
| |
| (注) |
指定都市等とは、
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都23区、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市及び福岡市の14市・地域をいう。以下同じ。
また、アルファベットは各頁共通。
ただし、この頁及び14頁については、平成15年4月に指定都市に移行したさいたま市を除く。 |
|
|
(福祉行政報告例・労働力調査 平成15年度監査実施結果報告)
| (1) |
関係先調査の状況
| 保護の申請に伴う関係先に対する資産・収入調査(※)は、全国平均で申請1件当たり23.1件。 |
|
| |
申請1件当たりの関係先に対する資産・収入調査件数(注)(平成15年度) |
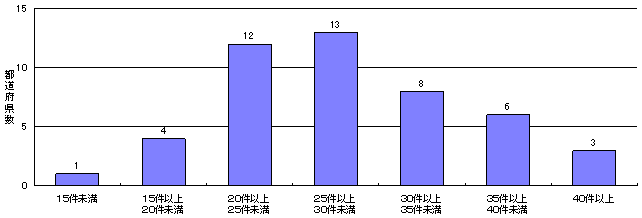
申請1件あたり調査件数
| 全国平均 |
23.1 |
件/件 |
| 最高 |
43.4 |
件/件 |
| 最低 |
6.1 |
件/件 |
|
| |
| ※ |
関係先に対する資産・収入調査
| ・ |
年金→社会保険事務所 |
| ・ |
預貯金→金融機関 |
| ・ |
生命保険→生命保険会社 |
| ・ |
収入・資産→税務部局、雇用先 等 |
|
|
| 注: |
福祉事務所((ア)においては都道府県内の福祉事務所(都道府県及び市町村が設置する福祉事務所をいう)、(イ)においては指定都市内の福祉事務所。以下同じ。)における調査件数の合計をそれぞれの申請件数の合計で除した平均。 |
|
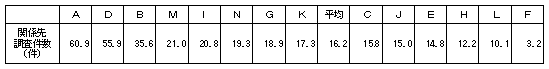
(平成15年度監査実施結果報告)
| (2) |
訪問調査活動の状況
| 被保護世帯の状況把握のために行う訪問調査活動は、1世帯当たり平均3.86回/年。 |
|
| |
被保護世帯1世帯当たりの年間訪問調査活動回数(注)(平成15年度) |
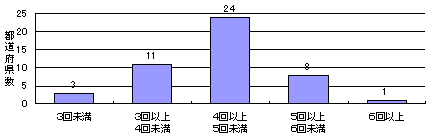
1世帯当たり年間訪問調査回数
| 全国平均 |
3.86 |
回/年 |
| 最高 |
6.91 |
回/年 |
| 最低 |
2.32 |
回/年 |
|
| |
注: |
福祉事務所における訪問調査回数の合計を被保護世帯数の合計で除した平均。 |
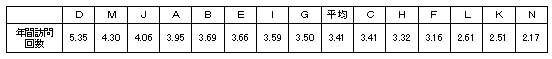
(平成15年度監査実施結果報告)
| (3) |
不正受給の状況
| 不正受給として地方自治体が保護費の返還を求めた件数は、被保護世帯千世帯当たり全国平均年間9.8件。 |
|
| |
被保護世帯千世帯当たり年間不正受給発見件数(※)(平成15年度) |
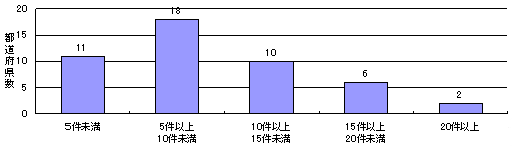
被保護世帯千世帯当たり不正受給発見件数
| 全国平均 |
9.8 |
件/千世帯・年 |
| 最高 |
26.5 |
件/千世帯・年 |
| 最低 |
0.8 |
件/千世帯・年 |
|
| |
| ※ |
不正受給発見件数
福祉事務所が不正受給を発見し、生活保護法第78条の規定により、不正受給をした者から不正受給による保護費を徴収することとした件数 |
|
|
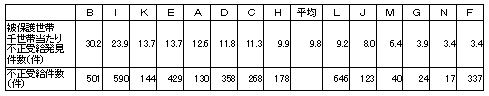
(平成15年度監査実施結果報告)
| (4) |
稼働による生活保護廃止の状況
| 1カ月間に「稼働収入増」を理由として保護を廃止された世帯数は、被保護世帯千世帯当たり全国平均で1.4世帯 |
|
| |
1カ月間の「稼働収入増」を理由とする保護廃止世帯数(平成15年9月)/被保護世帯数(平成15年度)の割合
| ※ |
被保護世帯に占める1カ月間の「稼働収入増」を理由とする保護廃止世帯数の割合を千分率で表記 |
|
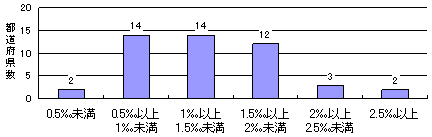
「稼働収入増」を理由とする保護廃止割合(千分率)
| 全国平均 |
1.4 |
世帯/千世帯・月 |
| 最高 |
2.8 |
世帯/千世帯・月 |
| 最低 |
0.1 |
世帯/千世帯・月 |
|
| |
E |
M |
K |
D |
G |
H |
J |
平均 |
F |
B |
N |
I |
L |
C |
A |
「稼働収入増」による
保護廃止割合
(千分率) |
3.8 |
2.6 |
2.5 |
2.5 |
1.8 |
1.7 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
1.3 |
1.0 |
1.0 |
0.8 |
0.5 |
0.2 |
「稼働収入増」による
廃止世帯数 |
118 |
16 |
26 |
75 |
11 |
30 |
25 |
41 |
152 |
22 |
5 |
24 |
58 |
12 |
2 |
平成15年度
年度平均世帯数 |
31,286 |
6,236 |
10,494 |
30,317 |
6,170 |
17,980 |
15,439 |
26,287 |
99,734 |
16,563 |
4,964 |
24,704 |
70,210 |
23,630 |
10,291 |
| ※ |
「稼働収入増」による廃止世帯数は、平成15年9月の1カ月当たりの数 |
|
(平成15年度福祉行政報告例)
| (5) |
生活保護の受給期間の状況
| 現に生活保護を受けている世帯の平成16年7月における平均受給期間は、全国平均 7.7年 |
|
| |
現に生活保護を受けている世帯の平成16年7月における平均受給期間 |
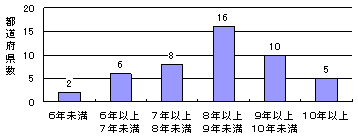
平均受給期間
| 全国平均 |
7.7 |
年 |
| 最高 |
11.0 |
年 |
| 最低 |
5.8 |
年 |
|
| |
M |
L |
H |
K |
E |
J |
N |
F |
平均 |
G |
D |
I |
B |
C |
A |
| 平均受給期間(年) |
5.4 |
5.7 |
5.8 |
5.9 |
5.9 |
6.2 |
6.4 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
7.8 |
7.9 |
8.5 |
8.9 |
12.3 |
(平成16年被保護者全国一斉調査)
| (6) |
医療扶助のレセプト点検の状況
| 医療扶助のレセプト点検による過誤調整率(※)は、全国平均0.75% |
|
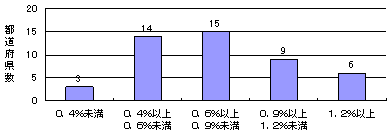
レセプト点検による過誤調整率
| 全国平均 |
0.75 |
% |
| 最高 |
3.38 |
% |
| 最低 |
0.33 |
% |
|
| |
| ※ |
過誤調整率
レセプト点検で発見した医療扶助請求の減額(過誤調整額)を社会保険診療報酬支払基金からの請求額で除した率 |
|
|
| |
I |
L |
F |
A |
平均 |
J |
K |
B |
H |
M |
C |
E |
D |
G |
N |
| 過誤調整率 |
0.88 |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.61 |
0.54 |
0.54 |
0.47 |
0.42 |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
0.32 |
0.23 |
0.17 |
(厚生労働省社会・援護局保護課調べ)
| (7) |
医療扶助に関する長期入院患者の居宅又は施設への移行の状況
| 実態把握及び退院条件の整備により、長期入院患者のうち居宅又は施設に移行した者の割合(※)は、
全国平均 4.6% |
|
| |
長期入院患者のうち居宅又は施設に移行した者の割合(平成15年度) |
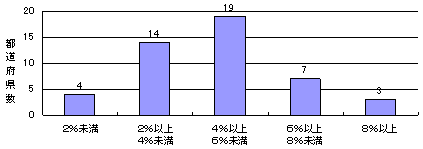
長期入院患者のうち居宅又は施設に移行した者の割合
| 全国平均 |
4.6 |
% |
| 最高 |
9.2 |
% |
| 最低 |
1.2 |
% |
|
| |
| ※ |
180日以上長期に入院している患者(長期入院患者)のうち居宅又は施設へ移行した者の数を、長期入院患者数で除した割合 |
|
長期入院患者の居宅又は施設への移行の手続
| 1 |
180日を超えて入院している者全員について、嘱託医がレセプト及び医療扶助要否意見書に基づき主治医の意見を聴く必要があるものを分類 |
| 2 |
現業員が主治医と連絡をとり、入院の継続の必要がないことが明らかなものを確認・調整 |
| 3 |
2について、現業員が当該患者及び家族を訪問し、実態把握(退院に必要な措置の確認等)した上で、退院阻害要因の解消を図り、実態に即した方法で適切な退院指導 |
|
|
| 区分 |
I |
M |
K |
E |
D |
J |
F |
平均 |
B |
C |
H |
G |
L |
A |
N |
| 移行患者割合(%) (4)/(1) |
14.0 |
8.4 |
8.2 |
7.3 |
6.9 |
6.2 |
5.4 |
5.1 |
4.3 |
4.2 |
3.6 |
2.7 |
2.0 |
1.5 |
0.4 |
|
|
938 |
333 |
513 |
1,466 |
1,640 |
953 |
5,593 |
1,446 |
1,464 |
1,009 |
1,314 |
226 |
3,503 |
1,047 |
241 |
| (2) |
(1)のうち主治医と確認・調整を行ったもの |
|
724 |
301 |
384 |
1,163 |
754 |
680 |
2,343 |
967 |
1,276 |
770 |
469 |
122 |
3,503 |
1,047 |
6 |
| (3) |
(2)の結果医療扶助による入院の必要がないとされたもの |
|
140 |
36 |
67 |
137 |
207 |
128 |
522 |
154 |
143 |
55 |
171 |
6 |
484 |
52 |
1 |
| (3)のうち |
居宅保護 |
56 |
16 |
27 |
43 |
32 |
31 |
100 |
30 |
31 |
27 |
14 |
1 |
33 |
1 |
1 |
| 施設入所 |
75 |
12 |
15 |
64 |
81 |
28 |
204 |
44 |
32 |
15 |
33 |
5 |
38 |
15 |
0 |
| (4) 計 |
131 |
28 |
42 |
107 |
113 |
59 |
304 |
74 |
63 |
42 |
47 |
6 |
71 |
16 |
1 |
(厚生労働省社会・援護局保護課調べ)
| (8) |
住宅扶助の状況
| 全被保護世帯の住宅扶助算定額の平均は、3万1,677円 |
|
| |
被保護世帯の平均住宅扶助算定額(注)(平成16年) |
| (ア) |
都道府県単位の平均住宅扶助算定額の分布状況 |
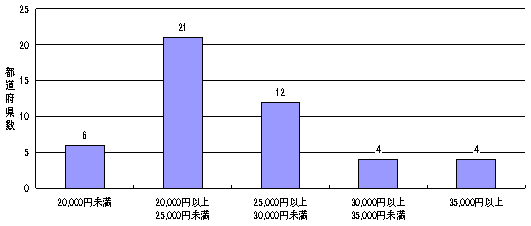
住宅扶助受給世帯1世帯当たりの住宅扶助算定額
| 全国平均 |
31,677 |
円 |
| 最高 |
44,437 |
円 |
| 最低 |
18,149 |
円 |
|
| |
| ※ |
平均住宅扶助算定額
住宅扶助として最低生活費に算定している額の総額を住宅扶助を受けている世帯数で除した平均 |
|
| 住宅扶助の仕組み
家賃の額が級地ごとに設定される一般基準額を超える場合は、厚生労働大臣が都道府県・指定都市・中核市ごとに定める特別基準額(例 東京都(1級地)単身世帯:53,700円)の範囲内で、家賃の実費を支給 |
|
| |
A |
H |
G |
B |
I |
D |
K |
C |
L |
M |
平均 |
F |
N |
J |
E |
住宅扶助
受給世帯
1世帯当たり
住宅扶助
算定額
(円) |
23,297 |
26,744 |
29,576 |
30,059 |
31,818 |
31,985 |
32,854 |
35,144 |
35,294 |
36,939 |
37,342 |
43,052 |
43,198 |
46,215 |
46,750 |
(平成16年被保護者全国一斉調査)
| (9) |
住宅扶助と公営住宅の関係
| 全被保護世帯のうち、公営住宅に居住している世帯は、全国平均21.6% |
|
| |
全被保護世帯のうち、公営住宅に居住している世帯の割合(平成14年) |
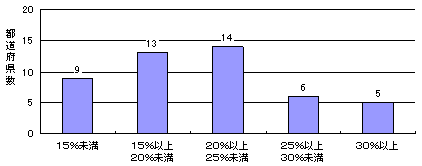
公営住宅居住割合
| 全国平均 |
21.6 |
% |
| 最高 |
41.0 |
% |
| 最低 |
10.7 |
% |
|
| |
I |
B |
H |
A |
C |
G |
K |
平均 |
F |
M |
E |
D |
L |
J |
| 公営住宅居住割合 |
53.3 |
27.7 |
25.5 |
24.0 |
23.8 |
23.7 |
21.1 |
20.8 |
18.6 |
18.4 |
16.1 |
15.3 |
13.6 |
13.6 |
| 被保護世帯数 |
22,250 |
15,320 |
14,400 |
9,780 |
20,820 |
5,410 |
8,850 |
24,387 |
89,550 |
4,990 |
26,970 |
27,600 |
57,770 |
13,320 |
| 公営住宅居住被保護世帯 |
11,860 |
4,240 |
3,670 |
2,350 |
4,960 |
1,280 |
1,870 |
5,075 |
16,620 |
920 |
4,340 |
4,210 |
7,840 |
1,810 |
(平成14年被保護者全国一斉調査)
| (3) |
会計検査院実地検査指摘、厚生労働省監査指摘等の状況 |
| |
| 会計検査院からは、就労収入や年金等の収入の無申告や過少申告等が指摘 |
|
| (1) |
会計検査院実地検査に基づき国会報告された事例(平成12〜16年) |
| |
|
平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
合計 |
| 検査対象 |
自治体数 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
120 |
| 事業主体(福祉事務所)数 |
110 |
130 |
130 |
130 |
112 |
612 |
| 指摘件数 |
自治体数 |
8 |
9 |
10 |
8 |
7 |
42 |
| 事業主体(福祉事務所)数 |
9 |
11 |
13 |
12 |
8 |
53 |
| ケース数 |
38 |
29 |
44 |
21 |
10 |
142 |
| 指摘件数 |
就労収入の無申告や過少申告 |
25 |
22 |
31 |
14 |
7 |
99 |
| 各種年金・恩給による収入の無申告や過少収入認定 |
9 |
5 |
7 |
2 |
1 |
24 |
| 就労収入及び各種年金等による収入の無申告 |
2 |
1 |
3 |
1 |
- |
7 |
| 年金・恩給担保借入金の収入及び借入完済後の年金収入の無申告 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
8 |
| 相続した土地の処分による収入の無申告 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
| 社会保険適用中の単独券による医療扶助給付 |
- |
- |
1 |
2 |
- |
3 |
| (2) |
厚生労働省指導監査において指摘した主な実施上の問題点(平成11〜15年度)
−監査を実施した福祉事務所数 364事務所− (厚生労働省監査結果) |
| (ア) |
病状把握及び就労指導の徹底 252福祉事務所に対して指摘
被保護者の病状を十分把握できていないこと等により、適切な就労指導を行うことができていない |
| (イ) |
扶養能力調査の適正な実施 247福祉事務所に対して指摘
母子世帯における離婚した前夫や高齢者世帯における子が被保護世帯に援助できるかという扶養可能性が十分調査できていない |
| (ウ) |
訪問調査活動の適正な実施 246福祉事務所に対して指摘
適切な訪問調査が行われていないことにより、被保護世帯の現状の把握が不十分なため、生活保護費の算定や自立・就労支援の実施が適切に行われていない |
| (エ) |
組織的運営管理の充実強化 161福祉事務所に対して指摘
処遇が困難な被保護世帯に対するケース診断会議の活用や査察指導員の適切な助言等、組織的な運営管理が不十分 |
| |
| 被保護世帯が抱える問題の複雑化に対応した専門職(就労支援員等)を配置している地方自治体は、76団体。 |
| ← |
生活保護費補助金(平成17年度よりセーフティネット支援対策等事業費補助金)により地方自治体の取組を支援 |
|
| |
○ |
生活保護費補助金による就労支援員等の配置状況(平成16年度) |
| |
| |
配置している
地方自治体数 |
配置数 |
| 就労支援員数 |
71 |
123 |
| 自立生活相談員数 |
6 |
10 |
| 合計 |
76(※) |
133 |
|
|
| ○ |
就労支援員
「職業相談の経験者、キャリアカウンセラー経験者等を就労支援員として雇用し、就労意欲の喚起、履歴書の書き方や面接の受け方の指導、公共職業安定所への同行訪問を行う」事業の実施に対して補助金を交付した地方自治体数及びその配置数。 |
|
| ○ |
自立生活相談員
「自治体(福祉事務所)に自立生活相談員を配置し、社会的な自立が困難となっている被保護世帯(母子、元ホームレス)に対し、実生活に即した適切な助言、相談及び指導・援助を行うことにより自立阻害要因の解消を支援する」事業の実施に対して補助金を交付した地方自治体数及びその配置数。 |
|
|
| |
○ |
就労支援員の配置の効果(厚生労働省社会・援護局保護課において就労促進事業を実施している地方自治体より聴取)
| a |
援助の専門性の確保 |
: |
ハローワークや都道府県労働局との連携のもと、豊富な知識及び経験により的確な就労支援を図ることが可能。 |
| b |
対象者からの信頼確保 |
: |
専門的知識をもつ相談員による指導が継続的に受けられることにより、被保護者等が福祉事務所に信頼感を持ち、指導がより効果的に。 |
| c |
現業員の負担軽減 |
: |
面接・連絡に要する時間及び精神的負担が軽減。 |
| d |
現業員の志気の向上 |
: |
専門的知識をもつ相談員が加わることにより、現業員の志気が向上。 |
| e |
面接相談時の就労支援 |
: |
生活保護の面接相談時の就労支援により、就労が決定するケースも少なくない。 |
|
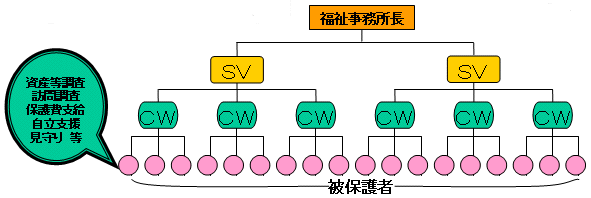
| |
| 組織的対応〜ハローワーク等関係機関や専門家等を活用した組織的・横断的対応 |
|