| 資料2 |
| 水産物の実態について |
2005年5月25日
JF全漁連(全国漁業協同組合連合会)
| 1. | 生産の概要 |
| (1) | 漁業種類 |
|
┬ | 漁船漁業:各種釣り、底びき網、刺し網、はえ縄、定置網 など | |
| ├ | 採貝・採藻 | ||
| └ | 養殖業:魚類(給餌)、貝類・海藻類(無給餌) |
| ◇ | 主に10トン以下の漁船を使用する漁業で、漁業種類も獲れる魚種も多種多様。大半が日帰りの操業。養殖業や定置網なども沿岸漁業に含まれる。 |
|
─ | 大中型まき網、沖合底びき網、沖合いか釣、近海カツオ、近海マグロ、サンマ棒受網 など |
| ◇ | 主として日本近海で操業(一部はロシア水域でも)。20〜200トン程度の漁船を使用。漁業種類によって数日から1ヶ月程度(操業海域を変えながら)操業。 |
|
─ | 遠洋マグロ、遠洋カツオ、大型いか釣、遠洋トロール、海外まき網 など |
| ◇ | 主に海外の200海里水域内、あるいは原則として外国の制約を受けない公海を漁場とする。 |
|
─ | 漁業、養殖業 |
| ◇ | 河川、湖沼等の内水面で行われる漁業。 |
| * | これらの漁業で漁獲・生産され、一般的に食用等に利用される種類は200〜300種類といわれている。(日本の近海では魚類だけでも約3,900種類が確認されている。) |
| 2. | 生産量・輸入量 |
| (1) | 国内生産量 |
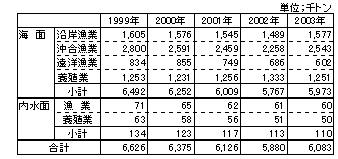
| (2) | 主な魚種の生産量(海面漁業) |
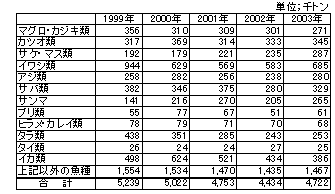
| (3) | 主な魚種の生産量(養殖業) |
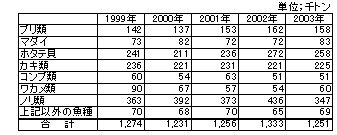
| (4) | 主な魚種の輸入量 |
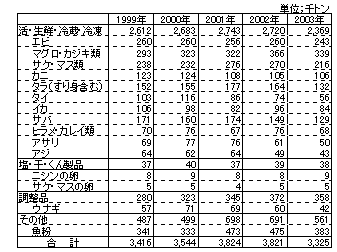
| (5) | 主な輸入先別輸入量 |
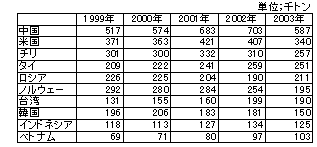
| 資料: | 農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」 財務省「貿易統計」 |
| 3. | 水産物の特性(生態等) |
| (1) | 移動範囲の広い魚類
|
| (2) | 移動範囲の狭い魚類
|
| (3) | 定着性のもの
|
| 4. | 魚介類の名称 |
ガイドラインでは、原則として標準和名を表示することとしているが、地方名や成長過程での名称も表示できることとし、併せて外国から輸入される水産物の名称についても整理した。
| (1) | 標準和名とその他の一般的名称(例) |
| 標準和名 | その他の一般的名称 | ||
| クロマグロ | ホンマグロ | ||
| シログチ | イシモチ | ||
| ババガレイ | ナメタガレイ | ||
| ウバガイ | ホッキガイ |
| (2) | 地方名(例) |
| 標準和名 | 地方名 | |||
| アナゴ | ハモ | (北海道・東北) | ||
| スルメイカ | マイカ | (北海道・三陸) | ||
| キダイ | ハナダイ | (神奈川) | ||
| (3) | 成長段階や季節に応じた名称(例) |
| 標準和名 | 成長名 | ||
| ブリ | ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ(東京) | ||
| ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ(大阪) |
|||
| 季節名 | |||
| シロザケ | アキアジ(秋頃の産卵回遊) | ||
| トキシラズ(春から初夏にかけて沿岸に回遊) |
| (4) | 輸入物(例) |
| 標準和名又はその他の名称 | 使用しない名称 | ||
| マジェランアイナメ、メロ など | ギンムツ、ムツ | ||
| キングクリップ | アマダイ | ||
| ナイルパーチ | スズキ、シロスズキ |
| 5. | つくり育てる漁業 |
| (1) | 養殖業 養殖業は大きく分けて、餌を与える魚類養殖と、無給餌の貝・海藻類養殖に分けられる。
|
また、その種の特性に応じて、育成段階等に応じて、養殖場所を移す場合がある。
| (1) | ブリ
|
| (2) | ギンザケ
|
| (3) | ホタテ
|
| (4) | カキ
|
| (5) | ワカメ
|
| (2) | 栽培漁業(種苗放流)
|