| ○ | 試用期間
|
| ○ | 新規学卒者に採用内定時に知らせる労働条件の項目及び方法 |
| 新規学卒者に採用内定時に知らせる労働条件の項目については、就業場所、従事する業務、労働時間及び賃金を知らせる企業がいずれも約9割となっている。一方、内定取消事由を知らせている企業は34.2%となっている。 その際、労働条件の項目を知らせる方法としては、その他口頭で説明が67.8%と最も多く、次いで労働条件を書いた説明書の配布が41.2%、就業規則の配布が26.8%となっている。 |
| ・ | 採用内定時に知らせる労働条件の項目(複数回答 単位:%) |
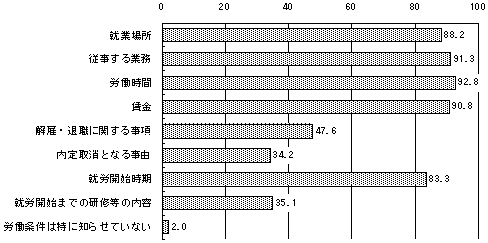
(無回答を除く集計) |
| ・ | 労働条件の項目を知らせる方法(複数回答 単位:%) |
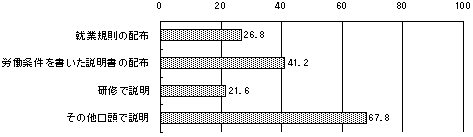
(無回答を除く集計) |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 新規学卒者に就労開始時に知らせる労働条件の項目及び方法 |
| 新規学卒者に就労開始時に知らせる労働条件の項目については、就業場所、従事する業務、労働時間及び賃金を知らせる企業がいずれも9割を超えている。また、解雇・退職に関する事項を知らせている企業は71.3%である。 その際、労働条件の項目を知らせる方法については、その他口頭で説明が55.5%と最も多く、次いで就業規則の配布が49.0%となっている。 |
| ・ | 就労開始時に知らせる労働条件の項目(複数回答 単位:%) |
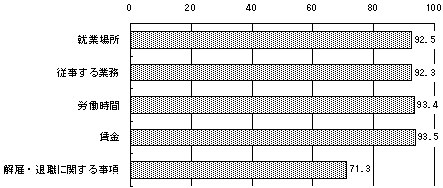
(無回答を除く集計) |
| ・ | 労働条件の項目を知らせる方法(複数回答 単位:%) |
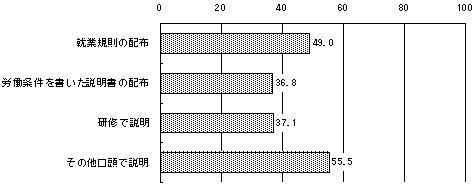
(無回答を除く集計) |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 新規学卒者の採用に際して労働条件を通知する時期 |
| 新規学卒者の採用に際して、就業場所、従事する業務、労働時間及び賃金については、内定時及び就業開始時のいずれにおいても新規学卒者に知らせる企業が8割を超えている。 解雇・退職に関する事項については、内定時及び就業開始時のいずれにおいても新規学卒者に知らせる企業は38.9%となっている。 |
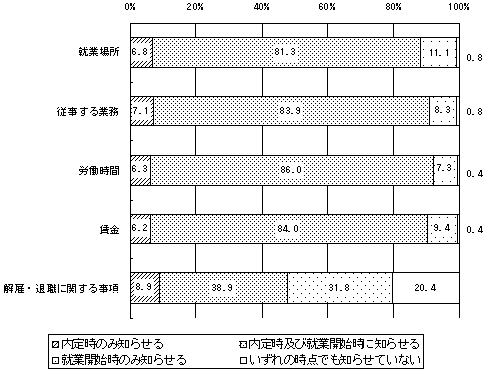
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 中途採用者に採用内定時に知らせる労働条件の項目及び方法 |
| 中途採用者に採用内定時に知らせる労働条件の項目については、就業場所、従事する業務、労働時間及び賃金を知らせる企業がいずれも9割を超えている。一方、内定取消事由を知らせている企業は25.5%となっている。 その際、労働条件の項目を知らせる方法としては、その他口頭で説明が72.8%と最も多く、次いで労働条件を書いた説明書の配布が37.5%、就業規則の配布が23.7%となっている。 |
| ・ | 採用内定時に知らせる労働条件の項目(複数回答 単位:%) |
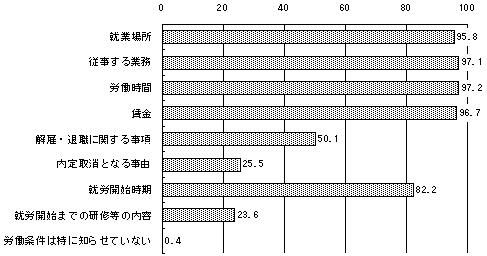
(無回答を除く集計) |
| ・ | 労働条件の項目を知らせる方法(複数回答 単位:%) |
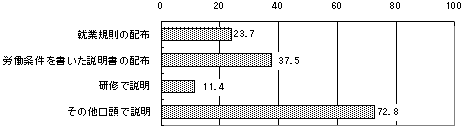
(無回答を除く集計) |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 中途採用者に就労開始時に知らせる労働条件の項目及び方法 |
| 中途採用者に就労開始時に知らせる労働条件の項目については、就業場所、従事する業務、労働時間及び賃金を知らせる企業がいずれも約9割となっている。また、解雇・退職に関する事項を知らせている企業は62.0%である。 その際、労働条件の項目を知らせる方法については、その他口頭で説明が65.3%であり、就業規則の配布が40.6%、労働条件を書いた説明書の配布が34.1%である。 |
| ・ | 就労開始時に知らせる労働条件の項目(複数回答 単位:%) |
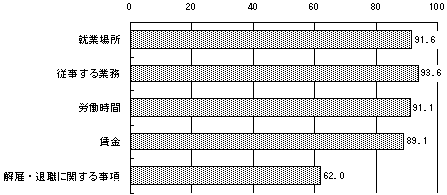
(無回答を除く集計) |
| ・ | 労働条件の項目を知らせる方法(複数回答 単位:%) |
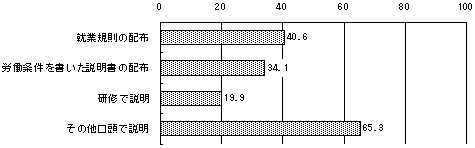
(無回答を除く集計) |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 中途採用者の採用に際して労働条件を通知する時期 |
| 中途採用者の採用に際して、就業場所、従事する業務、労働時間及び賃金については、内定時及び就業開始時のいずれにおいても中途採用者に知らせる企業がいずれも8割を超えている。 解雇・退職に関する事項については、内定時及び就業開始時のいずれにおいても中途採用者に知らせる企業は40.9%となっている。 |
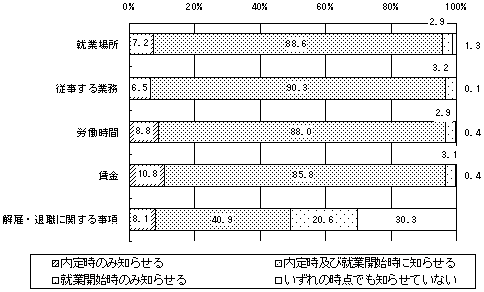
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 新規学卒者の採用内定の際に行うこと |
| 新規学卒者の採用内定に際しては、77.7%の企業が採用内定書を交付しているほか、49.3%の企業が採用内定者から誓約書を提出してもらっている。 一方で、11.7%の企業は、口頭のみで特に文書のやりとりはしていない。 |
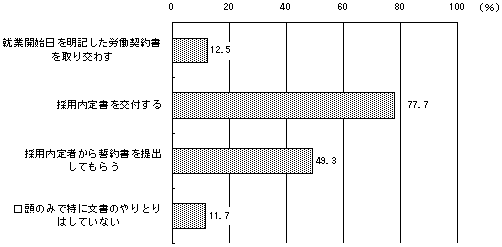
(複数回答 無回答を除く集計) |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | ここ5年間に採用内定取消がある企業の割合及びその理由 |
| ここ5年間に採用内定取消がある企業は7.3%であった。しかしながら、規模が1000人以上の企業については21.3%となっている。 採用内定取消の理由については、本人の非違行為が43.8%、本人の事情が36.3%となっている。 |
| ・ | ここ5年間に採用内定取消がある企業の割合(単位:%) |
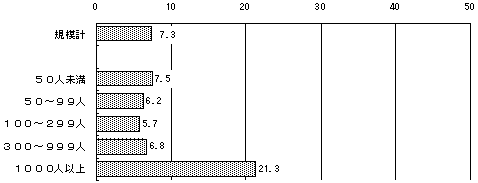
(無回答を除く集計) |
| ・ | 採用内定取消の理由(複数回答 単位:%) |
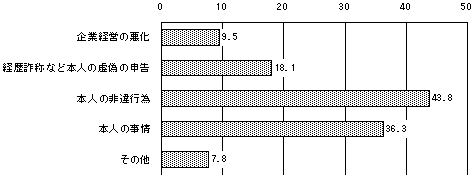
| ※ | ここ5年間において、採用内定取消があると答えた企業を対象として集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 採用内定取消の手続 |
| 採用内定取消の際に、採用ができなくなった旨を文書で通知した企業は24.2%であった。 また、採用できなくなった理由を添えて文書で通知した企業は23.5%であった。 |
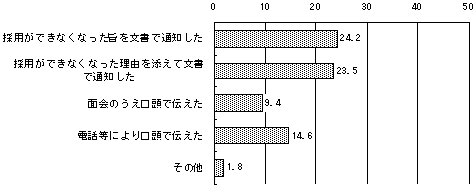
(複数回答 単位:%) |
| ※ | ここ5年間において、採用内定取消があると答えた企業を対象として集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 採用内定取消事由の定め |
| 採用内定取消事由の定めのある企業は24.6%であった。しかしながら、規模が1000人以上の企業は80.9%が採用内定取消事由を定めていた。 その内容としては、本人の事情が51.1%と最も多く、次いで本人の非違行為が43.2%となっている。 |
| ・ | 採用内定取消事由の定め |
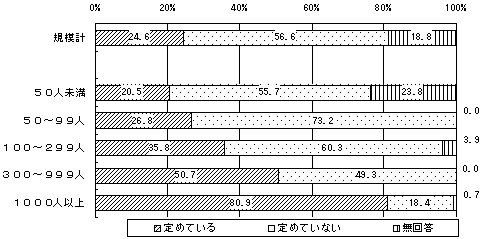
| ※ | ここ5年間において、採用内定取消があると答えた企業を対象として集計。 |
| ・ | 定められている採用内定取消事由の内容(複数回答 単位:%) |
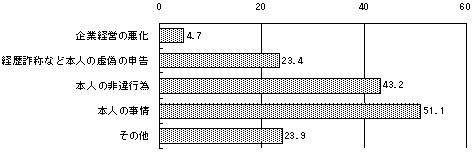
| ※ | 採用内定取消事由を定めていると回答した企業を対象に集計。 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 新規学卒者に対する採用内々定の有無及び性質 |
| 新規学卒者に対して、採用内定に先立って採用内々定を行っている企業は、3.6%であった。しかしながら、規模が1000人以上の企業については、41.3%の企業が、新規学卒者に対して、採用内定に先立って採用内々定を行っている。 採用内々定の性質については、採用内定と同じとする企業が47.3%であった。 |
| ・ | 新規学卒者に対する採用内々定の有無 |
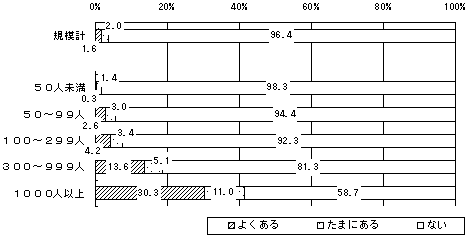
(無回答を除く集計) |
| ・ | 採用内々定の性質(複数回答 単位:%) |
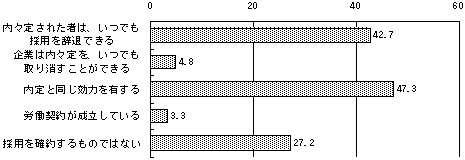
| ※ | 採用内々定がよくある又はたまにあると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 新規学卒者に対して採用内々定を行う方法 |
| 新規学卒者に対して、採用内定に先立って採用内々定を行う方法については、文書を交付する企業が42.1%であった。 また、対面の上口頭で伝える企業は36.0%であり、電話で伝える企業は35.8%であった。 |
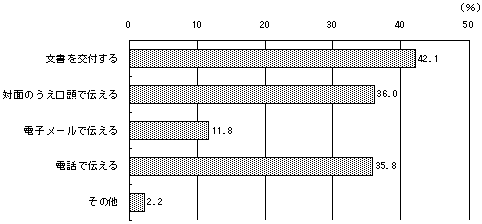
| ※ | 採用内々定がよくある又はたまにあると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 採用された従業員に対する試用期間の有無 |
| 採用された従業員に対して試用期間を設けることがある企業は、73.2%であった。 また、規模が300人以上1000人未満の企業において試用期間を設けている企業は90.2%であり、規模が1000人以上の企業においては87.0%であった。 |
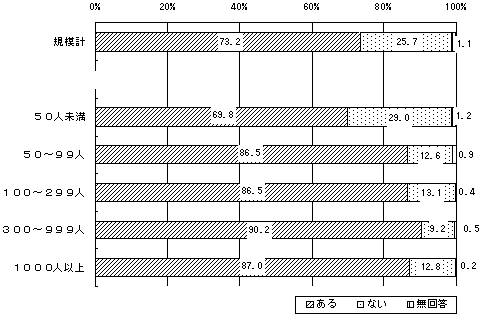
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 試用期間の規定の形式 |
| 試用期間を設ける形式としては、就業規則において定めている企業が71.1%となっている。 一方、慣行であり特に文書の規定等はないとする企業は19.6%となっている。 |
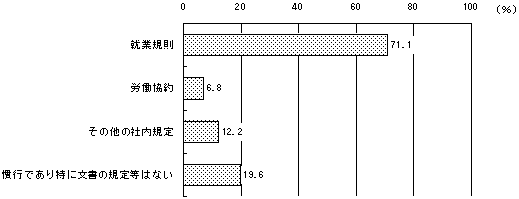
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 試用期間に関して採用の際に通知する事項 |
| 採用に際して、試用期間の有無及び長さを労働者に通知する企業は、いずれも9割を超えている。 また、試用期間中の解雇事由を通知している企業は43.5%、本採用を拒否する事由を通知している企業は36.2%となっている。 |
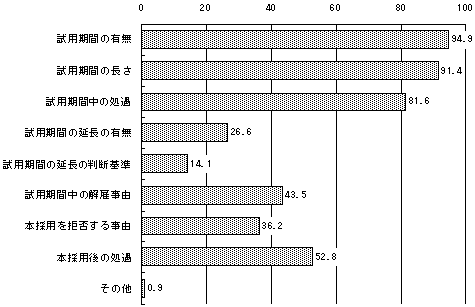
(複数回答 単位:%) |
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 採用形態、雇用契約の期間の定めの有無ごとの試用期間の有無 |
| 新規学卒者を雇用期間の定めのない契約で採用する場合には、79.1%の企業が試用期間を設けている。 また、中途採用者を雇用期間の定めのない契約で採用する場合には、93.3%の企業が試用期間を設けている。 |
| ・ | 新規学卒者における試用期間の有無 |
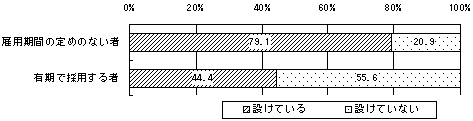
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあるとする企業を対象に無回答を除き集計 |
| ・ | 中途採用者における試用期間の有無 |
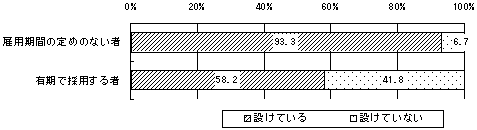
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあるとする企業を対象に無回答を除き集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 新規学卒者を採用する際の試用期間 |
| 新規学卒者を採用する際の試用期間については、企業の規模に関わらず、ほとんどの企業において、6か月程度より短くなっている。 |
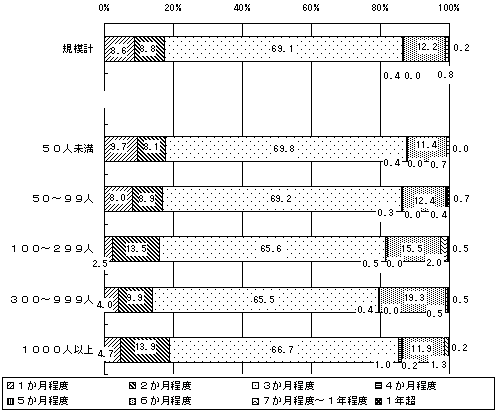
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあるとする企業を対象に無回答を除き集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 中途採用者の試用期間 |
| 中途採用をする際の試用期間については、企業の規模に関わらず、ほとんどの企業において、6か月程度より短くなっている。 |
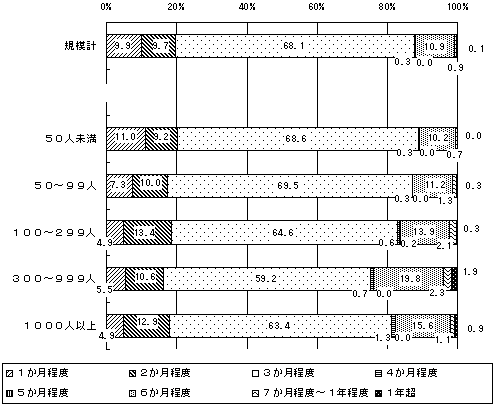
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあるとする企業を対象に無回答を除き集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 試用期間の延長 |
| 試用期間の延長については、延長しないこととしている企業が67.8%である。また、ここ5年間に延長した事例がある企業は8.6%となっている。 |
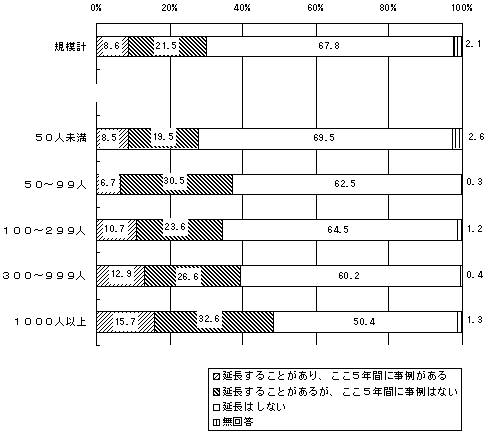
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 試用期間中の業務の内容 |
| 試用期間中の業務の内容については、原則として一つの部署に配属し、同じ業務に従事させるとする企業が64.1%となっている。 一方、もっぱら研修を行うとしている企業は2.1%となっている。 |
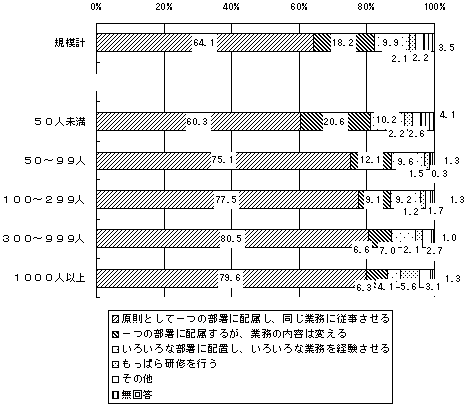
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 試用期間から本採用になる際の変化 |
| 試用期間から本採用になる際、業務内容、配属部署、資格等級及び就業時間については、特に変化しないとする企業が多い。 一方、賃金については、本採用になる際に、35.3%の企業が、賃金が変化する又は手当などが増えると答えている。 |
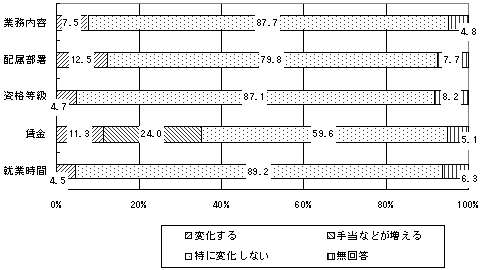
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 試用期間終了時の本採用拒否 |
| 試用期間終了時の本採用拒否の有無については、本採用しないことがあるが、ここ5年間に事例はない企業が58.0%となっている。 一方、本採用しないことがあり、ここ5年間に事例がある企業は13.1%となっている。 |
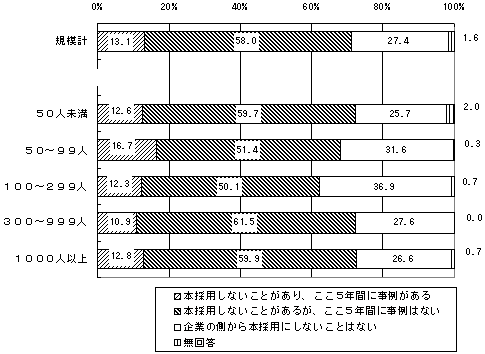
| ※ | 採用された従業員に試用期間を設けることがあると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 試用期間終了時の本採用拒否の判断基準 |
| 試用期間終了時に本採用せず、雇用を打ち切る際の判断基準については、30.2%の企業が設けている。規模が1000人以上の企業では53.2%が設けている。 試用期間終了時に本採用せず、雇用を打ち切る際の判断基準を定める形式としては、就業規則において定めている企業が84.5%である。一方で、慣行であり特に文書の規程はない企業は10.7%であった。 |
| ・ | 本採用拒否の基準の定めの有無 |
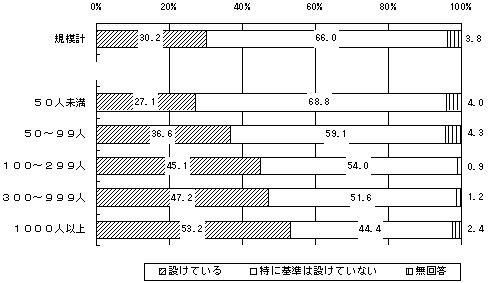
| ※ | 本採用しないことがあり、ここ5年間に事例がある、又は、本採用しないことがあるが、ここ5年間に事例はないと回答した企業を対象に集計 |
| ・ | 本採用拒否の基準の定めの形式(複数回答 単位:%) |
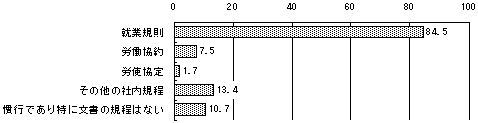
| ※ | 本採用拒否の基準を設けていると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 本採用拒否の通知時期 |
| 試用期間終了後の本採用拒否を本人に通知する時期については、試用期間が終わる前に余裕をもって伝える企業が45.7%となっている。 このうち、具体他的な通知時期については、1ヶ月程度前に通知する企業が48.6%と最も多くなっている。 |
| ・ | 本採用拒否の本人への通知時期 |
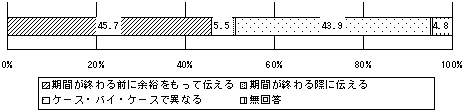
| ※ | 本採用しないことがあり、ここ5年間に事例がある、あるいは、本採用しないことがあるが、ここ5年間に事例はないと回答した企業を対象に集計 |
| ・ | 本採用拒否の本人への通知時期(余裕をもって伝える場合) |
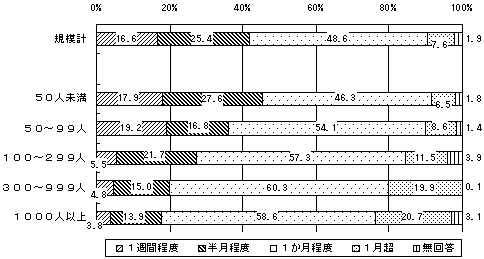
| ※ | 本採用せず雇用を打ち切る場合に、試用期間が終わる前に余裕をもって伝えると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 本採用拒否の本人への通知方法 |
| 本採用拒否をする場合に本人に通知する方法としては、口頭で通知する企業が70.8%となっている。 本採用拒否について本人に伝える際に、理由を伝える企業は86.7%となっている。 |
| ・ | 本採用拒否をする場合に本人に通知する方法 |
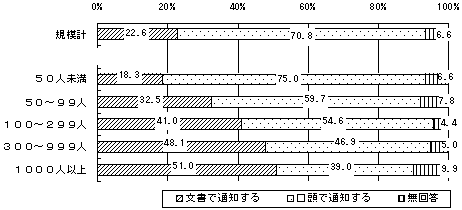
| ※ | 本採用しないことがあり、ここ5年間に事例がある、あるいは、本採用しないことがあるが、ここ5年間に事例はないと回答した企業を対象に集計 |
| ・ | 本採用拒否について本人に伝える際の理由の通知 |
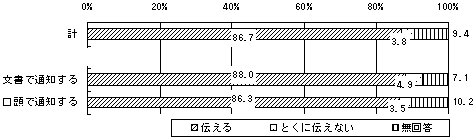
| ※ | 本採用拒否を本人に通知する場合に文書で通知する、あるいは、口頭で通知すると回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 本採用をしない場合の判断理由 |
| 本採用をしない場合の判断理由として、81.2%の企業が欠勤などの勤務状況を、75.7%の企業が仕事上の知識、能力を、69.0%の企業が素行をそれぞれ挙げている。 |
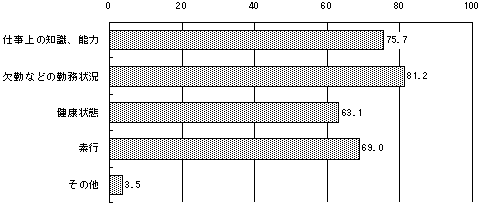
(複数回答 単位:%) |
| ※ | 本採用しないことがあり、ここ5年間に事例がある、あるいは、本採用しないことがあるが、ここ5年間に事例はないと回答した企業を対象に集計 |
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ○ | 正規従業員の採用に関する有期労働契約又は紹介予定派遣の活用 |
| 正規従業員を本採用する前に有期契約労働者として雇入れることを行っている企業は26.8%であった。 また、正規従業員を本採用する前に紹介予定派遣を活用している企業は4.1%であった。 |
| ・ | 正規従業員の採用に関する有期労働契約での雇入れの活用 |
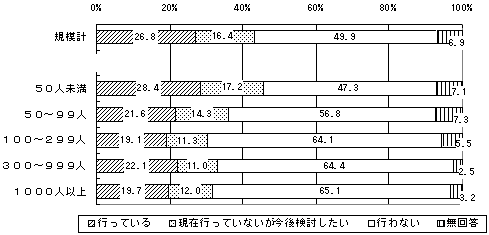
| ・ | 正規従業員の採用に関する紹介予定派遣での雇入れの活用 |
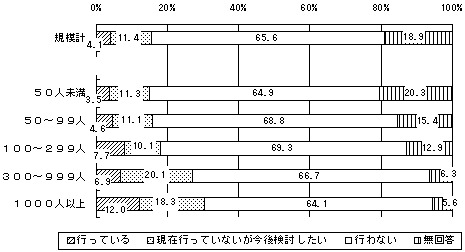
| 資料出所: | 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |