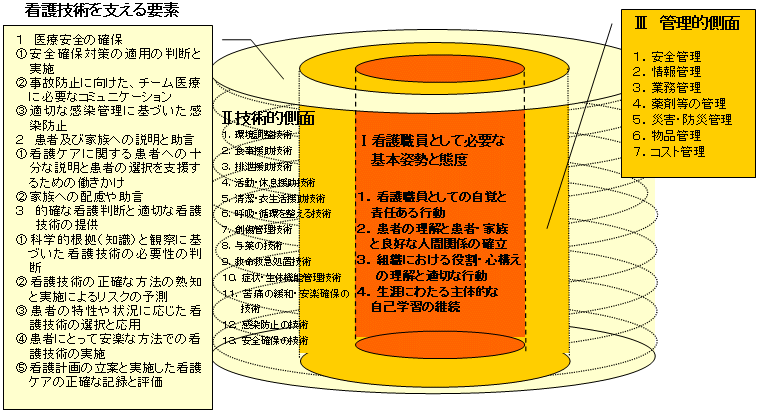| 「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会報告書」の概要 |
はじめに
医療安全の確保及び臨床看護実践の質の向上の観点から、新人看護職員研修について検討を行い、平成16年3月10日に報告書を取りまとめた。(参考1、参考2参照)
| ○ |
看護の現状
医療技術の進歩、患者の高齢化・重症化、平均在院日数の短縮化等の中で、
| ・ |
看護職員の役割の複雑多様化、業務密度の高まり |
| ・ |
多重課題への対応能力養成の必要性 |
| ・ |
看護職員の社会的責任の拡大 |
| ・ |
ヒヤリ・ハット事例での新人看護職員の占める割合の高さ |
|
| ○ |
看護の質を確保、向上させ、医療安全を確保するために、新人看護職員研修の充実の必要性は非常に高い。 |
| 2 |
新人看護職員研修の現状と課題
| |
新人看護職員研修の実施内容は様々であり、標準的な指針の策定が求められる。 |
|
| 3 |
看護基礎教育における現状と課題
| |
複数の患者の受け持ちや多重課題への対応等について、基礎教育で身につけることは困難。 |
|
|
| 第二部 |
新人看護職員研修到達目標及び新人看護職員研修指導指針 |
| 1 |
新人看護職員研修は、看護実践の基礎を形成するものとして極めて重要な意義を有する。 |
| 2 |
医療機関の全職員に対する組織的な研修の一環として位置付けられるべきものである。 |
| 3 |
多重課題を抱えながら複数の患者を受け持ち、安全に看護ケアを提供するための看護実践能力を強化することを主眼とする。 |
|
| II |
新人看護職員研修到達目標及び新人看護職員研修指導指針の前提 |
| 1 |
病院において看護ケアを提供する看護職員を想定。 |
| 2 |
到達目標及び指導指針の内容は、基本事項として提示するが、施設規模等の状況により、適宜調整することを想定。 |
|
看護職員として必要な姿勢及び態度並びに新人看護職員が卒後1年間に修得すべき知識、技術の目標を提示。到達目標は、以下の3つの要素に分けたが、これらは臨床実践の場で統合されるべきものである。(図1)
| |
(1) |
看護職員としての自覚と責任ある行動 |
| (2) |
患者の理解と患者・家族との良好な人間関係の確立 |
| (3) |
組織における役割・心構えの理解と適切な行動 |
| (4) |
生涯にわたる主体的な自己学習の継続 |
| |
(2―1)看護技術
(1)環境調整技術 (2)食事援助技術 (3)排泄援助技術 (4)活動・休息援助技術 (5)清潔・衣生活援助技術 (6)呼吸・循環を整える技術 (7)創傷管理技術 (8)与薬の技術 (9)救命救急処置技術 (10)症状・生体機能管理技術 (11)苦痛の緩和・安楽確保の技術 (12)感染防止の技術 (13)安全確保の技術
(2−2)助産技術 (1)妊産婦 (2)新生児 (3)褥婦 (4)証明書等
○看護技術を支える要素
(1)医療安全の確保 (2)患者及び家族への説明と助言 (3)的確な看護判断と適切な看護技術の提供 |
| |
(1)安全管理 (2)情報管理 (3)業務管理 (4)薬剤等の管理 (5)災害・防災管理 (6)物品管理 (7)コスト管理 |
|
図1 臨床実践能力の構造
I、II、IIIは、それぞれ独立したものではなく、患者への看護ケアを通して統合されるべきものである。
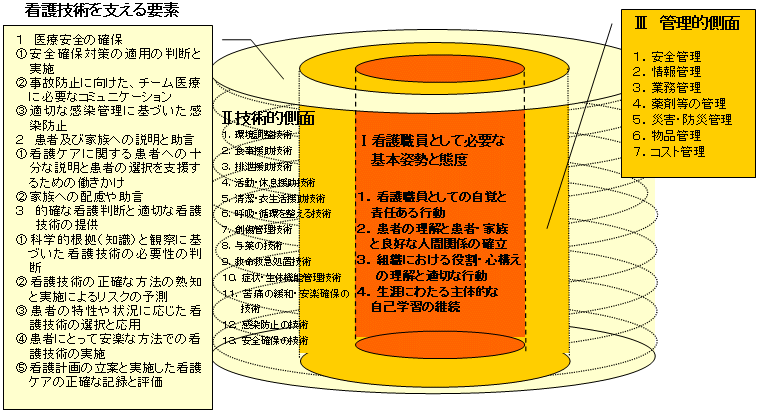 |
到達目標達成のために必要な要件、指導方法等を提示。
| 1 |
新人看護職員育成の方針 |
| 2 |
施設における研修体制の充実 |
| (1) |
研修体制整備の意義 |
| (2) |
職員の研修への参加 |
| (3) |
施設における教育担当部門の設置 |
| (4) |
看護部門における教育理念の明確化及び研修体制の整備 |
| (5) |
教育担当者及び新人看護職員に対する業務上の配慮 |
| (6) |
新人看護職員の精神的支援 |
| (7) |
関係部署、他職種との連携 |
| (8) |
看護基準及び看護手順等の整備 |
| (9) |
新人看護職員研修へのIT(情報技術)の導入 |
| (10) |
研修計画の評価、改善等 |
| (11) |
施設間の支援体制 |
| (1) |
看護管理者の役割及び教育担当者の配置 |
| (2) |
実地指導者の配置 |
| (3) |
実地指導者の負担の軽減 |
| (4) |
教育内容等の提示 |
| (5) |
各部署に必要な看護手順等の整備 |
| (1) |
実地指導者の要件 |
| (2) |
実地指導者研修の場 |
| (3) |
実地指導者研修のプログラム |
| (1) |
情報公開の意義 |
| (2) |
各施設の研修内容等の公開 |
| (3) |
就職前の学生への情報提供等 |
|
おわりに
全ての新人看護職員が求められる資質を確保できるような仕組みの構築に向けて、今後も継続して検討。