全国市長会 |
|
|
| ・ | 生活保護は、そもそも現金給付による所得再分配であり、国が行うべき典型的な仕事である。 |
| ・ | 生活保護費負担金の国庫負担割合引下げは、国の責任の後退であり、単なる地方への負担転嫁に過ぎない。 |
| ・ | 負担割合の引下げを行っても、地方の自由度は高まらず、三位一体改革の趣旨に沿うものではない。 |
| ・ | 「地方負担を増やすことにより保護率を下げるというインセンティブが働く」との国の考え方には、これまでの負担率の引上げ・引下げの経緯からみて、根拠がない。【下図参照】 |
| ・ | 保護率の近年の上昇は、社会的要因(単身高齢世帯、離婚による母子家庭、長期入院患者の増加等)と経済的要因(企業の倒産、リストラ・失業者・ホームレスの増加等)によるものである。【下図参照】 |
| ・ | 保護率の地域差が見られるが、これは地方自治体がただ漫然と保護を適用している結果ではなく、失業率の悪化、地域固有の歴史的背景など構造的要因によるものである。 |
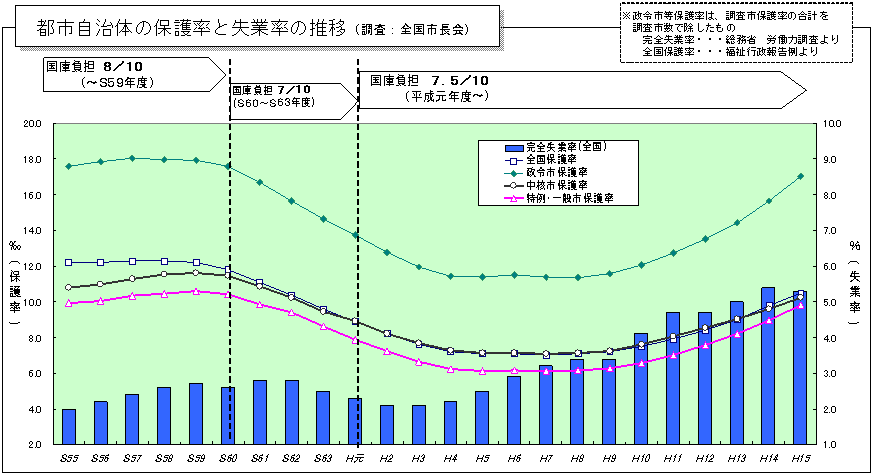 |
| <緊急調査>対象市100市 回答市75市 |
| 本会が、生活保護に関し、緊急にアンケート調査を実施したところ、次のような結果であった。(対象市:100市(政令市13市、中核市35市、特例市40市、一般市12市)、回答市:88市) |
|
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ |
|
||
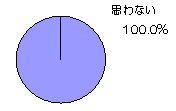 |
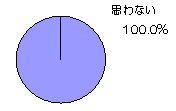 |
|
| ・ | 景気の長期低迷により、保護率が上昇していると考えられることから、景気・雇用対策など国による総合的な政策の推進が必要である。 |
| ・ | 老齢基礎年金額(満額で月額約67,000円)より生活保護基準額(月額で約110,000円)の方が高いなど、一般世帯と被保護者世帯との間に不公平感がある。 |
| ・ | 年金担保貸付制度を悪用するケースが目立っているが、これを取り締まる法的根拠がない。 |
| ・ | 医療扶助・介護扶助は現物給付であるため、保護を受けている者に費用負担意識がなく、過剰な受診やサービスの受給につながっている。 |
| ・ | 生活保護法による諸調査は、「報告を求めることが出来る」という規定となっているため、関係機関の協力が得られないと十分な調査が出来ない。 |
| ・ | 国における福祉施策と雇用施策との連携が不十分である。 |
| ・ | 本来、国が実施するべき生活保護のために、地方では、ケースワーカーとして10,852人(平成15年10月1日現在、厚生労働省「福祉事務所現況調査」より)の人員を割いており、極めて大きな財政負担になっている。 |
| ・ | ケースワーカーが一人で問題に対処せざるを得ないため、窮地に追い込まれる場合がある。 |
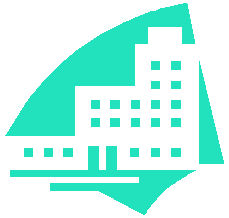
| 全国市長会 社会文教部 〒102-8635 東京都千代田区平河町2-4-2 TEL 03-3262-2318・FAX 03-3263-5483 URL http://www.mayors.or.jp/ |