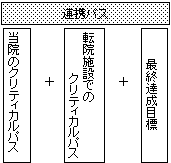|
|
医療制度改革について
平成17年3月18日
厚生労働省
平成17年3月18日
厚生労働省
| 1. | 我が国の医療費の水準について |
| 総医療費(OECDベース)の将来推計(対GDP比) |
<推計方法>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OECD加盟国の医療費の状況(2001年)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「抑制すべきは公的医療費であり、医療費全体は伸びてもよい」との議論について |
| ○ | いわゆる「混合診療」問題については、患者の立場から個別に見たときに保険外負担が過大な事例があり、国内未承認薬や必ずしも高度でない先進技術等について保険診療との併用等を求める患者の切実な要望に迅速かつ的確に対応するため、「必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保する」という国民皆保険制度の理念を基本に据え、「保険導入検討医療(仮称)」の創設等の改革を行うことで合意に至ったところ。(平成16年12月15日 厚生労働大臣、規制改革担当大臣による基本的合意) |
||||||||
| ○ | 米国においては、公的医療保障制度の対象者を限定し、大部分を民間保険等で対応しているが、
|
| (注) | 米国における公的医療保障制度としては、65歳以上の高齢者と障害者を対象とするメディケア(連邦政府)、低所得者を対象とするメディケイド(州政府)があるのみ。 |
| 2. | 医療費の伸びに関する分析 |
| 「社会保障の給付と負担の見通し」における将来推計の前提 |
|
| 2004年度〜2010年度 | 2010年度〜2015年度 | 2015年度〜2025年度 | |||
| 医療給付費の伸び | 4.2% | 4.0% | 3.6% | ||
| 人口の伸び | 0.0% | ▲ 0.2% | ▲ 0.4% | ||
| 人口の高齢化 | 1.7% | 1.6% | 1.4% | ||
| 1人当たり医療費 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | ||
| うち一般 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | ||
| うち高齢者 | 3.2% | 3.2% | 3.2% | ||
| (注) | 「人口の伸び」は、「日本の将来推計人口」(平成14年1月)の中位推計による。 「人口の高齢化」は、年齢別にみて1人当たり医療費の高い中高齢者の割合が将来増加することによる「医療給付費の伸び」への影響を示したもの。 「1人当たり医療費」の伸びは、平成7〜11年度の平均。ただし、加入員の年齢構成の変化による増減分(「人口の高齢化」)と、制度改正による一時的な伸びの減少分を除いたもの。 |
| 1人当たり医療費の伸び率の構造(平成7〜11年度) 〜診療報酬明細書の診療実日数、医療費による分析〜 |
|
| 年平均伸び率(%) | 伸びの要因 | ||||
| 全体 | 70歳未満 | 70歳以上 | |||
| 1人当たり医療費 (人口1人当たり医療費) |
2.6 | 2.1 | 3.2 | ― | |
| 1日当たり医療費 (受診1日当たり医療費) |
3.1 | 2.8 | 3.3 | 医学、薬学の進歩による高度な医療の開発と普及 疾病構造の変化による受診単価の変化 |
|
| 1人当たり日数 (人口1人当たり受診日数) |
▲0.5 | ▲0.8 | ▲0.1 | 入院期間の短縮、長期投薬の制限撤廃など適正化の効果 疾病構造の変化による受診日数の変化 |
|
| (注1) | 「社会保障の給付と負担の見通し」(平成16年5月 厚生労働省)において設定した医療費の伸びについて、その内訳を示したものである。 |
| (注2) | 人口の伸び、人口構造の高齢化等による医療費の伸びについては、各年で異なるためここでは、これらの人口に関連する伸びの影響については、含んでいない。 |
| 国民医療費、GDPの伸びの比較 |
|
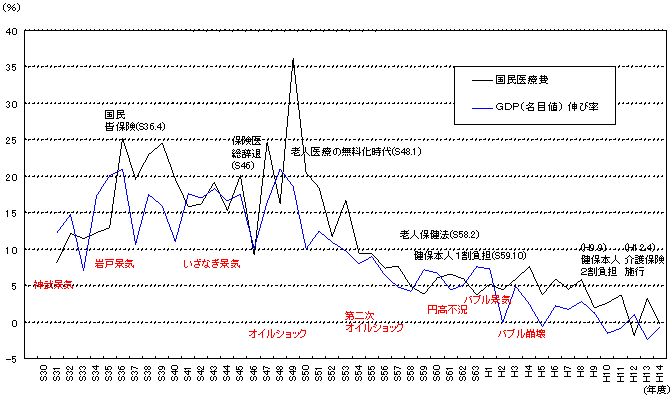
| 3. | 医療給付費の伸びを名目GDPの伸びに 抑制した場合のミクロ的影響 |
医療給付費の将来推計
(医療給付費を患者負担の増によりGDPの伸びの範囲に抑えるとした場合)
(医療給付費を患者負担の増によりGDPの伸びの範囲に抑えるとした場合)
|
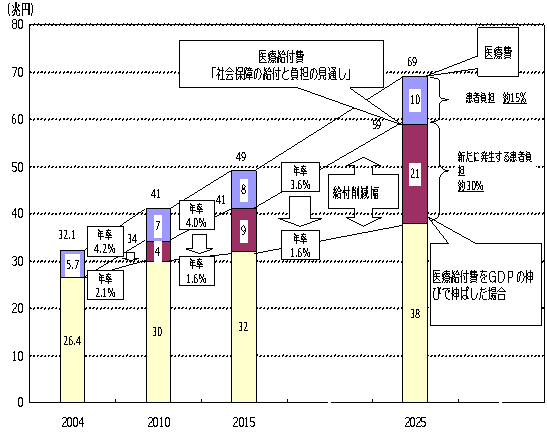 |
|||||||||||
|
給付費の縮小分を自己負担増のみで賄うとした場合のイメージ
| ○ | 2025年度の医療給付費をGDPの伸びの範囲内に抑制し、給付費の縮小分を自己負担のみで賄うとした場合、2025年度の自己負担率(実質15%)を2〜3倍程度引き上げることが必要 |
||||||||
| ○ | これは、制度の前提の置き方により異なるが、現在の
引き上げることに相当
|
平均的な自己負担額に与える影響(月額、粗い試算)
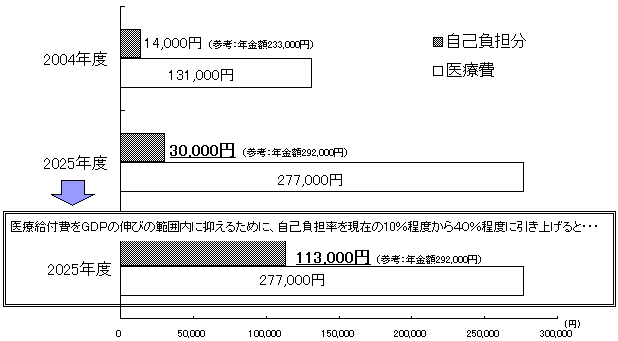 |
| (注1) | 医療提供の効率化や公定価格の見直しを図ることにより、実際の患者負担はこの試算よりも低くなる。 |
| (注2) | 「社会保障の給付と負担の見通し」(平成16年5月 厚生労働省)を基にした試算。高齢者世代の給付費、自己負担額は、老人医療受給対象者の1人当たり給付費、自己負担額に基づいて推計を行っている。 |
| (注3) | 年金額は、夫が平均的収入で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯における年金の受給開始時の見込みであり、名目額である。 |
| (注4) | 患者負担を引き上げた場合に医療費が縮減する効果を見込んだ場合、2025年度の医療費は231,000円、自己負担分は69,000円となる。 |
| 4. | 医療費適正化のための取組と そのマクロ的効果の試算 |
| 医療費適正化のための取組 |
【長期的に効果の現れる取組】
【中期的に効果の現れる取組】
【短期的に効果の現れる取組】
|
|
| 生活習慣病対策による医療費適正化効果 |
|
(単位:兆円)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (注1) | この表における生活習慣病分の医療費の範囲は、糖尿病(糖尿病性慢性腎不全含む)、脳血管疾患、虚血性心疾患、悪性新生物としている。(高血圧症、高脂血症等は含まれていない。) |
| (注2) | 適正化効果については、健康フロンティア戦略の目標値を勘案し、糖尿病は2015年度△10%、2025年度△20%、虚血性心疾患・脳血管疾患は2015年度△25%、2025年度△25%と仮定して算定している。 |
| (注3) | 悪性新生物の適正化効果は見込んでいない。 |
| 糖尿病を中心とした生活習慣病等の進行例 |
|
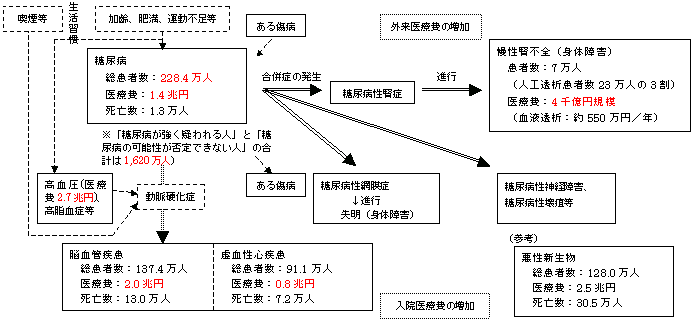
| 出典: | 患者調査(平成14年)、国民医療費(平成14年度)、人口動態統計(平成14年)、糖尿病実態調査(平成14年)、わが国の慢性透析療法の現況(2003年12月31日)等より |
| 糖尿病の発症予防・重症化予防の対策のイメージ |
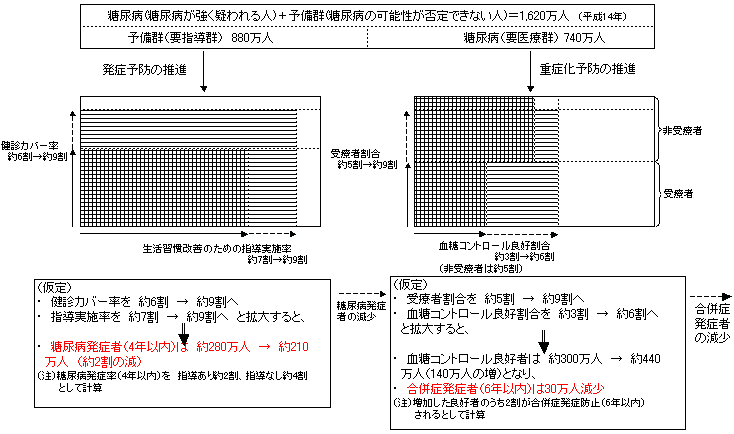
| 糖尿病の発症予防・重症化予防の対策は、心疾患、脳卒中等の対策とも共通しており、さらに相乗効果がある |
| (主傷病が虚血性心疾患の67%、脳血管疾患の57%、腎不全の80%、悪性新生物の29%は、副傷病まで含めると糖尿病・高血圧・高脂血症のうちいずれかを保有している) |
| ※ 糖尿病実態調査(平成14年)、N Engl Med 2002;346:393-406、Diabetes Research and Clinical Practice 28(1995) 103-117(熊本スタディ)、社会医療診療行為別調査(平成14年)等より |
| 生活習慣病の発症予防・重症化予防の流れ(イメージ) |
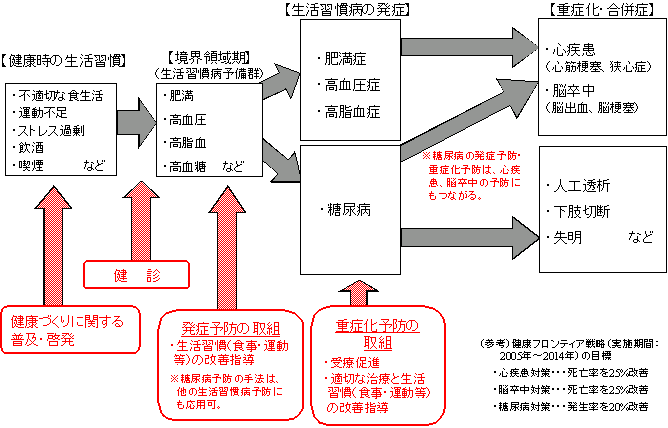
| 生活習慣病対策の具体策 |
|
|
| 平均在院日数が短縮した場合の医療費適正化効果(粗い試算) |
| ○ | 全国の平均在院日数(37.9日)が、最も短い長野県(28.8日)と同程度(24%減)となるものと仮定して、医療費の適正化効果について粗い試算を行うと、2.2兆円程度(2002年度ベース)となる。
|
||||
| ○ | 上記程度の効果が2025年度に現れるとすると、医療費の適正化効果は2025年度には4.9兆円程度となる。 (上記の半分程度の効果が2015年度に現れるとすると、2015年度には1.7兆円程度となる。) |
(参考)平均在院日数の各国比較
|
|
熊本市内のある急性期病院における「医療連携クリティカルパス(連携パス)」について
|
| 医療機能の分化・連携、平均在院日数の短縮の具体策 |
|
| 質の高い効率的な医療提供体制の構築 −医療機能の分化・連携/在宅医療の推進等による平均在院日数の短縮− |
| 医療計画や関連する補助金等の医療提供制度改革を行うことにより、質の高い効率的な医療提供体制の実現に向け、都道府県による実効性の高い施策展開を推進し、これを国が支援することとする。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
「脳卒中」に係る保健医療提供体制の実現に関する国と都道府県の役割 <イメージ>
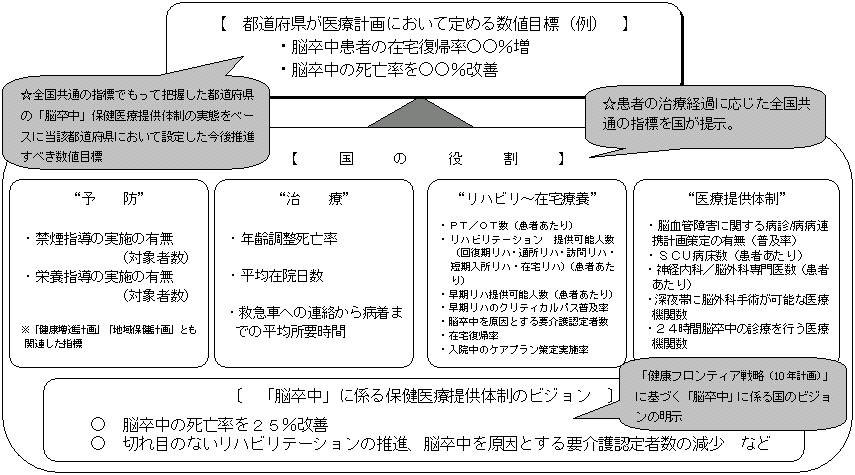
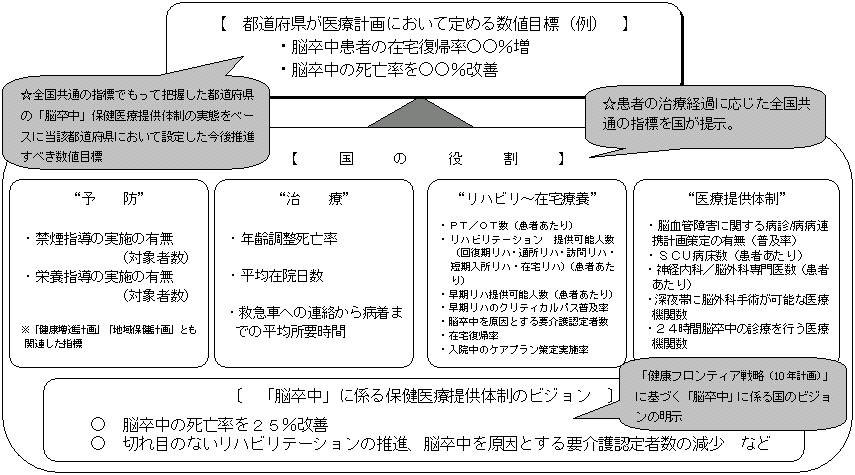
| 地域における高齢者の生活機能の重視の具体策 |
|
| 試算のまとめ |
| 生活習慣病対策の推進、医療機能の分化・連携の推進、平均在院日数の短縮、地域における高齢者の生活機能の重視を一体的かつ計画的に行うことにより、構造的な医療費適正化を進めると、中長期的に以下のような効果が期待できる。 |
| 2015年度 | 2025年度 | ||
| 「給付と負担の見通し」の推計額 | |||
| 国民医療費 (対国民所得比) |
49兆円 (11%) |
69兆円 (13%) |
|
| 給付費 (対国民所得比) |
41兆円 (9%) |
59兆円 (11%) |
|
| 生活習慣病対策の推進((1)) | 約1.6兆円 | 約2.8兆円 | |
| 平均在院日数の短縮((2)) | 約1.7兆円 | 約4.9兆円 | |
| 医療費適正化効果総額((1)+(2)) | 約3.3兆円 | 約7.7兆円 | |
| 対国民所得比 | 0.7% | 1.5% | |
| 給付費減少総額 | 約2.8兆円 | 約6.5兆円 | |
| 対国民所得比 | 0.6% | 1.2% | |
| (注) | 粗い試算の結果であり、今後、具体的な方策について更に議論を進める中で、その効果についても併せて精査を行う必要がある。 |
| 5. | 保険者の再編・統合 −政管健保を中心に− |
| 医療保険制度改革の方向性 |
|
|
|
都道府県単位を軸とする保険者の再編・統合と都道府県の関係
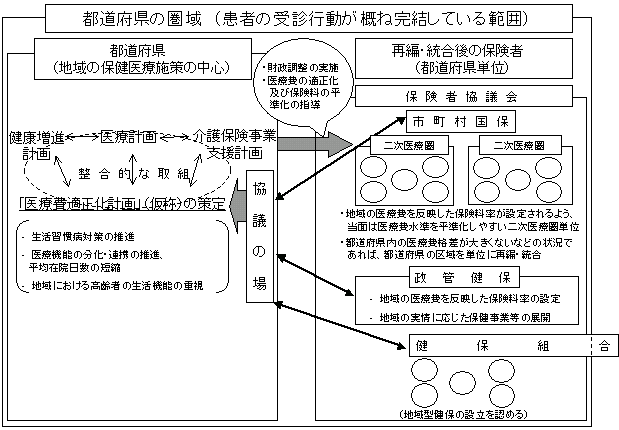
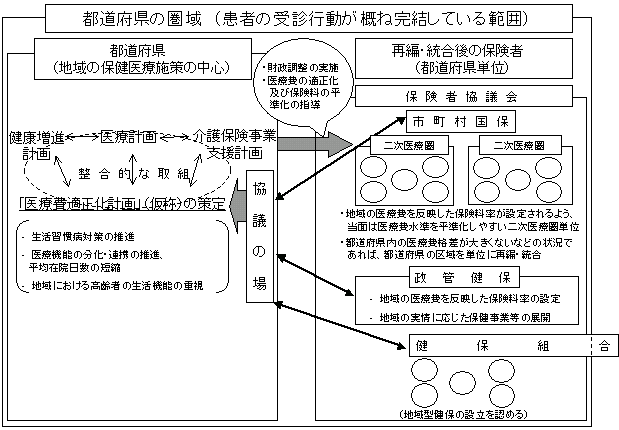
| 政管健保の平成13年度医療給付費等実績に 基づく都道府県別保険料率の機械的試算 |
(単位:‰)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国と政管保険者組織の関係(イメージ) |
| 地域の医療費水準に見合った保険料水準の設定、地域特性を踏まえた保健事業の推進といった保険者機能の発揮の観点から、国と政管保険者組織はどのような関係が望ましいか |
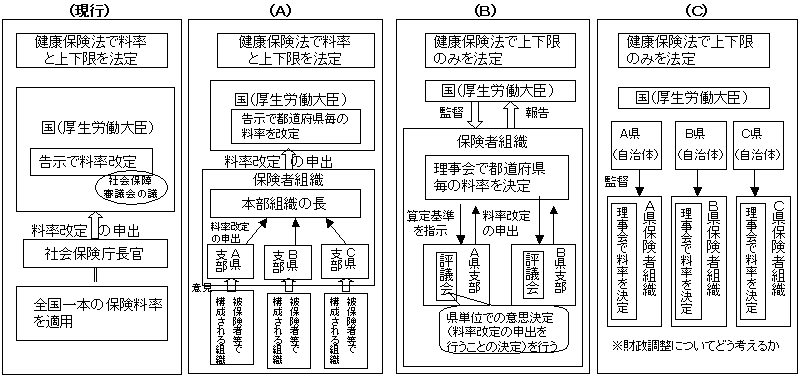
| 現行 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||
| 「自主性・自律性のある保険運営」 「安定的な財政運営」 「事務の効率性」 等の観点からの メリット・デメリット |
|
|
|
|
| 国と政管保険者組織の関係について |
現在、社会保険庁(国)で実施している政管健保について、国から分離し、保険者機能が発揮される主体による保険運営とすることの意義
|