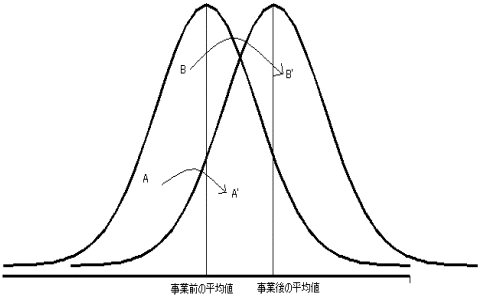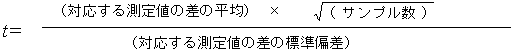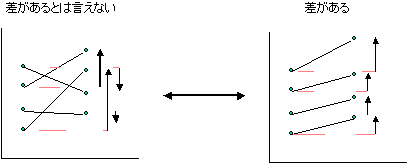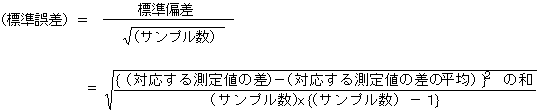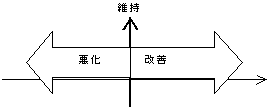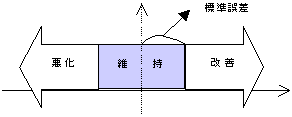| ○ | データの分析に当たっては、(1)筋力の向上、(2)栄養改善、(3)口腔ケア、(4)閉じこもり予防、(5)フットケアのプログラム別に解析を行った。
|
| ○ | 各プログラム別に、
| (1) | 要介護度別(要支援、要介護1,要介護2) |
| (2) | 年齢別(75歳未満、75歳以上) |
| (3) | 基礎疾患別(脳血管疾患の既往のある者、その他の疾患) |
での解析を行った。また、「筋力の向上」についてはマシン使用、未使用でそれぞれ解析を行った。
|
| ○ | 事業参加の前後での測定値の比較については、基本的には「対応のあるt検定」を用いて分析した。なお、以下の項目については「ウィルコクソンの符号付順位和検定」を用いた。
| (1) | 筋力向上については、「要介護度一次判定」、「老研式活動能力指標」 |
| (2) | 栄養改善については、「要介護度一次判定」 |
| (3) | 口腔ケアについては、「要介護度一次判定」、「歯肉炎」、「口腔清掃状況」、「口臭」、「むせ」、「食べこぼし」 |
| (4) | 閉じこもり予防については、「要介護度一次判定」、「外出頻度」、「日中主に過ごす場所」 |
| (5) | フットケアについては、「要介護度一次判定」、「身体機能に関する項目」 |
|
| ○ | 本分析においては、「改善」、「維持」、「悪化」の分類について、軽微な変化まで「改善」、「悪化」と判定されることがないように、基本的には「維持」に一定の幅を持たせている。このため、事業参加前後での測定値に少しでも変化があれば「改善」または「悪化」としていた「介護予防市町村モデル事業に係る実施集計結果(4月11日とりまとめ)とは異なる集計結果となっている。
|
| ○ | 分析結果の表中の「統計的有意差の有無」において、「*」は有意な変化があった項目であること、空欄は有意な変化が認められなかった項目であることを示す。また、「事業参加前の測定値」、「事業参加後の測定値」において、順位尺度(どちらが大きいかは分かるものの、どのくらい大きいかは分からないように決められている変数)である要介護度一次判定等については、「−」と表示している。 |