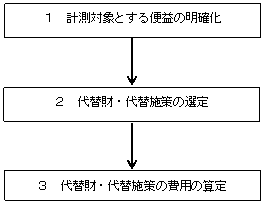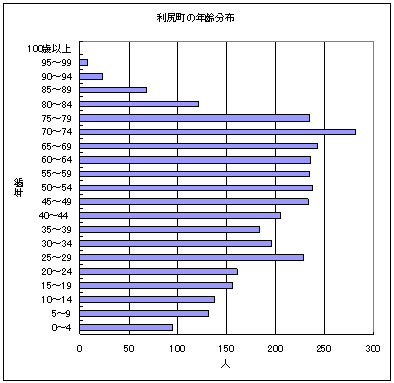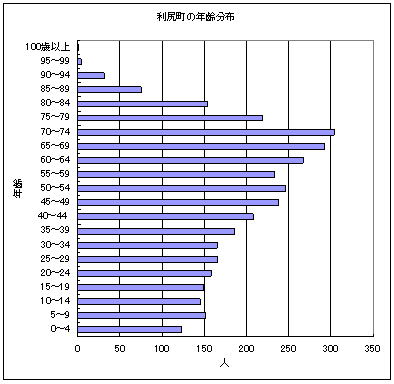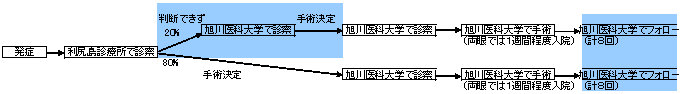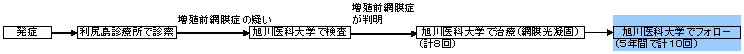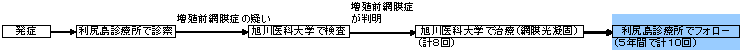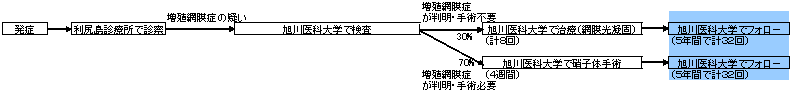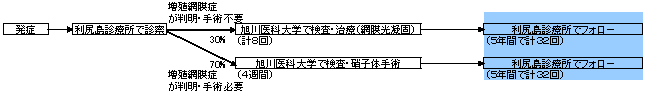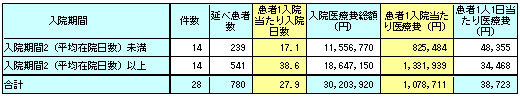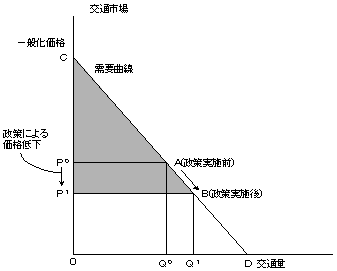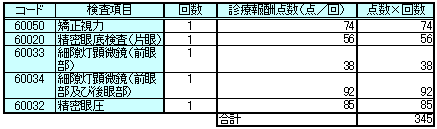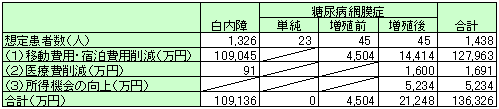| へき地保健医療対策検討会 |
資料4 |
| 第3回(H17.3.31) |
吉田委員提出資料
ITを活用した
へき地離島医療支援
遠隔医療システム導入の経済性評価
報告書
2005年3月29日
旭川医科大学医学部
眼科学講座教授
吉田晃敏
目次
|
本調査では、平成16年度厚生労働科学研究費補助金「医療技術評価総合研究事業」における、「離島・過疎地における新しいユビキタス遠隔医療支援(16210301)」において、遠隔医療システム導入の経済性評価を行う。
ここでは、「効果項目および受益主体の整理」、「効果計測手法の検討」、「医師へのヒアリング調査・アンケート調査」を行い、遠隔医療システム導入の経済評価手法の検証、経済効果の算出を試みる。 |
| (1) |
効果項目および受益主体の整理
旭川医科大学における遠隔医療システムの導入による効果とその受益主体について整理する。
|
| (2) |
効果計測手法の検討
既存研究事例等を参考に、各効果項目について計測手法を整理し、適切な手法を検討する。
|
| (3) |
アンケート調査
効果計測や課題検討のために必要な定性的な知見を医療関係者からのアンケート調査により収集する。
|
| (4) |
経済評価手法の検証・経済効果の試算
(2)で検討した手法を実際に適用し、旭川医科大学における遠隔医療システムの導入効果を計測する。
|
| (5) |
調査結果のとりまとめ
本調査結果のとりまとめを行い、今後の課題を整理する。 |
|
旭川医科大学遠隔医療センターにおける遠隔医療システム導入の経済評価を行うにあたって、まずその効果項目と受益主体を整理する必要がある。
既存の遠隔医療システムの経済評価の事例および報告書 等から、効果項目・受益主体をマトリクスの形で整理すると下表のようになる。 |
表 効果項目・受益主体の整理
| 効果\主体 |
医師 |
看護師 |
患者 |
患者の家族 |
国民 |
|
○ |
○ |
◎ |
○ |
− |
|
− |
− |
◎ |
○ |
○ |
| (3) |
高度な医療を身近な医療機関で受けられることによる安心感の向上 |
|
− |
− |
◎ |
○ |
○※ |
| (4) |
高度な医療を受けられることにより、早期に治癒し、復帰が早まることによる所得機会の増大 |
|
− |
− |
◎ |
− |
− |
| (5) |
高度な医療を受けられることにより、重度障害や失明等を回避できることによる損失の回避 |
|
− |
− |
◎ |
− |
− |
|
| 凡例) |
| ◎: |
特に大きな+の効果が期待される |
| ○: |
+の効果が期待される |
| −: |
効果が期待されない |
| : |
効果を計測する範囲 |
|
| ※ |
現在、直接に遠隔医療システムによる診療・治療を受ける患者およびその家族でなくとも、将来的にそうした診療を受ける可能性がある(潜在需要となる)国民にも、こうした安心感の向上効果があると考えられる。ただし、その受益範囲の特定が非常に困難であるため、今回は計測の対象としない。 |
|
2.で整理した効果項目を計測するための手法としては、以下のようなものが挙げられる。 |
表 各効果項目の計測手法
| 効果項目 |
計測手法 |
利用データおよび計測方法 |
|
| ■ |
消費者余剰法
遠隔医療システムの有無による移動費用の変化分により移動費用・移動時間・宿泊費用節減効果を計測 |
|
| ■ |
各主体へのアンケート・ヒアリングにより遠隔医療システム導入前後の平均的な移動費用・移動時間を算出 |
| ■ |
遠隔医療システムによる診療・治療の対象者数を調査 |
| ■ |
((各主体1人あたり移動費用+移動時間×時間価値)の節減額)×(主体別対象者数)により効果を計測
|
| ※ |
移動時間の価値(時間価値)は当該地域の平均的な賃金率を適用 |
|
|
| ■ |
代替法
遠隔医療システムによる医療費と、それに代替する従来の診療・治療手法の医療費の差分により効果を計測 |
|
| ■ |
遠隔医療システムによる症例別の1患者あたりの医療費 |
| ■ |
代替的な従来手法(離島に実際に医療機関を建設し、そこで診療する等)による症例別の1患者あたり医療費 |
| ■ |
(上記の医療費差分)×(症例別対象患者数)により計測 |
| ※ |
遠隔医療システムと代替的な手法とで診療・治療の効果が変わらないと仮定する必要あり |
|
| (3) |
高度な医療を受けられることにより早期に治癒し、復帰が早まることによる所得機会の増大 |
|
| ■ |
原単位法
遠隔医療システムの導入により仕事への復帰が早まる日数に1日あたりの平均所得(原単位)を乗じることにより計測 |
|
| ■ |
遠隔医療システムにより早期に診療/治療が終了する事例があるかを調査 |
| ■ |
そうした事例があれば、その事例に該当する患者のうち所得を得ている人の数に、復帰が早まる日数および1日あたり平均所得を乗じることにより効果を計測 |
|
| (4) |
高度な医療を受けられることにより、重度障害や失明等を回避できることによる損失の回避 |
|
| ■ |
原単位法
遠隔医療システムの導入により損失を回避できる確率の向上分×重度障害や失明等による損失額(原単位) |
|
| ■ |
対象地域における重度障害となる可能性のある患者数(年あたり)を調査 |
| ■ |
遠隔医療システムによる、損失回避確率の変化を調査 |
| ■ |
重度障害や失明等による損失額は障害者手当金、あるいは障害者賃金と健常者賃金との差、交通事故による障害の賠償額等を元に算定 |
|
| (5) |
高度な医療を身近な医療機関で受けられることによる安心感の向上 |
|
| ■ |
仮想評価法
(CVM:Contingent Valuation Method)
患者および家族へのアンケートにより、遠隔医療システムの導入に対する支払意思額(WTP)を調査 |
|
| ■ |
患者およびその家族へのアンケートにより遠隔医療システムの導入に対していくらであれば費用負担をしてよいか(支払意思額)について訊く |
| ■ |
((1)で調査した遠隔医療システムの診療・治療の対象者数)×(上記の支払意思額)により効果を計測 |
|
|
消費者余剰法は、交通施設整備の効果計測のために実務的に広く利用されている。たとえば、ある交通政策により移動のための一般化費用(=移動費用+移動時間×時間価値)が低下すると仮定する。このとき、一般化費用の低下により生じる消費者余剰(下図内解説参照)の増加分を便益として計測する手法が「消費者余剰法」である。
|
一方、1番目の財も、Q0番目の財も、実際の価格はP0円であることから、消費者の実際の支払総額は、0P0AQ0の面積となる。このとき、最高支払意思額と支払総額の差、三角形P0CAの面積を、均衡価格P0における消費者余剰という。 |
需要曲線は、消費者がその財(この場合、交通サービス)をなしですませるくらいなら支払ってもよいと考える最高支払意思額を表している。
図では、1番目の財の消費者は、C円までならこの財に支払ってもよいと考えている。同様に、Q0番目の財の消費者は、P0円までならこの財に支払ってもよいと考えている。よって、均衡価格がP0円であるときの、消費者のこの財に対する最高支払意思額の和は、台形OCAQ0の面積となる。 |
| 出典: |
赤井伸郎・金本良嗣(1999)「費用便益分析における地域開発効果」
(社会資本の費用効果分析に係る経済学的問題研究会『費用便益分析に係る経済学的基本問題』)を参考に建設政策研究センターで作成 |
図 消費者余剰法 |
代替法は、評価対象の事業と同等の便益をもたらす他の市場財の供給に必要な費用によって便益を計測する手法である。
代替法は、効用水準を維持するための支払意思額を代理の市場で計測しようとするものであるが、評価対象財そのものの市場ではないため評価値は正確には便益は言えず、便益の近似値として理解されるべきものといえる。
代替法は、直観的に理解しやすく、評価対象の非市場財に対して適切な代替財があり、また評価対象の非市場財の機能を代替するために必要な代替財の量が明確化できる場合には、有効な手法である。また一定の手法が確立すれば、評価者によらず安定的な計測結果を得ることができる。しかし、評価対象の非市場財を正確に代替しうる市場財が存在するケ−スは限られており、この代替財の選択如何で計測結果が変化することも多い。また代替財によって達成しようとする目標値を明確に設定しなければ適切な計測はできない。
代替法による計測の手順を以下に示す。
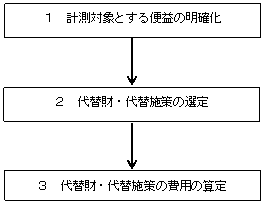
図 代替法
|
CVMとは,交通施設整備や医療機関の整備の便益を、個人や世帯が対価として支払ってもよいと考える金額(支払意思額)により評価する手法である。
CVMでは、経済単位を世帯あるいは個人とみなし、世帯・個人をベースとした便益評価を行う場合が多い。このため、具体的な便益計測においては、効果の及ぶ地域内から平均WTPの集計対象とする地域を設定し、アンケート調査等で計測した集計範囲内の一世帯当りWTPと、集計範囲内の世帯数(「集計世帯数」という)を把握し、両者の積を求め、それに効果の及ぶ期間(「評価期間」という)を乗じて便益を算定するという手法が取られる。
原単位法は、特定の便益計測手法が適用できない場合に、簡易に効果を計測することを主眼において適用される手法である。ある政策により変化する費用、あるいは便益を1人あたり、あるいは1日あたりなどの「原単位」としてまず計測し、それを受益対象者数に乗じて効果を計測する。
|
旭川医科大学の遠隔医療システムに関係した医師らに対して、次ページに示すようなアンケート調査を行った。 |
----遠隔医療システムの効果および今後の課題に関するアンケート----
1.遠隔医療システムの導入による効果として、「医療面の効果(医療の質の向上、早期発見・早期治療など)」、「患者アメニティ向上効果(患者の安心感・信頼感のアップなど)」、
「経済的な効果(患者・医師の移動費用の削減、インフォームドコンセントに 要する時間の短縮など)」、「その他」の4点について、考えられるものをご自由にご回答ください
<医療面での効果>
<患者アメニティ向上効果>
<経済的な効果>
<その他>
2.遠隔医療システムの今後の課題について、ご自由にご回答ください。
<運用上の課題>
<技術的な課題>
<その他> |
以下にアンケート結果について整理する。
| 効果\対象者 |
医師A |
医師B |
医師C |
|
地方医師のレベル維持、アップが期待できる |
診断に迷うときに専門医に遠隔診察していただくことにより、適切な助言を得ることができ僻地の医師個人にとっても自己のスキルアップになるだけでなく自分の診察に対してバックアップがあるという安心感につながり、僻地への赴任への抵抗感が減る可能性がある。当然、医療の質は向上し、判断に悩み悪化させてから専門医を受診させることも減り、早期治療につながる可能性がある。 |
大学病院レベルの高度先端医療を、医療過疎地、離島の住民にまで提供できる。 |
|
高度医療がある程度担保され、地域格差の縮小の可能性 |
その場にいながらにして専門医による診察を受けられることによる安心感が得られ、またその病院および医師への信頼も高まり不必要にドクターショッピングすることが減るなどの効果が期待される。 |
患者は、安心感を持ち、主治医と遠隔医療でであった医師の双方を信頼する。 |
|
装置が安価になれば、恩恵は大きい |
患者、医師ともに最低限の移動で済み、患者も不必要に何度も専門病院にいく必要がなく患者負担が減ると思われ、専門医も遠隔装置を通して患者を診察し話をできるため、遠方への出張を最低限に減らし時間的、費用的にも節約となることが期待される。 |
患者・医師の移動費用の削減、遺失利益の抑制、医療費の抑制、情報産業の活性化。 |
|
患者さんに対する”責任”が分散される効用 |
なによりも患者にとって遠くの専門医の診察と助言を得られることは僻地にいても必要な医療をうける機会が得られるという大きな安心感がえられる。 |
|
| 効果\対象者 |
医師A |
医師B |
医師C |
|
オンデマンドの体制の構築 |
遠隔をするためには遠隔をお願いする医師の協力と理解が必要。 |
環境整備(人、機器、システム)。中高年医師の情報機器使用再教育。診療科の特殊性を考えたシステム構築(産婦人科、精神科など)。 |
|
SLO等の機器との接続の可能性 |
通信インフラの整備が不可欠。(以前より敷居は低いが今回も礼文はADSLがないため設置できなかった。) |
インフラを医療過疎地にこそ整備する。利用者が優先順位を付けられる情報伝送システムの確立。 |
|
他の遠隔システムとの互換性 |
初期の設備投資がかかる。各拠点毎に設備投資が必要で各拠点への資金援助も含めた協力と理解が必要。将来的には各種の製品サポートのように、遠隔診療サポートセンターみたいなものがあって、診療に迷うとき、患者の要請があったとき、即座に遠隔診療を受けられる体制があれば大変便利。 |
|
| 効果\対象者 |
医師D |
医師E |
|
どこにいても均一の専門医レベルの医療が受けれると思います。島にいるから悪い医療を受けるといった、地域の格差がなくなると思いました。日本全国どこでも同じレベルの医療を受けれるというメリットを感じました。 |
上級医へのコンサルトにより精度の高い診断ができるとともに、自己研鑽に非常に役に立つ |
|
今回遠隔診療をして一番嬉しかったのが、執刀医に直接所見を見ていただけるという事です。外科系の世界では執刀していただいた先生の目を通し、患者さんを見ていただくことが大切だと思います。遠隔診療を通した執刀医からのアドバイスこそが患者さんにとっても一番納得がいき、かつ信頼される答えになっていると思います。 |
セカンドオピニオンが容易になる |
|
率直に結論を述べると今のところ削減できるものは何もないと思います。時間は私たち医師が費やしています。朝6時前には起き、船にゆられ、帰ってこれるのは20時頃。天候しだいによっては(私の場合に限りますが)週末は島ですごすことになっていしまいます。これは前項で述べることかもしれませんが・・・・。医者たった一人が頑張れば、その遠隔地で医療を受ける人間は救われるのです。 |
交通費の自己負担の軽減 |
|
やりがいがあります。患者さんが求めています。遠隔診療は何よりも患者様のためのものです。 |
|
| 効果\対象者 |
医師D |
医師E |
|
機器のアップデイトのコスト。医師にそれほど出張費を支払っていないのでこれが一番の問題ではないでしょうか。 |
各病院での予算上の交渉 |
|
今回はカメラ、音声を通してはとくに技術的な問題は感じませんでした。 |
遠隔地の場合マシントラブル時のエンジニア手配の難しさ |
|
患者さんの反響は大きいです。予約が一瞬で完売していました。
自分でもやりがいがありました。患者さんのためを思った親身になった医療であると思います。 |
|
| 効果\対象者 |
医師F |
|
1 自分の専門の科の診察をする場合あるいは同じ科でも専門分野が違う場合、病気の診断、あるいは患者を早急に移送する必要があるのかそうでないのかをみきわめる際に専門家からの助言は有用である。すなわち、医師のサイドからみても、その地域における医療の質の向上が見込めるのみならず、不要な患者の移送が避けられる。
2 遠隔地だと専門科のある大きな病院までに行くのに時間がかかるため、よほどの症状でない限り受診しない可能性がある。近くの施設で専門科の診察を受けることができるのであれば、受診がしやすくなり、疾患の予防、早期発見、早期治療に役立つと思われる。
3 大学病院等で行なった手術では、自分達の手術した患者のフォローを患者が地元に帰ったあとも継続して行なうことが可能である。そのため、患者データの管理が容易になり、結果のフィードバックが可能である。これは大学病院における医学研究・教育の面からも重要と思われる。 |
|
1 近隣に専門の医師がいないと受診しにくいが、これにより専門の医師の診察を容易に受けられる事になり、いつでも安心して受診できるようになる。
2 遠隔地で近隣に専門科の医師がいない場合、手術後早い退院の場合、不安のため長期の入院を希望する患者がいる。これにより、何かあった場合でも、すぐに診察を受けれるようになり、早期退院に対する不安が解消する。
3 自分の手術を執刀したドクターあるいは医療チームのフォローが受けられる。これは、自分の病状・経過をよく知っている医師にずっと見てもらえるため、安心感につながる。 |
|
1 患者の移動費用および受診のための休業による損失を軽減できる
2 早期退院に対する不安が解消することで、入院期間を短縮できるかもしれない。
3 医者の移動時間の削減
4 一度地元で診察し、次の病院を受診したのち、結局札幌・旭川の病院へ転送された場合を想定すると、同じ検査、診察を受けることで、医療費が余計にかかるのみならず、患者が同じような説明を複数回受ける事になり、これは、医療者側にとっても時間の重複になる。このシステムにより、これらのことが回避できる。
5 地元の病院で専門科の診察も受けることができるようになると、患者の受診機会が増え、症状の軽いうちあるいは症状が出る前に発見、治療ができるため、医療費の削減になるかもしれない。 |
|
|
| 効果\対象者 |
医師F |
|
初期投資費用
ランニングコストは誰が(どの施設が)支払うのか
複数の医師がかかわっているので、医療費はどのように分配するのか
診断の責任は、誰がとるのか
複数の医師で診断するとした場合、意見の相違があった場合どうするのか |
|
個人情報のセキュリティーの問題
画像の速度、鮮明度
立体画像の可能性
一般回線で可能かどうか
無線で可能であれば、遠洋漁業船あるいは空母などでも運用可能か?
遠隔操作による手術、処置 |
|
|
|
先に述べた5つの効果項目のうち、医師へのアンケート調査結果等から実際に効果として検証可能と考えられた以下の3つの項目について、利尻島−旭川医科大学等との間の遠隔医療システム導入の経済効果を計測する。 |
| (1) |
移動費用・宿泊費用節減 |
| (2) |
医療費の削減 |
| (3) |
高度な医療を受けられることにより早期に治癒し、復帰が早まることによる所得機会の増大 |
|
|
対象に、既存統計データおよび論文資料等を基に、経済評価手法の検証を行い、経済効果を試算する。
なお、これら3つの効果項目は最終的に貨幣換算することを念頭に検討するが、他にもQOLとして効果を計測する手法も考えられる。ただし、QOLはその適用範囲が非常に限定されている場合が多く、その調査にも多額の費用がかかるため、本調査では対象としない。 |
|
まず今回対象とする疾患は以下の2つとする。
既往論文「利尻島における高頻度の屈折異常」(高井佳子、五十嵐羊羽、佐藤慎、島本恵美、石子智士、木ノ内玲子、長南兼太郎、野村秀樹、下方浩史、吉田晃敏著、臨床眼科Vol.58 No.9、特集 第 57 回日本臨床眼科学会講演集(7))によれば、2002年の利尻島における眼科検診(対象者253名、平均64.4歳)の結果、疾患別の頻度は白内障51.7%、緑内障6.9%、糖尿病網膜症4.4%、網脈絡膜萎縮4.0%などとなっており、これら2つの疾患は代表的かつ遠隔医療システム導入による効果が大きいものと考えられることから、選定した。 |
さらに、効果の試算にあたっては、データの制約のため、以下の仮定を置くこととした。
| ○ |
論文「利尻島における高頻度の屈折異常」によれば、眼科検診の対象者中、白内障の頻度51.7%、網膜症の頻度が4.4%となっている。 |
| ○ |
ここでの眼科検診の対象者は60歳以上が7割強を占める |
| ○ |
よって、この疾患の頻度は概ね60歳以上の頻度と想定してよいと考えられる。 |
| ○ |
そこで、利尻町、利尻富士町の60歳以上人口2,564人(平成12年国勢調査結果)に上記の比率をかけたものを対象患者数とし、これらの患者全員の治療するためにかかる費用を遠隔医療システム有無それぞれの場合で計算し、その差をとることで効果を計測した。 |
|
なお、厳密には利尻島における毎年の発症者数を元に効果を試算することが望ましいが、そのためにはより精確な疫学調査を利尻島で行い、利尻島の全体平均的な発症者数等を把握する必要がある。今回はデータ制約のため、上記の方法で、まず現状の60歳以上の患者数のみを対象として効果を試算する。したがって、以下で計測される効果は比較的安全側の試算結果と言うことができる。
参考図 利尻町・利尻富士町の年齢分布
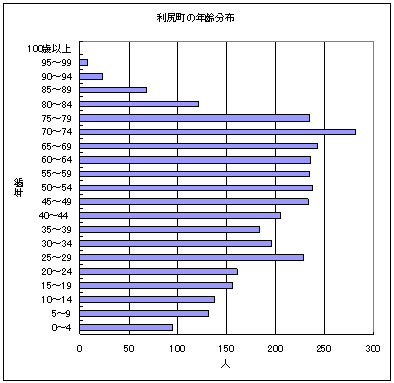 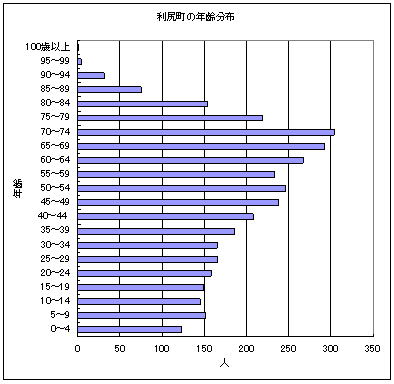
資料:国勢調査(平成12年) |
白内障患者の治療までのパスを次ページのように想定する。これは、遠隔医療システムに関係する医療関係者のこれまでの診療経験等に基づいて設定した。
|
<遠隔医療システムが無い場合の診療⇒治療までのパス>
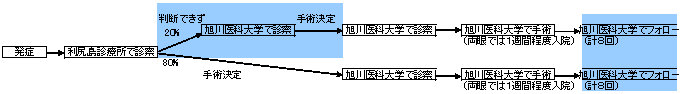
<遠隔医療システムがある場合の診療⇒治療までのパス>
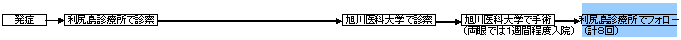 |
|
遠隔医療システム導入による患者の移動費用・宿泊費用節減は、以下の部分で起こる。
| ・ |
遠隔医療システムにより、旭川医大の医師が利尻島診療所に訪れた患者を診ることができるため、利尻島で判断に迷うことがなく、手術が必要であれば直接旭川医大に送ることができる |
| ・ |
フォローをすべて利尻島診療所で行うことができる。 |
|
効果計測のためのデータを以下に整理する。 |
| データ項目 |
遠隔医療システムなし |
遠隔医療システムあり |
| 1人あたり移動費用(片道) |
稚内〜鴛泊間1,880円
稚内〜旭川間8,070円
旭川駅〜旭川医科大学(タクシー)1,600円 |
0円※1 |
| 移動時間(片道) |
稚内〜鴛泊間100分
稚内〜旭川間217分
旭川駅〜旭川医科大学(タクシー)15分 |
0分※1 |
| 1人あたり宿泊費用(1泊) |
5,000円 |
0円 |
| 対象患者数(白内障) |
1,326人 |
1,326人 |
| ※1: |
厳密には、利尻島内の診療センターまでの費用・時間がかかるが、ここでは無視できるものとした。 |
| ※2: |
旭川周辺のビジネスホテルのシングル1泊料金を元におよそ5,000円と設定。 |
| ※3: |
移動費用・移動時間の出典は以下のとおり(途中の徒歩の時間、待ち時間等は含まず) |
| 稚内〜旭川間:JR特急スーパー宗谷 |
片道 8,070円(乗車券5,250円 特別料金2,820円)
乗車時間217分 |
|
ここで、患者1人につき付き添いが1人いると仮定し、さらに時間価値を北海道の平均賃金率データ(平成15年毎月勤労統計調査)より32.84円/人・分と設定すると、効果は以下のように試算できる。合計で約11億円の効果が期待される。 |
【事前の診察時】
移動費用・宿泊費用削減効果
=対象患者数(白内障)×20%×([1人あたり移動費用(片道)+移動時間(片道)×時間価値]×2+1人あたり宿泊費用(1泊)×1)×2=3,194(万円)
【フォロー時】
移動費用・宿泊費用削減効果
=対象患者数(白内障)×([1人あたり移動費用(片道)+移動時間(片道)×時間価値]×2+1人あたり宿泊費用(1泊)×1)×2×8=105,851(万円) |
【参考:時間価値の設定】
「平成15年毎月勤労統計調査地方調査−統計表」(北海道)の「第1−1表 産業別常用労働者1人平均月間現金給与額(現金給与総額)−規模5人以上−」より、平成15年の平均月間給与額は調査産業計で304,647円。一方、同調査の「第4−1表 産業別常用労働者1人平均月間出勤日数及び労働時間数−規模5人以上−」より、平成15年の平均月間総実労働時間は154.6時間。これより、時間価値は以下のように計算できる。
時間価値=304,647円÷154.6時間÷60=32.84円/分 |
|
遠隔医療システム導入による医療費の削減は以下の部分で起こる。
| ・ |
遠隔医療システムにより、旭川医大の医師が利尻島診療所に訪れた患者を診ることができるため、利尻島で判断に迷うことがなく、手術が必要であれば直接旭川医大に送ることができる→旭川医大での診療費1回分が減少する |
|
1回あたりの診療費は以下の各検査項目の診療報酬点数より、3,450円と算出できる。
表 検査1回あたりの診療費の算出
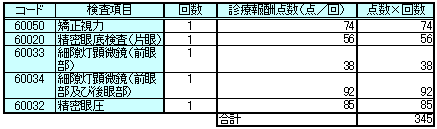 |
したがって医療費削減効果は以下のように計測できる。 |
医療費削減効果
=対象患者数(白内障)×20%×3,450円=91(万円) |
| (3) |
高度な医療を受けられることにより早期に治癒し、復帰が早まることによる所得機会の増大 |
|
白内障の場合は、遠隔医療システムにより高度な医療を早い時期に受けられることにより、手術日数が短くなるといった効果はそれほど大きくないと考えられる。そこで、白内障患者についてはこの効果は試算しない。 |
糖尿病網膜症については、「単純網膜症」「増殖前網膜症」「増殖網膜症」の3パターンに分けて治療までのパスを想定した。これは、遠隔医療システムに関係する医療関係者のこれまでの診療経験等に基づいて設定した。
なお、糖尿病網膜症のうち、この3パターンの比率はこれまでの診療経験等に基づき
「単純網膜症:増殖前網膜症:増殖網膜症」=2:4:4 と想定した。
| (A) |
単純網膜症のケース
<遠隔医療システムが無い場合の診療⇒治療までのパス>
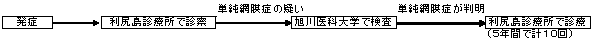
<遠隔医療システムがある場合の診療⇒治療までのパス>
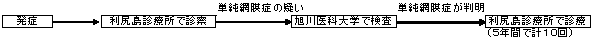 |
| (B) |
増殖前網膜症のケース
<遠隔医療システムが無い場合の診療⇒治療までのパス>
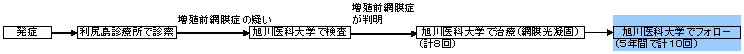
<遠隔医療システムがある場合の診療⇒治療までのパス>
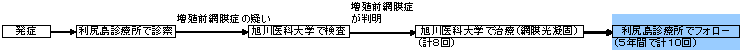 |
| (C) |
増殖網膜症のケース
<遠隔医療システムが無い場合の診療⇒治療までのパス>
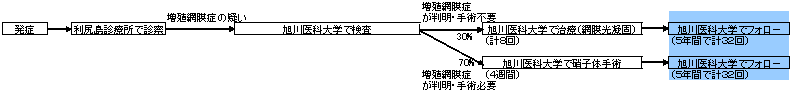
<遠隔医療システムがある場合の診療⇒治療までのパス>
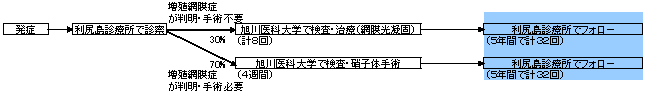 |
|
遠隔医療システム導入による患者の移動費用・宿泊費用節減は、以下の部分で起こる。
| ・ |
フォローをすべて利尻島診療所で行うことができる。 |
|
|
| データ項目 |
遠隔医療システムなし |
遠隔医療システムあり |
| 1人あたり移動費用(片道) |
稚内〜鴛泊間1,880円
稚内〜旭川間8,070円
旭川駅〜旭川医科大学(タクシー) 1,600円 |
0円※1 |
| 移動時間(片道) |
稚内〜鴛泊間100分
稚内〜旭川間217分
旭川駅〜旭川医科大学(タクシー)15分 |
0分※1 |
| 1人あたり宿泊費用(1泊) |
5,000円 |
0円 |
| 対象患者数(増殖前網膜症) |
45人 |
45人 |
| 対象患者数(増殖網膜症) |
45人 |
45人 |
| ※1: |
厳密には、利尻島内の診療センターまでの費用がかかるが、ここでは無視できるものとした。 |
| ※2: |
旭川周辺のビジネスホテルのシングル1泊料金を元におよそ5,000円と設定。 |
| ※3: |
単純網膜症の場合は、遠隔医療システム有無で診療パスが変化しないため、効果は発現しない。 |
|
ここで、患者1人につき付き添いが1人いると仮定し、さらに時間価値を北海道の平均賃金率データ(平成15年毎月勤労統計調査)より32.84円/人・分と設定すると、効果は以下のように試算できる。合計で約1億9千万円の効果が期待される。 |
【増殖前網膜症】
移動費用・宿泊費用削減効果
=対象患者数(増殖前網膜症)×([1人あたり移動費用(片道)+移動時間(片道)×時間価値]×2+1人あたり宿泊費用(1泊)×1)×2×10=4,504(万円)
【増殖網膜症】
移動費用・宿泊費用削減効果
=対象患者数(増殖網膜症)×([1人あたり移動費用(片道)+移動時間(片道)×時間価値]×2+1人あたり宿泊費用(1泊)×1)×2×32=14,414(万円)
合計=4,504(万円)+14,414(万円)=18,918(万円) |
|
これは(C)増殖網膜症のみに発現すると考えられる効果である。
| ・ |
増殖網膜症であることを、遠隔医療システムによる1回の診察で確定することができるため、約3ヶ月ほど早く手術を行うことができ、それにより在院日数を短縮することができるため、医療費も削減される。 |
|
ここで、その医療費削減効果を試算するために、旭川医科大学の2004年のDPCデータを用いて、糖尿病性増殖性網膜症で入院した28件について、国が定めた平均在院日数(入院期間2)を境に2群に分け、それぞれ、患者1入院当たりの入院日数、医療費を算出した。
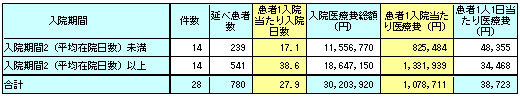
この表により、医療費削減効果は以下のように計測できる。 |
医療費削減効果
=対象患者数(増殖網膜症)×手術が必要となる確率(70%)×(1,331,939−825,484)円=1,600(万円) |
| (3) |
高度な医療を受けられることにより早期に治癒し、復帰が早まることによる所得機会の増大 |
|
これも(C)増殖網膜症のみに発現すると考えられる効果である。
| ・ |
増殖網膜症であることを、遠隔医療システムによる1回の診察で確定することができるため、約3ヶ月ほど早く手術を行うことができ、それにより在院日数も短縮できるため、3ヶ月+在院日数の分、早く社会復帰が可能となり、働いて所得を得たり、余暇を楽しむことができる。 |
|
ここで、1日あたりの所得を北海道の平均賃金率データ(平成15年毎月勤労統計調査)より14,861円/人・日と設定し、余暇の価値もこれと等しいと仮定すると、効果は以下のように試算できる。 |
所得機会の増大効果
=対象患者数(増殖網膜症)×手術が必要となる確率(70%)×(90日+38.6日−17.1日)=5,234(万円) |
【参考:1日あたり所得の設定】
「平成15年毎月勤労統計調査地方調査−統計表」(北海道)の「第1−1表 産業別常用労働者1人平均月間現金給与額(現金給与総額)−規模5人以上−」より、平成15年の平均月間給与額は調査産業計で304,647円。一方、同調査の「第4−1表 産業別常用労働者1人平均月間出勤日数及び労働時間数−規模5人以上−」より、平成15年の平均月間出勤日数は20.5日。これより、1日あたり所得は以下のように計算できる。
1日あたり所得=304,647円÷20.5日=14,861円/日 |
|
これまでの試算結果を下表にまとめる。合計でおよそ13億6千万円の経済効果が得られることがわかる。
表 試算結果のまとめ
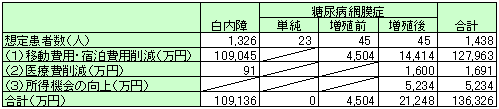 |
一方、遠隔医療システムのリース料は6ヶ月で約250万円程度であるため、20年稼働させたとしてもリース料は約1億円である。当然ながらその他に利尻島へ医師が出向く費用、複数の医師で診察する費用などがかかるが、それを考慮してもこの遠隔医療システムは社会的に効率的なシステムである可能性が示唆される。 |
| ■ |
遠隔医療システムに関わる医師へのアンケート等により、その効果と今後の課題について概略を把握できた。特に、3〜4地点で同一の患者を診察した場合の診断の責任の所在、あるいは費用の分担について検討していくことが喫緊の課題であることが示唆された。 |
| ■ |
限られたデータの元ではあるが、いくつかの仮定のもとで今回の遠隔医療システム導入の経済効果を試算することができた。その経済効果は約13億6千万円となり、導入費用を大きく上回る可能性が示唆された。ただし、これは多くの仮定の元での試算値であり、今後これらの仮定の妥当性等、現実性等について十分に精査検討する必要がある。
また、今後の課題としては、以下のようなものが考えられる。
|
| ■ |
今回計測できなかった「高度な医療技術を受けられる状況にあることによる安心感の向上」などを貨幣タームで計測すること。 |
| ■ |
遠隔医療システムの本格導入に向けて、制度的な課題を整理し、円滑なシステム運用に資する制度の変更に向けた検討を行うこと |