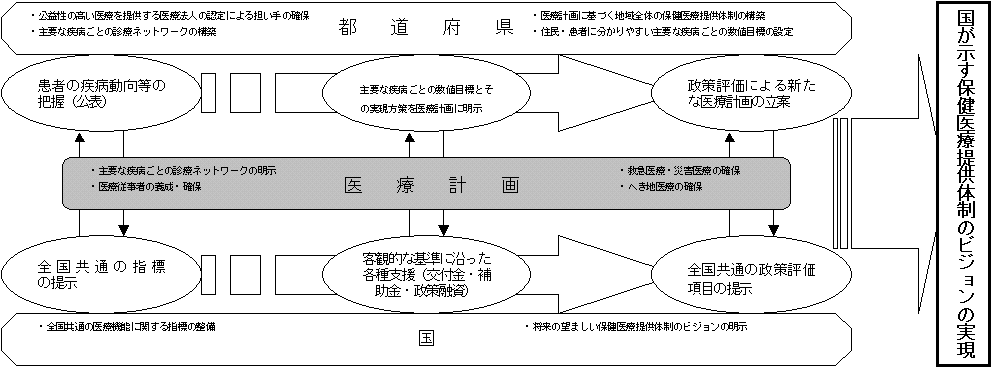医療計画を通じた
国と都道府県の役割の見直し
国が示す保健医療提供体制のビジョンの実現
|
【 国の役割と責務:保健医療提供体制のビジョンの実現 】
| ◇ | がんについて | → | 研究、予防及び医療を総合的に推進し、がんの罹患率と死亡率を激減させること |
| ◇ | 脳卒中について | → | 健康増進、予防及び入院治療から在宅復帰までの医療を日常医療圏に構築すること |
| ◇ | 小児救急を含む小児医療について | → |
| (1) | 子どもがいつでも適切な医療を受けられるよう小児救急医療体制をすべての日常医療圏に構築すること |
| (2) | 小児医療施設の役割分担と連携を推進し、小児科医師の適正な配置を図ること など |
|
|
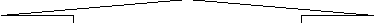
|
【 国が担うべき事務:全国共通した主要な疾病ごとの指標の提示 】
| ☆ | 都道府県が当該日常医療圏の適切な医療資源を把握しやすいよう、国が患者の疾病動向等に関する全国共通の指標を提示
 |
┌
|
|
|
└ |
| ・ | 全国共通の指標によって都道府県の医療機能、患者の疾病動向等が明確になることにより、質の高い医療提供体制の構築に向けた実効性のある都道府県の政策が期待 |
| ・ | 客観的な基準による各種支援(交付金・補助金・政策融資など)による政策の透明性の向上 |
| ・ | 政策評価による翌年度につながる都道府県の医療計画の見直し |
|
|
|
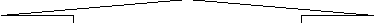
|
【 国による調査の実施:全国規模の主要な疾病ごとの医療機能調査の実施 】
| ☆ | 全国規模の医療機能調査を実施し、主要な疾病ごとに必要な医療機能を明らかにする
┌
|
|
└ |
| ・ | 全国規模の医療機能調査によって把握したデータの公表 |
| ・ | すべての国民が当該情報を活用できるような環境の整備 |
|
┐
|
|
┘ |
|
|
|
|
|
| ※ | 日常の生活において、原則として、主要な疾病ごとに患者が必要とする外来医療及び入院医療が完結する圏域を「日常医療圏」という。 |
|
医療計画によって都道府県が推進する質の高い効率的な保健医療提供体制の構築
|
【 都道府県の役割と責務:質の高い効率的な保健医療提供体制の構築 】
| ◇ | がんについて(例) | → | がんの死亡率を○○%改善 |
| ◇ | 脳卒中について(例) | → | 脳卒中患者の在宅復帰率を○○%増加 |
| ◇ | 小児救急を含む小児医療について(例) | → | すべての日常医療圏で24時間いつでも初期救急医療を含む小児医療を受診できる体制を構築 など |
|
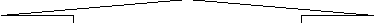
|
【 都道府県が担うべき事務:主要な疾病ごとの診療ネットワークを構築し医療計画に明示すること 】
| ☆ | 都道府県が当該日常医療圏に必要な医療資源を把握し、主要な疾病ごとの診療ネットワークを構築すること。
 |
┌
|
|
|
└ |
| ・ | 都道府県が全国共通の指標によって医療機能、患者の疾病動向等を明確にし、その結果を住民に公表 |
| ・ | 主要な疾病ごとに明確になった結果を踏まえ、あるべき保健医療提供体制の構築について各種支援(診療ネットワークの核となる医療機関の指定・交付金・補助金・政策融資など)を実施 |
| ・ | 政策評価の実施による翌年度につながる医療計画の見直し |
|
|
|
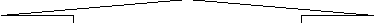
|
【 都道府県による医療機能調査の実施:主要な疾病ごとの医療機能調査の結果を公表すること 】
| ☆ | 国が示す全国共通の指標に沿って医療機能調査を実施し、主要な疾病ごとの適切な医療機能を明らかにする
┌
|
|
└ |
| ・ | 都道府県の医療機能調査によって把握したデータの公表 |
| ・ | すべての住民が当該情報を活用できるような環境の整備 |
|
┐
|
|
┘ |
|
|
|
|
|
| 数値目標によって住民・患者に分かりやすい医療計画制度の推進による医療の質の向上 |
┌
|
|
|
|
|
|
|
|
|
└ |
| (1) | 国として将来のあるべき保健医療提供体制のビジョンを提示するとともに、都道府県が当該日常医療圏に必要な医療資源を把握できるよう、患者の疾病動向等に関する全国共通の指標を提示。 |
| (2) | 都道府県は、国の提示する指標を基に医療ニーズと既に有する医療資源を把握し、その状況を公表。あわせて、今後あるべき医療を推進するための数値目標を医療計画に明示。 |
| (3) | 都道府県は数値目標の達成に向けた具体的な方策を医療計画で立案し、住民に公表。 |
| (4) | 国は数値目標が明示された都道府県の医療計画や現状の都道府県の医療資源、患者の疾病動向等を勘案し、客観的な基準に沿って各種支援を実施。 |
| (5) | 国が示す全国共通の政策評価項目に従って、都道府県は数値目標と現況を比較し、新たな医療計画を立案(見直し)。 |
|
┐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
┘ |
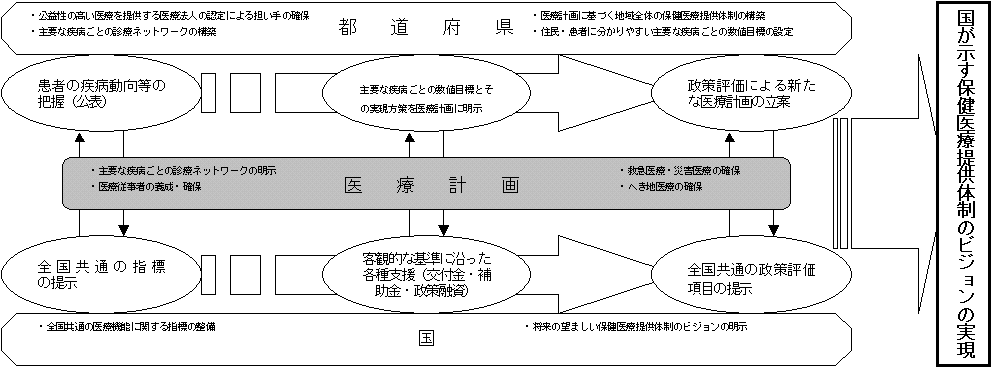
医療計画の作成に係る国と都道府県の役割の見直しに伴う新しい保健医療行政の姿(イメージ)
〜 都道府県の裁量性の向上と望ましい保健医療提供体制の構築に向けた国による支援との両立(共働) 〜
| 医 | 医療法第30条の4:厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。 |
| ◇ | 現行の国の医療政策に関する役割についての課題
| → | 医療法が定める良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に関する国の責務に対する具体的な役割が不明確。 |
| → | 今後、量だけでなく質を重視した効率的な医療提供体制に重点化する中で、質の高い効率的な医療提供体制に関する国の基本的な政策を法律上明確にする必要性が高まっていること。 |
| → | 透明性の高い客観的な政策誘導を行うことが求められていること。 |
|
|
| ◇ | 医療計画制度をめぐる課題
| (1) | 主な疾病ごとに医療機能が明示されていないこと |
| (2) | 都道府県が住民に対し中長期的な医療提供体制の目標と手順を示したものではないこと |
| (3) | 都道府県が具体的な数値目標を設定しそれを住民が評価ができるものとなっていないこと |
|
|
|
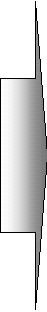 |
| ○ | 厚生労働大臣は、国民に対し安全安心で良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な方針(基本方針)を定める。 |
| ○ | 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県における医療計画を定める。 |
| ◇ | 今後特に求められる都道府県の役割
| (1) | 具体的な数値目標の設定と政策評価による実効性・透明性の高い医療提供体制の構築 |
| (2) | 医療機能の分化・連携を通じた効率的で良質な保健医療提供体制の構築 |
| (3) | 自由度の高い交付金・補助金による都道府県の裁量性の発揮 |
|
| → | 国は都道府県の保健医療提供体制を情報面と財政面で強力に支援。 |
|
医療計画の策定及びその実施状況の政策評価に関する基本的な事項(案)
| → | 都道府県に対し以下の内容を要請。
| (1) | 主要な疾病ごとの医療機能についての状況把握 |
| (2) | 保健医療提供体制の量的・質的な数値目標の設定 |
| (3) | 数値目標に関する達成状況に係る政策評価の実施 |
|
|
|