| 第11回厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会 |
資料 1−1 |
| 平成17年3月24日 |
医薬品販売制度改正検討部会において整理された検討項目2「医薬品の販売に当たっての必要な情報提供等」を議論するにあたり、詳細に検討する必要がある事項や留意する必要がある事項等について、次の頁以降、各論点ごとに掲げた。
《目次》
| 1. | 情報提供の内容
|
|||||
| 2. | 情報提供の手法
|
|||||
| 3. | 販売後の副作用発生時等への対応
|
|||||
| 4. | 医薬品の管理
|
1.情報提供の内容
|
| (1) | 情報提供が必要な場面 「どのような場面」を消費者側からみた場合、以下のような具体的な場面が考えられるが、それ以外にもあるか。
|
||||||||||||||
| (2) | 提供すべき情報の内容 「どのような情報提供」としては、医薬品の適正使用を確保する観点から次の情報が考えられるが、(1)のそれぞれの場面に応じて、どの情報が必要となるか。
|
|
|
||||
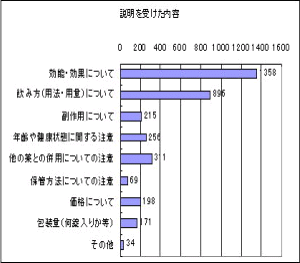 |
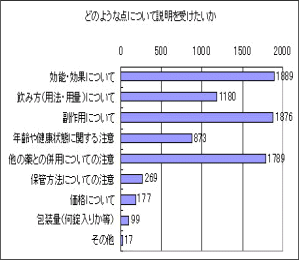 |
||||
|
|
||||
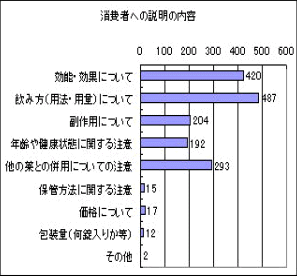 |
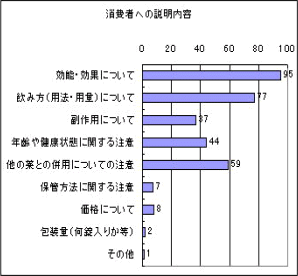 |
||||
|
|
||||
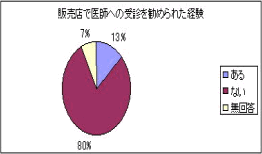 |
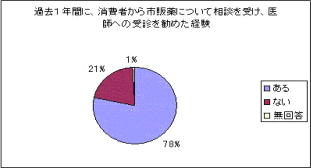 |
|
| ○ | 医薬品のリスクの程度と情報提供のあり方の関係
|
《参考》
| ○ | 薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について(昭和三三年五月七日)(薬発第二六四号)(抄) |
| 第 | 一 薬局の業務について
|
||||||||||||
| 第 | 四 医薬品販売業の業務について
|
| ○ | 薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について(平成一〇年一二月二日)(医薬発第一〇四三号)(抄) |
また、医薬品を一般に購入し、又は使用する者(以下「購入者等」という。)に対する情報提供については、平成八年の薬事法改正により薬局開設者及び医薬品販売業者の努力義務とされ、昨年四月より施行されたところであるが、その販売に際して薬剤師による情報提供が特に求められている医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)について、薬局等における情報提供等が十分行われていない場合があるとの指摘がなされているところである。
このため、「薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について」(昭和三三年五月七日薬発第二六四号)の薬局開設者の遵守すべき事項等を左記の趣旨により別添のとおり改正するので、貴管下関係業者への周知徹底方お願いする。
| 1 | (略) |
| 2 | 薬局等の開局中又は開店中は、薬剤師を薬局等に常時配置し、医薬品の販売に当たり、購入者等に対し、医薬品の適正な使用のために必要な情報を提供すること。 |
| 3 | 特に、承認後一定期間の市販後調査を課すとともに薬事法第二九条に規定する指定医薬品とされた医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)については、薬剤師が積極的に医薬品の適正使用に必要な情報提供及び副作用情報の収集等を行うこと。 |
| 4 | (略) |
|
| (1) | 消費者の病歴等を確認する必要性 消費者への情報提供や相談対応のためには、必要に応じて、消費者の病歴、副作用歴を確認する必要があるのではないか。 |
| (2) | 個人情報に配慮した情報提供のあり方 病歴や副作用歴を確認する必要がある場合としては、適応禁忌や併用禁忌に注意を要する医薬品を販売する場合等が想定されるが、禁忌等に関する注意喚起の方法として、個人情報に配慮するのであれば、消費者に病歴等を確認する方法のほか、特定の病歴等を有する者は禁忌である旨等を消費者に説明することや表示するといった方法もあるのではないか。 |
|
| ○ | 製造業者や国から販売店に提供する情報の内容 販売事業者が消費者への適切な情報提供を行うためには、製造業者が作成する添付文書以外に、製造業者や国が販売事業者に情報を提供する必要があるか。 (資料1−2を参照のこと。) |
|
| ○ | 提供すべき情報の更新の方法 新しい知見に基づき、提供すべき情報の追加・修正はどのように行われるべきか。 (資料1−2を参照のこと。) |
2.情報提供の手法
|
| (1) | 情報提供の手法 情報提供の手法には、どのようなものがあるか。 (情報提供の手法の例)
|
||||||||||
| (2) | 消費者自らの情報の入手 情報通信技術の活用により、消費者が販売事業者以外から情報を入手できるような仕組みが必要ではないか。 |
||||||||||
| (3) | 医薬品のリスクの程度と情報提供の手法との関係 医薬品のリスクの程度に応じて、必要な情報提供の手法に違いがあり得ると考えてよいか。 |
|
| (1) | 販売に従事する者が行う情報提供の方法 販売時に、販売に従事する者が行う情報提供の方法は、これまで以下のように整理しているが、具体的な場面における提供方法についてどのように考えるか。
|
||||||
| (2) | 積極的に行う情報提供の方法 積極的な情報提供をしようとした場合に、すでに同じ医薬品について過去に情報提供を受けたことがあるなどの理由により、消費者が情報提供を受けることが不要であると意思表示したときは、積極的に行う情報提供は省略してもよいか。 |
||||||
| (3) | 情報提供の機会を確保するための医薬品の陳列のあり方 専門家による消費者への情報提供の機会を確保するための医薬品の陳列のあり方(例:オーバー・ザ・カウンター)について、どう考えるか。 (検討項目2の(4)医薬品の管理の論点(2)に同じ) |
《参考》
| ○ | 薬事法の一部を改正する法律の施行について(昭和五〇年六月二八日)(薬発第五六一号)(抄) |
なお、第一――薬局等の管理態勢の適正化及び第二――医薬品の販売態勢の適正化及び不良医薬品の監視対策の強化については、新規参入の薬局等に対して特に留意するとともに、都道府県の薬剤師会、薬種商協会等関係団体が行う自主点検についてはその効果があがるよう指導されたい。
| 第 | 一 薬局等の管理態勢の適正化について (略) | ||
| 第 | 二 医薬品の販売態勢の適正化及び不良医薬品の監視対策の強化について
|
|
|
||||
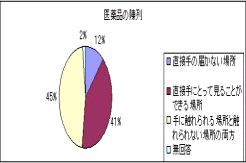 |
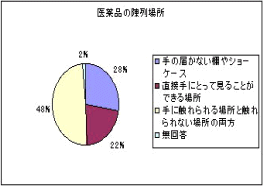 |
||||
|
|
||||
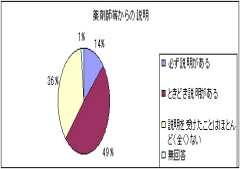 |
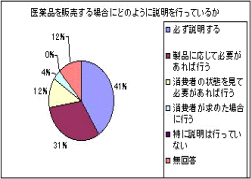 |
||||
|
|
||||
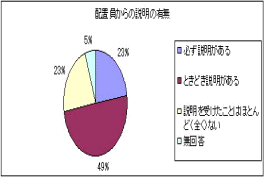 |
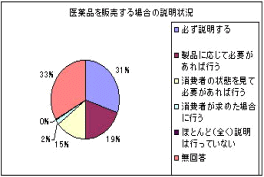 |
|
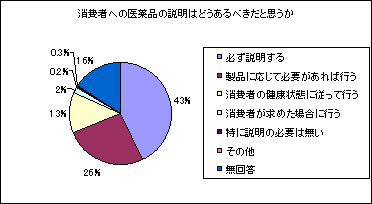
|
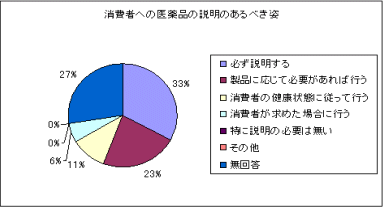
3.販売後の副作用発生時等への対応
|
| (1) | 副作用の重篤化の防止 副作用が発現した場合、副作用による健康被害を最小限に止めるため、早期の発見・受診等を促すにはどのような対応が必要か。 |
||||||
| (2) | 副作用の拡大の防止 副作用が発現した場合、一般消費者に副作用が拡がることを防止するには、どのような対応が必要か。 |
||||||
| (3) | 副作用の救済に関する情報提供 副作用の救済に関し、消費者に対してどのように情報提供を行うべきか。 消費者に対し、医薬品の購入前にそれが副作用救済制度の対象か否かを明らかにする必要があるか。 |
||||||
| (4) | 副作用に関する対応を行うべき者の知識・技能 副作用が発現した場合に、消費者からの相談に対応し、必要に応じ国へ副作用報告(使用方法、副作用の発現状況・処置等の経過の報告)を行うために必要な知識・技能は、どのようなものか。 |
||||||
| (5) | 副作用報告を行うべき者の範囲 副作用報告は、薬事法第77条の4の2第2項に基づき、医師、歯科医師、薬剤師及び薬局開設者等の医薬関係者に義務づけられているが、副作用報告を行うべき者の範囲についてどう考えるか。 |
||||||
| (6) | 副作用情報の消費者への周知方法 販売した医薬品に関して、新たな緊急の副作用情報があった場合、その医薬品を購入した消費者や購入しようとする消費者へ周知するにはどのような方法があるか。 (周知方法の例)
|
《参考》
| ○ | 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄) (副作用等の報告) |
| 第 | 七十七条の四の二 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具の製造業者若しくは輸入販売業者又は外国製造承認取得者若しくは国内管理人は、その製造し、若しくは輸入し、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具について、当該品目の副作用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
| 2 | 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品又は医療用具について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
|
| (1) | 販売後の使用方法等に関する相談への対応 販売後に消費者から使用方法等に関する問い合わせについては、店頭での対応のほか、電話、電子メール等による相談も想定されるが、それぞれについてどのような対応をとることが適切か。 |
| (2) | 他店舗で販売された医薬品に関する対応 消費者からの問い合わせがあった医薬品が、当該店舗において取り扱っている品目ではなかった場合であっても、対応する必要があるか。 |
《参考》
|
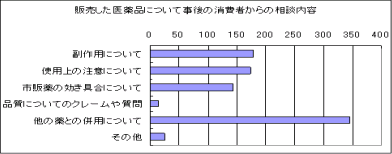
|
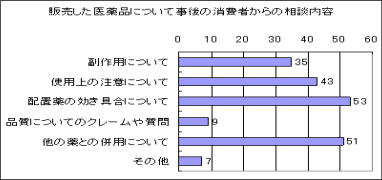
4.医薬品の管理
|
| (1) | 医薬品の管理の方法等 医薬品の管理はどのように行うべきか。また、医薬品の管理を行うためには、特別な知識・技能が必要か。必要な場合、具体的にどのような知識・技能が必要となるか。 (医薬品の管理業務の具体例)
|
||||||||||
| (2) | 構造設備の管理、従業員の監督 医薬品の管理のほか、構造設備の管理、従業員の監督の業務は、どのように行うべきか。 |
《参考》
|
|
||||
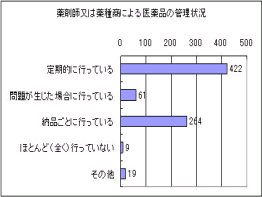 |
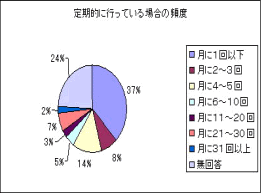 |
||||
|
|
||||
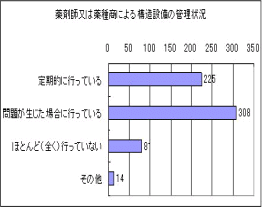 |
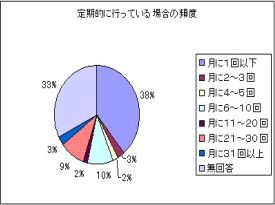 |
||||
|
|
||||
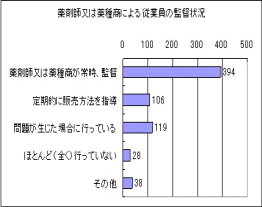 |
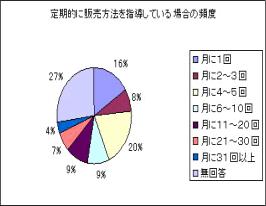 |
||||
|
|
||||
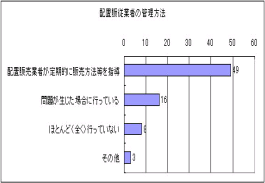 |
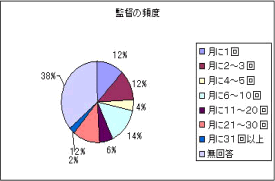 |
| ○ | 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄) (薬局の管理) |
| 第 | 八条 第五条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。 |
| 2 | 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。 |
| 3 | (略) (管理者の義務) |
| 第 | 九条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。 |
| 2 | 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。 (準用) |
| 第 | 二十七条 一般販売業の業務の管理については、第八条から第九条の二までの規定を準用する。(以下、略) (配置員に対する指導監督) |
| 第 | 三十四条 配置販売業者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、配置販売の業務に関し、その配置員を指導し、監督しなければならない。 |
| ○ | 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)(抄) (医薬品の管理) |
| 第 | 十条 薬局の管理者は、医薬品を他の薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。 (薬局の管理に関する帳簿) |
| 第 | 十一条の二 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 |
| 2 | 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。 |
| 3 | 薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 (準用) |
| 第 | 二十九条の三 一般販売業の許可を受けた者については、第二条から第七条まで、第十条から第十二条まで及び第十三条(卸売一般販売業の許可を受けた者であつて、法第二十六条第三項ただし書の許可を受けていないものについては、第十二条第一項第一号の二及び第七号を除く。)の規定を準用する。(以下、略) (薬種商の義務) |
| 第 | 三十五条 薬種商は、実地にその店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他薬種商販売業の業務につき保健衛生上支障を生ずるおそれがないようにしなければならない。 |
| 2 | 薬種商は、医薬品を他の薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。 |
| ○ | 薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について(昭和三三年五月七日)(薬発第二六四号)(抄) |
| 第 | 一 薬局の業務について
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 |
|
| ○ | 薬事法の施行について(昭和三六年二月八日)(薬発第四四号)(抄) |
なお、この通知において、薬事法を「法」と、同法施行令(昭和三六年政令第一一号)を「令」と、同法施行規則(昭和三六年厚生省令第一号)を「規則」と、薬局等構造設備規則(昭和三六年厚生省令第二号)を「構造設備規則」と、薬事法(昭和二三年法律第一九七号)を「旧法」と、薬事法施行規則(昭和二三年厚生省令第三七号)を「旧規則」とそれぞれ略称する。
| 第 | 三 薬局に関する事項 |
| 1 | ・2 (略) |
| 3 | 法第八条の管理に関する規定は、開局中は常時直接管理の状態にあることを原則とし、いわゆる名義貸し等の事態を強く禁止する趣旨であること。(以下、略) |
| 4 | 規則第一一条の業務日誌には、試験記録、事故品の処理状況等のほか、管理者の勤務の状況等その他の薬局の管理に関し必要な事項を記載させるものとすること。 |
| ○ | 薬局業務運営ガイドラインについて(平成五年四月三〇日)(薬発第四〇八号) 今般別紙のとおり「薬局業務運営ガイドライン」を定めたが、その趣旨、運用上の留意事項等は左記のとおりなので、御了知のうえその運用に遺憾のないよう配慮されたい。 |
| 1 | 〜2 (略) |
| 1 | 〜3 (略) |
| 4 | 構造設備 |
| (1) | 地域保健医療を担うのにふさわしい施設であること。特に清潔と品位を保つこと。 |
| (2) | 薬局等構造設備規則に定められているほか、処方せん応需の実態に応じ、十分な広さの調剤室及び患者の待合に供する場所(いす等を設置)等を確保するよう努めること。 |
| (3) | 患者のプライバシーに配慮しながら薬局の業務を行えるよう、構造、設備に工夫をすることが望ましい。 |
| (4) | 薬局は利用者の便に資するよう、公道に面していること。 |
| 5 | 開設者 |
| (1) | 開設者は、医療の担い手である薬剤師であることが望ましい。 |
| (2) | 開設者は薬局の地域保健医療の担い手としての公共的使命を認識し、薬事法、薬剤師法等の関係法令及びガイドラインに従った薬局業務の適正な運営に努めること。 |
| (3) | 開設者は薬局の管理者が薬事法第九条に規定する義務及びガイドラインを守るために必要と認めて述べる意見を十分尊重しなければならない。 |
| (4) | 開設者はその薬局に勤務する薬剤師等の資質の向上に努めなければならない。 |
| (5) | 開設者は、地域薬剤師会が地域の保健医療の向上のため行う処方せん受け入れ体制の整備等の諸活動に積極的に協力すること。 |
| (6) | 開設者は薬局の業務運営について最終的な責任を負う。 |
| 6 | 管理者 |
| (1) | 薬局の管理者は、ガイドラインに従った薬局業務の適正な運営に努めるとともに、保健衛生上支障を生ずる恐れがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従事者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。 |
| (2) | 薬局の管理者は、前項の管理者の義務を遂行するために必要と認めるときは、開設者に改善を要求しなければならない。 |
| 7 | (略) |
| 8 | 薬剤師の確保等 |
| (1) | ・(2) (略) |
| (3) | 薬局の業務に従事する薬剤師の氏名を、薬局内の見やすい場所に掲示すること。 |
| (4) | 薬剤師は、白衣、ネームプレート等を着用し、薬剤師であることを容易に認識できるようにすること。 |
| (5) | ・(6) (略) |
| 9 | 〜11 (略) |
| 12 | 業務 |
| (1) | (略) |
| (2) | 薬歴管理・服薬指導 薬剤師は、医薬品の有効で安全な使用、特に重複投薬や相互作用の防止に資するため、患者について調剤された薬剤ばかりでなく、必要に応じ一般用医薬品を含めた薬歴管理を行い、適切な服薬指導を実施すること。(以下、略) |
| (3) | ・(4) (略) |
| (5) | 受診の勧め 一般用医薬品等の販売に当たって、一般用医薬品の適用外と思われる場合は、患者が適正な受診の機会を逃すことのないよう、速やかに「かかりつけ医」等への受診を勧めること。 |
| (6) | (略) |
| 13 | 一般用医薬品の供給 |
| (1) | 薬局は調剤とあわせて一般用医薬品の供給に努めること。 |
| (2) | 一般用医薬品の販売に当たっては、必要に応じ薬歴管理を行うとともに、適切な服薬指導を実施すること。 |
| (3) | 習慣性や依存性のある医薬品及びその他乱用されやすい医薬品は十分注意して供給すること。 |
| 14 | 医薬品情報の収集等 |
| (1) | 常に、医薬品の有効性・安全性に関する情報、副作用情報、保健・医療・介護・福祉情報などを収集し、薬局業務に資すること。 |
| (2) | (略) |
| (3) | 医薬品等の副作用等について、薬局利用者からの収集にも努めること。 |
| 15 | 〜17 (略) |