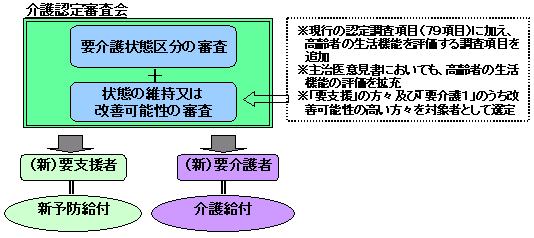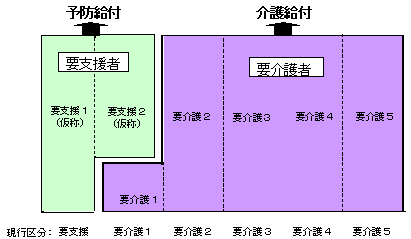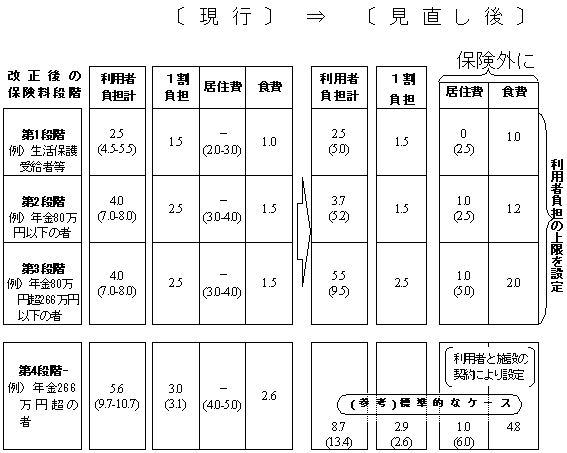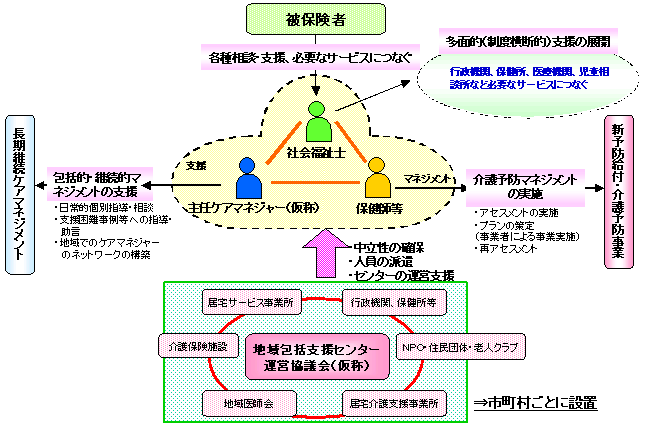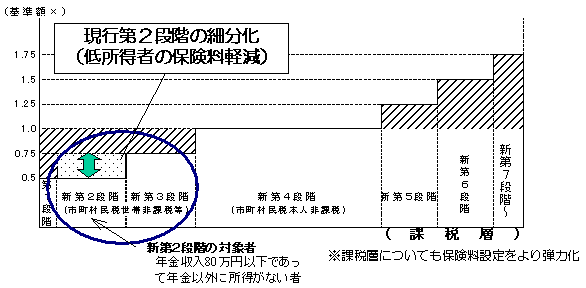|
| �@�o�ߑ[�u�I���ŕ��S���ƂȂ�҂��ˑR�Ƃ��Ė�U���W�O�O�O�l�i���ʗ{��V�l�z�[�������҂̖�Q���j�����܂��B �@���ی��@�{�s�O�Ɏs�����̑[�u�ɂ����ʗ{��V�l�z�[���ɓ������������̎҂̑����͏������Ⴍ�A�o�ߑ[�u�I���ɔ������S���ɂ��{�ݗ��p�̌p��������ƂȂ邱�Ƃ��l������B |
|
| �@���s�̕��S�y���[�u�̎��{���Ԃ�����ɂT�N�ԉ�������B |
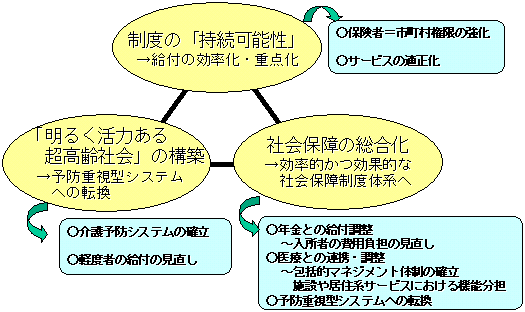
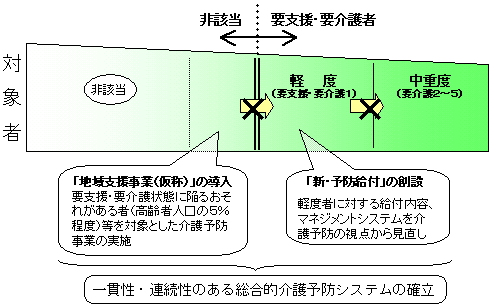
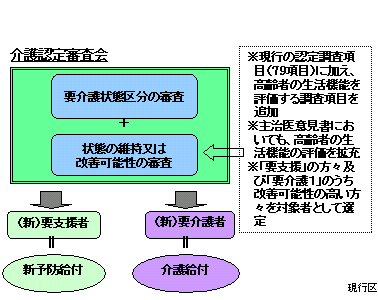
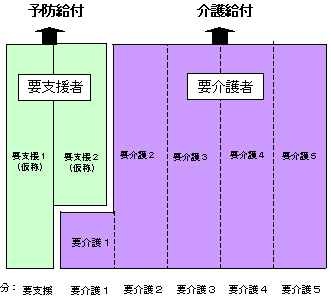
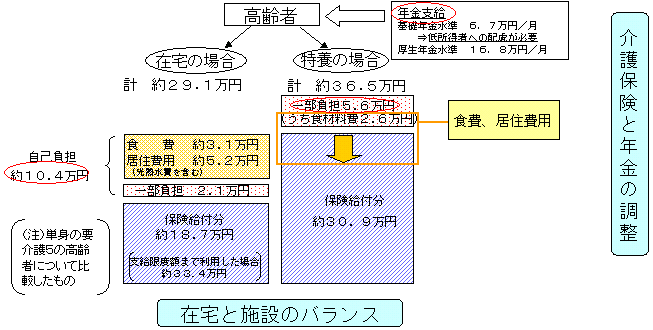
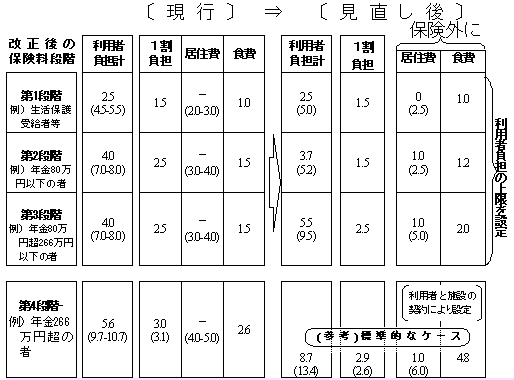
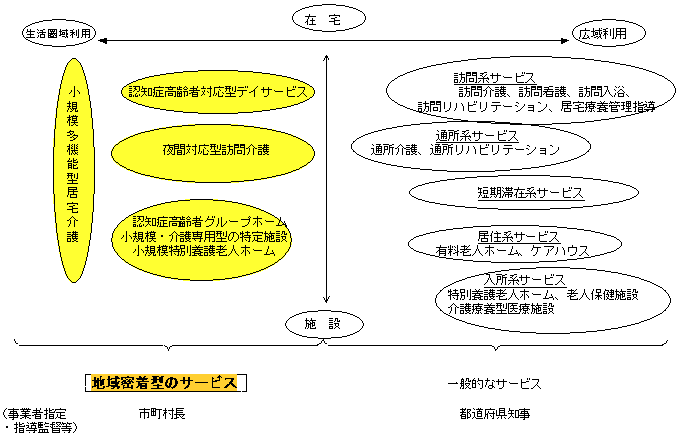
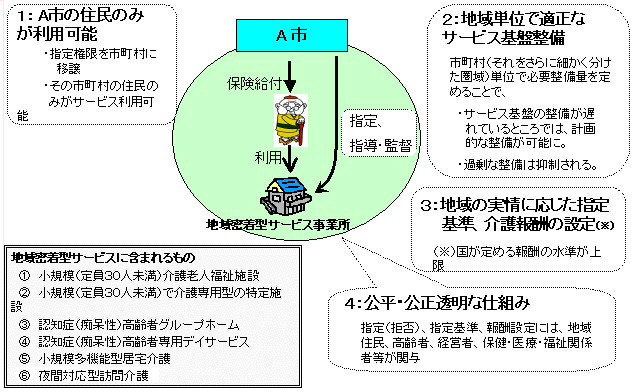
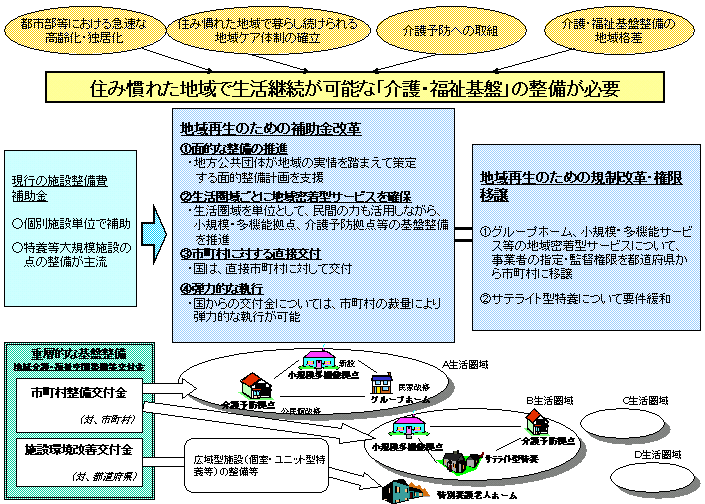
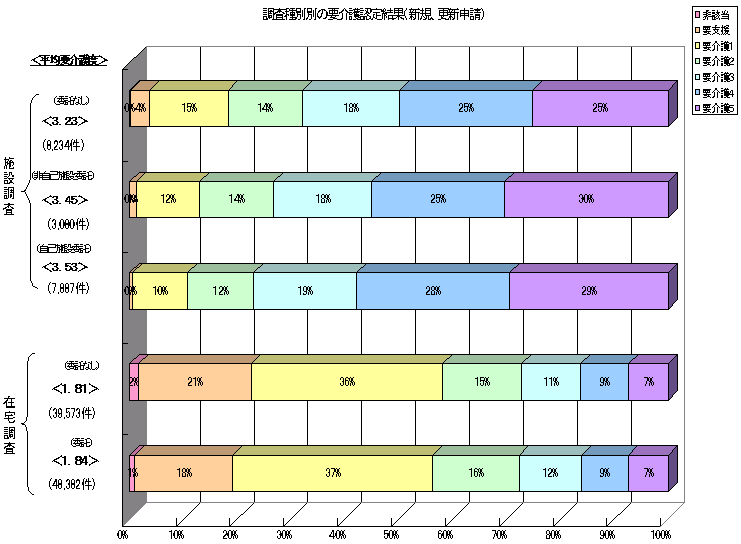
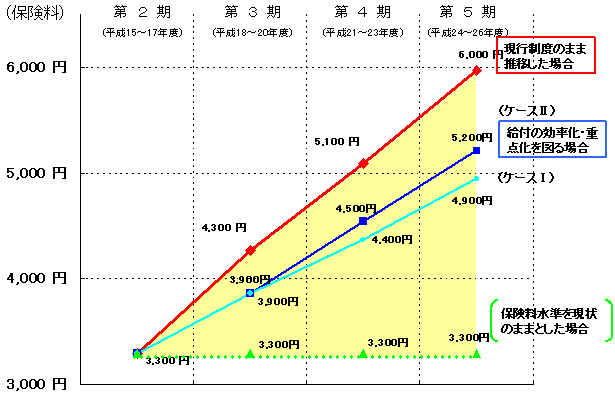
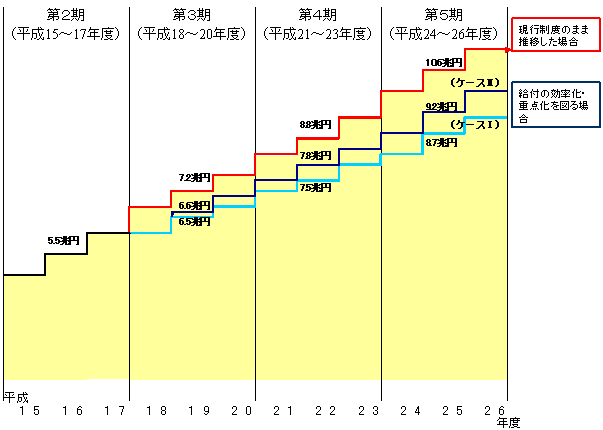
![�\�h�d���^�V�X�e���ւ̓]���i�S�̊T�v�j�̐}](images/s0209-8f20.gif)