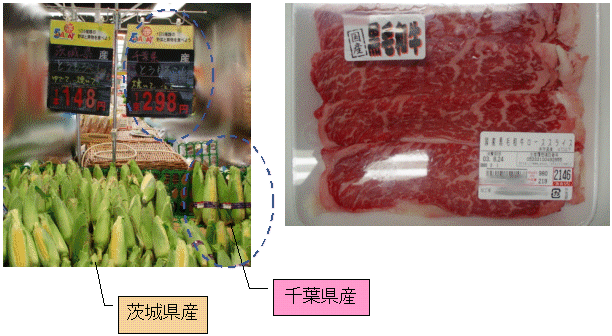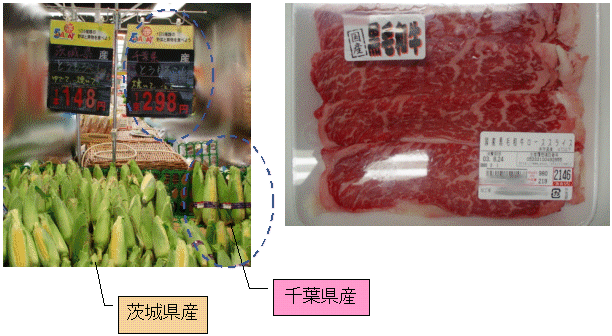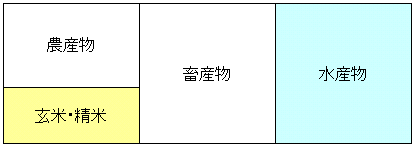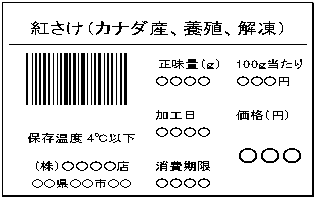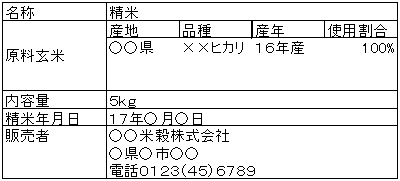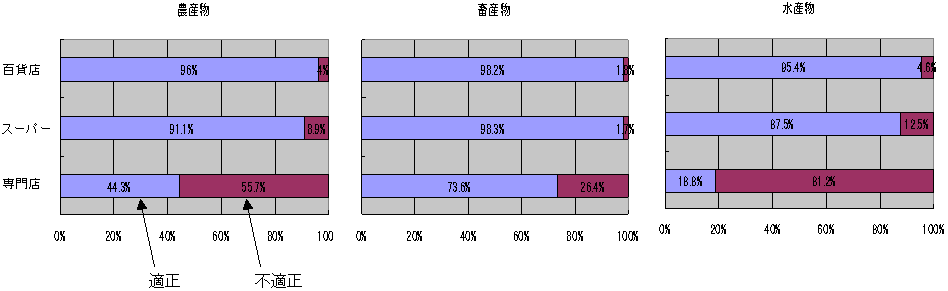戻る
生鮮食品の表示について
| ○製品に近接した掲示(ばら売り) |
○容器包装への表示 |
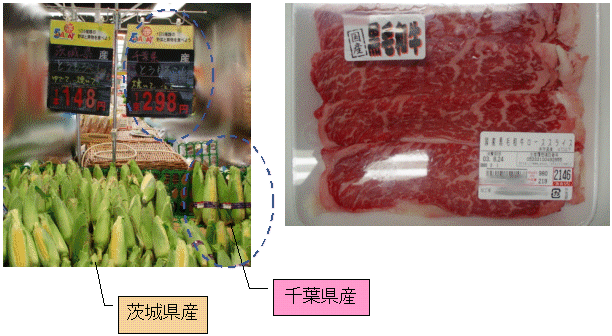 |
1.現状
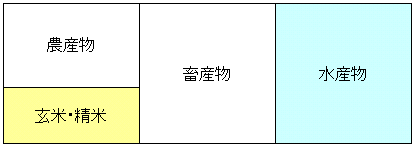
農産物、畜産物・・生鮮食品品質表示基準を適用
(ただし袋詰めされた玄米・精米・・玄米及び精米品質表示基準を適用)
水産物・・生鮮食品品質表示基準に加え、水産物品質表示基準を適用
参考1:JAS法における生鮮食品の範囲(混合)
| |
切断前 |
単品 |
同種混合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
異種混合 |
加工品を混合 |
加工品 |
| 刺身 |
魚 |
メバチマグロ赤身 |
メバチマグロ赤身+メバチマグロ中トロ |
メバチマグロ赤身+ミズダコ(生) |
メバチマグロ赤身+ゆでだこ |
ゆでだこ |
| カット野菜 |
野菜 |
キャベツ千切り |
キャベツ千切り+赤キャベツ千切り |
キャベツ千切り+カットレタス+タマネギ千切り |
キャベツ千切り+カットレタス+コーン(加工品) |
コーン缶詰 |
| スライス肉 |
− |
牛ロース肉 |
牛カルビ+牛ロース |
牛カルビ+豚ロース |
牛カルビ+牛塩タン |
牛塩タン |
参考2:JAS法における生鮮食品の範囲(乾燥)
【現状】
| ○ | 米穀、雑穀、豆類については生鮮食品扱い
|
| ○ | その他の農林水産物については、加工食品扱い |
【上記の考え方】
| ・ | 米穀、雑穀、豆類の「乾燥」工程:
農林水産業生産者による収穫後の調整、選別、水洗い等の作業の一環として必ず行われる
|
| ・ | その他の農林水産物の「乾燥」工程:
生鮮品の付加価値向上(保存性や食味向上、料理適正の獲得)のために行われるものであり、性格が異なることから、上記考え方をとっている。 |
| (2) 生鮮食品品質表示基準の表示事項=名称+原産地 |
名称:一般的名称を記載
原産地:下表のとおり
| |
国産品 |
輸入品 |
| 農産物 |
| ・ | 都道府県名を記載(市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。) |
|
| ・ | 原産国名を記載(一般に知られている地名を原産地として記載することができる。) |
|
| 畜産物 |
| ・ | 国産である旨を記載(主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。) |
|
|
| 水産物 |
| ・ | 水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を記載。水域名の記載が困難な場合は水揚港名又は水揚港が属する都道府県名を記載することができる。) |
|
| ・ | 原産国名を記載(水域名を併記することができる。) |
|
| (3) 水産物品質表示基準の表示事項=「解凍」+「養殖」 |
(解凍表示)
冷凍したものを解凍したものである場合、「解凍」の旨表示。
(養殖表示)
養殖※されたものである場合、「養殖」の旨表示。
| (表示例) |
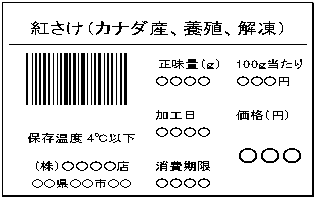 |
| ※ | 「養殖」とは、幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成することをいう。 |
(4) 玄米・精米品質表示基準の表示事項=
名称+原料玄米+内容量+精米年月日+販売者 |
(表示様式及び表示例)
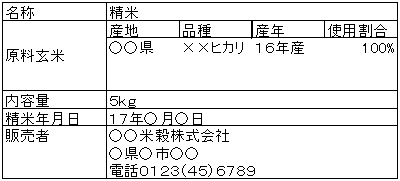
| ※ | 生産者が消費者に直接米を販売する場合も表示が必要。 |
| ※※ | 容器包装されていない米については、生鮮食品品質表示基準に従い名称+原産地の表示が必要。 |
| |
生鮮食品 |
加工食品 |
容器包装されていないもの
(対面販売、ばら売り等) |
対象 |
対象外 |
| 生産者直売 |
対象外(容器包装された
玄米・精米は対象) |
対象外 |
| 設備を設けて飲食 |
対象外 |
対象外 |
| 流通段階 |
対象(農協、卸売業者等) |
対象外(業者間取引) |
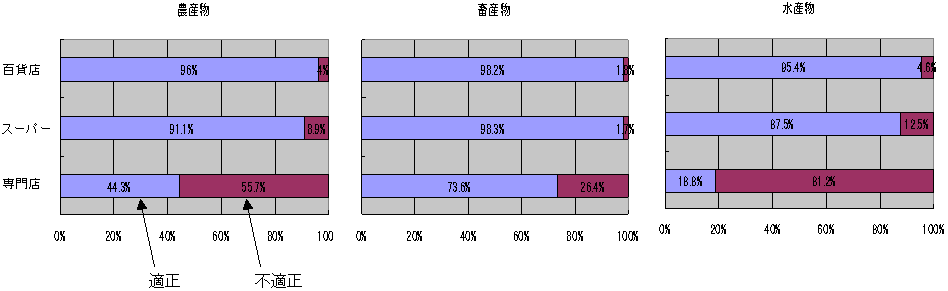 |
| 資料:総務省調査(食品表示に関する行政評価・監視結果報告書 平成15年1月) |
2.問題点及び検討課題
(1) 表示基準の対象範囲
| ○ | 加工食品については、ばら売りや対面販売については表示義務がないのに対し、生鮮食品には表示義務がある。このため、
| ・小規模小売店 ・直売所 等についても、表示が必要。 |
|
| ○ | 表示実施状況をみると、量販店では既に100%近い表示実施率であるのに対し、専門店では、十分に原産地表示がなされていない。
|
| ○ | 店舗の形態によっては、「店主に聞けばわかるので表示は必要ない」という意見もある。 |
|
| 課題1: | 生鮮食品の表示基準の対象範囲について、見直す必要はないか。 |
|
(2) 複数種類の生鮮食品を詰め合わせた場合の原産地表示方法
| 現行規定: | 異なる種類の生鮮食品で、複数の原産地のものを詰め合わせた場合、原産地はそれぞれの生鮮食品の名称に併記する。 |
|
┌
|
|
└ |
| 例: | 果物盛り合わせ(切断していないもの)→すいか(熊本県)、りんご(青森県)、バナナ(フィリピン)、・・・) |
| ※ | 切断したものの盛り合わせ(カットフルーツミックス)は加工食品。 |
|
┐
|
|
┘ |
|
問題点
| ○ | 生鮮食品の詰め合わせは店頭で行われる場合も多く、その組み合わせは一定していない。
|
| ○ | 多種類の生鮮食品を詰め合わせた場合、全ての生鮮食品に名称と原産地を表記するのは困難な場合もある。(包装の外部から詰め合わせ内容は確認可能) |
|
| 課題2: | 複数種類の生鮮食品を詰め合わせた場合の実行可能な表示方法を検討する必要はないか。 |
|
(3) 複数の原産地のものを混合した場合の原産地表示方法
| 現行規定: | 複数の原産地のものを混合した場合、多い順に全て記載。 |
|
|
問題点
| ○ | 特売品等の山積み販売の場合、複数県の商品を同時に販売するため、原産地を多い順に全て正確に記載することは困難。
|
| ○ | マグロのすき身、挽肉、刺身切り落としなど、複数産地由来のものを混合して販売する場合、原産地を多い順に正確に全て記載することは困難。 |
|
| 課題3: | 複数の原産地のものを混合販売する場合の実行可能な表示方法を検討する必要はないか。 |
|
┌
|
|
└ |
加工食品の原料原産地表示では、複数の原産地のものを混合使用する場合には、3位以下を「その他」とする等の表示方法を認めている。 |
┐
|
|
┘ |
(4) 記載する原産地の決定方法
| 課題4: | 記載すべき原産地があいまいな場合があり、考え方を整理する必要はないか。 |
|
例1)複数の原産地をまたがる場合
| ○ | 県境を超えて農地を有する農業者が生産した農産物については、現状では農地の所在地を原産地として記載する(属地主義)こととされているが、実際には農業者が所属する農協に一括して出荷するなど、厳密に分けて管理することが困難な場合がある。
|
| ○ | 同様な例として、以下のようなものがある。
| ・ | 県境を超えて集荷し、処理される鶏(食肉処理場で混合して処理) |
| ・ | 産地市場に集荷された農産物(県境、市町村境を超えて持ち込まれた農産物が、産地市場の所在地を原産地として出荷) |
| ・ | 浜値の高い港に水揚げされる水産物(A県沖で捕れたとらふぐを下関に水揚げ) 等 |
|
|
例2) 種子、種苗等を他地域から導入する場合
| ○ | 養殖水産物の場合、種苗(稚魚等)生産地と、養殖地が異なる場合がある。[現状:養殖地が原産地] |
(例:香川はまち(九州から稚魚を入手し香川で養殖)、愛媛かき(広島から稚貝を導入し愛媛で養殖))
| ○ | 他県で製造したり、輸入した菌床しいたけの菌床を用い、別の県でしいたけを栽培し、販売する例も存在。[現状:栽培した県が原産地]
|
| ○ | 国内栽培の農産物の場合、種子は外国で採取したものを使用する場合も多い。[現状:栽培した県が原産地] |
(例:ホウレンソウの種子は、大半が外国で採取したもの)
|
例3) 輸入される農畜水産物の場合
| ○ | 輸入される農畜水産物の原産国については、その根拠を通関の際の書類(輸入申告控等)に頼らざるをえないのが現状。
|
| ○ | 一方、以下の例のように、輸入される前に複数の国を経由する生鮮食品も存在。
| ・ | A国で栽培、収穫された農産物をB国経由(単なる船舶・航空機の変更の場合などは除く)で輸入→「B国産」 |
| ・ | A国で産まれ育った牛をB国でと畜、ブロックにして輸入→「B国産」 |
| ・ | 水産物の場合、採捕された国と切り身、冷凍した国が異なる場合が多いが、切り身の形態によって通関上の原産国が異なる。(3枚おろしの場合切り身にした国が、2枚おろしの場合採捕した国が原産国) |
|
|
(5) 生鮮魚介類
| ○ | 原産地の表示方法として、水域名、漁港名、都道府県名、輸入国名等が混在。
|
| ○ | 従来日本で食されていなかった外国の魚介類等が増加し、一部名称が誤認を与える場合が存在。(水産庁ガイドラインで整理されている。)
|
| ○ | 養殖水産物の表示
| ・ | カキ、ノリなど、一般に養殖であると認識されていながら、JAS法上養殖の定義に該当しないものの取扱い。 |
| ・ | 養殖の形態が様々である中での「主たる養殖場」の考え方。 |
|
|
| 課題5: | 生鮮魚介類の表示について、わかりやすく見直す必要はないか。 |
|
(6) 玄米・精米
| ○ | 容器包装された玄米・精米については、生鮮食品品質表示基準が適用されず、独自の表示方法となっている。(加工食品同様、一括表示様式が示されている)
(玄米・精米独自の表示事項)
| ・ | 原料玄米の内訳(産地、品種、産年) |
| ・ | 精米年月日 |
|
| ○ | 多様な消費者の志向に従い、ブレンド米、無洗米等、さまざまな形態の米が販売されている。 |
|
| 課題6: | 玄米・精米の表示について、わかりやすく見直す必要はないか。 |
|
トップへ
戻る