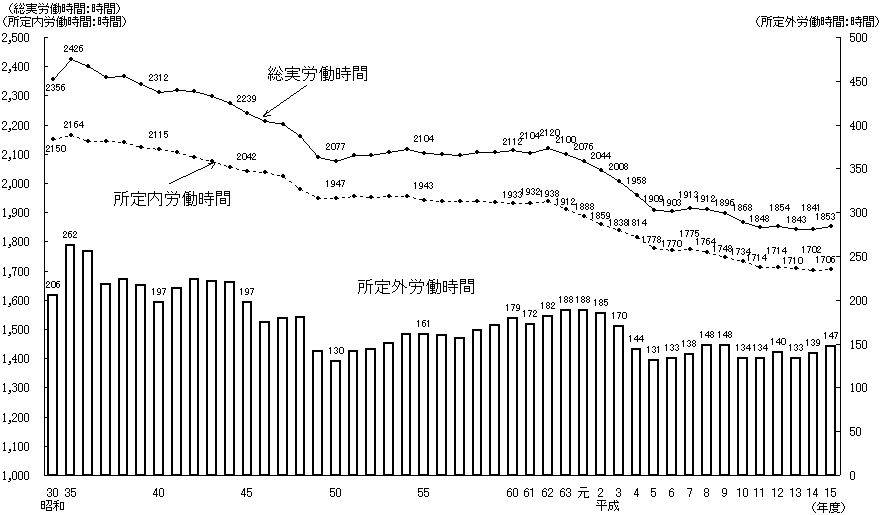
|
| 労審発第186号 平成16年12月17日 |
| 厚生労働大臣 尾辻 秀久 殿 |
| 労働政策審議会 会長 西川 俊作 |
| 労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
| 労働条件分科会 分科会長 西村 健一郎 |
| 1 | 労働時間対策については、国際的に経済構造調整を求められていた情勢等を背景に、昭和63年以後累次の閣議決定において「年間総実労働時間1800時間」を政府目標とし、平成4年に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促進法」という。)を制定してからは、同法に基づく労使の自主的取組を促進し、労働時間の計画的な短縮を推進してきたところである。 特に「年間総実労働時間1800時間」という数値目標は、完全週休2日制の下で年次有給休暇を完全取得するような働き方を、労使はじめ国民に認知させる上で大きな役割を果たすとともに、我が国が内需拡大等を強く求められていた平成年代初頭の経済環境に照らしても有意義なものであった。 こうした目標の下での労使による真摯な取組や、これに対する行政の指導援助の結果、完全週休2日制の普及等が進展し、労働者1人当たりの平均年間総実労働時間は平成4年度に1958時間であったものが平成15年度には1853時間と約100時間短縮したところである。 |
| 2 | 近年、年間総実労働時間は短縮から横ばいに転じ、平成12年度以後おおむね1850時間前後で推移しているが、15年度の総実労働時間を一般労働者、パートタイム労働者別に12年度と比較してみると、一般労働者で17時間増の2016時間、パートタイム労働者で12時間増の1184時間となっており、いずれも所定外労働時間を中心に増加する中で、パートタイム労働者の比率が2.1ポイント上昇し、結果的に年間総実労働時間の増加を止めている状況にある。 また、「労働力調査」により週労働時間別の雇用者の分布をみると、経済のグローバル化の進展に伴う企業間競争の激化等を背景に、35時間以上60時間未満の雇用者が減少する一方、35時間未満の雇用者と60時間以上の雇用者がともに増加し、いわゆる「労働時間分布の長短二極化」が進展している。 さらに、「就労条件総合調査」により年次有給休暇の取得状況をみると、取得日数の減少及び取得率の低下傾向が8年間続き、平成15年度には取得日数が8.5日、取得率が47.4%となった。年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合も、平成10年度の19.5%から平成15年度の14.4%へ趨勢的に低下している。 こうした中で、過重労働による脳・心臓疾患の労災認定件数が年間310件以上を記録し、精神障害等の労災認定件数も増加するなど、働くことをめぐる健康障害が社会問題化していると言って過言ではない。 |
| 3 | 一方、人材を基盤とする我が国において、急速な少子高齢化、労働者の意識やニーズの多様化等が進む中で、経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である労働者が職業生涯を通じて意欲と能力を十分に発揮できるようにしていくことが重要である。 したがって、今後のあるべき姿としては、労働者一人一人の心身の健康が保持されるとともに、その職業生涯の各段階において、家庭生活、地域活動及び自己啓発等に必要とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を発揮できるような環境を整備していくことが求められる。 同時に、グローバル化の進展に伴い企業間競争が激しさを増し、時間ではなく成果によって評価される仕事が拡大する中で、企業の側にとっても、効率的な事業運営の観点から、こうした環境の整備を通じて、企業活動の担い手である労働者が着実に成果を上げられるようにしていくことが期待される。 また、社会的にみても、こうした環境の整備を通じて、男性を含めて労働者が家庭や地域で過ごす時間が増加することにより、家庭や地域の再生、ひいては少子化の緩和にも資することが期待される。 |
| 4 | 労働時間をめぐって我々が直面している諸問題と、今後のあるべき方向性との乖離を是正していくためには様々な取組が必要とされるが、とりわけ今後の労働時間対策においては、事業場における労働時間、休日及び休暇(以下「労働時間等」という。)の在り方を、労働者一人一人の希望も踏まえつつ、その健康や生活に配慮したものとしていくことが必要である。 その際、個々の労使が時短促進法の下で培ってきた事業場における推進体制を発展的に継承し、労働時間等の在り方を改善する労使の自主的取組を促進していくことが効果的である。 以上の認識に立って、本分科会としては、9月28日以後4回にわたる調査審議の結果、「平成18年3月31日までに廃止するものとする」と規定されている時短促進法及び同法に基づく労働時間対策等について、下記のとおり見直すことが必要であるとの結論に達した。 |
| 1 | 法改正の基本的な方向性 時短促進法については、労使の自主的取組を促進するための努力義務を中心とする法律という基本的な性格は保ちつつも、労働時間の短縮の目標(「年間総実労働時間1800時間」)に向けた取組を推進するための法律から、事業場における労働時間等の設定を労働者の健康や生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへ改善するための法律に改めることが適当であること。
|
| 2 | 具体的な改正内容 |
| (1) | 労働時間短縮推進計画について 働き方の多様化が進展する中で、全労働者一律の目標を掲げる計画は必ずしも時宜に合わなくなっていることにかんがみ、改正法においては、時短促進法における「労働時間短縮推進計画」に代えて、事業主が労働時間等の設定の改善に向けた取組を適切に進めるに当たって必要となる事項等を取りまとめた指針を定めることが適当であること。 この指針は厚生労働大臣が定めることとし、
指針に掲げる事項の具体的内容に関しては、改めて検討することが必要であるが、現段階で盛り込むことが考えられる内容の一端として、以下のようなものも考えられること。
さらに、改正法に基づく指針については、労働者の生活に配慮した労働時間等の設定という点に着目するならば、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針等との位置付けや関連を明確にした上で、次世代育成支援対策推進法に基づく事業主の取組にも資するものとするなど、事業主が他の法令に基づく要請に応えて進める取組の一助となるようなものとすることが適当であること。 |
| (2) | 事業場における実施体制について これまでも時短促進法に基づく「労働時間短縮推進委員会」(以下「時短委員会」という。)が一定の成果を上げてきたことを踏まえれば、事業場における労働時間等の設定の改善を効果的に進めるためには、個々の労使の話合いが十分に行われる体制の整備が不可欠であること。 このため、改正法において、事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るという責務を果たす観点から、労働者の健康と生活に配慮し、労働時間等の設定の改善を図るための措置を調査審議する委員会(以下「労働時間等設定改善委員会」という。)の設置等の体制整備に努めるものとすることが適当であること。 こうした体制整備により、事業場において、(1)の指針を踏まえつつ、例えば少子化対策など他の法体系に基づく課題についても、労働時間等の設定の改善と関連付けて労使間の調査審議を促進することが期待されること。 また、フレックスタイム制等の弾力的な労働時間制度については、労働時間等の設定の改善に資するものであることから、労働時間等設定改善委員会において一定の要件の下に導入の決議を行う場合は、現在の時短委員会の決議に認められているのと同様に、
その際、これまでの時短委員会をはじめとする労働時間に関する労使協議機関の設置状況にかんがみれば、労働時間等設定改善委員会の設置の促進が重要な課題であり、まずもって国の効果的な指導啓発によって、その新設を促すことが不可欠であること。 新設が困難な事業場については、既存の委員会が設置されている場合、その委員会を労働時間等設定改善委員会として活用できる余地があれば、それを可能とするような措置を講じることによって労働時間等設定改善委員会の設置を促進することが適当であること。具体的には、事業者が労使の代表を指名し、労働者の健康の保持増進等に関する調査審議を行うこととされている衛生委員会について、委員構成や基本的性格の相違に留意しつつ、以下の要件を満たす場合に限り、労働時間等設定改善委員会と同等のものとして取り扱えるようにすることが考えられること。
|
| (3) | 事業主に対する支援の在り方について 時短促進法の指定法人「労働時間短縮支援センター」及び指定法人に対する交付金に基づく施策等については、労働時間の短縮に取り組む事業主に対する支援措置として一定の成果を上げてきたところであるが、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月閣議決定)等を踏まえ、この際、廃止することが適当であること。 一方、改正法の下で事業主は労働時間等の設定の改善に向けて取り組むこととなるが、中小企業事業場や労働組合の無い事業場においては、労働時間等設定改善委員会の設置や指針に基づく措置の実施等を円滑に行う上で支援が欠かせない場合も考えられることから、必要な範囲に絞って効果的・効率的に実施することが適当であること。その際、事業主の意識面での啓発に力点を置くことが適当であること。 |
| (4) | その他所要の改正について 時短促進法においては、同一の業種に属する二以上の事業主が共同して労働時間を短縮する措置を実施する場合、「労働時間短縮実施計画」を作成することができることとされているが、改正法においては、これを、同一の業種に属する二以上の事業主が共同して労働時間等の設定を改善する措置を実施するときに作成することができる計画(労働時間等設定改善計画(仮称))に改めるなど所要の改正を行うことが適当であること。 |
| (1) | 今後の目標の在り方について 「年間総実労働時間1800時間」については、時短促進法に基づく労働時間短縮推進計画において目標値とされてきたものであるが、近年の状況の下では従来どおりの目標値として用いることは時宜に合わなくなっている。しかしながら、今後に向けての対応については、目標を掲げること自体に意義が存在し、例えば一般労働者に限って引き続き目標を掲げることが必要であるという意見と、今後、労働時間が成果に直結しない働き方が一層広がるという展望に立てば数値的な目標は不要であるという意見に分かれた。 本分科会としては、目標に関して、改正法に基づく指針の策定の際に、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等の課題ごとに、その要否や内容を個別に検討していくことが適当であると考える。 |
| (2) | 労働時間法制について 労働時間に関する施策の在り方に関し、労働者委員からは、
一方、使用者委員からは、現在、特例措置の見直しや割増賃金率の引上げについて議論できる経営環境には無く、むしろ高度な人材の活躍の場を拡げる等の観点から、労働時間規制の適用除外についての議論を急ぐべきであるという意見が示された。 本分科会としては、労働時間に関する施策の在り方については、現在実施している諸外国のホワイトカラー労働者の労働時間法制に係る調査結果や、平成17年度実施予定の労働時間の実態調査結果等をみた上で、引き続き検討していく必要があると考える。 |
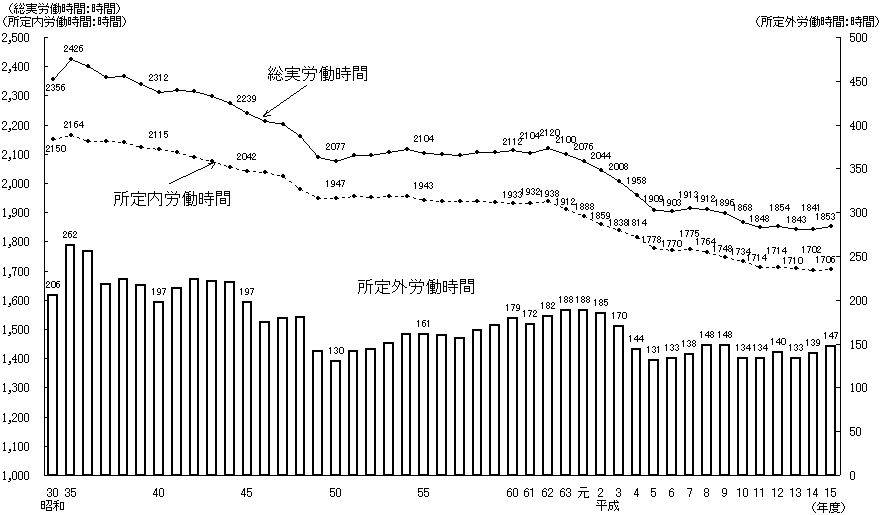
|
|
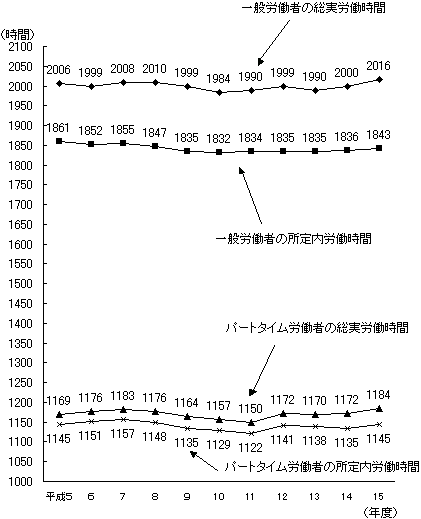
| (資料出所) | 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 | ||||
| (注) |
|
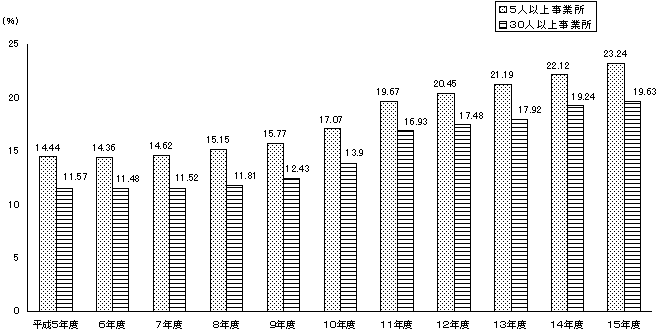
|
| 週の労働時間が「35時間未満の者」及び「60時間以上の者」の全体に占める割合がともに増加する一方、「35時間以上60時間未満の者」の割合が減少しており、「労働時間分布の長短二極化」が進行している。 特に、30歳代の男性で週の労働時間が60時間以上の者の割合が高くなっている。 |
| 平成5年 | 平成15年 | 差 | |
| 週35時間 未満の者 |
929万人 | 1259万人 | +330万人 |
| 18.2% | 24.1% | +5.9ポイント | |
| 週35時間以上 〜週60時間 未満の者 |
3625万人 | 3308万人 | ▲317万人 |
| 71.1% | 63.4% | ▲7.7ポイント | |
| 週60時間 以上の者 |
540万人 | 638万人 | + 98万人 |
| 10.6% | 12.2% | +1.6ポイント | |
| 合計 | 5099万人 | 5220万人 | +121万人 |
| 平成5年 | 平成15年 | 差 | |
| 週60時間以上の者 | 153万人 | 196万人 | + 43万人 |
| 20.3% | 23.7% | +3.4ポイント |
| ※ | 資料出所:総務省「労働力調査」 |
| ※ | 資料は雇用者数により作成。ただし、「30歳代男性で週労働時間60時間以上の者の比較」については、統計上の制約から雇用者のみのデータが得られないため、雇用者と自営業主等を合計した就業者数により作成。 |
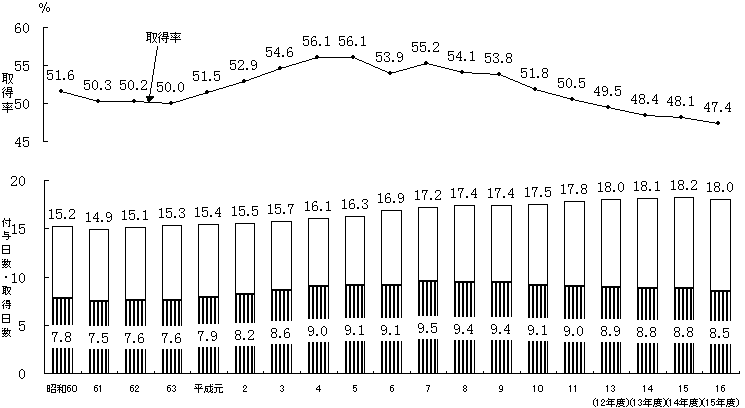
|
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![週休2日制等の普及率の推移(調査産業計、企業規模30人以上)[企業割合]のグラフ](images/s0131-9c5.gif)
|
||||||||||||
![週休2日制等の普及率の推移(調査産業計、企業規模30人以上)[労働者割合]のグラフ](images/s0131-9c6.gif)
|
||||||||||||
|
(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 1 | 本表は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号の「業務に起因することの明らかな疾病」に係る脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)について集計したものである。 |
| 2 | 認定件数は当該年度に請求されたものに限るものではない。 |
| 3 | 平成13年12月に脳・心臓疾患の認定基準が改正されている。 |
| 4 | 平成14年度以前の死亡に係る請求件数については把握していない。 |
|
(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 1 | 認定件数は当該年度に請求されたものに限るものではない。 |
| 2 | 平成11年9月に精神障害等の判断指針が策定されている。 |
| 1. | 単身赴任者数の推移 |
| ○ | 『就業構造基本調査』において、「雇用者であって、単身かつ有配偶である者」の数の推移をみると一貫して増勢にあり、単身赴任者数が増加していることがうかがわれる。
|
| 2. | 帰省の頻度 |
| ○ | 「月に2〜3回」の者と「ほぼ毎週」の者を合計すると、単身赴任者全体の6割強に上る。
|
| 3. | 帰省に要する時間(「短期休暇」の場合) |
| ○ | 「2〜4時間」の者が5割強に上り、次いで「4〜6時間」の者が多い。 |
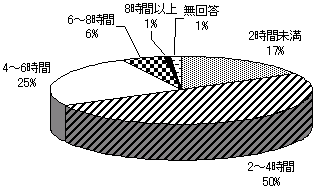
|
| 4. | 単身赴任者が赴任先住居に戻ってから出勤するまでの時間 (短期休暇の場合) |
| ○ | 約4分の3の者が「1日前」(月曜日から仕事が始まるとすれば日曜日のうち)に赴任先住居に戻っている。 |
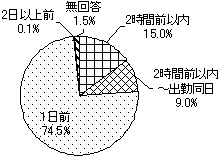
|
|
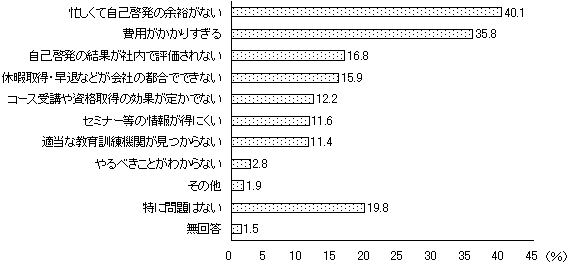
|
| 1. | 労使協議機関の有無
|
| 企業規模・労働組合の有無 | 労使協議機関「あり」の比率 |
| 計 | 41.8% |
| 5,000人以上 | 77.9% |
| 1,000〜4,999人 | 66.1% |
| 300〜999人 | 60.1% |
| 100〜299人 | 37.3% |
| 50〜99人 | 24.2% |
| 30〜49人 | 16.5% |
| 労働組合「あり」 | 84.8% |
| 労働組合「なし」 | 17.1% |
|
| 平成 | 元年 | 58.1% |
| 平成 | 6年 | 55.7% |
| 平成 | 11年 | 51.0% |
| 2. | 労使協議機関の下部組織の専門委員会の状況
|
|||||||||||||||||||||||
M.A.(%)
|