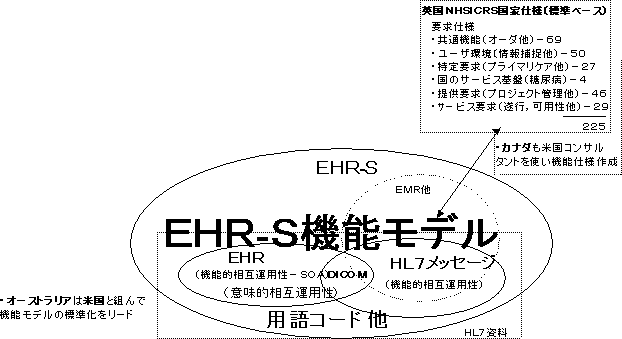
| 「共通の機能に対応するソフトウエアー部品の標準化」の報告 (高田班、飯田班検討事項) |
| ・ | 今までの検討内容 |
| ・ | 世界の最新状況 |
| ・ | 今後の進め方 |
| 保健医療福祉情報システム工業会JAHIS特別委員、画像情報マネージメント協会JIIMA特別会員、ホーム・アイランズ・セキュリテイ協議会HISC理事、OMGアンバセダ、WfMCフェロー |
| 長谷川 英重 高田班研究協力者 |
| 1) | 平成14年度厚生労働科学特別研究事業「コンポーネントの標準化による電子カルテ開発の研究」を(財)全日本病院協会の協力を得て、国際標準OMGのEDOCやHL7の情報モデルに準拠し、MS社.NETの上での実装を検証したコンポーネントベースでの部品化実証の成果を活用し、 |
| 2) | 平成15年度に、よりユーザの開発運用への適応性を高めたEAの考え方やユーザとベンダーがコンセンサスを取って、標準をベースにシステム統合を効率よく行うIHEの方法を参考に、より現実的な対象での実証を行い、16年度はその成果を整理し、外部に提供できる様にまとめる作業を推進中。 |
| ・ | 平成15から16年にかけて、EHRの標準化や実際の開発が著しく進み、本研究事業においてもその関連で確認を行い今後の対応を明らかにする必要がある。
| ||||||||
| ・ | 最新のNHIIの動きに照らし合わせると、「標準的電子カルテ」の方向は比較的うまく対応している。フォロー要 |
| ・ | オーストラリア、カナダや英国は、医療情報システムの基盤については国際標準をベースに、業務アプリケーションは国内の標準とすることでEHRSを推進していた。 |
| ・ | 米国はこれらの国の動きを分析し、米国でのEHRシステム推進上、機能モデルの標準化による多様性が必須と判断し、2004年から強力に推進 |
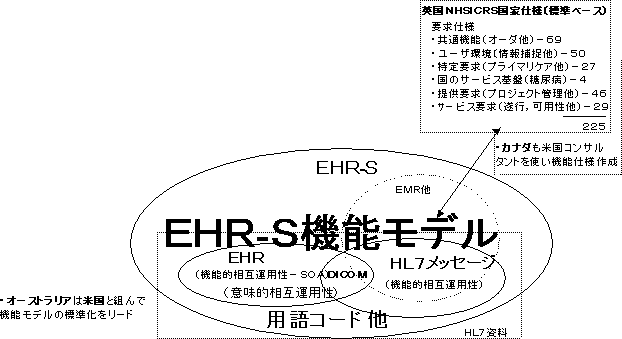
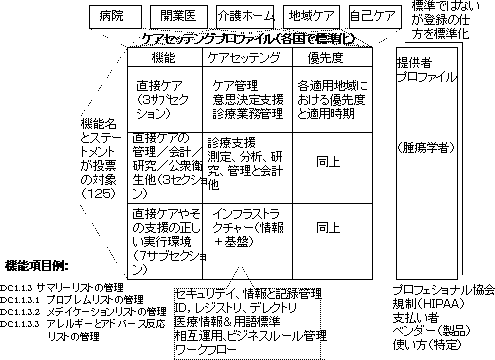
| ・ | 医療情報基盤は、国家レベルでのEHR開発を進める場合には、まず其の開発と運用が最優先とされ、さらに各国の既に構築されている情報基盤の活用が進められている。 |
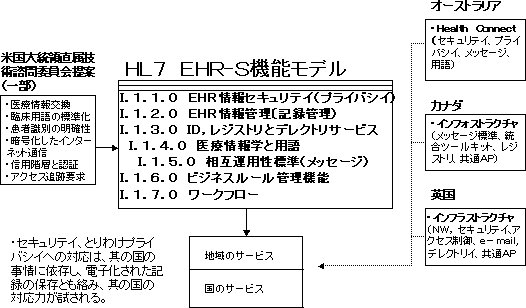
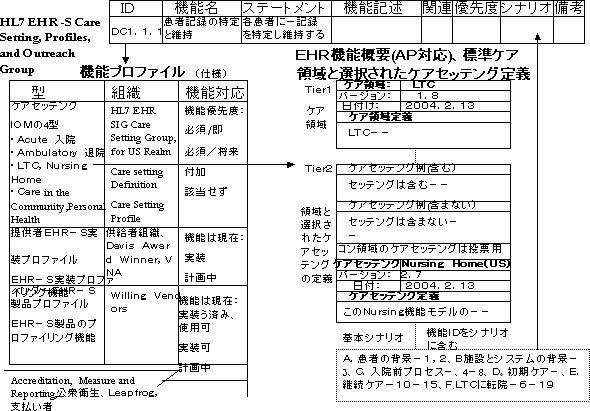
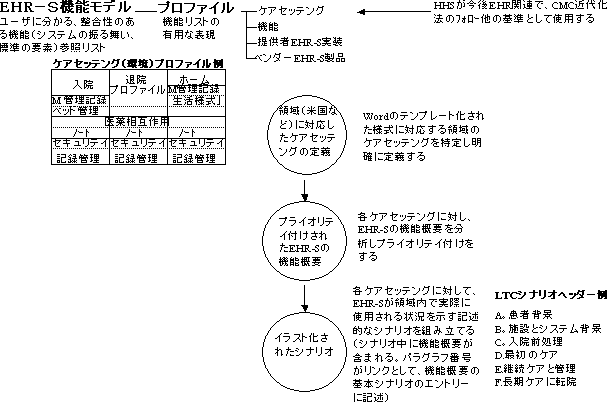
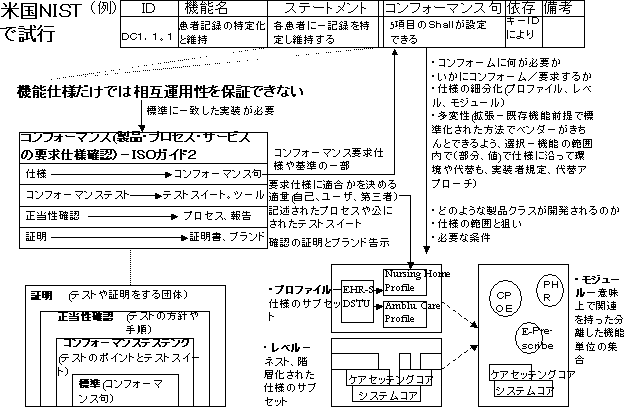
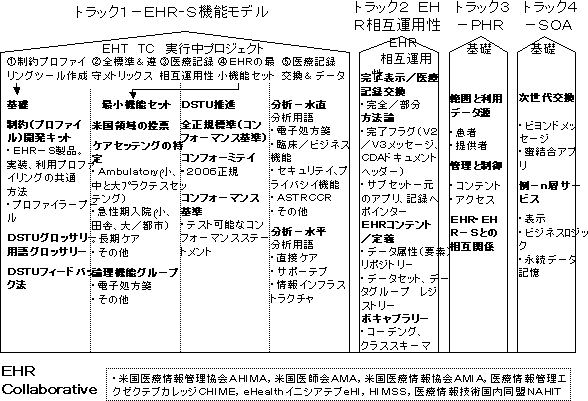
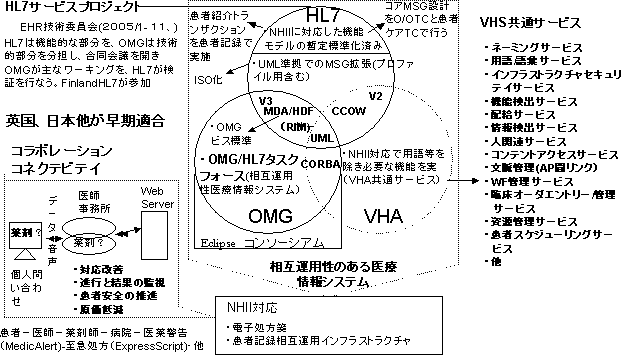
OMG Healthcare Day ワシントンDC 2004.11.4 |
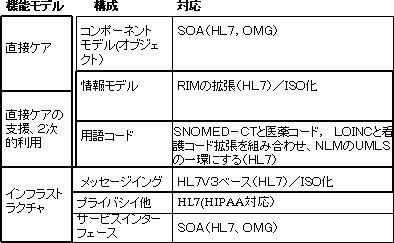
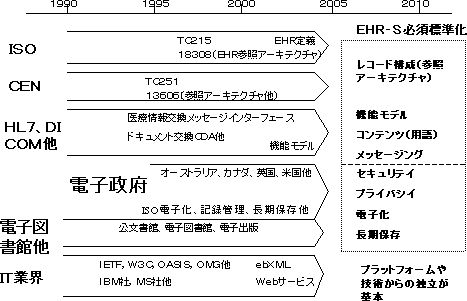
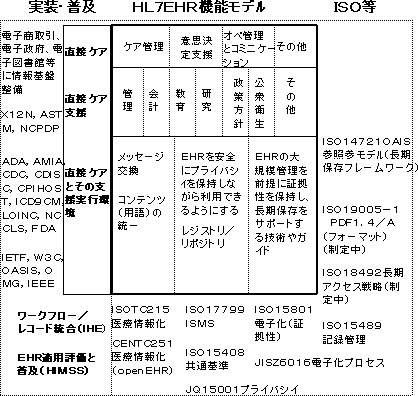
| ・ | EHRの定義は、各国の各機関によって色々定義されていたが、EHRに関してのトップダウンでの研究開発や標準化により、EHRの入れ物や仕組みがシステク技術的に体系化された。 |
| ・ | またHL7などの臨床面からの医療情報システムのボトムアップでの標準化、特にEHR‐S機能モデルの標準化の進展により、業務アプリケーションを含むEHRシステムをどのように標準化していくかのコンセンサスの調整期を経て、EHR,EHRシステム全体の機能的、意味的相互運用性を実現するための定義がまとまってきた。 |
| ・ | 特に2003年4月に米国政府が発表した、「2004年度中に機能モデルの標準化を行い、適用期間にはインセンテブを与える」との動きは、世界的インパクトを与えた。その標準化作業は関連者に大きな負担と調整を強いているが、結果としては、多様で複雑な医療情報システムのコンセンサスを進め、開発、運用を抜本的に改善するための方法論の確立を推進している。 |
| ・ | ISOTC215も2002年から粘り強く検討を進めていたTR20514EHR Definition, Scope and Contextのともタイミングが合い、今後はこれをさらにIS化に向け関連者への啓蒙が重要。 |
| ・ | ISOTC215 Health informaticsは1998/8設立されたISOでは新しい技術委員会であるが、もっとも活発で、今までに18の標準が発行され,その家2004年度だけで既に10の標準が発行されている。 |
| ・ | 設立当初はWGが5(1-Health record and modeling coordination,2-Messaging and communication,3‐Health concept representation,4-Security,5-Health card)であったが、現在は6-Pharmacy and medicines businessを含めた6WGから構成され、26の項目の標準化が進められてている。 |
| ・ | ISOはHL7やDICOMと異なり、国を代表する仕組みであるが、多くの国に影響し、グローバルで国際的な標準化で威力を発揮する。昨今のEHRの開発の広がりや、HL7やCENTC251などを中心に多くの地域や業界の標準化が活発化するとその役割は益々大きくなってきている。 |
| ・ | TC215では、2001/8以降Ad‐Hocグループにより、情報システムの観点から幅広い調査と検討を進め、EHRの参照アーキテクチャ18308を発行、CENTC251やHL7等蜜に連携し、さらにEHRの体系的な定義を行うTR20514の制定を日本リードで進めている。 |
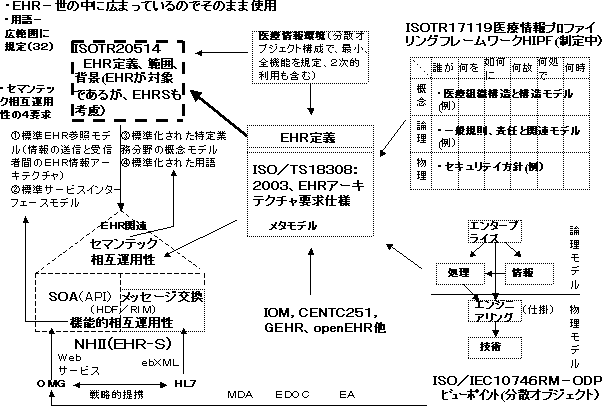
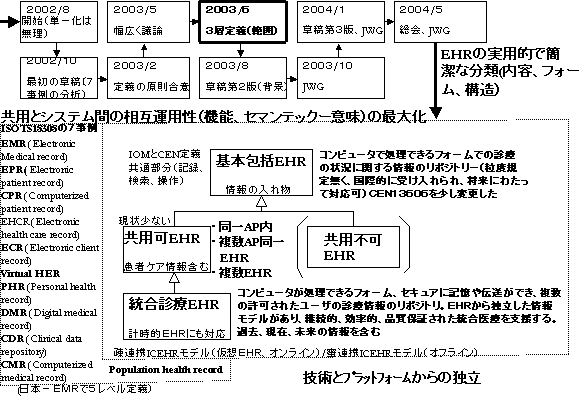
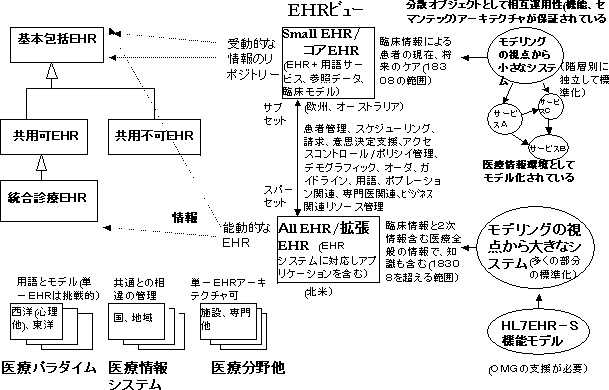
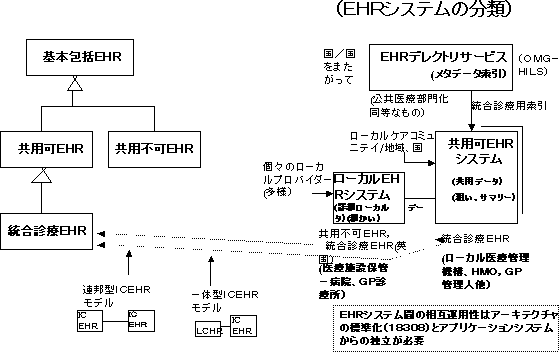
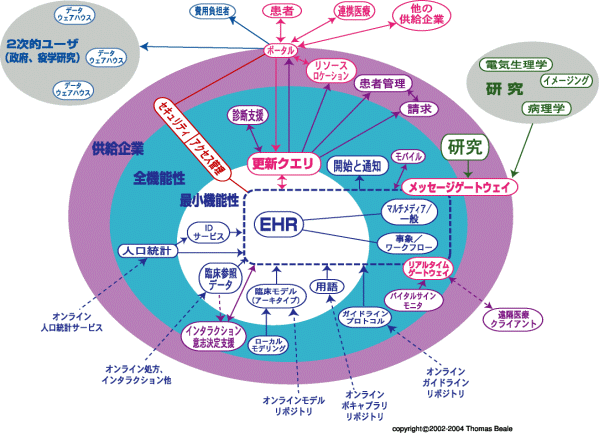
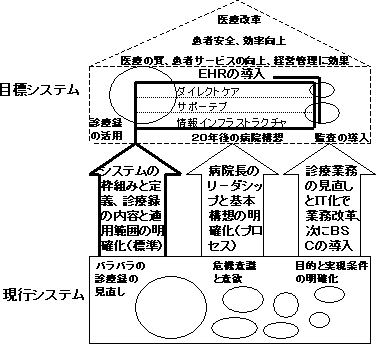 IT Vision No6(2004)より |
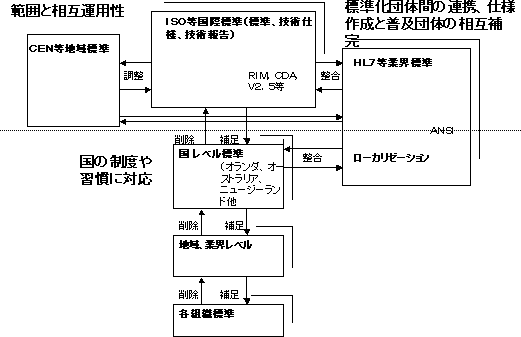
| ・ | 2004/4ブッシュ大統領が「10年以内に全ての米国人のためのEHRを作る」と発表した。「21世紀の医療システムが19世紀の紙による仕事をしている」と言い、「紙による記録は多くの間違いと非効率で、医療提供者間のコミュニケーションを妨害している」と言った。HHSに医療産業のデジタル化を命じ、医療情報技術コーデネータが指名され、開発や維持に責任を持ち、相互運用性のある医療情報技術の全国での実現をガイドする。そして医療ミスの削減、品質向上、医療支出に対するより高い価値の創出を行う。
|
| ・ | 2004/5のHHS主催のITサミットで、HHSのTommy Thompsonが、EHRのインフラ確立のスピーアップを宣言した。 良いITシステムで年14兆円($140B)医療費の10%を節減する。 HL7がEHRモデルを標準化することは医療機関の間でのやり取りを許す“相互運用”の“決定的な第一歩”となる。新たな技術標準は年内に政府から発表され、これにより病院や医師は国内での情報が共有できるようになる。ブッシュ大統領は政府内で医療情報技術に使う100億円($100M)の予算を倍増するようアドバイスした。この法案は両党合意で成立した。
| ||||||
| ・ | EHRは医療エラーを大幅に減らすが実現はスローで、困難で金が掛かり、直接のインセンテブもないので注意深く対応要 |
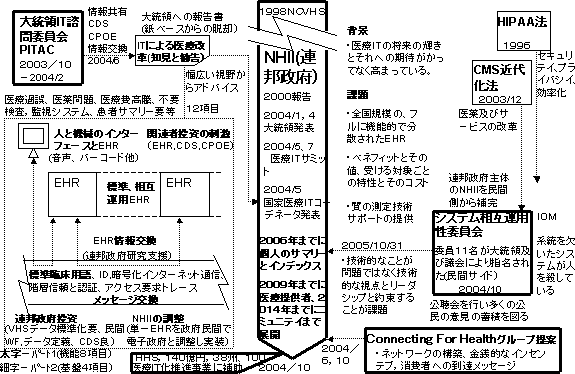
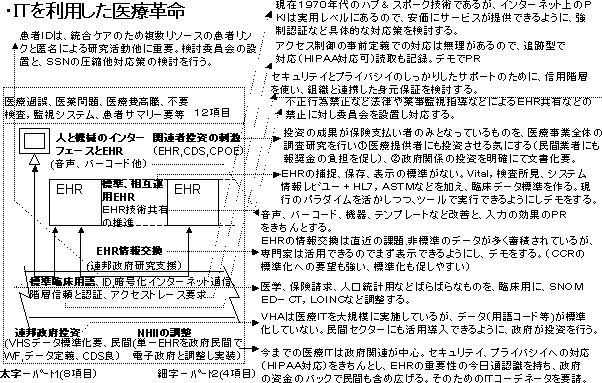
NHII関係者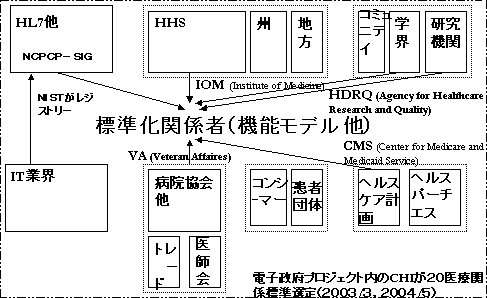 |
2004.9 HL7総会基調講演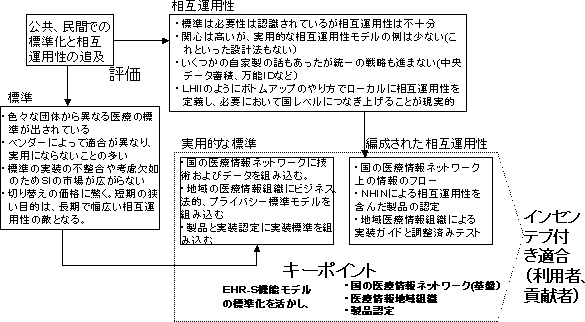 |
| 2994.9HL7総会基調講演 ・EHR−Sの機能モデルの標準化を活かし
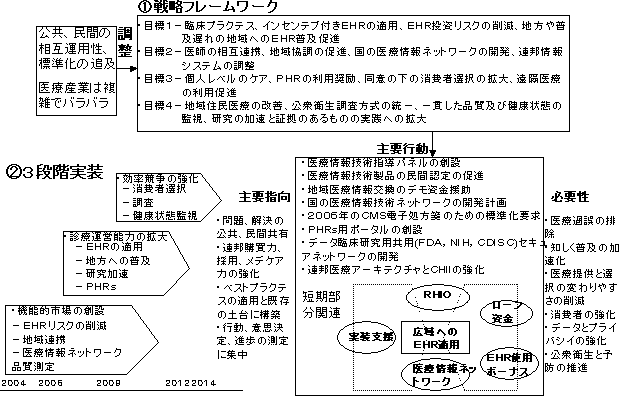 |
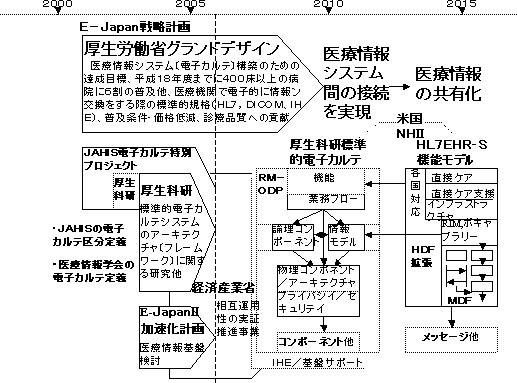
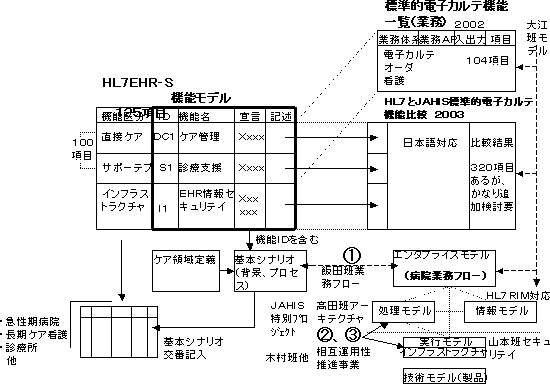
| ・ | 米国のNHIIは、オーストラリア、英国そしてとりわけカナダのEHR開発を参考にしていると言われている。従来の(1)HL7のメッセージ基盤に(2)VA開発のサ−ビス部分をOMGで標準化し、(3)SNOMED−CTなどの用語を組み合わせたかたちとなる。日本としては今後実際に標準的電子カルテを開発していく上での課題は次のとうり。 |
| 1) | 国の医療情報ネットワークと地域での開発運用をどのように進めて行くのか。 |
| 2) | その上に標準化され認定された共通の部品や製品をどのように提供サポートして行くか。 |
| 3) | 標準化や相互運用性をさらにレベルアップしていく体制をどのように確立していくか(経済産業省の相互運用性実証推進事業との連携を含めて) |
| ・ | ブッシュ大統領がこの1月の一般教書演説で、「医療情報をコンピュータで処理することにより、危険な医療ミスをなくし、コスト削減を図り、医療を改善する(By Computerizing Health Records, we can avoid dangerous medical mistake, reduce costs, and improve care)」と、ヘルスケアIT技術のアップグレードについての要望を明確化した。 |
| ・ | 英国は2002/10,NHS( National Health Service-1M人,£50B/年予算)の近代化NPfIT( National Project for IT)を1兆円以上をかけ、「必要な時に、必要なところで、より良い情報にもとずき、患者により良い保健を提供」を開始した。 |
| ・ | カナダは2002/6,「相互運用性のあるEHRソリューションで世界的リーダになる」を目標に官民で投資、プロジェクト推進組織Infowayを設立、地方(州)の展開を含め3−4,000億円規模で推進中。 |
| ・ | オーストラリアは2001年以降第二次Health Onlineプロジェクト推進中。最も先行し、少ないリソースを活かす戦略的な展開を行っている。 |
| ・ | 先進国の先行プロジェクトに続き急速に多くの国々で立ち上がりつつある。 |
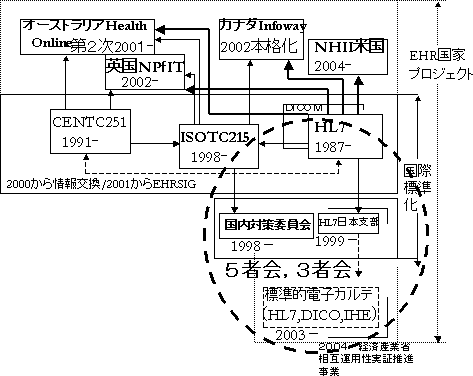
| ・ | 医療情報システムの標準化は、DICOMやHL7などの業界標準化がボトムアップで先行した。 |
| ・ | その後ヨーロッパ中心のトップダウンの研究開発の成果がGEHRやopenEHRとしてまとめられ、CEN等に反映された。 |
| ・ | HL7とCENとの間での競合から、交流、連携となり、ISOTC215やHL7EHRSIG,EHRcomなどの体制が整備されEHRの標準化が加速された。 |
| ・ | 欧米では2001年以降EHRの国家プロジェクトが始まった。 |
| ・ | 国内でも5年ほど前から、ISOTC215やHL7等への対応が進められ、EHRに向けた新たな段階を迎えている。 |
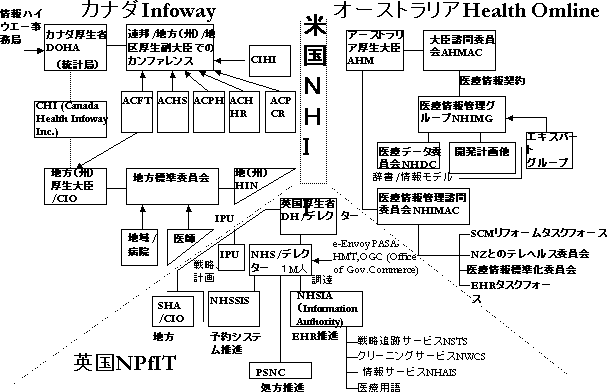
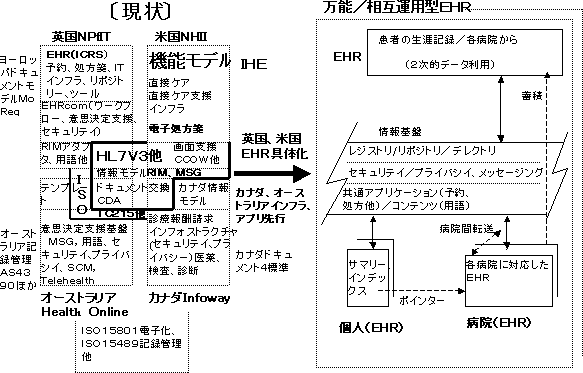
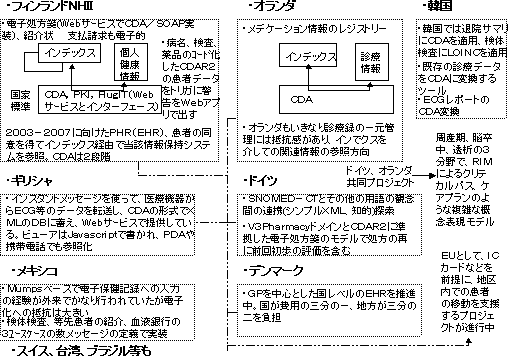
| ・ | EHRは医療情報の共有という従来の医療情報システム間の情報交換での機能的相互運用性からさらに一歩進んだ医療情報のセマンテックのレベルでの相互運用性を目指すものである。 |
| ・ | 従来の院内中心のシステムは、まず院内外のシステムとの情報交換を効率よく安全に行うとともに、意思決定支援CDSなどの機能と情報の整備や用語コードの統一などを含めた大規模な対応が必要となる。 |
| ・ | このため国の状況に合わせ、関連者のコンセンサスを十分に取りながら計画的に進める必要がある。 |
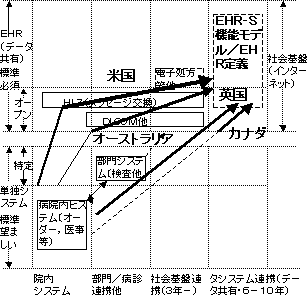
| ・ | 国家規模のEHR開発プロジェクトは、各国の政策が大きく影響している。オーストラリアは医療産業が最大の産業であり、特に東南アジアを中心に開発途上国への事業展開を目指し、国が早い時期に集中的に先行投資している。 一方英国は国内の事業として継続的に資金を投入している。 |
| ・ | これらに対し、カナダは、北欧の政策に学び電子政府プロジェクトをはじめ投資主導型(効果が明確になるに従い投資が加速化)で国家規模のプロジェクトを進めておリ、政府、公共と民間でCanada health Infoway(略称Infoway)Inc.を設立し、EHRプロジェクトの相互運用性と投資の推進とフォローを行っている。 |
| ・ | また米国は医療の産業化をめざし、診療に市場型を取り入れ、民間主導での改革を進めている。一方GDPの14%以上という巨額の医療費を使いながら多くの課題も抱え、EHRによる抜本的な対応を求められている。EHR開発先行国のプロジェクトを注意深く検討しNHIIを立ち上げつつある。 |
| ・ | EHRシステムの開発にはそれぞれの先行国から学ぶことは多いが、特にカナダと米国からは、産業化と投資主導型の推進方法は直接的にベンチマーキングを行う必要性は高いと思われる。 |
| ・ | カナダは、国自体が世界に向けた事業を展開しなければとの危機意識が高く、また広い国土に分散した国民の医療福祉をITで対応していくとの考え方が北欧と共通しています。 |
| ・ | EHRに関しては、1999年の報告にもとずき準備し、2002年に戦略投資組織のInfowayを設立し、国際レベルのEHR開発に向けてのプロジェクト推進を積極的に推進しています。世界の動きを見ながらインフラの充実とポテンシャルの高いアプリケーションを標準重視で進めている。 |
| ・ | HL7カナダはCIHI(Canada Institute Health Information)の傘下にあり、設計、実装の2技術委員会があり活発に活動している。 |
| ・ | また米国のNHIIに、目的、プロセス、内容で最も影響を与えた。 |
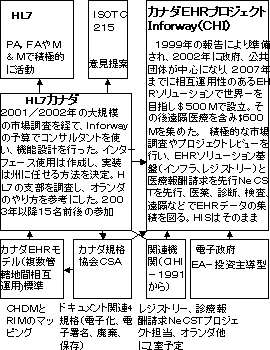
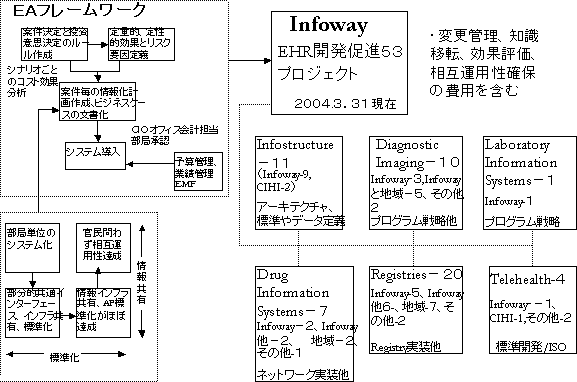
| ・ | IHEは放射線関連の分野から、標準を使用したシステムの実装を格段に高い効率と品質を実現することを目指し5年前に設立され、目覚しい成果を挙げている。 |
| ・ | EHRの開発は一方で、患者や医療関係者へのアンケートを含めその実現にはいろいろ苦労をしているのも事実である。 「臨床に係る人とシステムの開発者が一体となって研究開発していかなければ、真に臨床の現場で利用できるようなシステムにはならないであろう」ということがコンセンサスになってきている。 |
| ・ | その意味で、IHEは利用者として、「医療機関」と「ベンダ」がIT化についての考え方、実現手段を共有できる点でEHRの実現で重要な役割を持つ。 HIMSSはIHEのスポンサーとしてまたこれらの会員を中心にした大組織で、EHR実現に向けた環境つくりに重要な役割を果たすことになる。 |
| ・ | IHEのこれまでの成果の蓄積で、米国メデアも単に効率向上ではなく、お互いのビジネスチャンスの拡大に貢献していると高く評価している。また最近は、放射線関連から分野を広める一方ITI(ITインフラストラクチャ)へのサポートを拡大し、特にEHR−LR(計時的記録)の実装の設計と既存の標準でのデモを2004HIMSSで予定している。 |
EHR開発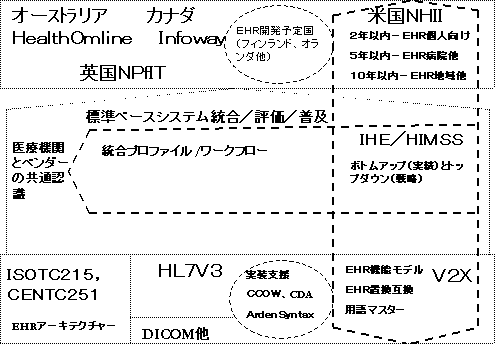 |
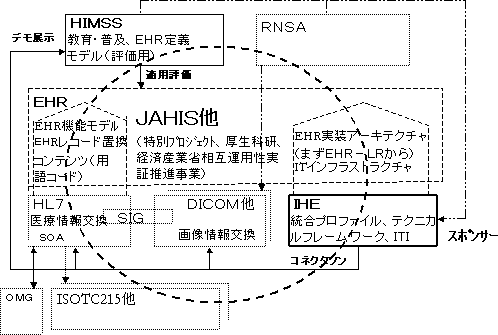
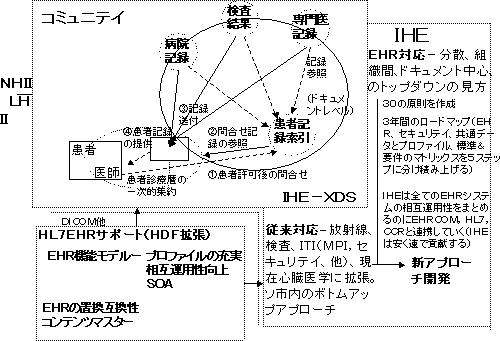
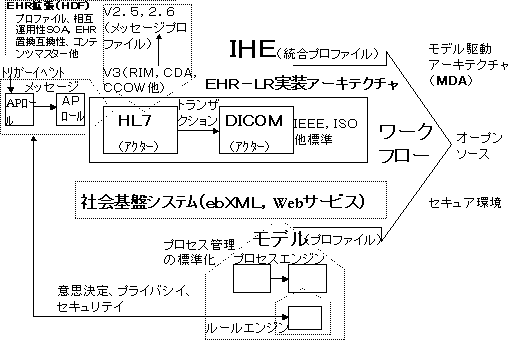
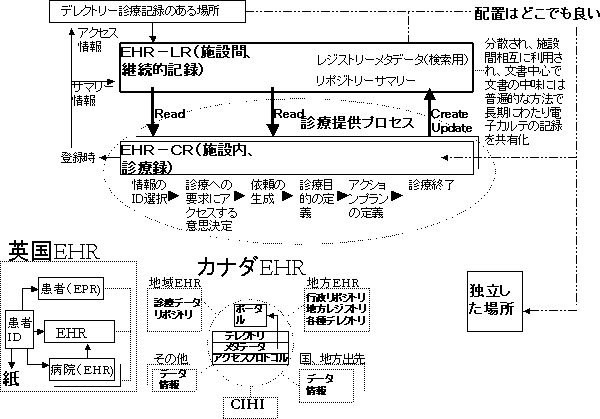
| HIMSSEHR定義モデルV1(EHR委員会) | |
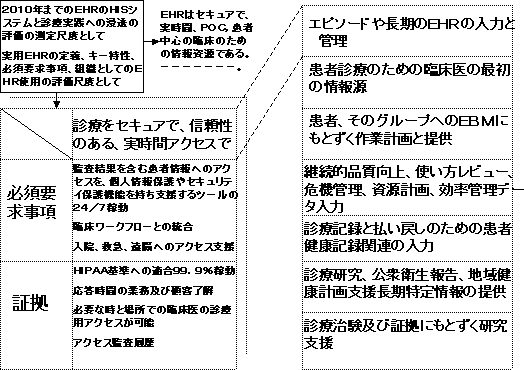 | |
|
 |
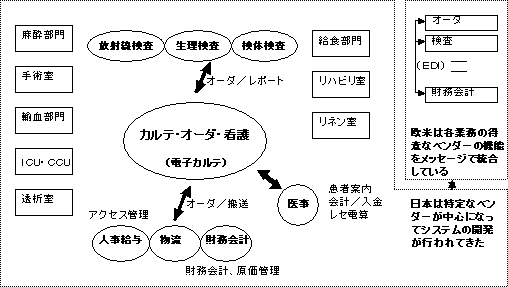
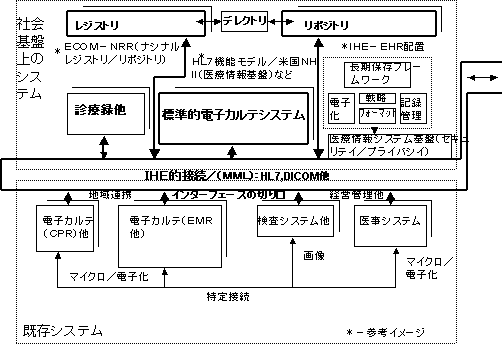
| 経済産業省から7月30日に「医療情報システムにおける相互運用性の実証事業」が公募されました。 右の図のような構成事例や実証事業例が示されていますが、これらを実現していく上で、IHEがマルチベンダーによる、安価で素早い実装を行うシステム統合の考え方が有効になると考えられる。
IHEの実績のあるボトムアップの考えと、EHRに向けたトップダウンでのITインフラストラクチャーの支援を活かした対応が求められる。 |
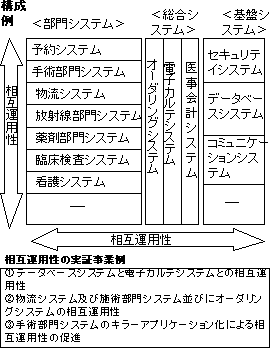 |
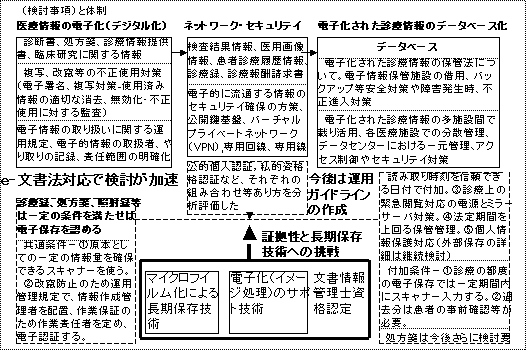
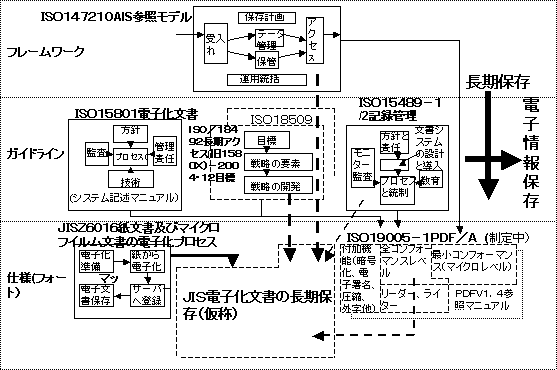
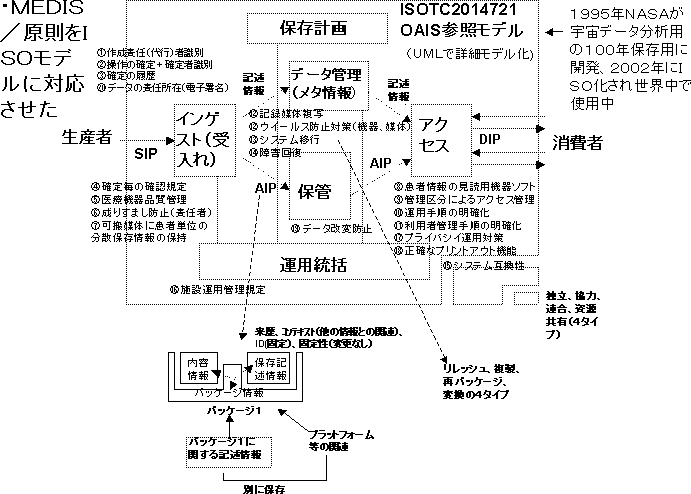
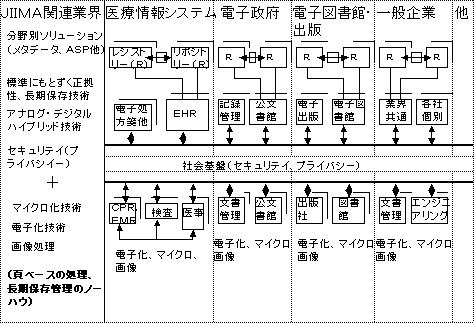
| ・ | 欧米を中心にEHRの開発が10年規模の国家プロジェクトとして動きだし、EHR関連標準もフレームが固まってきた。 |
| ・ | 日本においても大きな方向付けが厚生労働省のグランドデザインで示され、e‐Japan戦略の中でも重点項目として位置付けられ、IHEの考え方を活かせる経済産業省の相互運用性の実証推進事業の公募も開始された。今後これらの事業と関連し,まず基盤をしっかり確立し、関連部署が標準化をはじめ必要な施策を分担連携して推進する体制の整備が期待される。 |
| ・ | 医療機関側、ベンダー側それぞれで実施する一方、実装に重点を置くIHEの考え方を活かし、医療機関ベンダーのエキスパートが現場の状況を詳細に把握しながら、標準を活かし、安価にすばやくシステムを組み立て、関連者間でのコンセンサスと信頼感を一層増進することが期待される。 |
hide.hasegawa@mx8.ttcn.ne.jp