| へき地保健医療対策検討会 | 資料-3 |
| 第1回(H17.1.24) |
無医地区調査表(案)
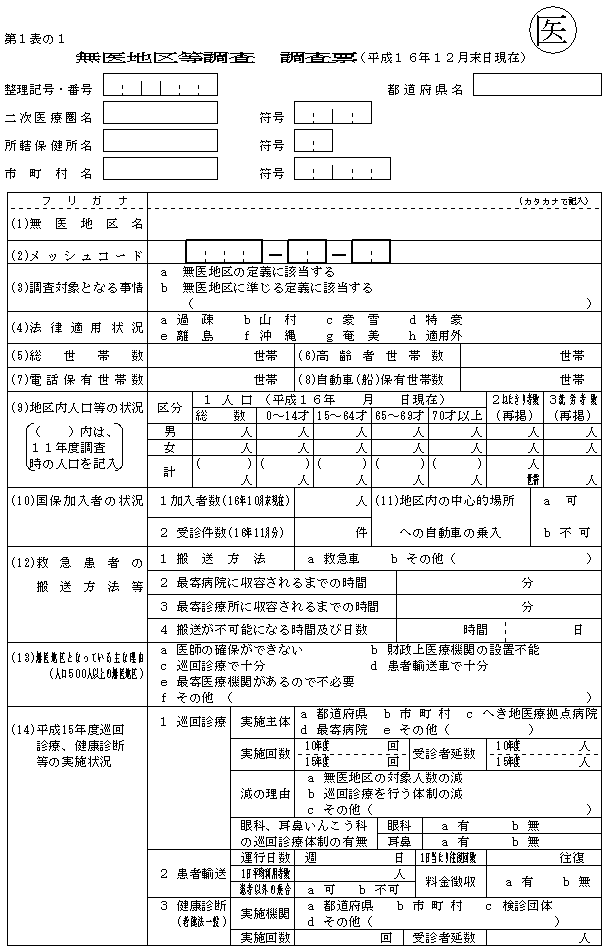
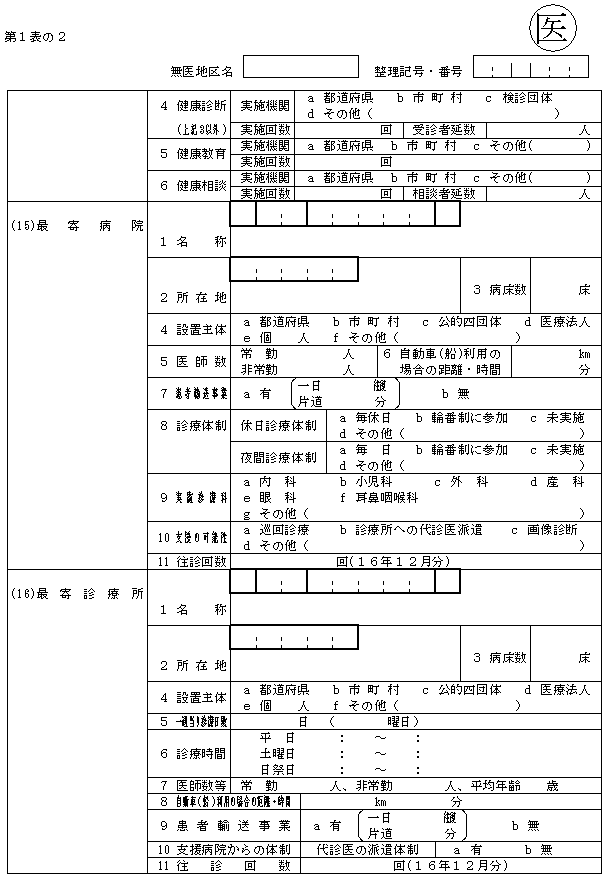
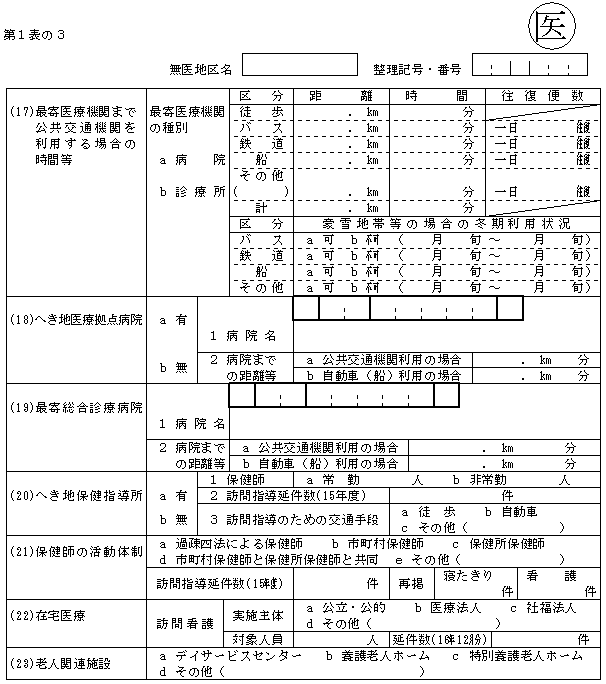
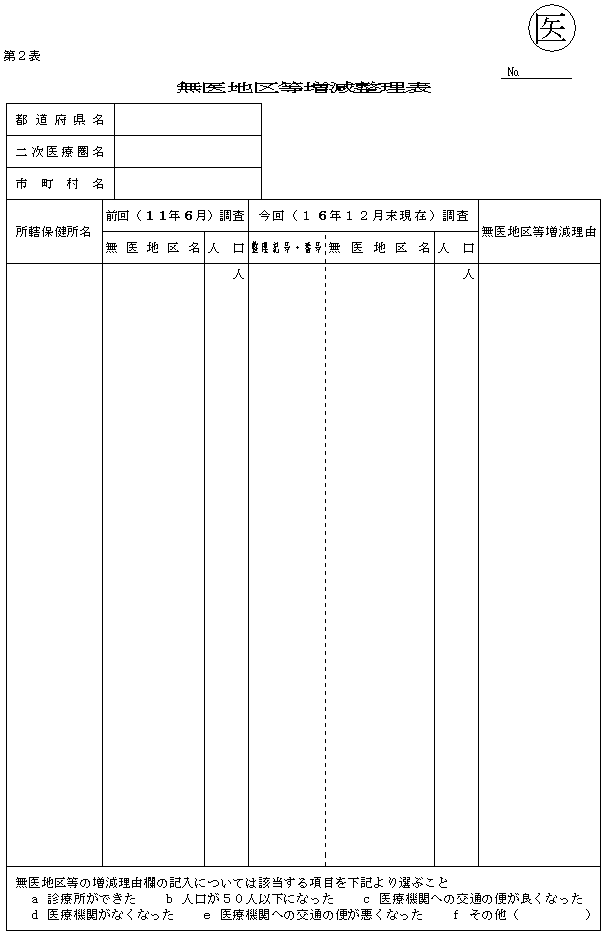
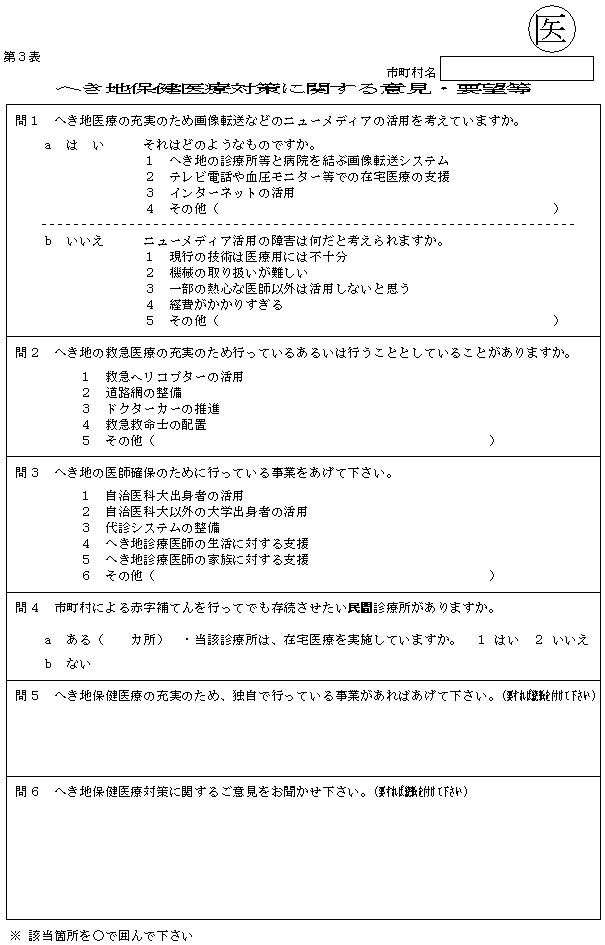
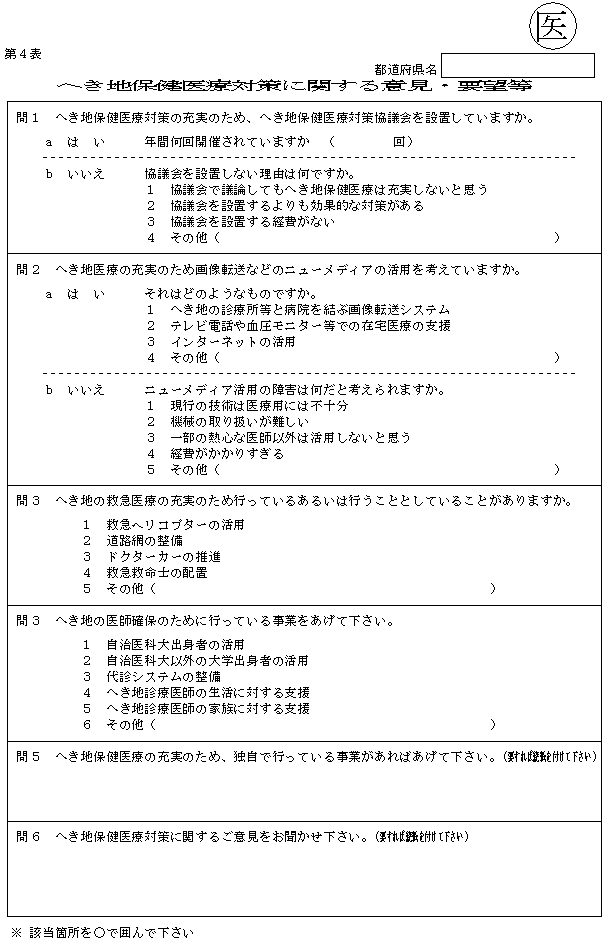
平成16年12月末現在
厚生労働省医政局
目次
1 調査の目的
2 調査の対象
3 調査事項
4 調査機関
5 調査票の作成者
6 調査日及び調査票の提出期限
7 用語の定義
1 第1表
2 第2表
3 第3表
4 第4表
(別紙)
二次医療圏コード一覧
I 調査の概要
1 調査の目的
この調査は、全国の無医地区等の実態及び医療確保状況の実態を調査し、へき地保健医療体制の確立を図るための基礎資料を得ることを目的とする。
2 調査の対象
全国の無医地区及び無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区(以下「無医地区に準じる地区」という。)を有する市町村とする。
3 調査事項
無医地区等の状況、最寄医療機関までの交通事情及び無医地区等の内情等を調査する。
4 調査機関
この調査は、厚生労働省医政局長が各都道府県知事の協力を得て行うものとし、知事は無医地区等を有する市町村長を指導して行うものとする。
5 調査票等の作成者
この調査票等は、原則として次の区分により各都道府県知事及びその指導の下に市町村長が作成する。市町村長は、調査票等の作成にあたっては、必要に応じ都道府県又は所轄の保健所長と協議等を行い、責任をもって作成する。
(1)市町村長が作成するもの …………………………… 第1表、第2表、第3表
(2)都道府県知事が作成するもの ……………………… 第4表、地図
6 調査日及び調査票等の提出期限
(1) この調査日は、平成16年12月末現在とする。
(2) 市町村長は平成17年 月 日までに調査票等を都道府県知事に送付すること。
(3) 都道府県知事は、提出された調査票について必要な審査を行い、無医地区等の整理記号・番号等を付し、また、併せてへき地保健医療対策に関する都道府県の意見・要望等及び地図を作成し、各1部を平成17年 月 日までに厚生労働省医政局長あて提出すること。
7 用語の定義
(1)「無医地区」
本調査で無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区をいう。
(注)ア この定義でいう「医療機関」とは、病院及び一般診療所をいい、へき地診療所等で定期的に開診されている場合を含む。
(ア)診療日の多少にかかわらず、定期的に開診していれば無医地区とはならない。
(イ)診療所はあるが、医師の不在等の理由から、「休診届」がなされている場合は無医地区として取り扱う。
イ この定義でいう「おおむね半径4kmの区域」のとり方は地図上の空間距離を原則とするが、その圏内に存在する集落間が、山、谷、海などより断絶されている場合は分割して差し支えない。(15,16ページ例参照)
ウ この定義でいう「容易に医療機関を利用することができない」場合とは、夏期における交通事情が次の状況にある場合をいう。
(ア)地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関がない場合
(イ)地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関はあるが、1日3往復以下であるか、または4往復以上であるが、これを利用しても医療機関まで行くために必要な時間(徒歩が必要である場合は徒歩に必要な時間を含む)が1時間をこえる場合。
(ウ)ただし、上記(ア)または(イ)に該当する場合であっても、タクシー、自家用車(船)の普及状況、医師の往診の状況等により、受療することが容易であると認められる場合は除く。
(たとえば、道路事情(舗装状況、幅員等)、地理的条件(都市の郊外的存在)、近在医師の往診が容易である等医療機関がないことについて、住民の不便、不安感がないというような事情を考慮して判断すること。)
(2)「無医地区に準じる地区」
無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区をいう。
(注) この定義でいう、「各都道府県知事が判断し」とは、無医地区の定義には該当しないが、無医地区として取り扱うべき特殊事情として次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に、無医地区に準じる地区として適当と認められる地区であるか判断する。
ア 半径4kmの地区内の人口が50人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶されていて、容易に医療機関を利用することができないため、巡回診療が必要である。
イ 半径4kmの地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね3日以下)又は診療時間が短い(概ね4時間以下)ため、巡回診療等が必要である。
ウ 半径4kmの地区内に医療機関はあるが眼科、耳鼻いんこう科などの特定の診療科目がないため、特定診療科についての巡回診療等が必要である。
エ 地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関があり、かつ、1日4往復以上あり、また、所要時間が1時間未満であるが、運行している時間帯が朝夕に集中していて、住民が医療機関を利用することに不便なため、巡回診療等が必要である。
オ 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運行数が少なくなり、住民が不安感を持つため、巡回診療等が必要である。
II 調査票の記入要領
1 第1表「調査票」
○本票は無医地区等ごとに作成すること。
○符号(コード番号等)については、都道府県が記入することとし、都道府県の統計業務担当部局と連絡のうえ、誤記のないように特に留意すること。
(参照)
- 都道府県別市町村別符号及び保健所符号一覧(厚生労働省大臣官房統計情報部)
- 市町村別地域メッシュコード一覧(総務省統計局)
- 二次医療圏コード一覧(別紙)
○本票において、時間の記入は、分単位((12)の4は除く)で記入すること。
(例:1時間25分→85分)
○本票において、時刻の記入は、1日24時間表示方式によること。
(例:午後1時30分→13:30)
整理記号・番号 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二次医療圏名 |
それぞれ無医地区等が所在する二次医療圏等の名称を記入するとともに、その符号を記入すること。
(注)二次医療圏とは、医療法第30条の3第2項第1号に規定する区域をいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 無医地区名 |
無医地区等の中心的集落の名称又は当該地区について固有の名称があれば、その名称を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) メッシュコード |
当該地区の中心的な場所の第3次地域メッシュコードを記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 調査の対象となる事情 |
該当するものの記号を○で囲むこととし、「b無医地区に準じる定義に該当する」に該当する場合は、その具体的事情を( )内に簡潔に記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 法律適用状況 |
次により該当するものの記号を○で囲むこと。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 総世帯数 |
当該地区内の総世帯数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 高齢者世帯数 |
当該地区内の世帯における男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成する世帯、又は、これに18歳末満の者が加わった世帯の世帯数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 電話保有世帯数 |
当該地区内の世帯における電話機(有線放送電話用を含む)の保有世帯数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 自動車(船)保有世帯数 |
当該地区内の世帯における自動車(離島内に所在する無医地区等であって島内に医療機関がない場合には自動車に替えて船とする)の保有世帯数を記入すること。 (注)1 ここにいう自動車とは、道路運送車両法にいう普通自動車、三輪及び四輪の小型自動車及び軽自動車(二輪を除く)とする。 (注)2 ここにいう船とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法に規定する小型船舶操縦士以上の資格がなけれは操縦することができない船舶をいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 地区内の人口等の状況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 人口 (平成16年 月 日現在) |
当該地区内の住民の数で、把握している直近の住民基本台帳人口とし、その時点を明記すること。 なお、計欄の上段( )には、前回調査時点の数を記入(前回調査時には無医地区等に該当しなかった場合には空白)すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ねたきり者数 |
身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障のあるいわゆるねたきり者の数及びその者の居る世帯数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 就労者数 |
職業に従事している者の数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)国保加入者の状況 |
当該地区内における平成16年11月末日現在の国民健康保険被保険者数及びこれらの者の平成16年12月の受診件数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)地区内の中心的場所への自動車の乗入 |
該当するものの記号を○で囲むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)救急患者の搬送方法等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 搬送方法 |
消防署に設置されている救急車が出動する体制が整っている地区にあってはaを○で囲み、その他の地区にあってはbを○で囲むとともに、その場合の方法を( )内に簡潔に記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2,3 最寄病院・診療所に収容されるまでの時間 |
上記の搬送方法によって、電話等で要請してから最寄の病院、診療所に収容するまでの所要時間を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 搬送が不可能になる時間及び日数 |
1日のうち、救急患者の搬送が不可能となる時間があれば、その時間数を記入すること。また、平成15年度中に天候等により外部との交通が遮断された日があれば、その日数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)無医地区となっている主な理由(人口500人以上の無医地区) |
人口500人以上の無医地区において、該当するものの記号を○で囲むこととし、「fその他」に該当する場合は、その理由を( )内に簡潔に記入すること。(2以上の理由に該当する場合(重複)もある。) なお、人口500人未満の無医地区及び無医地区に準じる地区においては、記入を要しないものであること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)平成15年度巡回診療、健康診断等の実施状況 |
当該地区を対象として行われる巡回診療、患者輸送、健康診断、健康教育、健康相談の15年度実績を記入すること。 (注)1 「巡回診療」とは、投薬処理等を含んだ診療を行うものをいう。また、実施主体、減の理由、眼科、耳鼻いんこう科を含んだ巡回診療体制の有無については該当する記号を○で囲むこととし、「その他」に該当する場合は、その実施主体・理由を( )内に記入すること。 2 「患者輸送」とは、曜日、日時を定める等定期的に行っているものをいい、臨時的(救急輸送等)に行ったものは除く。また、料金徴収の有無、患者以外の乗合を認めているか該当するものの記号を○で囲むこと。 3 「健康診断」とは、循環器検診、がん集団検診、成人病健康診断、妊産婦健康診査、乳幼児健康診査等をいう。 4 「健康教育」とは、講演、パンフレット配布等不特定数に対して行う健康に関する啓蒙、普及等の活動をいう。 5 「健康相談」とは、健康の失調、機能障害又は慢性疾患等を有する者又はその家族等に対し、健康保持、疾病の予防、療養方法、リハビリテーション等に関する相談、指導を行うことをいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)最寄病院 |
当該市町村内か否かを問わず、道路状況等から判断して、当該地区から最も近い一般病床を有する病院をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 名称 |
最寄病院の名称を記入するとともに、医療施設基本ファイル(厚生労働省大臣官房統計情報部)に使用している当該病院の整理番号を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 所在地 |
最寄病院の所在地及び市町村コードを記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 病床数 |
医療法上の許可病床数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 設置主体 |
該当するものの記号を○で囲むこととし、「fその他」に該当する場合は、その設置主体を( )内に記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 医師数 |
当該病院の診療に従事する医師数を常勤、非常勤ごとに記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 自動車(船)利用の場合の距離・時間 |
全行程を自動車(又は船)のみで利用した場合の、その距離と所要時間を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 患者輸送事業 |
当該地区と病院間に、定期的な患者輸送事業が実施されているか否かにより、該当するものの記号を○で囲むこととし、「a有」に該当する場合には、1日の輸送回数及び片道の所要時間(分)を( )内に記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 診療体制 |
当該病院の休日診療、夜間診療について該当するものの記号を○で囲むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 実施診療科 |
当該病院の診療科(休診の診療科は除く)について該当するものの記号を○で囲むこと。なお、a〜fの診療科以外の診療科がある場合は、「gその他」の記号を○で囲むとともに、その診療科をすべて( )内に記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 支援の可能性 |
当該地区に対する医療支援の可能性について該当できるものの記号を○で囲むこと。(複数回答も有り得る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 往診回数 |
当該地区内における平成16年12月分の往診回数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)最寄診療所 |
当該市町村内か否かを問わず、道路状況等から判断して、当該地区から最も近い診療所(歯科単独の診療所を除く。)をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 名称 |
最寄診療所の名称を記入するとともに、医療施設基本ファイル(厚生労働省大臣官房統計情報部)に使用している当該診療所の整理番号を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 病床数 |
医療法上の許可(届出)病床数を記入すること。 なお、無床の診療所の場合にあっては「無」と記入すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5 1週当りの診療日数 |
1週当りの診療日数(救急患者の診療を除く)を記入することとし、曜日等を決めて診療している場合には「( 曜日)」にその曜日を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 診療時間 |
救急患者以外の患者の診療を受付ける時間帯を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 医師数等 |
当該診療所の診療に従事する医師数を常勤、非常勤ごとに記入すること。なお、平均年齢欄には、常勤、非常勤全員の年齢の平均を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 支援病院からの体制 |
当該病院の診療に従事する医師数を常勤、非常勤ごとに記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 所在地 4 設置主体 8 自動車(船)利用の 9 患者輸送事業 11 往診回数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)最寄医療機関まで公共交通機関を利用する場合の時間等 |
最寄医療機関とは、当該地区から最も近い医療機関(上記最寄病院又は最寄診療所のいずれか一方)をいい、その種別について該当するものの記号を○で囲むとともに、当該地区の中心的場所から最寄医療機関まで公共交通機関を利用する場合の順路に従い、距離、時間及び夏期における1日(平日)の往復便数を記入すること。この場合、途中に交通機関の乗継ぎがあって、その乗継ぎのための待ち時間が生じるのが普通の状況の時は平均的な待ち時間を加えてよいこと。また、豪雪地帯等の場合で、冬期間のうち1ケ月以上交通機関が機能を果たさないか否かによって該当するものの記号を○で囲むこととし、「b不可」に該当する場合は、その平均的期間を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)へき地医療拠点病院 |
当該地区を担当するへき地医療拠点病院が指定されているか否かによって該当するものの記号を○で囲むこと。なお、「b無」に該当する場合は、次の1、2についての記入を要しないものであること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 病院名 |
当該へき地医療拠点病院の名称を記入するとともに、医療施設基本ファイル(厚生労働省大臣官房統計情報部)に使用している当該病院の整理番号を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 病院までの距離等 |
当該地区の中心的場所から、へき地医療拠点病院までの距離及び時間について、公共交通機関を利用する場合と、全路程が自動車(又は船)のみで利用できる場合(できない場合には記入を要しない)のそれぞれの場合において記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(19)最寄総合診療病院 |
最寄総合診療病院とは、従前の医療法の規定による総合病院に相当する病院のうち、当該地区から最も近い病院をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 病院名 |
当該最寄総合診療病院の名称を記入するとともに、医療施設基本ファイル(厚生労働省大臣官房統計情報部)に使用している当該病院の整理番号を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 病院までの距離等 |
当該地区の中心的場所から、最寄総合診療病院までの距離及び時間について、公共交通機関を利用する場合と、全路程が自動車(又は船)のみで利用できる場合(できない場合には記入を要しない)のそれぞれの場合において記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20)へき地保健指導所 |
当該地区のためのへき地保健指導所の有無により、該当するものの記号を○で囲むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 保健師 |
当該へき地保健指導所の訪問指導に従事する保健婦数を常勤、非常勤ごとに記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 訪問指導延件数 |
当該地区を対象として行われる訪問指導のうち、当該へき地保健指導所が行う訪問指導の15年度実績を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 訪問指導のための交通手段 |
上記2の訪問指導を行うための通常の交通手段について、該当するものの記号を○で囲むこととし、「cその他」に該当する場合は、その手段を( )内に簡潔に記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(21)保健師の活動体制 |
上記(20)へき地保健指導所の有無について、「b無」に該当する場合のみ記入すること。 当該地区を担当する保健師について、該当するものの記号を○で囲むこととし、「eその他」に該当する場合には、( )内に簡潔に記入すること。なお、当該保健師が15年度中に、地区内の者に対して行った訪問指導の延件数と再掲で寝たきりと看護の件数も記入すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(22)在宅医療 |
当該地区に対する訪問看護を行っている訪問看護ステーションがあれば、その実施主体について該当するものの記号を○で囲むこと。また、当該地区内における訪問看護の対象人数と地区内の者に対して行った訪問看護の平成16年12月分の延件数を記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(23)老人関連施設 |
当該地区内に設置されている老人関連施設がある場合は、該当するものの記号を○で囲むこととし、「dその他」の場合は、その施設を( )内に記入すること。 |
2 第2表「無医地区等増減整理票」
本表は、無医地区等を有する市町村単位毎に作成するものとし、前回(11年6月)と今回を対比させて作成するものとする。
整理番号・番号 |
第1表「調査票」の整理記号・番号に付した上3桁目の記号及び下3桁の数字と一致させること。
|
|||||||
無医地区等増減理由 |
前回調査時と比較して増又は減となった理由は理由項目例から選ぶこと。 |
3 第3表「へき地保健医療対策に関する意見・要望等」
本表は、無医地区等を有する市町村単位毎に作成するものとする。
4 第4表「へき地保健医療対策に関する意見・要望等」
本表は、各都道府県が作成するものとする。
III 地図の作成要領
無医地区等を記入する地図は都道府県全域が1枚に表示されているもので、原則として20万分の1以内のものを用いることとし、下記要領により都道府県知事が無医地区等地図として取りまとめ作成すること。
| (1) | 無医地区等の記入 | ……… | 「無医地区」は赤線、「無医地区に準じる地区」は青線にて表示すること。半径4kmの枠いっぱいに円(円を基礎とした他の図形、半円、タイコ型等を含む)を描くこととし、単に中心集落の表示にとどめないこと。 |
| (2) | 無医地区等一連番号の記入 |
……… | 上記無医地区等には都道府県において第1表に付した無医地区記号・番号を明記すること。 |
| (3) | 最寄医療機関の表示 |
……… | 医療機関の所在地に赤色で病院はH、診療所はCと記入すること。 |
| (4) | 二次医療圏の表示 | ……… | 二次医療圏について、境界を緑線にて表示し、圏域名を明記すること。 |
IV 無医地区の設定例
注 略称は次のとおりとする。
H ……… 病院
C ……… 診療所
| (例1) | 道路沿いに集落がある場合 医療機関から4km以遠の地域を半径4km毎に区分して定める。 |
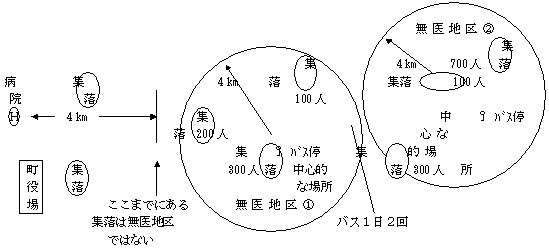
| (例2) | 医療機関を中心に集落が分散している場合 「定期交通機関なし、無医地区(豪雪)」 医療機関から半径4kmにない地域を半径4kmごとに区分して定める。 |
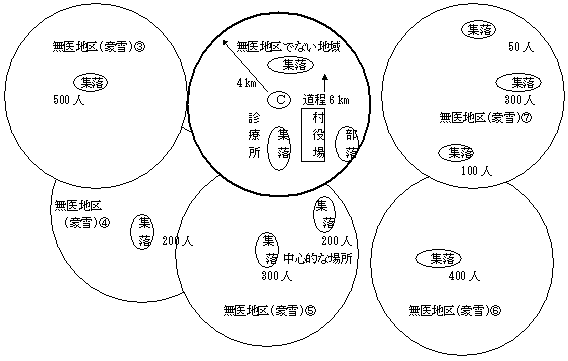
| (例3) | 山や谷をはさんで集落がある場合で半径4kmではかれば一つの無医地区となる場合でも集落間が断絶されているときは分けて地区を定める。 |
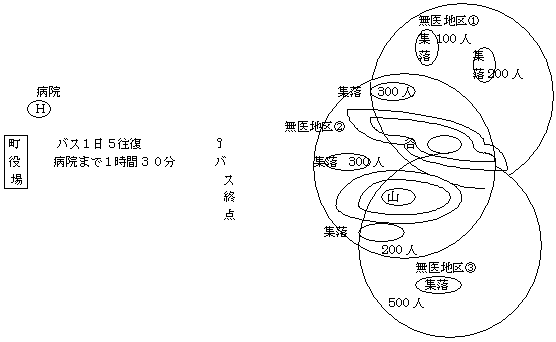
| (例4) | 離島の場合も同じ方法による。無医地区 |
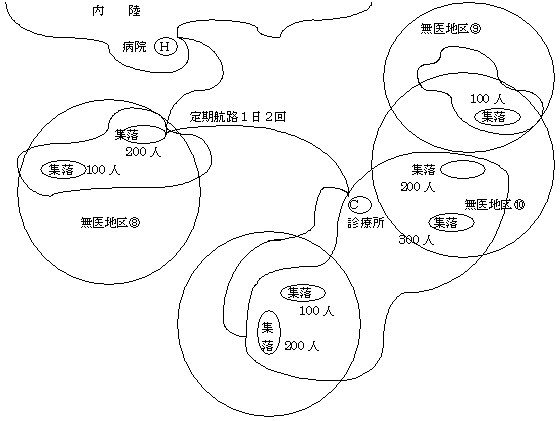
(別紙)
|
|