| 支出の実態(一般家計、グループホーム、入所施設) |
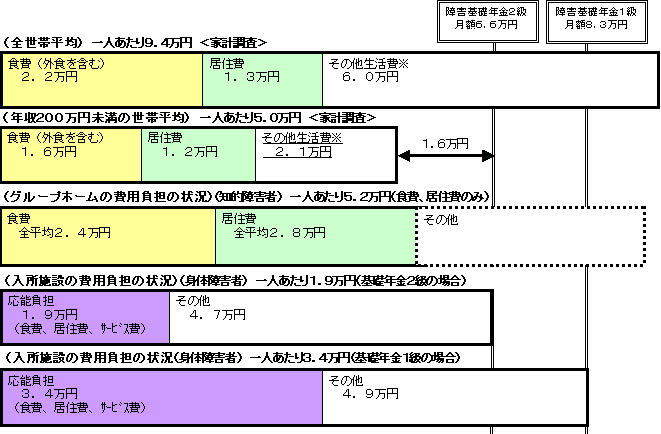
| ※ | その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である |
| 費用負担に関する考え方 |
| 障害福祉サービス(個別給付)に係る 利用者負担の見直しの必要性 |
|
| 現行の費用徴収の仕組み(負担の不均衡) |
| 平成15年度実績 | 支援費 | 児童入所施設 (親等) |
||||||
| ホームヘルプ | 入所・通所施設 | |||||||
| 生活保護 | 0円 | 0円 │ 53,000円
|
0円 | |||||
| 市町村民税非課税 | 0円 | 2,200円 | ||||||
| 市町村民税課税 (均等割課税) |
1,100円上限 (50円/30分) |
4,500円 | ||||||
| 市町村民税課税 (所得割課税) |
1,600円上限 (100円/30分) |
6,600円 | ||||||
| 所得税課税 | 2,200円上限 (150円/30分) 〜費用全額 |
9,000円〜費用全額 | ||||||
| 実質的な負担率 | 約1% | 約10%(入所) 約1%(通所) |
約5% | |||||
| 費用負担をしている者の比率 | 約5% (本人) |
約90%(入所・本人) 約5%(通所・本人) |
約70% | |||||
| ※1 | 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。 |
| ※2 | 精神障害者社会復帰施設は、負担の仕組みが異なり、食費、施設利用料等の実費については全額自己負担であり、直接サービスに係る負担はない。 |
| 支出の実態(一般家計、グループホーム、入所施設) |
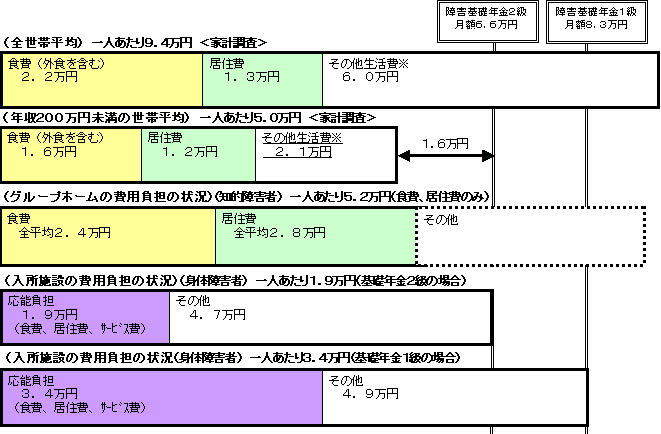
| ※ | その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である |
| 障害福祉サービスに係る利用者負担の見直しの考え方 ー実費負担+サービス量と所得に着目した負担ー |
負担能力の乏しい者については、経過措置も含め負担軽減措置を講ずる。 |
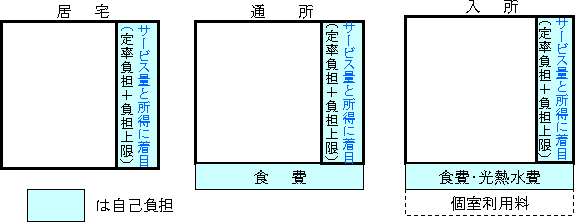
|
| 負担軽減する者の範囲(負担能力等の区分) |
|
|||||||||||||||
| ※ | 医療保険、介護保険等の他制度においては、障害のある者もない者も世帯の一員である場合には、経済的な面においては他の世帯構成員と互いに支え合う一体的な生活実態にあるという前提で、負担能力の有無を認定する際に、個人単位ではなく、「生計を一にする者」の全体の経済力を勘案しており、例えば健康保険においては、家族に保険料を求めない被扶養者制度等が設けられている。 |
| ※ | 「生計を一にする者」の範囲については、法律事項ではないことから、法の施行時までに具体的に検討。 |
| 食費等の実費負担の見直しの考え方 |
生活に係る実費については自己負担とすることを原則
|
| │ | │ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。それまでは、現行と同じ仕組み。 |
| 障害福祉サービスの利用者負担の見直し ーサービス量と所得に着目ー |
所得にのみ着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組みに見直す。
|
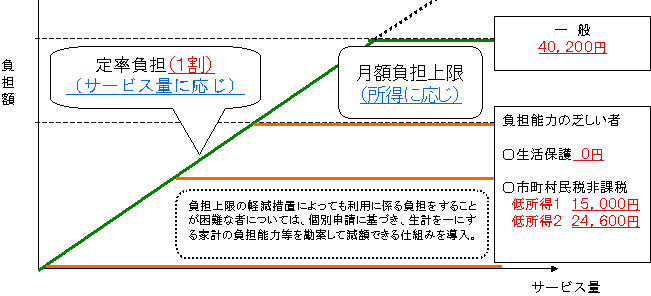
| ※ | 負担上限の該当の有無は、各サービスに係る負担額の合計で計算する。 |
| ※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。移行までは、現行と同じ仕組み。 |
| 定率負担に係るグループホーム、 入所施設(20歳以上)の個別減免(低所得1,2) |
|
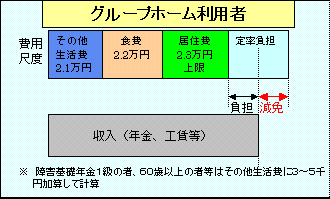 |
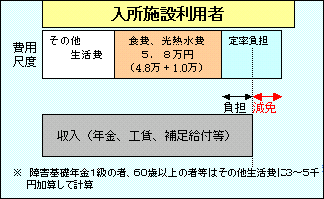 |
| 定率負担の個別減免(グループホーム/入所施設 )に係る収入認定 |
|
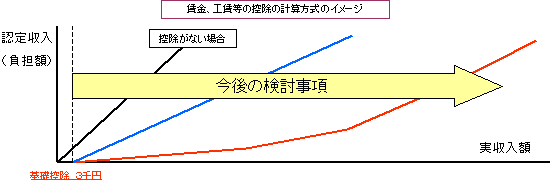
| 定率負担に係る特別減額制度(生活保護への移行防止)の概要 ー地域生活、入所施設共通ー |
| 本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限を適用。 |
| ||||
| ↓より低い | 上限額を適用 | |||
| ||||
| ↓より低い | 上限額を適用 | |||
|
| ※ | 認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとする。 |
| 今回講じた主な経過措置の概要 |
| 1 | 地域生活関係の経過措置(施行後3年間)
|
||||||||||||
| 2 | 入所施設関係の経過措置(施行後3年ごとに段階的に見直し)
|
| 平均的な利用者負担の例(在宅) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均的な利用者負担の例(グループホーム/入所施設) |
|
グル │ プホ │ ム ・ 入所施設個別減免 3年経過措置 |
特別減額制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改正案による各事業平均(マクロ)の負担の変化 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
食費等が同水準(5.8万円)であれば |
食費等が同水準(5.8万円)であれば
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。 |
| ※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。それまでは、現行と同じ仕組み。 |
| 平成17年度予算(内示)の概要(福祉サービス国庫ベース) |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ※ | 精神の施設は、平成17年度中には新施設・事業体系に移行しないので改正影響は生じない。 また、精神の平成17年度の居宅は12ヶ月分に置き換えたもの(予算上は11ヶ月分で41億円)。 |
| ※ | 児童入所施設関係は、平成18年10月施行のため平成17年度中は改正影響は生じない。 |
| 障害に係る公費負担医療制度の 利用者負担見直しの必要性 |
|
|
| 必要な医療を確保しつつ、費用を皆で負担し支え合うことにより、中長期的な障害者制度全体の持続可能性を確保(福祉・医療のバランスのとれた財源配分の確保) |
| 障害に係る公費負担医療制度の概要 |
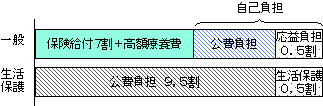 |
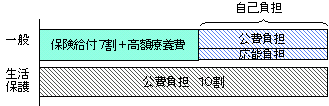 |
| 精神通院 (昭和40年創設) |
更生医療 (昭和29年創設) |
育成医療 (昭和29年創設) |
|
| 対象疾患 | 精神疾患 | 視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由、内部障害 等 |
視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由、内部障害 等 |
| 対象年齢 | 全年齢 | 18歳以上 | 18歳未満 |
| 月平均 利用件数 |
約70万件 (平成14年) |
約8万件 (平成14年) |
約1万件 (平成14年) |
| 1件平均 医療費 |
約3.2万円 (通院のみ) |
約40.0万円 (入院・通院) |
約41.2万円 (入院・通院) |
| 平均負担額 | 約1,600円/月 | 約3,200円/月 | 約5,600円/月 |
| 課税世帯割合 | 約1〜2割(推計) | 約5〜6割 | 約7〜8割 |
| 一人あたり医療費の構成(精神通院) |
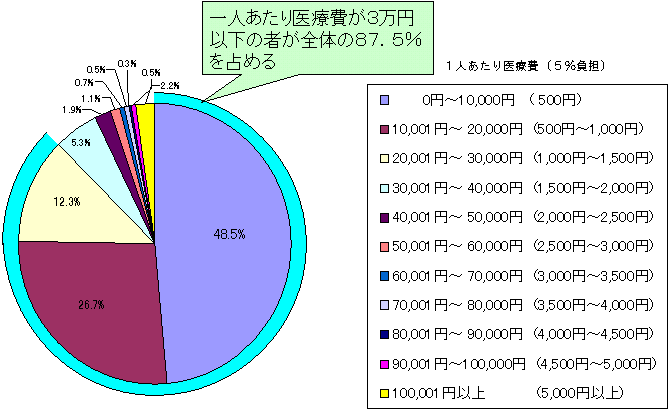
| 障害に係る公費負担医療の負担軽減措置の課題 |
○ 現行水準
|
| 医療内容面での見直し |
|
| 医療費と所得に着目した自己負担 |
医療費のみに着目した応益負担(精神)と所得にのみ着目した応能負担(更生・育成)を、次の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合する。
|
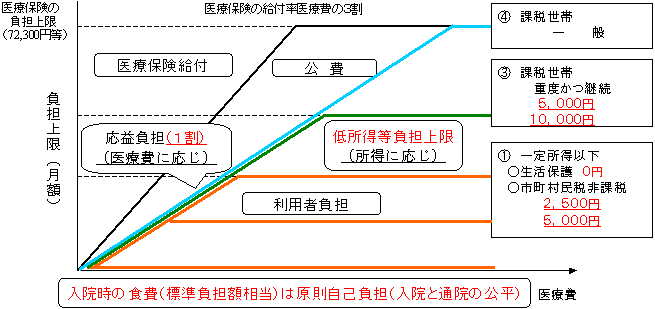
| 入院時の食費負担(標準負担額) |
|
| 制度改正案の概要 |
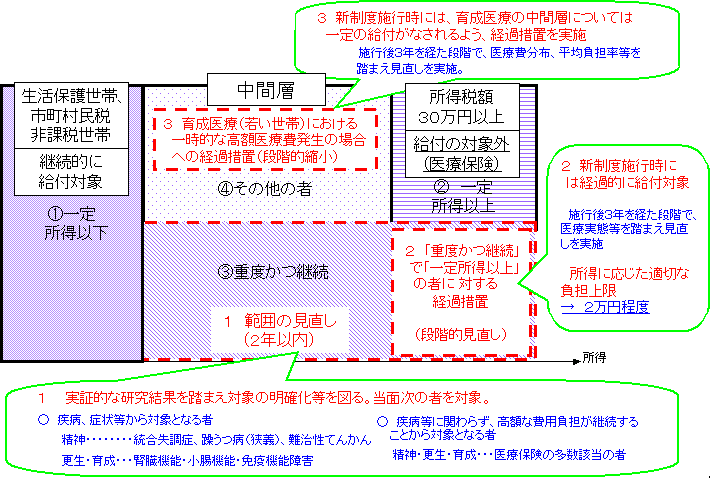
| 平成17年度予算(内示)の概要(公費負担医療国庫ベース) |
| 平成16年度 | 平成17年度 | 増減分 | 改正影響 | ||
| 精神通院 | 477億円 | 547億円 | +70億円 | △12億円 | |
| 更生医療 育成医療 |
111億円 | 108億円 | △3億円 | △26億円 |
| (参考資料) |
| 主な入所施設の費用負担の変化 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデル的な利用者の負担(精神通院) |
モデル1 精神通院:うつ病 月1回の受診と継続的な服薬 月額医療費約1万円
モデル2 精神通院:統合失調症 デイケア等を利用 月額医療費約15万円
|
| モデル的な利用者の負担(更生医療・育成医療) |
モデル3 更生医療:腎疾患 通院で人工透析を実施 月額医療費約28万円
モデル4 育成医療:先天性心臓疾患 月額医療費約150万円
|