図1 一括表示様式(主要項目のみ)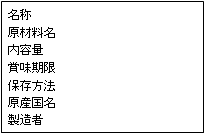 |
| 資料1 |
| わかりやすい表示方法について 報告書 (案) |
| ┌ │ │ │ │ └ |
厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 表示部会食品表示調査会 及び 農林水産省農林物資規格調査会表示小委員会 の共同開催 |
┐ │ │ │ │ ┘ |
| 1. | 表示方法をめぐる現状と課題
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | 表示方法の見直し方向(総論)
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | 表示位置
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | 原材料名の表示見直し
|
| (1) | 表示方法の概要 |
| 加工食品の表示方法については、食衛法、JAS法により規定されており、JAS法の加工食品品質表示基準においては、容器包装に所定の様式に従って一括して表示することが定められている(図1:一括表示)。 |
図1 一括表示様式(主要項目のみ)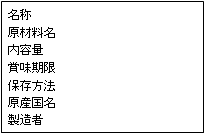 |
| また、生鮮食品については、JAS法に基づき名称、原産地を表示することとなっているが、表示方法については容器包装のほか、製品に近接した場所への掲示、またはその他見やすい場所に表示することとなっている。 |
| (2) | 表示方法をめぐる課題 |
| JAS法では、加工食品について義務表示事項を枠内に一括して表示する一括表示が原則であり、その様式が厳密に定められている。これにより、消費者は一括表示を見れば、法律に規定された義務表示事項に関する情報を知ることができることになっており、全ての加工食品に表示が義務付けられる中で、統一的な表示方法として秩序を保つのに大きな役割を果たしてきた。 しかしながら、多様な加工食品が存在し、表示を実施する事業者も多様化する中で、スーパーマーケット等の店頭で見られるいわゆるプライスラベル(図2)による表示が普及するなど、従来の一括表示に規定された表示方法のみでは、消費者への情報提供の観点から必ずしも十分に対応できない状況が明らかとなってきた。 |
図2 プライスラベルの例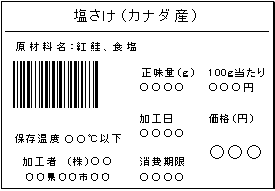 |
| また、国内外の食品以外も含めた諸制度の中で、表示様式まで厳密に規定しているのはJAS法だけとなっている。以上の状況を踏まえれば、JAS法の一括表示の基本的考え方は維持しつつ、表示様式を弾力化し、情報提供に多様性をもたせることも必要と考えられる。とりわけ、一括表示の中で最大のスペースを占める原材料表示については、原材料に加え食品添加物、遺伝子組換え、アレルギー物質を含む旨、原料原産地についても記載され非常に多くの情報を含んでいることから、わかりやすく適切な表示方法を検討する必要がある。この際、今後きたるべき高齢化社会を踏まえ、大きく、見やすい表示であることと、必要な情報を過不足なく提供できることの両面から、将来的には商品へのラベルのみならず、表示事項の一部についてICタグ等の電子情報技術を活用した情報提供も視野に入れて検討を進める必要がある。 |
| (1) | 表示様式の弾力化 |
| 表示方法を考える上で重要な点は、わかりやすく、誤認を与えないこと、表示事項が簡潔に理解しやすく表示されているかという点である。 この点から、一括表示様式を厳密に規定している点について見た場合、他の食品と比較しやすいというメリットはある。一方、容器包装された全ての加工食品に表示が義務付けられた今日にあっては、
なお、現在スーパーマーケット等の店頭で普及しているプライスラベルについては、義務的表示事項が過不足なく記載されているのであれば、JAS法に基づく一括表示として扱うべきである。 |
| (2) | 表示の文字の大きさの統一 |
| (資料2参照) |
| (1) | 名称、内容量 |
|
図3 名称と内容量の主要表示面への記載と一括表示の記載省略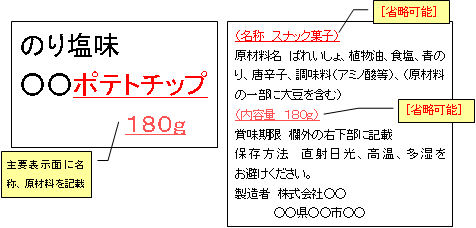 |
| (2) | 賞味(消費)期限、保存方法 |
| 賞味期限(消費期限)については、現行の加工食品品質表示基準においても、一括表示に記載することが困難な場合は、一括表示の賞味期限欄に記載箇所を表示すれば、一括表示外に記載することが可能となっている。また、この場合、保存方法についても、賞味期限の記載箇所に近接して記載することが可能となっている。 このため、多くの食品で印字等による賞味期限の記載が行われているが、記載箇所の表示が具体的でなかったり、項目名を書かずにロット番号などと一緒に印字されている等により、消費者からは「賞味期限がどこに書いてあるかわかりにくい商品がある」等の指摘がある。 このため、賞味期限の記載にあたっては、記載箇所を「キャップに記載」「この欄の上部に記載」等と具体的に示すとともに、印字の色を背景と対照とすること、消えにくい印字とすること、ロット番号その他の情報とは明確に識別できるようにすること等について、事業者に対し改めて徹底する必要がある。 |
| (3) | 製造者等 |
| JAS法では、「製造業者等の氏名又は名称及び住所」(製造者等)を一括表示内に記載することとされている。製造者等は、JAS法上表示内容に責任を持つ者であり、この表示責任者が特定されるためにも、「製造者」等の事項名を付して、他の表示事項と近接して表示されることが望ましい。この際、名称、住所に加え、電話番号や会社の問い合わせ窓口などを併記することも、消費者による商品情報確認を容易にする手段として有益である。 |
| (1) | 原材料表示の基本ルール |
| 原材料表示は、JAS法の加工食品品質表示基準に基づき、「原材料名」という事項名を記載した上で、使用した原材料を全て重量順に表示するのが原則となっている。この際、食品添加物は、(食品添加物以外の)原材料と分けて記載することとされており、食品添加物以外の原材料−食品添加物の順に記載されるのが通例である。 また、原材料名欄には、アレルギー物質を含む旨の表示、遺伝子組換え食品の表示、原料原産地表示が混在しており、その食品の特性を知るための最大の情報源となっている。 |
| (2) | 原材料表示見直しの基本的考え方 |
| 上記のように、原材料表示は、食品の特性を表現する重要なツールで、いわばその商品の特性を消費者に的確に提供しながら、誤認を招かないような形で適正に行われるべきである。こうした観点から、原材料表示については、義務表示と任意表示を組み合わせながら今後とも充実することが必要である。 一方、原材料表示は加工食品の一括表示の中で最も複雑であり、表示内容も多いことから、「表示全体のわかりにくさ」の大きな要因ともなっている。特に、多くの原材料を使用する商品や複数の加工食品の組み合わせからなる商品においては、原材料表示が膨大な量となり、消費者にとってわかりやすいとは言い難いものもある。このため、現行で規定された義務表示方法について、表示の目的を明確化した上で商品実態に即して現実的に見直し、必要に応じ簡素化を図ることが必要である。 また、加工食品の原材料や製法は多種多様であり、中間原料や多様な形態の原材料が使用される。このため、原材料表示の基本ルールである(1)使用した原材料を全て表示する、(2)原材料に占める重量の割合の多い順に表示する、という2点を遵守して適正に表示するために、個別の品質表示基準や業界の取り決め等で原材料の表示方法を定めた一部の食品以外では、個々の事業者が工夫して表示を行っている。その結果、同種の食品であっても個別の事業者ごとに原材料の記載順や表記方法がまちまちである等の状況が生じている。こうした点についても、運用改善が必要である。 |
| (3) | 商品の特性を的確に伝えるための原材料表示の充実 |
加工食品の原材料は、その商品の特性を付与する上で加工技術と並んで重要な位置を占めており、消費者にとっても商品選択の材料となることから、特色ある原材料を使用した旨の強調表示が行われている。この際、消費者の誤認を防ぐ観点から、その使用割合が100%の場合を除き、当該原材料の使用割合を併記することが義務付けられている(加工食品品質表示基準第5条)。
なお、原料原産地表示制度が本格的に導入されたことに伴い、特定の原産地のものを強調する場合、強調する産地だけでなく、全ての産地を使用した割合の多い順に表示する場合は、原産地ごとの使用割合は省略可能となることから、今後、本規定を活用した原料の原産地に関する情報提供が促進されることが期待される。
|
| (4) | 弁当の原材料表示の見直し |
図4 弁当の原材料表示の見直し例
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (5) | 原材料表示の運用改善 |
|
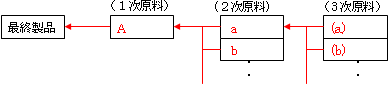
|
|