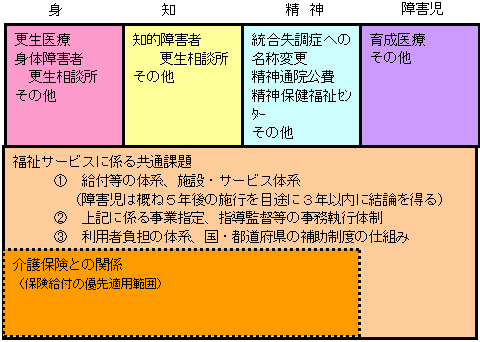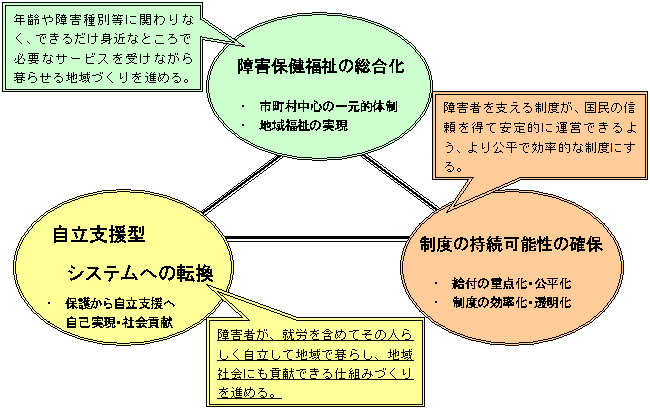
|
本案は、厚生労働省としての試案であり、今後、関係審議会の意見を聴き、関係機関等との調整を行い、(1)地域の基盤や実施体制の整備に一定の準備期間を要する項目と、(2)制度の持続可能性の確保の観点から、できる限り速やかに実施すべき項目等に区分して、実施スケジュール等を整理するものである。 なお、精神障害固有の問題については、本案に記載するものの他、「精神保健医療福祉の改革ビジョン(厚生労働省精神保健福祉対策本部 平成16年9月)」に基づき、改革を進める。 また、介護保険制度との関係については、基本的考え方、論点について、別途整理して提示する予定である。 |
I 改革の基本的視点
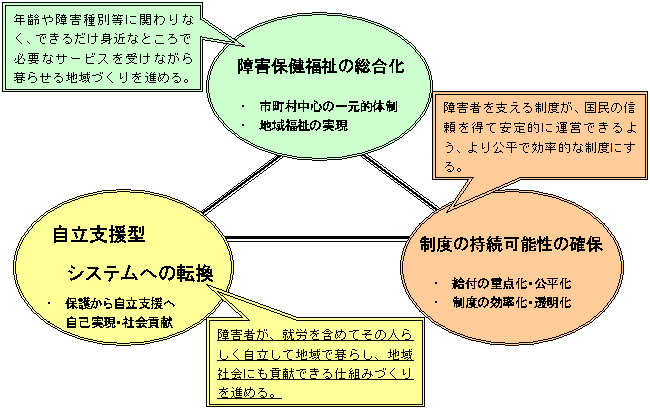
II 改革の基本的方向
1 現行の制度的課題を解決する。
|
2 新たな障害保健福祉施策体系を構築する。
|
| 介護保険との関係整理(別途整理) |
| 1 現行の制度的課題の解決を図る。 |
(1)市町村を中心とするサービス提供体制の確立
【基本的考え方】
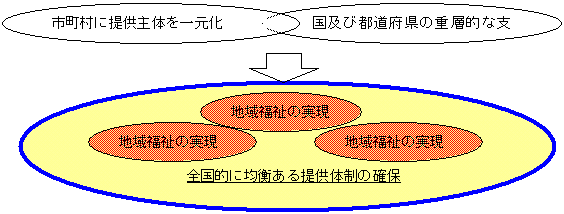
<福祉サービス実施主体の現状>
<在宅サービスを実際に提供した市町村数(全市町村に占める割合)>
※身体、知的、障害児は平成16年1月、精神は平成16年3月のデータ |
| 1) | 福祉サービスの提供に関する事務の市町村移譲と国・都道府県による支援体制の確立 |
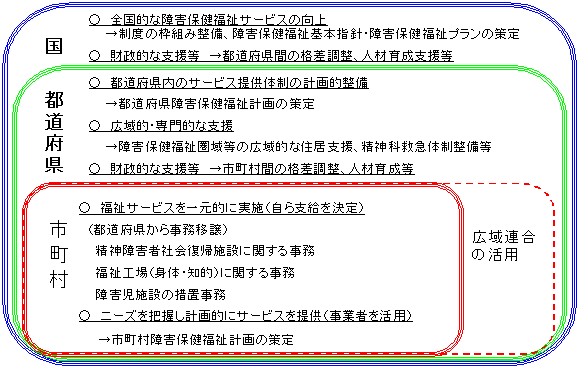
| ※ | 障害児については、被虐待等の要保護性を有する者に係る実施主体の問題があり、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を得る。 |
| 2) | 障害保健福祉サービスの計画的な整備手法の導入 |
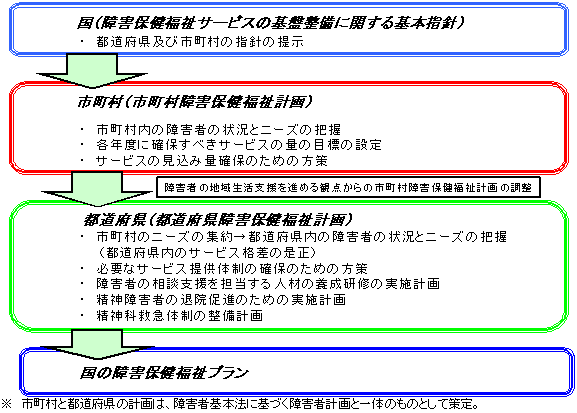
このほか、次のような取り組みを進める。
|
【基本的考え方】
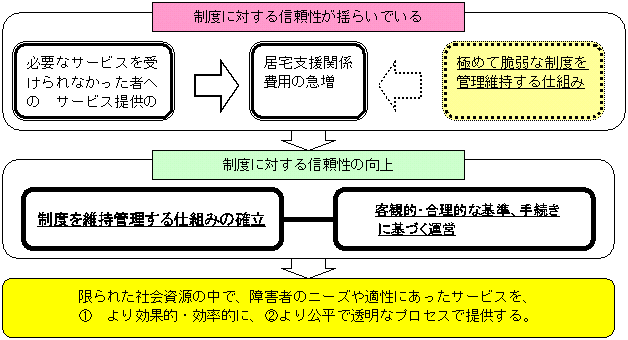
<ホームヘルプサービスの増額の内訳>
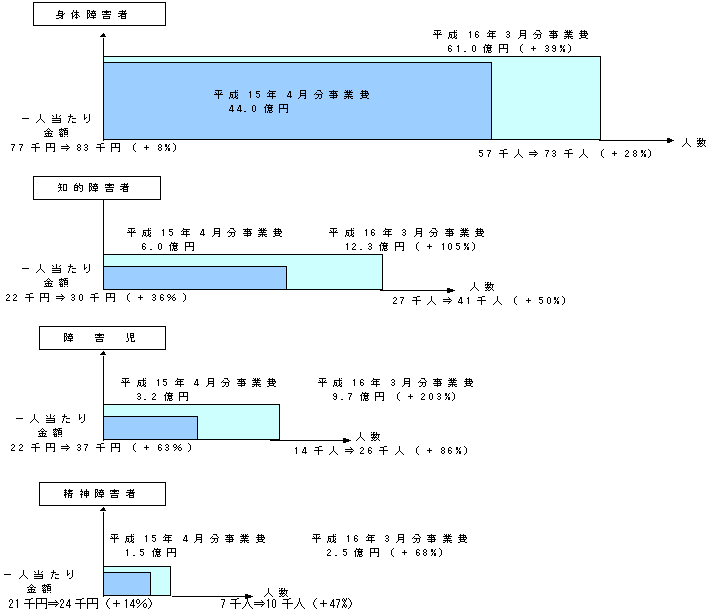
| 1) | 市町村を基礎とした重層的な障害者相談支援体制の確立とケアマネジメント制度の導入 |
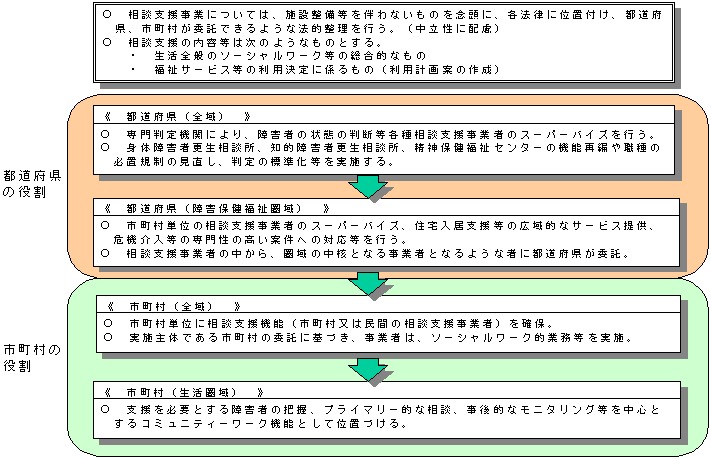
| 2) | 利用決定プロセスの透明化 |
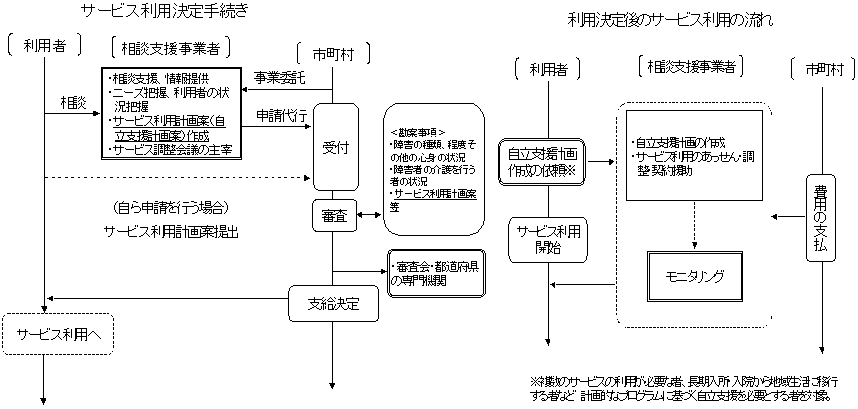
このほか、次のような取り組みを進める。
|
【基本的考え方】
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
<障害保健福祉関係の財政構造>
障害保健福祉部平成16年度予算総額6,942億円(義務的経費5,873億円、裁量的経費1,060億円、公共投資関係9億円)
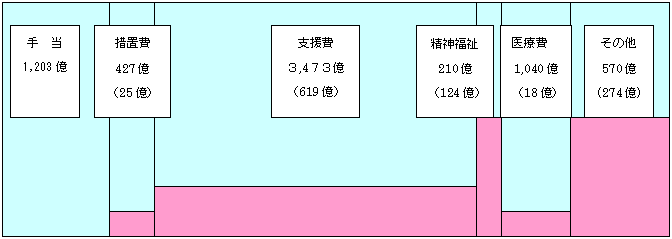
| ※1 | 上図には公共投資関係は含まれていない。また、( )内の数値は裁量的経費の額を示している。 |
| ※2 | 施設訓練等支援費に係る医療費は、医療費ではなく支援費で整理している。 |
| 1) | 福祉サービスに係る応益的な負担の導入
|
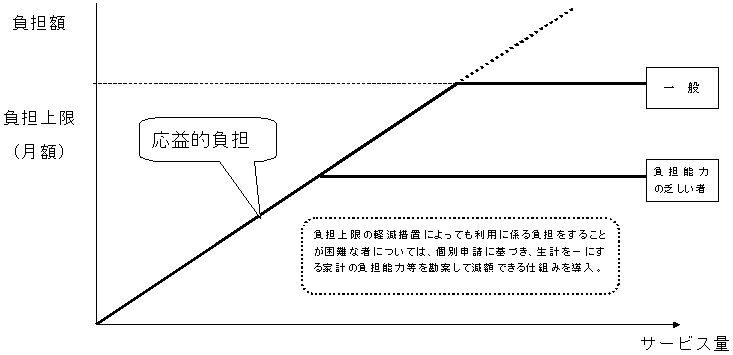 |
| ※負担上限の該当の有無は、各サービスに係る負担額の合計で計算する。 |
| 2) | 地域生活と均衡のとれた入所施設の負担の見直し
|
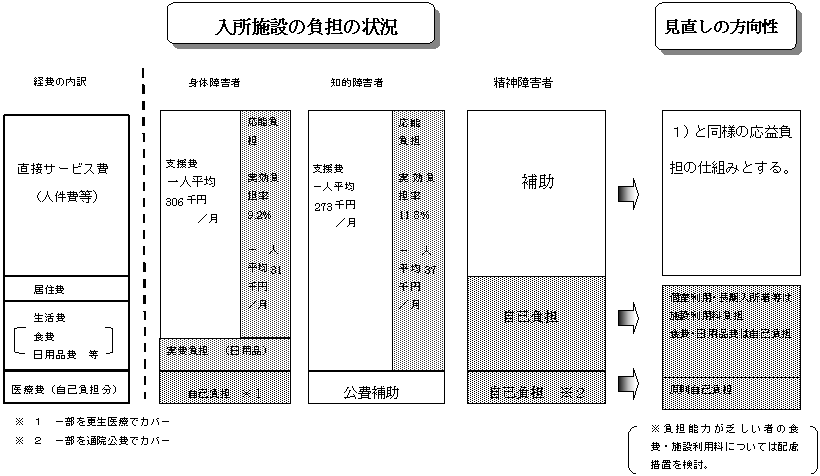
| 3) | 障害に係る公費負担医療の対象の見直し
|
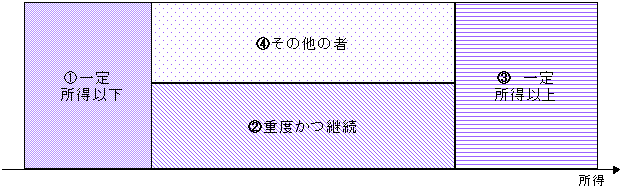
|
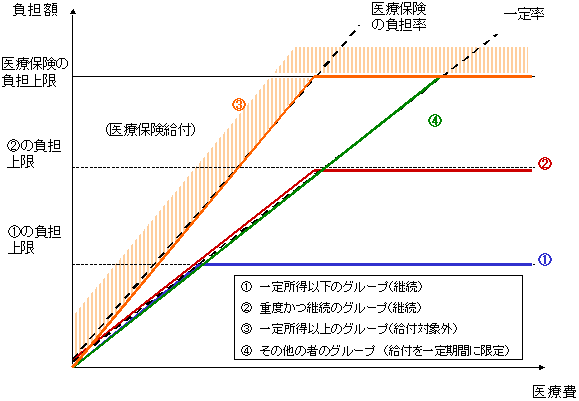
| 4) | 国・都道府県の補助制度の見直し
|
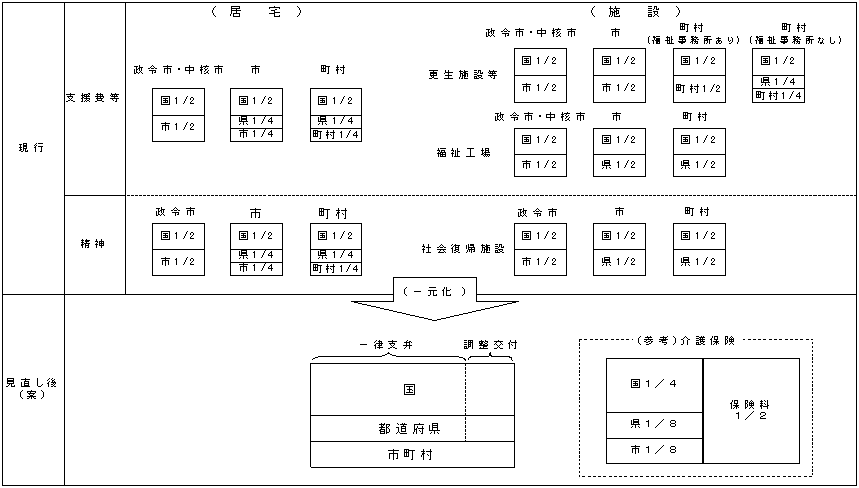
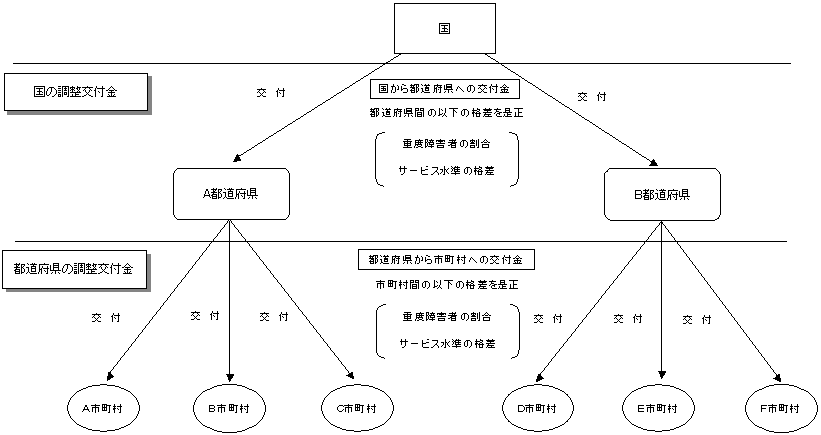
| 2 新たな障害保健福祉施策体系の構築 |
(1)障害保健福祉サービス体系の再編
【政策目標】
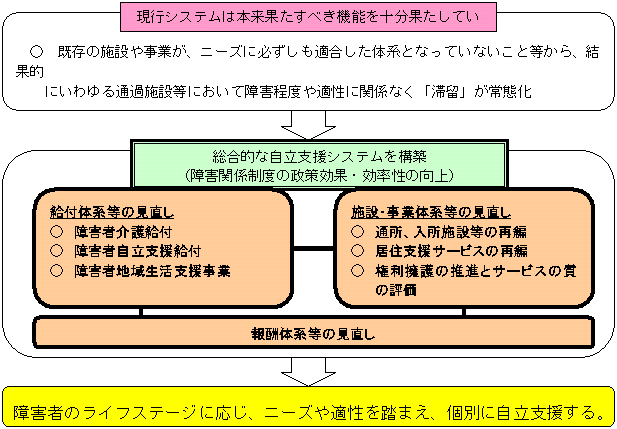
<就労支援で成功している授産施設の退所状況>
| 退所者のうち就職を理由に退所する割合 | ||
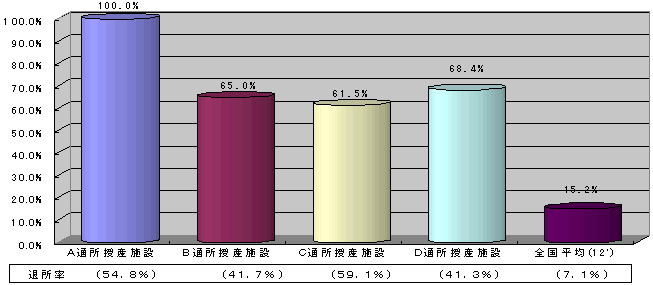 | ||
|
| 1) | 総合的な自立支援システムの構築 |
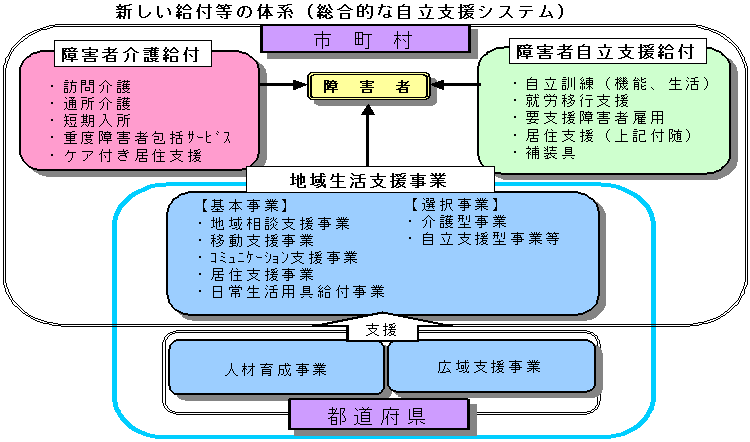
| 2) | 障害者の施設、事業体系や設置者、事業者要件の見直し
|
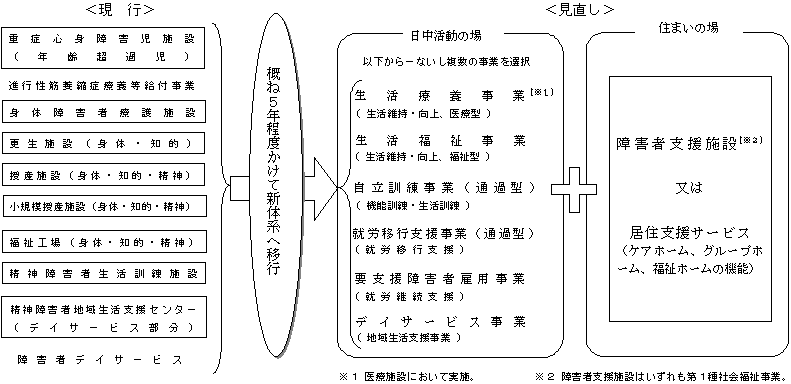
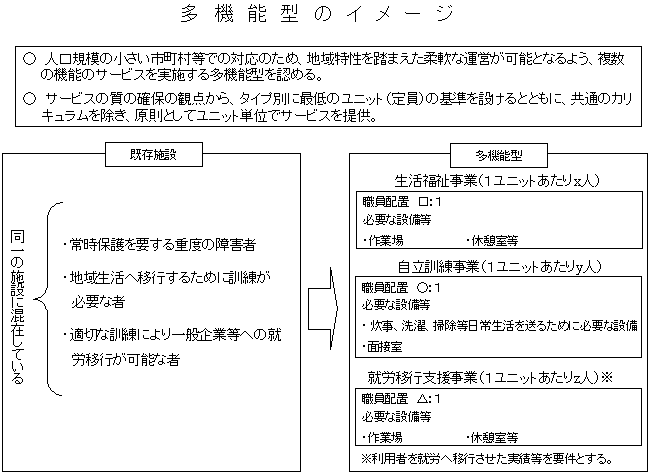
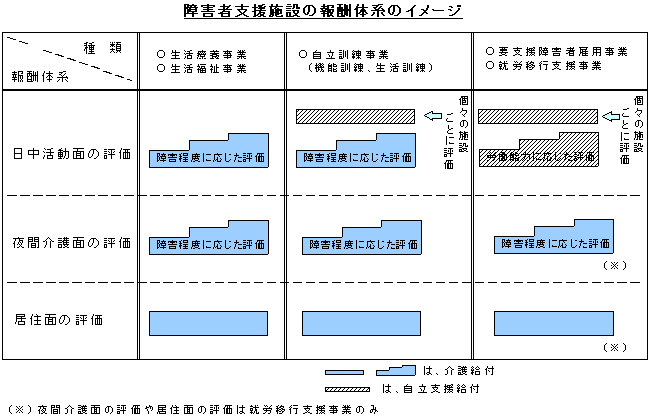
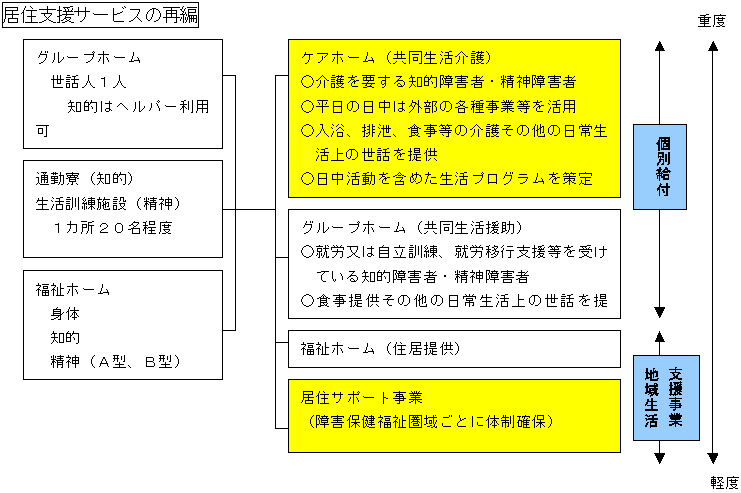
|
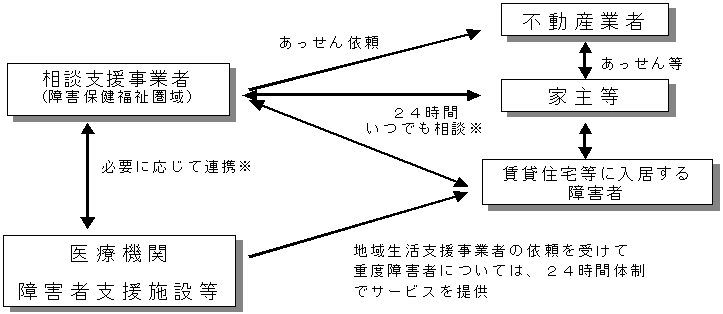
このほか、次のような取り組みを進める。
|
| 1) | 雇用施策と連携のとれたプログラムに基づく就労支援の実施
|
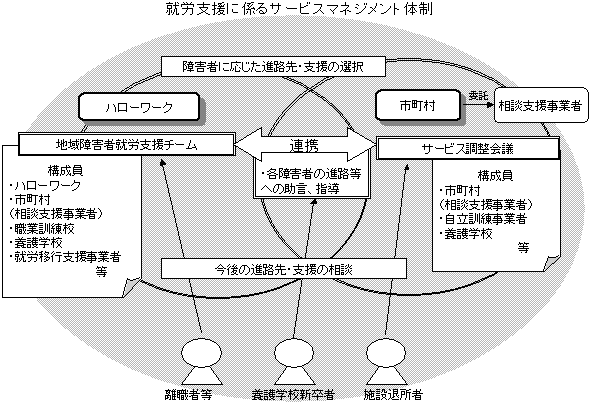
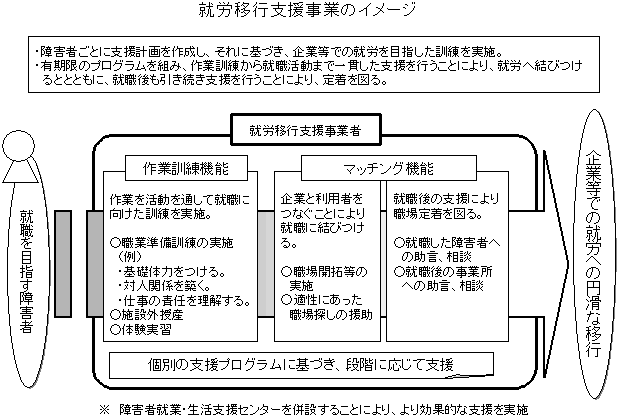
| 2) | 極めて重度の障害者に対するサービスの確保 |
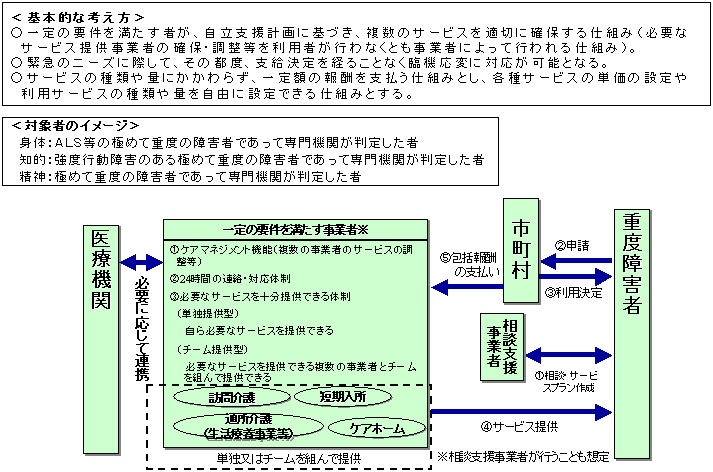
| 3) | 障害児施設、事業のサービス体系の見直し(概ね5年後施行を目途に3年以内に結論)
|
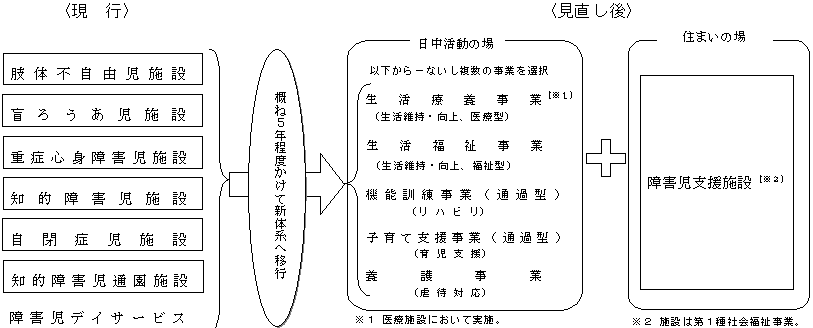
【政策目標】
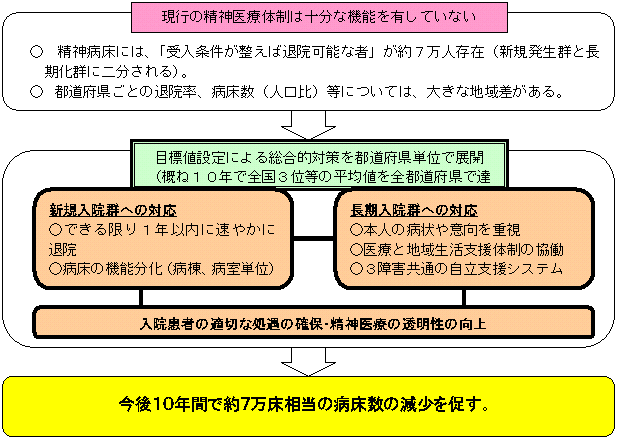
<受入条件が整えば退院可能な者の推移>
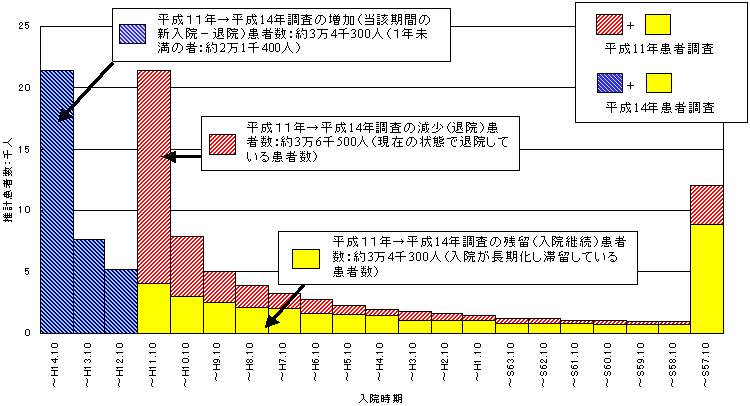 【資料出所】 患者調査(平成11年・平成14年) |
|
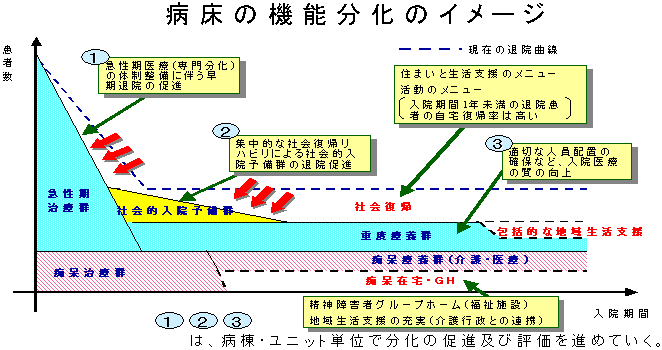
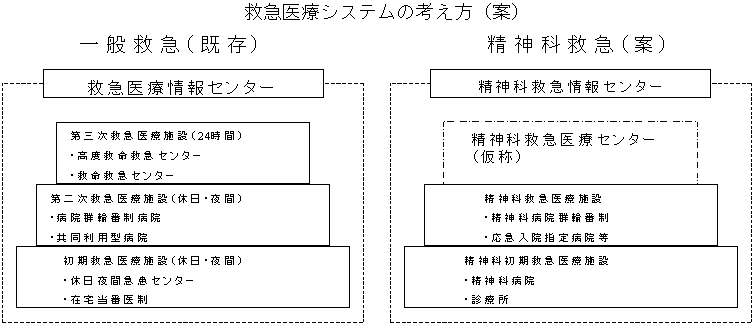
このほか、次のような取り組みを進める。
|
III 法改正に向けて
【基本的な考え方】
| ○ | 各障害者共通の自立支援のための給付・サービス体系や利用者負担体系、財政システムの整備や、各障害別の課題(統合失調症への名称変更など)等に対応するために、次期通常国会に法案を提出すべく関係機関等と調整を進める。なお、被虐待障害児の措置権の問題等もある障害児関係の一部事項については、概ね5年後の施行を目途に、社会保障審議会障害者部会等で引き続き検討し概ね3年以内に結論を得る。 |
| ○ | この場合、福祉サービスに係る共通部分については、障害者施策を総合的に進める視点のほか、制度運用の整合性の確保、制度に関わる者の事務負担の軽減、財政の有効活用等の観点から、現行の各障害別の法律を個別に改正するのではなく新たな共通の法的枠組みを導入する可能性について検討する。 |
| ○ | 各障害に共通の給付・サービス体系等に係る介護保険制度との関係については、年内に結論を得て、必要な内容を法改正に反映する。 |