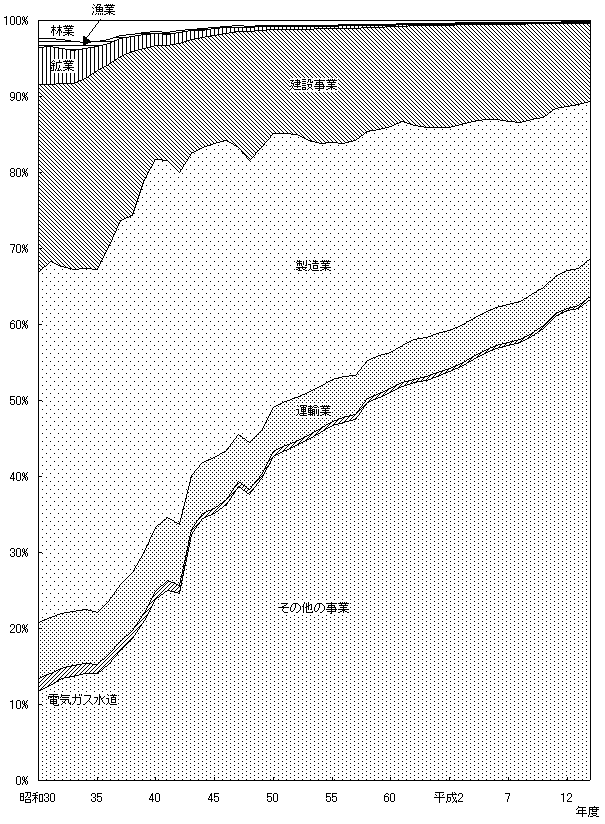 |
| 資料出所:労働者災害補償保険事業年報 |
| 参考資料1 | 労災保険料率の設定に関する検討会開催要綱 |
| 参考資料2 | 「労災保険料率の設定に関する検討会開催要綱」参集者名簿 |
| 参考資料3 | 規制改革・民間開放推進3か年計画について(抜粋)(PDF:51KB) |
| 参考資料4 | 労災保険率表 |
| 参考資料5 | 労災保険率の設定に関する基本的考え方関連資料 |
| 参考資料5-1 | 労災保険率設定の基本的考え方 |
| 参考資料5-2 | 労災保険率の算定における業種間調整について |
| 参考資料5-3 | 平成15年度労災保険率の改定について |
| 参考資料5-4 | 労災保険制度の業種区分について(考え方) |
| 参考資料5-5 | 労災保険のメリット制について(概要) |
| 1 | 目的 労災保険料率については、現在、業種毎の安全衛生対策とあいまって同種災害の防止努力を促進しつつ、業種を異にする事業主間の負担に係る過大な不公平感の是正を目的として、51の業種区分毎に料率を設定しているところである。 こうした中で、平成15年12月、総合規制改革会議において、業種別リスクに応じた適正な保険料率の設定について、平成16年度中に結論を得べきこととされたところである。 このため、産業構造や就業実態の変化等を踏まえ、料率設定の具体的な方法等について、より専門的な見地から検討を行うこととする。 | ||||||||||||
| 2 | 参集者の構成等
| ||||||||||||
| 3 | 検討内容等
| ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| (1) | 検討会は公開とする。 | ||||||||||||
| (2) | 検討会の事務は、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課労災保険財政数理室が行う。 | ||||||||||||
| (3) | この要綱は、平成16年4月15日から適用する。 |
| (五十音順) | ||||||||||||||||
|
| (平成15年4月1日改定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 参考資料5 |
| 労災保険率 | 業務災害分 | 短期給付分
|
|||
| 長期給付分
|
|||||
| 非業務災害分(通勤災害及び二次健康診断等給付分) | |||||
| 労働福祉事業及び事務の執行に要する費用分 | |||||
| 1 | 短期給付 短期給付は、原則として、災害発生の業種に賦課しているが、災害発生から3年を経ている短期給付(長期療養者分)については、当該事業主の業種の賦課とはせず、全業種一律賦課として算定している。 これは、
| ||||||
| 2 | 長期給付 年金等給付は、支給開始時にその将来給付に要するすべての費用を災害発生の業種に賦課しているが、被災後7年を超えて支給開始したものについては、当該事業主の業種の賦課とはせず、全業種一律賦課として算定している。 これは、
したがって、災害発生から7年以内に支給開始した長期給付は、当該事業主の業種に将来給付費用のすべてを賦課することとし、災害発生日から7年を超えて支給が開始される年金等給付は、全業種一律賦課として算定しているものである。 |
| 1 | 算定料率が前回改定時の算定料率より低下した業種については、原則として、算定料率の低下幅程度の引下げとした。 ただし、算定料率が設定料率を上回っている業種については、両者の差を縮小させるため、算定料率の低下幅の1/2程度の引下げとした。 |
| 2 | 事業主の保険料負担の大きな変動を避けるため、料率の改定幅は平成13年度改定と同様に、±4/1,000を上限とした。 |
| 3 | 既に最低料率となっている業種の算定料率は前回改定時の算定料率よりほぼ0.5/1,000低下したため、設定料率の最低料率は、前回から0.5/1,000引き下げた5/1,000となった。 |
| 1 | 事業の種類別とする理由 労働者災害補償保険制度(以下「労災保険」という。)は、業種別に料率を設定する制度を採用している。 これは、業種ごとに災害率、災害の種類及び作業態様が異なることを踏まえ、事業主に対する保険料負担の公平性及び災害防止意欲促進の観点から、業種別に料率を設定することが適切であるとの判断に基づくものである。 したがって、労災保険率は、事業の種類ごとに、過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業及び事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めている。 |
| 2 | 事業の種類区分の考え方 日本標準産業分類は、主として産業活動を中心に分類されているが、労災保険の事業細目表は、災害率、災害の種類、作業実態、業界組織、保険技術等を主眼として定められているものである。これは、労災保険制度が業務災害に対する事業主の補償責任の法理を基盤としているからである。 労災保険の事業細目表の分類にあたっては、事業主の保険料負担の公平性あるいは労働安全衛生対策の面で災害率、災害の種類、作業態様による分類を、また保険集団としての規模及び分類等の保険技術上の問題を、さらに費用負担の連帯性、災害防止活動の浸透の面で業界組織による分類を配慮して定められているものであって、事業の規模の大小は考慮していない。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料出所:労働者災害補償保険事業年報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
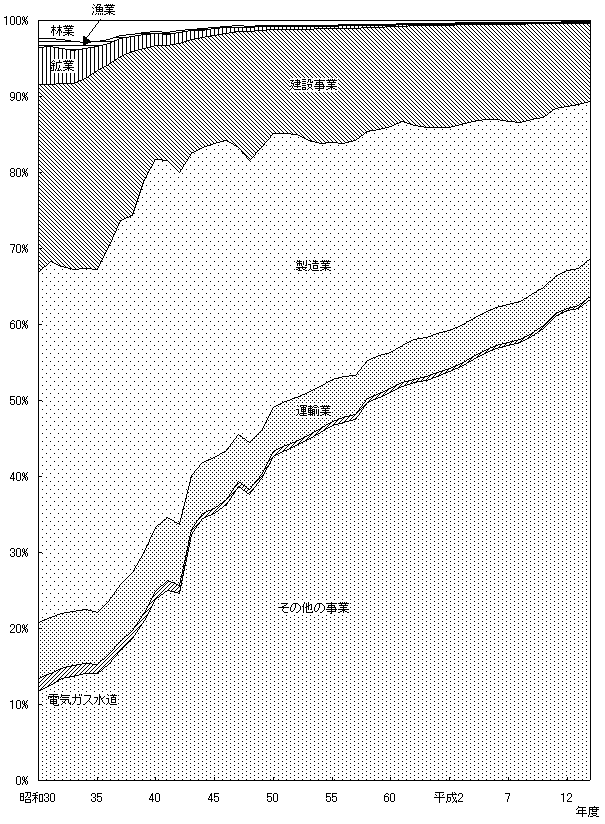 |
| 資料出所:労働者災害補償保険事業年報 |
| 1 | 趣旨 事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、当該事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げ下げするものである。 |
| 2 | 継続事業(一括有期事業を含む)の場合
〔継続事業のメリット制概略図〕
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 有期事業の場合
〔有期事業のメリット制概略図〕
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 特例メリット制 特例メリット制は、以下の(1)、(2)、(3)の要件をすべて満たす事業について、(3)の安全衛生措置を行った年度の翌年度の4月1日から9月30日までの間にメリット制の特例の適用の申告があるとき、安全衛生措置を講じた年度の次の次の年度から3年度の間について、メリット制が適用になる年度に限り、適用するものである。
特例メリット制を適用する場合、継続事業の場合と同様に計算したメリット収支率が85%を超え又は75%以下となる場合は、事業の種類に応じて定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を45%の範囲内で上げ下げし、これに非業務災害率を加えた率を、その事業についての基準となる3月31日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とする。 〔特例メリット制概略図〕
|
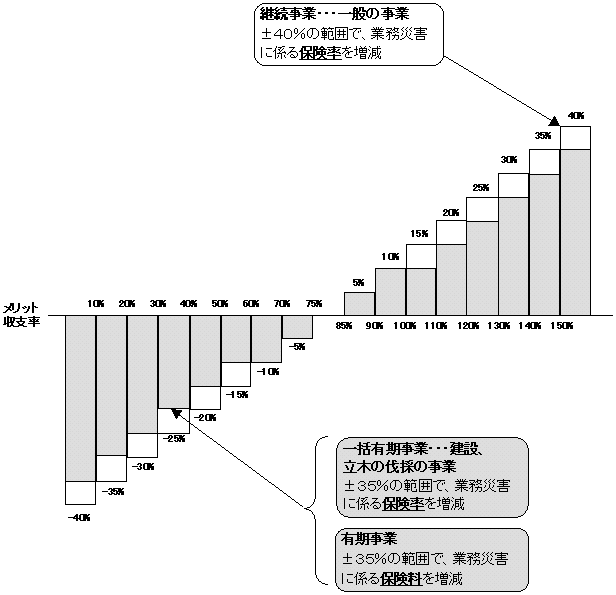
| 年度 | メリット増減幅 | 備考 | ||||
| 継続事業 | 建設事業 (有期) |
立木の伐採 (有期) |
建設事業 (一括有期) |
立木の伐採 (一括有期) |
||
| 昭和22年度 |
労災保険法 の制定 |
|||||
| 昭和26年度 |
±30% | | | | | | | | | | | ↓ |
メリット制 適用開始 |
||||
| 昭和30年度 |
±20% | | | | | | ↓ |
|||||
| 昭和40年度 |
±20% | | ↓ |
±20% | | ↓ |
±20% | | ↓ |
一括有期 事業の創設 |
||
| 昭和51年度 |
±35% | | ↓ |
±25% | | ↓ |
±25% | | ↓ |
±25% | | ↓ |
±25% | | ↓ |
|
| 昭和55年度 |
±40% | | | | | | | | | | | ↓ |
±30% | | ↓ |
±30% | | ↓ |
±30% | | | | | | ↓ |
±30% | | | | | | ↓ |
|
| 平成13年度 |
±35% | | | | | | ↓ |
±35% | | | | | | ↓ |
||||
| 平成14年度 |
±35% | | ↓ |
±35% | | ↓ |
||||