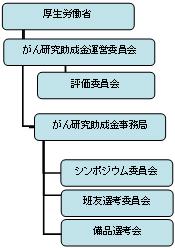| A. |
研究事業概要
(1)関連する政策体系の施策目標
| 基本目標 |
がん政策医療の推進 |
| 施策目標 |
がんに関する高度専門的医療、新たな社会ニーズに対応するモデル的医療の実施 |
| 国立病院機構の政策医療ネットワークを活かし多施設共同による新しい診断・治療法の開発普及 |
| 医療内容の高度化・多様化に対応した臨床研修の向上、医療専門職の養成 |
| 研究成果や最新の医療、標準的医療等に関する情報発信 |
(2)事務事業の概要(継続)
がん研究助成金は、昭和38年に創設され「がん対策の企画及び行政を推進し、並びにがん医療の向上を図る」ことを目的として必要な研究に対して交付されている。
当該助成金は、がん政策医療ネットワークを構成する全国の国立病院機構施設、がん専門医療施設等の多施設共同による、がんの新しい予防、診断・治療法の開発普及、医薬品の臨床試験など臨床に直結した研究を主体としている。
がん研究助成金においては、特にがん政策医療の推進やがん医療の全国的な均てん化を推進していく上での基盤づくりのための研究、がんの臨床や研究において将来性の期待される萌芽的な研究に重点を置いており、がん医療・研究の先端を切り拓くことを主眼とする厚生労働科学研究費補助金「がん克服戦略研究事業」とは研究の目的及び内容を異にしている。
また、研究を効果的に推進するため、関連学会や社会的要請に基づき計画的かつ集中的に実施する研究を「指定研究」、がんの診断・治療・予防法を確立するための臨床研究及びそれに関連する基礎研究並びに行政的研究を含めて総合的に実施するものを「総合研究」、関連学会等で重要性が認識されている研究を「計画研究」として位置づけている。
当該助成金にかかる事務は国立がんセンター総長に委任されており、研究課題及び研究者の選定、研究費の配分、研究成果の評価について審議するため行政関係者、学識経験者等24名で構成される運営委員会を設置している。
平成15年度の研究課題数は95課題(指定課題10,総合研究8、計画研究75、機械開発研究2)研究者総数は823名となっている。
主な研究課題として、(1)各種がんの予防、診断・治療法の開発、(2)がん臨床試験体制の確立、(3)がん情報ネットワークの構築、(4)がん登録による発生頻度及び死亡率の把握等があげられる。 |
(3)予算額(単位:百万円)
| H13 |
H14 |
H15 |
H16 |
H17 |
| 1,850 |
1,850 |
1,850 |
1,850 |
1,850 |
(4)趣旨
| ● |
施策の必要性と国が関与する理由
がんは昭和56年以来わが国の死因の第一位を占めており、がん対策は厚生労働省における最も重要な施策のひとつとして位置づけられている。がん研究助成金による研究は厚生労働省医政局国立病院課のがん政策医療推進の一環として行われているものであり、厚生労働省として実施する行政的意義は非常に大きい。とくにがん研究助成金は「がん対策に関する企画及び行政を推進し、並びにがん医療の向上を図る」ことを目的として、国立がんセンターを中心とする多施設共同により、わが国のがん対策を推進していく上での基盤づくりのための研究、がん予防、診断・治療に係る臨床研究や疫学研究、萌芽的な研究などに重点を置いており、がん政策医療の目的に沿って実施されていることから、行政施策との関連性は非常に強い。また、がん研究助成金においては、がん政策医療ネットワークを構成する全国の国立病院機構をはじめ、がん専門医療施設、大学等の積極的な参加のもとに多施設共同による研究が実施されており、参加施設のレベルアップを図るとともに厚生労働省のがん政策医療やがん医療の均てん化を全国的に推進する上でも重要な役割を果たしている。 |
| ● |
他省との連携
文部科学省管轄の大学等が幅広く参加している。この結果、大学研究成果との融合・発展がなされ、多角的な研究展開が図られ、がん領域の研究全体の向上を目指している。 |
| ● |
期待される成果
当該助成金の特筆すべき成果のひとつとして、世界的に通用する質の高い臨床試験体制の確立が上げられる。これにより全国のがん専門医療施設約190カ所の多施設共同によるがん臨床試験の実施体制(JCOG)が構築されるとともに、がん臨床試験の品質管理及び品質保証(データマネジデント)の方法論が確立され、その第一歩として肺がんに対する化学療法と放射線療法の同時併用による標準的治療法が確立された。また、1990年からは14万人規模の大規模コホート研究が開始され、がん死亡の危険度を定量的に評価することが可能となった。この他、頭頚部がんに対する陽子線この他、機能温存手術の開発普及、発がん要因の探索などがんの診断・治療および予防に関して、国際的にも注目される成果を上げている。 |
| ● |
前年度の総合科学技術会議および科学技術部会での評価に対する取り組み
第3次対がん10カ年総合戦略の指針を基に課題採択を行うと共に、厚生労働科学研究費の研究で対応されていない分野を積極的に公募している。また、指定研究等の多施設共同研究により見いだされた新たな研究の方向性の内、研究内容を深める課題設定も行い、有機的な研究課題設定ができるシステムとなっている。
がん研究助成金の運営にあたっては運営委員会が設置されており、研究課題及び研究者の選定、研究費の配分、研究成果の評価等について、運営委員会における審議のもとに適正な運用が図られている。事前・中間・事後と評価をおこない、運営委員による指摘を研究者に逐一連絡し、対応を適時的に行ってきた。特に中間発表会による課題評価は厳密におこなわれ、運営委員の評価が研究継続の可否、及び研究費の配分金額にも反映され研究者は本助成金の目指すアウトラインからはずれることなく研究を深めていくことができる。この評価については関連学会や社会的要請に基づき総合的に判断される。長期にわたり計画的及び集中的に実施する必要のある研究を指定研究と位置づけ実施している。この他各分野の専門的知識を入れながら評価基準を設けて研究期間を原則2年間ないし3年間を単位とし、研究の成果及び評価結果に応じて研究課題の見直しも行い、有効性と効率性にも配慮した適正運用が図られている。
また、この評価の結果に基づく研究の成果については「厚生労働省がん研究助成金報告集」やインターネットホームページにより公表し成果の普及と外部からの評価にも耐えうるものとなっている。 |
|
(5)事業の概略図
がん研究助成金事業概略図
| がん研究助成金は運営委員会により、運営方針等事業展開が決定される。課題評価のための評価委員会は運営委員会委員により構成されている。運営委員会の決定事項は事務局により処理され、シンポジウムの運営、班友選考、備品選考に当たっての委員会等が事務局により開催され、常に公正かつ多角的な判断がなされる体制となっている。 |
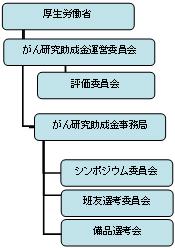 |
|