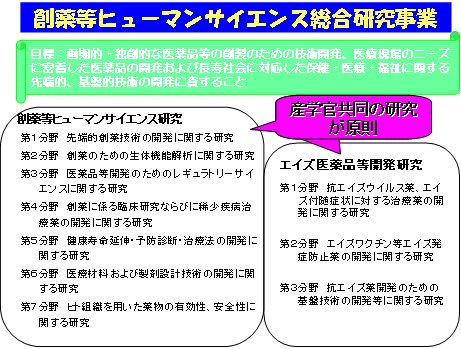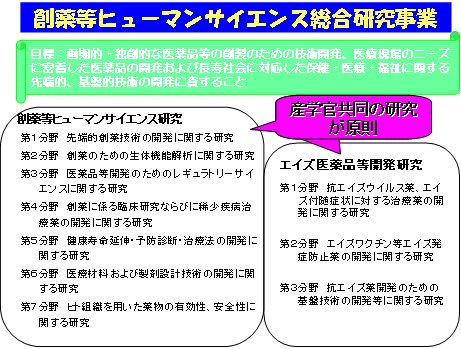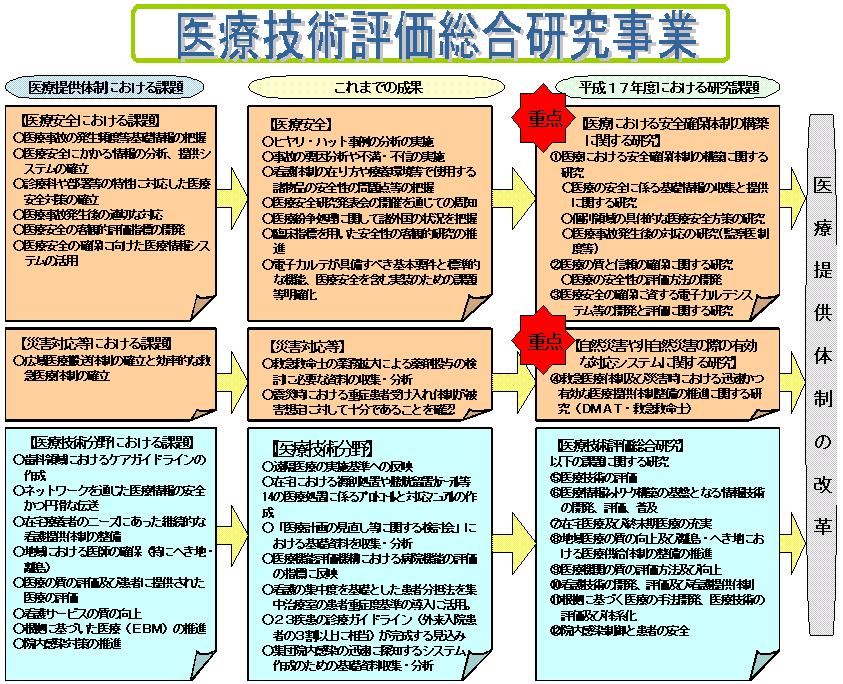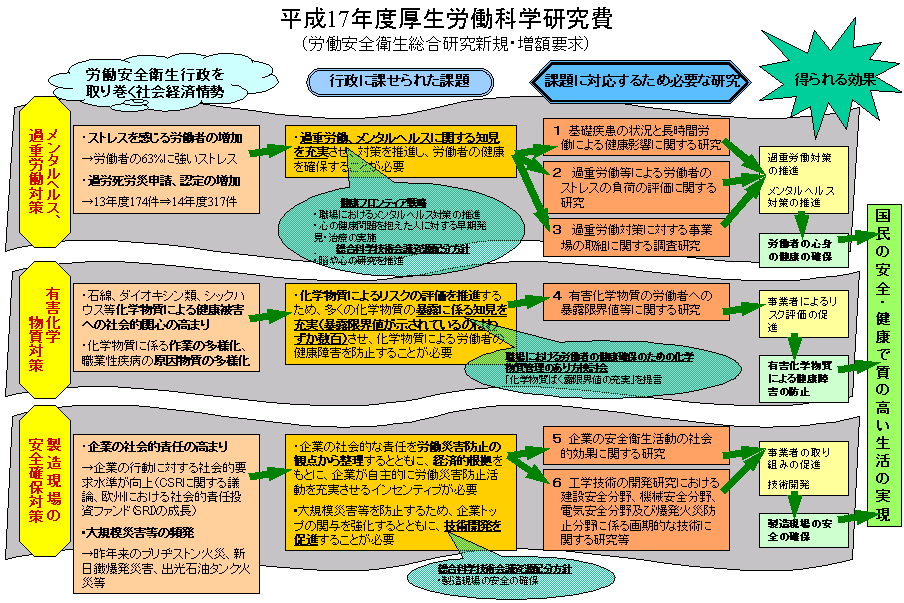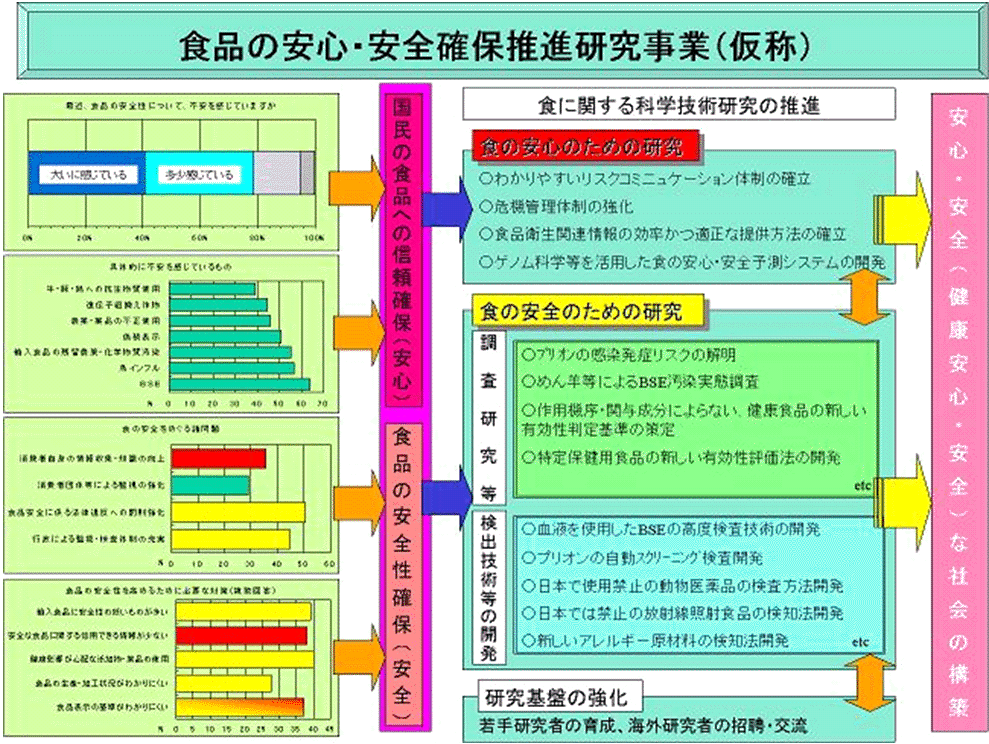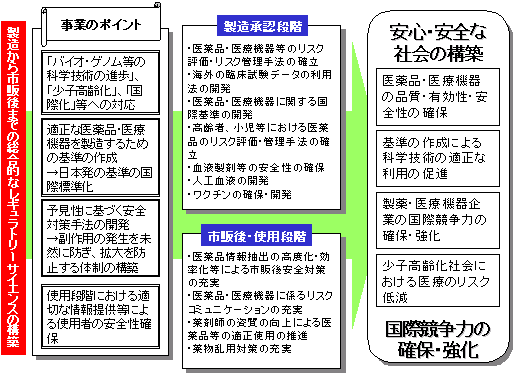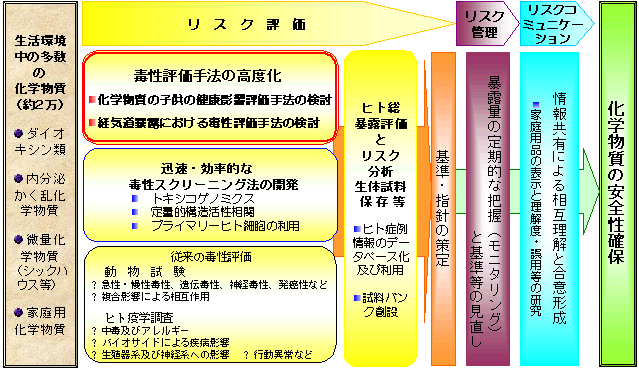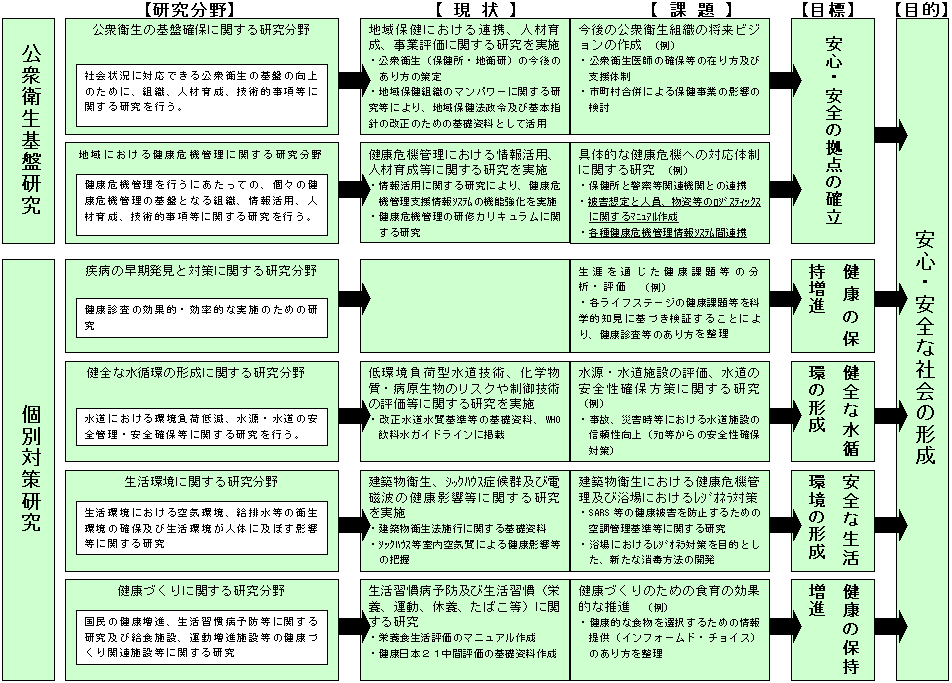| 【横断的基盤研究事業】 |
| (改)1. |
食品安心・安全推進研究分野
消費者等の食品の安全性に対する理解促進のためのリスクコミュニケーション手法の構築や、いわゆる食品テロ対策に関する研究を行う。 |
| (新)2. |
食品リスク分析調査研究分野
食品に起因する現実的な健康被害は食中毒で、平成14年度では1,850件、27,626名の食中毒が発生、18名の死者(微生物に起因するもの11名、植物性自然毒1名、動物性自然毒6名)が発生している。カンピロバクター、リステリア等の食中毒菌は市販食品を広く汚染しており、定量的リスクアセスメントによる微生物リスクの科学検証が必要なことから、全国の食中毒検体や食品検査における菌分離・PFGEによる遺伝子情報等を一元的に収集・データベース化し、病原性菌の分離状況・対象食品・フードチェーン中のポイント等の因子をシミュレーション解析し、定量的微生物リスク予測に基づくリスクの存在を前提とした衛生管理手法の開発を行う。
|
| 【個別研究分野】 |
| 1. |
バイオテクノロジー応用食品対策研究分野
FAO/WHO専門家会議やコーデックス委員会等での議論を踏まえ、ヒト血清スクリーニング試験系やモデル動物を用いた試験実験系などの遺伝子組換え食品のアレルギー性評価手法や試験法等を確立するとともにし、抗生物質耐性マーカー遺伝子の移行性に関する評価を行う。
また、後代での遺伝子の変化が遺伝子組換えに起因する変化であるか否かは明らかではないため、挿入遺伝子に係る後代種での変化が食品の安全性に影響を及ぼさないか等の調査・分析を行うことやその追跡調査(ポストマーケットモニタリング)に必要な手法・検査方法を検討・開発する。
更に遺伝子組換え微生物や遺伝子組換え魚等の新たな食品の開発とその実用化が進んでいることから、適切かつ有用な検知法の開発を進めていく。
消費者の漠然とした遺伝子組換え食品への不安に対しては、安全性等に関する情報をいかに正確に伝え、理解を得るかが大きな課題となってきているところである。このため、国民に遺伝子組換え食品の安全性に関する理解を深め、これら食品等への安心感を持ってもらうためのリスクコミュニケーションに関する調査及び分析を行う。
|
| (新)2. |
健康食品等の安全性・有効性評価研究分野
特定保健用食品の有効性審査については、これまで西洋医薬品的審査(1つの関与成分に注目し、作用機序、有効性を審査)に基づき行っているところであるが、伝統的健康食品やハーブ類など、実際に効果はあるものの、作用機序、関与成分が特定できないものは審査できないのが現状である。「『健康食品』に係る今後の制度のあり方について(提言)」においても、「食品そのものまたは複数の成分が関係していると考えられ、関与成分の特定が困難な食品等についても研究するべきである」とされており、これらを踏まえ、特定保健用食品の次世代の審査基準を策定するための研究を行う。
|
| (改)3. |
牛海綿状脳症対策研究分野
牛海綿状脳症(BSE)については、これまで異常プリオンタンパクの検出法の開発等により我が国のBSE検査技術レベルの向上が図られ、世界でもトップクラスの検査体制が整備された。しかしながら、食品を介したBSEの人への健康影響レベルついては不明であることから、食品安全対策を検討する上で困難を来している。これらの状況を踏まえ、異常タンパクプリオンの高感度検査法の開発を行うとともに、BSE感染牛由来材料を用いた感染実験による感染・発症機構の検討を行うことにより、食品を介するBSEリスクの解明について研究を行う。
|
| 4. |
食品中の添加物に関する研究分野
添加物の安全性に関しては消費者の関心も高く、新たな科学的知見に基づいて安全性の見直しや品質の確保を進めていくことが強く求められている。そこで、化学的合成品を含めた添加物の規格・試験法に関する国内外の動向を踏まえた検討や、天然物に由来する既存の添加物についての毒性メカニズムの解明等を研究により行うことにより、リスク評価や衛生対策の検討に必要な基礎的知見を収集する。
なお、国内外の既知の情報収集等による添加物の指定や摂取実態の調査等は、事業費により行う。
|
| 5. |
食品中の汚染物質対策研究分野
近年、重金属などの汚染物質が食品中に含まれていることが報告されており、その安全確保対策が強く求められている。食品への汚染が十分解明されていない汚染物質やその健康影響が不明なものについて、科学的データを得るための調査研究を早急に実施することが必要であり、取り組みを強化する。
健康影響メカニズムの解明など衛生対策の必要性の検討などに必要な基礎的知見の収集などを研究により行い、基準の策定に必要な汚染実態の調査などは、事業費により行う。
|
| 6. |
食品中の微生物対策研究分野
リスク管理とは、リスク評価の結果、リスクを科学的に洗い出し、そのリスクを軽減、回避、未然に防止するための施策決定をとることである。具体的には、どのようなリスクをどのように管理するかをデータに基づき、選択する必要があるが、この分野の研究の目的は、リスク評価の結果からとるべき管理手法を選択し、さらに実行された施策の評価に必要な研究である。
健康被害の状況についてより正確に把握するためには、ハイリスクグループ(性別、年齢等)の有無、致死率、散発事例、地域差、通常の食中毒症状を呈さない食品由来疾病の調査等、従来の食中毒統計では把握することが困難な健康被害の状況について、正確に推測することが必要であり、そのための調査手法を開発する。
危害の特徴付けとは、摂取した菌数によりどのくらいの確率で発症するかを解析することである。病原体をヒトに投与することができないことから、食中毒事例の検食等を用いて摂食菌量及びその発症率等を推定することは有用な手法である。
リスク管理手法の選択に際し考慮すべき要因、すなわち、どこまでのリスク軽減を求めるべきか、各リスク軽減措置に要する費用、軽減措置の導入に伴い予想される新たなリスク、軽減措置による恩恵とそのもののリスク等、政策を決定するために必要な要因について量的に評価できるデータの収集及びその効率的手法の開発を行う。
実行されたリスク管理手法が、遵守されているかを確認(モニタリング)し、再評価するリスク管理における施策評価も行う。
|
| 7. |
食品中の化学物質対策研究分野
食品中に含まれる内分泌かく乱化学物質の試験法、毒性発現メカニズム、試料分析・モニタリング等に関する研究を行い、食品中に含まれる内分泌かく乱化学物質の健康影響の解明を強力に推進する。さらに、内分泌かく乱化学物質のリスク管理に関する研究を行い、もって内分泌かく乱化学物質が及ぼす毒性等が明らかになった場合の適切なリスク管理及び規制等の対策の実施に資する。
食品に含まれるダイオキシンに分類される各種類縁化合物の正確な毒性把握をはじめ、食品の汚染実態調査、人体の汚染状況の把握、母乳による乳幼児への影響に関する研究、職域における健康影響把握等を一層推進することにより、ダイオキシン類の健康影響を体系的に解明する。
| ・ |
ダイオキシン類や内分泌かく乱化学物質の消化管からの吸収調査 |
| ・ |
人体からの排泄促進及び排泄機序 |
| ・ |
食品や煙草煙、日用品の汚染実態 |
| ・ |
容器包装からの溶出実験 等 |
|
| (新)8. |
アレルギー表示に関する研究分野
食品のアレルギー表示については、平成14年4月から、食品中に含まれる5品目(卵、乳、小麦、そば、落花生)については、義務表示とし、その検知法については、同年11月に公定法を通知している。一方、アワビ、いか等の19品目については、通知により表示を奨励しているが、義務表示ではないため、その検知法については、公定法を定めていない。アレルギー表示制度については、施行後約2年が経過し、現在「食品の表示に関する共同会議」において、その対象品目についても検討を行っているが、「19品目についても、食品中にその原材料が含まれているのか、いないのかを検査によって科学的に証明できることが重要であり、これまで研究が行われて来なかったことから、新たな研究により、この19品目について食品中からの検知法の開発を行う。
|
| (新)9. |
輸入食品の安全性等に関する研究分野
放射線照射食品の検知法、我が国で使用実態がない動物用医薬品の検知法等輸入食品特有の問題について、最新の知見に基づく検査方法を開発し、輸入食品の安全確保の推進に資する。
また、近年の食品輸入の拡大をはじめとした食品安全分野における検査ニーズの多様化や増加などへの対応のため、指定制度から登録制度に移行したところである。今後、登録検査機関が行う検査件数は増加し、また、検査を行う食品も多岐にわたることが予想されることから、登録検査機関について、さらなる信頼性確保を図るため、信頼性確保の指標となる外部精度管理の実施方法及び評価方法について研究を行う。
|
| 【若手研究者の育成】 |
| 1. |
若手研究分野
食品安全に係る研究推進と若手研究者を育成する観点から、若手研究者が主体的に研究できる環境の整備が必要であり、そのため、若手研究者を対象とした公募枠を設定し、自ら主体的に研究計画を立て遂行する仕組みを設立し、若手研究者の育成を行うこととする。 |