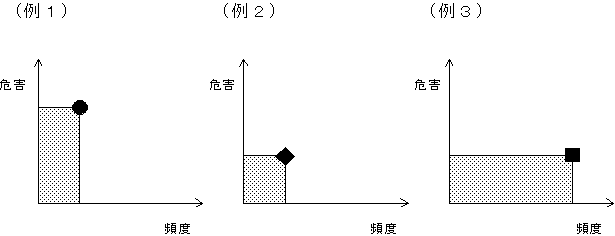| 第6回厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会 |
資料 6 |
| 平成16年9月27日 |
【「リスク」の捉え方】
| ○ | 「リスク」の捉え方として、頻度と危害の大きさの積で捉えるというのは非常に重要な考え方である。 |
| ○ | 全ての行為に「リスク」が伴うもの。安全性というのは「リスク」を許容範囲内に抑えるという考え方は重要。 |
| ○ | 年齢や薬剤等の因子はそれぞれ危害の大きさとか、危害を修飾する因子であると考える。 |
| ○ | 発生する事象の程度、「危害」と事象の発生確率、「頻度」でだいたいかけ算して、割合が大きいのはより危ない、リスクが大きいという考え方かもしれないが、発生確率が同じでも、人にとっては確実に「1」になる。 |
| ○ | 発生確率がある程度高いのが分かっている、特定のグループ(ハイリスクグループ)に対して未然に伝えるのが、そもそもの目的で医師・薬剤師がいる。 |
| ○ | 物性によるリスク分類は順番に並べることができるが、そこに個体差が加わると、0.1%の確率であってもその人にとっては100%。 |
| ○ | リスクの図にある面積が等しければ同じように扱えばいいかというとそうではなく、危害が高くて頻度が少ないものと、頻度が大きくて危害が少ないものとでは当然対処の仕方が違う。 |
| ○ | 人がリスクを回避することが可能かどうか、危害の対象が限定的なのか、広域なのか、さまざまなファクターによってリスクの取扱いは変わってくる。 |
【検討・作業の進め方】
| ○ | 危害の程度と頻度の形としてリスクマップをまずつくってみることが重要。専門の人である程度合意があるという前提条件で次に動く。 |
| ○ | 「リスク」という言葉や定義にとらわれることなく、リスクファクターをリストアップし、それぞれの薬でそれぞれの因子がどの程度のものかを整理してはどうか。 |
| ○ | リスクの程度をどう表現するかということが先にあって、薬のリスクの全体像を把握できたところで、それぞれの特性をもったリスクに対して、どういう情報提供がなされるべきかが次にくる。 |
| ○ | 販売形態の形は、専門委員会で出た議論をベースに置いた上で、今までどおりのやり方でやるべきかどうかが検討の対象になる。 |
| ○ | 定量化するのは難しい。わりと副作用が多いとか、間違いやすいとかをよくみて検討してほしい。 |
| ○ | 適正に使用しても確率的に起こり得るリスクがある一方で、誤使用からくるリスクもある。予期せぬ使用、誤使用系のリスクも薬のリスクはどのようにうまく組み込めるか。適正使用のリスクと不適性使用のリスクをトータルしてクラス分けをしていただきたい。 |
| ○ | 患者は、想像もできないような飲み方をする場合があることに対しても知恵を使ってほしい。 |
| ○ | 健康食品等と薬との関係がどうなのかということを意識して検討してほしい。 |
| ○ | 医学・薬学の人によって、危害の程度と頻度というマップはできるが、その次に飲む人の要素を入れてやるといろいろな議論が出てくるので、やり方について工夫が必要。 |
| ○ | 販売形態によって情報提供のされ方が違う。情報提供が誰によって行われるかもきちんと考慮して、情報提供について考えてほしい。 |
(参考)
| 第5回厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会 |
資料 8 |
| 平成16年9月6日 |
【1】医薬品の物性等に関連するリスク
| ○ | 医薬品の薬理作用。 |
| ○ | 医薬品の成分そのものが持つ副作用(既知、未知を問わず。)。 |
| ○ | 副作用の重篤化。 |
| ○ | 成分量、包装、剤型の違い。 |
| ○ | 誤使用を惹起しやすい剤型であるかどうか。 |
| ○ | 乱用の危険性があるかどうか。 |
| ○ | 医療用医薬品や食品との相互作用(いわゆる飲み合わせ、食べ合わせの問題)。 |
【2】消費者の体質等に関連するリスク
| ○ | 小児、妊婦、高齢等の消費者の状況。 |
| ○ | 消費者の病歴や副作用歴等の服用する者の違い。 |
【3】その他のリスク
| ○ | 医薬品の取り扱いやすさ。 |
| ○ | 消費者に医薬品の副作用の危険性に関する情報が十分に提供されない状態。 |
| ○ | 副作用情報が収集されないこと。 |
| ○ | 情報提供だけでなく、消費者に医薬品を適切に使用させるための指導の必要性。 |
| ○ | 消費者の知識不足による誤飲。 |
| ○ | 医療用医薬品の一般用医薬品への転用(スイッチ)等に伴う使用環境の変化によって発生する予想できない副作用。 |
(参考)
| 国際標準化機構 (ISO) |
事象の発生確率と事象の結果の組み合わせ
| 備考 1. | 用語“リスク”は、一般に少なくとも好ましくない結果を得る可能性がある場合にだけ使われる。 |
| 2. | ある場合には、リスクは期待した成果、又は事象からの偏差の可能性から生じる。 |
| 3. | 安全に関する事項については、ISO/IEC Guide51:1999を参照のこと。 |
<出典>
TR Q 0008:2003 リスクマネジメント−用語−規格において使用するための指針
| ※ | TR Q 0008: | ISO/IEC Guide73として制定されたリスクマネジメントの用語を翻訳した標準情報 |
| コーデックス委員会(Codex Alimentarius) |
食品中に危害が存在する結果として生じる健康への悪影響の起こる確率とその程度の関数
(A function of the probability of an adverse health effect and the severity of that effect, consequential to a hazard(s) in food.)
<出典>
Principles and Guidelines for the Conduct of Microbiological Risk Assesment (1999年)
| 厚生労働省 医療安全対策検討会議 |
| 1 | リスクとリスク・マネジメントの一般的な用法 リスク・マネジメントは、従来、産業界で用いられた経営管理手法であり、事故を未然に防止することや、発生した事故を速やかに処理することにより、組織の損害を最小の費用で最小限に食い止めることを目的としている。 リスクとは「損害の発生頻度とその損害の重大さ」の二つの要素によって定義付けられている。世の中の全ての事象にリスクは付随しており、安全とはリスクが許容できるものであるという状態をいう。「リスクは常に存在する」こと、また同時に「適切な管理によってリスクを許容範囲にまで減らすことができる」ことが「リスク・マネジメント」の出発点である。 リスク・マネジメントについての政策立案に当たっては、(1)危険についての社会的許容範囲、(2)リスク・マネジメントに要する費用対効果の両面からの十分な検討が必要である。 |
<出典>
医療安全推進総合対策〜医療事故を未然に防止するために〜(平成14年4月)
| 経済産業省 リスク管理・内部統制に関する研究会 |
リスクは、一般には「危険」すなわち悪い結果の発生可能性という意味で使われるが、より広く捉えて、良い結果と悪い結果の双方の発生可能性を含む「不確実性」と捉えられることもある。企業にとってのリスクとは、狭義には「企業活動の遂行を阻害する事象の発生可能性と捉えられるが、近年では、より広く「企業が将来生み出す収益に対して影響を与えると考えられる事象発生の不確実性」として、むしろ、企業価値の源泉という見方で積極的に捉えられるようになってきている。
本指針では、リスクを広く捉え「事象発生の不確実性」と定義し、リスクには損失等発生の危険性のみならず、新規事業進出による利益又は損失の発生可能性等も含むと考える。
<出典>
リスク新時代の内部統制〜リスクマネジメントと一体となって機能する内部統制の指針〜(平成16年6月)
| 広辞苑 第五版(岩波書店) |
| ・ | 危険。「――を伴う」 |
| ・ | 保険者の担保責任。被保険物。 |
| リスク学事典(TBSブリタニカ) |
狭義には、ある有害な原因(障害)によって損失を伴う危険な状態(peril)が発生するとき、[損失]×[その損失の発生する確率]の総和を指す。リスクを前提にすると、精神的には不安・心配や恐怖が伴う。
(参考2)
【「リスク」に関する指標】
| A | 発生する事象の程度(危害) |
| B | 事象の発生確率(頻度) |
【「リスク」の捉え方】