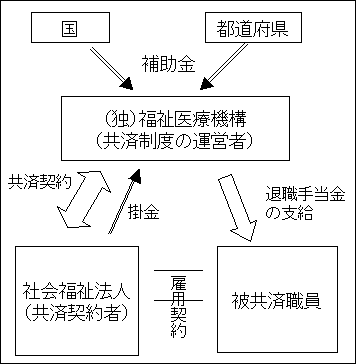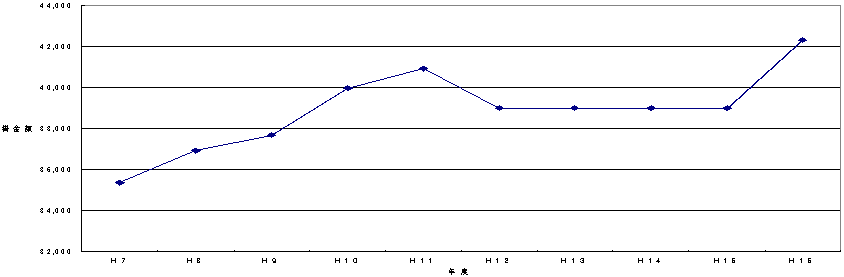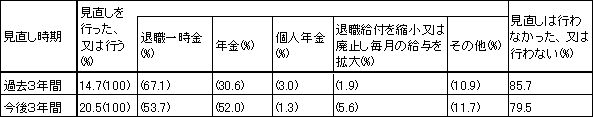| |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
| 社会福祉施設等 |
438,019 |
465,059 |
496,727 |
533,109 |
567,285 |
| |
保護施設 |
4,351 |
4,357 |
4,476 |
4,593 |
4,643 |
| 児童福祉施設 |
169,234 |
175,279 |
182,612 |
191,640 |
199,702 |
老人福祉施設
うち特別養護老人ホーム
ケアハウス
老人デイサービス
老人短期入所施設 |
178,577
133,692
3,617
28,576
625 |
194,926
144,759
4,412
32,539
890 |
213,409
156,811
5,114
37,935
1,067 |
233,714
171,247
5,666
42,288
1,246 |
252,790
184,202
6,323
47,078
1,414 |
| 障害者施設 |
77,147 |
80,495 |
83,906 |
89,224 |
93,570 |
| その他施設 |
516 |
521 |
556 |
553 |
551 |
特定社会福祉事業
うち老人居宅介護等事業
痴呆対応型老人共同生活支援事業 |
8,214
7,334
− |
9,481
8,026
305 |
11,768
9,390
977 |
13,385
10,466
1,840 |
16,029
11,336
3,192 |
申出施設等
うち介護老人保健施設 |
−
− |
−
− |
13,537
4,713 |
17,072
6,518 |
20,323
7,633 |
| 合計 |
438,019 |
465,059 |
510,264 |
550,181 |
587,608 |
|