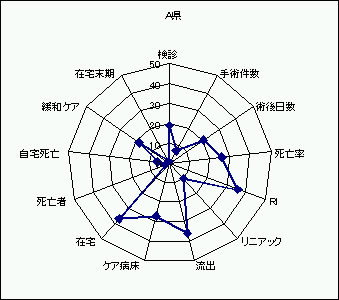
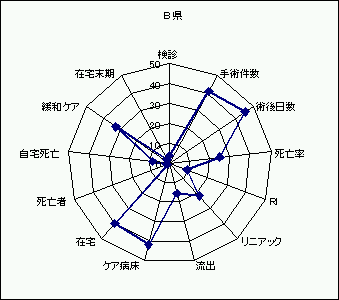
平成16年9月24日
| 「医療計画の見直し等に関する検討会」 ワーキンググループ委員名簿 |
| (氏名) | (役職) |
|||
| ○ | おがた ひろや 尾形 裕也 |
九州大学大学院医療経営・管理学教授 | ||
| かしわぎ えつろう 柏樹 悦郎 |
元富山県砺波厚生センター小矢部支所長 (平成15年9月30日〜平成16年3月31日) |
|||
| かわぐち ひろゆき 河口 洋行 |
国際医療福祉大学大学院助教授 | |||
| かわはら かずお 河原 和夫 |
東京医科歯科大学大学院政策科学分野教授 | |||
| はせがわ としひこ 長谷川 敏彦 |
国立保健医療科学院政策科学部長 | |||
| はせがわ とものり 長谷川 友紀 |
東邦大学医学部助教授 | |||
| まつだ しんや 松田 晋哉 |
産業医科大学医学部教授 | |||
| ||||
| 目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| I 現行の医療計画制度について |
1.医療計画制度の背景と目的
(1)医療法の改正経緯からみた医療計画制度の変遷
| 1) | 第1次医療法改正による医療計画制度の誕生 わが国の医療に関する基本法として1948年に制定されて以来、医療法は、医療体制の充実を通じ、国民医療の確保、向上に大きな役割を果たしてきた。 一方で、わが国の医療体制については、病床の増加等量的には相当程度の整備が行われてきた反面、病院、診療所などの医療資源が地域的に偏在している、あるいは、医療施設相互の機能の連係が十分でないことから、医療資源の効率的活用を図りつつ、人口の高齢化、医学医術の進歩、疾病構造の変化に対応して、国民に対し適正な医療をあまねく確保するため都道府県ごとに医療計画を作成し、地域における体系だった医療体制の実現を目指す医療法の改正法案が国会に提出され、1985年に成立したところである。この改正により、都道府県には、医療計画の作成が義務づけられた。その内容は、(1)必要的記載事項として、医療圏の設定と必要病床数の算定を、また、(2)任意的記載事項として、へき地医療及び救急医療の確保等医療を提供する体制の確保に関する必要な事項を、それぞれ定めることであった。 |
| 2) | 第2次、3次、4次医療法改正と医療計画制度の変遷 1992年には第2次医療法改正が行われ、医療提供の理念が規定されるとともに、高度な医療を提供する特定機能病院と長期入院患者のための療養型病床群が医療法に位置づけられ、医療施設機能の体系化が進められた。 1997年の第3次医療法改正においては、医療機関の機能分担の明確化及び連携を促進するため地域医療支援病院制度が創設されたことを受け、医療計画制度においても、地域医療支援病院、療養型病床群の整備目標、救急医療の確保などを「必要的記載事項」としたことにより、それまでの必要病床数の算定など医療提供体制の量的整備を中心的な目的としていた医療計画から新たな一歩を踏み出すこととなった。 2000年の第4次医療法改正では、地域において望ましい水準の病床を確保するという医療計画の意義が薄れたことを踏まえ、非過剰地域における必要病床数についても、その性格について、過疎地域等の必要な整備が抑制されないよう留意しつつ再検討を行った結果、従来の必要病床数から基準病床数へ名称が変更された。また、「その他の病床」が主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための「療養病床」と病院の病床のうち精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床である「一般病床」に区分され、病床の機能分化の推進が図られることとなったことに応じ、経過措置を講じながら基準病床数の算定の方式を改めることとした。 |
(2)医療計画制度の目的
| 1985年の第1次医療法改正により医療法に位置づけられて以降、医療計画は「当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画(医療法第30条の3)」であると規定されている。また、改正当時の厚生省の通知では「高齢化社会が進展する中で国民に対し適正な医療を確保していくため、医療資源の効率的活用に配慮しつつ、医療供給体制のシステム化を図ることを目的(「医療計画について」昭和61年8月健政発第563号)」と規定しているが、具体的な目標を明示したものはない。 都道府県における医療計画の運用に当たっては、高齢化に向けての医療サービスや医療の提供体制の構築と医療資源、とりわけ病床数の適正化が目標とされてきた過程があり、特に制度発足当初は、医療圏の設定、必要病床数の算定による病床規制に主眼が置かれる傾向にあった。近年では、医療資源の充実に伴い、適切な医療の確保に加え、医療資源の地域格差の是正及び公平性の確保、医療機能分化と連携の推進等がその目的として打ち出されている。また、厚生労働省が2003年8月に公表した「医療提供体制の改革のビジョン」においても、質の高い効率的な医療提供体制の構築を図ること等が示されたことや、最近の医療安全に関する国民の関心の高まり等を受け、今後の医療計画については、患者の視点の尊重に重点を置き、安全、安心な医療の確保、患者に対する情報の提供と選択の支援等が新たな目的として期待される。 |
2.医療計画制度の評価
(1)医療計画制度の影響に関する評価
| 医療計画制度の影響を評価するに当たって、保健医療システム評価の指標としてよく使用される「効果的であること(effectiveness)」、「効率性(efficiency)」、「公平性(equity)」という3つの指標を使用し、評価を試みた。 第一に「効果的であること」については、医療計画の導入後、医療機器の充実、高齢者医療の整備の進展、平均在院日数の短縮及び人口当たり手術件数の増加において顕著な傾向が見られる。また特に、死亡率の低下は高齢者において顕著である。これらが全て医療計画の影響によるものであるか否かについての判断は難しいが、結果として保健医療システムに関して「効果的であること」の指標が上がっていると評価し得る。 第二に「効率性」については、全病床について1992年以降、それまで見られた病床の増加が止まっており、病床当たりの取扱い患者数も増加しているといえる。このため過剰な医療資源は、全体として抑制されているように見え、病床の利用状況も効率化していると評価できるが、一方で医療費の伸びは止まっていないことが指摘できる。 第三に「公平性」については、1984年に比べ1999年の方が、一人当たりの所得が低い県への医療費の流入が増加する傾向がみられ、医療費負担に関する地域間の公平性が増加していることが評価できる。また、各都道府県において最初に作成された医療計画の公示日から2001年までの間に、既存病床数が基準病床数を下回っている地域が減少しており、病床に関する地域間格差の是正という点で公平性が増加していることが評価できる。 |
(2)医療計画の作成とこれに基づく都道府県の執行に関する評価
| 医療計画制度の評価については、マクロで眺めた結果のみならず、個々の都道府県が作成するいわゆるミクロの医療計画の作成と執行の過程の評価が重要である。 医療計画制度では、基準病床数の算定以外は具体的な数値目標が示されていない。がん、循環器疾患、小児医療、高齢者医療等といった医療機能に応じた施設整備、及び、医療従事者の確保についても、特定の中核的な医療機関の整備を除くと、具体的な数値目標が医療計画に十分に示されていない場合が多い。 このことは、医療計画が大まかな社会目標を提示し、その実現をめざしているものの、それにたどり着くまでの道筋を定めるいわゆる実施計画としての役割を十分果たしていないことを示唆している。 また、医療計画に関する具体的な数値目標が不明確であることにより、医療計画の評価と評価に基づく既存医療計画の見直しを困難にしていると言える。 |
(3)国際比較による評価
| 1960年代より世界保健機関(WHO)は、医療計画制度の重要性を指摘しており、狭義の医療のほかに保健を含めた分野(保健医療分野)において、何らかの計画が立てられている国は多い。 イギリスや北欧諸国のように、財源と供給体制の運営主体が政府である場合には、医療計画は政府の保健医療分野におけるサービス提供に係る計画そのものであり、いわゆる規制を目的とした計画ではない。 一方で、民間の病院が多く、医療費高騰の問題が生じている国々では、医療資源の適正化等を図るための規制を目的とした医療計画が作成されてきた。日本が当初、医療計画制度を創設するに当たって参考としたアメリカ、フランス及びドイツは、いずれも1970年代に医療資源の適正化等に係る規制を目的とした医療計画を作成した国々であった。この3カ国にオランダ、オーストリア、台湾及び日本を加えた合計7か国(地域)にこうした規制的な医療計画が存在してきたことが確認されている。なお、日本を除く6か国(地域)においては、規制対象が病床のみならず、医療機器や医療技術にも及んでいる。 これらの6か国(地域)では、医療計画を、医療資源の適正配分を目指し、特に医療費に対して病床や医療機器が与える影響に着目し、医療費を適正化するための手段としている。フランス及びドイツでは当初、むしろ病院や病床を増加・整備するための法律(制度)として作られたが、その後の石油危機による経済の悪化により、医療費の負担の在り方が課題となり、医療費適正化のために病床を抑制する目的に転化して使われている面がある。 |
| アメリカ | フランス | ドイツ | 日本 | |
| 全病院数における 民間病院の割合(%)*1 |
64.6 | 74.8 | 62.6 | 86.0 |
| 法律名 (制定年) |
国家医療計画 資源開発法 (1974) |
病院改革法 (1970) |
病院財政安定法 (1972) |
医療法改正 (1985) |
| 現状 | 連邦法廃止 (1986) 州規制存続 (機器のみ) |
病床規制は 廃止の方向で 検討中 |
維持 (医療機器撤廃) (1998) |
維持 |
| 病床規制 | ○*2 | ○*3 | ○*4 | ○ |
| 医療機器の規制 | ○ | ○ | ○*5 | × |
| *1: | アメリカ、フランス、日本は全病院を対象とした2000年時点の調査から作成。ドイツは一般病院を対象とした1999年時点の調査から作成。 |
| *2: | 1986年連邦法が廃止。 |
| *3: | 次回の医療計画見直しでは病床規制は廃止の方向。 |
| *4: | 次回の医療計画では参照値のみが示され、規制はなくなる予定。 |
| *5: | 1998年に廃止された。 |
| これらの6か国(地域)とも、病床数は当初増加していたものの、1980年ごろから減少に転じている。しかし、これらの6か国(地域)に限らず、他の先進国も1980年代以降、病床数が減少していることから、病床規制と病床数の減少との因果関係を立証することは難しい。むしろ一般的には、平均在院日数の短縮により、不必要となった病床が増加したことによるものと考えられ、結果として、これらの国(地域)においては医療計画制度における病床規制は次第に不要となってきているといえる。 また、これらの国における近年の傾向としては、ケースミックス(各種疾患を診断群に整理分類して管理する方法)などの導入により、各医療機関の医療行為の実情を把握できる情報システムを構築し、それらの情報に基づき医療計画の作成、見直しを行っていること、医療計画の主たる目的が量的な規制から、医療機関間の連携の促進、医療の質の保証等、質的な側面に重点が移っていること、特に、フランス、ドイツ及びオランダでは、量的規制としての病床規制をなくす方向で検討が行われていることなどが指摘できる。 |
3.医療計画制度を取り巻く環境の変化
| 医療計画制度が1986年8月に施行されて以来、47都道府県における医療計画の作成は、1989年3月までに一巡した。その後、5年以内の期間ごとに改定を重ね、全ての都道府県において医療計画の改定が行われているところである。 また、政策目的達成の有効な手段の一つである補助金については、都道府県における医療計画の計画作成のための「医療計画推進事業」や医療施設の機能分化を推進するための「医療機能分化推進事業」があるが、これによって二次医療圏ごとの医療施設の機能分化や連携が機能しているとは言えない状況である。 さらに、医療計画の内容は、医療圏を設定し、基準病床数を算定することにより適切な病床数を確保すること、救急医療等の記載事項に基づき二次医療圏に必要な医療機能等を確保するため関係者間での調整を行うこと等で構成されているが、基準病床数の算定に係るもの以外、現行制度のもとでは都道府県が実効性をもって医療計画の内容を実現できる事項が少ない。 そのほか、医療計画を取り巻く環境の変化については、次のことがあげられる。今後の医療計画制度のあり方については、最終利用者である住民や患者の声が、医療計画にうまく反映されるよう、更なる工夫が望まれるだけでなく、保健、福祉、介護など関連した計画との整合についても重要な課題となっている。 |
(1)政府の役割に関する歴史的動向
| 保健医療サービスは、(1)需要の予測不可能性、(2)情報の非対称性及び(3)外部性、が存在することから、市場に任せるより、むしろ政府により直接介入すべきものと考えられてきた時代があった。しかし、1980年代に入ると保健医療サービスであっても市場重視の傾向が顕著になり、さらに、1990年代になると市場の機能が適切に維持されるための政府の役割が議論されるようになり、政府を市場の調整者とする考え方が普及してきた。こうした考え方を受け、わが国における政府の役割としても、市場のルールを明確にし、モニタリング、評価などを行うことが期待されている。また、これまで、政府と市場との関係は、効率性の問題を中心に議論されてきたが、安全や公平、セーフティー・ネットの確保といった役割が一層、期待される傾向にある。政府には、直接サービスを提供する機能(役割)よりも、市場の調整者、安全や公平の監視者等としての機能(役割)を果たすことへの期待が高まっている。 |
(2)医療制度改革に関する国際・国内的動向
| 1) | 医療制度改革の国際的動向 各国の医療システムについては、イギリスに代表されるような財源が税、供給体制が国という公的部門を中心とするものから、ドイツのように社会保険、民間病院を中心とするもの、そしてアメリカのように、財源、供給体制ともに民間部門を中心とするものなどいくつかの類型に分類される。制度改革の重点は、その類型によって異なるが、共通する3つの領域として、「財政」、「供給体制」、そして「政府の役割」が挙げられる。 近年、医療制度改革の波が世界に拡がっている。このような国際的な改革の動向は1970年代の費用抑制を主たる目的とする政策ではなく、変貌する医療需要に対応し、システムの効率化を図るため、サービスや供給体制、行政(政府)の役割の見直しをも含んだものとなっている。具体的な改革の内容としては、「財政」面では、税あるいは社会保険方式の見直し、社会保険の自己負担割合や財源の見直し、効率的、効果的な支払い方式の導入等があげられる。「供給体制」面では、医療分野における規制緩和や国立や公的病院の民営化、また、「政府の役割」の面では、医療行政の地方分権化などがあげられる。 |
| 2) | わが国の医療制度改革 わが国の医療提供体制についても、1985年に第1次医療法改正が行われて医療計画制度が導入された後も、様々な改革が行われてきた。1996年7月には、医療制度及び医療保険制度の両面から検討する場として厚生省に国民医療総合政策会議が設置され、同年11月に21世紀初頭における医療提供体制のあり方について、(1)医療機関の体系化、(2)かかりつけ医機能の向上をはじめとする医療の充実、(3)病床数の適正化等医療提供体制の効率化、(4)医療における情報提供の推進などを内容として報告がとりまとめられた。 また、1996年12月の与党合意に基づき設置された与党医療保険制度改革協議会が1997年4月に取りまとめた「医療制度改革の基本方針」等の求めに応じ、同年8月に厚生省において「21世紀の医療保険制度」が取りまとめられた。これは、「診療報酬体系」、「薬価基準制度」、「医療提供体制」、「医療保険の制度体系」、「高齢者医療制度」の5分野に及ぶ総合的なものであった。 さらに、1999年の大学病院における患者取り違えによる医療事故がきっかけとなり、医療の安全性や質、情報の開示等に国民の関心が高まり、医療安全対策に関する種々の改革が推進されてきている。 2000年の第4次医療法改正の医療法改正においては、病床区分の見直し、医療情報提供の推進や医療従事者の資質の向上が盛り込まれたところである。また、2001年9月に発表された「21世紀の医療提供の姿」では、「医療提供体制の効率性」「競争が働きにくい医療提供体制」「国民の安心できる医療の確保」「医療提供に共通する情報基盤等の近代化・効率化」の課題を踏まえた今後のわが国の医療の目指すべき姿が発表された。2003年3月に閣議決定された「規制改革推進3か年計画(再改定)」では、「医療計画の病床規制の結果」、「既存の病床が既得権益化され、当該地域に質の高い医療機関が参入することを妨げている」等の問題点が指摘され、2005年度前半までに「病床規制の在り方を含め医療計画について検討し、措置するべきである」とされている。2003年8月には「患者の視点の尊重」「質が高く効率的な医療の提供」「医療の基盤整備」を柱とした「医療提供体制の改革のビジョン」が示された。 このように今後の医療提供体制の改革については、患者と医療人との信頼関係の下に、患者が健康に対する自覚を高め、医療への参加意識を持つとともに、予防から治療までのニーズに応じた医療サービスが提供される患者本位の医療を確立することを基本とすべきである。このためには、患者の選択のための情報提供の推進、質の高い医療を効率的に提供するための医療機関の機能分化・連携の推進と地域医療の確保、医療を担う人材の確保と資質の向上、生命の世紀の医療を支える基盤整備などの分野での改革が必要とされている。このような状況の中で、医療計画がこれらの改革に資するための都道府県段階における実行計画としての機能をより発揮するため、医療計画制度そのものの積極的な見直しが求められている。 |
(3)医療に関する規制改革と医療計画
| 医療に関する規制改革について言えば、医療は、(1)国民に必須のサービスであること、(2)患者と医療者の間に情報の非対称性が認められること、(3)救急医療など時間的に逼迫した状況が生じ得ること、等から、これまで特に直接規制を中心として種々の規制の対象とされてきたところである。 一方で、2002年12月に総合規制改革会議から提言された第二次答申では、医療計画について以下のことが指摘されている。
こうした問題点を踏まえ、同答申においては、
との指摘がなされ、2003年3月の「規制改革推進3か年計画(再改定)」において同様の内容が閣議決定され、2005年度前半までに措置することとされている。 |
(4)超高齢社会と医療需要
| わが国はこれから10年間で人口の4分の1が65歳以上に、さらに30年後には3分の1が65歳以上という人類未踏の超高齢社会を迎える。これにより、医療需要は量的にも質的にも大きく変貌することが見込まれる。この10年間に入院回数、外来総患者数は急増し、特に高齢者でその増加が著しいことが予測される。手術入院が年間150万〜250万回に増加するとの試算もあり、高齢者及び退職者(60歳以上)がその大半を占めることとなると予測される。60歳以上の者の医療費については、10年後には全医療費の65〜70%を占めることが予測される。 疾病構造についても、早期の退行性病変、がん及び循環器疾患から、後期の退行性病変、すなわち老人性痴呆や寝たきりに移行してくると考えられる。高齢者は一般に多種の慢性疾患を抱え、増悪と軽快を繰り返すことから、医療提供側はこのように慢性化し、かつ、急変する1人1人の医療需要への適切な対応が求められ、機能分化と連携の推進が不可欠となる。 他の先進諸国においても同様の課題への対応が進められているが、わが国の場合はそれらの国々に比べても高齢化のスピードが速く、超高齢社会に最初に到達することに加え、近年の医療事故の多発によって国民の医療に対する不信感が高まり、安全で良質な医療サービスの提供が強く求められていることなど、大きな課題が存在する。医療計画制度はこれらの課題に対応し、医療システムの再構築を図ることにより、国民の信頼を回復するための重要な手法となることが期待される。 |
(5)患者の望む医療像
厚生労働省が2003年8月に公表した「医療提供体制の改革のビジョン」における大きな柱は患者の視点の尊重であり、
等の医療の再構築を通じ、患者が望む医療を実現していくこと、そして、こうした患者の選択を通じて医療の質の向上と効率化が図られることが期待されており、医療計画制度においても患者の視点に沿った見直しが求められている。 |
| II 今後の医療計画制度のあり方について |
1.医療計画制度のあるべき姿
| 医療計画制度については、先に述べたとおり、具体的な数値目標が示されていないことや、これまではとりわけ病床数の適正化を目的としてきた過程があり、特に制度発足当初は、医療圏の設定、必要病床数の算定による病床規制に主眼が置かれる傾向にあったことが指摘できる。近年では、医療資源の充実に伴い、適切な医療の確保に加え、医療資源の地域格差の是正及び公平性の確保、医療機能分化と連携の推進等が求められる傾向にあり、医療計画制度のあるべき姿も見直される必要がある。 医療を取り巻く状況、現行の医療計画制度の問題点等を踏まえ、医療計画制度が今後目指すべき方向、すなわち、医療計画制度のあるべき姿について、次のとおり提案する。
|
2.医療計画に盛り込まれるべき内容
(1)目的
| 医療における政府の役割の変化と規制緩和の流れ、超高齢社会の到来、患者の医療需要の変化等に対応した医療提供体制を実現するための手法として医療計画が実効性のあるものとなるためには、医療法に定める医療計画制度の目的とそれに基づく具体的な数値目標を明確にする必要がある。本ワーキンググループにおいては、これまで目的としてきた「地域における適切な医療の確保」と「地域格差の是正」に加え、「患者の望む医療の実現」と「質が高く効率的かつ検証可能な医療提供体制の構築」を位置づけ、これに関する新たな数値目標を創設することを提案したい。 |
(2)圏域
| 1) | これまでの圏域設定の考え方と実例にかかる評価 これまで二次医療圏は、身近で一般的な医療を確保できる圏域であって、保健医療施策を担う中核的な行政機関としての保健所が原則として各1か所含まれる範囲が標準的なものとされてきた。また、二次医療圏の平均的な人口規模は約35万人であって、わが国の圏域数は341から369前後で設定されてきた。この規模は広域市町村圏等の数とも一致し、日本人の日常生活圏と重なることから、全体としては一定の合理性を認めることができるが、一方では、以下の問題点も指摘されてきた。
| ||||||||||
| 2) | 今後の方向 臓器移植等三次医療圏を越えて広域的なネットワークが存在する医療や、救命救急センター、総合周産期母子医療センター等、二次医療圏と三次医療圏の中間に属するような医療が存在することから、医療に関してその機能ごとに明確に一次医療圏、二次医療圏又は三次医療圏と振り分けるのは困難である。 また、医療の質及び効率性と医療の近接性には、トレードオフの関係があることが指摘されている。つまり、医療の質及び効率性を高めるためには、マンパワーの確保等の観点から医療資源の集中化が求められるが、一方で、医療の近接性が犠牲にされる場合があるからである。このため、患者数が少なく高度な技術、専門医の確保が困難な分野等は、医療の近接性をある程度犠牲にしても医療資源を集中化することが望ましく、慢性疾患のケアなど、医療資源の確保が比較的容易であり、継続的な医療が必要とされるものについては医療の近接性が重視されるべきである。 こうした考え方を踏まえ、今後、圏域設定を検討する際には、次の2点について考慮すべきである。
|
(3)基準病床数
| 1) | 基準病床数を設定することについての考え方 基準病床数については、地域ごとに必要な病床数を明らかにすることにより、効率的な医療資源の分配を可能とし、地域格差の是正が図れるとする積極的な肯定評価と、医療ニーズ(特に入院受療)に関する必要性を評価する適切な基準がない状況においては病床数により制限を行うほかに供給者誘発需要(supplier-induced demand)をコントロールする方法がないという消極的な肯定評価がある。 一方で、先に述べたとおり、総合規制改革会議の第二次答申においては、基準病床数算定の問題として、現在の医療計画が医療機関(病床)の量的なコントロールを行っていることにより、医療機関の競争が働きにくく、既存病床の既得権益化が生じ新規参入が妨げられていること、病床数の基準が現状追認的なものとなっており、対人口比の地域間格差があること、地域の実情やニーズに応じた適切な機能別の病床数の確保ができていないこと等の問題点が提言されているところである。 | ||||||||
| 2) | 適正な医療提供の確保との関係でみた基準病床数の存否 基準病床数を廃止し、医療機関の参入又は撤退を全く自由にするという意見の論者も、限られた医療資源を効率的に活用し、医療の必要度に応じて入院治療が必要な患者が速やかに入院治療を受けることができるよう適切な機能別の病床数を確保することの必要性は認めるところである。他方で、供給側による誘導の結果として入院の必要度が低い患者が入院治療を受けるといった事態が生じることがないようにしなければならない。 このため、基準病床数を廃止する場合には、適切な医療提供体制を確保するために最低限必要な条件として次の事項が必要であると考える。
この仕組みを支えるためには、各医療機関により、1)正確な分類に基づいたケースミックス(各種疾患を診断群に整理分類する方法)を用いた患者構造の明確化、2)治療結果、3)在院日数、4)費用(経営指標)が一定のルールにより都道府県に報告されることにより、医療の透明性が確保され、患者の選択の促進と競争環境の整備が図られるものと考えられる。 なお、これらは基準病床数制度廃止のみを目的としたものではなく、医療の質の向上と効率化に資するという点に留意すべきである。 | ||||||||
| 3) | 基準病床数を維持する場合に必要な改善点 上記の最低限必要とされる条件が整備されるまでの間において、適正な医療提供の確保のため基準病床数を維持する場合には、現行の基準病床数算定について指摘されている問題点を踏まえ、少なくとも以下の点について検討され、改善されるべきである。
|
(4)記載事項
| 1) | これまでの記載事項の考え方と果たしてきた機能に関する評価 医療計画に必ず記載しなければならない事項として、主として病院の病床の整備を図るべき地域単位として区分する区域(二次医療圏)の設定、基準病床数の算定及び地域医療支援病院の整備の目標、休日夜間等の救急医療の確保、へき地医療の確保等が医療法により規定されている。この他、政策的に推進すべきものについて厚生省の局長通知である医療計画作成指針に示されているものを含め、都道府県においては、それぞれ地域の実情を踏まえて医療計画に記載することにより地域の医療を提供する体制の確保に関し一定の効果を上げているところである。しかしながら、医療計画制度については、これまで明確な目的とそれに基づく具体的な数値目標が示されていないことから、作成された医療計画では、記載事項についても理念的なものにとどまり、医療計画の達成度を把握、評価し得るような具体的な内容にまで踏み込んでいる例は少なく、進捗状況を逐次把握し評価できる仕組みとはなっていない。 |
| 2) | 今後の方向 今後の方向としては、医療計画制度における新たな目的を明確化した上で、記載事項については医療計画の目的を達成するための具体的な数値目標として位置づけ、進捗状況の把握と達成度の評価を実施できるよう、あらかじめ数値化できる適切な指標を選択、導入しておく必要がある。 |
3.作成手続き
(1)医療計画を有効に機能させるための情報収集等
| 医療計画が有効に機能し実施されていくためには、地域の実情を踏まえた具体的な目標の設定、目標に向けて実施するための医療計画の作成、定期的な評価と見直しが必要である。これを実効性あるものにするためには、医療計画の作成と実施に必要な時間、予算及び調査の手法の3つが重要な条件となる。特に、調査の手法については、これまでの国や都道府県、あるいは市町村で行った調査内容をまず分析し、それをもとに必要な部分を補うための費用対効果の高い調査を行うようにすべきである。そしてこれらの調査の過程において医療計画を点検、評価できるような仕組みを当初から考えておくと効率的である。 |
(2)関係者等の意見調整(関連する他の計画との調整)
| 医療計画の作成に当たっては、医療計画に関係する部局との連携を図り、数値目標の設定を適切に行うのみならず、執行管理、評価、見直しを含めて効率的、効果的に実施できるような組織横断的な体制づくりが不可欠である。その際、健康づくり対策、介護保険、母子保健等、関連のある他の計画等との調整を行う必要がある。 また、市町村、関係団体、学識経験者等の意見を反映しながら計画を策定する必要がある。 |
(3)住民参加を求める仕組み
| 医療計画を通じて患者の視点を尊重した医療提供体制を実現するためには、情報の発信者(専門家、行政機関、医療機関等)と、患者や住民との間の情報量の格差を是正する仕組みが必要である。 住民が計画作成に積極的に参加し、住民の医療ニーズを反映した医療計画を作成するためには、住民が有する情報量を増大させ、医療機関、医師会等の関係団体及び都道府県が有している情報量との格差を可能な限り是正していく必要がある。情報の格差の是正については量的なものに限らず、解釈するための能力の格差を克服する必要がある。情報量の格差の克服は、情報公開による対応が必要であり、解釈するための能力の格差の克服のためには、都道府県又は専門家側が住民に対して、わかりやすい言葉で説明し十分かつ対等な立場で議論できる環境を整備する必要がある。 具体的な住民参加の手法としては、積極的な参加を拡充する方策として、パブリックコメント、アンケートなどが制度的に用いられているが、実際に住民の意向がどの程度反映されるかについては保障され得ない。現実には、専門性の高い分野ほど住民側の持つ情報の量が乏しいと考えられ、その意向が反映される程度は制限されることに配慮すべきであり、積極的に住民が参加できるシステムを構築する必要がある。 |
4.医療計画に基づいた都道府県の執行管理と推進の方策
(1)医療計画に基づいた都道府県の執行管理の方策
| 医療計画が有効に機能し実施されていくためには、地域の実情を踏まえた具体的な数値目標の設定、目標に向けて実施するための医療計画の作成、定期的な評価と見直しが必要である。 例えば、住民の視点に立った評価手法として、後述する「ライフコースアプローチ」(主要な疾患・健康問題について、患者の病態に応じて必要となる医療サービスごとの供給量や質に係る指標を用いて、地域ごとの医療サービスの現状を把握し、整備・改善のための数値目標を設定することにより地域医療水準の定量的評価を行う方法。)を用いる場合には、まず、(1)地域の実情を把握した上で、(2)当該地域における確保すべき医療提供体制についての指標を設定し、(3)設定された指標について具体的な数値目標を定める。そして(4)この数値目標を達成するための活動計画としての医療計画を作成し、(5)一定期間の後に、数値目標と現実の達成度とを比較して評価を行い、(6)評価結果のフィードバックにより医療計画の見直しを行う、という過程を経て医療計画の執行管理を行うこととなる。指標の設定については、原則として、都道府県が地域の保健医療に関して抱えている課題の実情に即して決定する必要があるが、全国的な課題については、都道府県間の比較ができるよう、国において共通の指標を導入することも検討する必要がある。 このように、医療計画の進捗状況を逐次把握し、定期的な評価を行うことにより、医療計画の推進に関して関係者の動機付けを図るとともに、評価結果に基づき、執行方法や医療計画の内容を見直すことが可能となる。都道府県における行政の透明性の確保と説明責任を果たすためにも、医療計画の作成プロセスの明確化と評価結果の公表など積極的な情報公開が必要である。 |
(2)都道府県の医療計画推進の方策
都道府県の医療計画担当者に対し、医療計画を推進する際に有効な方法について、アンケート調査(「医療計画策定のための調査」(2001年3月))を行った結果、有効とされたものは次のとおりであった。
医療計画の推進方策として、都道府県の担当者は「計画推進のための委員会の設置・開催」が最も有効であると考えている。市民へのPRも4番目に入っているが、委員会の開催や医師会、病院協会の会合に出席すること等に比べると順位が低い。先に述べたように、従来の医療計画は、医療提供側の視点を中心に作成される傾向が強く、患者や住民等、消費者側の視点が反映されにくいものとなっていることが推測される。 なお今後、医療計画の具体的な数値目標や評価結果等について都道府県が住民へ積極的に情報提供することにより、住民の意見が反映され、都道府県や医療提供側が住民等、消費者側のニーズに即したサービスの提供を実施していくインセンティブが働くことになると考えられる。 また、推進方策として「補助金を出す」ことが有効であると考えられている。国及び自治体においても、医療提供体制の整備に関する助成金等は種々あるが、医療計画と医療提供に係る各々の事業との整合性が十分図られていないのが現状である。医療提供体制の充実を図るための総合的な計画として医療計画を位置づけ、推進するためには、都道府県段階で助成金他関連制度の運用に当たり、医療計画の記載事項の実現に向け、有機的関連づけを図る必要がある。 |
5. 医療計画に関する評価とその結果の都道府県行政への反映
(1)評価の重要性と評価方法
| 繰り返し述べてきたとおり、医療計画の実効性を上げるためには、具体的な数値目標の設定と評価を行い、医療計画の推進に関して関係者の動機付けを図るとともに、評価結果に基づき、執行方法や医療計画の内容を見直すことが重要である。都道府県行政の透明性の確保と説明責任を果たすためにも、医療計画の作成プロセスの明確化と評価結果の公表が必要である。 評価を行う時期については、事前・中間・事後の3種類があり、評価方法も定性的、定量的な方法がある。評価を効率的、効果的に行うためには、医療計画を作成する際、同時に評価方法等についても検討し、でき得る限り定量的な方法で実施することが必要である。 |
(2)目的の明確化
| 評価を行うためには、医療計画の目的が明確化されていることが必要である。なぜなら評価というのは目的の達成度を測定することだからである。しかし、目的は階層構造をなしており、一つの要因のみで目的を達成しうることは一般的に少ない。その要因が目的達成にどのくらい影響を与えたかを明らかにするためには、目的の階層と因果の構造を明らかにし、影響する他の要因を同定する必要がある。 |
| 1) | 数値目標設定の意義 医療計画の目的が明確化され、その実現に向けて執行する過程においては、数値目標を示し、数値目標に対する執行状況を測定することにより問題解決過程を進行管理することが可能となる。従来、医療計画の中に具体的な数値目標を記載しているところはほとんどなく、こうした視点が欠けていたことは否定できない。 医療計画の目標を数値化した指標として示すことにより、医療計画を実施する上での執行管理や執行後の評価を実施することが可能となる。 |
| 2) | 数値目標設定の方法 目標の設定では、医療計画が達成されたときの状況の具体的予測が求められる。「誰が」「どこで」「何を」「どのようにして」「いつまでに」「どうする」のか(5W1H)を明確にする必要がある。更に、「わかりやすく」「測りやすく」「較べやすく」「変えやすく」という基準から目標を選ぶ必要がある。 また、数値目標を設定し計画の指標とするものは一般の住民にもわかりやすいものであり、かつ、地域における健康課題の解決に有用なもの、数値を把握しやすいものを選定する必要がある。 |
(3)住民の視点に立った評価方法(ライフコースアプローチ)の提案
| 1) | 情報格差の是正の重要性 近年、行政施策への住民参加が求められており、また、「医療提供体制の改革のビジョン」においても、患者の視点の尊重が重要な柱となっている。医療計画の作成に当たる審議会等においても、一般的に、住民代表が参加している場合が多いが、医療に関しては、提供側である医療関係者等と消費者側である患者、一般住民との間に圧倒的な情報の非対称性があることから、これまでは医療提供側の視点に立った計画にならざるを得ない面があった。 こうした状況を踏まえ、ここでは主要な疾病に関して疾病の経過に基づいたシナリオを作成することにより、医療サービスの消費者・提供者の双方が情報を共有し、評価することができる新たな方法を提案したい。疾病の経過の各段階において医療計画の評価に資すると考えられるものを指標化し、一部、都道府県別の評価を試みた。 | ||||||||||||
| 2) | ライフコースアプローチの活用 医療計画を住民の視点に立った計画とし、実効あるものとするためには、次のような基本的な命題に応えていく必要がある。
という具体的内容が必要であり、これに対応するためにはライフコースアプローチを提案することが有効である。 | ||||||||||||
| 3) | 医療計画における執行管理と疾病の選定 ライフコースアプローチを用いて医療計画の執行管理を適切に実施するためには、地域の疾病構造等を把握した上で、その状況や住民のニーズ等を踏まえ、取り上げるべき疾病の優先順位を設定する必要がある。一般に、優先順位は、社会的影響、医療計画による介入の効果、その他の価値(公平性、費用など)等に基づいて決定される場合が多く、疾病の選定過程及びその根拠となるデータ等は公表されることが必要である。その際、都道府県は、優先順位を設定するためのデータ等を入手する手段についての検討が必要となる。 実際に都道府県において医療計画を作成する際の取り上げるべき疾病の優先順位の設定、ライフコースアプローチを用いた医療計画の執行管理の具体的な方法等は、それぞれ都道府県において検討されるべきものである。以下は各ライフステージの代表的な疾病である。
| ||||||||||||
| 4) | ライフコースアプローチを用いることにより期待される効果 地域において重要な疾病が選定され、疾病に係る治療等の過程として地域における医療機能が明らかにされ、それらを指標とした達成度を評価することによって、種々の波及効果が期待される。例えば、地域における必要な医療の確保状況はもとより、選定する疾病に係る指標によっては、医療施設の機能分化の状況や機能連携の状況等を明らかにし、住民に対して分かりやすく周知することが可能となる。また、これらの状況を踏まえ、都道府県が強化すべき医療施策が明らかになることにより、予算の確保や医療施策に対する住民の理解を得ることが容易となる。 | ||||||||||||
| 5) | ライフコースアプローチの具体的なシナリオと評価 以下に乳がんを例にとり、ライフコースアプローチの具体的なシナリオと評価の実例を示す。 |
| 【例:乳がん】 ■シナリオ■ Aさんは45歳の主婦である。定期健診1で乳房のしこりを指摘されて、近くの病院を受診した。そこでは画像検査の結果、乳がんと診断された。 医師は乳房を切除する手術を勧めたが、Aさんは、他の治療法がないか別の医師の意見を聞きたいと申し出た。これによりエックス線などの資料のコピーを借りて、別の専門病院を受診した2。専門病院はその地域でも手術件数が多く、治療成績が優れていることで知られている3。そこでは乳がん専門のB医師の意見を参考にして手術を行った。術後の経過は順調で、切除した乳房の美容形成についてもB医師から別の医師の紹介を受けた4。 3年後、定期的な経過観察で乳がんが骨に転移し再発していることが確認された5。B医師から放射線治療医、がん化学療法専門医6の紹介を受け、相談の結果、放射線療法を選択した。 がんは、一旦は縮小したものの、その後、別な場所にも転移が見つかった。このため、化学療法に切り替えて、治療を継続したが、次第に抗がん剤の効かなくなり、Aさんは痛みから夜眠れずに体力が衰えてきた。そこでAさんには、自宅の近くで、在宅医療、緩和ケアを行っている病院が紹介された7。以降、定期的に訪問診療・訪問看護を受けて、睡眠薬、鎮痛薬の処方をしてもらい、体力が衰えたときや痛みの強いときに数日間入院することを繰り返している。 |
| 1 | 検診:一定以上の年齢の住民は、主要ながんについてがん検診を受けることができること。 到達度評価の指標:がん検診受診率、サブグループ別、個人ベース。 |
| 2 | 情報:重大な疾患についてはセカンドオピニオンが可能なこと。 到達度評価の指標:セカンドオピニオン対応医療機関数・患者数(疾患別)。 |
| 3 | 医療の質:病院の特徴、主要な手術・処置の件数、成績などの情報が整備され、受診にあたって参考とすることができること。 到達度評価の指標:情報のフォーマットの整備、公開している医療機関数・割合。 |
| 4 | 連携:患者中心の医療サービスがseamlessに用意されていること。重要な疾患についてはこのようなケアコーディネーションを行う体制が整備されていること。 到達度評価の指標:主要ながんについてのケアプロセスを明示し、それぞれ満たしている医療機関数・割合。 |
| 5 | 追跡:術後のがん登録、長期間のフォローアップが行われ、長期の治療成績などの情報が整備されること。 到達度評価の指標:がん登録割合、フォローアップ率。 |
| 6 | がん専門医:二次医療圏ごとに、がんに対する放射線治療、癌化学療法を行う専門医が整備されていること。 到達度評価の指標:放射線治療、癌化学療法専門医師数。 |
| 7 | 緩和ケア:二次医療圏ごと、在宅医療、緩和ケアを行う施設が整備されていること。緩和ケアは長期間の入所を目的としたもののみではなく、外来を中心として短期間の入所を行う施設も用意されていることが望ましい。 到達度評価の指標:緩和ケア実施医療機関数、在宅医療実施医療機関数。 |
県別指標の評価の例
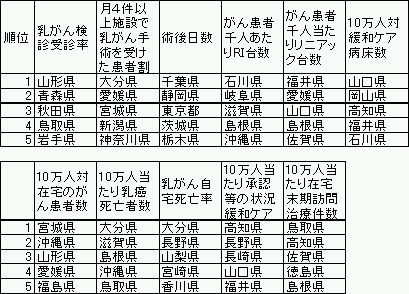
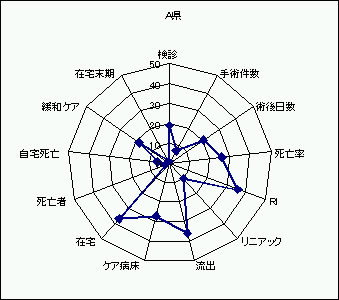 |
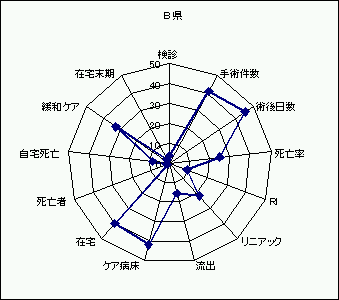 | |
| 目盛りは、47都道府県の中での順位。 | ||
| III 当面取り組むべき課題 |
| IIの今後の医療計画のあり方を踏まえつつ、当面取り組むべき課題を具体的に示せば、以下のとおりである。 |
1.基準病床数その他病床関係
(1)基準病床数の算定式
| 1) | 現状 現行の基準病床数の算定式は、二次医療圏ごとに算定する療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関するものと、都道府県の区域ごとに算定する精神病床に係る基準病床数、結核病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数それぞれに関するものを定めることとなっている。 2003年8月末までに届けられた病床区分の届出は一般病床923,047床、療養病床346,045床であったが、その後の医療施設動態調査(2004年5月末概数)における両病床は、一般病床913,955床、療養病床346,838床となっている。 療養病床及び一般病床に係る基準病床数は、新たな病床区分が定着するまでの間(2001年3月〜政令で定める日(現行では未制定))は現行の一般病床・療養病床全体で一つの基準病床数算定式により算出した数が標準となっているが、新たな病床区分が定着した後は、療養病床、一般病床の病床の種別に応じて算定した数の合計数を標準とするとされている。 |
| 2) | 当面取り組むべき方策 (1)一般病床・療養病床 一般病床及び療養病床について、2003年9月末から2004年5月末までの医療施設動態調査(概数)により、一般病床と療養病床の間の移行状況をみると、一般病床から療養病床へ移行する傾向は継続してみられているものの、大きな変動はなく、新たな病床区分は、ある程度定着したものと考えられることから、一般病床と療養病床の新たな算定式を作成する必要がある。 一般病床は、近年の医療の進歩に伴い平均在院日数の短縮が著しいが、一方、高齢化により入院回数が増加することが予測される。年齢階級別の入院の発生率は、近年あまり大きな変化はなく、大きな地域差も認められない。そこで一般病床の算定式は、平均在院日数×入院回数/病床利用率で求められる。 平均在院日数は、現状追認による地域格差を是正する上では、全国一律の数値を使用することが望ましい。今後、平均在院日数の短縮を見込むための平均在院日数推移率についても全国一律の数値を使用すべきとの考え方と、各地域が目標を設定し、目標管理を行うことについても検討すべきとの意見もある。入院回数は全国または9ブロックでの年齢階級別・性別の入院回数割合を基礎に算出できる。また、病床利用率についても全国値を使用すべきである。 高齢者等が生活する場としては在宅が望ましく、病状やニーズに応じて在宅、次いで保健施設や福祉施設、そして医療施設であると考えられるが、現状は必ずしもニーズに応じた振り分けになっていない。長期療養を提供する医療施設の病床数については、地域において長期療養に係る医療又は介護を必要とする入院・入所需要から介護施設(介護療養型医療施設を除く。)において対応可能なケースを差し引いた数となる。 (2)精神病床 精神病床の算定式は、精神病床等に関する検討会において別途検討がなされ、報告されたところである。 (3)結核病床 結核病床については、厚生科学審議会感染症分科会結核部会の下に設けられた検討小委員会において現在検討中である。 (4)感染症病床 現行の基準病床数は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第38条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第1種感染症指定医療機関及び第2種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数とするとなっており、引き続き、同様の取扱いとすべきである。 |
(2)病床の特例
| 1) | 現状 特定の病床等については、各区域で整備する必要があるものに限り、各区域で基準病床数を超える病床が存在する等(病床過剰地域)の場合でも必要に応じ例外的に(都道府県知事の勧告が行われることなく)整備できるものとされている。 特例の取扱いは、基準病床数の見直しの際、大規模な都市開発等により急激な人口の増加が見込まれ、現在人口により病床数を算定することが不適当である場合等、医療計画公示前に基準病床数に含める場合と、医療計画公示後において、がん等の特定の病床に係る特例の対象となる病院の病床等を基準病床数とみなす場合とがある。 最近の特定の病床等の特例に関する改正としては、構造改革特区に関する地方公共団体等からの第2次提案における要望を踏まえ、国内の治験を推進する観点から患者以外の被験者に対する臨床試験に係る病床を医療法施行規則第30条の32の2第1項に規定する特例の病床等の特例として追加している。 |
| 2) | 当面取り組むべき方策 現在の医療技術の進歩や疾病構造の変化を踏まえ、(1)その病床において提供される医療の内容、質に照らし、地域における既存病床数と基準病床数の関係如何を問わず特例的に整備すべきもの、(2)こうした事情が認められなくなっているものに着目し、見直しを検討すべきである。その際、現行の医療法施行規則第30条の32の2第1項に定められている14項目の病床について、例えば次のものについては見直しが必要と考える。 (1)がん及び循環器の病床に係る特例 第1号関係のがん及び循環器の病床は、1998年以降、特例の病床としての実績がないことから、今後も特例病床として、整備する必要があるかどうかについて検討すべきである。 (2)リハビリテーションの病床に係る病床 第4号関係のリハビリテーションの病床は、発達障害児の早期リハビリテーション、その他の特殊なリハビリテーションに係る病床に限定されている。このため、亜急性期のリハビリテーションを行う病床の整備の必要性について検討すべきである。 (3)緩和ケアの病床に係る特例 第8号関係の緩和ケア病床は、全国的に整備されつつある。今後は、緩和ケアに関し地域の中核的、指導的な役割を担うもの、例えば、地域がん診療拠点病院に設置される緩和ケア病床等に限定することについて検討すべきである。 (4)診療所の病床を転換して設けられた療養病床に係る特例 第14号関係の診療所の病床を転換して設けられた療養病床は、1998年3月31日に現に存する病床を転換して設けられた療養病床と限定されている。療養病床については、第4次医療法改正により、医療法上も一般病床と区分され、全国的に整備が進んでいることから、診療所の病床を転換して設けられた療養病床を、今後も特例病床として継続する必要があるかどうかについて検討すべきである。 |
(3)既存病床数の補正
| 1) | 現状 既存病床数の補正は、次のとおり、医療法施行規則第30条の33で規定されている。 (1)職域病院等の病床数の補正 職域病院等の病床(診療所の療養病床に係る病床を含む。)は、一般住民が利用している部分を除いては、職域関係者など本来の目的とされる利用者の利用実態に応じた病床数に限り、既存病床数には算定しないこととなっている。 (2)ICU病床等の病床数の補正 ICU病床等のうち、バックベッドが確保されているものは、患者一人で2床を占有する形態となっていることから、ICU病床等を既存病床数として算入しないこととしている。 (3)介護老人保健施設の入所定員に係る補正 既存の病床数の補正に関し介護老人保健施設の入所定員の取扱いについては、医療法第7条の2第4項において、当該地域における既存の病床数を算定するに当たっては、介護老人保健施設の入所定員は、厚生労働省令の定めるところにより、既存の療養病床の病床数とみなすとされており、その取扱は次のとおりである。
| ||||||
| 2) | 当面取り組むべき方策 (1)職域病院等の病床数の補正 職域病院等の範囲に指定されている病院の中には、重症心身障害児施設である病院のように入所患者が限定されているものから、一般住民も入院できる病院まであり、現在は、病院ごとに病床の補正の式により算定した数が0.05以下であるときは補正しない(病床数全てについて既存病床数として算定する)こととなっている。今後は、補正対象の病院を原則、重症心身障害児施設である病院、肢体不自由児施設である病院若しくは自閉症児施設である病院のように入所患者が限定されているもの又は法務省が開設する医療刑務所病院、自衛隊駐屯地内の自衛隊病院等地域住民が通常利用しないものに限定すべきである。 (2)ICU病床等の病床数の補正 ICU病床等の範囲は、放射線治療病室(RI病床)、集中強化治療室(ICU病床)、心疾患強化治療室(CCU病床)及び無菌病室(無菌病床)であるが、実態として、必ずしも後方病床が確保されていない場合があることから、今後は、補正の対象としないこととすべきである。 (3)介護老人保健施設の入所定員に係る補正 介護老人保健施設は介護保険法に基づく福祉的な側面が強い施設であること、入所定員の取扱いについて、既存病床数への算定方法が統一されていないことから、既存のものを含めて、病床数の算定対象から除外することも含め、その見直しを検討すべきである。 |
2.記載事項関係
(1)記載事項として追加することが期待される事項
| 後述(2)の評価方式の導入を考慮し、評価可能な形で盛り込むことが期待される事項をあげれば以下のとおりである。 (1)公的病院等の位置づけ及び公私の役割分担の明確化 地域における医療機関の機能分担と連携の確保については、医療計画作成指針において、公的病院等と民間の医療機関との役割分担を含め、医療に関する施設相互の機能分担及び業務の連携を踏まえたものを記載することとされているが、これまでは医療機関の提供する医療サービスの内容や患者構造について十分に検討が行われてこなかった。都道府県が医療計画の見直しをする際には、どのような医療サービスを提供しているかに基づいて公的病院等の位置づけや公的病院等と民間の医療機関との役割分担をさらに明確化する方策を検討する必要がある。 (2)政策的に推進すべき医療や機能との関連 新たに政策的に推進すべき医療施策や医療を取り巻く最近の情勢を踏まえ、当面次の事項を医療計画に位置づける必要があると考える。
|
(2)医療計画の評価の導入
| 1) | 現状 医療計画は、医療提供施設の整備の目標を記載することになっているが、具体的な目標の記載が乏しく、評価体制がある都道府県はほとんどみられない。 |
| 2) | 当面取り組むべき方策 医療計画の実効を上げるため、ライフコースアプローチを用いた評価方法等について、早期に導入することが望まれる。その評価の手法、着眼点等については、あらかじめこれを明らかにしておくことが期待される。その際、医療機能調査の充実が有効である。 |
(3)医療機能調査の活用
| 1) | 現状 都道府県においては、医療機関の施設、設備、症例数、平均在院日数、紹介先とその件数及び専門職員数等に関する調査(医療機能調査)を行い、調査に基づき医療機能の整備の必要性を検証し、不足している医療機能については、その整備の方法及び整備の目標等について医療計画に記載している。また、調査により得られた医療機関の医療機能に関する情報を各医療機関に提供している。 |
| 2) | 当面取り組むべき方策 医療機関の機能分化と連携、患者の選択を通じた医療の質の向上を推進するため、医療機能調査結果の地域住民への公表等を積極的に進めるとともに、ライフコースアプローチを用いた医療計画の目標設定と評価を行う際の基礎資料として、当該調査を充実し、有効に活用すべきである。 |
(4)医療情報の整備と活用
| 都道府県においては、各医療機関が設備、提供する医療サービスの内容、症例数、平均在院日数、専門職員数などの情報整備・公開を促し、利用者、その他の関係者が情報を活用できるよう環境整備に取り組むべきである。 |