| 現状 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
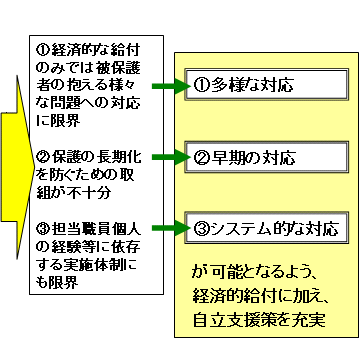 |
| 社会保障審議会−福祉部会 | |
| 生活保護制度の在り方に関する専門委員会 | |
| 第16回(平成16年9月24日) | 資料 |
| ○ | 自立支援の在り方について |
| 1 | 生活保護制度の見直しについて |
| 1. | 現状と見直しの方向性 |
| 現状 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
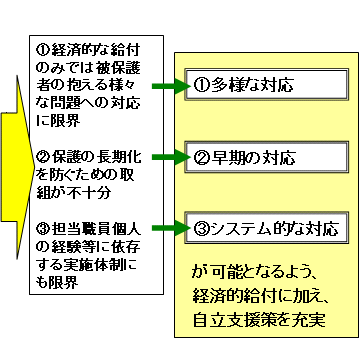 |
| 2. | 具体的な取組としての自立支援プログラム −生活保護制度に自立支援プログラムを導入し、自立・就労支援を強力に推進
|
| 3. | 自立支援プログラムのイメージ |
| 有子世帯(ひとり親世帯の親等)の自立支援プログラム |
| 要保護者の職歴、資格、就労阻害要因等を踏まえ、次のようなプログラムに基づく取組を求める。 |
| − | 原則として就労を求めるが、適職がない場合等には、職業訓練等による職業能力開発(技能修得等)、試行雇用や福祉的就労等を求める。職業能力開発(技能修得等)等も不可能な場合には、健康管理・意欲向上支援等を実施する。 |
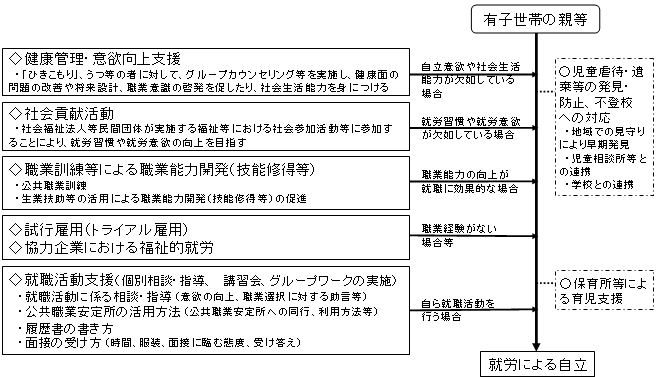
| 就労経験の少ない若年者等の自立支援プログラム |
| 就労経験の少ない若年者等の健康状態、就労意欲、能力、学歴等を踏まえ、次のようなプログラムに基づく取組を求める。 |
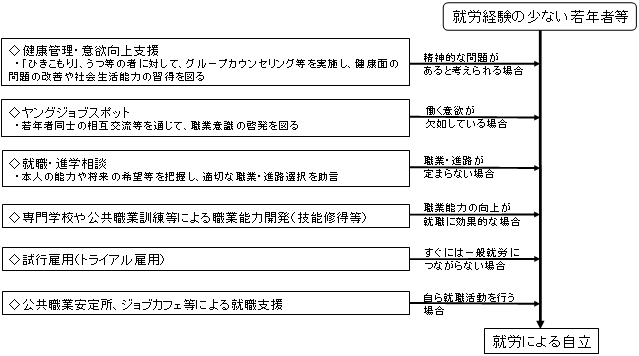
| 社会的入院患者等(精神障害者等)の自立支援プログラム |
| 社会的入院患者等(精神障害者等)の居宅生活への復帰やその維持・向上等を支援するため、 要保護者の病状、退院阻害要因等を踏まえ、次のようなプログラムに基づく取組を求める。 |
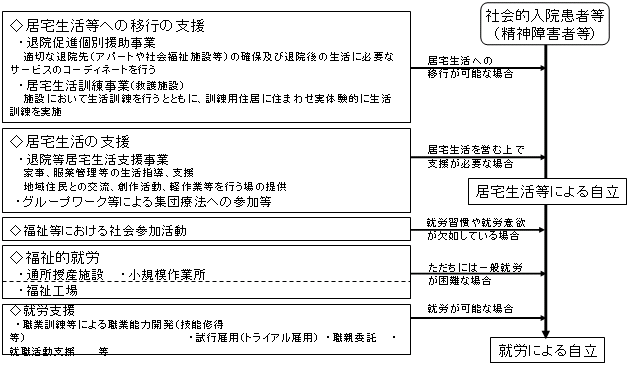
| 多重債務者の自立支援プログラム |
| 要保護者が多重債務を抱えていることを早期に把握し、その多重債務の原因等を踏まえ、他のプログラムに優先して、次のようなプログラムに基づく取組を求める。 |
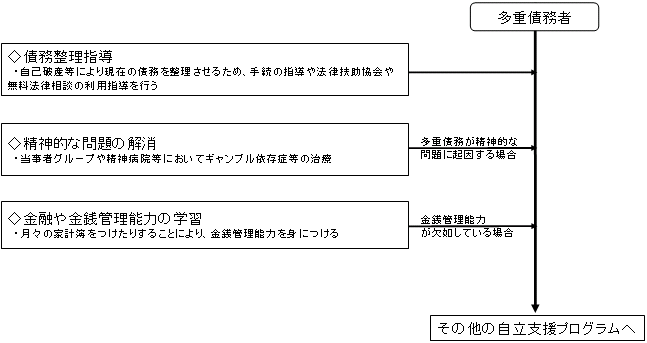
| ホームレスの自立支援プログラム |
| ホームレスの健康状態、就労意欲、職歴等を踏まえ、次のようなプログラムに基づく取組を求める。 |
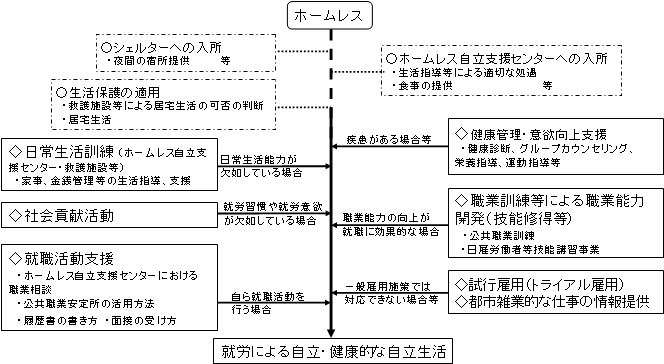
| 高齢者の自立支援プログラム |
| 要保護者の健康状況等を踏まえ、次のようなプログラムに基づく取組を求める。 |
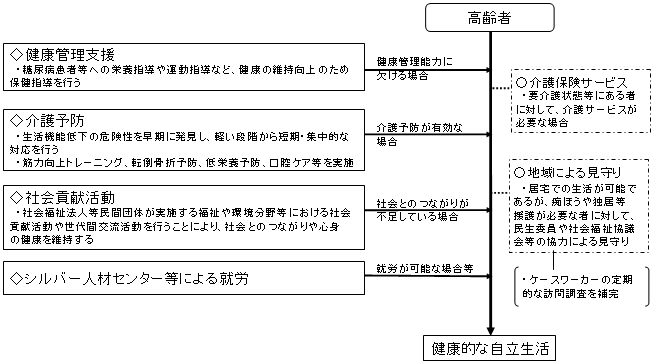
| 4. | 自立支援プログラムの実施体制
|
| 2 | 諸外国における取組の例 |
| 1 | アメリカにおける取組の例 |
| ○ | NY市の自立支援策 |
|
|
 |
|
| ※ | NY市の取組
(平成16年8月30日 読売新聞から) |
| ○ | NPO法人の取組 |
|
|
 |
|
| ※ | NPO法人における自立支援メニュー (個々人に必要なものを組み合わせて行う)
(Goodwill Industries の資料から) |
| 2 | ドイツにおける取組の例 (第9回布川委員提出資料から抜粋) |
| (3) | 事例紹介と成果 資料に、ヴァーレンドルフという小さな町の社会事務所で1998年に担当者からヒアリングした事例をあげています。 |
| E.Eさん | 母24歳、男児4歳の母子世帯、就労扶助に従事、 収入・資産・児童手当220マルク、養育費立替支給329マルク |
| 3 | 日本における取組の例 (第9回布川委員提出資料から抜粋) |