




|





|
| 近年、精神障害者向けの各種サービス・事業が特に充実。 |
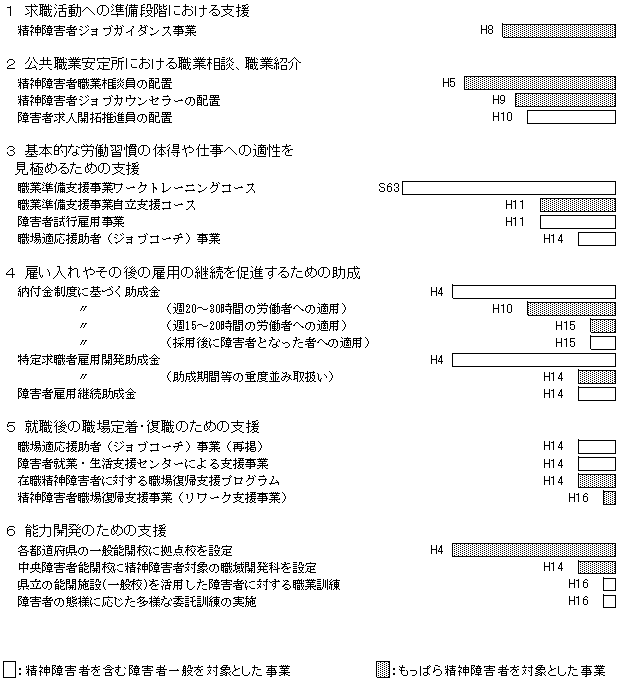
|
精神障害者については、 そこで、主治医・事業主・障害者等による協働体制を確立した上で、精神障害者の復職・雇用促進・雇用継続について以下のような支援を行う「精神障害者の雇用の段階に応じた体系的支援プログラム」を実施する。 |
| ○ | 休職している障害者に対し、センター内での作業体験、ストレス対処講習、体力回復のためのトレーニング、リハビリ出勤支援等を通じ、生活リズム構築、基礎体力向上、作業場面・対人場面への適応力向上のための支援を行う。 |
| ○ | 事業主に対し、職場の受入体制の整備(復職計画策定、従業員教育等)や家族・医療機関等との連携体制の整備等に関する助言を行う。 |
2.雇用促進支援
| ○ | 事業主が精神障害者の雇用を計画的に進めていくことができるよう、採用計画の立案等に関するコンサルティングを行う。 |
| ○ | 職場にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対し、新規雇用に向けた支援を行う。 |
| ○ | 事業主に対し、障害者の状態に応じた雇用管理や職場の体制整備、家族・医療機関等との連携体制の整備等に関する助言を行う。 |
3.雇用継続支援
| ○ | 職務遂行や人間関係について問題が生じた場合、職場にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対し、職場定着に向けた直接的な支援を行う。 |
| ○ | 事業主に対し、障害者の状態に応じた雇用管理や職場の体制整備、家族・医療機関等との連携体制の整備等に関する助言を行う。 |
| ○ | 事業所への巡回訪問等を行うことにより、支援ニーズの早期把握、長期的な定着支援に努める。 |
| 精神障害者の雇用の段階に応じた体系的支援プログラム |
主任障害者職業カウンセラー(精神障害者担当)が統括
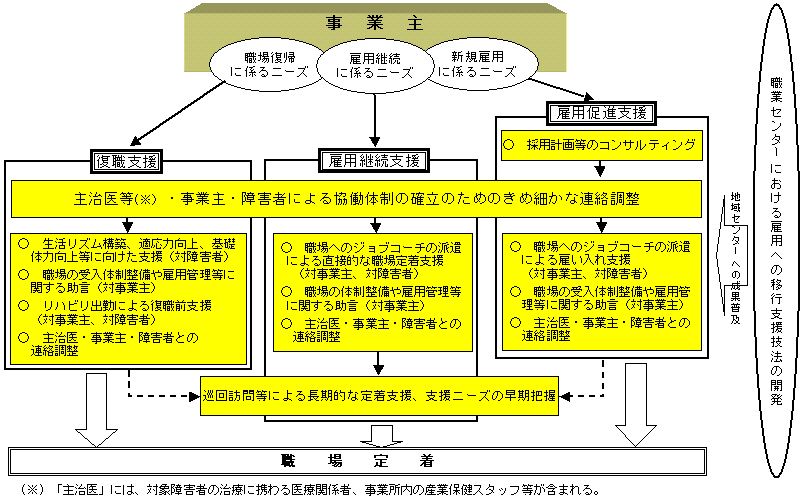
|
障害者の雇用を促進するためには、職業リハビリテーション等の障害者・事業主に対する直接的な支援に加え、事業主が障害者を雇用しやすくするための環境整備が不可欠である。特に、精神障害者については、他障害に比べて雇用に不慣れな事業主が多いことから、雇用に関するノウハウ・情報の普及を図るとともに、精神障害者に適した就業形態の導入をはじめとする精神障害者の職場定着・復職に向けた取り組みを事業主が自発的に行うことを支援していくことが必要である。 そこで、「精神障害者雇用環境整備事業」を創設し、以下のような支援を実施する。 |
| 1. | 事業主向け相談窓口の設置 精神障害者の新規雇用・復職・雇用継続に対する各種支援策に関する基礎的な情報を提供するとともに、精神障害者の障害特性に関する情報や雇用管理ノウハウを有する外部の専門機関(地域障害者職業センター、地域産業保健センター、精神保健福祉センター等)への適切な橋渡しを行うため、事業主向け相談窓口を、企業とのネットワークを有する事業主団体に委託して設置する。 |
| 2. | プライバシーに配慮した精神障害者の把握確認ガイドライン検討委員会の設置 精神障害者に雇用率を適用することとした場合に必要となる障害者雇用状況報告提出のために企業が従業員の中の精神障害者を把握する際、プライバシー面等において不適切な対応や混乱が生じるおそれがあることから、不適切な掘り起こしを避けるためのガイドラインを作成し周知を図る。 |
| 3. | 精神障害者職場適応コーディネーター(仮称)の配置助成(納付金事業) 精神障害者の職場定着及び復職にあたり、本人、外部の医療機関、企業内産業保健スタッフ、職リハ機関、職場の上司等との連絡調整を行いながら支援を行うスタッフを企業が配置する場合、その費用の一部を助成する制度を創設する。 |
| 4. | グループ就労に対する支援(納付金事業) 常用雇用への移行段階として、企業において数人の精神障害者のグループが指導員の指導を受けながら就労する形態をとる場合に支援を行う。 |
| 5. | 週15時間労働からの支援(納付金事業) 週15時間以上勤務からの精神障害者の雇用支援を強化する。 |