| <前回までの議論(第11回、第12回> 加工食品の一括表示について、 〇表示の様式を厳密に規定している現行の規定は見直すべき。(様式の自由化) 〇ただし、一括して表示するという考え方は維持すべき。 〇表示方法について、商品特性に応じ、事業者が創意工夫を図ることができるようにすべき。(ITの活用の可能性なども含む。) |
| 資料2 |
| <前回までの議論(第11回、第12回> 加工食品の一括表示について、 〇表示の様式を厳密に規定している現行の規定は見直すべき。(様式の自由化) 〇ただし、一括して表示するという考え方は維持すべき。 〇表示方法について、商品特性に応じ、事業者が創意工夫を図ることができるようにすべき。(ITの活用の可能性なども含む。) |
一括表示方法のあり方について、主な表示項目ごとに、以下の観点を参考に検討。
|
| ○一括表示の様式に従い、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者等の表示が必要。 |
現行の一括表示様式
※このほか、食品によっては固形量、内容総量、原産国名、原料原産地名等が必要。 |
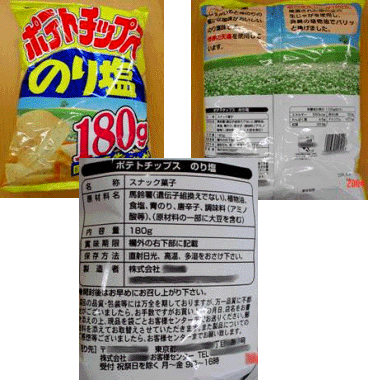 |
|
| ※ | これらの「名称」は、日本の表示規準上の「名称」と異なり、商品名でも構わない。 |
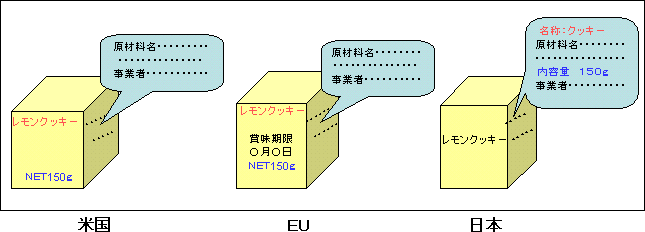
| ○一括表示の様式に従い、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者等の表示が必要。 |
|
| ○商品名から一般的名称が明らかな食品について、一括表示内の名称表示の必要性。 ○(2)の名称規制がある食品については、名称規制のあり方の検討の中で適切に対応する必要。 ※[名称規制については、「JAS制度のあり方検討会」において別途検討されており、7月1日に中間取りまとめが公表され、パブリックコメントを募集中。] |
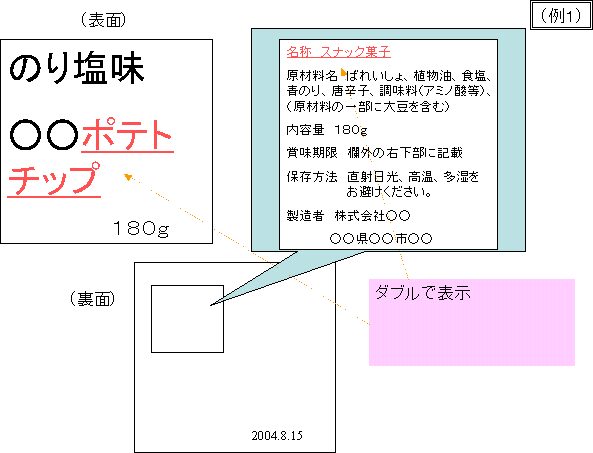
| ○一括表示に、単位を明記して記載。(計量法では、一括表示の規定はなし) |
|
| ○内容量について、見やすい表示箇所の検討。(一括表示内に表示する必要性) |
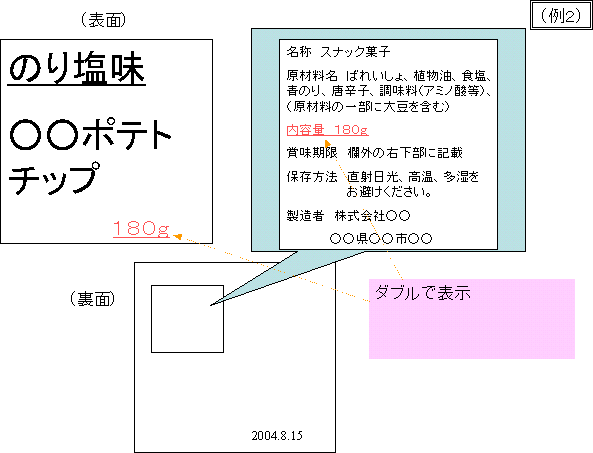
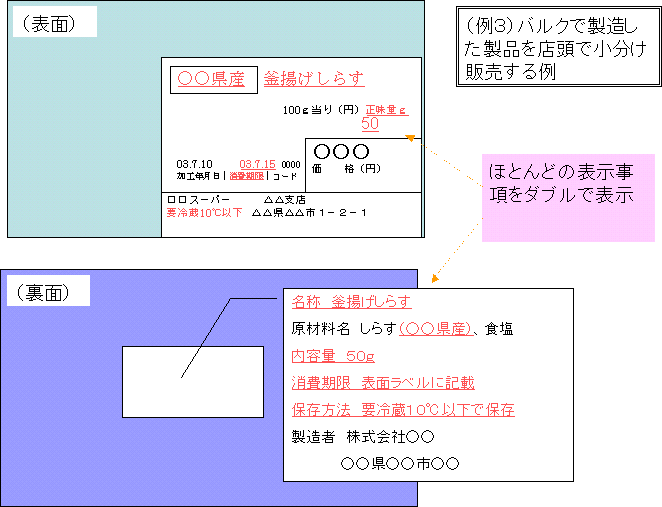
| ○一括表示に記載。ただし、一括表示に記載することが困難な場合は、賞味期限欄に記載箇所を表示すれば、一括表示外への記載が可能。 ○保存方法についても、賞味期限に近接して一括表示外への記載が可能。 |
| ○記載箇所を具体的に示していなかったり、印字のみであるために「どこに書いてあるかわかりにくい商品がある。」との指摘がある。 |
| ○記載箇所がわからなかったり、印字の意味が理解できないことのないよう、記載箇所等の明確化。 |
| ○一括表示に「製造業者等の氏名又は名称及び住所」を記載。 ○JAS法では、表示を行う者が製造業者→「製造者」、加工包装業者→「加工者」、販売業者→「販売者」、輸入品→「輸入者」と表示。 ○食衛法では、「製造所または加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名」とされ、「製造所」についてはあらかじめ厚生労働大臣に届け出れば製造所固有記号による記載が可能。 |
| ○「製造者」「加工者」等の用語の使い分けが複雑でわかりにくい。 ※[製造者の表示については、製造所固有記号の検討の中で、別途検討] |
| ○一括表示に、使用した原材料を重量割合の多い順に、食品添加物以外の原材料と食品添加物に分けて記載。 ○アレルギー表示、原料原産地表示、遺伝子組換え表示についても、原材料表示の一部として表示。 |
| ○原材料表示が充実されつつある中、わかりやすい表示を実現するために工夫は可能か。 ○アレルギー表示以外の強調表示を認めるべきか。 |