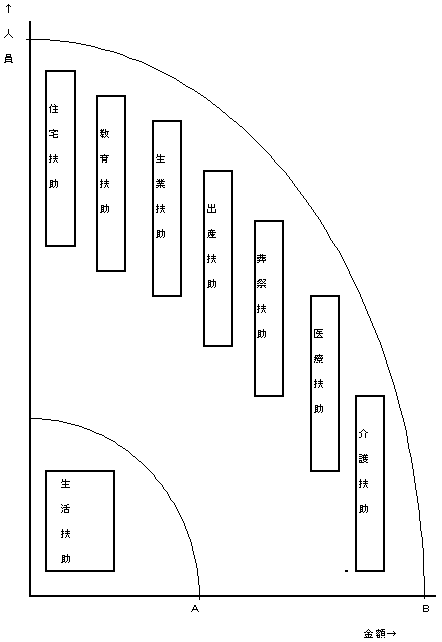
| A 生活扶助要否判定基準 (資力調査) |
B その他各種扶助要否判定基準 (所得調査ないし資力調査の緩和) |
【岡部委員提出資料】 |
|
||||||
| ○ | 現在の制度では、一時期的に生活困窮に陥った(要保護状態にある)人でその状況が解消されれば直ちに経済的な自立が図られる可能性が高い場合でも,利用しうる資産のすべてを活用(処分)したうえでなければ生活保護の適用を受けることができません。その結果,利用者自身の生活基盤が十分でないため生活再建に結びつかない、あるいは自立意欲の低下を招いたりと保護からの脱却が難しくなることが少なくありません。 |
| ○ | そこで一時的な生活困窮状態が解消されれば,以前の自立した生活状態に復帰可能と判断される場合は,生活再建に寄与すると思われる一定範囲内の資産の保有を認め生活保護を適用していくことが望ましいと考えます。 |
| ○ | また生活困窮状態に陥る前の要保護のおそれのある低所得層に対して予防的な対応をすることが、生活保護受給の長期化を防ぐことにつながってくると考えます。 |
| ○ | そこで、生活保護制度の受給資格を、要保護のおそれのある低所得層と要保護状態にある貧困層とに分け、前者を所得調査(ないし資力調査の緩和)を条件とする生活扶助を除く各種扶助の要否判定基準、後者を資力調査を条件とする生活扶助要否判定基準という大きくは2つの基準で生活保護制度をとらえていく必要があると考えます。その結果、生活扶助+その他各種扶助、その他各種扶助の併給、その他各種扶助単給の3つの保護受給パターンが考えられます。生活扶助基準は併給基準、それ以外は単給基準という方法をとります(図表参照)。 |
| ○ | また受給期間の観点から各種扶助を、次のように組み替えていくことも考えられます生活扶助を初めとする各扶助に含まれる「一時扶助」及び「生業扶助」「出産扶助」「葬祭扶助」をすべて「臨時的扶助」として一本化し、経常的扶助(生活扶助、住宅扶助教育扶助、医療扶助、介護扶助)と臨時的扶助の2つの柱からなる制度に組み替える方向も考えられます。 |
| ○ | さらには医療扶助・介護扶助については、将来的には生活保護制度から独立させ、別個の制度とすることが望ましいと考えます。これは、生活保護制度を所得保障+対人サービスに純化の方向で考えることでもあります。 |
| ○ | 労働関係部局との連携を強化し、生活保護受給者を対象としたトライアル雇用制度の創設や、職業訓練校の生活保護受給者枠の創設など、労働行政の中で生活保護受給者への支援策を確立していく方向で考えていくことが必要です。また、自治体による無料職業紹介事業を積極的に活用していくことも方策の一つと考えます。 |
| ○ | 「就労支援員」の活動は効果が上がっていることから福祉事務所に標準配置する方向で考えるとともに、それを推進していくための財政的手当を国がなんらかの形で行うことも必要と考えます。 |
| ○ | 「アセスメント」→「プランの作成」→「具体的な支援の実施」からなる体系的な就労支援プログラムを構築し、プログラムに基づく具体的な支援を実施する方向で考える必要があります。 |
| ○ | 保護廃止後の不安を解消し、自立への意欲を向上させるために保護の廃止時に一定の要件を満たす利用者に対し支給する「自立支度金」を創設していくなど方策を講じる必要があります。 |
| ○ | 現行制度では、稼働能力の活用が可能な利用者に対しては,その可能な範囲における活用を義務づけていますが,傷病等により稼働能力がない利用者や,稼働能力はあるものの現在の社会経済情勢の中で実際に稼働能力を活用することが困難な利用者については,特に能力活用を義務づけをしていません。 その結果,利用者の中には長期間にわたり不就労状態が続き,自立意欲そのものの低下や社会との関われが希薄となっている利用者もおり、また,不就労者に対する市民感情の問題も生じています。 |
| ○ | 稼働能力の活用が困難な利用者に対しては,社会参加を促進する観点からも,能力の範囲に応じて,ボランティア活動や福祉的就労を福祉事務所が支援するとともに,利用者自身も努力するなど,社会的側面における自立の助長の考え方を導入することが必要です。 |
| ○ | 生活保護ワーカーの配置が社会福祉法による標準数(都市部80対1、郡部65対1)を下回る自体体が増加傾向にあります。生活保護を適正運営するためには,少なくとも標準数の配置は必要不可欠です。 |
| ○ | そこで、生活保護ワーカーの配置基準を法定化したうえで,これが遵守できるような仕組みを構築する必要があります。また,自治体の自助努力で基準を上回る体制を整備し,適正運営に努力している自治体に対しては,財政支援を実施するなど,自治体のインセンティブが促進されるような仕組みを構築する必要があります。 |
| ○ | 生活保護の適正運営を維持・向上するためには,生活保護関係職員の資質向上は欠かせません。しかし、全国的には、生活保護ワーカーや査察指導員の経験年数・資格保有率等が低下傾向にあります。 |
| ○ | 国において,専門家による生活保護ワーカー及び査察指導員を対象とした実務研修をはじめとした資質向上策について検討し,効果的実施プログラムを確立する必要があります。また,自治体の努力により,生活保護関係職員の資質向上に努め,実施水準が高い自治体に対しては,それに応じた財政支援を実施するなど,自治体のインセンティブが促進されるような仕組みを構築する必要があります。 |
| ○ | 他法他施策が多様化・複雑化する中で,研修等の充実をもっても,生活保護ワーカーがすべての知識を習得するのは,困難な状況にあります。そこで他法他施策の活用については,専門家の配置や組織として専門性を確立すること等対応していくことが必要と考えます。 |
| ○ | ナショナルミニマムとしての生活保護制度を適正に運営するためには、現行の国庫負担割合を堅持する必要があります。 |
| ○ 生活保護の基準等に関する定期的検証の場を設けることが必要と考えます。 |
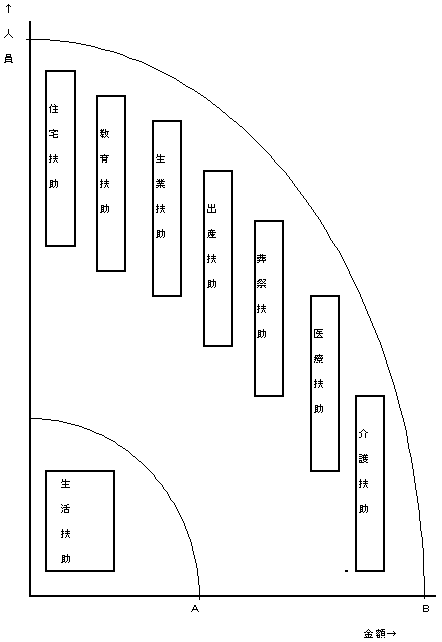
|