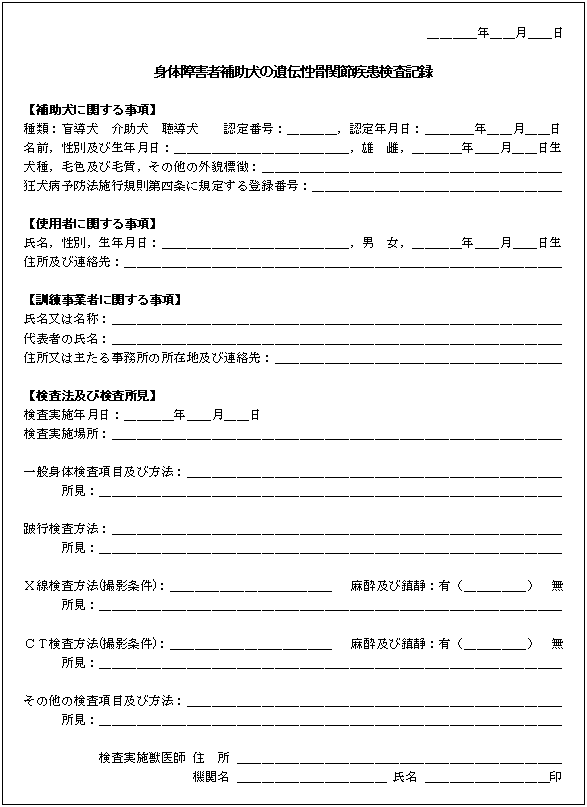
| 担当 | 竹垣 守(内3072) 上村 勉(内3075) |
1.はじめに
昨今,社会のニーズとともに,身体障害者の積極的な社会参加を促進すべく,種々の検討が行われている。身体障害者補助犬(盲導犬,介助犬,聴導犬)の活用もその一つであり,平成14年5月には,“身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り,身体障害者の自立および社会参加の促進に寄与することを目的”とし,身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)が制定されている。
身体障害者補助犬を有効に活用するためには,まず,“補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに”,“各身体障害者に必要とされる補助を的確に把握し,その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより,良質な身体障害者補助犬を育成”することが必要である(同法第3条)。
また,身体障害者補助犬法では,国等の管理する施設,公共交通機関のほか,不特定多数の者が利用する施設への補助犬の同伴を認めている(同法第7−9条)。これにともない,補助犬の使用者には,“補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない”こと(同法第13条),さらに,その補助犬の“体を清潔に保つとともに,予防接種及び検診を受けさせることにより,公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない”ことが求められている(同法第22条)。
身体障害者補助犬に求められる上記の要求を満たすために,補助犬の育成に関して種々の検討が行われており(たとえば『介助犬に関する検討会報告書』,『介助犬の訓練基準に関する検討会報告書』,『聴導犬の訓練基準に関する検討会報告書』等を参照),一方,公衆衛生上の危害発生防止に関しても研究が行われている(『「身体障害者補助犬の衛生確保のためのガイドライン」作成研究 研究報告書』)。
こうした諸々の検討を通じて,身体障害者補助犬の育成および使用については,おおよその統一的見解が確立されているといえる。しかし,身体障害者補助犬における遺伝性疾患の問題については,「介助犬に関する検討会」,「介助犬の訓練基準に関する検討会」,「聴導犬の訓練基準に関する検討会」等においてその重要性が指摘されつつも,いまだ適切な対応が行われていないのが現状である。身体障害者補助犬法第3条に記されているとおり,“良質な身体障害者補助犬を育成”することはこの法律が求めるところであり,このためには遺伝性疾患を有する犬を補助犬の候補に選択せず,また,育成せず,そして供給しないことが重要である。
疾患に罹患した身体障害者補助犬を使用することは,とくにそれが犬の運動器や視覚等に障害が発生している場合,使用者の安全を確保するために避けるべきであり,また,遺伝的にこうした障害が発生する可能性がある犬は,将来の危険性を考慮し,補助犬としての育成から除外しなければならない。加えて,疾患に罹患した状態での補助犬としての使用は,犬にとっても大きなストレスを生じ,寿命等にも影響が及んでいることは十分に推察されるところである。
こうした状況のもと,良質な身体障害者補助犬を確保し,育成するとの観点から,「身体障害者補助犬の遺伝性疾患に関する検討会」を平成15年3月に発足させ,考慮すべき補助犬の遺伝性疾患の選定とそれらの診断適期,診断法等について検討を行うこととした。
本検討会は,これまで10回にわたって議論を重ね,今般,結論を得たのでここに報告する。
2.身体障害者補助犬における遺伝性疾患の重要性
遺伝性疾患あるいは遺伝病とは,遺伝にもとづく原因によって発症する疾患,すなわち遺伝子上に発症原因がプログラムされている疾患である。素因をも含めればきわめて多くの疾患が遺伝性ということができるが,遺伝的素因を除き,直接的な原因が遺伝的であるものに限っても,多種の動物において多様な遺伝性疾患が知られており,今後の研究の進展によっては,さらに多くの疾患が遺伝的であることが証明される可能性がある。
遺伝性疾患は遺伝にもとづいて親から子へと伝達されるものであり,その発症は,当然,その原因遺伝子を有する生物集団において高頻度に認められることになる。また,家畜などのように限定された範囲内で繁殖が行われる場合には,とくにある特定の個体群に高頻度に発生することが少なくない。また,多くの品種が作出されている犬などの飼育動物では,品種によって特異的に高頻度に発生が認められる遺伝性疾患があることは周知の事実である。
身体障害者補助犬も例外ではなく,遺伝性疾患を有する個体が使用されていることがある。身体障害者補助犬が何らかの疾病を発症すると,その機能が十分に果たせなくなることは明らかであり,これによってその使用者である身体障害者自身に不都合が生じ,場合によって危険が発生することも予期される。したがって,身体障害者補助犬は,常に健康に保つことがきわめて重要である。遺伝性以外の一般的な疾病に関しては,適切な日常管理を行うことにより,できる限り発症を予防することが推奨されるが,遺伝性疾患に関しては,育成の段階,あるいはそれ以前の段階で適正に対応し,良質な犬を身体障害者補助犬として提供することにより,使用開始後の発症を予防することが可能である。
この点において,身体障害者補助犬における遺伝性疾患の発症を予防する意義はきわめて大きく,そのための適切な対応を行うことが重要であると考えられる。
3.検討の対象とすべき遺伝性疾患の選択
前項に述べたように,他の動物種と同様に,犬にも多種の遺伝性疾患が存在する。理想的には,身体障害者補助犬からそれらの遺伝性疾患のすべてを除外すべきであろう。しかし,現実にはそれは不可能であり,また,身体障害者補助犬として良好に使用できる犬の相当数を確保するためにも,本検討会では,補助犬としての実際の使用に際してとくに障害を誘発するもののみを検討の対象とすることとした。ただし,ここで検討する遺伝性疾患以外についても,可能な限り身体障害者補助犬から除去されていくことが望ましいのはいうまでもない。
本検討会において検討の対象とする遺伝性疾患は,出生時に容易に診断が可能な疾病は割愛し,身体障害者補助犬としての育成期あるいはそれ以降に発症するものとした。また,その選択に際しては,主に以下の二つの点を考慮した。すなわち,第一に,発症時に身体障害者補助犬としての機能が失われ,その使用者に危険が生じる可能性がある疾病であること,第二に,身体障害者補助犬として使用されることが多いレトリバー等の大型犬種に多発する疾病であることである。
以上の観点から種々の検討を行った結果,身体障害者補助犬の遺伝性疾患として重要であるのは,骨関節疾患および眼疾患であるとの結論に達した。前者は犬の運動能力の著しい低下をもたらすことにより,また,後者は犬の視覚の低下あるいは消失をもたらすことにより,犬に苦痛を与えるばかりでなく,身体障害者補助犬としての機能を著しく低下させ,使用者の安全にも危惧を生じさせるものである。
とくに,骨関節疾患については,遺伝的背景が明確な疾病として股関節形成異常,また遺伝的原因が推定されている疾病として肘関節形成異常が重要であり,一方,眼疾患については,視覚が完全に消失する白内障と網膜症が重要であると結論し,以下,これらの疾病の診断適期および診断法等について検討を行った。
なお,骨関節疾患として骨軟骨症,眼疾患として悪性ブドウ膜炎などにも遺伝的素因の存在が示唆されているが,これらについてはいまだ十分な知見が蓄積されているとはいえず,ここでは注意を喚起するにとどめることにした。
4.遺伝性疾患の診断のための検査の適期
身体障害者補助犬の遺伝性疾患の診断にあたり,確定診断ができる限り早期に実施されることが望まれる。遺伝性疾患の早期の確定診断が行えれば,当該犬を育成から除外し,補助犬育成のための労力および費用が無効となるのを防止することが可能となる。また,当該犬に対して,身体障害者補助犬としての使用による苦痛を与えることなく,不必要なストレスが生じることを防止することもできるであろう。
このためには,身体障害者補助犬の遺伝性疾患の診断は,補助犬の候補として選択される以前,あるいは補助犬としての訓練が開始される以前に完全に実施できることが望ましい。しかしながら,現状において,これは非常に困難あるいは不可能であり,ある程度の月齢,場合によっては年齢に達した以降でなければ,診断が行えない例があることは事実である。
そのため,本検討会においては,検討の対象とした各種の疾患について,ほぼ確実に診断が行えることを前提に,また,身体障害者補助犬としての育成の過程も考慮し,できる限り早期の検査を実施するとともに,必要に応じて検査を反復して行うことを提言する。なお,将来,遺伝子診断等の技術が完全に確立されるなど,診断技術が向上した際には,現状の診断適期が変更されることを期待したい。
(1)遺伝性骨関節疾患の診断適期
骨関節疾患として股関節形成異常および肘関節形成異常を対象とし,それらの発症時期等を考慮のうえ,診断の適期に関する種々の検討を行った。その結果,これらの骨関節疾患については,1歳未満において何らかの症状が認められた場合には,その時点においてただちに検査を実施し,症状が認められない例については,1歳〜1歳6か月齢のときに検査を行うことを推奨する。また,この1歳〜1歳6か月齢時の検査で異常が認められなかった例であっても,それ以降に症状が発現したときには,すみやかに検査を行うべきである。
なお,上記の1歳〜1歳6か月齢は,盲導犬と介助犬の場合,訓練所において訓練が開始される時期にほぼ一致しており,育成の面からも検査を行いやすい時期であると考える。一方,聴導犬では,様々な方法で育成が行われ,育成の時期を一概に規定することはできないが,1歳ないし1歳6か月齢あるいはそれ以前に育成が開始されているのであれば,この時期における検査を実施し,これ以降に育成が開始される例では,その時点で検査を行うものとする。
(2)遺伝性眼疾患の診断適期
眼疾患として白内障および網膜症を検討の対象とし,それらの発症時期等を考慮のうえ議論を重ねた結果,これらの眼疾患については,1回目の検査を2〜3か月齢,2回目の検査を1歳〜1歳6か月齢,3回目の検査を3歳齢のときに行い,これ以降は,可能な限り1年に1回の検査を実施することを推奨する。
なお,ここで,2〜3か月齢は,初回のワクチン接種時に相当し,また,1歳〜1歳6か月齢は,上記のとおり,盲導犬と介助犬の場合,訓練所において訓練が開始される時期にほぼ一致するものである。また,聴導犬の場合の検査については,上記の骨関節疾患の診断適期と同様に考える。
2〜3か月齢時の検査では,先天性疾患を含めてすべての眼疾患の有無について検討し,また,1歳〜1歳6か月齢時には,白内障と網膜症を発症する時期となることから,とくにこれらの疾病について精査する。また,3歳齢以降の検査は,成犬となってから発症する例を診断するために必要である。
5.遺伝性骨関節疾患とその診断
(1)遺伝性骨関節疾患の検査法の概要
股関節形成異常,肘関節形成異常ともに,触診を含む一般身体検査を実施したうえ,跛行検査,さらに画像診断を実施することにより診断する。
画像診断の検査法としては,X線検査を主とする。また,肘関節形成異常の一種である内側鉤状突起離断の診断には,CT検査も有用である。
(2)股関節形成異常とその診断
股関節形成異常(あるいは股関節形成不全,股関節異形成)は,徐々に変形性関節症(骨関節症)が進行し、様々な程度の歩行障害を生じる疾病である。
本症は,大型犬に多く発生し,発生率は犬種によって異なるが,およそ10〜50%程度と推測されている。
本症の発生要因としては,関節自体のゆるみと発育期における軟骨内骨化異常が考えられ,ゆるみの原因としてコラーゲンの形成異常が示唆されている。また,発育期の過剰栄養が大きな要因になっていることも報告され,発育期の飼育環境が本症の発症あるいは症状の進行に寄与することが推察されている。遺伝的背景については積極的に研究されているが,多因子であることが推測されているにとどまり,決定的な因子の解明には至っていない。
本症の診断にはX線検査が広く行われている。その方法には数種が開発されており,それぞれに利点と欠点が認められる。このうち,世界的にもっとも広く実施されている方法は,アメリカ合衆国のOrthopedic Foundation for Animals(OFA)が提唱した方法であろう。本法は,後肢を進展位で撮影するもので,特別な器具を必要とせず、容易に実施できるという利点を有する。しかし,1歳前後あるいはそれよりも若齢の犬においては,その確実性がやや低いという問題がある。
これに対して,最近開発されたPenn-Hip法は,より早期に,より信頼性の高い診断が可能である。ただし,この方法を用いるには,本法の特許を有する企業の用意する特別な器具が必要であり,さらにまた,同企業の講習を受けることが義務づけられている。したがって,現状においては,本邦において身体障害者補助犬の遺伝性疾患の診断法として推奨するには困難がともなうといわざるをえない。
以上の諸点を考慮した結果,本検討会では,股関節形成異常の診断法として,OFAが提唱した方法を採用することを推奨する。ただし,今後の状況によっては,再検討が必要となることもあろう(附1.股関節形成異常の診断)。
(3)肘関節形成異常とその診断
肘関節形成異常という名称は,elbow dysplasiaに由来し,以前は肘突起癒合不全を示すことが多かった。しかし,最近,この疾病名に関して様々な議論が行われ,現在では肘突起癒合不全と肘関節離断性骨軟骨炎(症),内側鉤状突起離断の三つの疾患を総称するようになっている。
肘関節形成異常も,股関節形成異常と同じく,変形性関節症を発生し,様々な程度の跛行を生ずる。
また,好発犬種が大型犬であることも,股関節形成異常と同様である。発生頻度は犬種により異なる。OFAの統計によると,肘突起癒合不全の発生率は,犬種により10〜45%にわたり,レトリバーでは11〜12%とされている。しかし,この値は,OFAに送付されたX線写真をもとにして求めたものであり,必ずしもすべての犬における発生状況を正確に反映しているとは限らない。なお,他の二つの疾患については,発生率に関する大規模な調査の報告はないようである。
肘突起癒合不全と肘関節離断性骨軟骨炎,内側鉤状突起離断の原因は必ずしも同一ではない。遺伝的背景については,肘関節離断性骨軟骨炎は遺伝性であることが推察されている。また,肘突起癒合不全は,シェパードに多発することから何らかの遺伝性が推定されている。今後の研究の進展により,遺伝因子が確認される可能性も高いと考えられる。
肘関節形成異常の診断も,上記の股関節形成異常と同様に,X線検査所見にもとづいて実施する。なお,内側鉤状突起離断に関しては,CT検査も有力な診断法となる(附2.肘関節形成異常の診断)。
(4)骨関節疾患の検査記録および診断書
骨関節疾患に関する以上の検査および診断の終了後,それを証するため,検査ならびに診断を実施した獣医師は,骨関節疾患検査記録および診断書を作成し,検査および診断の依頼者に提出する。
検査記録には,対象である犬の同定に関する記載のほか,実施した検査の方法,それにより得られた知見等を記載する。また,診断書には,犬の同定に関する記載ならびに診断,補助犬としての使用に係る総合評価等を記載する(附3.身体障害者補助犬の遺伝性骨関節疾患検査記録(様式)および附4.身体障害者補助犬の遺伝性骨関節疾患診断書(様式))。
6.遺伝性眼疾患とその診断
(1)遺伝性眼疾患の検査法の概要
本検討会では,白内障および網膜症を重要な遺伝性疾患として取り上げたが,これらの診断を行うにあたり,この二つの疾患のみを対象とすることはなく,当然,他の眼疾患の存在についても併せて検査を実施することが必要である。
検査法としては,広汎照明法により眼の一般状態を検査した後,眼圧測定,細隙灯顕微鏡による検査,倒像眼底検査,直像眼底検査,隅角検査を実施し,さらに可能な場合には網膜電図を記録する。
なお,生後2〜3か月齢時に実施する1回目の検査においては,上記の各種検査のうち,直像眼底検査と隅角検査は省略してもよいこととする。直像眼底検査は精査法であるため,スクリーニング検査としての性格が強い1回目の検査では必ずしも必要ではなく,また,隅角検査は,隅角鏡のサイズが幼犬への使用に適さないことが多いためである。
(2)白内障とその診断
白内障は,水晶体に白濁を生ずる眼疾患である。
白内障には様々な原因が存在するが,犬の白内障の原因としてもっとも多く認められるのは遺伝的なものであろう。
遺伝性の白内障は,先天的に生じ,出生時にすでに症状が認められることもあるが,出生後に発症する例も多い。また,犬種によっても,発生率や主たる発症の時期が異なっている。身体障害者補助犬として多用されるレトリバーは,遺伝性白内障が頻発すると一般に考えられており,1歳未満から1歳6か月齢時に症状を発することが多い。
身体障害者補助犬の白内障の診断に際しては,症状が発現した時期を考慮のうえ,外傷性白内障,炎症に続発する白内障,栄養欠乏性白内障,中毒性白内障,糖尿病性白内障などとの鑑別診断を実施の後,遺伝性白内障であることを確認する。なお,疑わしい例については6か月後に再検査を実施する(附5.白内障の診断)。
(3)網膜症とその診断
網膜の疾患のうち,進行性網膜萎縮等の遺伝性の網膜症は,しばしば犬に発生し,とくに,身体障害者補助犬として多数が使用されているレトリバーに多発することが知られている。
進行性網膜萎縮は,視細胞は正常に発生するが,その後,視細胞内に存在する光受容器に関連する蛋白質が遺伝的に異常をきたすことにより発症する。病変は,視細胞の桿体細胞の変性から始まり,次いで錐体細胞が変性を起こし,最終的には失明にいたる。本疾病は,数か月から数年の経過をとり,緩徐に進行するのが特徴である。
網膜症の診断は,主に眼底検査,すなわち倒像眼底検査,直像眼底検査により実施し(スクリーニング検査としての性格が強い生後2〜3か月齢時の検査では直像眼底検査は省略してもよい),タペタム層と非タペタム層,血管,視神経乳頭に出現する病変像にもとづいて診断を行う。また,網膜電図を記録することができれば,さらに診断は確実となる。なお,一部には本症の遺伝子診断が開始されたが,いまだその診断の確実性は保証されているとはいえない状況であり,現段階では遺伝子検査成績は確定診断の根拠とはしないものとする(附6.網膜症の診断)。
(4)眼疾患の検査記録および診断書
眼疾患に関する以上の検査および診断の終了後,それを証するため,検査ならびに診断を実施した獣医師は,眼疾患検査記録および診断書を作成し,検査および診断の依頼者に提出する。
検査記録には,対象である犬の同定に関する記載のほか,実施した検査の方法,それにより得られた知見等を記載するものとする。また,診断書には,犬の同定に関する記載ならびに診断,補助犬としての使用に係る総合評価等を記載する(附7.身体障害者補助犬の遺伝性眼疾患検査記録(様式)および附8.身体障害者補助犬の遺伝性眼疾患診断書(様式))。
7.遺伝性疾患の診断体制のあり方に関する提言
身体障害者補助犬がその機能を十分に発揮し,また,使用者の安全に危惧を生じさせないためには,犬が健康であることが必要である。しかし,身体障害者補助犬として用いられることが多いレトリバーには遺伝性疾患の発生が少なくないことは周知の事実である。この対策を講ずることを目的として,身体障害者補助犬法の制定に際し,「現在,身体障害者補助犬に多く使用されている犬種には,遺伝性疾患が少なくないことから,その選定には格段の配慮が求められる。このため,早急に厚生労働省内に専門委員会を設置し,補助犬の選定と健康管理に関する指針の策定並びに優良補助犬の確保の対策について検討を進めること」との同法案に対する附帯決議が行われている。
本検討会はこの附帯決議にもとづいて設けられたものであり,身体障害者補助犬法の施行にあたり優良な補助犬を供給する一助とすべく種々の検討を行った結果,身体障害者補助犬に認められる遺伝性疾患として股関節形成異常および肘関節形成異常,白内障,網膜症が重要であると結論し,その診断適期ならびに診断法等に関する指針を提示した。
本検討会において推奨した検査適期に適正な検査が行われるためには,身体障害者補助犬の育成に関わる諸機関ならびに諸団体の理解と協力が必要であり,今後,行政機関等の適切な対応が行われることを希望する。
また,身体障害者補助犬の遺伝性疾患の検査ならびに診断に従事する獣医師に関しては,骨関節疾患では,画像検査を行う獣医師は整形外科領域において相当の知識と経験を有することが必要であり,眼疾患についても,検査と診断を行う獣医師は眼科領域における相当の知識と経験を有する必要がある。獣医師の側からも,身体障害者補助犬の遺伝性疾患の制圧に向けての積極的な取り組みがなされることを期待する。
さらに将来的には,各々の遺伝性疾患の診断を円滑に遂行するため,骨関節疾患および眼科疾患のそれぞれの専門家等から構成される判定委員会の設置について是非とも考慮すべきであろう。
加えて,身体障害者補助犬として育成することを目的として犬の繁殖を行う場合には,遺伝性疾患を有していない犬を繁殖に供することが重要である。疾患の遺伝子を欠く犬を用いて繁殖を行うことにより,その個体群における遺伝性疾患の発生頻度は低下することになる。身体障害者補助犬から遺伝性疾患を排除するためには,繁殖の面からも適正な対応が求められる。すなわち,育成を行う犬に限らず,繁殖に供する犬についても,可能な限り遺伝性疾患の検査を実施し,疾病の存在が確認された場合には繁殖に用いないようにする配慮がなされるべきである。良質な遺伝子を有する犬を親犬として,身体障害者補助犬の計画的な繁殖が行われることを望みたい。
犬に発生する種々の疾病のうち,遺伝性の疾患については,早期に適切な診断が行われれば,身体障害者補助犬として使用される以前に高い確率でそれを排除することが可能である。身体障害者補助犬の育成に関わる諸機関ならびに諸団体と行政機関,さらに獣医師等は,相互の協力を通じ,遺伝性疾患を欠く優良な身体障害者補助犬を確保されるよう努め,身体障害者補助犬法の趣旨である身体障害者の自立および社会参加の推進に寄与されるよう望むものである。
【検査法】
(1)一般身体検査および跛行検査
犬が立ち上がるときの後躯の強さ,歩行時の後肢の動きなどを観察する。次いで,股関節の可動域,スムーズさを検査する。
さらに,鎮静下でオロトラニサインの有無を確認し,その状態でX線検査に移行する。
(2)X線検査
X線検査は,できる限り麻酔または鎮静処置を施したうえで実施することが望まれる。
X線検査にあたっては,両後肢を平行に進展させ,左右対称とし,第6腰椎から膝関節までを含めて撮影する。このとき,大腿骨は坐骨結節にかかり,また,閉鎖孔の形態は左右対称となる。寛骨臼の細部を観察する場合は,後肢を屈曲させ,いわゆるカエル足位で撮影する。
【判定法】
X線所見は,OFAの基準に準拠して判定する。すなわち,寛骨臼と大腿骨頭のかみ合わせ,寛骨臼背側縁と大腿骨頭との重なり(acetabular supported area),ノルベルグアングル(正常値は105度以内),寛骨臼や骨頭の形状,その周囲における変形性関節症時に出現する異常(軟骨下骨の骨硬化,骨増生,モーガン線,変形等)の有無,その他の所見にもとづいて総合的に判定する。
判定結果は,「きわめて良好(excellent)」,「良好(good)」,「ほぼ良好(fair)」,「ボーダーライン(borderline)」,「軽度(mild)」,「中等度(moderate)」,「重度(severe)」の7段階に分類する。
このうち,「きわめて良好」,「良好」,「ほぼ良好」は,正常な関節である。
また,「ボーダーライン」は,寛骨臼と大腿骨頭との重なりが50%以下の例,あるいはX線写真が良好でないために判定が不能な例であり,その後に異常が発現する可能性があると考えられる症例である。
股関節形成異常と判定される例は,「軽度」,「中等度」,「重度」に分類される。「軽度」は,変形性関節症の変化がごくわずかなものであり,「中等度」と「重度」は,変形性関節症の異常が認められ,また,寛骨臼の平坦化,骨頭の変形がみられ、ときに亜脱臼ないし脱臼を呈するものである。
【判定の解釈】
上記の7段階の判定のうち,股関節形成異常と判定された例については,身体障害者補助犬としての使用について考慮する必要がある。ただし,股関節形成異常であっても,「軽度」との判定の場合は,当該犬の役割によっては,使用不可としなくてもよい例があると考えられる。この点については,今後,さらに議論の余地があろう。
また,「ボーダーライン」と判定された場合は,3か月後,あるいは可能であれば6〜8か月後に再度,検査を実施することが望ましい。
なお,本法は2歳齢以降に検査を実施した場合に十分な信頼性が確保されるものであり,1歳齢前後で検査を行った場合には,その信頼性は必ずしも確実とはいえないという問題を有する。1歳齢時に「きわめて良好」と判定された例では,2歳齢時に再度の検査を実施しても,100%の個体が再び正常と判定されたとの成績が得られているが,一方,1歳齢時に「良好」または「ほぼ良好」と判定された例では,2歳齢時にはそれぞれ97.9%と76.9%が正常と判定されるにとどまっている。すなわち,1歳齢時に検査を実施する場合,「きわめて良好」と判定された例以外は,その後に本症を発症する可能性を完全には否定できない点に留意すべきである。
【検査法】
(1)一般身体検査および跛行検査
前肢による歩様,負重時の頭や肩の動きを観察する。次いで,肘関節を触診し,腫脹,熱感等の有無を確認する。また,肘関節の可動域が狭くなっていないかなどの観察を行う。
(2)X線検査
基本的には,内外側方向と前後方向から撮影を行う。
肘突起癒合不全が疑われる場合,肘関節を大きく屈曲させて撮影すると観察が容易となる。
また,内側鉤状突起離断の場合は,この2方向に加え,前後方向の撮影を25度外側から投射する方向で行うと,離断した鉤状突起内側部が確認できることがある。
(3)CT検査
CT検査は,麻酔下で両前肢を平行に保定し,肘関節を横断する形で2mmスライス程度で撮影する。
【判定法】
以下の所見にもとづいて診断を実施する。
すなわち,肘突起癒合不全では,肘突起が尺骨から分離し,突起周囲に骨硬化および骨増生が認められる。
肘関節離断性骨軟骨炎では,上腕骨内側顆に骨欠損陰影が確認できることが多い。また,肘関節周囲の骨硬化、骨増生などの変形性関節症の症状が認められる。
内側鉤状突起離断では,鉤状突起の陰影が不明瞭であり,同時に肘関節の滑車面に沿って骨硬化像や骨増生が観察される。離断した鉤状突起の確認はしばしば困難であり,可能であればCT検査を実施することが望まれる。
【判定の解釈】
肘関節形成異常と診断された例については,原則として,身体障害者補助犬としての使用を考慮する必要がある。
ただし,これらの疾患は,手術等の治療を施すことにより,その後の変形性関節症の進行が遅延する可能性がある。すなわち,早期の診断ならびに治療が行われることにより,身体障害者補助犬として使用することが可能な例も生じると考えられる。
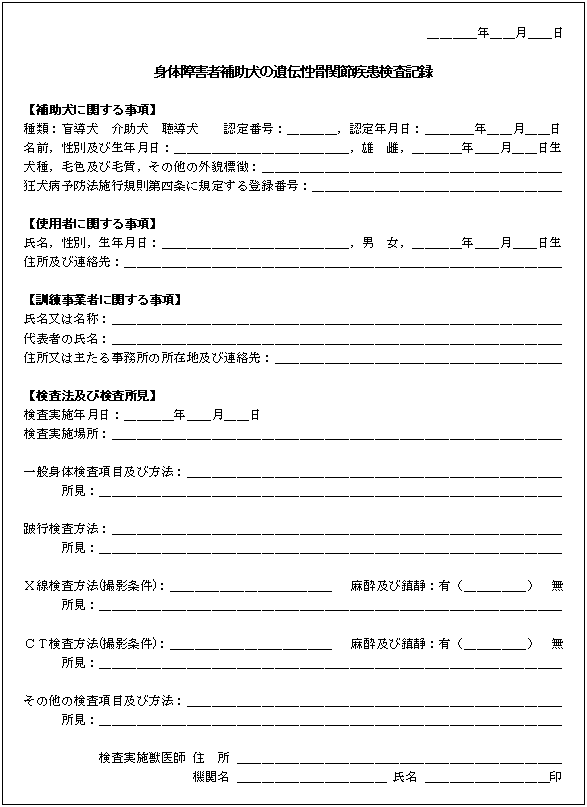
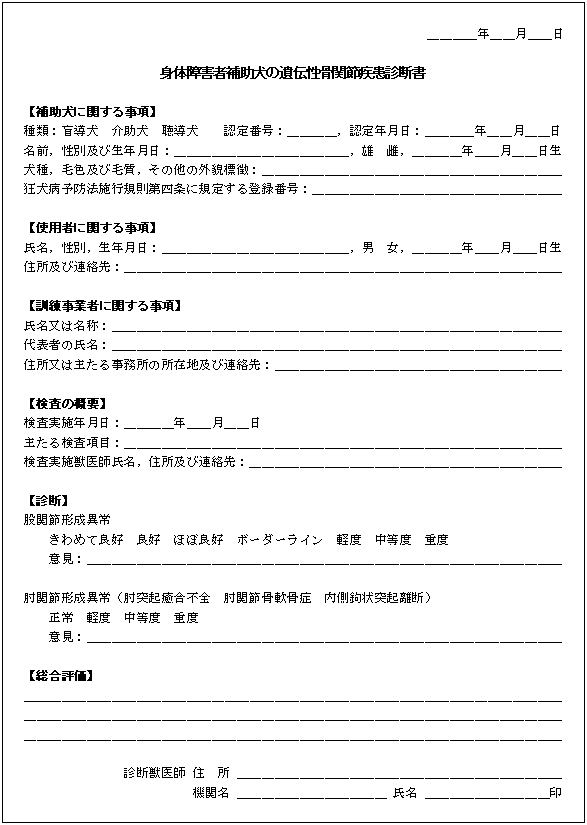
【検査法】
(1)稟告の聴取
視覚を評価するため,犬の飼育者等から当該動物の視覚に関連した日常行動に関する問診を実施する。その項目は,以下のとおりとする。
| ・ | 日常生活において物にぶつかることはないか?(一般的な視覚の判断材料) |
| ・ | 不慣れな場所ではどうか?(一般的な視覚の判断材料) |
| ・ | アイコンタクトはとれるか?(一般的な視覚の判断材料) |
| ・ | ボールなどを追うことはできるか?(動体に対する視覚の判断材料) |
| ・ | 遠くから呼んだときの反応はどうか?(遠方視覚の判断材料) |
| ・ | 段差を確認できるか?(至近視覚の判断材料) |
| ・ | 昼と夜で視覚に差異が生じないか?(錐体桿体機能にもとづく視覚の判断材料) |
| ・ | 対光反射試験(直接・共感反射) |
| ・ | 視覚検査(威嚇反射試験,綿球落下試験,迷路通過試験) |
| ・ | 前眼部の視診(眼瞼,睫毛,結膜,角膜) |
| ・ | 眼内の視診(前房,虹彩,水晶体) |
| ・ | 環境光下における検査 環境光(室内照明)のもとで細隙灯顕微鏡の光源を拡散光(diffuse)とし,6倍程度の拡大率で水晶体を観察する。 |
| ・ | 暗室内におけるスリット光による検査 暗室内において,細隙灯顕微鏡の光源をスリット光とし,これを角膜に対して40〜60度の角度から照射してプルキンエ・サンソン像による水晶体の光学切片を作成する。この状態でスリット光を左右に移動し,水晶体全体をスキャンして観察する。 |
| ・ | 暗室内におけるスリット光による徹照像検査 暗室内において,細隙灯顕微鏡の光源をスリット光とし,これを角膜中心部に向ける(0度に設定)ことにより網膜に照射する。このときの網膜からの反帰光を利用して水晶体を観察する。 |
【判定法】
白内障と診断された場合,以下のものを除いて,一般に遺伝性と判断する。
すなわち,外傷,炎症,代謝性疾患,栄養欠乏にともなう白内障として診断される根拠がある例,また,少数ではあるが,限局性であることが明白な白内障の例を除外し,これ以外の両側性あるいは片側性白内障,とくに皮質内白内障は遺伝性と考える。
なお,皮質内や水晶体極部等に生じたきわめて限局性の白内障で,肉眼でわずかに認知できる程度の例については,少なくとも6か月を経過した後に再検査を実施する。
【判定の解釈】
白内障と診断された例については,原則として,身体障害者補助犬としての使用を考慮する必要がある。
ただし,きわめて限局性の病変が認められるのみで,それが進行しない例においては,当該犬の視覚の状態にもよるが,身体障害者補助犬としての使用を継続することが可能な例もあると思われる。
【検査法】
(1)稟告の聴取
眼疾患の検査は同時に実施されるため,稟告の聴取は白内障の場合と共用である。
(2)散瞳前の眼検査
散瞳前の諸検査についても,白内障の項に記述したものと共用とする。
(3)眼底検査
眼底検査は,散瞳後,暗室において倒像鏡または直像鏡を用いて実施する。
基本的には,倒像鏡検査は眼底のスクリーニング検査であり,直像鏡検査は,スクリーニング検査で異常が認められた場合,その部位を精査するために行われる。
(4)網膜電図の測定
眼底検査のみでも網膜症の確定診断は可能であるが,網膜電図を測定すれば,診断はさらに確実なものとなる。
【判定法】
網膜症は,以下の所見にもとづいて診断する。
初期には,タペタム層と血管に主たる病変が認められる。タペタム層は,多くの桿体が存在する周辺部の反射がわずかに亢進する。また,血管は,とくに動脈の太さに変化が生じ,太い部分と細い部分が混在し,色調が薄くなる。さらに,血管の長さも短くなり,網膜の周辺部では血管が認められないことがある。
病態が進行した例では,タペタム層と非タペタム層,血管,視神経乳頭に病変が出現する。タペタム層は,この領域の全体で反射が亢進し,色調にも変化が認められる。一方,非タペタム層では,脱色素領域が確認される。血管は,動脈,静脈ともに,狭細化が著しく,消失することもある。視神経乳頭は,白色から暗色の色調を呈するようになる。
網膜電図では,フラッシュ光の刺激強度や暗順応時間,鎮静薬または麻酔薬の投与などの諸条件が検査成績の解釈に影響を及ぼすが,一般に,初期には電位の低下が認められ,進行例では電位が生じず,波形はフラットとなる。
【判定の解釈】
網膜症と診断された例については,身体障害者補助犬としての使用を避けるべきである。
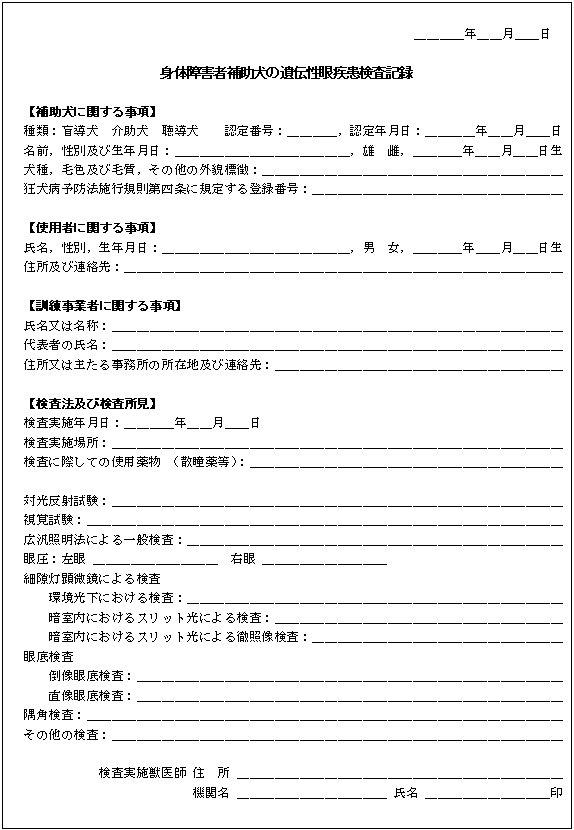
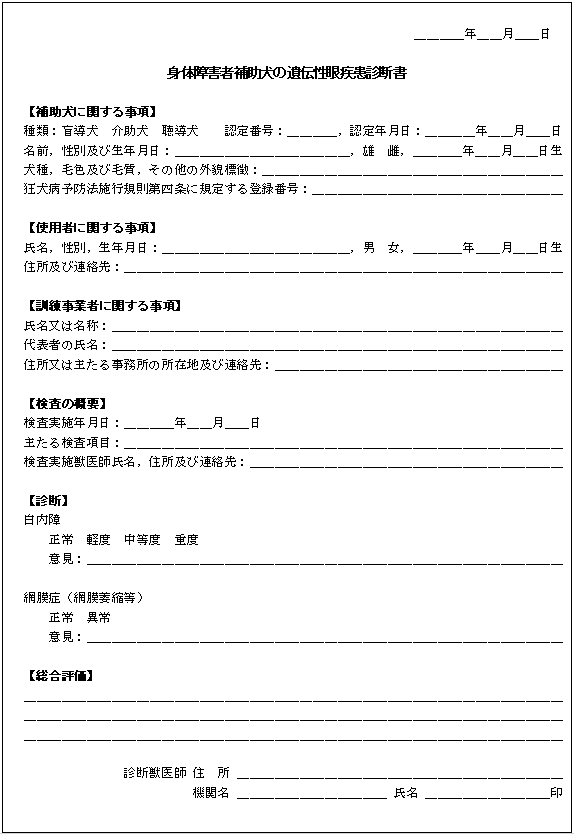
| 委員 | (敬称略・五十音順) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ○ 座長 | ||||||||||||||||||||||
| 協力員 | |||
|