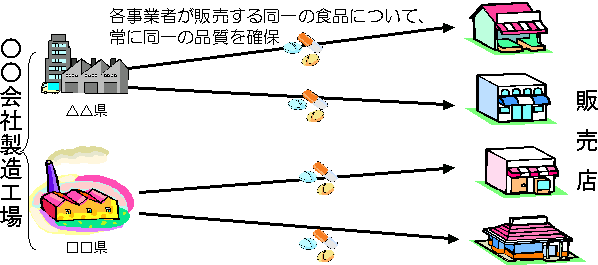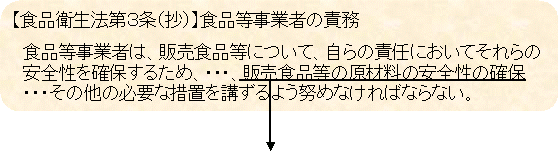| (1) |
食生活の乱れ等による健康に関する表示の重要性の高まり、
食品の健康の保持増進効果(食品機能)に対する国民のニーズの増大・多様化 |
| (2) |
多種多様な食品機能の研究開発の進展 |
| (3) |
健康と食に関する情報の氾濫 |
| (4) |
「健康食品」の利用増加と健康被害の発生 |
| (5) |
「食育」の必要の高まり |
| (6) |
消費者への情報提供の歪み |
|
|
今後、
| ◎ |
国民が様々な食品の 機能を十分に理解できるよう、正確で十分な情報 提供が行われること、 |
| ◎ |
あわせて、普及啓発を行うこと、 |
| ◎ |
安全性を一層確保す ること、 |
が必要。 |
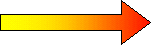 |
(1)表示内容の充実
| (1) |
「条件付き特定保健用食品(仮称)」の導入 |
| (2) |
規格基準型特定保健用食品の創設 |
| (3) |
疾病リスク低減表示の容認 |
| (4) |
特定保健用食品の審査基準の見直し |
(2)表示の適正化
| (1) |
「バランスのとれた食生活を心がけましょう」等の表示の義務づけ |
| (2) |
「ダイエット用食品」等における栄養機能食品の表示の禁止 |
| (3) |
栄養素名の表示の義務づけ |
| (4) |
栄養機能食品の対象外のビタミン、ミネラルの表示の適正化 |
(3)安全性の確保
| (1) |
錠剤、カプセル状食品に係る「適正製造規範(GMP)ガイドライン」の作成 |
| (2) |
錠剤、カプセル状食品の原材料に係る安全性ガイドラインの作成 |
(4)普及啓発等
行政・民間団体の行う普及啓発、データベース、アドバイザリースタッフ、健康増進法の虚偽誇大禁止規定の監視強化 |
|