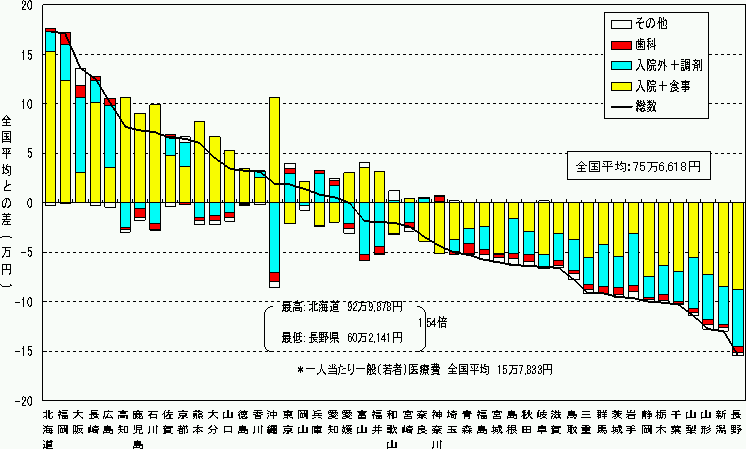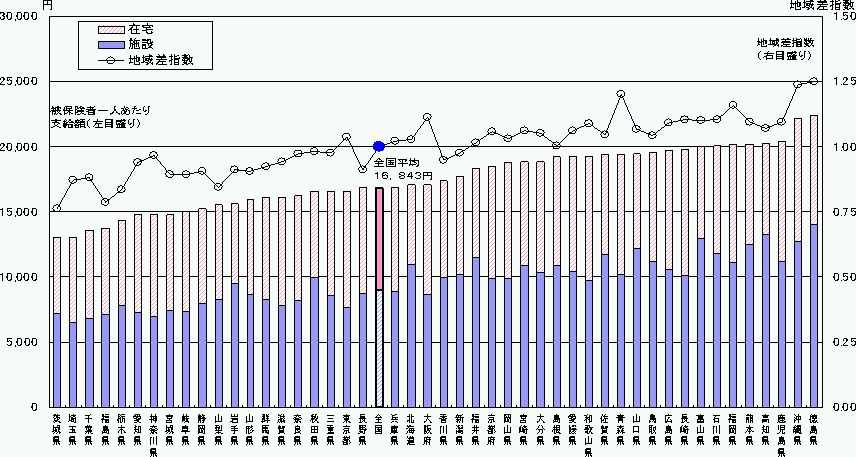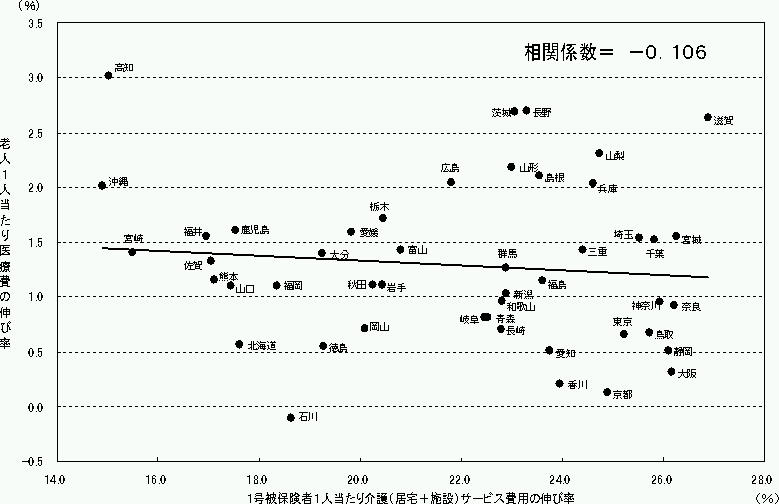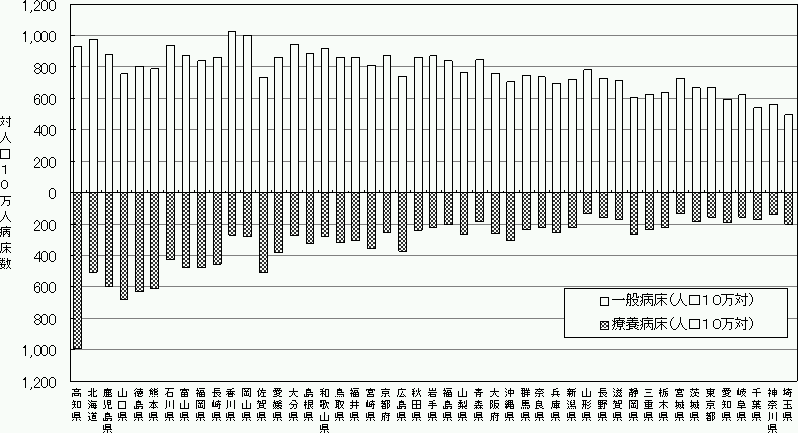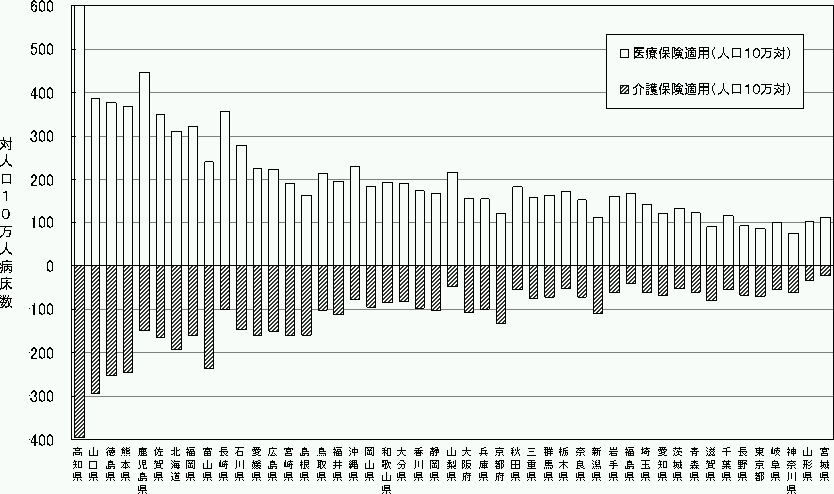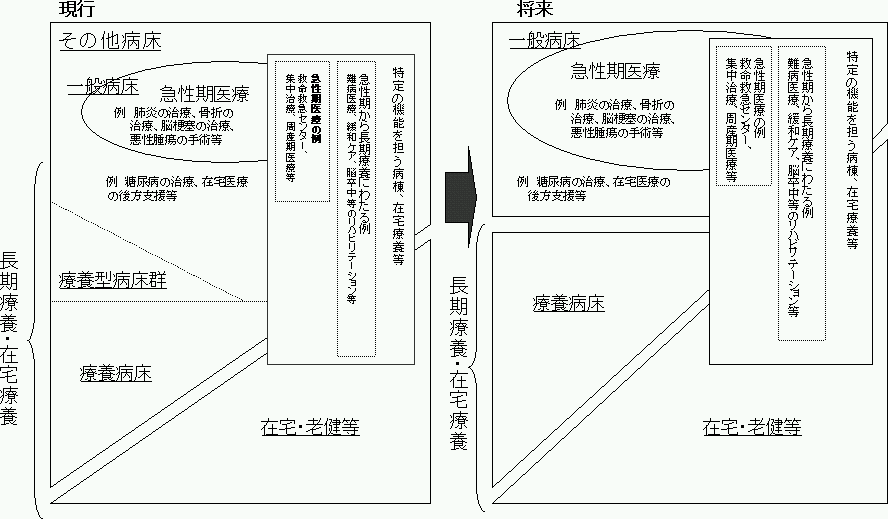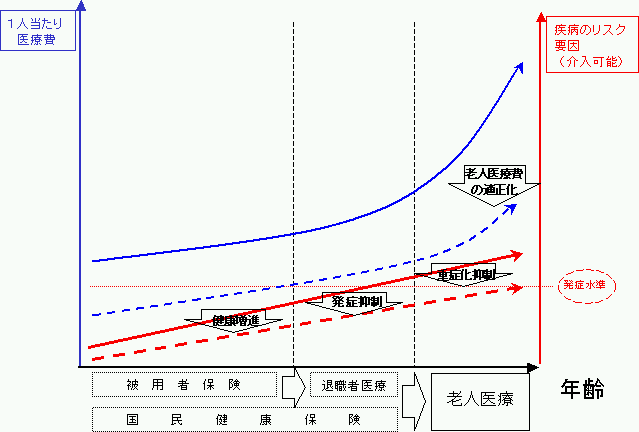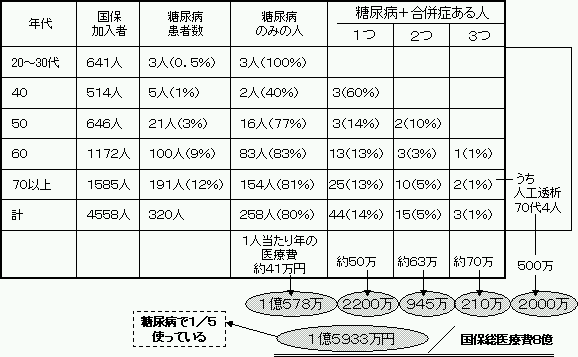|
国民皆保険制度の創設
(被用者保険に加入していない国民は、年齢を問わず基本的に国保に強制適用) |
老人保健制度 + 退職者医療制度の創設 |
|
||||||
| (国民皆保険制度) | (国民皆保険制度) | (国民皆保険制度) | ||||||
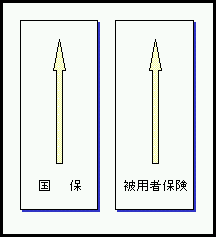 |
|
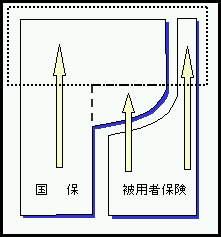 |
さらなる 高齢者 医療費の 増大 |
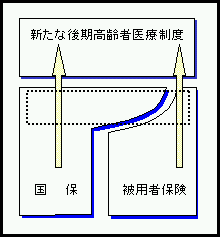 |
||||
| 職域及び地域の「連帯」に基づき各保険者が成立し、個々の保険者の内部において「世代間の連帯」が行われる | 国民皆保険制度を堅持するため、「保険者の枠組みを超えた世代間の連帯」の仕組みを導入 | 「保険者の枠組みを超えた世代間の連帯」のさらなる明確化 |
若年期からの保健事業と高齢者医療
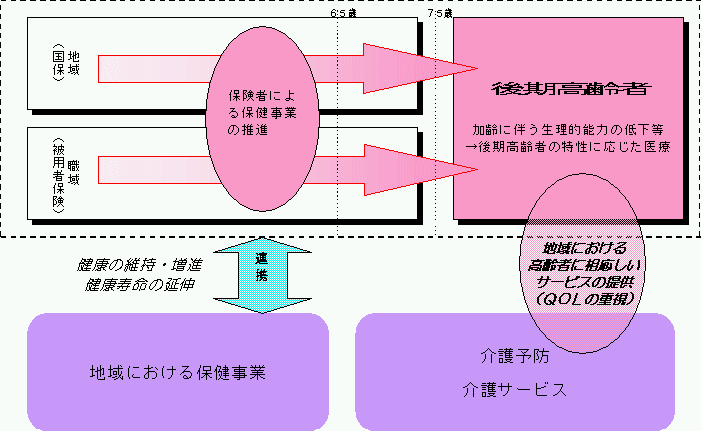
年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較(年額)
(平成12年度実績に基づく推計値)
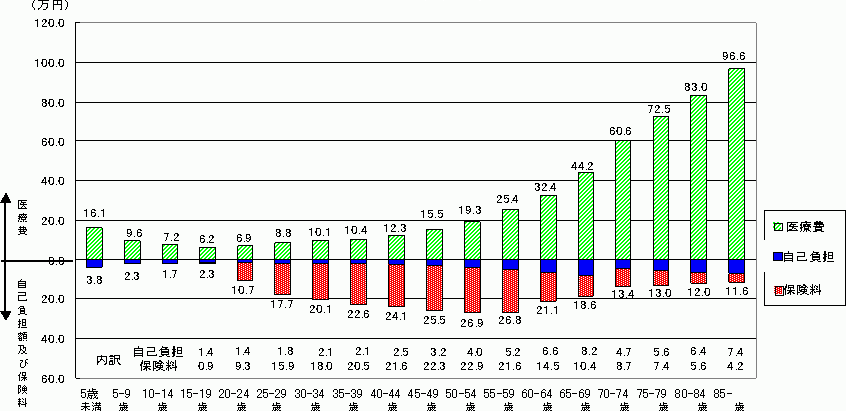
| (注) | 1. | 加入者1人当たり医療費と自己負担は、それぞれ加入者の年齢階級別医療費及び自己負担をその年齢階級の加入者数で割ったものである。 | |
| 2. | 自己負担は、医療保険制度における自己負担である。 | ||
| 3. | 加入者1人当たり保険料は、被保険者(市町村国保は世帯主)の年齢階級別の保険料を、その年齢階級別の加入者数で割ったものである。 | ||
| 4. | 端数処理の関係で、数字が合わないことがある。 |
| 資料: | 「健康保険被保険者実態調査(厚生労働省保険局)」、「国民健康保険実態調査(厚生労働省保険局)」、「医療給付受給者状況調査(社会保険庁)」等を用いて推計。 |
年齢階級別医療保険制度加入状況の変化
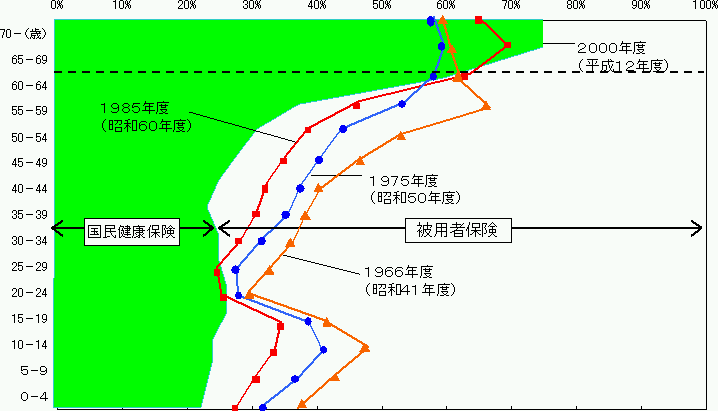
|
雇用の変化
|
年齢階級別大卒男性の標準労働者割合の推移
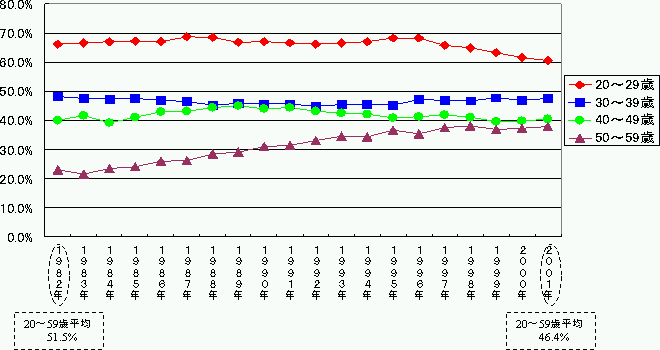
| 資料出所 | :平成14年度厚生労働白書(原調査:厚生労働省大臣官房統計情報部「賃金構造基本統計調査」) |
高齢者の特性について(加齢に伴う諸指標の変化)
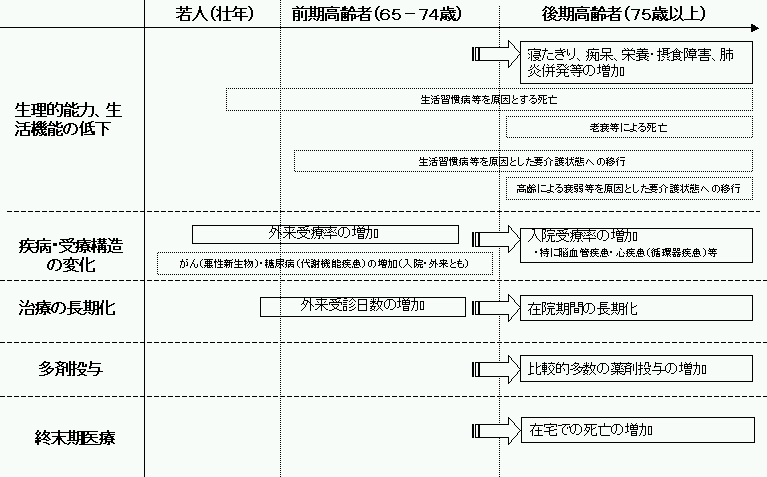
労働力人口比率
〜後期高齢者と前期高齢者〜
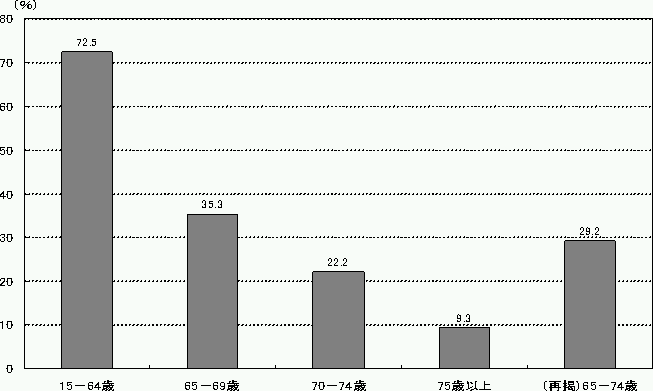
|
世帯員の年齢・所得の種類別にみた個人が得ている所得金額(平成12年の所得)
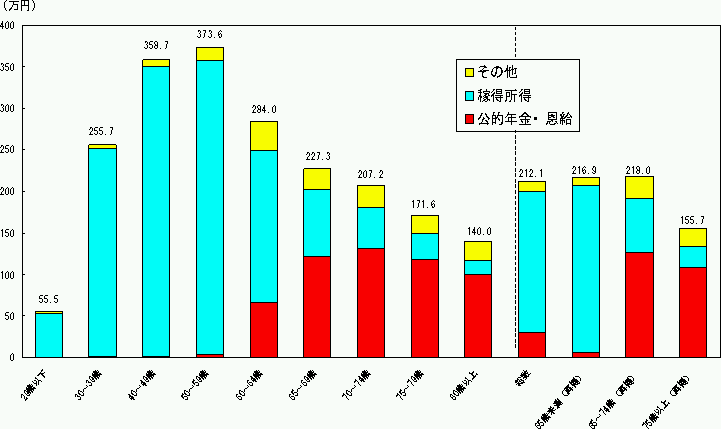
| 資料: | 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成13年 国民生活基礎調査」(大規模調査年)の個票データにより、厚生労働省保険局調査課において集計 | ||||||
| (注) | 所得の定義は同調査における所得の種類を基に以下のように定義した。
|
公的年金額の比較
| 昭和58年度 | 平成13年度 | 増減率 | ||
| 厚生年金保険 (老齢年金) |
年金額(円) | 1,359,552 | 2,098,068 | 154.32% |
| 年金月額(円) | 113,296 | 174,839 | 154.32% | |
| 受給者数(人) | 2,709,622 | 8,950,857 | 330.34% | |
| 平均被保険者期間 | 289ヶ月 | 394ヶ月 | 136.33% | |
| 国民年金 (老齢年金) |
年金額(円) | 310,572 | 620,208 | 199.70% |
| 年金月額(円) | 25,881 | 51,684 | 199.70% | |
| 受給者数(人) | 6,202,685 | 16,930,232 | 272.95% | |
| 平均被保険者期間 | − | 346ヶ月 | − | |
| 老齢福祉年金 | 年金額(円) | 301,200 | 412,000 | 136.78% |
| 年金月額(円) | 25,100 | 34,333 | 136.78% | |
| 受給者数(人) | 2,350,700 | 107,336 | △95.43% | |
|
個人の所得分布:75歳以上(平成12年の所得)
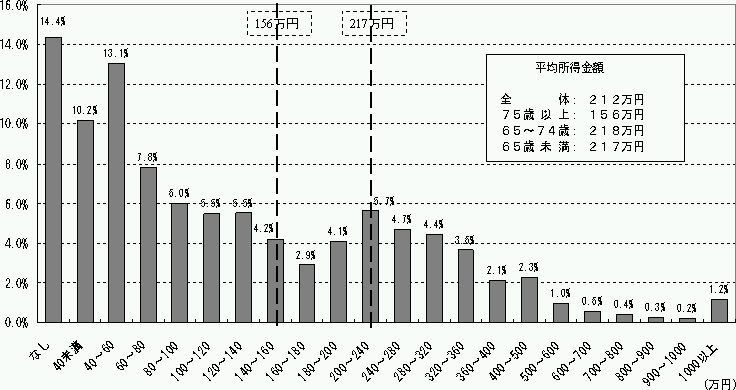
| 資料: | 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成13年 国民生活基礎調査」(大規模調査年)の個票データにより、厚生労働省保険局調査課において集計 |
| 注1) | 国民生活基礎調査による所得であり、雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得、公的年金・恩給、家賃・地代の収入、利子所得等のほか、仕送りなどを含む実質的な収入額である。 |
| 2) | 「所得なし」には、所得額の記入のない者を含む。 |
| 国民健康保険料の賦課・徴収について |
| 1. | 保険料 国民健康保険の保険料は、所得等被保険者の負担能力に応じた負担となる応能部分と、被保険者1人当たりの一定額等となる応益部分によって構成されている。応能部分と応益部分の構成比率の標準は政令で定められているが(下表参照)、各方式の選択、構成比率については、市町村が実情に応じて運用することとしている。 また、低所得者については、応益部分の保険料を軽減する仕組みが取られている。 ※軽減率は、各市町村の応益割合(保険料収入に占める応益保険料の割合)により異なる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 2. | 徴収 世帯主から保険料を個別に徴収(普通徴収)する。 ※平成14年度の収納率:90.39%
|
|||||||||||||||||||||||
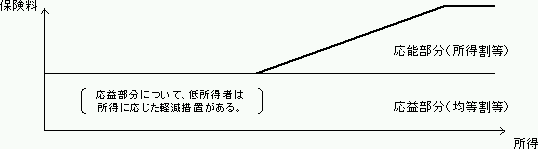
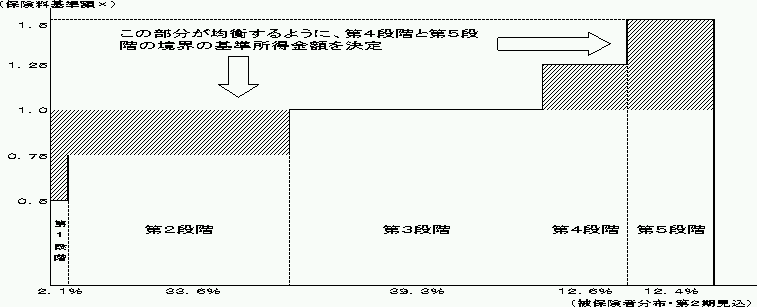
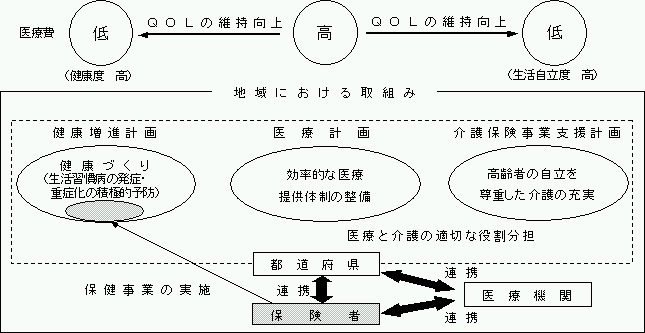
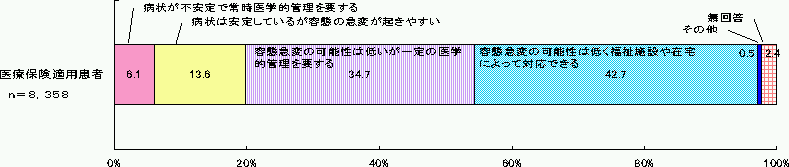
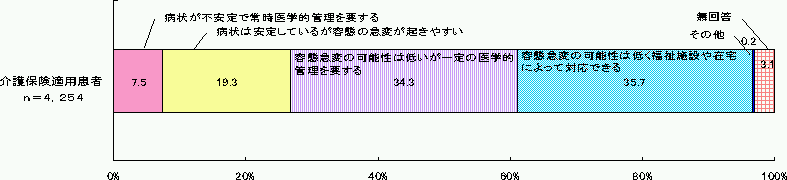
![[年齢階級別]のグラフ](images/s0513-4r.gif)