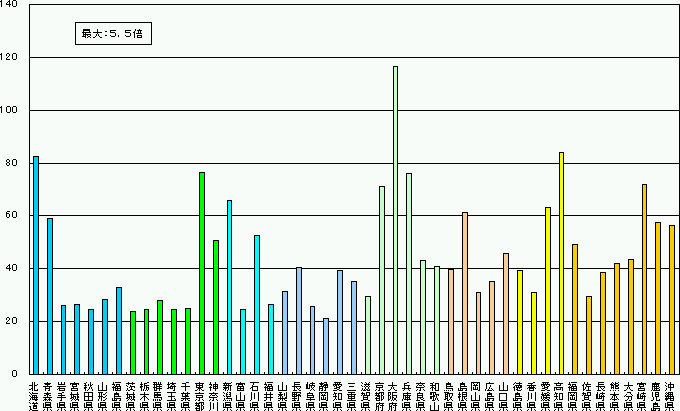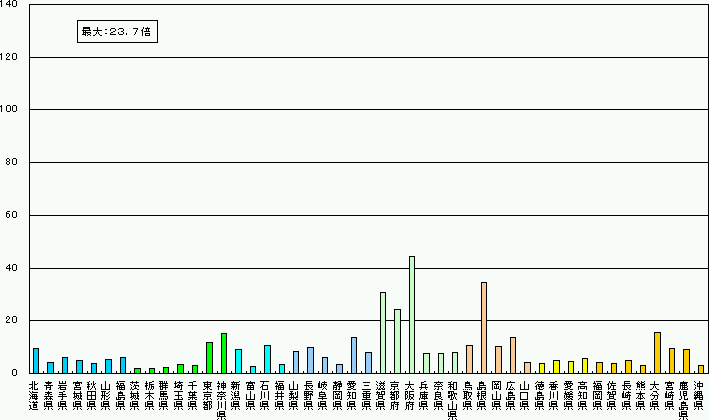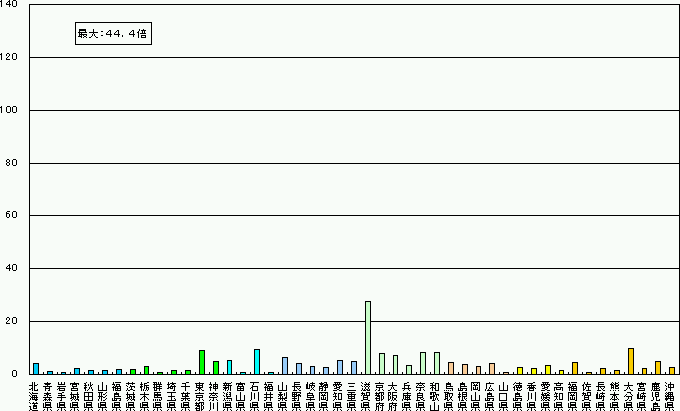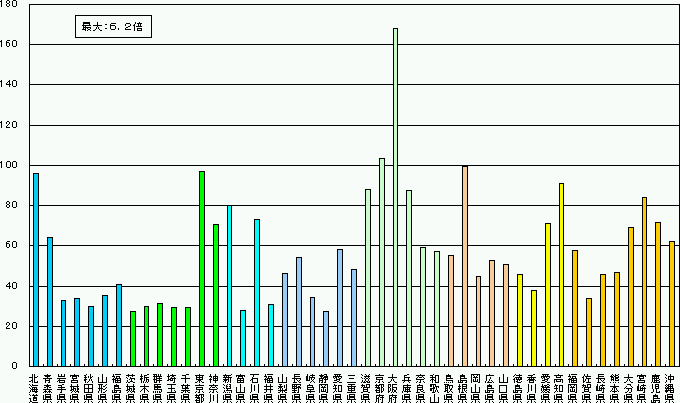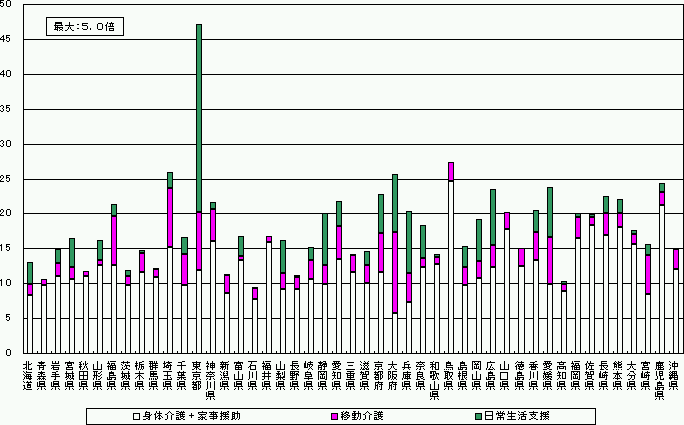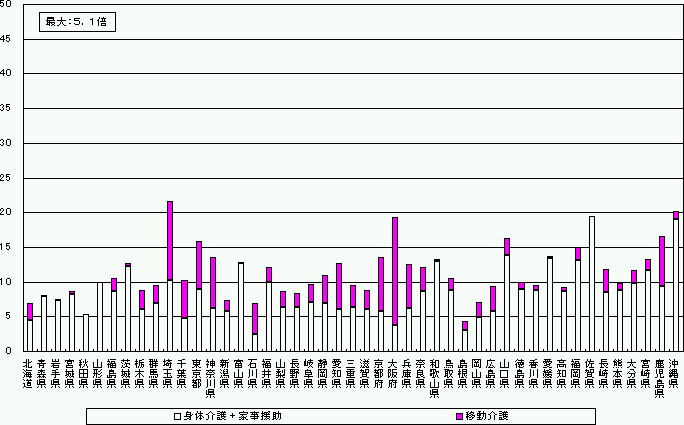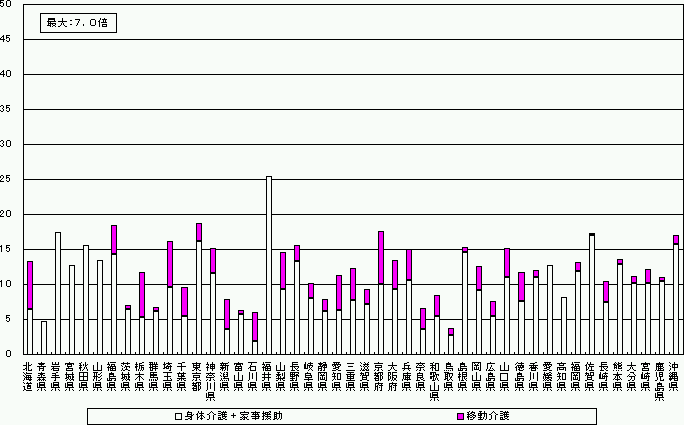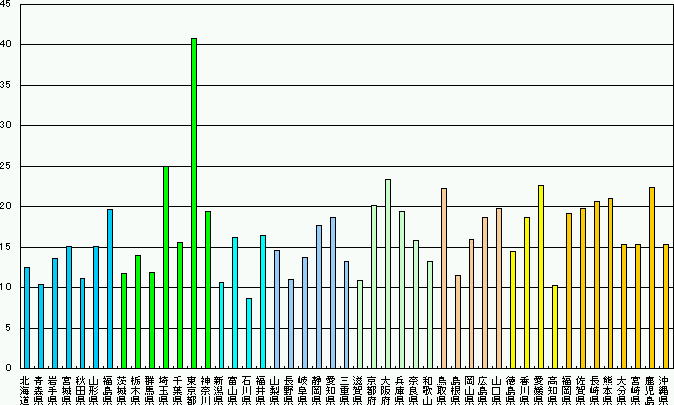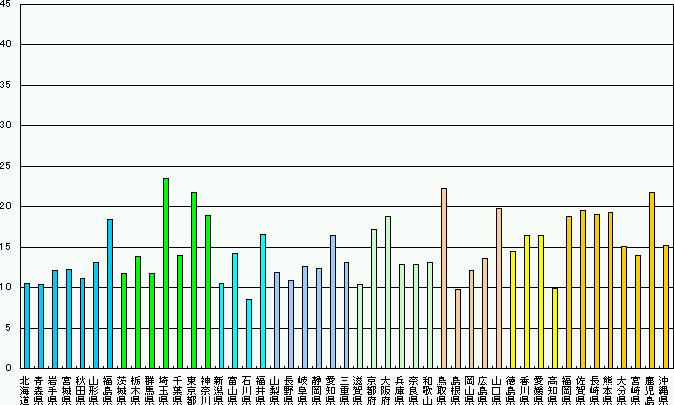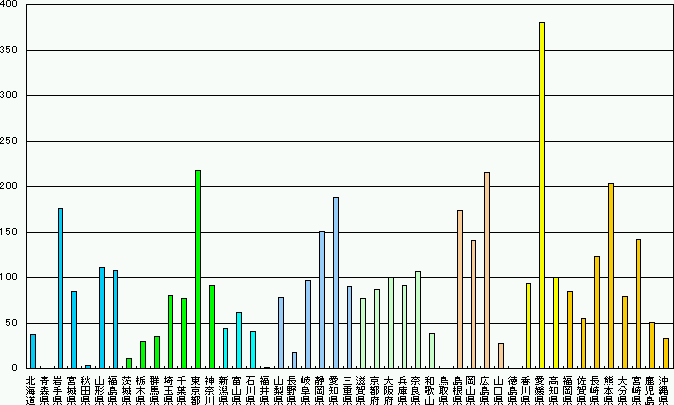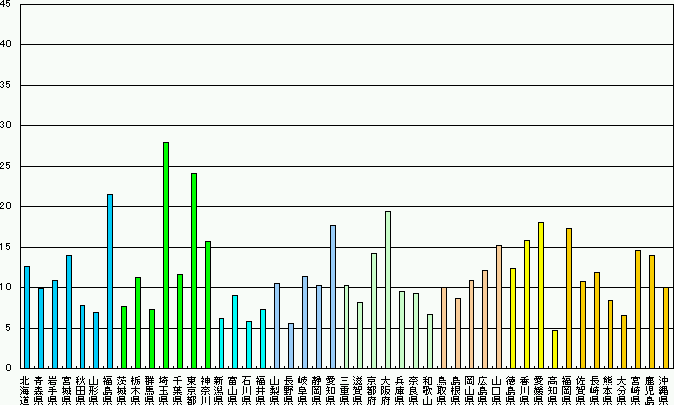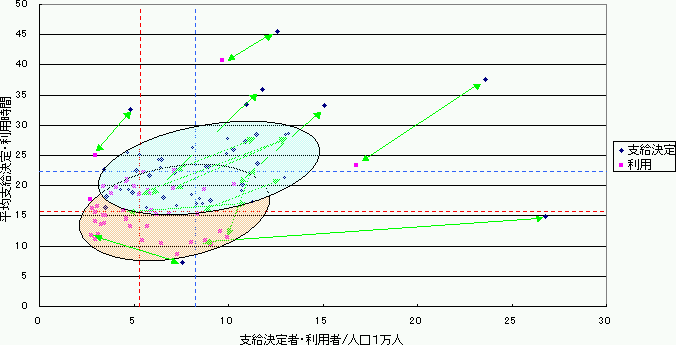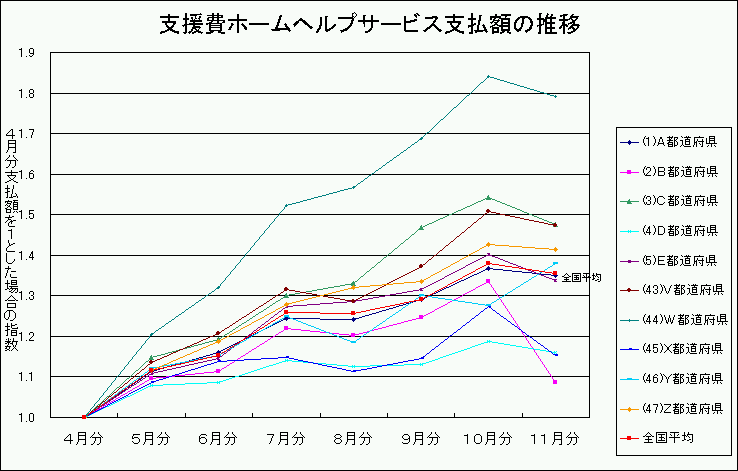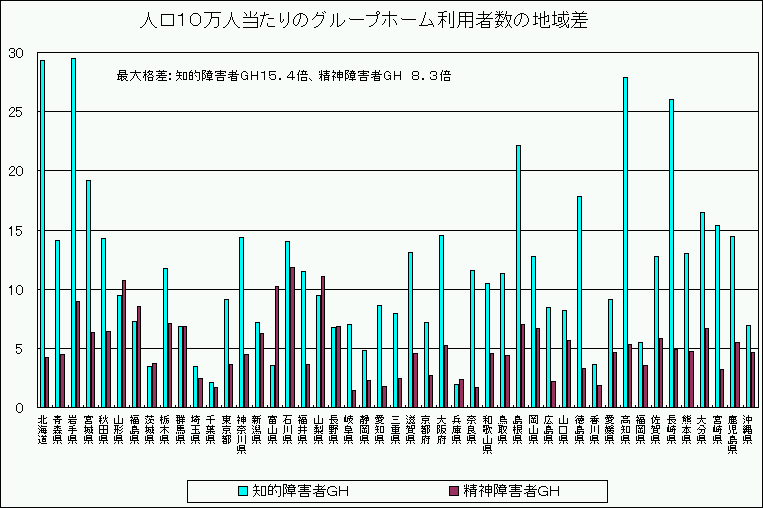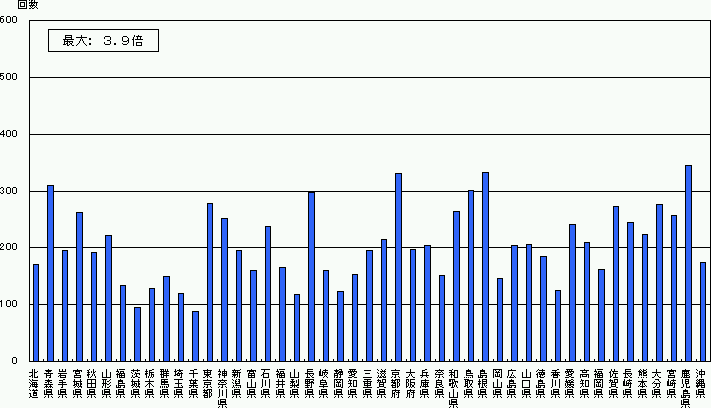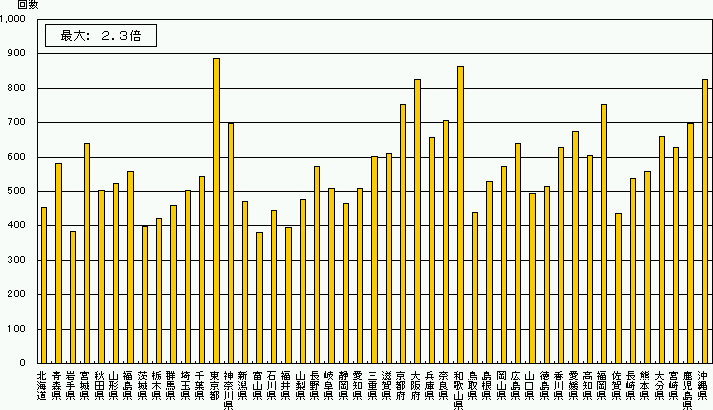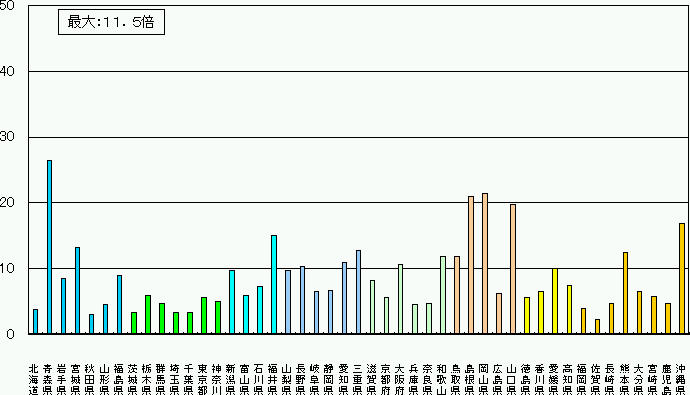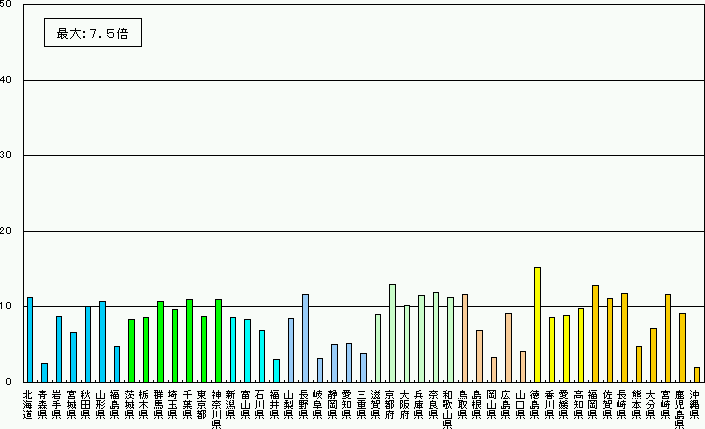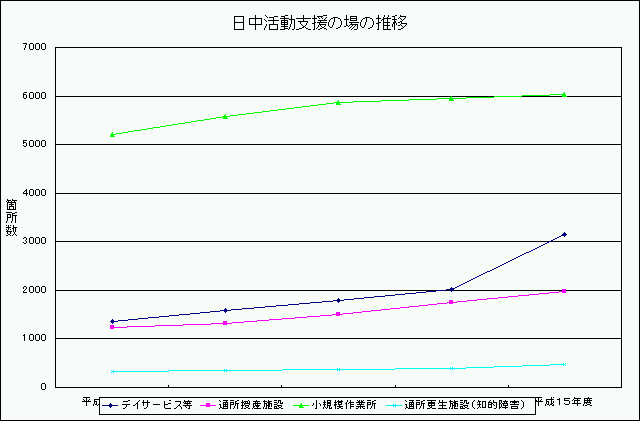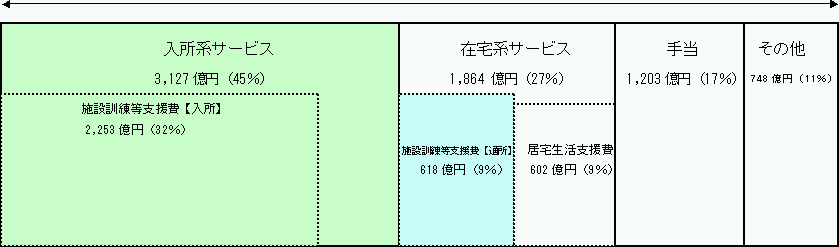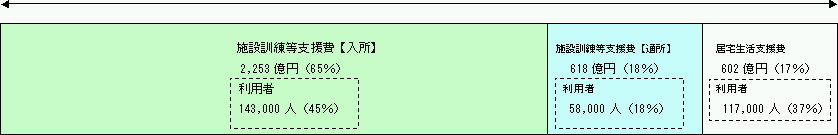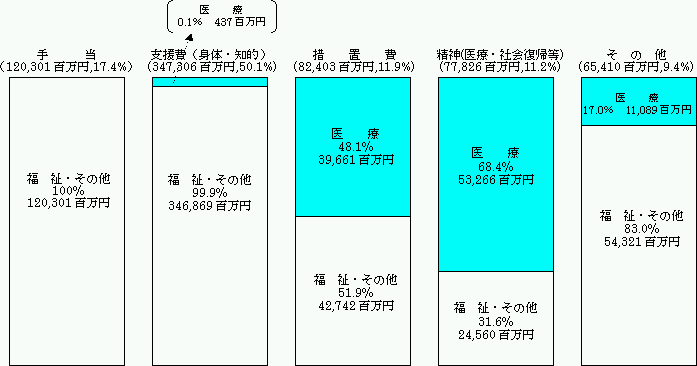人口10万人当たりの身体障害者ホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月)
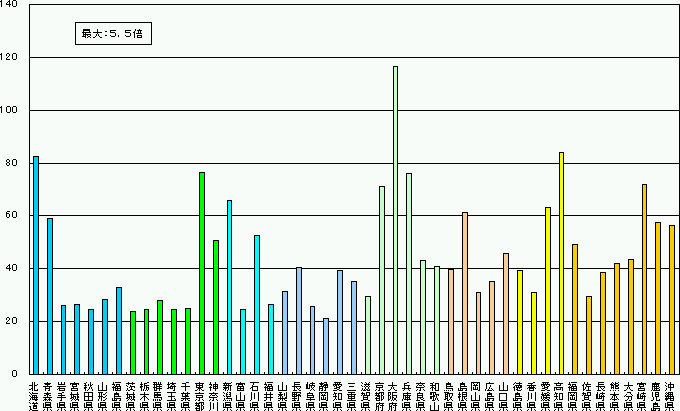
人口10万人当たりの知的障害者ホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月)
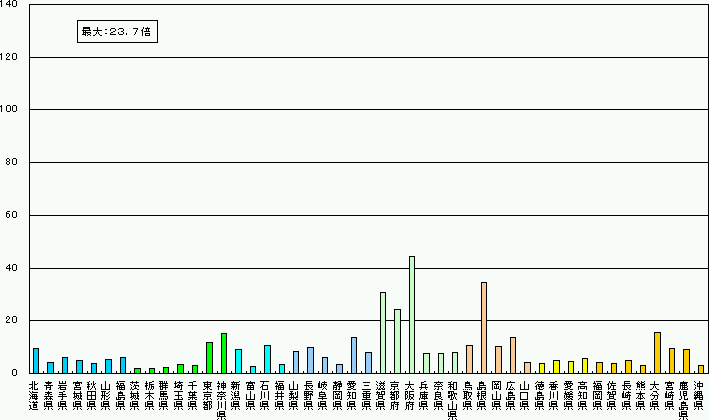
人口10万人当たりの障害児ホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月)
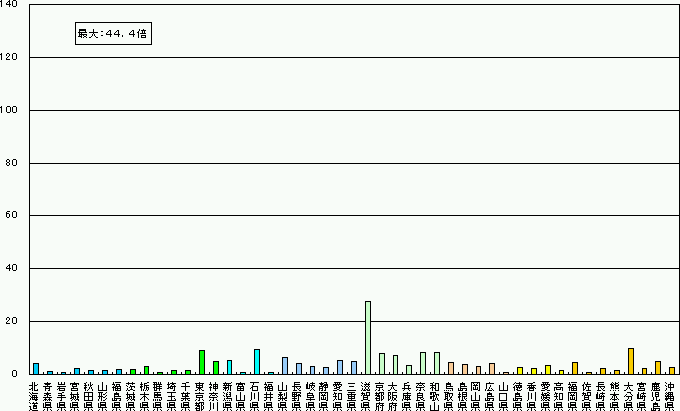
人口10万人当たりの精神ホームヘルプサービス利用者数(平成15年9月)
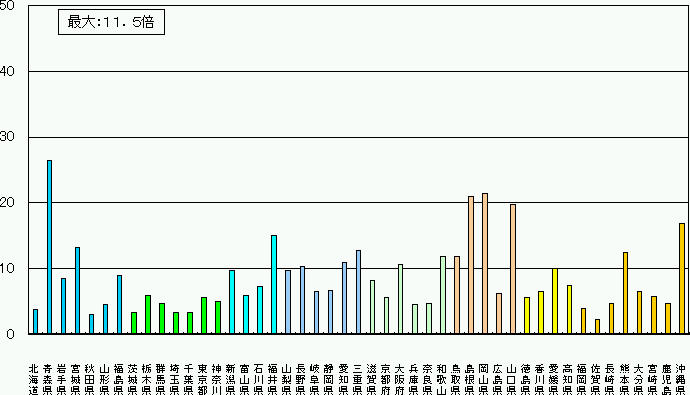
|
| 【データ出典】厚生労働省精神保健福祉課調べ |
人口10万人当たりの支援費ホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月)
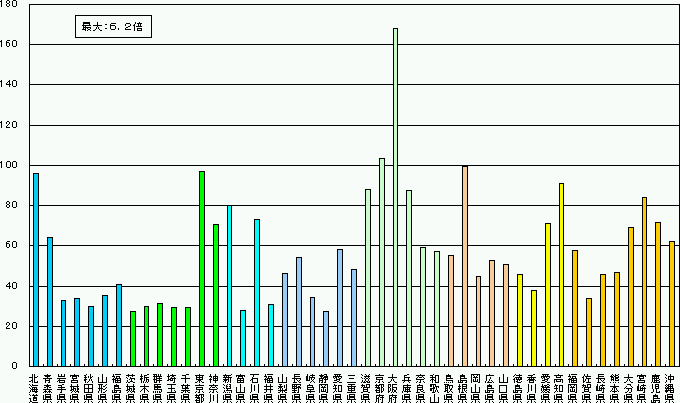
身体障害者ホームヘルプサービス平均利用時間の内訳
(平成15年4月)
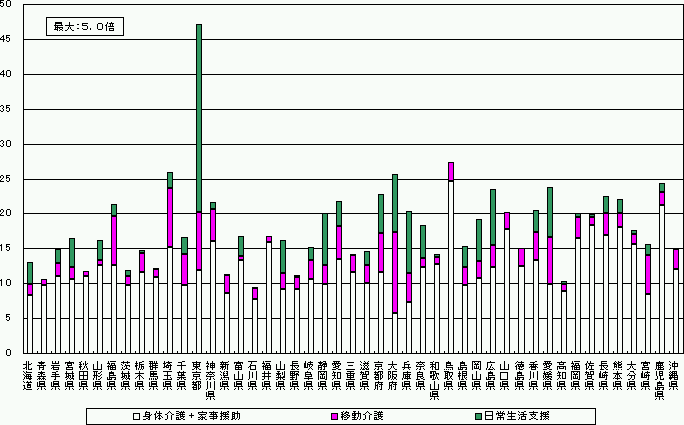
知的障害者ホームヘルプサービス平均利用時間の内訳
(平成15年4月)
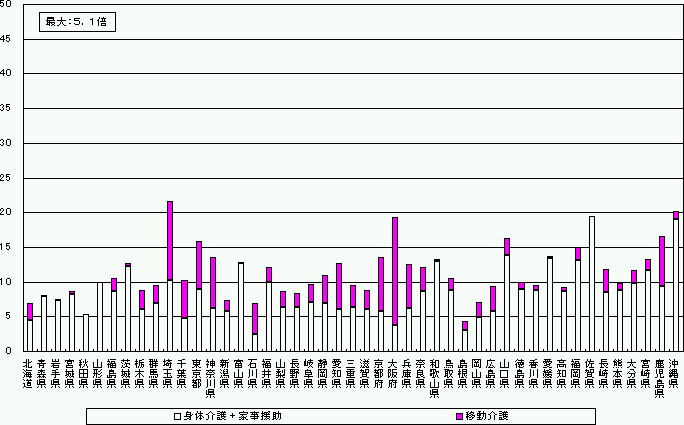
障害児ホームヘルプサービス平均利用時間の内訳
(平成15年4月)
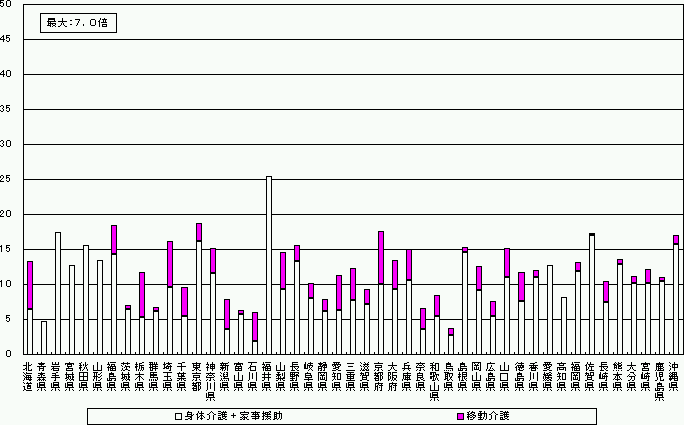
精神ホームヘルプサービス一人当たり平均利用時間数(平成15年9月)
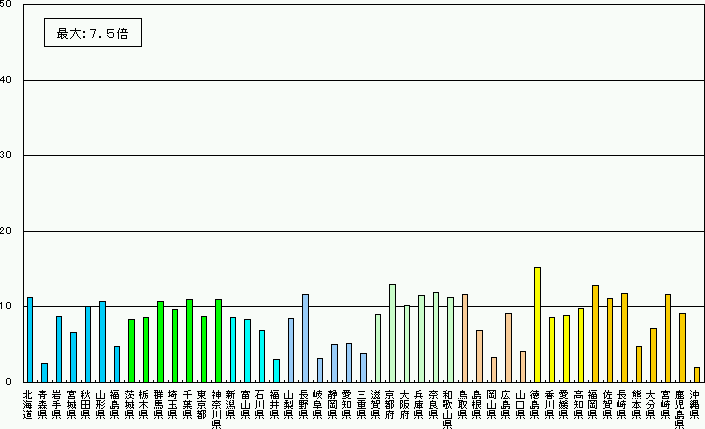
|
| 【データ出典】厚生労働省精神保健福祉課調べ |
支援費ホームヘルプサービス一人当たり平均利用時間数
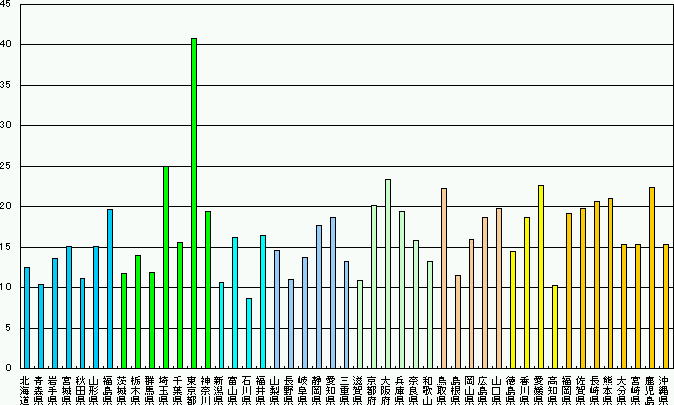
支援費ホームヘルプサービス一人当たり利用時間数
(除く日常生活支援)
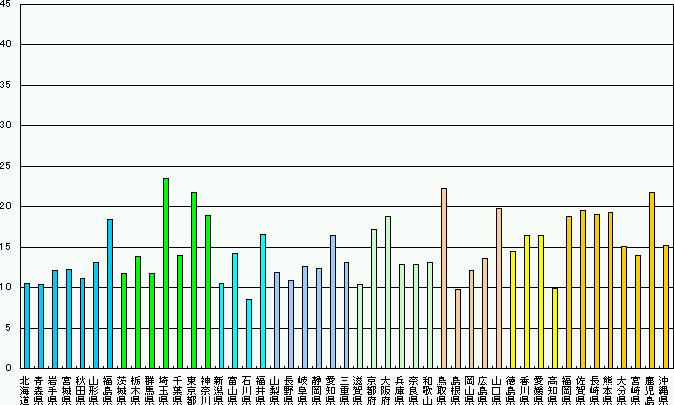
支援費ホームヘルプサービス一人当たり利用時間
(日常生活支援)
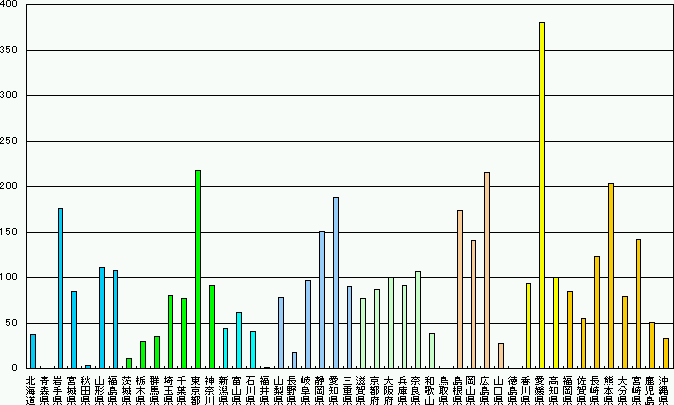
支援費ホームヘルプサービス一人当たり利用時間数
(移動介護)
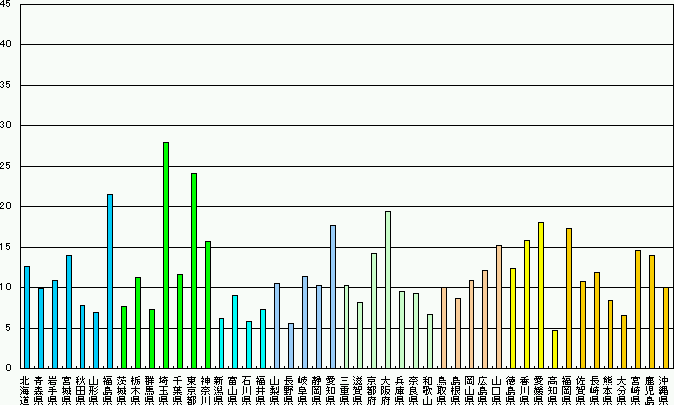
各都道府県におけるホームヘルプサービスの支給決定と利用の状況
(平成15年4月)
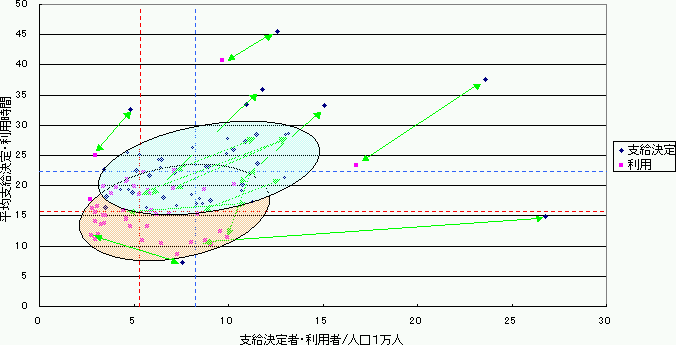
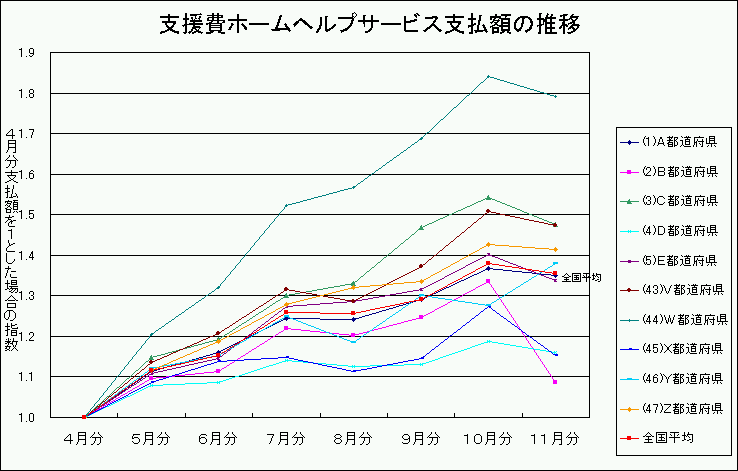
| 【データ出典】厚生労働省障害福祉課調べ |
| (注) 人口1万人当たりの支援費ホームヘルプサービス利用者数(平成15年4月分)が最も多いところ5都道府県と、最も少ない5都道府県を抽出したもの。 |
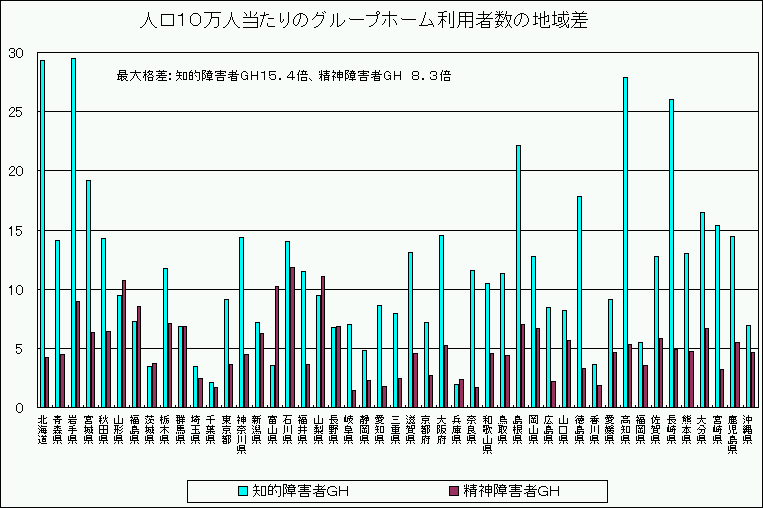
【データ出典】厚生労働省調べ(平成15年4月現在) |
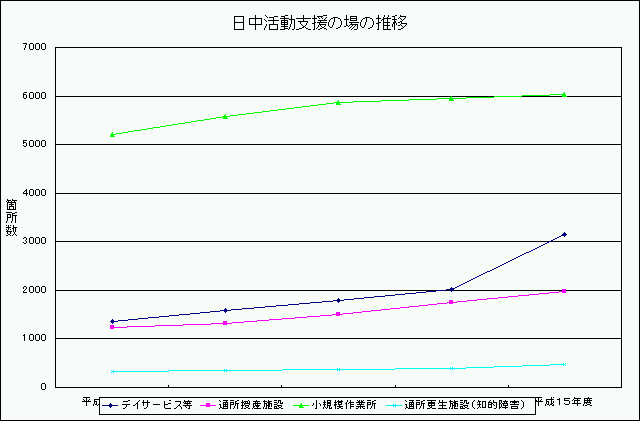
【データ出典】社会福祉施設等調査、WAMNET。ただし、小規模作業所は、きょうされん調べによる。
(注)「デイサービス等」には、精神障害者地域生活支援センターを含む。 |
65歳以上高齢者100人当たりホームヘルプサービス年間利用回数
(平成11年度)
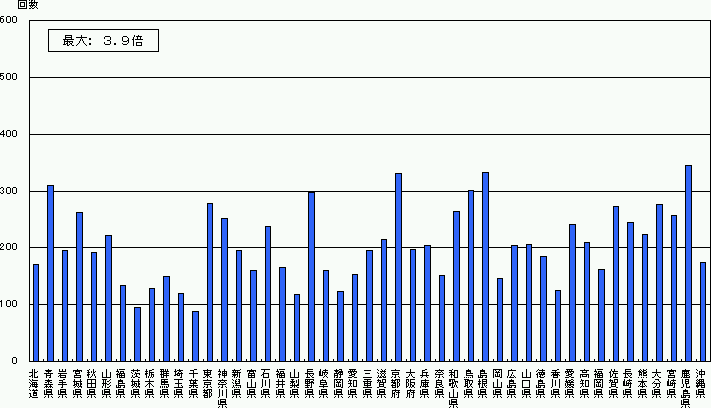
【データ出典】老人保健福祉サービス利用状況地図(老人保健福祉マップ)(平成12年版)
(注)100人当たり年間利用回数=(当該都道府県の利用延人員)/(当該都道府県の65歳以上人口)×100 |
65歳以上高齢者100人当たりホームヘルプサービス年間利用回数
(平成14年度)
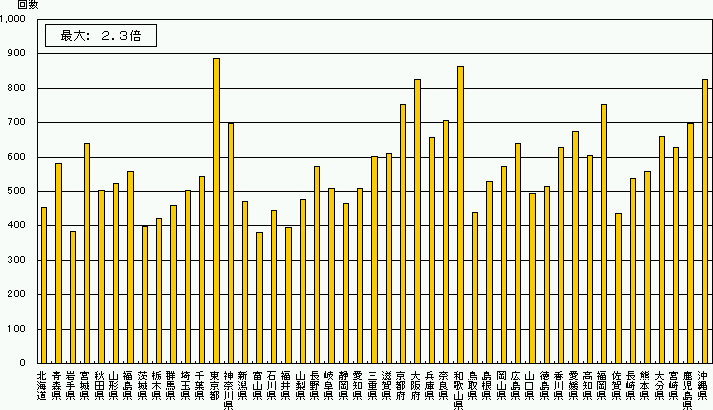
【データ出典】介護給付費実態調査報告(平成14年度)
(注)介護給付費明細書に記載された介護給付費単位数サービスコードごとのサービス提供回数を計上。 |
| ○ | 支援費の支給決定に当たって、支給量やサービス類型の適用等に係る詳細な基準や専門機関を設けるべき。(36)
|
| ○ | 利用者負担の応益化や負担額の引き上げ、負担額の上限廃止をすべき。(34)
|
| ○ | 早朝、夜間及び深夜における加算額の算定方法をサービス利用開始時による算定から実際の提供時間による算定へと変更すべき。(21)
|
| ○ | ケアマネジメントを制度化すべき。(15)
|
| ○ | 家事援助、移動介護及び日常生活支援にも身体介護と同様に、30分未満の単価を設定すべき。(14)
|
| ○ | 移動介護の身体介護「有」と「無」の区分をなくし、一本化すべき。(12)
|
| ○ | 身体障害者の短期入所にも知的障害者及び障害児の短期入所と同様に、日中のみの利用を設定すべき。(10)
|
| ○ | 障害児のデイサービスにも身体障害者及び知的障害者のデイサービスと同様に、時間による単価を設定すべき。(9)
|
| ○ | 知的障害者及び障害児のホームヘルプサービスにも身体障害者のホームヘルプサービスと同様に、日常生活支援の単価を設定すべき。(9)
|
| ○ | 居宅生活支援費の支払方法を計画に基づく支払いから、提供実績に基づく支払いへと変更すべき。(7)
|
| ○ | グループホーム世話人の業務と、グループホームでのホームヘルパーの業務を明確にすべき。(6)
|
| ○ | 施設訓練等支援費を日単位で支給できるようにすべき。(6)
|
| ○ | グループホームの程度区分を2区分から3区分へと変更すべき。(6)
|
| ○ | 移動介護の身体介護「有」と「無」の単価の格差を縮小すべき。(5)
|
| ○ | デイサービスの単価を引き上げるべき。(5)
|
| ○ | 短期入所の日中のみの利用にも送迎加算を設定すべき。(5)
|
| ○ | 支援費の支給量に上限を設定すべき。(5)
|
| ○ | グループホームに人員配置基準を設定すべき。(4)
|
| ○ | 日常生活支援の単価を引き上げるべき。(4)
|
| ○ | ホームヘルプサービスや移動介護を複数で利用できるようにすべき。(4)
|
| ○ | 宿泊を伴う短期入所に時間による単価を設定すべき。(3)
|
| ○ | 身体介護を長時間利用する場合、単価を引き下げるべき。(3)
|
| ○ | 過疎地域や離島等に配慮した地域加算を設定すべき。(3)
|
| ○ | 中・高生がデイサービスを利用できるようにすべき。(3)
|
| ○ | グループホームに重症心身障害者・児加算を設定すべき。(2)
|
| ○ | グループホームの単価を支援体制に応じて設定すべき。(2)
|
| ○ | 施設訓練等支援費の単価を人員配置に応じて設定すべき。(2)
|
| ○ | 重症心身障害者・児の短期入所における医療系と非医療系の単価の格差を縮小すべき。(2)
|
| ○ | デイサービスに重症心身障害者・児加算を設定すべき。(2)
|
| ○ | 介護保険と同様に、乗降介助の単価を設定すべき。(2)
|
| ○ | 夜間等に見守りを行う巡回型のホームヘルプサービスを設定すべき。(2)
|
| ○ | 視覚障害者、全身性障害者以外の身体障害者も移動介護を利用できるようにすべき。(2)
|
| ○ | 移動介護での乗用車利用を認めるべき。(2)
|
| ○ | 介護保険事業所で居宅生活支援サービスを利用できるようにすべき。(2)
|
| ○ | 身体介護での通院と移動介護での通院を一本化すべき。(2)
|
| ○ | 同一人に対する身体障害者サービスと知的障害者サービスでの利用者負担額の上限を一本化すべき。(2) |