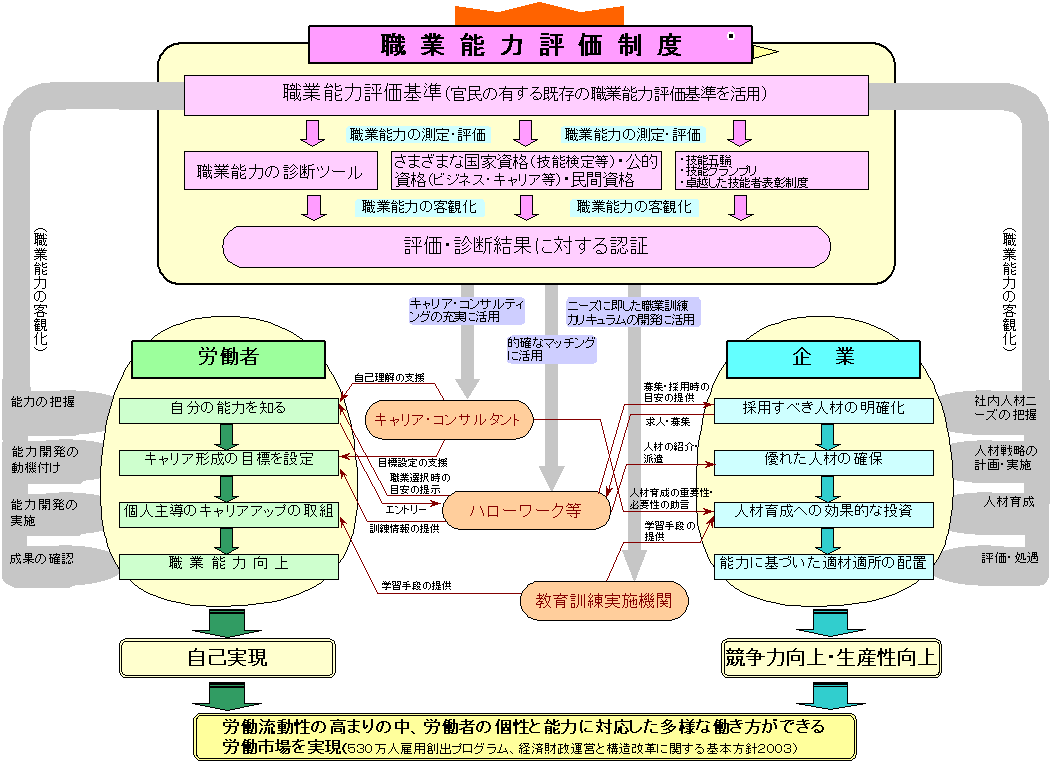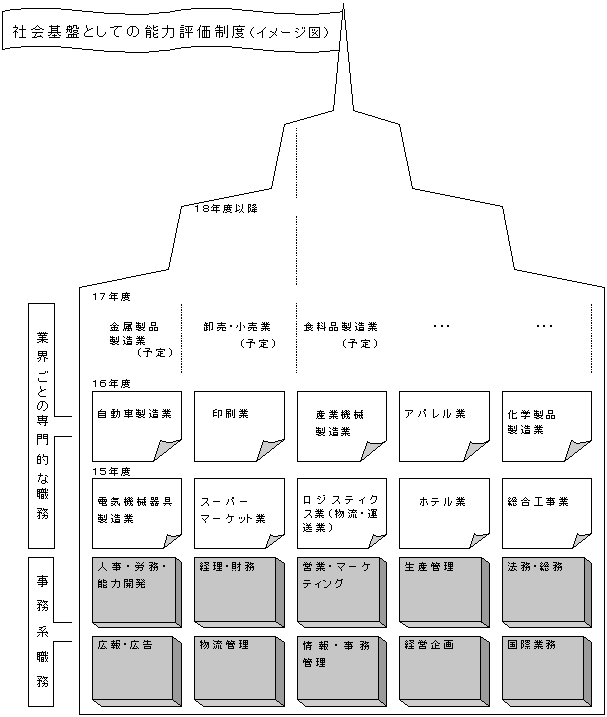
<参考 能力評価基準の活用場面の一例>
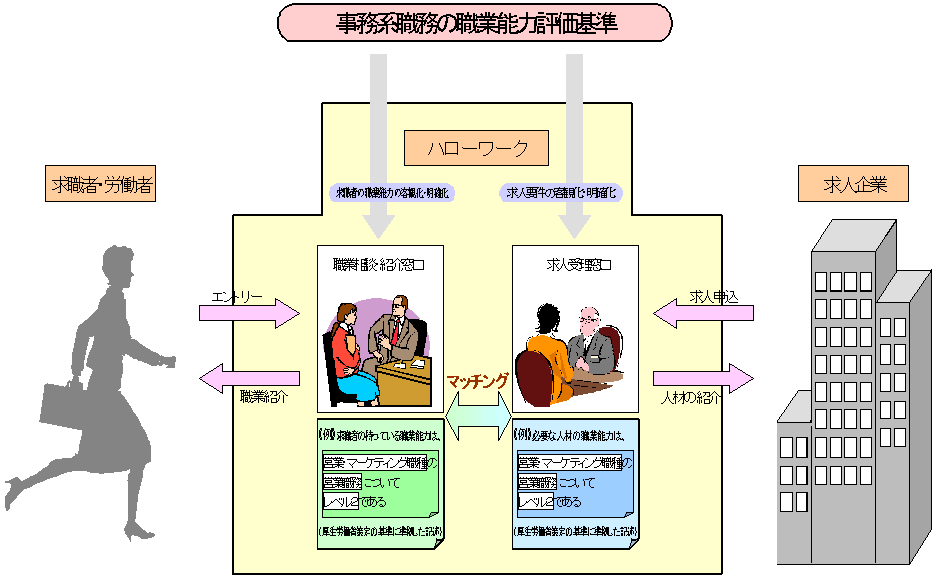
<能力評価基準の例(事務職)>
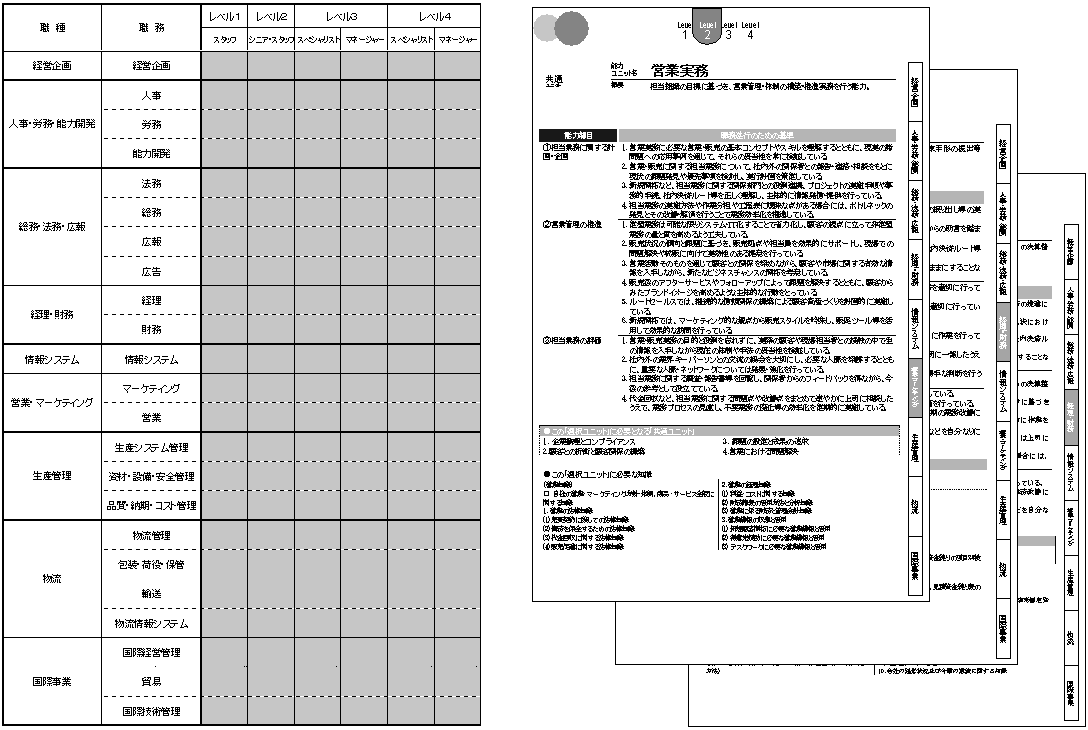
| 労働者のキャリア形成に対する支援について |
|
|
|
||||||||
|
|
| キャリア形成促進のための支援 |
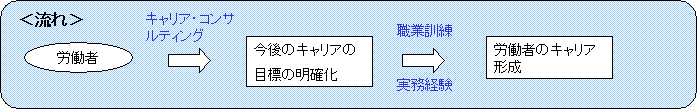
労働者のキャリア形成のため、職業能力開発促進法上、以下の事項が規定。
| ・ | 事業主の責務(法4条) |
| ・ | 多様な職業能力開発機会の確保(法8条) |
| ・ | 自ら又は共同して行うOJT、Off-JTの実施(法9条) |
| ・ | 教育訓練機会の確保、多様な職業能力検定の受検(法10条) |
| ・ | キャリア形成支援(情報提供、相談、配置等雇用管理への配慮)(法10条の2) |
| ・ | 労働者が自ら職業に関する教育訓練等を受ける機会を確保するための各種教育訓練休暇の付与や時間の確保(法10条の3) |
| ・ | 計画的な職業能力開発の推進(法11条) |
|
| (1) | 訓練給付金:年間職業能力開発計画に基づき、その従業員に職業訓練を受けさせる場合、職業訓練に要した経費や職業訓練期間中に支払った賃金の一部を助成 |
| (2) | 職業能力開発休暇給付金:年間職業能力開発計画に基づき、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティングを受けさせるために休暇を与えた場合、事業主が負担した入学料、受講料や休暇期間中に支払った賃金の一部を助成 |
| (3) | 長期教育訓練休暇制度導入奨励金:連続1か月以上の長期教育訓練休暇制度又は5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入し、計画に基づき、その従業員に当該休暇を付与した場合、奨励金として一定額を助成 |
| (4) | 職業能力評価推進給付金:年間職業能力開発計画に基づき、その従業員に、一定の資格試験等を受けさせた場合、受検料等の経費や受検に要した期間中に支払った賃金の一部を助成 |
| (5) | キャリア・コンサルティング推進給付金:年間職業能力開発計画に基づき、その従業員に一定のキャリア・コンサルティングを受けさせた場合、外部機関への年間委託費用の一部を助成(初年度のみ支給) |
|
<公的機関における養成>
| ・ | 職業能力開発大学校等において、毎年約1,100名を養成 |
| ・ | キャリア形成促進助成金の活用 (事業主が労働者のキャリア・コンサルタントの養成訓練の受講やキャリア・コンサルタント能力評価試験の受検を支援した場合に助成) |
| ・ | 教育訓練給付制度の活用 (労働者自らがキャリア・コンサルタントの養成訓練を受講した場合に支援) |
| ○ | 教育訓練給付制度の活用 労働者が主体的に能力開発の取り組むことを支援し、その雇用の安定を図るため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合、労働者が負担した費用の一定割合に相当する額を支給。 |
| ○ | 長期教育訓練休暇制度導入奨励金(キャリア形成促進助成金の活用) (1)連続1か月以上の長期教育訓練休暇制度、又は(2)5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入し、計画に基づき、その従業員に当該休暇を付与した場合に制度導入費用等を支援。 |
| 職業能力評価制度の整備 |
|
<能力評価基準の策定状況>
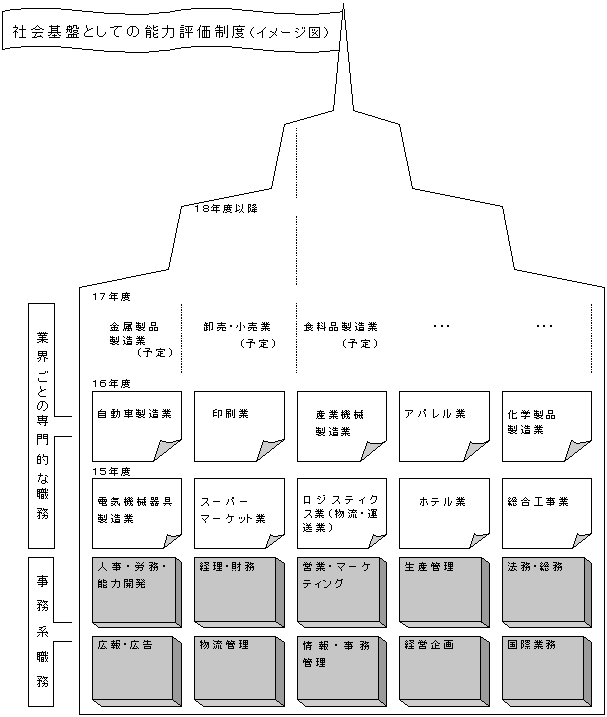
<参考 能力評価基準の活用場面の一例>
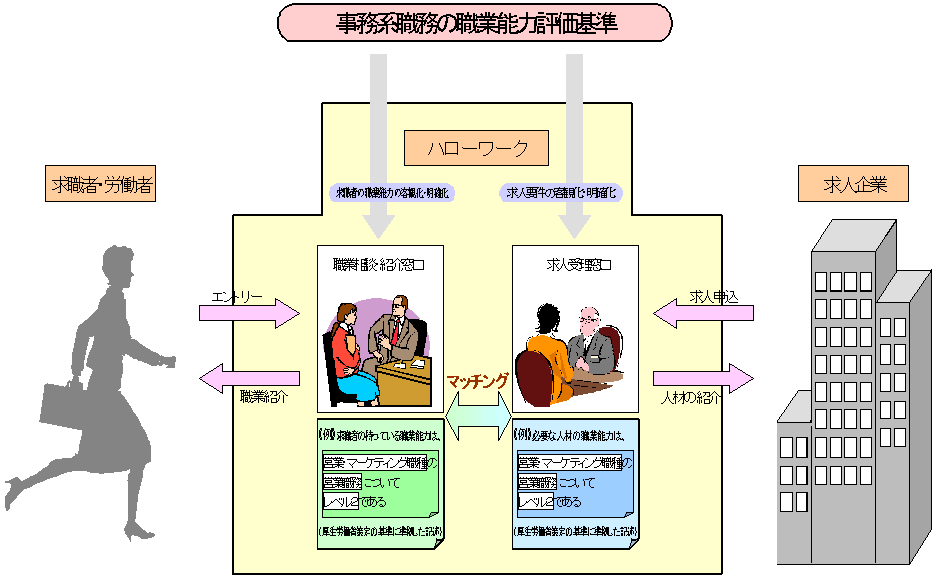
<能力評価基準の例(事務職)>
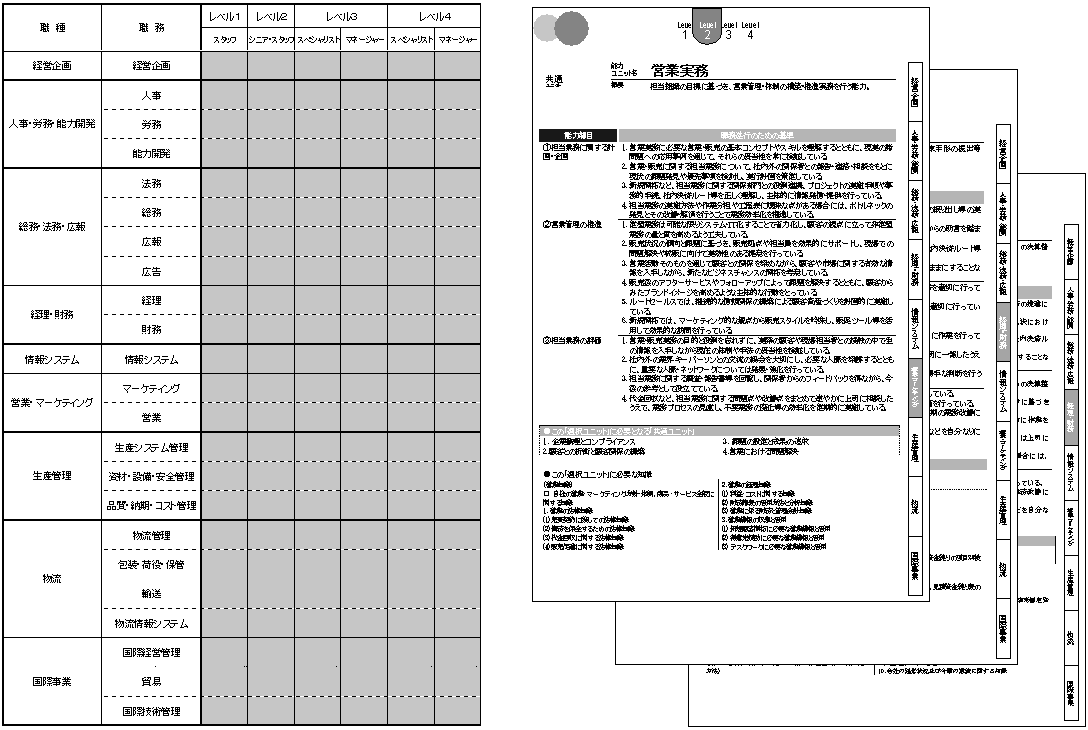
| 若年者向け職業能力評価・公証の仕組みの整備 |
|
<若年者就職基礎能力認証事業(YES−Program)のイメージ図>
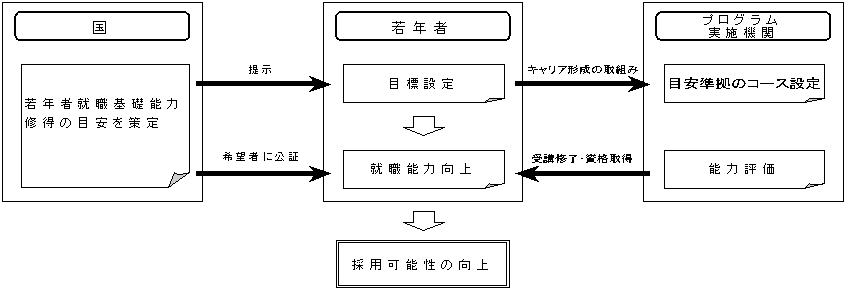
| 社会基盤としての「職業能力評価制度」 |