| ※ 収入: | 就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助、交通事故の補償等を認定。 |
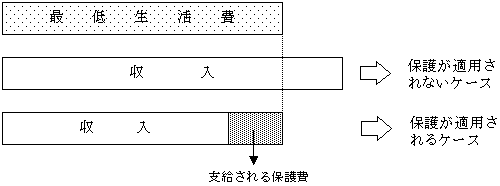
| 1 目的 |
| ○ | 生活に現に困窮している国民に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図ること。 |
| 2 対象者 |
| ○ | 資産、能力等すべてを活用した上でも、生活に困窮する者。
| ||
| ○ | 困窮に至った理由を問わない。 |
| 3 保護の内容 |
| ○ | 保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成。
| |||||||||||||||
| ○ | 各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定。
(平成15年度生活扶助基準の例)
|
| 4 保護の実施機関 |
| ○ | 都道府県知事及び市町村長により設置される福祉事務所の長。 |
| 5 保護受給に至る手続 |
| ○ | 申請による場合
|
| ○ | 職権による場合
|
| 6 保護の要否の判定と支給される保護費 |
| ○ | 厚生労働大臣が定める基準で測定される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に保護を適用。最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給。
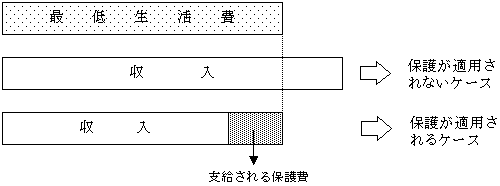
| ||
| ○ | 収入としては、上記のほか預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も認定するため、これらを使い尽くした後に、初めて保護適用となる。 |
| 7 保護適用後の調査及び指導 |
| ○ | 世帯の実態に応じ、年2〜12回の訪問調査。 |
| ○ | 収入・資産等の届出を義務付け、定期的に課税台帳との照合を実施。 |
| ○ | 就労の可能性のある者への就労指導。 |
| 最低生活費の体系 |
| ○ | 最低生活費を計算する尺度となる保護基準は、厚生労働大臣が、要保護者の年齢、世帯の構成、 所在地等の事情を考慮して扶助別に(8種類)に定める。
|
│
│ ↓
│
│ ↓
│
│ ↓
│
│ ↓
このほか必要に応じ教材費などの実費が計上される。
│
│ ↓
│
│ ↓
このほか、出産、葬祭などがある場合は、それらの経費が一定額加算される。
│
│ ↓
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会・援護局作成 「第1回社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会(平成15年8月6日)」説明資料より抜粋