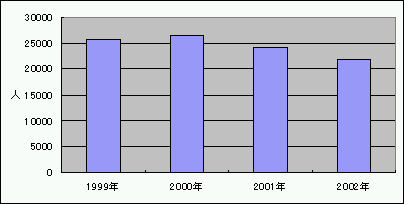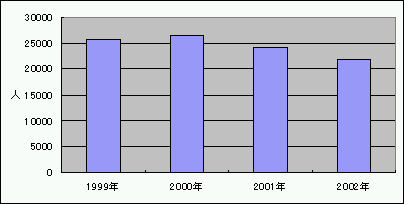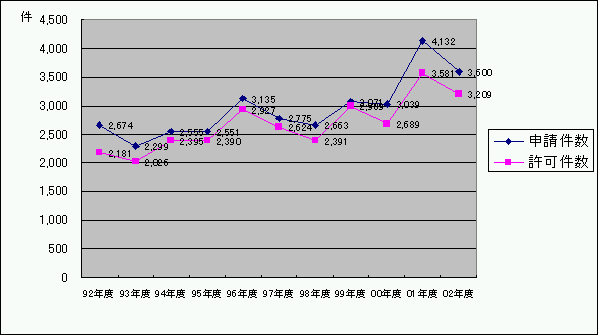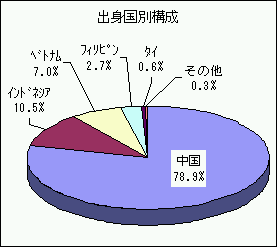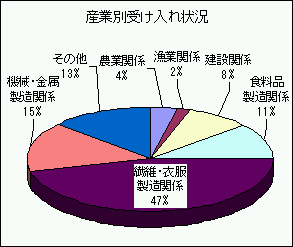| (1) | �@�ݗ����i�̊g��
�@�������̍ݗ����i�ɂ��Ē�`���g�傷��ƂƂ��ɁA�Ɩ��Ɛ莑�i�ɌW�镪��ɂ��āA����͈͂��g�傷��B
�k�Z�p�̒�`�l
| �@ | �@���݁A���ǖ@�掵���ꍀ��̊���߂�ȗ߁i�ȉ��A�ȗ߁j�́u�Z�p�v�̍��̉����Ɍf���銈���Ɋւ��āA�S�Ă̋Ǝ�ɂ����āA�u��w�𑲋Ƃ��Ⴕ���͂���Ɠ����ȏ�̋�������͏\�N�ȏ�̎����o���ɂ��v�Ƃ���v�����폜����B���݁A����Z�p�҂ɂ��ẮA����Z�p�Ɋւ��鎎���̍��i�A�܂��͎��i�ۗ̕L��O��ɁA���̗v�����ɘa����Ă���B�S�Ǝ�ɂ��������v���ɘa���g�傷�邱�Ƃ����߂���B |
�k�l���m���E���ۋƖ��̒�`�l
| �@ | �@�ȗ߂̐l���m���E���ۋƖ��̍��̉����Ɍf���銈���Ɋւ��āA��w�𑲋Ƃ��Ă��Ȃ��ꍇ�ɋ��߂���u�\�N�ȏ�́v�����o���Ƃ����v�����u�l�N�ȏ�́v�Ɖ�������B��w���ƂɌW��N���͒ʏ�S�N�ł���A�����N���̎����o���ŏ\���ł���ƍl������B |
�k��Ɠ��]�̒�`�l
| �@ | �@�ȗ߂̊�Ɠ��]�̍��̉����Ɍf���銈���Ɋւ��āA�\���ɌW��]�̒��O�ɊO���ɂ���{�X�A�x�X���̑��̎��Ə��ɂ����āu��N�ȏ�p�����āv�Ɩ��ɏ]������Ƃ����v�����u��J���ȏ�p�����āv�Ɖ�������B�O���ɂ����č̗p��A��{�I�ȋƖ��E���{�ꌤ�C�i�P�J�����x�j���I������A�����ɓ��{�ɂ����Ċ��p�������i�O���l�Ƃ��Ă����{�ŏA�J�������j�ꍇ�ɁA�P�N�ȏ�Ƃ����v���͒����B |
�k�����E�o�c�̒�`�l
| �@ | �@�ȗ߂̓����E�o�c�̍��̉����Ɍf���銈���Ɋւ��āA�����ɂ��Ắu��l�ȏ�̖{�M�ɋ��Z����҂��]�����邱�Ɓv���v���Ƃ���Ă��邪�A������폜����B��l�ȏ�̖{�M���Z�҂��]�����Ȃ��Ă��A���{�o�ς̊������Ɏ����铊�����s�Ȃ��O���l������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���B |
�k�Ɩ��Ɛ莑�i����ɂ��������͈͂̊g��l
| �@ | �@�ٌ�m�A���F��v�m�Ƃ������u�@���E��v�Ɩ��v�A��t�A���Ȉ�t�Ƃ������u��Áv�ɂ����ẮA�O�҂ɂ�����A�O���@�����ٌ�m�A�O�����F��v�m�������A���{���̖@���㎑�i��L����҂��s�Ȃ����ƂƂ���Ă���Ɩ��ɏ]�����銈���i������u�Ɩ��Ɛ莑�i�v�j�ƂȂ��Ă���A�v��������߂Č������B�ٌ�m�A���F��v�m�A��t�A���Ȉ�t�ɂ��ẮA���Ƃ��A�A�����J�A���B�A�����������̐�i���A�o�ϘA�g�����������鍑�A�A�W�A���������F�肷�铯�l�̎��i�ɂ��āA���i�v���̊ɘa�ɂ���āA�ݗ����i�i�����E�؍݁A�A�J�j��F�߂�悤�ɂ���B
�@��Ɗ����̍��ۉ��ɔ����A���O���ٌ̕�m�A���F��v�m�ɑ���j�[�Y�͍��܂��Ă���B���݂��A�O���ٌ�m�ɂ��@�������̎戵���Ɋւ�����ʑ[�u�@�A���F��v�m�@��\�Z���̓�ɂ���Ĉ��̋Ɩ����F�߂��Ă��邪�A���͈̔͂͌��肳��Ă���B�܂��A��t�A���Ȉ�t�ɂ��Ă��A���{�l�Ɍ��肵�Ȃ��Ă��A�Ɩ��Ɏx��̂Ȃ��͈͂œ��{����K�����Ă���A���̋Z�p�����������Ƃ͉\�ł���B
�@�����́A���̑����K�����v��c�ɂ����Ă����Ɏw�E����Ă���A���������̗����̌���A���Y�Ɩ��T�[�r�X�ɌW�鋣���̊��������̊ϓ_����A�Ɩ��͈͂̌������A���i�Ԃ̑��ݏ�����A���i�̔p�~�����܂߂����x�̂���������������ƂƂȂ��Ă���B |
|
| (2) | �@�ݗ��N���̉���
�k�ő�ݗ����Ԃ̂T�N�ւ̉����l
| �@ | �@���݁A�u�O���v�u���p�v�y�сu�i�Z�ҁv�ȊO�̍ݗ����i�ɔ����ݗ����Ԃ́A�R�N���邱�Ƃ��ł��Ȃ��i�@����̓�A�R���j���ƂƂȂ��Ă��邪�A������T�N�ɉ�������B���Ƃ��A�h�C�c�A�C�M���X�͂T�N�A�t�����X��10�N�ƂȂ��Ă���B�ݗ����Ԃɂ��ẮA1999�N10���ɉ������s�Ȃ��A�ݗ����Ԃ̉������s�Ȃ��Ă��邪�A���̌�̍��ۓI�Ȍo�c���̕ω��܂��A����ɉ������邱�Ƃ��]�܂����B |
�k�ݗ����Ԃ̋敪�̍ו����Ƌ敪�I���̎��R���l
| �@ | �@�ݗ����Ԃ́A�ȗ߂ɂ����āA14���i�̂����A�u���s�v������13���i�ɂ��āA�ݗ����Ԃ��R�N���͂P�N�ƂȂ��Ă���i�u���s�v�݂̂P�N�A�U�����͂R���j�B������T�N�Ɋg�傷��ƂƂ��ɁA���Ԃ̋敪���T�N�A�S�N�A�R�N�A�Q�N���͂P�N�ւƍו���������ŁA�ݗ����i�F��ؖ�����\������O���l���A���̋敪�̂Ȃ�����A�]������Ɩ��ɉ������ݗ����Ԃ�I�ׂ�悤�ɂ���B�����Ȃ�A�ݗ����Ԃɉ�������̖��m�����}����ƂƂ��ɁA�\�����鑤�̊O���l���_��ȑΉ����\�ƂȂ�B |
�k�ݗ����ԂƗL���J���_����ԂƂ̐������l
| �@ | �@���݁A���Ǔ��ǂ̎w���ɂ��A�ݗ����ԂP�N�̏A�J�r�U�N�X�V���A�ٗp�_����P�N�Ƃ��Ė��N�X�V���J��Ԃ��Ă����Ƃ�����B�O���l�͎��Ȃ̃L�����A�E�v�����m�ɂ����Ă���A���{��ƂłR�N�A�T�N�Ɠ����āA���̊Ԃǂ̂悤�Ȏd���𐬂��������邩����Ɉӎ����Ă���B�O�q�̂悤�ɍݗ����Ԃ���������Ă��A�L���J���_����Ԃ��P�N�ł́A���x�ȋZ�p�A���m�����������O���l����{��ƂɎ䂫���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�ݗ����Ԃ̌������̍ۂɂ́A�L���J���_����ԂƂ̐��������Ƃ邱�Ƃ��K�v�ł���B���s�̘J����@��ł́A�L���J���_����Ԃ͂P�N�i���x�̐��I�m����L����҂͂R�N�j�ł���A���ꂪ2004�N�P�����A�R�N�i���T�N�j�ɉ��߂���B���̂��߁A�ݗ����ԂƘJ���_����Ԃ��R�N�ɍ��킹�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B����ɍݗ����Ԃ��T�N�ɉ�������ꍇ�ɂ́A���ǖ@��̍ݗ����i�̗v���ƁA�����J����@��̍��x�Ȑ��m������L����҂̗v�������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B |
|
| (3) | �@�ݗ����i�F��ؖ����s��t���R�̂���Ȃ閾�m��
�@�O���l���A�Z���؍݈ȊO�̎��i�ɂ����ē������悤�Ƃ���ۂɂ́A�ݗ����i�Y�����E��K�����̗v���ɓK�����Ă��邩�ǂ�����@����b���R�����A�F�߂�ꂽ�ꍇ�̂ݍݗ����i�F��ؖ�������t�����B�����ĕs��t�����肳�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�ʕ\�ȏ�̋�̓I�ȗ��R����������Ȃ��B�ȗ߂��邢�͍����ɂ���āA�s��t���R����薾�m�ɂ����A���ǂɂ���Ċ���قȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O�@���邱�Ƃɂ��Ȃ���B
�@���̏ꍇ�A�l���i�v���C�o�V�[���j�̖��ɂ��ő���̔z�����K�v�ł���B���Ƃ��ΐ\���҂̓K�����Ɋւ�����݂̂����J������ŁA�R�������̓I�ɖ��m�ɂ����A���Ǎs���̓����������߂�ƂƂ��ɁA�O���l�̑��ł��\������ۂɏ\���������s�Ȃ����Ƃ��\�ƂȂ�B
|
| (4) | �@�ݗ����i�擾���̎葱���ɌW�鏈���̊ȑf���E�v����
�@���{�ɓ�������]����O���l�́A�O�q�̒ʂ�A�{�l�܂��͑㗝�l�̐\���ɂ��A�R���ŔF�߂�ꂽ�ꍇ�ɍݗ����i�F��ؖ�������t����A�݊O���قɂ����Ă������č��̔������āA�����E�؍݁A�A�J���\�ƂȂ�B�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\���ɓ������ẮA���ʂ̐\�����̂ق��A�ݗ����i�ʂ̏��ނ��K�v�ƂȂ邪�A�ݗ����i�ɂ���ẮA�����̏��ނ��K�v�ł���A�܂��L�����e�E���@�������G�ł��邽�߁A�����͍s�����m�����@�ւ�����������ԂS���Ă���B���������āA�s�v�ȏ��ނ̒�o�����߂Ȃ��ƂƂ��ɁA��ʂɂ�������₷���L�����@�Ƃ���B
�@����ɁA�@���ȓ����Ǘ��ǂɂ����鏑�ސR���Ɏ��Ԃ�������Ƃ��������w�E����Ă���B�l���͂��邪�A���ςłQ�`�R�J���A�����ꍇ�ɂ͔��N�Ƃ����R�����Ԃ�v����P�[�X������B���������́A�D�G�ȊO���l��������������Ď��Ƃ𐋍s��������Ƃ��炷��Η]��ɒ����Ƃ��킴��Ȃ��B����́A�s���葱�@����K�p���O�ƂȂ��Ă���A�W���������Ԃ��ݒ肳��Ă��Ȃ��B���������ώG�Ȏ葱���ɌW���Ԃ�R�X�g���́A��Ƃ��X�s�[�h���������ăr�W�l�X��W�J�����ő傫�ȏ�Q�ƂȂ�B�ώG�Ȏ葱���̂��߁A�����f�O����P�[�X������A�葱���̊ȑf�����}����A�O���l���炪�\�����s�Ȃ����Ƃ��\�ƂȂ낤�B
�@�����āA���Ƃ��Ήߋ����N�Ԃɂ킽��\���ɂ����ĕs���ɂȂ������Ⴊ�Ȃ��A�������ꂽ�O���l�Ɋւ��Ď��̂���������������Ȃ��悤�Ȋ�Ɠ���D�ǎ��Ǝ҂Ƃ��ĔF�肷�鐧�x��݂��A�����������Ǝ҂��㗝�l�Ƃ��čݗ����i�F��ؖ����̌�t��\������ꍇ�ɂ́A���ʂɐv�����ȈՂȎ葱���ɂ��A���Y�\���ɑ��鏈�����s�Ȃ���悤�ɂ��ׂ��ł���B
�@�Ȃ��A�C�M���X�ł́A�d�q�\���V�X�e������������Ă���A�\������P���łV���A��P�T�ԂłX������������Ă���B
|
| (5) | �@�Љ�ۏዦ��̑�������
�@���{�Ƃ̐l�ތ𗬂������ȍ��Ƃ̊Ԃɂ����ĎЉ�ۏዦ��̒��������邱�Ƃ́A�C�O�̗D�G�Ȑl�ނ���{�ɗU�v�����ł��A����߂ďd�v�ł���B���݂܂ł̂Ƃ���A���{�����������Љ�ۏዦ��̓h�C�c�i2000�N�����j�A�C�M���X�i2001�N�����j�̂Q�J���Ƃ̂��̂ɉ߂��Ȃ��B
�@���ʁA�A�����J�A�؍��Ƃ̊ԂŌ����������ӂɒB�������Ƃ͕]���ł��邪�A���������A�Љ�ۏᐧ�x����������Ă��鍑�Ƃ̊Ԃł̋���̒������߂����Ă����悤���߂����B���ɁA���Ɍ����̍��i�t�����X�A�x���M�[�j�A�\������̂��鍑�i�I�����_�A�C�^���A�A���N�Z���u���O�A�J�i�_�A�I�[�X�g�����A�j�A���̑��̏d�_���i�A�W�A�����j�Ƃ̋���́A�O���n��Ƃ����{�ɗD�G�Ȑl�ނ𑗂荞�ރC���Z���e�B�u�Ƃ��Ȃ낤�B
|
| (6) | �@���x�l�ނ̒�Z���i�Ɍ��������x�i���{�ŃO���[���J�[�h�j�n�݂̌���
�@���I�E�Z�p�I����̊O���l�����̔\�͂���{�ŏ\�ɔ����ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�ނ炪���{�ɂ����Ď��Ȃ̃L�����A�v�������I�ɍl���邱�Ƃ��ł������p�ӂ���K�v������B���Ƃ��C�M���X�ł́A2002�N�P���A�Ȋw�A���Z���̐��Z�p�҂̎�����g�傷��ϓ_����A�u���x�Z�\�ږ��v���O�����v�����Ă���B�}�\�T�̓��_�v�Z���@�Ɋ�Â�75�_�ȏ゠��ꍇ�A���l���Ȃ��Ă��܂��P�N�Ԃ̑؍݂�������A����ɍő�R�N�̑؍݉������\�ƂȂ��Ă���B�܂����v�S�N�ԁA���x�Z�\�ږ��Ƃ��ďA�J������ɂ́A��Z���\���ł��邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@�����l�ނȂǁA�ɂ߂č��x�Ȑ��I�E�Z�p�I����̊O���l�̎���A��Z�̑��i�́A���E�I�ɂ݂Ċ��ɂЂƂ̑傫�ȗ���ɂȂ��Ă���B���{�ɂ����Ă������������x�E�V�X�e���̑n�݂Ɍ����Č������s�Ȃ��K�v������B
| �}�\�T�|�C�M���X�̍��x�Z�\�ږ��v���O�������_���@ |
| �w�� |
���m���ێ���=30�_�A�C�m���ێ���=25�_�A�w�m���ێ���=15�_ |
| �E�� |
�w�����x���̐E�ɂT�N�i���m���ێ��҂͂R�N�j�ȏ�A�J=15�_�A�㋉���x���Ȃ������E�ɂQ�N�ȏ�=10�_ |
| �ߋ��̎����i�N���j |
�S���|���h�ȏ�=25�_�A10���|���h�ȏ�=35�_�A25���|���h�ȏ�=50�_�@��EU�����A�A�����J�A���{�̏ꍇ |
| �A�J��]����ł̋Ɛ� |
�u��O�I�ȁv�Ɛт�����ꍇ=50�_�A�u�d�v�ȁv�Ɛт�����ꍇ=25�_ |
| ��ʊJ�ƈ���ʘg |
���ƕی��T�[�r�X�̈�ʊJ�ƈ�Ƃ��ďA�J����]����C�O�̈�t�����v���邽�߂̓��ʘg |
|
| �o�T�F�w�ʏ������Q�O�O�R�x�i�o�ώY�Əȕ���15�N�V���j |
|