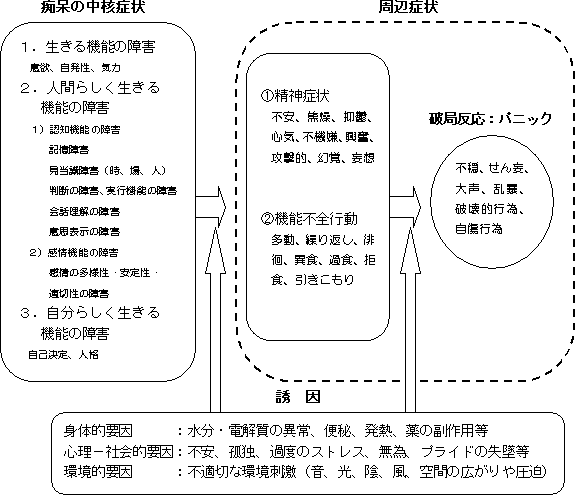
| 痴呆の人の介護をしている家族から 介護保険給付(サービスメニュー)への意見 |
| 社会保障審議会介護保険部会委員 (社)呆け老人をかかえる家族の会 永島 光枝 |
| ※(1) | 痴呆の理解・啓蒙について介護予防も含む一般社会への働きかけ、早期に情報をとり、家族が適切な早期対応ができる支援方法として電話相談の実施、および電話相談事業への支援。 | ||
| ※(2) | 数時間にわたる見守り支援のサービスメニュー「見守りの介護」が必要です。
|
| ※(3) | 緊急時に対応できる介護保険サービスの確保
| ||||
| (4) | 「家族介護でない在宅介護」を推進する。
| ||||
| ※(5) | グループホームに家族などが第二の我が家のように出入りでき、家族もグループホームで共通の顔なじみのメンバーとなれるような、(たとえば家族の泊まりや介護参加ができるような)制度と職員の理解と研修を進める。これによって、本人の気持ちの安定と家族の安心が共に得られ、「共に地域で暮らす」ことが出来る。 | ||||
| ※(6) | 終末介護を行う施設・グループホームなどへの加算を検討する。 又、グループホーム利用者が、介護保険の訪問看護を利用できるようにする。 | ||||
| ※(7) | グループホームの家賃について、一定の基準(考え方)を示すことが必要ではないか。 | ||||
| ※(8) | 医療度の高い人や疥癬の患者へ「医療用ショートステイ」の整備
|
| (9) | 痴呆の人が入院した場合、対応が困難との理由で退院を余儀なくされている現状がある。必要な期間、入院を継続できるように、入院時の痴呆の人の付き添いを、介護保険利用によるヘルパーサービスとして利用できるように制度を検討すること。 |
| (10) | 老人保健施設ショートステイ時の送迎を介護保険でつける。 |
| (11) | 施設で使用されている食器・箸・スプーンなどの品質やデザインの見直し。 |
| (12) | 施設利用時の施設備品のメニューの整備(エアーマット、車椅子クッション、高機能車椅子) |
| 第6回11月社会保障審議会介護保険部会発言補(永島)再掲 |
| ・ | 痴呆性高齢者について要支援または介護予防の段階において何らかの効果的支援が必要です。その段階には在宅での家族支援も啓蒙、教育、情報提供が必要。家族の会などの活用、組織作り及びその支援。 |
| ・ | 前述に関連して、一般地域住民への痴呆理解の促進に取り組むため、市町村保健センターに積極的な役割を果たせる仕組みを考えるべき。(介護保険以後、保健センターとの距離が遠くなっているかに感じる。) |
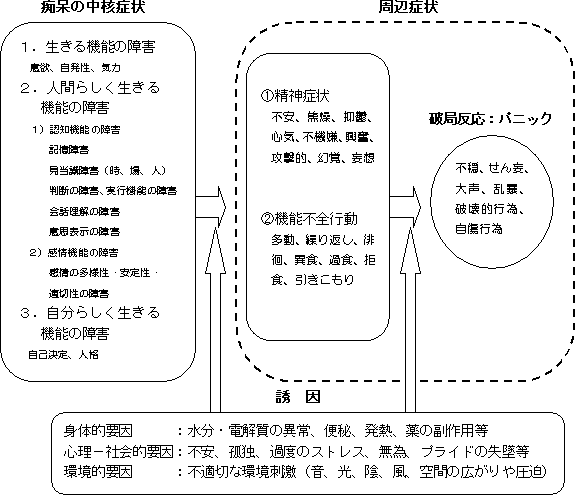 |
| 「痴呆バリア・フリー百科」より一部改編 |
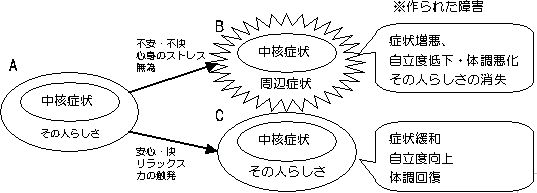 |
| 「高齢者の尊厳を支える介護」より一部改編 |
|
| 正常な人の視点からみた アルツハイマー病者の特徴 (豪ニューサウスウェールズ州アルツハイマー病協会の『手引き』より) |
痴呆の人自身の視点からみた説明 (クリスティーン・ボーデンさん他) |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
| ※ | クリスティーン・ボーデン(クリスティーン・ブライデン)氏 1995年に46歳でアルツハイマー病の診断を受け、翌年、首相・内閣府第一次官補を最後にオーストラリア政府を退職。診断前後の自らの経験をまとめて、1998年に「Who will be when I die?(私は誰になっていくの?)」を出版する。1998年に再婚、クリスティーン・ブライデンとなる。 現在、国際痴呆症支援ネットワーク、オーストラリアアルツハイマー病国家プログラム運営委員会のメンバーとして活躍。 |